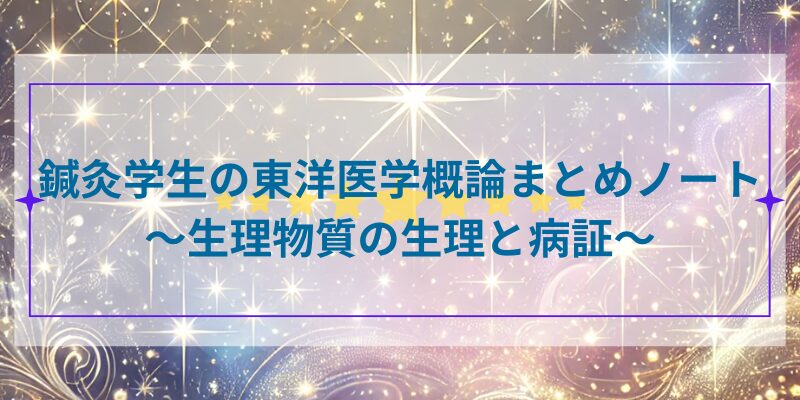こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
今回は、東洋医学の基本中の基本ともいえる「生理物質の生理と病証」について、学生時代のノートをもとにまとめました。
学びが進むにつれて、「精」「気」「血」「津液」など、だんだんとなじみのない専門用語が増えてきて、正直ちょっと難しく感じることもありますよね。

この大藤は、たった一本の幹から広がる生命の力そのもの。
東洋医学が大切にしているのも、こうした「目には見えないけれど、確かに存在しているもの」です。
とくに今回のテーマである生命エネルギーは、東洋医学の中心概念。
「イメージでとらえる力」がとても大事だと、学ぶほどに感じています。
この記事では、精・気・血・津液それぞれの「働き=生理」と、「バランスが崩れたときに起こる不調=病証」について、初学者にもやさしい言葉で解説していきます。
東洋医学の勉強をはじめたばかりの方、国家試験対策をしている鍼灸学生さん、自分の体調管理に活かしたい方にも、ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。
🌟生理物質の生理と病証
東洋医学では、人体を構成する基本的な物質を「生理物質」と呼び、陰陽の視点から分類します。
- 陰:血・津液・精(=物質的なもの、身体を滋養・潤す)
- 陽:気(=エネルギー的なもの、身体を動かす)
ここからは、まず「精」について見ていきましょう。
🌟精(せい)の生理と病証
精とは、私たちの身体の根本をつくる生命のエッセンスのようなもの。
Kagayaが東洋医学を学び始めた頃、「精=いのちの燃料」のようなイメージを持ちました。
精には2種類あり、次のように区別されます。
- 先天の精:両親から受け継いだ生まれつきのエネルギー。加齢や過労で消耗しやすく、回復しにくい。
- 後天の精(水穀の精):飲食物から得られ、日々補えるエネルギー源。
- どちらの精も腎に蓄えられ、成長・発育・生殖・老化に深く関係しています。
精の働きは多岐にわたります。たとえば……
- 生殖:精子・卵子の形成、妊娠・出産の基盤
- 滋養:身体の発育や生命維持に関与
- 血・気への化生:精から血・気が生まれます(※特に腎精→骨髄→血)
- 神の維持:精神活動の安定にも深く関与
🔍精が不足するとどうなる?
精が不足する状態を「精虚(せいきょ)」または「腎精不足」といいます。
- 子どもの場合:発育不良、学習障害
- 大人の場合:不妊、性機能低下、耳鳴り・難聴、健忘、脱毛、白髪
- 高齢者:骨や歯のもろさ、尿漏れ、虚弱体質
これらはすべて、「腎の力=精の力」が弱っているサインとも言えます。
Kagayaも鍼灸学校に通っていた頃、疲労がたまって抜け毛や耳鳴りが気になった時期がありましたが、「あ、腎精が消耗してるかも」と思えるようになったのは、この概念を学んだおかげでした。
🛠️日常でできる精のケア
腎精を守るには、無理をしすぎない生活・睡眠・栄養が大切です。
さらに、鍼灸やセルフケアグッズも有効です。
- 早寝・早起きで腎の休息時間を確保
- 黒豆・黒ごま・山芋・くるみなど「腎を補う食材」を活用
- 温灸器やカイロで「命門」や「腎兪」に温熱刺激
- 円皮鍼(パイオネックス)を「太渓」や「関元」に貼って補腎のケア
精を補うことは、東洋医学的にみて「若さ・免疫・活力」を支える根本ケアにつながります。
精を大切にして、自分らしくエネルギーあふれる毎日を送りたいですね。
🌟気の生理と病証|身体を動かす“エネルギーの流れ”
東洋医学でいう「気(き)」とは、身体を構成し、生きるために必要なエネルギーそのものです。
初めて学ぶ方にとっては、ふわっとした言葉に感じるかもしれませんが、気の存在を意識できるようになると、不調のサインや改善の方向性がぐっとわかりやすくなります。
🧬気の種類とその働き
- 原気:生命活動のエンジン。腎から生じ、全身に活力を送る
- 宗気:呼吸と血液循環を支える。胸中に集まり心肺を助ける
- 営気:血液の中にあり、栄養を届ける役割
- 衛気:体表を守り、外邪から身体を防御(免疫機能のような役割)
このように、気は私たちの内と外のバランスを保つために、いくつもの役割を果たしています。
🔥気の5つの主な作用
- 推動作用:血や津液を巡らせ、成長や内臓の働きを促進
- 温煦作用:身体を温め、体温を維持
- 防御作用:外邪(風邪やウイルス)を防ぐ
- 固摂作用:汗や尿、血液が漏れ出ないようにコントロール
- 気化作用:水分や栄養を別の形(気・血・津液)に変化させる働き
つまり、気が元気なら、からだもこころも元気ということなんです。
💡気の乱れによって起こる病証
🪫虚証:気が足りない・流れない
- 倦怠感・息切れ・無力感・風邪をひきやすい
- 声が小さい・話すのがおっくう
- 食欲不振・舌の色が淡い
- 自汗(ちょっと動いただけで汗が出る)
長時間の過労・睡眠不足・過度なダイエットなどで起こりやすく、Kagayaも疲れすぎた日は「気虚だなぁ…」と感じることがあります。
- 気陥:気の力が弱まり、内臓が下垂(脱肛・子宮脱など)
- 気脱:重度の衰弱やショックなどにより、意識が遠のく危険状態
🌀実証:気が滞る・逆流する
- 胸やお腹が張って苦しい
- イライラ・気分が落ち込みやすい
- ゲップやおならで楽になる
- 肺:咳・喘息・息苦しさ
- 胃:しゃっくり・ゲップ・吐き気
- 肝:イライラ・怒りやすい・頭痛
気は“流れ”が命です。滞っても逆流しても、不調の原因になります。
🧘♀️気を整えるセルフケア習慣
- 朝日を浴びて深呼吸(宗気アップ)
- おへそ周りを温める(原気の強化)
- イライラしたら「太衝」や「内関」にセルフ指圧
- ▶ 温灸器やお灸で「中脘」「気海」にケア
気の巡りを整えることは、感情・内臓・免疫すべてに良い影響を与えてくれます。
「なんだか元気が出ないな…」という日は、ぜひ自分の“気”を感じてケアしてあげてくださいね。
🌟血(けつ)の生理と病証|こころとからだを支える“栄養の流れ”
東洋医学における血(けつ)は、現代医学でいう“血液”とは少し意味が異なります。
赤くて栄養に富んだ体液として、全身に滋養を届けるだけでなく、精神(=神)を安定させる役割も持っています。
- 滋養作用:全身の臓腑・器官・組織を養い、健康な発育・維持を助ける
- 神の維持:精神を安定させる、感情や思考にも影響
Kagayaは授業で「血が足りないと“こころ”が不安定になる」と聞いたときに、“眠れない・そわそわする・生理が乱れる”という体験がぴったり当てはまったことを思い出しました。
🩸血の虚証|足りない・養えない
血虚(けっきょ)
- 顔色が白い・めまい・動悸・疲れやすい
- 不眠・夢が多い・健忘(忘れっぽい)
- 目のかすみ・爪が割れやすい・髪のパサつき
- 月経量が少ない・周期が遅れる・経血が薄い
これは単なる「貧血」ではなく、心身両面にあらわれる“養う力”の不足なのです。
Kagayaも、看護師として働いていたころ、夜勤明けに「目がかすむ・立ちくらみ・不安感が強くなる」などの症状が出ていた時期があり、いま思えば典型的な「血虚」状態でした。
🩺血の実証|滞る・熱をもつ
血瘀(けつお)
- 刺すような痛み・夜間に強くなる固定痛
- しこり・瘀斑(青紫色のあざや点)
- 月経時の塊・経血の色が黒っぽい
- 顔色・舌が紫がかっている
「血の滞り=うっ血」は、冷えやストレス、過労、生理トラブルに深く関係します。
血熱(けつねつ)
- 発熱・ほてり・盗汗・口渇
- 出血(鼻血・喀血・吐血・血尿)
- 皮膚の赤み・かゆみ・じんましん・湿疹
- 精神不安・不眠・夢が多い
Kagayaの経験では、夜ふかし・甘いもの・辛い物の食べすぎで起こる“ほてり・かゆみ・眠れない”という症状は、まさに「血熱」に近いと感じます。
🌿血を養うためのセルフケア
- 鉄・ビタミンB群・葉酸などを含む食品を意識(レバー・黒きくらげ・ほうれん草)
- 夜は早めに寝て「肝(血を貯える臓)」を休ませる
- ▶ 温灸器やカイロで「三陰交」「肝兪」を温めて血の流れをサポート
血は「こころ」と「からだ」両方を潤してくれる大切な存在。
現代の忙しい生活ではどうしても消耗しがちですが、意識して養う習慣を取り入れることで、安定した毎日がつくれます。
津液の生理とよくある不調
津液(しんえき)とは、体内を潤し、栄養を届ける「正常な水分」のことです。
- 津:さらさらとした液体(汗・涙・尿・鼻水など)
- 液:やや粘り気のある液体(関節液・唾液・精液・骨髄液など)
- 主な作用:滋潤(うるおす)、濡養(養う)、血脈を満たす
津液の不調とその症状
🌿虚証:津液不足タイプ
- 津液の生成不足や過労・加齢による消耗
- 乾燥傾向が強まる
- 喉の渇き・乾いた咳
- 乾燥肌・フケ・髪のパサつき
- 便秘や尿量の減少
おすすめセルフケア:お風呂上がりの保湿+内側から潤す「なつめ茶」「枸杞茶」などを取り入れて。
🌧実証:痰湿(津液の停滞)タイプ
- 運動不足・脂っこい食事・冷えなどにより津液がうまく巡らず停滞
【痰湿が進むと…】
▼ 浮腫・下痢・重だるさ(=湿)
▼ 腹鳴・喘息・水様便(=飲)
▼ 咳・多痰・不眠・めまい・精神症状(=痰)
おすすめセルフケア:身体を温め、水分代謝を助ける温灸や半身浴がおすすめです。
🌟おすすめの東洋医学テキスト|学生にも読みやすい!
はじめは用語の多さに圧倒されますが、以下の本はKagayaが実際に助けられたテキストです。
講義と合わせて読むと、理解が深まります。
どれも図解が豊富で、理解を助けてくれます。初学者には特におすすめです。
🌟まとめ|生理物質は「見えないけれど確かにあるもの」
東洋医学を学びはじめると、つい用語の暗記に追われがちですが、実際は「感じる力」や「イメージする力」がとても大切です。
Kagayaもはじめは「血って何?」「気が滞るってどういうこと?」と戸惑いました。
でも、日々の観察や勉強の中で、次第に腑に落ちていきました。
あなたも、焦らず、自分のペースで“見えないもの”を感じていってくださいね。