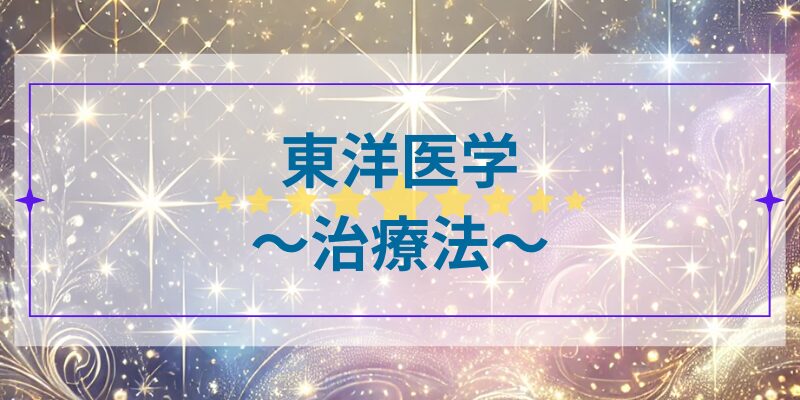東洋医学の治療について誤っている記述はどれか。
- 弁証施治は八綱病証を用いる。
- 補瀉は虚実に応じて行う。
- 正治とは順証に対する治法である。
- 標治法は経絡の変動を調整する。
東洋医学の特色で適切でないのはどれか。
- 四診によって証の決定を行う。
- 本治による病では奇穴を用いる。
- 未病を治す。
- 虚実に基づいて補瀉を施す。
東洋医学の特色で適切でないのはどれか。
- 本治による病では奇穴を用いる。
- 未病を治す。
- 虚実に基づいて補瀉を施す。
- 四診によって証の決定を行う。
🌟鍼の補寫法とは?東洋医学における補法と寫法の基本
東洋医学において「補寫(ほしゃ)」とは、気血のバランスを整えるための基本的な鍼の操作法を指します。
「補」は足りないものを補う、「寫」は過剰なものを瀉す(抜く・減らす)という意味です。
この補寫法は、患者さんの状態が「虚証」か「実証」かに応じて使い分ける必要があり、刺鍼のタイミングや方向、鍼の太さや深さにまで影響します。以下の表は、補法と寫法を比較したものです。
| 補法 | 寫法 |
| 呼気時に刺入し、吸気時に抜く | 吸気時に刺入し、呼気時に抜く |
| 経絡の流注に沿って刺入する | 経絡の流注に逆らって刺入する |
| 細い鍼を用いる | 太い鍼を用いる |
| 浅く入れ、後に深くする | 深く入れ、後に浅くする |
| 抜鍼後に鍼孔を閉じる | 抜鍼後に鍼孔を開く |
たとえば、冷え性や疲労感が強い虚証の方には「補法」を用いて、気血の不足を補います。呼気に合わせて鍼を刺すのは、息を吐いて脱力するタイミングで身体が受け入れやすくなるためです。
経絡の流れに沿って細い鍼をやさしく深めていき、最後は鍼孔をそっと押さえて気を留めるイメージです。
一方で、炎症や痛み、イライラ感などが強い実証のケースでは「寫法」を使います。
吸気のタイミングで刺して呼気で抜き、経絡の流れに逆らうように刺すことで、停滞している気を動かし、外へと放出するイメージです。
使用する鍼もやや太く、刺入は深めに始めて浅く引いていく動作でエネルギーを散らします。
さらに、抜鍼後の処置も重要で、補法では鍼孔からエネルギーが漏れないようにしっかり閉じる一方、寫法では鍼孔を少し開いて気が外に抜けやすくします。
この違いを理解しておくと、臨床現場での応用力が格段に高まります。
迎随の補瀉で補法はどれか。
- 地機に足関節に向けて刺す。
- 陰市に膝関節に向けて刺す。
- 三陽絡に手関節に向けて刺す。
- 孔最に肘関節に向けて刺す。
迎随の補瀉で補法はどれか。
- 外関穴では手関節に向けて刺す。
- 太淵穴では肘関節に向けて刺す。
- 三陰交穴では膝関節に向けて刺す。
- 足臨泣穴では足関節に向けて刺す。
迎髄の補瀉で瀉法となるのはどれか。
- 太白穴に踵の方向に向けて刺す。
- 復溜穴に足関節の方向に向けて刺す。
- 陽池穴に肘関節の方向に向けて刺す。
- 経渠穴に手関節の方向に向けて刺す。
補瀉迎随による経穴刺鍼で瀉法となるのはどれか。
- 陰谷へは足関節の方向に向けて刺す。
- 委中へは足関節の方向に向けて刺す。
- 尺沢へは手関節の方向に向けて刺す。
- 陽谿へは肘関節の方向に向けて刺す。
鍼の補瀉で正しいのはどれか。
- 入した鍼に軽い振動を与えるのは瀉である。
- 呼気に刺入し吸気に抜くのは瀉である。
- 経絡の流れに逆らって刺すのは補である。
- 抜鍼後の鍼痕を素早く押さえるのは補である。
鍼治療の補瀉で正しい記述はどれか。
- 太い鍼を用いるのは補である。
- 抜鍼後に鍼孔を押さえるのは瀉である。
- 呼気に刺入し、吸気に抜鍼するのは瀉である。
- 経絡の流注方向に沿って刺入するのは補である。
補瀉について誤っている記述はどれか。
- 一般的に太い鍼は瀉法になる。
- 速く刺入し速く抜くと瀉法になる。
- 経絡の流れに沿って刺入すると補法になる。
- 吸気に刺入し呼気に抜くと補法になる。
鍼治療の補瀉で誤っている記述はどれか。
- 呼気に刺入し吸気に抜くのは補である。
- 経絡の流れに逆らって刺すのは補である。
- 弾爪は補である。
- 鍼孔を押さえるのは補である。
補法に該当しない刺鍼法はどれか。
- 吸気に刺入し、呼気に抜く。
- 細く柔らかい鍼を用いる。
- 抜鍼後は素早く鍼孔を閉じる。
- 経気の流れにしたがって鍼を静かに刺入する。
実証に対する鍼治療の手技として正しい記述はどれか。
- 抜鍼しても鍼孔を閉じない。
- 呼気時に刺入し吸気時に抜く。
- 鍼尖を経絡の流れに沿って刺入する。
- ゆっくり刺入しゆっくり抜く。
陽実証に対する刺法で適切なのはどれか。
- 速刺速抜で刺鍼する。
- 抜鍼後に直ちに鍼孔を閉じる。
- 経気の流れに沿って刺鍼する。
- 呼気時に刺入し、吸気時に抜く。
肘関節に向けて刺入すると補法になる経穴の部位はどれか。
- 尺骨内縁と尺側手根屈筋の間、手関節背側横紋の上方5寸
- 長掌筋腱と橈側手根屈筋腱の間、手関節掌側横紋の上方5寸
- 肘頭と肩峰角を結ぶ線上、肘頭の上方2寸
- 肘後外側、上腕骨外側上顆の上縁、外側顆上稜の前縁
「咽喉の閉塞感、怒りっぽい、抑うつ、胸脇苦満」 本病証に用いる鍼の補瀉法で適切なのはどれか。
- 呼気に刺入し、吸気に抜鍼する。
- 細い鍼を用いる。
- 経穴をよく按じてから刺入する。
- 抜鍼後、鍼孔を指で塞がない。
🌟灸の補寫法|艾の大きさ・燃え方・熱感で見分ける補法と寫法の違い
鍼と並ぶ東洋医学の伝統的な治療法として「お灸(きゅう)」があります。
艾(もぐさ)を燃やして皮膚表面を温め、身体の冷えや滞りを改善するものですが、このお灸にも「補寫法(ほしゃほう)」の考え方があります。
灸における補寫とは、「温めて補う操作」と「熱刺激で寫す操作」を分けて使うことを意味します。
補法は身体にエネルギーを与えるための穏やかな操作、寫法は不要なものを取り去るための強い操作と理解してください。
以下の表で、その違いを視覚的に確認しましょう。
| 補法 | 寫法 |
| 熱さを緩やかにする | 熱さを激しくする |
| 自然に燃やす | 風を送り疾く燃焼させる |
| 小さい艾を用いる | 大きい艾を用いる |
| 柔らかく捻る | 硬く捻る |
| 底面を狭くする | 底面を広くする |
| 良質の艾を用いる | 粗悪な艾を用いる |
| 灰を取らずに重ねてすえる | 灰を一壮ごとに取ってすえる |
補法では、身体にじんわりと温かさが浸透していくような心地よい熱感を目指します。
小さく、柔らかく、良質な艾を使用し、自然にゆっくりと燃焼させることで、気血の巡りを穏やかに助けていきます。
底面を狭く捻ってやさしくすえることで、熱刺激が皮膚の深部へやさしく届き、虚証に適したケアになります。
一方、寫法では熱さをしっかりと感じる強めの刺激で、鬱滞した気や血、寒邪を散らしていくことを目的とします。
そのために、大きく固く捻った粗めの艾を用い、風を送って素早く燃やすことで強い熱を発生させます。
底面は広くして接触面積を増やし、灰は都度取り除いて次の壮(すなわち1回の灸)へ移ります。
また、灰を取らずに連続してすえる補法は、「温かさを持続的に与える」という意味での積極的な補益にあたります。
逆に、毎回灰を取り除いて新たに艾を置く寫法は、「熱刺激をリセットしながら繰り返すことで排出を促す」操作となります。
このように灸の補寫法は、熱の強さ・艾の質・燃え方・操作の細部によって決まる非常に繊細な技術です。
患者さんが「気持ちよかった」と感じる灸の多くは、実はこの補法のテクニックが応用されていることが多いです。
反対に、患部に強い冷えや痛みがあるときには、敢えて寫法的な熱刺激を加えることで、結果的に治癒反応を高めることもあります。
臨床では、補法・寫法を単体で使うだけでなく、同じ施術の中で「まず寫してから補う」あるいは「補った後に寫す」など、状態に応じた組み合わせも必要です。
お灸は、操作がシンプルに見えて、実は奥が深い治療法なのです。
瀉法はどれか。
- 抜鍼後、鍼孔を閉じる。
- 艾炷に風を送って燃やす。
- 前揉捻してから刺鍼する。
- 灰の上から施灸する。
補法となる艾の取扱いはどれか。
- 皮膚に密着させる。
- 火力を強める。
- 底面を広くする。
- 軟らかくひねる。
施灸で補法になるのはどれか。
- 灰に重ねてすえる。
- 底面を広くする。
- 皮膚に密着させる。
- 風を送って燃やす。
施灸で補法はどれか。
- 艾炷を強く押しつけて置く。
- 取穴数を多くする。
- 艾炷の底面を小さくする。
- 間を置かず施灸する。
補の施灸で誤っているのはどれか。
- 灰の上に重ねて施灸する。
- 風を送り燃焼させる。
- 艾炷を軟らかくひねる。
- 小さい艾炷を用いる。
補の施灸法として誤っているのはどれか。
- 灰を取らずに施灸する。
- 底面を狭くする。
- 皮膚に密着させる。
- 自然に燃やす。
🌟選穴の基本|局所選穴と循経選穴の考え方と臨床応用
鍼灸治療を行う上で最も重要な判断のひとつが「選穴(せんけつ)」です。
選穴とは、どの経穴(ツボ)に鍼や灸を行うかを決めることを指します。
ツボの選び方次第で、治療効果は大きく変わります。
選穴には大きく分けて2つの方法があります。
それが、局所選穴と循経選穴です。
それぞれの考え方と使い分け、そして国家試験でも問われやすいポイントについて、以下に詳しく解説します。
- 局所選穴
- 愁訴のある局所とその近辺に取穴すること
- 循経選穴
- 愁訴がどこの経絡と関連するか判断し、その経絡の経穴を取穴すること
① 局所選穴とは?
「痛いところに打つ」「凝っている場所にお灸する」といった、愁訴のある部位やその周辺にツボを取る方法です。
とくに肩こり・腰痛・筋肉痛などの運動器疾患に用いられやすく、即効性が期待されます。
たとえば、肩こりなら肩井(けんせい)・肩中兪(けんちゅうゆ)、腰痛なら腎兪・志室・大腸兪などが定番です。
局所の圧痛点や硬結を指標にすることで、患者さんの訴えと一致しやすく、初心者でも取り組みやすい方法です。
ただし、局所にしかアプローチしないと、根本原因に届かないこともあります。
② 循経選穴とは?
循経選穴は、愁訴の部位が属する経絡(気の通り道)を特定し、その経絡上にある経穴を選んで取穴する方法です。
これは東洋医学的な弁証(証に基づいた診断)に基づき、全身の気血のバランスを整えることを目的としています。
たとえば、右肘の外側に痛みがある場合、そこは手の陽明大腸経が通っています。
したがって、その経絡上にある曲池や合谷を選ぶことで、肘の痛みにも対応できます。
また、遠隔部にある経穴(例:合谷や太衝)を選ぶことで、広範囲な調整も可能です。
循経選穴のメリットは、局所の状態がわかりにくいときや、複数の部位に症状があるときに、全体を整えることができる点にあります。
つまり、ただその場を治すのではなく、体質や体調を見ながら治療方針を立てることができるのです。
臨床では「併用」がカギ
多くの場合、局所選穴と循経選穴は併用します。
たとえば「肩こりがつらい」と訴える方に対しては、肩井(局所)と同時に、合谷(大腸経)や後渓(小腸経)といった経絡の上の遠隔取穴を合わせることで、より効果的に施術できます。
国家試験では、「局所選穴・循経選穴の定義」や「どちらが適しているか判断する状況」などが問われることがあります。
臨床の感覚とともに、言葉としての定義も押さえておくと安心です。
腰殿部外側と大腿外側の脹痛に対して、侠渓を取穴した治療の法則はどれか。
- 局所取穴
- 難経六十九難の取穴
- 分刺による取穴
- 循経取穴
🌟三刺とは?陰陽の邪を調え気血を巡らせる古典的刺鍼法
東洋医学における鍼灸の技法には、古代中国の医学書『黄帝内経(こうていだいけい)』に記された多様な刺鍼手法があり、その中でも特に基本となるのが「三刺(さんし)」です。
三刺とは、陰と陽の邪気を体外に出し、水穀の気(飲食物から得た生命エネルギー)を巡らせるための3種類の刺し方を指します。
「三」という数は単なる数ではなく、「天地人」「気血津」「陰陽中」など東洋哲学における調和の象徴でもあります。
- 陰陽の邪気を出し、水穀の気の巡りをよくする方法
三刺の詳細な分類は諸説ありますが、一般的には以下の3つの技法を指すとされています:
- 毛刺(もうし):皮膚の表層(浅い部)に対して刺す。風寒などの外邪が表にあるときに行う。
- 複刺(ふくし):中間層に複数回刺して気血の滞りを解消する。筋肉層への刺鍼。
- 輸刺(ゆし):深部、特に骨や臓腑に近い部位まで刺す。慢性的な痛みや深在性の病に使用。
このように、表・中・裏(浅・中・深)という身体の三層構造に対して、それぞれの深さに応じた刺鍼を行うのが三刺の考え方です。
これはまさに「全体の気のバランス」を整える古典的かつ体系的な刺鍼アプローチといえるでしょう。
現代で言えば、例えば風邪のひき始め(悪寒や肩のこりなど)がある場合には「毛刺」で皮膚に近い場所に刺激を与えて発汗を促し、筋緊張による肩こりや腰痛には「複刺」、関節や骨の深部痛には「輸刺」を使うというように、症状の深さと刺鍼の深さを合わせていくことが大切です。
古典では「陰陽の邪を調え、五臓六腑の気を動かす」と表現されていますが、現代に置き換えれば自律神経の調整、免疫系の活性化、血流の促進など、多面的な効果があると考えられます。
また、三刺はその後に発展する「五刺」「九刺」「十二刺」といった刺鍼法の元祖とも言える考え方であり、国家試験においてもその位置づけや目的を問われることがあります。
単なる技術名として暗記するのではなく、「なぜそのような刺し方があるのか」という哲学と目的を理解することが合格へのカギです。
陰陽の邪気を出し、水穀の気の循りを良くする刺法はどれか。
- 五刺
- 三刺
- 九刺
- 十二刺
🌟五刺とは?五臓の病と組織に応じた古典的刺鍼法の理解
前章の三刺に続いて、今回は『霊枢・官能』に記載されている古典的刺鍼法「五刺(ごし)」について解説します。
五刺は、五臓に対応する5つの刺法で、それぞれの臓と関係の深い組織や病態に対して、適切な刺鍼方法を示したものです。
つまり五刺は、単なる刺し方の違いというよりも、病の深さ・部位・性質に応じて五臓の性質を踏まえたアプローチを表現したものといえます。
以下の表で、それぞれの名称・対応臓・特徴を確認しましょう。
| 名称 | 臓 | 特徴 |
| 関刺 | 肝 | 筋痺 |
| 豹文刺 | 心 | 経絡の血の滞りを取る |
| 合谷刺 | 脾 | 肌肉 |
| 半刺 | 肺 | 皮気を取る |
| 輸刺 | 腎 | 骨痺 |
それぞれの刺法をもう少し具体的に見てみましょう。
- 関刺(かんし):肝と筋に関係し、筋肉や関節のこわばり・引きつれに対して行う。筋痺に対応。
- 豹文刺(ひょうもんし):心と血脈に関係し、血の滞りを取り除く。皮下に浅く点々と刺すような技法で、瘀血やうっ血傾向に有効。
- 合谷刺(ごうこくし):脾と肌肉に関係し、肉付きのよい部位(例:背部・臀部など)に行う刺法。肥厚した組織や筋肉性の凝りに適応。
- 半刺(はんし):肺と皮に関係し、皮膚表層の冷えや浮腫・風寒の侵入などに対して、斜刺で行う技法。
- 輸刺(ゆし):腎と骨に関係し、骨や深部関節に及ぶ慢性痛・骨痺などに対して深く刺す技法。
このように五刺は、五臓とそれに対応する五体(筋・脈・肉・皮・骨)に基づいた古典的な全身治療の体系ともいえます。
それぞれの刺法には、対象とする深さ・部位・目的が明確に示されており、現代の臨床にも応用可能です。
例えば、ぎっくり腰のような筋肉の急性緊張には「関刺」、冷えによる表層のこわばりには「半刺」、静脈瘤や瘀血のある部位には「豹文刺」、筋層のコリには「合谷刺」、関節痛や骨性の問題には「輸刺」が適応となるケースがあります。
国家試験では、「名称と適応部位の組み合わせ」「五臓との関係」「特徴を記述する問題」などが出題されることがあるので、以下のようにセットで覚えておくのがおすすめです。
五刺の語呂合わせ:
「カン(肝)と筋を 関節(関刺)で伸ばし、
心の血を 豹のように点刺し(豹文刺)、
脾の肉は 合谷に、
肺の皮には 半刺し、
腎の骨には 輸刺(ゆし)だよ。」
五刺について正しい組合せはどれか。
- 関刺 ──── 血脈
- 輸刺 ──── 骨
- 豹文刺 ─── 肌肉
- 合谷刺 ─── 筋
鍼の刺法について正しい組合せはどれか。
- 豹文刺 ─── 腎
- 半刺 ──── 肺
- 輸刺 ──── 血絡
- 報刺 ──── 腹痛
五臓五刺で正しい組合わせはどれか。
- 腎 ─── 輸刺
- 肺 ─── 関刺
- 脾 ─── 半刺
- 肝 ─── 合谷刺
五臓五刺で関刺を用いるのはどれか。
- 腎
- 肝
- 心
- 脾
五臓五刺で心に応ずる刺法はどれか。
- 輸刺
- 豹文刺
- 半刺
- 合谷刺
五臓五刺の方法で肺の臓に対する刺法はどれか。
- 半刺
- 合谷刺
- 関刺
- 豹文刺
五臓五刺で鍼を深く刺入し、骨痺を取る刺法はどれか。
- 輸刺
- 半刺
- 合谷刺
- 関刺
🌟九刺とは?臨床応用にも役立つ古典刺鍼技法の体系
前章の「五刺」では五臓と組織の関係に基づく刺法を学びましたが、今回の「九刺(きゅうし)」はさらに多様な症状・部位・深さに対応する高度な刺鍼技術です。
『霊枢・官能』に記載される九刺は、古代中国における鍼治療の知恵が詰まった体系として、現代の臨床にも応用できます。
九刺はそれぞれ刺入の目的や対象が明確に定められており、体表から骨・経絡・臓腑に至るまで幅広くカバーする構造となっています。
以下の表で各刺法の名前と内容を確認しましょう。
| 種類 | 内容 |
| 遠道刺 | 病が上にあるとき、下合穴に刺す |
| 巨刺 | 左に症状があれば右側、右にあれば左側に刺す |
| 分刺 | 分肉に刺す(筋肉間への刺鍼) |
| 経刺 | 経脈上をやや深く刺す |
| 絡刺 | 絡脈を浅く刺して出血させ瀉す |
| 輸刺 | 五臓の病に対し、輸穴を刺す |
| 毛刺 | 皮膚の浮痺に対して浅く刺す |
| 大瀉刺 | 鈹鍼(へいしん)で深部に強く瀉す |
| 焠刺(さいし) | 筋痺に対し圧痛点を刺す |
それぞれの刺法の目的と特徴を簡潔にまとめると、以下のようになります。
- 遠道刺:上下の対角を使う刺法。例えば頭痛に対して足のツボを使うなど、経絡の遠隔部を活かす。
- 巨刺:左右交叉で刺す。右肩痛に左側を、左膝痛に右側を刺すなど、経絡のバランス調整に用いる。
- 分刺:筋肉と筋肉の間(筋膜・筋溝)を刺して筋痺を緩める。深部刺鍼の基本でもある。
- 経刺:経脈上に沿ってやや深く刺入。主に実証に対応する。
- 絡刺:絡脈(支流)の病に対して浅く刺して出血を促し、血瘀を解消。瘀血証の代表刺法。
- 輸刺:五臓の病気に対して各輸穴に刺す。古典的な臓腑治療の根幹。
- 毛刺:表層(皮毛)の浅い刺鍼。風寒表証やアレルギー皮膚炎などにも応用される。
- 大瀉刺:特別な鈹鍼(先が扁平な鍼)を使って病邪を強く抜く。実証の極みに使用。
- 焠刺(さいし):圧痛点や筋の緊張部位(阿是穴)を狙って刺し、筋痺を除く。
このように九刺は、解剖学的な構造・経絡・左右上下・深さ・病態など、多面的にアプローチできるよう設計されています。
単なる「名前の羅列」として暗記してしまうのではなく、なぜそう刺すのか?を意識することで臨床応用力が格段に高まります。
九刺の覚え方(語呂合わせ):
「遠く(遠道)に巨人(巨刺)が分け入る(分刺)
経(経刺)と絡(絡刺)を輸送(輸刺)して
毛(毛刺)を抜き、
大(大瀉)に刺し、
焠(焠刺)で締める」
国家試験では「名称と内容の組み合わせ」「刺鍼対象の深さ」「病態との関連」がよく問われます。
たとえば「絡脈に対する刺法は?」「左右の交叉刺法は?」などは頻出ですので、語呂合わせと一緒に意味も押さえておきましょう。
患部の左右反対側に治療する刺法を含むのはどれか。
- 五刺
- 十二刺
- 九刺
- 三刺
古代刺法で毛刺が含まれるのはどれか。
- 三刺
- 九刺
- 五刺
- 十二刺
誘導法に相当する鍼の刺法はどれか。
- 遠道刺
- 分刺
- 偶刺
- 豹文刺
遠道刺の刺法はどれか。
- 病、上にあれば下に取る。
- 病、体表にあれば皮毛を刺す。
- 病、右にあれば左に取る。
- 病、分肉にあればその間を刺す。
次の文で示す刺法はどれか。 「病上にあればこれを下にとり、腑兪を刺す。」
- 巨刺
- 経刺
- 遠道刺
- 輸刺
次の文で示す刺法はどれか。 「右を病めば左を取り、左を病めば右を取る。」
- 巨刺
- 経刺
- 輸刺
- 分刺
右肩関節痛に対して左肩に刺鍼する刺法はどれか。
- 絡刺
- 遠道刺
- 毛刺
- 巨刺
鈹鍼を用いる古代刺法はどれか。
- 焠刺
- 傍鍼刺
- 絡刺
- 大瀉刺
次の文で示す刺法はどれか。 「燔鍼を刺して即ち痺を取る。」
- 輸刺
- 焠刺
- 分刺
- 大瀉刺
九変に応ずる刺法で筋痺のときに圧痛点へ刺すのはどれか。
- 経刺
- 輸刺
- 焠刺
- 絡刺
九変に応じる刺法について誤っている組合せはどれか。
- 輸刺 ──── 深部に熱があるとき
- 毛刺 ──── 皮膚に浮痹があるとき
- 分刺 ──── 肌肉に邪気があるとき
- 遠道刺 ─── 病が上部にあるとき
🌟十二刺とは?12の刺鍼パターンで読み解く東洋医学の臨床戦略
これまで三刺・五刺・九刺と段階的に古典刺鍼法を学んできましたが、最終章となる「十二刺(じゅうにし)」はその集大成ともいえる高度な技術体系です。
十二刺は『霊枢・官能篇』に記載されており、12種類それぞれが特定の病態や解剖構造に対応して設計されています。
冷え・痛み・腫れ・瘀血・筋の拘縮など、東洋医学的な“邪気”の性質や範囲に応じて、的確に刺し分けることが求められる技術です。
以下の表で、十二刺の種類とその適応を整理してみましょう。
| 種類 | 内容 |
| 陰刺 | 寒厥のとき、左右の太渓に刺す |
| 偶刺 | 心痺に対し、兪募配穴を刺す |
| 直鍼刺 | 寒気が浅いとき、皮膚をつまみ刺す |
| 傍鍼刺 | 長期の痺に、中心と傍らに刺す |
| 賛刺 | 癰物(できもの)に浅く刺して出血 |
| 輸刺 | 熱があるとき、深く真っ直ぐ刺す |
| 短刺 | 骨痺に、骨に届くよう揺らし刺す |
| 浮刺 | 皮膚がひきつる冷えに斜刺 |
| 揚刺 | 寒気の範囲が広いとき、中心と四隅から刺す |
| 報刺 | 痛む部位を手で追って刺す |
| 斎刺 | 深く限局した痺に、一直線に3本刺す |
| 恢刺 | 筋痺に、方向を変えながら刺して緩める |
このように十二刺では、冷え・痺れ・腫れ・痛み・熱・筋緊張などの具体的な症状に対して、「どこに・どのように・何本刺すか」を細かく規定しています。
まさに刺鍼の処方箋といえる内容です。
例えば:
- 陰刺は「寒厥(極端な冷えや血流障害)」に対し、左右の太渓穴(腎経)を用いて陰気を補う。
- 賛刺は「癰物(できもの)」に対して刺絡を行い、排膿を促進する。
- 恢刺は筋痺の際に、鍼を入れてから揺らすことで筋緊張を和らげる方法。
- 報刺は痛みが移動する場合に、その動きを追って次々と刺すユニークな方法です。
また、「斎刺」や「揚刺」のように複数の鍼を立体的に使う刺法もあり、現代で言えばトリガーポイント鍼や交差刺鍼と共通する部分も見られます。
十二刺の語呂合わせ例(前半6つ):
「陰(陰刺)の心(偶刺)に まっすぐ(直鍼刺)
横にも(傍鍼刺) 浅く出血(賛刺)
熱には 真っ直ぐ深く(輸刺)」
後半6つも語呂にまとめたい場合は、次章で追加できます。
国家試験では、「名称と適応」「対象とする病態」「使用する経穴の例」などが出題されやすい分野です。
刺鍼の数・方向・深さ・対応する邪気の範囲を意識して整理すると記憶に残りやすくなります。
次の文で示す症状に用いる刺法はどれか。 「足から膝にかけて冷えがあり、水様便が出る。」
- 陰刺
- 偶刺
- 報刺
- 短刺
古代刺法で兪募配穴に発展したのはどれか。
- 揚刺
- 偶刺
- 傍鍼刺
- 報刺
「寒気の浅きもの」 に対する刺法はどれか。
- 斉刺
- 賛刺
- 直鍼刺
- 恢刺
骨痺に対する刺法はどれか。
- 短刺
- 揚刺
- 浮刺
- 報刺
十二刺のうち、患部に一鍼、その傍に一鍼ずつ刺す刺法はどれか。
- 斉刺
- 報刺
- 恢刺
- 揚刺
十二刺で筋痺の治療に用いる刺法はどれか。
- 賛刺
- 恢刺
- 揚刺
- 報刺
痹証と十二刺の組合せで正しいのはどれか。
- 寒痹 ─── 輸刺
- 心痹 ─── 陰刺
- 筋痹 ─── 恢刺
- 骨痹 ─── 直鍼刺
十二刺の偶刺に基づいた治療穴の組合せで正しいのはどれか。
- 中府 ――― 列欠
- 太淵 ――― 列欠
- 中府 ――― 肺兪
- 太淵 ――― 肺兪
十二刺の刺法で正しい組合せはどれか。
- 寒痺を治す ─── 偶刺
- 筋痺を治す ─── 浮刺
- 心痺を治す ─── 恢刺
- 骨痺を治す ─── 短刺
十二刺に含まれないのはどれか。
- 直鍼刺
- 浮刺
- 賛刺
- 大瀉刺
🌟まとめ|補寫法と古典刺鍼法を理解して、臨床と国家試験に活かそう
ここまで、鍼灸における基本的な刺灸技術として「補寫法」から始まり、「選穴」、そして古典に記載された「三刺・五刺・九刺・十二刺」まで、順に学んできました。
- 補寫法では、気血の虚実に応じた操作の違い(鍼・灸の方向・タイミング・道具)を整理。
- 選穴では、局所選穴と循経選穴の違いを理解し、臨床での応用例を紹介。
- 三刺・五刺・九刺・十二刺では、それぞれの目的・深さ・対象病態・経絡との関係を表と語呂でまとめました。
これらの刺鍼法は、単に歴史的価値のある知識というだけでなく、現代の鍼灸臨床においても非常に重要な基礎技術です。
冷え・痛み・痺れ・瘀血など、東洋医学で表現される様々な症状に対して、どの方法を選び、どのように刺すかを判断する力が問われます。
国家試験では、それぞれの刺法と適応、五臓との関連、また操作方法や刺す部位に関する記述問題・選択問題が頻出です。
特に九刺・十二刺は内容が多く混乱しやすいため、表と語呂合わせを活用して繰り返し復習するのがおすすめです。
そして、こうした知識を「点」で覚えるのではなく、実際の臨床や実技演習と結びつけて体感として理解しておくことで、真に使える知識となります。
これから臨床に出ていく鍼灸学生の皆さんや、国家試験を控えた方々にとって、本記事が知識の整理や理解の助けとなれば幸いです。