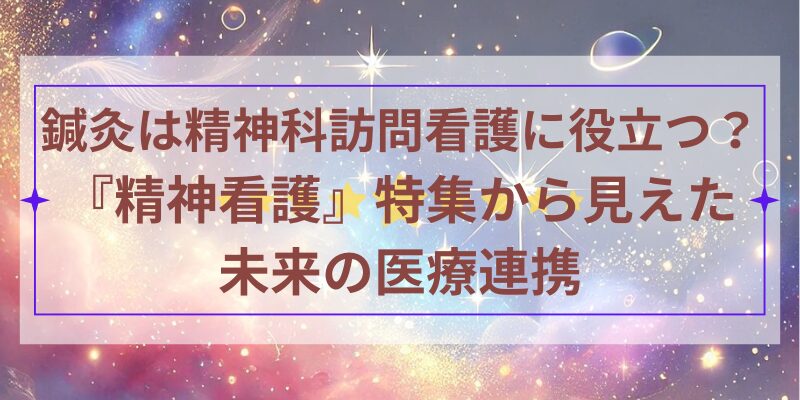🌟鍼灸と精神科訪問看護の出会い──『精神看護』特集を読んで
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
先日、日本ASPセラピー普及協会から届いた一通の案内が、Kagayaの心に強く残りました。
それは、精神科看護の専門誌『精神看護』(医学書院)2025年5月号にて、戦場鍼(BFA:Battlefield Acupuncture)が特集されたという内容でした。
戦場鍼といえば、Kagayaが今とても注目している耳鍼療法の一つで、精神科訪問看護の現場にも応用できる可能性を秘めた手技です。
訪問先で出会うクライアントさんの中には、「病院に行くまでもないけどつらい」「薬だけには頼りたくない」「身体の不調とこころの不調が絡み合っている」そんな訴えを抱えている方がたくさんいます。
そんな背景もあって、この特集の存在を知った瞬間、「これは絶対に読まなきゃ!」とAmazonで即ポチ。
届くのをワクワクしながら待ちました。
届いた雑誌を手に取ったときの第一印象は、正直「薄っ…!」でした(笑)。
ページ数も少なく、「これで1,650円…?」と一瞬だけ躊躇しました。
でも、そこは専門誌。
内容に期待を寄せつつ読み進めると、その情報の濃さに「読んでよかった…!」と心から思えました。
精神科と鍼灸、まったく違うようで、実は深くつながる領域。
今後の可能性を強く感じる1冊でした。
🌟専門誌ならではの視点──薄くても内容は濃かった
正直に言うと、届いた雑誌を開いた瞬間は「えっ、これだけ?」という印象でした。
ページ数が思ったよりも少なく、見た目のボリュームだけで判断すれば、1,650円という価格に少し躊躇してしまう方もいるかもしれません。
ですが、読み進めるうちに、その印象は一気に覆されました。
1ページ1ページに凝縮された専門的な情報が詰まっていて、むしろ「薄いからこそ無駄がない」「大切なことだけが丁寧に伝わる」そんな印象に変わっていったのです。
今回の特集記事は、一見「精神科看護師向け」に見えながらも、内容の深さ・視点の鋭さから言えば、むしろ鍼灸師、精神科医、そしてダブルライセンス(複数資格)を持つ人材にこそ刺さる構成になっていました。
たとえば、BFA(戦場鍼)を精神科領域に応用する際のエビデンスや、施術ポイントとなる耳介の解剖学的解説、患者への適応場面、さらには今後の臨床研究の方向性まで、実践者が現場で必要とする情報が網羅されています。
特に印象的だったのは、BFAを単なる“リラクゼーションの手技”として紹介するのではなく、「医療としての可能性」「科学的裏付けを持った補完医療」として真正面から取り上げていた点です。
このような切り口は、一般的な鍼灸雑誌や東洋医学系の媒体ではなかなか見られないもので、西洋医学との共存・統合を目指す実践者にとっては非常に貴重です。
Kagaya自身、読みながら思わずページに付箋を貼りまくり、メモを取りながら熟読しました。
BFAの導入における課題や、看護師・医師との連携のあり方、精神科訪問看護という特殊な環境での応用例など、臨床と直結する内容ばかりだったからです。
また、鍼灸を学んだ者であれば一度は感じる「医療現場での立ち位置の曖昧さ」「説明の難しさ」にも、この特集は明確な光を投げかけてくれていると感じました。
雑誌というと「読むだけ」で終わってしまいがちですが、今回の特集は現場での実践にすぐ活かせる具体的な視点を提供してくれるものでした。
精神科看護と鍼灸という一見交わりにくい領域が、専門誌の力によってこんなにも接点を持ちうるのかと、読後は希望すら感じました。
まさに「薄くても、深い」。
それがこの『精神看護』特集の真価だったと思います。
🌟戦場鍼(BFA)とは?精神科との関係性とは?
BFA(Battlefield Acupuncture:戦場鍼)とは、その名の通り、戦場で生まれた特殊な耳鍼療法です。
2001年にアメリカ空軍の医師リチャード・ニー(Dr. Richard Niemtzow)によって開発され、当初は負傷兵の痛みを軽減し、麻酔薬の使用を減らすための「即効性のある鎮痛法」として導入されました。
この技術は現在、NATO軍や米軍の一部ではすでに正式な医療手技として採用されており、医師や看護師が戦地でBFAを実施することが許可されています。
驚くべきは、手技のシンプルさと即効性。
短時間で施術が完了し、非薬物的に痛みやストレス反応を和らげることができるため、戦場という過酷な環境において重宝されているのです。
使用される針は「ASPニードル(Aiguilles Semi-Permanentes)」と呼ばれるごく小さなチタン製の鍼。
皮膚に半永久的に固定される構造をしており、通常は数日〜1週間ほど耳介に留置されたまま、自然と脱落します。
刺激する耳のポイントは、以下の5か所です:
- Cingulate Gyrus(帯状回)
- Thalamus(視床)
- Omega 2(感情領域)
- Point Zero(ゼロ点)
- Shen Men(神門)
この「C-T-O-P-S」と呼ばれる5点刺激は、脳の痛覚・情動・自律神経系に関与する領域に対応しており、痛みや緊張、不安、フラッシュバックといった症状の緩和に高い効果があるとされています。
そして近年、この戦場鍼が注目されているのは、戦場に限らず「日常の中にあるストレス・トラウマ・情緒不安」に対しても有効であることがわかってきたからです。
たとえば、以下のような症状への応用が報告されています:
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
- 不安障害・パニック障害
- うつ状態
- 慢性的な不眠
- 薬物依存・離脱症状
このような背景をもとに、今回『精神看護』2025年5月号では、BFAのメンタルケアへの可能性、精神科臨床への応用事例、現場での導入方法などが詳しく紹介されていました。
特に印象深かったのは、「BFAは単なる“リラクゼーション”ではなく、神経生理学的な理論に裏付けられた医療的アプローチである」という立場から、多角的に解説が行われていた点です。
こうした鍼灸手技が専門誌で取り上げられることはまだ珍しく、しかも精神科領域に特化した媒体での特集は画期的とも言えます。
日本においては、鍼灸が「医療」として捉えられる機会がまだ少ないですが、BFAのように明確な効果機序と症例実績を持つ手法であれば、今後、精神科訪問看護や地域医療との連携が進んでいく可能性があります。
まさに、「戦場で使われた鍼が、日常のこころを救う」──そんな時代が、すぐそこに来ているのかもしれません。
🌟精神科看護と鍼灸の橋渡し役になりたい
『精神看護』誌の特集を読み進めながら、Kagayaが強く感じたことがあります。
それは、精神科訪問看護の現場にこそ、鍼灸の力がもっと活かされるべきだということです。
Kagayaは看護師として精神科訪問の現場に関わる中で、日々クライアントの「こころ」と「からだ」の両面に寄り添っています。
しかし、そのケアの中にはまだ「できるのにできない」「やりたくても制度が追いついていない」ジレンマがたくさんあります。
その最たる例が、鍼灸の医療現場での位置づけです。
現在の日本では、鍼灸は「民間療法」「代替医療」「リラクゼーション」の枠に押し込められている印象が強く、医療者の多くも「よく知らないけど、気持ちよさそう」という程度の認識にとどまっています。
実際、精神科クリニックや訪問看護ステーションにおいても、「鍼灸って何ができるの?」「精神科に効くの?」という疑問をよく耳にします。
そのたびに「もっと知ってほしい」「連携できれば、もっと良いケアができるのに」と思わずにはいられません。
ですが今回の特集を読んで、BFA(戦場鍼)のように明確な技術・目的・手順・エビデンスがある鍼灸手技が紹介されたことで、「鍼灸=医療としての可能性」がようやく見え始めたと感じました。
とくに、精神症状に対するBFAのようなアプローチは、これまで薬物療法に依存してきた精神医療において、新たな選択肢となり得ます。
しかも、副作用のリスクが少なく、即時性もある。
これは、慢性期・軽症例・薬物抵抗性の方へのサポートとしても非常に魅力的です。
また、今後、鍼灸が診療報酬の中に位置づけられる未来もあり得るとKagayaは考えています。
たとえば、リハビリテーションや疼痛管理の一環として「包括評価」や「補完医療枠」での算定が可能になるような制度改革が進めば、訪問看護の場でも鍼灸師が正規にチームに加わることができます。
現場で働く者としては、「制度が整うのを待つ」のではなく、現場から事例を積み上げ、実践を通して信頼を得ることが第一歩だと思います。
そしてその役割は、医師や看護師だけでなく、私たち鍼灸師にもあるはずです。
看護と鍼灸。
これまで別々の道を歩んできたように思えるこの2つの専門性を、一人の人間の中で融合させ、橋渡し役となる。
それこそが、Kagayaのようなダブルライセンス人材が担うべき使命の一つではないかと思っています。
「東洋医学なんて信じられない」「怪しい」そう言われることもあるかもしれません。
でも、エビデンスを持ち、臨床で実績を積み、必要としている方に届けていけば、少しずつでも信頼は築けるはず。
私たち一人ひとりが、鍼灸と精神科医療の“架け橋”になる。
そんな未来を、今こそ現場からつくっていきたいと思います。
🌟APネットワーク──精神科医と鍼灸師の連携へ
『精神看護』誌の中で、特に注目したのが「APネットワーク」という取り組みの紹介でした。
これは、Acupuncture and Psychiatry Network(APネットワーク)と呼ばれる連携体制で、精神科医と鍼灸師が協力し、患者の症状やニーズに応じて相互に紹介し合うという、これまでにない斬新なシステムです。
たとえば、うつ病や不安障害で通院中の方が、「薬を減らしたい」「眠れないけれど、これ以上強い薬は飲みたくない」と悩んでいたとします。
そうした際に、精神科医が鍼灸師に治療を依頼するという流れが、このネットワーク内では可能になります。
逆に、鍼灸師が施術中に「この症状は単なる自律神経の乱れではないかもしれない」「医師の診断や投薬が必要だ」と感じたときには、信頼できる精神科医に紹介することができます。
このような連携が成立すれば、「鍼灸か、薬か」という二者択一ではなく、「鍼灸と薬のバランスをどう取るか」という視点で治療を進めることが可能になります。
実際のAPネットワーク構成を見ると、以下のような比率になっているそうです:
- 鍼灸師:約90%
- 医師:5%
- 看護師:0.5%
- 心理士:0.3%
この比率から見ても、鍼灸師が主体となって運営されているネットワークであることがわかります。
そして一方で、看護師の参加が非常に少ないという点も浮き彫りになります。
しかし考えてみてください。
患者さんの生活に最も近い場所で寄り添っているのは、訪問看護師です。
症状だけでなく、その人の暮らし・性格・悩みに寄り添う役割を担っているからこそ、東洋医学や鍼灸の視点を取り入れることには大きな意味があります。
たとえば、「不眠」や「食欲低下」「倦怠感」など、“なんとなくの不調”や“原因の見えにくい症状”に対して、薬以外のアプローチとして鍼灸を提案できるようになれば、それだけで患者さんの選択肢はぐっと広がります。
また、訪問現場では「病院に行きたくない」「精神科に通うのが怖い」と感じている方も少なくありません。
そんな時、“鍼灸”という穏やかな手法が入り口になることもあります。
医師・鍼灸師・看護師・心理士といった多職種がそれぞれの専門性を持ち寄り、患者さんにとってベストなケアを届ける。
APネットワークのような連携体制は、精神科医療の可能性を大きく広げてくれると感じました。
そして何より、「鍼灸と看護、どちらもわかる人材」がそこに加わることで、ネットワークはさらに機能的になると思います。
Kagaya自身も、鍼灸と精神看護の両分野を行き来しながら、その“架け橋”としての役割を果たしていきたいと感じています。
🌟看護師にもっと鍼灸の知識を
精神科訪問看護の現場にいると、看護師としての知識や経験だけでは対応しきれない「からだの不調」「こころの揺らぎ」に直面することがよくあります。
そんなとき、Kagayaは鍼灸師としての視点があるからこそ、より広い選択肢を持って関われると実感しています。
しかし、鍼灸の可能性を看護師が知らない、あるいは正しく理解していないという現実は、まだまだ根強いのが現状です。
「鍼灸って痛そう」「本当に効果あるの?」「民間療法ってことでしょ?」──これらは実際に、看護師同士の会話や研修の場で何度も耳にした声です。
実際、看護師向けの研修や大学教育の中で、東洋医学や鍼灸が取り上げられることはほとんどありません。
それゆえ、連携の可能性や施術の効果が現場で共有されることもなく、「知られていない=使われない」状態が続いています。
それはとてももったいないことです。
なぜなら、鍼灸には痛み・不眠・便秘・不安・不定愁訴といった「薬だけでは解決しきれない症状」に対して、穏やかで副作用の少ない選択肢としての可能性があるからです。
たとえば、精神疾患を抱える方の多くが訴える「眠れない」「食欲がわかない」「頭が重い」「身体がだるい」などの症状。
これらは西洋医学的には原因不明とされがちですが、東洋医学では「気虚」や「肝うつ気滞」「瘀血」などの概念で捉えることができます。
そのような視点を、看護師が少しでも持てるようになれば、薬の調整だけに頼らない、より個別性の高い看護が実現できるのではないでしょうか。
また、BFA(戦場鍼)のような簡便かつ即効性のある耳鍼療法であれば、看護師が介入する補完療法の一つとしても導入が可能です。
実際、アメリカでは看護師が耳鍼を用いてメンタルケアを行っている事例も報告されています。
今後は、看護協会や精神科看護の学会、看護大学の講義などで、鍼灸の基礎知識や臨床応用について紹介される機会が増えていくことを、心から願っています。
また、臨床の現場でも、鍼灸師と看護師が互いの専門性を学び合えるカンファレンスや事例共有の場があれば、より実践的な連携が進むはずです。
Kagayaはその第一歩として、訪問看護師自身が東洋医学を学び、現場で活かせるような研修や勉強会の開催も視野に入れています。
「知らないから使えない」ではなく、「知っていれば選べる」ように。看護師が東洋医学と鍼灸の知識を持つことは、患者さんにとっての安心感と希望の幅を広げることにもつながるのです。
🌟【きらぼしの鍼灸ケアでも、こころのケアを大切に】
「プライマリ・ケアサポート きらぼし」では、からだとこころの両方に寄り添う施術を大切にしています。
西洋医学と東洋医学、そして看護師としての視点を融合させながら、クライアントの訴えの背景にある“目に見えにくい不調”を丁寧にくみ取ることを心がけています。
特に、精神的な不安定さが身体症状として現れているケースでは、鍼灸が非常に有効です。
たとえば、気分の落ち込みや不安感、不眠、食欲不振、倦怠感、月経不順、ストレス性の胃腸トラブルなど、病院では“様子を見ましょう”と言われがちな症状も、東洋医学ではれっきとした“未病”としてアプローチの対象となります。
Kagayaが実践しているケアの中心には、耳ツボ療法(Auricular Therapy)と全身調整の鍼灸があります。
耳ツボは、自律神経系、ホルモンバランス、消化器系、情緒安定に関係する反射区が集まる部位です。
BFA(戦場鍼)で用いられる5点(C-T-O-P-S)や、神門・内分泌・胃腸・心などのポイントにやさしく刺激を加えることで、交感神経の過緊張をやわらげ、リラックス状態へと導く効果が期待されます。
また、全身の経絡や体質を踏まえた鍼灸施術では、その人特有の「気・血・水」のバランスや「五臓六腑」の状態を観察し、オーダーメイドのツボ選びと施術を行っています。
実際に、こんなことでお悩みの方が多くいらっしゃいます:
- 最近、気分が沈んでやる気が出ない
- イライラして眠れない夜が続いている
- 薬を飲むのに抵抗があるけれど、他の方法が分からない
- ストレスでお腹の調子が乱れやすい
- 自律神経の乱れが慢性化している気がする
「病院に行くほどでもないけれど、でも確かにしんどい」──そんなグレーゾーンの状態に対して、“選ばれる居場所”としての鍼灸ケアを提供することが、きらぼしの使命だと考えています。
また、Kagayaの施術は単なる「症状を取るための鍼」ではありません。
生活背景、家庭環境、服薬状況、セルフケア力、社会的孤立感なども視野に入れたホリスティックな支援を目指しています。
こころとからだは、切り離せるものではありません。
だからこそ、心身両面に働きかける鍼灸の力を最大限に活かし、ひとりひとりの「今ここ」の声に耳を傾ける時間を大切にしています。
「こんなこと相談していいのかな?」「話すだけでもラクになるかもしれない」──そう思ったときは、どうか遠慮なくご連絡ください。
あなたのその一歩を、きらぼしは全力で受け止めます。
🌟まとめ:鍼灸と精神科看護は、もっと手を組める
今回、『精神看護』誌において戦場鍼(BFA)が特集されたことは、単に「鍼灸の活用事例が紹介された」というだけではありません。
むしろこれは、これからの精神医療がどのように変わっていくか──その未来の方向性を指し示す一歩だったと、Kagayaは強く感じました。
従来、精神科のケアは「投薬+カウンセリング」が基本でした。
そして鍼灸は「肩こりや腰痛に効く民間療法」というイメージが根強く、医療との境界線は曖昧なままでした。
しかし、BFAのように科学的なエビデンスを持ち、精神症状への効果が認められてきた技術が登場したことで、鍼灸が医療チームの一員として機能しうる時代が見えてきたのです。
それは、医師が鍼灸を「治療オプションのひとつ」として選ぶ未来。
それは、看護師が「耳鍼でリラックスをサポートできる」ようになる未来。
そしてそれは、患者さん自身が「薬以外にも頼れる選択肢がある」と安心できる未来。
このような医療のあり方を実現するには、多職種の連携が欠かせません。
医師、鍼灸師、看護師、心理士──それぞれの専門性を活かしながら、患者さんの「生きづらさ」や「不調」に寄り添う体制が必要です。
そして、連携を実現するためには、東洋医学や鍼灸に対する正しい理解が医療者の間に広まることが前提になります。
残念ながら、現時点では「怪しい」「効果が不明」「根拠がない」といった偏見がいまだ根強く残っています。
だからこそ、私たち鍼灸師やダブルライセンスの専門職が果たすべき役割は非常に大きいのです。
東洋医学の用語や概念を、医療者にわかる言葉で翻訳し、臨床で活かす方法を提案する。
そして実践を重ね、実際に成果を示していくこと。
それが信頼につながり、未来の制度や教育の土台になっていきます。
何よりも大切なのは、患者さん自身が選べる環境をつくることです。
「薬だけでなく、他の選択肢もある」と知ること、「身体にやさしい方法もある」と感じられることが、心の安定と回復力を生み出します。
こうした新しい医療の形は、制度や保険の枠組みを待つのではなく、現場の私たちの実践から生まれていくものだと、Kagayaは考えています。
このブログ記事を通して、少しでも多くの医療者、看護師、鍼灸師、そして支援を必要とする方々に「希望」と「可能性」が届くことを願っています。
さあ、鍼灸と精神科医療がもっと手を組む未来へ。
その架け橋となる一歩を、今ここから踏み出してみませんか?
🌟耳ツボや自律神経ケアのご相談は「きらぼし」へ
「病院では様子を見るしかないと言われたけど、今すぐできることが知りたい」
「薬を増やす前に、ほかの方法も試してみたい」
そんな時は、ぜひ一度ご相談ください。
プライマリ・ケアサポート きらぼしでは、耳ツボ療法や全身調整の鍼灸を通じて、こころとからだをやさしく整えるオーダーメイド施術をご提供しています。
ご自宅への訪問、または小平市・東久留米市のシェアサロンでの施術も可能です。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら
どんな些細なことでも大丈夫です。
鍼灸師・看護師のKagayaが、あなたのお悩みに寄り添いながら丁寧に対応いたします。