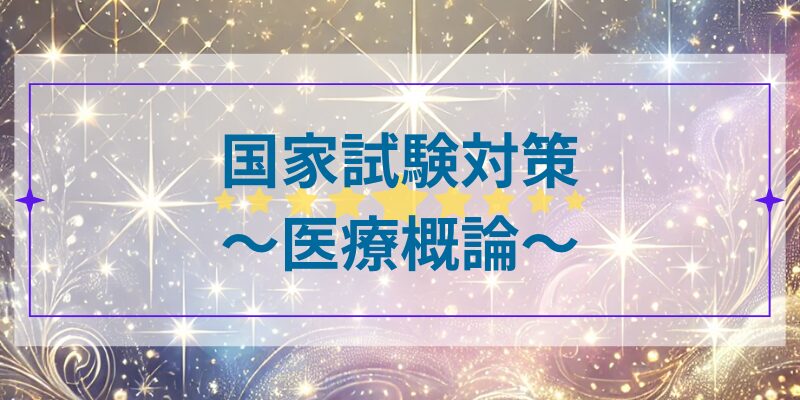こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
今回は医療制度や医療提供体制についての知識をまとめていきます。
医療概論は、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師国家試験においてほぼ毎年出題される重要科目です。
中でも「医療法」「医療提供体制(一次~三次医療)」「病院・診療所の分類」「医療計画」は、出題率も高く、用語や制度をしっかり整理しておく必要があります。
はじめて医療制度を学ぶ方でもわかりやすいように、過去問ポイントも交えながら整理していきます。
🌟医療法とは?その目的と医療提供体制の全体像
医療法とは、医療の安全と質を確保し、国民が適切な医療を受けられるようにするための基本的な法律です。
この法律の目的は、次のように定められています。
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保し、国民の健康の保持を図ること(医療法第1条の2)
そのために、医療法では以下のような医療提供体制の構築が進められています。
- 一次医療:日常的な病気やケガへの対応(例:かかりつけ医)
- 二次医療:入院や専門的な検査・治療が必要な中程度の医療(例:中規模病院)
- 三次医療:高度な専門治療・救命医療(例:特定機能病院)
この三層構造により、医療資源を無駄なく分配し、患者の状態に応じた最適な医療が提供される仕組みがつくられています。
🌟医療施設の種類とその違い
医療施設にはいくつかの種類があり、それぞれ定義・機能・人員配置が異なります。
国家試験では「病院と診療所の違い」や「特定機能病院・地域医療支援病院の特徴」が頻出です。
表で整理して覚えましょう。
| 施設名 | 定義・特徴 |
|---|---|
| 病院 | 入院患者20人以上を受け入れられる施設(医師・看護師などの配置義務あり) |
| 診療所 | 入院患者19人以下または外来のみ対応(例:クリニック、医院) |
| 助産所 | 助産師が管理し、正常な妊産婦の出産を取り扱う施設(医師不在) |
| 特定機能病院 | 高度な医療・研究・教育機能を持つ大規模病院(大学病院など) |
| 地域医療支援病院 | 地域の診療所などと連携し、紹介患者の診療を主に担う |
診療所やクリニックと病院の違いは「入院ベッド数20人以上」という明確な基準があります。
また、特定機能病院や地域医療支援病院には厚生労働大臣または都道府県知事の承認が必要であることもポイントです。
以下のような出題例が見られます。
Q. 病院とは、入院施設を有し、19人以上の入院患者に対応する施設である。(○×問題)
正解は ×。「20人以上」が正解です。こうした数値の引っかけ問題にも注意が必要です。
次章では、こうした医療施設の配置や連携を支える「医療計画」について解説します。
🌟医療計画・5事業と5疾患・地域医療構想
医療法に基づき、各都道府県は「医療計画(第6次:2024年~2029年)」を策定しています。
この計画の目的は、地域において誰もが適切な医療を受けられるよう、医療提供体制を効率よく整備することです。
✅医療計画で定められる「5事業」とは
- 1. 救急医療:急病・事故対応(救急車搬送など)
- 2. 災害医療:地震・台風など災害時の医療体制
- 3. 周産期医療:妊産婦・新生児への専門医療
- 4. 小児医療:子どもへの医療体制の整備
- 5. 地域包括ケア:高齢者を支える在宅医療・介護連携
✅重点的に対策すべき「5疾病」とは
- 1. がん
- 2. 脳卒中
- 3. 急性心筋梗塞
- 4. 糖尿病
- 5. 精神疾患
これらは死亡率・重症化リスクが高く、国民的な課題となっているため、計画的な医療体制が求められています。
✅地域医療構想と病床機能の再編
高齢化が進む中、各地域では「地域医療構想」が進められており、将来必要とされる医療需要に合わせて病床を再編しています。
- 高度急性期病床(救命救急など)
- 急性期病床(手術・集中治療)
- 回復期病床(リハビリ中心)
- 慢性期病床(療養・介護中心)
このように病床機能を分類・再配置することで、地域全体の医療資源を最適化することが狙いです。
国家試験では「5事業・5疾病」「地域医療構想」「病床機能報告制度」などが選択肢としてよく登場します。
出題対策としては「分類をセットで覚える」ことと、語呂合わせ(例:「ガンと脳と心と糖とココロ」=5疾病)なども活用しましょう。
🌟国家試験対策としての学習ポイントまとめ
ここまで学んできたように、医療概論では法律・制度・分類といった「暗記+理解」が求められます。
国家試験では、選択肢の微妙な違いや用語の定義を問う「ひっかけ問題」も多く出題されるため、ポイントを絞った学習が大切です。
✅よく出る内容を整理しよう(チェックリスト)
- 医療法の目的:「良質かつ適切な医療を効率的に提供」できる体制の確保
- 一次・二次・三次医療の定義と具体例(かかりつけ医/中規模病院/特定機能病院)
- 病院と診療所の違い:入院ベッド数の違いがポイント(20人以上 vs 19人以下)
- 助産所の特徴:医師不在で正常分娩のみを取り扱う
- 特定機能病院と地域医療支援病院:それぞれの役割と指定要件
- 5事業・5疾病:何度も問われる頻出項目(語呂合わせも有効)
- 地域医療構想と病床分類(急性期・回復期・慢性期など)
✅過去問対策のコツ
過去問を解く際は、次の点に意識を向けましょう。
- 「数字」に注目する:19人以下、20人以上、5つの事業・疾病など
- 法律や用語の主語を確認:「都道府県が策定するのは?」など
- 類似用語との混同に注意:「診療所」と「助産所」など
また、制度はすぐに改正されることもあるため、可能な限り最新版(2024年時点では第6次医療計画)に基づく内容を確認しましょう。
✅語呂合わせで覚えるヒント
暗記に苦手意識がある方には、次のような語呂もおすすめです。
- 5疾病:「がんと脳と心と糖とココロ」
- 5事業:「救災しゅうしょほう」(救急・災害・周産期・小児・包括ケア)
- 病床機能:「高・急・回・慢」と語呂で流れをイメージ
こうした工夫で、「医療概論」は覚えやすく、そして得点源にもなります。
🌟鍼灸国家試験過去問
第9回-2
成人男性の喫煙率が最も高い国はどれか。
- スウェーデン
- アメリカ合衆国
- 日本
- オランダ
第10回-1
我が国の医療制度の特色でないのはどれか。
- 自由開業医制度
- 国民皆保険制度
- 医療機関選択の自由
- 現金給付制度
第14回-2
予後不良状態にある末期患者が示す態度の5段階に含まれないのはどれか。
- 怒り
- 協働
- 否認
- 受容
第15回-2
我が国における脳死について正しい記述はどれか。
- 脳死は法制化されていない。
- 深昏睡と同じである。
- 心臓移植に用いる心臓は脳死した者から摘出される。
- 脳死の判定は医師の裁量による。
第24回-3
緩和医療について正しいのはどれか。
- がん患者以外に適用してはならない。
- 病気の早い段階で始めてはならない。
- 疾病の根治を目指すものではない。
- 心理的な痛みへの対応は不要である。
第31回-2
人生の最終段階に実施する医療を示すのはどれか。
- バイオエシックス
- QOL
- ノーマライゼーション
- ターミナルケア
第11回-2
我が国で最も有資格者が多いのはどれか。
- 薬剤師
- 医師
- はり師
- 看護師
第23回-2
平成24年度衛生行政報告例による就業者数統計で最も少ない医療職種はどれか。
- きゅう師
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師
第24回-1
嚥下訓練の実施に最も関与する職種はどれか。
- 介護支援専門員
- 精神保健福祉士
- 理学療法士
- 言語聴覚士
第25回-1
急性期病院からの退院支援において、患者および家族と相談する際に同席すべき院内の職種として最もふさわしいのはどれか。
- 保健師
- 臨床心理士
- 医療ソーシャルワーカー
- 管理栄養士
第31回-1
多職種連携によるチーム医療について望ましいのはどれか。
- リーダーを特定の職種に固定する。
- 他の職種の業務内容に立ち入らない。
- 患者・家族は参加しない。
- 職種間で目的と情報を共有する。
第27回-1
介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行うことを目的とするのはどれか。
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設
- グループホーム
- 地域包括ケア病棟
第1回-1
我が国の現状で正しいのはどれか。
- 65歳以上のすべての人が老人保健の対象者である。
- 国民健康保険にはすべての国民が加入している。
- 国民医療費の増加要因の一つに人口の高齢化がある。
- 国民医療費は約15兆円である。
第1回-2
国民医療費に含まれるのはどれか。
- 薬局でかぜ薬を求める経費
- 正常分娩の経費
- 人間ドックの経費
- 診療所の初診料
第12回-2
我が国の国民医療費に含まれるのはどれか。
- 看護の費用
- 正常分娩の費用
- 予防接種の費用
- 健康診断の費用
第14回-1
我が国の国民医療費に含まれるのはどれか。
- 正常分娩の費用
- 入院時差額費用
- 健康診断の費用
- リハビリテーションの費用
第30回-2
我が国の国民医療費に含まれるのはどれか。
- 入院時室料差額の費用
- 正常分娩の費用
- 訪問看護の療養費用
- 予防接種の費用
第3回-2
国民医療費が増す原因の中で医療の需要を増大させるのはどれか。
- 診療の専門指向
- 高度医療への患者の要求
- 医療機械の導入
- 医薬品価格の上昇
第21回-1
医療の需要を最も増大させる要因はどれか。
- 先進医療機器の導入
- 診療報酬の引き上げ
- 医療機関の増加
- 人口集団の高齢化
第26回-1
平成26年度の国民医療費について正しいのはどれか。
- 介護保険の費用が含まれる。
- 40兆円を超える。
- 国民所得比は15%を超える。
- 財源は患者負担が30%を超える。
第29回-1
我が国の国民医療費の現状について正しいのはどれか。
- 対国民所得比は15%を超える。
- 財源は患者負担が30%を超える。
- 国民一人あたりの医療費は年間30万円を超える。
- 国民医療費は50兆円を超える。
第20回-1
介護保険制度について正しい記述はどれか。
- 介護認定は保健所に申請する。
- 要介護のレベルは4段階ある。
- 短期入所サービスは居宅者に対するサービスの1つである。
- ケアプランは利用者が作成することはできない。
第27回-2
介護保険の第1号被保険者はどれか。
- 20歳以上
- 18歳以上
- 65歳以上
- 40歳以上
第28回-1
要介護者に対して、居宅、通所、短期間宿泊により、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を行うのはどれか。
- 小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護
第30回-1
介護保険制度の保険者はどれか。
- 国
- 都道府県
- 市町村
- 介護施設
第5回-2
公費負担によらない医療はどれか。
- 原子爆弾被爆者医療
- 労災保険医療
- 特定疾患治療
- 養育医療
生活保護法で現物給付を原則とする扶助はどれか。
- 医療扶助
- 住宅扶助
- 教育扶助
- 生活扶助
第17回-1
我が国の公費負担医療制度に定められていないのはどれか。
- 労災患者の入院医療費
- 未熟児の入院医療費
- 入院勧告された結核患者の入院医療費
- 措置入院された精神障害者の入院医療費
第24回-2
生活保護法による現物給付はどれか。
- 教育扶助
- 介護扶助
- 生活扶助
- 住宅扶助
第2回-1
施術者と患者との関係で正しい記述はどれか。
- 施術者は共感する態度で接してはならない。
- 患者には施術についての自己決定権はない。
- 施術者には守秘義務がある。
- 患者へのインフォームド・コンセントは必要でない。
第3回-1
施術者の倫理について誤っているのはどれか。
- 患者の人権の尊重
- QOL(生活の質)への配慮
- インフォームド・コンセントの実施
- 施術者本位の施療
第4回-1
施術者の倫理について誤っているのはどれか。
- 十分な情報の提供
- 生活の質の尊重
- 施術内容の一方的決定
- プライバシーの保護
第5回-1
インフォームド・コンセントについて直接関係ないのはどれか。
- 十分な説明
- 理解と納得
- 情報の提供
- プライバシーの保護
第6回-1
インフォームド・コンセントに含まれる権利はどれか。
- 人権尊重の権利
- 適切な治療やケアを受ける権利
- 医療上の情報や説明を受ける権利
- プライバシー保障の権利
第7回-1
施術者の倫理について誤っているのはどれか。
- 生命の尊重
- QOLの向上
- 一元的医療の考え
- プライバシーの保護
第8回-1
施術者のとるべき態度でないのはどれか。
- 施術者本位の施術
- 施術過程の記録保持
- 患者の自己決定権の尊重
- 施術内容の患者への情報提供
第9回-1
施術者の行為として適切でないのはどれか。
- 全人的な施術
- 施術内容の記録保持
- 処方せんの交付
- 賠償保険加入
第10回-2
施術者の倫理について誤っているのはどれか。
- 鎮痛薬の投与
- 守秘義務
- 患者の自己決定権の尊重
- 施術手技の研さん
第11回-1
施術者の倫理について適切でないのはどれか。
- 施術の説明と同意
- 施術内容の記録保持
- 酒気帯び状態での施術
- 自己の健康管理
第13回-1
バイオエシックスの対象でないのはどれか。
- 安楽死
- 損害賠償
- 人工授精
- 医療財政
第13回-2
インフォームド・コンセントを含む医の倫理の国際規定はどれか。
- ヒポクラテスの誓い
- ヘルシンキ宣言
- アルマ・アタ宣言
- ジュネーブ宣言
第15回-1
パターナリズム(父権主義)について正しい記述はどれか。
- 小児医療に特有の問題である。
- 患者は医療内容について説明を受け同意する。
- 治療方針は医療者が決める。
- 医師患者関係は契約関係である。
第16回-1
医の倫理と関係のないのはどれか。
- ヒポクラテスの誓い
- インフォームド・コンセント
- 公費医療給付
- 患者の権利宣言
第17回-2
施術者の倫理について誤っているのはどれか。
- 十分な情報の提供
- 施術内容の記録保持
- 患者のQOLの向上
- 患者の要求の優先
第18回-2
QOLの考え方から最も遠いのはどれか。
- 自然死
- 緩和ケア
- 尊厳死
- 延命治療
第19回-2
インフォームド・コンセントに含まれる権利はどれか。
- 治療の危険性の説明を受ける権利
- 男女の平等を求める権利
- 病院の経営状態を知る権利
- 公的医療費の扶助を受ける権利
第20回-2
医療従事者の倫理について適切でないのはどれか。
- 援助者としての立場をとる。
- 情報提供と説明を十分に行う。
- 患者の要求を優先する。
- 守秘義務がある。
第23回-1
個人情報保護法による患者情報の取り扱いについて正しいのはどれか。
- 本人への開示を遅滞しない。
- 苦情へは対処しない。
- 内容を更新しない。
- 利用目的は特定しない。
第26回-3
施術者の倫理について正しいのはどれか。
- 収益向上のためにはQOLは考えなくてもよい。
- 業務上知り得た患者の秘密は研究目的であっても漏らしてはならない。
- 「ヒポクラテスの誓い」は現代には通用しない。
- 「患者の権利宣言」は日本には適用されない。
第27回-3
患者に対する施術者の役割で適切なのはどれか。
- 援助者
- 指導者
- 管理者
- 保護者
第29回-2
患者が治療に対して積極的に関わり、その決定を遵守するのはどれか。
- コンプライアンス
- 患者の自己決定権
- アドヒアランス
- インフォームド・コンセント
第30回-4
患者が「よろしくお願いします」と言い、医療従事者が「お任せください」と言う会話から考えられる両者の関係はどれか。
- インフォームド・アセント
- インフォームド・コンセント
- セカンドオピニオン
- パターナリズム
第31回-4
「医師は子どものことを思う親のように、患者は親に保護される子どものように行動する」と表現される医療従事者と患者の関係性はどれか。
- セカンドオピニオン
- パターナリズム
- 契約モデル
- 工学モデル