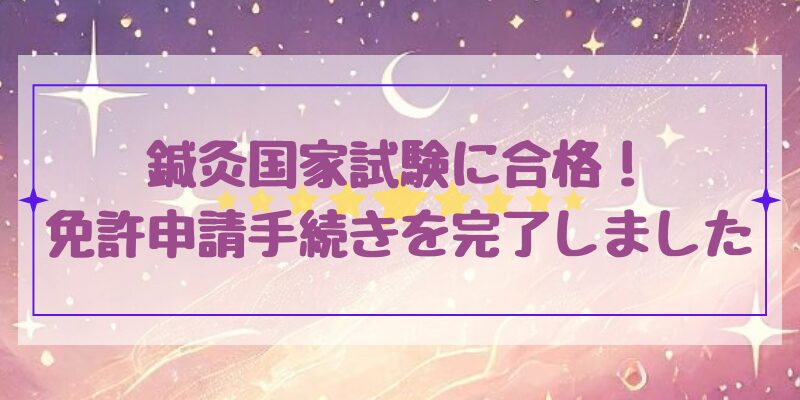🌟鍼灸国家試験に合格!でもすぐには鍼灸できないって本当?
令和7年3月26日午後2時、ついに鍼灸国家試験の合格発表がありました。
合格発表の前から「たぶん受かってるはず」と思いつつも、やっぱり万が一もあるわけで…。
落ちたときのダメージを考えて、どうしても準備が中途半端になっていました。
でも、受験番号があったときのあの瞬間。「やったー!」よりも、「やっと終わった…」という脱力感が強かったです。
そして、すぐに思ったのが「開業届け、出さなきゃ!」ということ。
実はKagayaは4月1日に保健所へ開業届を出しに行く予定だったのですが、よくよく確認してみたら、すぐに開業できるわけではなかったんです。
なぜかというと、「鍼灸治療ができるのは名簿登録が完了してから」だから。
つまり、国家試験に合格しても、すぐに鍼や灸を使った施術はできないということになります。
これは、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律(いわゆるあはき法)にも記載されています。
厚生労働省からの指導では、名簿登録まで約2週間かかるとされています。
そして免許証が手元に届くのは、だいたい1か月後の5月頃になるケースが多いようです。
実際、看護師のときもそうでした。
「合格=即、看護師」と思っていたら、免許証が来るまで何もできなかった記憶があります。
ということで、開業届けを出すタイミングも名簿登録を見越して調整しなければいけません。
勢いで手続きしてしまうと、違法施術扱いになってしまう可能性もあるので注意が必要です。
それにしても驚いたのが、免許の申請手続きは全部自分でやらないといけないということ。
看護師のときは学校が一括でやってくれた記憶があるので、「えっ?全部自分で?収入印紙も?」と最初は戸惑いました。
さらにお金もかかります。
受験料だけで4万円近く払ったのに、免許申請にもまた約4万円かかるのです。
ある知人が「鍼の免許だけ取れば灸は申請しなくていいかも」と冗談半分に言っていました。
たしかに「はり師」だけでも最低限の施術は可能です。
でも将来的に灸頭鍼などの技術を使う可能性も考えると、両方申請しておいたほうが安心ですね。
Kagayaは「どうせやるならちゃんと両方取っておこう」と思い、鍼も灸も申請する方向で進めました。
なお、合格発表の時点で申請に必要な書類を一式揃えておくと、スムーズに手続きができます。
名簿登録を一日でも早く完了させたい人には、事前準備がとても大事です。
Kagayaも事前に調べて、診断書や住民票、必要書類の記入など、できることは先に終わらせておきました。
🌟診断書の取得体験談と注意点
鍼灸師の免許申請に必要な書類のひとつが、医師による「診断書」です。
この診断書は、「業務遂行に支障をきたす精神疾患がないこと」「麻薬中毒などに該当しないこと」を医師が確認し、証明するものです。
国家資格にふさわしい人間かどうかを判断するためのものですね。
Kagayaは今回、立川クリニックで診断書をお願いしました。
事前に電話などで予約を取る必要はなく、当日そのまま行っても対応してもらえるとのことだったので、思い立って午前中に訪問。
しかし、同じような申請目的の方や風邪症状の方で混み合っていて、結果的に1時間以上の待ち時間となりました。
時期的に、待合室では咳をしている人も多く、「うつされたらどうしよう…」と内心ヒヤヒヤ。
感染症対策としてマスクは必須ですね。
呼ばれて診察室に入ると、初老の穏やかな医師が対応してくれました。
診察はいたってシンプル。
問診と軽い視診、そして腕をじっくり見て「注射跡がないか」を確認されました。
「この診断書って、麻薬中毒者じゃないことも見るんですよ」と説明を受け、「まあ、麻薬中毒なら病院に来ないでしょうけどね〜」とユーモアを交えた言葉に、少し緊張がほぐれました。
ちなみに、精神疾患の有無については、あくまで医師の主観的判断で、特別な検査などは行われません。
現在治療中かどうか、日常生活に支障があるかなどを質問される程度です。
診断書の発行料は2,000円(税込)でした。
これが高いか安いかは病院によってまちまちですが、Kagayaの感覚では「思ったより安かったな」という印象です。
ネット上では、都内で4,000円〜5,000円を請求されるケースもあるとのことで、2,000円で即日発行してくれるのは良心的かもしれません。
ただし、注意点としては、
- 病院によっては予約制であること
- 診断書の内容が指定されている場合があること
- 即日発行できない場合もあること
このあたりは、必ず事前に確認しておくと安心です。
できれば免許申請書のフォーマット(または学校から配布されたもの)を持参するとスムーズに話が進みます。
診断書は、国家試験の合否が確定する前に取得しても問題ありませんが、有効期限が設けられている場合もあるため、申請書類とあわせて確認しておきましょう。
Kagayaは合格発表の少し前に取得しましたが、何かあって取り直すことになったら嫌だったので、ギリギリにしてもよかったかもしれません。
まとめると、診断書は手続きの中ではそれほど難易度の高いステップではありませんが、病院選びとタイミングには注意が必要です。
🌟住民票の取得と本籍記載の落とし穴
免許申請で必要になるもう一つの重要書類が「住民票」です。
Kagayaは看護師免許を申請した際には「戸籍謄本」が必要だった記憶があり、そのときは本籍地がある青森の親戚にお願いして、わざわざ代理で取ってきてもらいました。
手間もお金もかかって、なかなか大変な思い出です。
なので今回も同じように、戸籍謄本がいるのかな?と思いながら、ついでに青森旅行がてら取りに行こうと計画していたのですが、調べてみると今回の鍼灸師免許申請では「本籍が記載された住民票」でOKとのことでした。
え、そうなの?本籍記載の住民票なら東京都内で取得できるじゃん…!ということで、慌てて計画を変更。
Kagayaが住んでいる小平市では、住民票の取得は出張所の窓口でもできます。
ただし、本籍入りの住民票は窓口申請限定で、スマホ申請や郵送では対応していません。
そしてここで活躍するのが、マイナンバーカード。
最近ではコンビニ交付サービスが普及していて、セブンイレブンやファミリーマートなどのマルチコピー機を使って、手軽に住民票が取得できるようになっています。
ただし注意点として、本籍地の記載がある住民票をコンビニで出力できるかどうかは自治体によって異なります。
小平市の場合は可能でしたが、すべての市区町村で対応しているわけではありません。
申請前に、自治体の公式ホームページや役所に電話で確認しておくと安心です。
Kagayaは結局、小平市の出張所で窓口申請し、無事に本籍記載の住民票を取得することができました。
発行手数料は200円。
手続きもすぐに完了し、「これで青森までの旅費が浮いた!」と少し得した気分に(笑)。
もちろん、青森への旅行はいつかゆっくり観光で行きたいと思っているのですが、今回のように急ぎの手続きや申請がある場合は、やはり手間と費用を減らせる方法を選ぶことが大事だと実感しました。
なお、住民票の申請用紙にある「本籍・筆頭者を記載するか否か」の項目には、必ずチェックを入れるようにしましょう。
これが記載されていない住民票では、申請書類として不備となってしまう可能性があります。
また、住民票の有効期限についても要注意です。
多くの提出先では「発行から3か月以内」とされています。
つまり、あまりに早く取りすぎると使えなくなることも。
Kagayaの場合は、合格発表の直前に取りましたが、もし不合格だったら住民票が無駄になるところでした(泣)
住民票ひとつとっても、意外と落とし穴が多いもの。
手軽に取得できるようになったとはいえ、本籍記載・有効期限・記載内容の確認はしっかり行いましょう。
🌟鍼師と灸師で別々!? 申請書記入の落とし穴
鍼灸師というと、ひとつの資格のように聞こえますが、実は違います。
「はり師」と「きゅう師」は、それぞれ独立した国家資格であり、免許申請も個別に行わなければなりません。
これはつまり、申請書類も2枚用意して、2回記入する必要があるということです。
Kagayaは最初これを知らず、「えっ、別々なの?!」と驚きました。
学校の先生にも言われていたのに、書類を手にして初めて実感しました。
「鍼灸師って言うんだから、ひとつの申請でいいじゃん」と思ったのは、きっとKagayaだけではないはずです。
正直、ちょっとした疑問と違和感を感じます。
だって、3年間「鍼灸師養成課程」で学んで、まとめて国家試験を受けたのに、申請では分けるって、ちょっと理不尽じゃないですか?
これは国家資格としての制度上の区分で、法律的には「はり師免許証」「きゅう師免許証」という2枚の免許証が発行されるため、それぞれに別の申請書が必要になるという仕組みです。
実際の申請書類は、基本情報(氏名・住所・生年月日など)に加え、合格した国家試験の回数、受験番号などを記載する必要があります。
この情報、当然「はり」も「きゅう」も同じなのに、2枚に分けて記入するって…うん、めんどくさい(笑)。
もうひとつのポイントは、事前に記入しておくことの重要性です。
当日、慌てて記入して郵送するとなると、記載ミスや不備が起こりやすく、結果として手続きに時間がかかってしまいます。
Kagayaは合格発表前に記入を済ませて、内容だけ空欄にしておいて、合格したら番号だけ書き込むように準備しておきました。
あとは収入印紙の貼付位置や封筒の記載方法など、申請時に間違いやすいポイントも事前にチェックリストで確認しておくと安心です。
そして、これも声を大にして言いたい。
「申請書類の書式がめっちゃ古い」。
パソコン入力やオンライン申請が主流の時代に、手書きオンリー&郵送って…。
制度改正が進むことを願います。
そんなわけで、はり師・きゅう師を同時に申請する人は、申請書2通+印紙2つ必要になるので、準備は念入りに。
🌟意外と高い!? 申請手数料と収入印紙のリアルコスト
国家試験に合格して、ほっとひと息…。
そんな余韻に浸る間もなく待っているのが、「免許申請の手続き」です。
この章では、申請にかかるお金──特に申請手数料と収入印紙代について、実際の金額や支払い方法、注意点をリアルにお伝えします。
まず結論から言うと、申請に必要な費用は合計で約2万円弱です。
- はり師免許:収入印紙 9,000円
- きゅう師免許:収入印紙 9,000円
- 登録手数料(振込):11,200円
はり・きゅう両方を申請する場合は、18,000円分の収入印紙+11,200円の振込手数料=約3万円近い出費になります。
この金額を見て、「いやいや、受験料で4万円近く払ったばかりなのに、また3万円?!」と、さすがに驚きました。
もちろん国家資格としての登録には事務的なコストがかかることは理解していますが、「合法的ボッタクリ」と感じてしまうのも正直なところです。
ちなみに、収入印紙は郵便局や一部のコンビニで購入可能です。
ただし、9,000円分の収入印紙をコンビニで売っているケースは少ないので、最寄りの大きめの郵便局での購入がおすすめです。
注意したいのは、収入印紙は一度購入すると返金できないということ。
いくら「ほぼ受かってる!」という自信があっても、合格発表前に収入印紙を購入するのはリスクが伴います。
Kagayaも診断書や住民票については「万が一ムダになっても仕方ないか」と思って先に準備していましたが、収入印紙と登録料の振込は合格が確定するまで待ちました。
登録手数料11,200円は、指定された口座にATMや窓口から振込を行う形式です。
振込の際は、必ず氏名と生年月日を併記して送金する必要があります。
ここを間違えると処理に時間がかかり、名簿登録の遅延につながる可能性もあるので要注意です。
そして、これらの書類や印紙、振込明細などをすべて封筒にまとめて、指定の提出先(厚生労働省所管の担当課)へ郵送。
Kagayaはこの一連の流れを、合格発表当日にすべて終わらせました。
仕事を早退して、郵便局へダッシュ。
まるで申請マラソン(笑)。
ちなみに、提出後から名簿登録が完了するまでにはおよそ2週間かかるとされています。
免許証が届くのはさらにその後になります。
ということで、申請費用は事前に心構えしておくべし!
🌟合格発表当日のリアルな動きと郵送手続き
いよいよ迎えた、鍼灸国家試験の合格発表日。
令和7年3月26日、午後2時。待ちに待ったこの瞬間、胸のドキドキはピークに達していました。
この日は朝から落ち着かず、仕事に集中できるわけもなく…。
午後からは早退させてもらい、スマホ片手に合格発表ページを更新しながら、郵便局へと向かいました。
看護師国家試験のときは、学校のパソコン室にみんなで集まって、一斉に番号を確認したのを覚えています。
「あった!」「やったー!」と叫び声が飛び交い、拍手と涙のオンパレードでした。
でも鍼灸の専門学校では、そんなイベントはありませんでした。
そもそも学校にはパソコン室自体がないという現実(笑)。
結局、Kagayaはひとりで静かにスマホを開き、自分の受験番号を確認しました。
番号を見つけた瞬間、「やった!」よりも、「ホッとした…」という安堵感が大きかったです。
ここまでの努力が、ようやく報われた気がしました。
そこからは、感傷に浸る間もなく、手続きを一気に済ませなければなりません。
- 郵便局で収入印紙(はり・きゅう 9,000円ずつ)を購入
- 指定口座に登録手数料(11,200円)を振り込み
- 診断書、住民票、申請書類を再確認
- 封筒に全てを同封して、指定先へ速達で郵送
Kagayaはすべての準備を終えていたので、合格が確認できた瞬間から1時間以内に投函まで完了しました。
このスピード感、大事です。
なぜなら、名簿登録は書類が到着した順に処理されるから。
申請が早ければ、名簿登録も早まり、それだけ早く免許証も届きます。
つまり、開業や施術をスタートできる時期が早まるのです。
ちなみに、申請書類の送付先は都道府県によって異なるので、送付前に厚労省や都道府県の公式サイトで再度確認しましょう。
封筒には「鍼師・きゅう師 免許申請書類在中」としっかり明記し、必要があれば簡易書留や速達を利用するのがおすすめです。
追跡番号もあるので安心です。
提出が完了したあとは、登録されるまで約2週間。
その後、正式に名簿に記載され、晴れて「免許保持者」となります。
この間は施術行為ができないため、開業や施術のスケジューリングも慎重に立てる必要があります。
Kagayaはこの空白の2週間で、チラシやHP作成、備品の整理に力を入れて過ごしました。
改めて感じたのは、合格して終わりではなく、そこからが本当のスタートだということ。
🌟まとめ|AI時代でも生き残る“鍼灸師×看護師”という選択肢
少し話は逸れますが、先日テレビで放送された「世界一受けたい授業」で、“AIによって将来なくなる職業”が特集されていました。
そのリストの中にはなんと、医師や薬剤師といった医療系の職種も含まれていたのです。
「えっ、あれだけ難しい勉強をして、国家資格を取って、長い実務経験を積む職業でもAIに取って代わられるの…?」と、正直驚きを隠せませんでした。
確かに、AIやロボット技術の進化によって、病理診断・処方設計・検査データの解析などは、高精度に自動化されつつあります。
医師や薬剤師の知識や技術を、AIが代替する未来が来る可能性は否定できません。
でも、番組内で興味深かったのは、「なくならない職業」として、看護師やリハビリ職、介護職が取り上げられていたことでした。
それを見たとき、「やっぱり、人の手・心・まなざしでしか成り立たないケアには、AIは入り込めないんだな」と改めて実感しました。
さらにリストを見ていくと、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、そして鍼灸師の名前はありませんでした。
…いや、そもそも知られていないだけでは?というツッコミを入れたくなる気持ちもありますが(笑)、逆にいえば、「まだAIが真似できない職業」として生き残っているのかもしれません。
実際、鍼や灸を打つ行為は、ツボの選定・体調や皮膚の状態の見極め・繊細な触診など、高度な感覚と経験が必要です。
機械が精密に動けたとしても、「この人には今、どんな刺激が最適か?」という判断や、患者さんの表情から感情を読み取って声をかけることは、人間にしかできないことです。
Kagayaは、鍼灸師としての感覚に加えて、看護師としての視点を持てるというのは、今後さらに大きな強みになると感じています。
医療現場での臨床判断、観察力、全人的な視点、そしてコミュニケーションスキル。これらをベースに、東洋医学の知識と技術を加えることで、「人にしかできないケア」を提供できるのではないかと思います。
国家試験を受けて、免許申請をして、やっとここまで来たけれど、これはゴールではなく「スタートライン」。
どんな時代が来ようとも、技術だけでなく「あなたにやってほしい」「あなたに話を聞いてほしい」と言ってもらえる存在になれるよう、日々学び続けたいと思います。
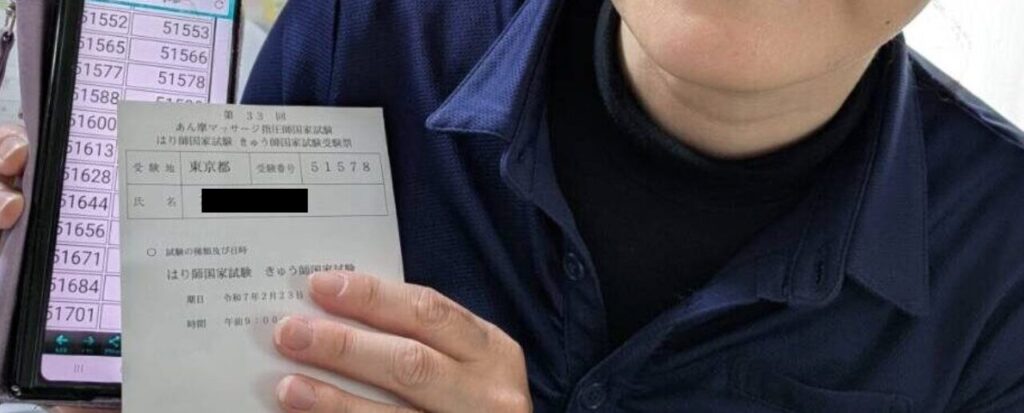
\免許を取ったその先に/
きらぼしではこんな施術活動をしています!
鍼灸師×看護師として、プライマリ・ケアサポートきらぼしでは
以下のようなケアを行っています。
- 🔹 自律神経の乱れや慢性疲労へのケア
- 🔹 小児・障がい児(者)への訪問鍼灸+療育
- 🔹 精神科訪問看護の知識を活かしたメンタルサポート
- 🔹 ご自宅でのリラックス灸ケア・セルフケア指導
Kagaya自身が免許取得後に試行錯誤してきたことを、ブログや施術を通して皆さんにお届けしています。
国家試験に合格したばかりの方や、これから開業を考えている方も、ぜひ気軽にご相談くださいね。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら