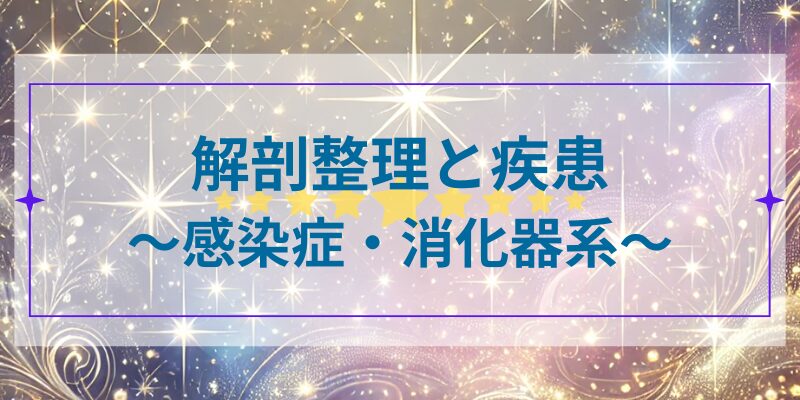感染症
細菌感染症
- 猩紅熱
- 肺炎球菌性肺炎
- 腸チフス、パラチフス
- 破傷風
- ジフテリア
- 細菌性赤痢
- レジオネラ症
- コレラ
- 百日咳
ウイルス感染症
- ポリオ(急性灰白髄炎)
- 麻疹(はしか)
- 風疹
- 伝染性単核(球)症
- 流行性角結膜炎
- 流行性耳下腺炎
- 手足口病
- インフルエンザ
- 突発性発疹
- 水痘・帯状疱疹
- 咽頭結膜熱
性感染症
- 性器クラミジア感染症
- 梅毒
- エイズ
感染症の分類
- 連鎖球菌感染症
- 猩紅熱
- 肺炎球菌性肺炎
- エンテロウイルス感染症
- 手足口病
- ポリオ
- アデノウイルス感染症
- 咽頭結膜熱
- 流行性角膜炎
- ヘルペス感染症
- 水痘・帯状疱疹
- 流行性単核(球)症
- 突発性発疹
水痘・帯状疱疹
- 空気感染、接触感染
- 初期感染⇒水痘(小児期)
- 急性丘疹性疾患
- 発熱と皮疹(紅色丘疹⇒水痘⇒膿疱⇒痂皮)
- 潜伏感染⇒三叉神経節や脊髄後根神経節に潜伏
- 免疫力低下⇒回帰感染
- 帯状疱疹(高齢者)
- 片側上半身
- 帯状の水疱、赤い発疹、痒み
- 神経様疼痛
- 知覚過敏
- 顔面神経麻痺⇒ラムゼイ・ハント症候群
エイズ(後天性免疫不全症候群)
- ヒト免疫不全ウイルス(HIV)⇒CD4陽性Tリンパ球
- 性感染
- 血液感染
- 母子感染
- 経過
- 急性期⇒風邪に似た症状
- 無症候期⇒長い潜伏期間
- エイズ関連症候群⇒体重減少、発熱、下痢
- エイズ発症期⇒ニューモシスチス肺炎、悪性腫瘍
- 診断
- HIV抗体検査陽性
- 日和見感染症、悪性腫瘍
- CD4陽性Tリンパ球減少
核感染症の特徴
- 偽膜性大腸炎
- 抗生物質による菌交代現象により、クロストリジウム・ディフィシルが大量に増殖して発生する内因性感染
- 3種混合ワクチン
- 百日咳
- ジフテリア
- 破傷風
- 院内感染と関連がある黄色ブドウ球菌
- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)
- 猩紅熱
| 病態 | A群溶血連鎖球菌感染症の飛沫感染 小児 |
| 症状 | 発症後24時間以内に全身の発赤 イチゴ舌、口囲蒼白 |
- 破傷風
| 病態 | 破傷風菌が傷口から侵入して感染 外毒素が神経行性に運ばれて中枢神経を侵す 潜伏期間3日~3週間 |
| 症状 | 創傷部周辺の緊張・痙攣・項部硬直・便秘・頻脈を発症 後弓反張、開口障害、嚥下障害、顔面けいれん |
- ジフテリア
| 病態 | 潜伏期間1~7日 |
| 症状 | 発熱、咽頭痛、偽膜形成、気道閉塞 心筋・神経障害の合併症 |
- 麻疹(はしか)
| 病態 | 3歳以下の小児 潜伏期間10日 |
| 症状 | カタル期・発疹期・回復期に分けられる カタル期:発熱、咳、鼻水、結膜炎、コプリック班 発疹期:発症後3~4日に解熱後、再び高熱が出て丘疹性発疹が出る |
- 風疹(三日ばしか)
| 病態 | 小学生低学年に好発する急性発疹性疾患 2~3日で軽快 |
| 症状 | 発熱、発疹、リンパ節腫脹 妊婦が感染した場合、胎児が先天性麻疹症候群を起こす可能性がある |
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
| 病態 | ムンプスウイルスによる飛沫感染 潜伏期間2~3週間 |
| 症状 | 発熱、耳下腺腫脹 髄膜炎、精巣炎(睾丸炎)、卵巣炎、難聴、膵炎を合併することあり 思春期以降の男性が発症すると30%の確率で精巣炎を合併する |
- 梅毒
| 病態 | 梅毒トレポネーマ(スピロヘータ)による感染 性行為感染 母子感染⇒先天性梅毒 |
| 症状 | 1期:所属リンパ節腫脹 2期:バラ疹、扁平コンジローム、脱毛 3期:ゴム腫 4期:大動脈瘤、進行麻痺 |
- ボツリヌス菌食中毒
| 病態 | 細菌性食中毒 潜伏期18時間前後 加熱により不活性化する |
| 症状 | 神経毒による球麻痺症状 眼症状 唾液・汗・涙の分泌障害 |
正しい組合せはどれか。
- 流行性耳下腺炎 ─── ムンプスウイルス感染
- 消化性潰瘍 ───── 大腸菌感染
- イレウス ────── アレルギー
- 虫垂炎 ─────── ビタミンC欠乏
感染症について正しい組合せはどれか。
- 日本脳炎 ─── 細菌
- 狂犬病 ──── リケッチア
- 百日咳 ──── ウイルス
- コレラ ──── 細菌
感染症と媒介生物の組合せで正しいのはどれか。
- トキソプラズマ症 ――― シラミ
- デング熱 ――――――― 蚊
- 日本脳炎 ――――――― ネズミ
- 発疹チフス ―――――― ダニ
感染症とその特徴との組合せで正しいのはどれか。
- 帯状疱疹 ────── 痂皮
- 麻疹 ──────── イチゴ舌
- 流行性耳下腺炎 ─── コプリック斑
- 猩紅熱 ──────── 精巣腫脹
ウイルスと疾病との組合せで誤っているのはどれか。
- ヘルペスウイルス ─── 帯状疱疹
- アデノウイルス ──── 流行性角膜炎
- ノロウイルス ───── 食中毒
- ライノウイルス ──── 手足口病
疾病と感染経路との組合せで誤っているのはどれか。
- 風疹 ──────── 胎盤感染
- インフルエンザ ─── 飛沫感染
- 破傷風 ─────── 経口感染
- エイズ ─────── 性行為感染
疾患と病原体との組合せで誤っているのはどれか。
- トラコーマ ────── クラミジア
- トキソプラズマ症 ─── マイコプラズマ
- エイズ ──────── HIV
- アスペルギルス症 ─── 真菌
疾患と病原体との組み合わせで誤っているのはどれか。
- 水痘 ──────── 帯状疱疹ウイルス
- 流行性耳下腺炎 ─── サイトメガロウイルス
- 急性灰白髄炎 ──── ポリオウイルス
- 猩紅熱 ─────── A群溶血性連鎖球菌
疾患と症状との組合せで誤っているのはどれか。
- 細菌性赤痢 ─── 膿粘血便
- 猩紅熱 ───── コプリック斑
- ジフテリア ─── 咽頭・喉頭偽膜
- 破傷風 ───── 牙関緊急
細菌性腸炎の原因菌と食品の組合せで誤っているのはどれか。
- カンピロバクター ――― 鶏肉
- 腸炎ビブリオ ――――― 生鮮魚介類
- サルモネラ属 ――――― ハチミツ
- ブドウ球菌 ―――――― にぎりめし
感染症について正しい記述はどれか。
- 生命に対する危険度が最も高いのは5類感染症に分類される。
- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌は院内感染の原因になる。
- 腸管病原性大腸菌で起こる感染症を菌交代症という。
- 大量の抗菌薬を投与しないと日和見感染が起こる。
感染症について正しいのはどれか。
- 麻疹は「三日ばしか」と言われている。
- 帯状疱疹は単純ヘルペスウイルスによる感染である。
- 梅毒はクラミジアによる感染である。
- インフルエンザウイルス感染は迅速な検査が可能である。
感染症について正しいのはどれか。
- ムンプスウイルスは空気感染する。
- 風疹は精巣炎を合併する。
- MRSAは院内感染の原因となる。
- ボツリヌス菌による食中毒の主たる症状は血便である。
感染症について正しいのはどれか。
- 風疹は「三日ばしか」と言われる。
- 流行性耳下腺炎は空気感染する。
- 日本脳炎はネズミの媒介によって感染する。
- 水痘は精巣炎を合併しやすい。
食事後最も短時間で発症する食中毒の原因菌はどれか。
- 腸炎ビブリオ
- 病原大腸菌
- サルモネラ
- ブドウ球菌
感染型細菌性食中毒の原因菌でないのはどれか。
- カンピロバクター
- 腸炎ビブリオ
- ボツリヌス菌
- サルモネラ菌
細菌性食中毒で正しい記述はどれか。
- サルモネラ属は潜伏期が1週間である。
- ボツリヌス菌毒素は高温加熱によっても不活性化されない。
- 腸管病原性大腸菌ではベロ毒素によって発症する。
- 腸炎ビブリオによる食中毒はボツリヌスより発症頻度が低い。
潜伏期が最も短い食中毒の原因菌はどれか。
- 腸炎ビブリオ
- サルモネラ属
- ボツリヌス菌
- ブドウ球菌
ウイルスが原因となる疾病はどれか。
- エイズ
- 発疹チフス
- 淋病
- ジフテリア
DNAウイルスはどれか。
- 麻疹ウイルス
- 風疹ウイルス
- B型肝炎ウイルス
- エイズウイルス(HIV)
ウイルス性の経口感染症はどれか。
- ポリオ
- コレラ
- 赤痢
- 麻疹
水系流行による感染症でないのはどれか。
- 結核
- ワイル病
- コレラ
- ポリオ
性行為感染症でないのはどれか。
- クラミジア感染症
- A型肝炎
- エイズ
- 尖圭コンジローマ
垂直感染を起こさないのはどれか。
- エイズ
- A型肝炎
- トキソプラズマ症
- B型肝炎
血液を介して感染する疾患はどれか。
- 結核
- C型肝炎
- 赤痢
- インフルエンザ
蚊が媒介する感染症はどれか。
- 日本脳炎
- エイズ
- 腸チフス
- ペスト
新興感染症はどれか。
- 結核
- コレラ
- エイズ
- マラリア
蚊が媒介する感染症はどれか。
- 麻疹
- コレラ
- 赤痢
- マラリア
病原微生物が関与する癌はどれか。
- 肺癌
- 食道癌
- 肝細胞癌
- 乳癌
4類感染症はどれか。
- 腸管出血性大腸菌感染症
- コレラ
- 細菌性赤痢
- 狂犬病
努力義務とされていない予防接種はどれか。
- 流行性耳下腺炎
- 百日咳
- 破傷風
- ジフテリア
予防接種法による二類疾病はどれか。
- 日本脳炎
- 風疹
- インフルエンザ
- 破傷風
エイズについて誤っている記述はどれか。
- 世界では北アメリカ地域の患者数が最も多い。
- 我が国の患者数は増加している。
- 感染症法の対象疾患である。
- 感染はウイルスによる。
人畜共通感染症(人獣感染症)でないのはどれか。
- 日本脳炎
- 結核
- 狂犬病
- ポリオ
予防接種に生菌ワクチンが使用されているのはどれか。
- ジフテリア
- インフルエンザ
- 麻疹
- 破傷風
真菌による疾患はどれか。
- ツツガムシ病
- カンジダ症
- ウエストナイル熱
- マラリア
ウイルスによる感染症はどれか。
- オウム病
- 百日咳
- エボラ出血熱
- マラリア
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)で1類感染症はどれか。
- 後天性免疫不全症候群(AIDS)
- コレラ
- エボラ出血熱
- 重症急性呼吸器症候群(SARS)
後天性免疫不全症候群は感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)で何類に分類されているか。
- 3類
- 2類
- 4類
- 5類
後天性免疫不全症候群について感染の危険性があるのはどれか。
- 唾液
- 涙
- 母乳
- 汗
ダニ以外で媒介される疾患はどれか。
- 日本脳炎
- ツツガムシ病
- 重症熱性血小板減少症候群
- 日本紅斑熱
五類感染症はどれか。
- ジフテリア
- 後天性免疫不全症候群
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 急性灰白髄炎
体液を介して感染する疾患はどれか。
- 腸チフス
- B型肝炎
- 破傷風
- コレラ
我が国で予防接種が行われていないのはどれか。
- 後天性免疫不全症候群
- 麻疹
- 水痘
- 結核
我が国の院内感染で問題となっている病原体はどれか。
- 鳥インフルエンザウイルス
- MRSA
- 破傷風菌
- 日本脳炎ウイルス
細菌感染症はどれか。
- マラリア
- デング熱
- ハンセン病
- SARS
地球上から根絶された感染症はどれか。
- 破傷風
- コレラ
- ポリオ
- 痘そう
予防接種に生ワクチンを使用するのはどれか。
- 百日咳
- 肺炎球菌
- 日本脳炎
- 麻疹
リケッチア感染症はどれか。
- 梅毒
- ジフテリア
- ツツガムシ病
- デング熱
再興感染症はどれか。
- ウエストナイル熱
- SARS
- エボラ出血熱
- 結核
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に定められた感染症で致命率が最も高いのはどれか。
- エボラ出血熱
- デング熱
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 中東呼吸器症候群(MERS)
空気感染対策が有効なのはどれか。
- 赤痢
- 結核
- ポリオ
- コレラ
結核対策で早期発見を目的とするのはどれか。
- 家庭訪問指導
- 定期予防接種
- 結核登録
- 定期健康診断
帯状疱疹について誤っている症状はどれか。
- 小水疱を伴う発疹
- 悪寒を伴う高熱
- 皮膚の発赤
- 神経痛様疼痛
皮膚疾患について正しいのはどれか。
- 円形脱毛症はウイルス感染が原因である。
- 帯状疱疹は分節性の神経性皮膚炎である。
- 接触性皮膚炎はウイルスとの接触により起こる。
- 脂漏性湿疹は油脂を取り扱う人に多い。
エイズ感染の原因とならないのはどれか。
- 輸血
- 握手
- 針刺し事故
- 性交渉
創傷感染症について正しい記述はどれか。
- せつ、ようの原因は連鎖球菌が多い。
- 蜂巣織炎とは筋肉の感染症である。
- ひょう疽は四肢の慢性炎症をいう。
- 破傷風菌の毒素は中枢神経を障害する。
呼吸器を介して感染する疾患はどれか。
- 日本脳炎
- マラリア
- A型肝炎
- 風疹
皮膚化膿症の主な原因となる菌はどれか。
- ガス壊疽菌
- ブドウ球菌
- 緑膿菌
- 大腸菌
ウイルス感染症でないのはどれか。
- 脊髄癆
- 日本脳炎
- 急性灰白髄炎(ポリオ)
- ヘルペス脳炎
ヘルペスウイルスの感染症でないのはどれか。
- 水痘
- 手足口病
- 突発性発疹
- 帯状疱疹
エイズについて正しい記述はどれか。
- 予防接種が有効である。
- 食物からも感染する。
- 感染者は隔離の必要がある。
- ウイルスが原因である。
細菌が原因となる感染症はどれか。
- 腸チフス
- インフルエンザ
- カンジダ症
- C型肝炎
日和見感染の原因でないのはどれか。
- カンジダ
- インフルエンザウイルス
- ニューモシスチス・カリニ
- 緑膿菌
感染症で誤っている記述はどれか。
- 伝染性単核症では頸部リンパ節が腫脹する。
- 腸炎ビブリオ食中毒の潜伏期は数日間である。
- カリニ肺炎はエイズに合併する。
- 単純性疱疹は再発する。
性行為感染症でないのはどれか。
- クラミジア感染症
- 副睾丸結核
- 淋病
- 梅毒
感染が原因でない疾患はどれか。
- よう
- 化膿性骨髄炎
- ひょう疽
- 大動脈炎症候群
破傷風について正しい記述はどれか。
- 菌の内毒素によって発症する。
- 経口的な感染が多い。
- 予防にワクチンが有効である。
- 破傷風菌は好気性である。
食中毒の原因で致死率が最も高いのはどれか。
- ボツリヌス菌
- 黄色ブドウ球菌
- 腸炎ビブリオ
- サルモネラ属
「施術後、患者の血液のついた鍼を廃棄する時に誤って施術者の指に刺さった。」 鍼刺し事故後、感染率が最も高いのはどれか。
- 成人T細胞白血病
- C型肝炎
- HIV感染症
- B型肝炎
アデノウイルス感染症はどれか。
- 突発性発疹
- 手足口病
- 流行性角結膜炎
- 伝染性単核球症
アデノウイルス感染症はどれか。
- 手足口病
- 流行性角結膜炎
- 流行性耳下腺炎
- 伝染性単核球症
帯状疱疹の治療に用いられるのはどれか。
- 抗真菌薬
- 抗寄生虫薬
- 抗ウイルス薬
- 抗菌薬
帯状疱疹について正しいのはどれか。
- 発疹は両下肢に好発する。
- 小児期に発症する。
- 抗ウイルス薬が有効である。
- コプリック斑が出現する。
潜伏期間が最も長いのはどれか。
- 流行性耳下腺炎
- 破傷風
- ジフテリア
- エイズ
季節性インフルエンザウイルス感染症の特徴で正しいのはどれか。
- 感染経路は飛沫感染である。
- 膿性痰を認める。
- ワクチンで感染を防ぐことができる。
- 潜伏期は1週間前後である。
院内感染と関連が深いのはどれか。
- 肺炎球菌
- 破傷風菌
- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
- A群溶血連鎖球菌
院内感染と関連が深いのはどれか。
- MRSA
- ボツリヌス菌
- 肺炎球菌
- 破傷風菌
細菌感染症はどれか。
- 百日咳
- 流行性角結膜炎
- 手足口病
- 帯状疱疹
細菌感染症はどれか。
- デング熱
- 日本脳炎
- 手足口病
- 破傷風
予防接種が有効な感染症はどれか。
- 猩紅熱
- 百日咳
- C型肝炎
- 腸チフス
「26歳の男性。全身倦怠感を主訴に来院した。視診上、黄疸を認め、ウイルスマーカー検査ではIgM-HA抗体陽性、HBs抗原陰性、HCV-RNA陰性であった。」感染の原因として最も考えられるのはどれか。
- 鶏生肉
- いずし
- 生ガキ
- ハンバーガー
「26歳の男性。全身倦怠感を主訴に来院した。視診上、黄疸を認め、ウイルスマーカー検査ではIgM-HA抗体陽性、HBs抗原陰性、HCV-RNA陰性であった。」本疾患で正しいのはどれか。
- 発熱を前駆症状として発症する。
- 慢性化する。
- 輸血によっても発症する。
- インターフェロン療法が有効である。
消化器系
胃
- 横隔膜のすぐ下にある
- 第11胸椎の高さで食道からつながる
- 胃の粘膜
- 胃小窩
- 粘膜の表面にあるくぼみ
- 胃腺の開口部がある
- 胃腺
- 胃液やホルモンが分泌される
- 噴門腺
- 粘液細胞
- 幽門腺
- G細胞⇒ガストリンを血液中に分泌する
- 胃底腺
- 主細胞⇒ペプシノゲンを分泌する
- 副細胞⇒ムチンを分泌する
- 壁細胞⇒胃酸と内因子を分泌する
- 固有筋層
- 強い蠕動運動で食べ物をすりつぶす
- 胃小窩
- 胃の働き
- 機械的消化
- 胃にいったん「ためて」「こなして」流す構造
- 食道から食べ物が胃の中に流れてくる
- 迷走神経の反射により、胃体部付近から収縮運動が起こる(蠕動運動)
- 胃の中の食べ物がすりつぶされて胃液と混ざる
- 閉じられていた幽門が開き、ドロドロの内容物が少しずつ小腸へ運ばれる(幽門括約筋が幽門の開閉をする)
- 科学的消化
- こなしながら強力な胃酸で食べ物を分解する
- 塩酸、ペプシノゲン、粘液で胃酸で胃が溶けないように保護する
- 機械的消化
- 胃酸分泌の促進
- 頭相の流れ
- 視覚や嗅覚、味覚などの情報が脳から延髄に送られる
- 迷走神経反射(副交感神経)を介して胃のG細胞が刺激される
- G細胞からガストリンが分泌される
- 血液によって運ばれたガストリンが胃底腺の壁細胞を刺激する
- 胃酸(塩酸)が分泌
- 胃相の流れ
- 食べ物が胃に流れてきて胃壁が伸展する
- 求心性の迷走神経によって延髄に伝えられる
- 迷走神経がG細胞を刺激して大量のガストリンが分泌される
- 血液によって運ばれたガストリンが胃底腺の壁細胞をさらに刺激する
- 食物中の栄養素がG細胞を刺激してさらにガストリンを分泌する
- 多量の胃酸(塩酸)が分泌
- 頭相の流れ
- 胃酸分泌の抑制
- 腸相の流れ
- 消化された酸性の内容物が十二指腸へ運ばれる
- S細胞からセクレチンが分泌
- G細胞のガストリン分泌が抑制される
- 壁細胞から胃酸(塩酸)分泌も抑制
- K細胞からGIPが分泌され、血液を介して壁細胞へ送られる
- 胃酸(塩酸)の分泌をさらに抑制
- 腸相の流れ
- 胃酸の働き
- 微生物を殺菌する
- 鉄を小腸で吸収しやすくする
- 胃底腺の主細胞からでるペプシノゲンをペプシンに変え、タンパク質を分解する
- 主細胞⇒ペプシノゲン
- 壁細胞⇒塩酸
- G細胞⇒ガストリン
小腸
- 十二指腸+空腸+回腸からなる
- トライツ靱帯で十二指腸を支えている
- 小腸の内部
- 表面積を増やす構造
- 輪状ヒダ
- 小腸の粘膜の内腔にあるヒダ
- 絨毛
- 輪状ヒダの表面にある突起で腸絨毛とも呼ばれる
- 輪状ヒダ
- 表面積を増やす構造
- 分泌細胞
- 外分泌細胞
- 杯細胞
- 粘液を分泌
- パネート細胞
- 殺菌酵素のリゾチームを分泌
- 杯細胞
- 内分泌細胞
- S細胞
- セクレチンを分泌
- I細胞
- コレシストキニンを分泌
- S細胞
- 吸収上皮細胞
- 絨毛を覆う細胞の中で一番多い
- 膜消化
- 小腸粘膜の微絨毛で行われる消化
- 管腔内消化
- 消化管内で分泌される消化酵素による消化
- 外分泌細胞
- 消化酵素
- アミノペプチターゼ
- タンパク質のペプチドを分解する
- マルターゼ、スクラーゼ
- 糖質を分解する
- アミノペプチターゼ
- 十二指腸
- 膵臓を囲んでいる
- 小十二指腸乳頭
- 副膵管から膵液が十二指腸へ流れる開口部
- 大十二指腸乳頭
- 主膵管からの膵液と総胆管からの胆汁が十二指腸へ流れる開口部
- ファーター乳頭ともいう
- オッディ括約筋
- 大十二指腸を囲む平滑筋で膵液と胆汁の流れを調節する
- 十二指腸空腸曲
- 第2腰椎の左側にある
- 十二指腸上部の分泌腺
- ブルンネル腺(十二指腸腺)
- 炭酸水素ナトリウムを含んだアルカリ性の粘液を分泌する腺
- 空腸と回腸
- 空腸
- 厚く弾力性があり、蠕動運動が活発
- 輪状ヒダ
- 絨毛
- 平滑筋(輪走筋、縦走筋)
- 回腸
- 平滑筋が薄く、輪状ヒダは数は数が少なくて背が低い
- パイエル版(集合リンパ小節)
- 腸にある免疫組織(腸管免疫)
- M細胞が抗原を取り込む
- 樹状細胞などがヘルパーT細胞に抗原提示
- ヘルパーT細胞はB細胞を形質細胞へと分化させる
- 形質細胞のIgA抗体が異物を排除する
- 空腸
膵臓
- 中に膵管が通っている
- 膵尾部は脾臓と接している
- 膵臓の外分泌
- 膵管を通って消化液の膵液が分泌される
- セクレチン
- 胃の内容物が流れてくると十二指腸のS細胞から分泌
- 導管細胞に作用し、重炭酸イオンを含む膵液を分泌させる
- 胃の内容物(酸性)を中和する
- 胃酸分泌の抑制
- 幹細胞の胆汁分泌促進
- コレシストキニン
- 脂質の多い物が流れてくると小腸のI細胞から分泌される
- 腺房細胞に作用し、消化酵素を含む膵液を分泌させる
- 消化酵素が栄養素を分解する
- 胆嚢の収縮
- オッディ括約筋の弛緩
- 膵液の消化酵素
- 膵アミラーゼ(炭水化物)⇒デンプンをマルトースに分解
- 膵リパーゼ(脂質分解酵素)⇒トリグリセリド(中性脂肪)をモノグリセリドと脂肪酸に分解
- トリプシノゲン・キモトリプシノゲン(タンパク質分解酵素)⇒トリプシン・キモトリプシン⇒ポリペプチドをオリゴペプチドに分解
大腸
- 大腸の壁を縦に走る筋肉(縦走筋)が3本の束になって結腸ヒモをつくる
- 間膜ヒモ
- 大網ヒモ
- 自由ヒモ
- 腹膜垂
- 結腸ヒモに沿ってぶら下がっている脂肪
- 結腸膨起
- 筋肉の収縮でできるふくらみ
- ハウストラともいう
- 半月ヒダ
- 筋肉の収縮でできる内面にあるヒダのこと
- アウエルバッハ神経叢(筋層間神経叢)
- 縦走筋と輪走筋の間にある
- 平滑筋の運動を調節する
- マイスネル神経叢(粘膜下神経叢)
- 粘膜下組織にある
- 粘膜の腺分泌を調節
- 消化管運動
- 内容物をすりつぶして肛門側へ送る仕組み
- 分節運動
- 輪走筋の収縮と弛緩による運動
- 内容物を細かく砕いて腸液と混ぜ合わせる
- 振子運動
- 縦走筋の収縮と弛緩による運動
- 内容物を細かく砕いて腸液と混ぜ合わせる
- 蠕動運動
- 消化管の入り口側が収縮し、肛門側が弛緩する運動
- 内容物を前に押し進めていく
排便
- 排便の流れ
- 液状の便から水分を吸収し便の形状を変える
- 大腸に入った内容物を蠕動運動によって肛門へ運ぶ
- 回腸の末端部である回盲口には、内容物の逆流を防ぐ回盲弁がある
- 上行結腸と盲腸の間
- 逆行する逆蠕動と分節運動、振子運動で内容物を細かく砕く
- 液状
- 横行結腸から下行結腸
- 液状になった内容物から水分を吸収
- 粥状
- 下行結腸からS状結腸
- 内容物からさらに水分を吸収して固形に近づけていく
- 半粥状~半固形状
- 直腸
- 水分が吸収されて固形の便になる
- 排便のしくみ
- 胃に食べ物が入ると胃結腸反射がおきて結腸内の便が一気に直腸に送られる
- 便が直腸へ送られると直腸壁が伸展する
- その情報が骨盤内臓神経を介して仙髄に伝えられる
- 骨盤内臓神経を介して指令をだす
- 内肛門括約筋を弛緩させる
- 直腸壁を収縮させる
- 大脳へ直腸に便が入ったことを伝える
- 脳は便意を感じ、便を使用と決める
- 陰部神経によって、外肛門括約筋を弛緩させる
- 骨盤内臓神経を介して指令をだす
- 弛緩性便秘
- 高齢者や無力体質の人に多い
- 腹痛はなく、便意も弱い
- 直腸性便秘
- 便意をがまんする人に多い
- 習慣性便秘
- 痙攣性便秘
- 便意は強いが排便困難で残便感がある
- 腹痛がある
- 兎糞便
を食道がん
- 90%以上が扁平上皮癌
- 高齢男性に多い
- 中部食道~下部食道に好発
- 早期癌は無症状
- 進行癌は嚥下困難、体重減少、誤嚥性肺炎
- 浸潤による症状
- 大動脈(吐血)
- 反回神経(嗄声)
- 頸部交感神経(ホルネル症候群)
- 眼瞼下垂
- 縮瞳
- 発汗減少
- 上大静脈(上大静脈症候群)
- 顔面浮腫
消化性潰瘍
| 胃潰瘍 | 十二指腸潰瘍 | |
| 好発部位 | 胃角部付近 | 十二指腸の始まり |
| 心窩部痛 | 食後 | 空腹時 |
- 男性多い
- ヘリコバクターピロリ菌
- ストレス
- 消炎鎮痛薬(NSAIDs)
- ニッシェ像
胃癌とダンピング症候群
- 胃癌
- 腺癌が多い
- ヘリコバクターピロリ菌感染が危険因子
- 進行癌の病期分類にブルマン分類を用いる
- 転移しやすい
- シュニッツラー
- ウェルヒョウ
- クルーケンべルグ
- ダンピング症候群
- 胃切除後の合併症
- 食べ物が急激に腸内に入ることで起こる
- 早期ダンピング症候群(食後20~30分)
- 悪心
- 冷汗
- 動悸
- 脱力感
- 腹痛、下痢
- 後期ダンピング症候群(食後2~3時間)
- 低血糖症状
クローン病と潰瘍性大腸炎
| クローン病 | 潰瘍性大腸炎 | |
| 全消化管の全層 | 炎症部位 | 大腸の粘膜 粘膜下層 |
| 非連続性 | 炎症の広がり | 連続性 (直腸から口側へ) |
| 下痢 (血便は少ない) | 便 | 粘血液 |
| 縦走潰瘍 敷石状病変 痔瘻 | 特徴 | 全周性潰瘍 |
- 共通症状
- 腹痛
- 下痢
- 発熱
- 体重減少
- 貧血
- 共通合併症
- ブドウ膜炎
- アフタ性口内炎
- 結節性紅斑
- 関節炎
- 強直性脊椎炎
過敏性腸症候群
- 原因不明
- 腸に器質的異常がない⇒内視鏡では異常所見はみられない
- 症状
- 腹痛(左下腹部痛)
- 排便、排ガスにより軽快する
- 便秘型
- 下痢型
- 交代性下痢、便秘型
- 陰性所見
- 痔瘻
- 発熱
- 嘔吐
- 血便
腸閉塞・イレウス
- 腸内容が肛門側に移動できなくなった状態
- 症状
- 排便、排ガスの停止
- 腹痛、嘔吐、腹部膨満
- 陰性所見
- 下痢
- 腹部単純X線検査
- 小腸ガス
- 鏡面像(二ボー)
| 分類 | 腸の血行障害 | 腸雑音 |
| 単純性(閉塞性) | 伴わない | 亢進(金属音) |
| 複雑性(絞扼性) | 伴う | 亢進(金属音) |
| 麻痺性 | 伴わない | 減弱・消失 |
大腸癌
- 腺癌が多い
- デュークス分類
- 症状
- 早期癌⇒無症状
- 進行癌⇒腹痛、便通障害、便の細小化、血便、腸閉塞
- 転移
- 血行性転移(肝・肺)
- 腫瘍マーカー
- CEA
消化管の問題
腸管とその構造との組合せで正しいのはどれか。
- 回腸 ───── 腹膜垂
- 空腸 ───── 腸腺
- 十二指腸 ─── 腸間膜
- 横行結腸 ─── 腸絨毛
正しい記述はどれか。
- 大腸には内腔に輪状ヒダがある。
- 腹膜垂は小腸にみられる。
- 胃の角切痕は大弯にある。
- 門脈は肝門に入る。
胃について正しい記述はどれか。
- 幽門は第11胸椎の高さにある。
- 角切痕は小弯の一部にみられる。
- 胃底腺の主細胞は塩酸を分泌する。
- ガストリン分泌細胞は噴門に分布する。
胃について正しいのはどれか。
- 幽門では括約筋が発達している。
- 胃底部で幽門につながる。
- 主細胞から塩酸が分泌される。
- 大弯に小網が付着する。
胃について正しい記述はどれか。
- 胃体の上方への膨隆部を胃底という。
- 大弯から小網が垂れ下がる。
- 胃体部粘膜には輪状ヒダがある。
- 噴門には発達した弁がある。
パイエル板(集合リンパ小節)があるのはどれか。
- 胃
- 虫垂
- 回腸
- 十二指腸
小腸について正しい記述はどれか。
- 総胆管が空腸に開口する。
- 虫垂は小腸に属する。
- 十二指腸の長さは約12cmである。
- 集合リンパ小節(パイエル板)は回腸下部に多い。
小腸について正しいのはどれか。
- 粘膜固有層にパイエル板がある。
- 全長にわたって腸間膜がある。
- 表面に腹膜垂がある。
- 粘膜上皮は多列円柱上皮である。
小腸について正しいのはどれか。
- 十二指腸空腸曲は腰椎の右にある。
- 半月ヒダがある。
- 回腸には腸間膜がない。
- 上皮は内胚葉から分化する。
小腸にみられないのはどれか。
- 孤立リンパ小節
- 輪状ヒダ
- 腸絨毛
- 腹膜垂
小腸について誤っている記述はどれか。
- 腸腺は絨毛の根元に開口する。
- 粘膜に半月ヒダがある。
- 空腸は腸間膜をもつ。
- 二層の筋層からなる。
十二指腸について誤っているのはどれか。
- 膵頭をC字状に囲む。
- 下行部に総胆管が開く。
- 腹膜後器官である。
- 回腸に移行する。
大腸について正しい記述はどれか。
- 直腸は腸間膜をもつ。
- 小腸と同じ長さである。
- 輪状ヒダがある。
- 盲腸から虫垂が突出する。
上行結腸について正しいのはどれか。
- 輪状ヒダを持つ。
- 脾臓に接する。
- 肝臓の方形葉下面に接する。
- 右結腸動脈が分布する。
消化管で腹膜垂がみられるのはどれか。
- 横行結腸
- 回腸
- 十二指腸
- 直腸
膵臓について誤っている記述はどれか。
- 膵臓全体が腹膜に覆われる。
- 膵島はホルモンを分泌する。
- 膵管は十二指腸に開口する。
- 外分泌部は消化酵素を分泌する。
膵臓について正しい記述はどれか。
- 膵尾は十二指腸に付着する。
- 肝臓の下面に隣接する。
- 膵管は幽門に開口する。
- 後腹膜器官である。
膵臓について誤っている記述はどれか。
- 腹膜後器官である。
- 脾動脈の枝が分布する。
- 膵管は膵臓の中を通る。
- 内分泌腺の膵島は頭部に多い。
膵臓について正しい記述はどれか。
- 後腹壁に付着している。
- 第4・第5腰椎の高さにある。
- 膵液はランゲルハンス島から分泌される。
- 左端は十二指腸に接している。
膵臓について正しいのはどれか。
- ランゲルハンス島は膵頭部に多い。
- 膵管は十二指腸に開口する。
- 腹膜で全体が覆われる。
- 膵頭部は脾臓に接する。
腹膜後臓器はどれか。
- S状結腸
- 回腸
- 肝臓
- 膵臓
間膜を持たない消化器はどれか。
- 胃
- 空腸
- 直腸
- 肝臓
消化と吸収
胃液分泌を促進するのはどれか。
- 交感神経活動の増加
- セクレチン分泌の増加
- 酸による十二指腸粘膜の刺激
- 食物による胃壁の伸展刺激
胃液分泌を促進するのはどれか。
- セクレチン分泌の増加
- 交感神経活動の増加
- 食物による口腔粘膜の刺激
- 酸による十二指腸粘膜の刺激
胃液分泌を抑制するのはどれか。
- 迷走神経の活動亢進
- ガストリンの分泌
- 食塊による胃壁の伸展
- セクレチンの分泌
胃液の分泌を促進する消化管ホルモンはどれか。
- ガストリン
- コレシストキニン
- セクレチン
- ソマトスタチン
胃液の塩酸で活性化される消化酵素はどれか。
- キモトリプシノーゲン
- ペプシノーゲン
- トリプシノーゲン
- ヌクレアーゼ
胃腺から分泌されないのはどれか。
- ペプシノゲン
- ガストリン
- セクレチン
- ムチン
ペプシノーゲンを分泌する胃腺の細胞はどれか。
- 内分泌細胞
- 副細胞(粘液細胞)
- 主細胞
- 壁細胞(傍細胞)
小腸粘膜で吸収される物質はどれか。
- 庶糖
- ブドウ糖
- でんぷん
- 麦芽糖
小腸での吸収に適した構造はどれか。
- 回盲弁
- 絨毛
- 十二指腸腺
- 腸腺
小腸上皮から吸収後、中心乳び管に入るのはどれか。
- グルコース
- ビタミンB1
- 中性脂肪
- アミノ酸
大腸について正しい記述はどれか。
- 水分の約95%が吸収される。
- 大腸液は消化酵素を含む。
- 蠕動運動は交感神経によって促進される。
- 盲腸から上行結腸にかけて逆蠕動が起こる。
大腸について正しい記述はどれか。
- 蠕動運動は交感神経の活動によって促進される。
- 大蠕動が起こらない。
- 大腸液は消化酵素を含まない。
- 水分の約80%が吸収される。
膵液のpHはどれか。
- 強酸性
- 弱酸性
- 中性
- 弱アルカリ性
脂肪の消化に関与しないのはどれか。
- リパーゼ分泌
- アミラーゼ分泌
- 胆汁分泌
- 乳化作用
消化管からの吸収について正しいのはどれか。
- グルコースは胃で吸収される。
- 水分の約50%は直腸で吸収される。
- モノグリセリドは小腸で吸収される。
- アミノ酸は結腸で吸収される。
消化液と消化酵素の組合せで正しいのはどれか。
- 腸液 ――― ペプシン
- 唾液 ――― アミラーゼ
- 膵液 ――― マルターゼ
- 胃液 ――― リパーゼ
摂食を抑制するのはどれか。
- グレリン
- オレキシン
- ロイコトリエン
- レプチン
唾液に含まれる酵素はどれか。
- ヌクレアーゼ
- リパーゼ
- ペプシン
- アミラーゼ
消化管で受動的に吸収されるのはどれか。
- ブドウ糖
- カルシウムイオン
- 水
- ナトリウムイオン
消化管ホルモンについて正しい記述はどれか。
- コレシストキニンは胆嚢を収縮する。
- セクレチンは膵液分泌を抑制する。
- ガストリンは胃液分泌を抑制する。
- ソマトスタチンは胃液分泌を促進する。
消化管ホルモンが消化液分泌に及ぼす作用で正しいのはどれか。
- ガストリンは胃液分泌を抑制する。
- セクレチンは膵液分泌を促進する。
- コレシストキニンは膵液分泌を抑制する。
- ソマトスタチンは胃液分泌を促進する。
消化管からの吸収の仕組みで誤っているのはどれか。
- ろ過
- 受動輸送
- 能動輸送
- 拡散
消化管疾患
腸閉塞症について誤っている組合せはどれか。
- 閉塞性腸閉塞 ─── 糞塊
- 腸重積 ────── 血便
- 麻痺性腸閉塞 ─── 下痢
- 絞扼性腸閉塞 ─── 腸捻転
疾患と痛みが放散する部位との組合せで誤っているのはどれか。
- 狭心症 ────── 左肩
- 十二指腸潰瘍 ─── 右肩
- 胆石症 ────── 右肩
- 尿管結石 ───── 鼡径部
疾患と検査との組合せで誤っているのはどれか。
- 急性膵炎 ─── 内視鏡検査
- 大腸癌 ──── 便潜血反応
- 胆石症 ──── 超音波検査
- 肝癌 ───── CT検査
癌と腫瘍マーカーとの組合せで正しいのはどれか。
- 乳癌 ───── AFP
- 胃癌 ───── CYFRA
- 子宮体癌 ─── SCC
- 大腸癌 ──── CEA
口腔内所見と疾患の組合せで正しいのはどれか。
- アフタ性口内炎 ――― 潰瘍性大腸炎
- 口角炎 ――――――― ビタミンA欠乏症
- う歯 ―――――――― 悪性貧血
- 舌炎 ―――――――― くる病
過敏性腸症候群について正しい記述はどれか。
- 下血をみることが多い。
- ストレスとは無関係である。
- 発熱を繰り返す。
- 便秘と下痢とを繰り返すタイプがある。
ダンピング症候群を起こす原因はどれか。
- 過敏性腸症候群
- 食道炎
- 虫垂炎
- 胃切除
胃切除後症候群の症状でないのはどれか。
- 下痢
- 腹痛
- 嚥下障害
- 冷や汗
下痢の原因疾患でないのはどれか。
- クローン病
- 過敏性腸症候群
- 虫垂炎
- 大腸炎
クローン病の合併症はどれか。
- 巨大舌
- 痔瘻
- 唾液減少
- 手掌紅斑
食道癌でみられないのはどれか。
- 吐血
- 脾腫
- 嚥下性肺炎
- 嗄声
胃潰瘍について誤っている記述はどれか。
- 好発部位は胃の大弯である。
- ヘリコバクター・ピロリの感染と関係がある。
- 女性より男性に多い。
- エックス線像でニッシェがみられる。
潰瘍性大腸炎の特徴でないのはどれか。
- 敷石状病変
- 粘血便
- 全周性潰瘍
- 中毒性巨大結腸
麻痺性イレウスの症状で誤っているのはどれか。
- 嘔吐
- 腹痛
- 膨満感
- 下痢
潰瘍性大腸炎の合併症でないのはどれか。
- 結節性紅斑
- ブドウ膜炎
- 痔瘻
- 口腔内アフタ
胃切除術後のダンピング症候群の所見で誤っているのはどれか。
- 下痢
- 冷汗
- 高血糖
- 腹痛
「70歳の男性。嚥下障害と体重減少で来院し、食道癌と診断された。さらに右眼瞼下垂と縮瞳が認められた。」 本疾患について適切なのはどれか。
- 腺癌が多い。
- 予後は良い。
- 化学療法は用いられない。
- 中部食道に多い。
「70歳の男性。嚥下障害と体重減少で来院し、食道癌と診断された。さらに右眼瞼下垂と縮瞳が認められた。」 本症例にみられる合併症はどれか。
- 上大静脈症候群
- 反回神経麻痺
- 顔面神経麻痺
- ホルネル症候群
過敏性腸症候群でよくみられるのはどれか。
- 血便
- 嘔吐
- 下痢
- 発熱
脱水を起こしやすいのはどれか。
- 胃下垂
- 大腸ポリープ
- 食道憩室
- 腸閉塞
痔瘻を合併しやすいのはどれか。
- 急性細菌性腸炎
- 潰瘍性大腸炎
- 過敏性腸症候群
- クローン病
「45歳の男性。最近、心窩部から背中の皮膚にかけて痛みが起きる。胸やけ、食欲不振もある。上部消化管内視鏡検査では、胃角部に潰瘍を認め、ヘリコバクター・ピロリの感染を疑った。」 本症例の背中の皮膚の痛みで最も適切なのはどれか。
- 空腹時に起こる。
- 体性痛である。
- 内臓痛である。
- 関連痛である。
「45歳の男性。最近、心窩部から背中の皮膚にかけて痛みが起きる。胸やけ、食欲不振もある。上部消化管内視鏡検査では、胃角部に潰瘍を認め、ヘリコバクター・ピロリの感染を疑った。」 ヘリコバクター・ピロリの検査はどれか。
- 尿素呼気検査
- 尿沈渣検査
- 胃液測定
- 血清ペプシノーゲン測定
ホルネル症候群がみられやすいのはどれか。
- 胃癌
- 食道癌
- 肝臓癌
- 大腸癌
潰瘍性大腸炎の特徴で正しいのはどれか。
- 大腸壁の全層に炎症を起こす。
- 直腸から口側へと病変が連続する。
- 痔瘻合併の頻度が高い。
- 回盲部に好発する。
食道癌について正しいのはどれか。
- 女性に多い。
- 腺癌が多い。
- アルコールは危険因子である。
- 若年者に多い。
大腸癌について正しいのはどれか。
- 便潜血検査は死亡率減少に寄与する。
- 近年減少傾向である。
- 大部分が扁平上皮癌である。
- 血清CEAが早期診断に役立つ。