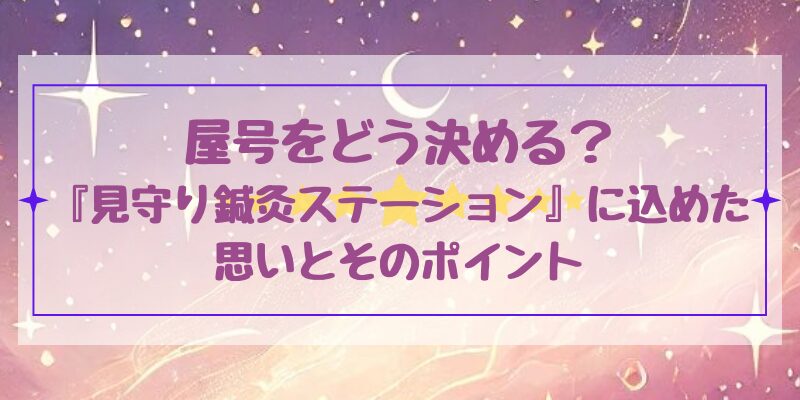🌟なぜ屋号をつけるのか?個人事業主にとっての名前の力
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
突然ですが、みなさんは「屋号(やごう)」をつけていますか?
開業に向けて準備を進めていると、どこかのタイミングで「屋号、どうしようかな」と迷う瞬間があると思います。
税務署の開業届や名刺作成、ホームページ制作、SNSのアカウント名など、屋号は事業の“顔”になる要素の一つです。
でも、実は個人事業主には必ずしも屋号は必要ではないのです。
例えば、訪問鍼灸を始める場合、保健所への届け出は「個人名」で登録されます。
これは医療系国家資格である鍼灸師の業務が、あくまで個人の責任に基づいて行われるからです。
そのため、広告や名刺に屋号をつけたくても、法的には「Kagaya ○○治療院」などといった表現に制限があるケースもあります。
さらに、保険請求や受領委任制度に関わる場面でも、個人名での登録が基本となります。
つまり、保健所や保険関係の届出において、屋号はあくまで任意であり、つけたからといって何か特別な権利が生まれるわけではありません。
でも……それでも私は屋号をつけたいと思いました。
理由はとてもシンプルです。
- 名刺に書いたときに印象が良くなる
- SNSやホームページでのブランディングになる
- 活動に統一感が生まれ、自分自身の指針にもなる
実際、名刺に「Kagaya(看護師・鍼灸師)」とだけ書くと、何となく素っ気ない印象になります。
連絡先だけのカードでは伝えられる情報が限られてしまいます。
女性がリラクゼーション系のサービスを提供する場合、名前の響きだけで“違う業種”と誤解されてしまうこともあるのが現実です。
だからこそ、「しっかりとした屋号を持ち、どういう活動をしているかを明示する」ことが大切だと考えるようになりました。
ただし、屋号の名乗り方にも法律的な注意が必要です。
たとえば、「○○クリニック」や「○○診療所」など、病院や診療所と紛らわしい表現は医師法で禁止されています。
こうした法的制限をクリアしつつ、活動内容や理念をうまく伝える屋号を考えるには、少し工夫とアイデアが必要になります。
本記事では、そんな屋号の考え方や注意点、そして私が考えた「見守り鍼灸ステーション きらぼし」という屋号に込めた意味を丁寧にご紹介していきます。
屋号を考えている方、ブランディングに悩んでいる方、ぜひ参考にしてくださいね。
🌟使用できない屋号の名称とは?法律と広告規制から考える
屋号を考えるときに、ただオシャレだったり印象が良かったりする名前をつければよいというわけではありません。
実は、私たち鍼灸師が開業するうえで「使ってはいけない名称」が明確に法律で定められているのです。
それが「医師法第3条第1項および第3項」です。
この法律では、病院や診療所と紛らわしい名称を用いてはいけないと明記されています。
たとえば、「○○診療所」や「○○クリニック」など、医師や病院が連想される名前をつけてしまうと、違法行為とみなされる可能性があるのです。
以下がその条文の抜粋です:
第1項:疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
第3項:助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を附けてはならない。
つまり、病院のように見えてしまう表現や、助産師業務と誤解を招く名称もアウトです。
この規制の背景には、患者さんが医療機関と誤認してしまい、不要な混乱や誤解を招くことを避ける目的があります。
たとえば、訪問鍼灸師が「○○診療所」と名乗ってしまうと、あたかも医師の診療行為を行う場所のように受け取られてしまいます。
また、名称の付け方によっては「医業類似行為に対する広告の制限」にも触れてしまう恐れがあります。
📛 使用してはいけない名称例
- ○○診療所:病院・診療所に誤認されやすい
- ○○クリニック:同上。特に美容鍼などでよく見かけますがNG
- 鍼灸医○○施術所:「医」という文字は医師を想起させるためNG
- ○○鍼灸科治療院:「科」は診療科を連想させるためNG
- ○○流家伝鍼灸院:施術方法・経歴を誇張表現すると広告制限に触れる
- ○○治療院:漠然としていて業務内容がわかりづらい
特に「クリニック」「科」「医」という文字は要注意ワードです。
これらを使用すると、開業届の段階で保健所から指摘が入ることもあるため、事前に避けるべきと覚えておきましょう。
また、鍼灸師に限らず、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師、整体などの分野でも、技術や経歴、特別な流派を強調する表現は広告制限に該当するとされており、「○○式」「伝統家伝」などの表現も使えないことがあります。
実はこのあたりの内容、国家試験にも出題されたことがあります。
つまり、私たち施術者にとって“常識”として知っておくべきルールだということです。
開業準備中の方、屋号を決めかねている方は、必ず医師法の条文と広告ガイドラインを一度確認することをおすすめします。
屋号はブランディングの第一歩であると同時に、信頼感や誠実さを示す重要な要素。
だからこそ、ルールを守った上で、自分の活動内容が伝わるような工夫が求められます。
次章では、「では、どういった屋号のつけ方が理想的なのか?」という点について、実例を交えてご紹介します。
🌟基本的な屋号の考え方とつけ方のコツ
屋号とは、個人事業主やフリーランスがビジネス上で使用する
「商号」のようなものです。
株式会社のように法人格を持たない場合でも、屋号を持つことでブランディングや信頼性の向上につながります。
特に鍼灸師として開業する際には、屋号がそのまま「治療スタイル」や「対象となる患者層」へのメッセージとなるため、しっかり考えてつける価値があります。
では、どのように屋号を考えていけばよいのでしょうか?
ここでは基本のルールと、開業にふさわしいネーミングのコツを紹介します。
屋号は「覚えやすく」「誤解されない」が大原則
屋号でまず重要なのは、「覚えやすさ」と「誤解されないこと」です。
- 言葉が長すぎない
- 読みやすく、発音しやすい
- 業種やサービス内容が伝わる
たとえば、「Kagaya鍼灸治療院」のように、自分の名前+業種名+施設名を組み合わせたシンプルな構成は、国家試験でもお手本のような屋号とされています。
近隣に同じような屋号がないかを確認しよう
意外と見落としがちですが、開業前に必ずやっておきたいのが「屋号の類似チェック」です。
近隣に似たような名前の治療院や整体院、鍼灸院がある場合、患者さんが混乱してしまうだけでなく、既存の店舗に迷惑をかけてしまうこともあります。
Googleマップやホットペッパービューティーなどでエリア検索を行い、似た屋号がないかをリサーチすることをおすすめします。
また、インスタグラムやLINE公式アカウント名が既に使われていないかもチェックすると、SNS展開の際にスムーズです。
屋号の構成は「名前・場所・業種」が基本形
理想的な屋号は、以下のような構成が推奨されます。
- 個人名(Kagaya)+業種(鍼灸)+施設名(治療院)
- 地域名(小平)+業種(訪問鍼灸)+ステーション
- 特徴や理念(見守り)+業種(鍼灸)+拠点名(きらぼし)
このような構成であれば、保健所にも問題なく届け出ることができ、患者さんにとってもサービスの内容が明確に伝わります。
また、ネーミングのセンスが光る屋号であれば、名刺の印象も良くなり、紹介や口コミの際にも覚えてもらいやすくなります。
法律的に「文句なし」の屋号とは?
「Kagaya鍼灸治療院」のような屋号は、国家試験的にもパーフェクトですし、保健所や税務署でも「一発合格」と言われるような名称です。
なぜなら、個人名を明示しつつ、何の施術を行っているかが一目瞭然だからです。
「治療院」という表現も医療機関ではないことを明確にしており、医師法や広告ガイドラインにも触れません。
一方で、「○○クリニック」「○○科鍼灸院」などは紛らわしい名称に該当し、法的にNGとなります。詳しくは前章をご覧ください。
屋号は、あなたのビジョンやサービスを象徴する「看板」です。
とくに鍼灸師としての独立を考えている方にとって、しっかりと意味を込めたネーミングをすることは、今後の事業展開にも良い影響を与えます。
🌟Kagayaの屋号について思うこと
Kagayaが屋号をつけようと思った理由は、単に「かっこいいから」「ブランディングのため」といった表面的なものではありません。
Kagayaが大切にしているのは、障がい児(者)とその保護者の方々に寄り添うこと。
対象となるお客様は、一般的な美容鍼や慢性痛の治療を求めてくる方とは少し異なります。
たとえば小児科でよくある話ですが、保護者が「この先生に診てもらいたい」と医師を追いかけて病院を転院するケースがありますよね。
病院名や施設のブランドではなく、「○○先生だからお願いしたい」という“人”に対する信頼が最も大きな要素になっているのです。
Kagayaのサービスも同じです。
実際、訪問先の保護者さんからすれば「Kagayaが来てくれるならそれでいい」という声のほうが多いと思います。
事業所名や屋号なんて、正直どうでもいい…というのが現実かもしれません。
でも、それでもKagayaはあえて屋号をつけたいと思いました。
その理由のひとつが、名刺の見栄えです。
Kagayaの場合、自宅が事業所になる予定で、名刺には住所を記載したくありません。
でも「Kagaya(看護師・鍼灸師)」だけでは、ちょっと物足りないというか、名刺のデザインとして締まりがない気がしてしまったのです。
名前だけではなく、「この人は何をやっている人なのか」「どんな価値を提供してくれるのか」が伝わる屋号があれば、相手にも安心してもらえるし、自分の信念も明確になります。
だからこそ、「ちゃんと伝わる名前」を考えたい。
屋号をつけるというのは、Kagaya自身の理念や方向性を言語化する作業でもあるのです。
これはあくまでKagayaの感覚かもしれませんが、名刺・SNS・パンフレットなどで、屋号があると“事業”としての信頼感が出てくる気がします。
そして何より、「きらぼし」や「見守り鍼灸ステーション」といった屋号の響きや意味合いが、今後の活動やサービス内容を説明するときに、大きな武器になると感じています。
だからKagayaは、たとえ制度上は個人名だけで活動できたとしても、屋号をつけようと決めました。
🌟見守り鍼灸ステーション きらぼし に込めた意味
最終的にKagayaが選んだ屋号は、「見守り鍼灸ステーション きらぼし」でした。
この屋号には、Kagayaの想いとこれからの活動方針をすべて詰め込んでいます。
まず、「見守り」という言葉。
これは、ただ鍼灸で痛みや不調を治すだけでなく、障がい児(者)の成長をそっと支える存在でありたいという気持ちから選びました。
鍼灸治療はもちろん行いますが、それだけではなく、保護者が少しでも安心して休める時間をつくること、子どもたちがその子らしくいられる空間や関わりを提供することも、Kagayaの大切な役割です。
実際、障がい児のケアは「日中一時支援」「放課後等デイサービス」など制度内の枠がありますが、「学校が終わったあと」「18歳を過ぎたあと」の支援は抜け落ちやすく、保護者が仕事を続けることも難しい状況があります。
そこで、Kagayaが目指すのは、夕方の卒後支援・預かり+鍼灸のケアという新しいスタイル。
言ってしまえば「見守りサービス付き鍼灸師」です。
治療というより、“寄り添いながらそばにいる存在”という感覚に近いです。
次に、「ステーション」という言葉について。
これは訪問看護の「ステーション」からインスピレーションを得ました。
「ステーション=拠点から動き出す場所」という意味合いがありますよね。
たとえKagayaが1人でやっている事業だとしても、「ステーション」という言葉を使うことで、各家庭へ、各地域へ、必要なところに動いていくサービスだという印象を持ってもらえるのではと思いました。
「出張」「訪問」などの言葉も検討しましたが、どこか業務的で冷たく感じてしまい、「ステーション」の方が、温かみと柔らかさがあって好きです。
そして最後の「きらぼし」。
これは別の章で詳しく語っていますが、「きらぼし」という言葉には、「暗い夜道でも、かすかに光る星があるように、どんな状態の人でも輝きを持っている」という意味を込めました。
夜空のように静かで優しく、でも確かに存在している小さな光。
それがきらぼしであり、Kagayaが関わるすべての子どもや家族に、そんな光を届けたいと思ったのです。
さらに、この屋号は、言葉にしたときの「語感」や「親しみやすさ」も意識しました。
「見守り鍼灸ステーション きらぼし」と口にすると、優しく、柔らかい響きが残ります。
お堅くもなく、あやしくもなく、安心して話しかけてもらえる雰囲気があると感じています。
もちろん、今後サービス内容が広がっていく中で、屋号を変えるタイミングがくるかもしれません。
でも、今この瞬間のKagayaの想いをそのまま言葉にしたのが、この「見守り鍼灸ステーション きらぼし」です。
ただの“名前”ではなく、“姿勢”や“想い”を表す言葉。だからこそ、大切にしていきたいと考えています。
🌟「きらぼし」の由来
「きらぼし」という屋号は、ふとした日常の中で、自然と生まれた名前でした。
学校の帰り道。
自転車をこぎながら、Kagayaは「屋号、どうしようかなあ」と考えていました。
ふと空を見上げると、小平の夜空には星が静かに輝いていました。
街灯が少ない地域だからこそ、余計な光が遮られ、星の光がよく見える。その光景に、なぜか心がスッと落ち着いたのを覚えています。
そのとき思ったのです。
「ああ、星のような存在になりたい」と。
決してまぶしく照らすわけではないけれど、暗い中でふと気づくとそこにある光。
困っているとき、迷っているときに、目印になるような存在。
Kagayaがやりたいこと、目指したいサービス像にぴったりでした。
実はその頃ちょうど、鍼灸とともに「スヌーズレン療法」も取り入れたいと考えていました。
五感を通して心と体を整えるスヌーズレンの考え方と、夜空の星の光が、不思議と重なったのです。
そこで、宇宙や天体に関する言葉をいくつか書き出してみました。
- コスモ
- ギャラクシー
- ミルキーウェイ
- ネビュラ
- スターライト
でもどれも少し洋風すぎて、Kagayaのサービスにはフィットしないと感じました。
もっとやさしくて、親しみやすくて、和のニュアンスもある名前がいい。
そこで浮かんできたのが、「きらぼし」でした。
子どもが使うような、やわらかくて、あたたかい響き。難しい言葉ではないけれど、想いを込めるには十分な余白がある言葉。
さらに、以前から好きだったある言葉も背中を押してくれました。
「やりたいこととやるべきことが一致する時、世界の声が聞こえる」
重い障がいがあっても、「自分が自分らしく」生きられるように。
まわりの声に押し流されるのではなく、「世界の声=自分の内なる感覚」を信じて進めるように。
そんな風に支えられる存在になりたいと考えていたからこそ、「きらぼし」という名前がしっくりきました。
ちなみに、保健所や税務署で屋号の由来を聞かれることはほとんどありません。
届け出はあくまで形式的なものです。
でも、Kagayaにとってこの「きらぼし」は、単なる形式ではなく、これから出会う家族・子どもたちと心をつなぐ“最初の言葉”だと思っています。
「きらぼし」という名前を聞いて、ほっとしたり、ちょっと興味を持ったり、やさしさを感じてもらえたら、それだけで成功だと思っています。
屋号の由来に正解なんてありません。
でも、その名前に“どんな想いを込めたか”が、サービスを受ける側にじんわりと伝わることが大切。
「きらぼし」。
それは、Kagayaの覚悟であり、願いであり、スタート地点でもあるのです。
🌟ボツになった屋号案たちと、それでも込めたかった想い
「見守り鍼灸ステーション きらぼし」に決定するまでに、実は色々な屋号を考えてきました。
その中には採用を見送ったけれど、今でも「いいな」と思っている名前もあります。
鍼灸リハビリ看護ステーション きらぼし
「きらぼし」という屋号を考え始めたとき、一番最初に思い浮かんだのが「鍼灸リハビリ看護ステーション きらぼし」という名称でした。
理由はとてもシンプルで、「この流れができたら、すごくいいケアになるのでは」と感じたからです。
鍼灸で痛みを和らげ、筋緊張をゆるめる。
その状態で、リハビリ(機能訓練)を行い、動きを引き出す。
そしてそれを、日常生活の中で看護師が継続的に見守っていく。
この3ステップがうまく連携できれば、拘縮や変形、いわゆる廃用症候群の多くは予防できると思っています。
実際、リハビリが進まない理由の多くは「疼痛」です。
動かそうにも痛みがあれば動かせない。
リハビリ職がどれだけ頑張っても、患者さんが「痛い」と言えばそこで止まってしまいます。
その痛みを和らげる方法として、薬(鎮痛剤)に頼るのではなく、鍼灸というアプローチがもっと医療の現場に浸透すればいいのにと、日々感じています。
でも、現実はなかなか難しい。
医師会と鍼灸師会の微妙な関係性、保険制度の壁、そして職域のプライド争い。
まるで古い縦割りの仕組みが、患者さんの利益よりも組織の都合を優先しているように思えてしまうのです。
もちろん、病院も鍼灸院も経営を続けるためにはシビアな面があります。
きれいごとだけでは語れないのも事実です。
でも、だからこそ「横の連携」が必要だとKagayaは思います。
鍼灸×リハビリ×看護。
この連携があれば、ひとりの人の生活をまるごと支えることができます。
特に高齢者や障がい児(者)のケアでは、「どこか一つ」だけでは足りません。
ただし、名称として「看護ステーション」とつけると、訪問看護ステーション(=公費で動く看護事業所)と誤解される恐れがあることがわかりました。
制度的にも、名称の誤認はトラブルにつながりかねません。
たとえば「鍼灸リハビリ看護ステーション」と言っても、一般の方から見たら「保険で動いてくれる看護サービスなんだ」と誤解される可能性があります。実際には自費訪問を中心に展開していく予定なので、その誤認は避けたい。
だから、「順番を変えてみようかな?」とも考えました。
「訪問看護リハビリ鍼灸ステーション」といった形です。
でも、それでもやっぱり「看護ステーション」という言葉の印象は強く、公費事業所を連想させてしまいます。
理想と現実のバランスを取りながら、制度の中に収まりつつ、でも志は曲げない。
そんな難しい選択の連続です。
今後、もし複数の専門職と連携する体制が整えば、また改めて「鍼灸リハビリ看護ステーション」のような名称を使う日が来るかもしれません。
でも今は、ひとりで動ける範囲を丁寧に、誤解のない形で始めていくことが大切だと感じています。
療育鍼灸院 きらぼし
最初に思いついたのは、「療育鍼灸院 きらぼし」でした。
Kagayaは、看護×療育×鍼灸という3つのアプローチを融合させたサービスを考えています。
そのため、ただ「鍼灸院」と名乗るより、「療育」と入れた方が、より具体的で伝わるのではと思いました。
さらに、スヌーズレン療法や感覚統合を取り入れた空間をつくりたいという夢もあり、将来的には小さなテナントを借りて「スヌーズレン鍼灸ルーム」をつくる構想も持っていました。
でも、現時点では訪問中心のスタイルなので、実店舗がないのに「院」と名乗るのは少し違和感があると感じ、今回は不採用にしました。
内装が可愛い保育所型のベビーシッター事業なども見て、「いつかは店舗も持ちたいな」と思う気持ちもあります。
ですが、それは利用者さんのニーズがあってこそ。
無理に形にせず、今は“訪問”という形で最大限できることをしていこうと思っています。
訪問キュア&ケアステーション きらぼし
「治す(キュア)」と「癒す(ケア)」を両立させるという意味で、まさにKagayaが提供したいサービスの核を表現している言葉でした。
訪問で鍼灸を行い、痛みや緊張を和らげる。
それによって心身が整った状態で生活ができるようになり、継続的に看護師として“見守る”形で支えていく。
そういった「治療と生活支援のハイブリッド」こそ、Kagayaの目指すスタイルです。
しかし…いざ「キュア&ケア」と口にしてみると、どうにも言いづらい。
人前で言うにはちょっと照れてしまう響きでした(笑)
何より「プリキュアみたい」とツッコミが入りそうで、少しポップすぎる印象に不安が残りました。
せっかくのコンセプトが、ネーミングのせいで“あやしいお店”に見えてしまっては元も子もないので、泣く泣く不採用に。
ただし、「キュア(治す)」「ケア(寄り添う)」の両立という考え方自体は、今もKagayaの軸となっています。
名前としては採用しなかったけれど、サービス内容としてはずっと大切にしていきたい理念です。
名前だけじゃない、「意味」を選ぶ
このように、色々な名前を考えてみる中で気づいたことがあります。
それは、名前そのもの以上に、「その言葉にどんな意味を込めたか」が大切だということです。
「療育鍼灸院」も「キュア&ケアステーション」も、それぞれ理想があって、伝えたい世界観がありました。
けれど、制度との兼ね合いや口に出したときの印象、誤解されるリスクを踏まえて、慎重に選ばなくてはなりません。
最終的に残った「見守り鍼灸ステーション きらぼし」は、そうしたすべてをバランスよく内包した名前だと感じています。
それでも、ボツにした名前たちにも、Kagayaの想いや理想が詰まっていたことは間違いありません。
🌟まとめ:屋号は“理念を伝える一言”になる
ここまで、Kagayaが悩みに悩み抜いてきた屋号の変遷と、その背景にある想いをお伝えしてきました。
改めて感じるのは、屋号を決めるというのは、ただのネーミングではなく「自分が何をしたいのか」「どんな人とつながりたいのか」を言語化する作業なんだということです。
「鍼灸リハビリ看護ステーション」「療育鍼灸院」「キュア&ケアステーション」など、さまざまな案が浮かび上がっては消えていきました。
その度に自分自身の事業の核や方向性を問い直すきっかけになり、言葉と向き合うことの大切さを実感しました。
屋号を決めきれない理由の一つは、まだサービスの形が完成していないことにもあります。
訪問鍼灸としてスタートするつもりですが、看護や療育も組み合わせていきたい。
スヌーズレンの導入や、卒後支援としての「夕方預かり」も視野に入れています。
つまり、屋号だけを先に決めるというより、コンセプトが固まった時に自然と「この名前しかない」と思える瞬間が来るのかもしれません。
論文のタイトルを後からつけるように、事業の方向性がまとまってきたときに、「これが私の屋号です」と胸を張って言える名前が見つかるのだと思います。
それでも今のところは、「見守り鍼灸ステーション きらぼし」がしっくりきています。
見守り、という言葉には「治療して終わり」ではなく、寄り添い続ける姿勢が含まれています。
鍼灸という枠を超えて、看護や福祉、教育、家族のケアまでトータルで関わっていきたいという思いにピッタリでした。
「きらぼし」という名前にも、目立たなくても誰かの心に灯をともすような存在でありたいという願いを込めています。
もちろん、まだまだ模索中ではあります。
制度上の制約や地域ニーズ、協力者の有無なども関係してきますし、柔軟に変化していく覚悟も持っています。
でも、今はこの名前で、できるところからはじめていこうと思います。
読者のみなさんも、もし今、屋号を考えているところなら、ぜひ自分の気持ちに正直に向き合ってみてください。
響きやかっこよさよりも、「自分らしさ」を優先すると、愛着が持てる名前が見つかるかもしれません。
そして、もし何か良い屋号のアイデアがあれば、Kagayaにもぜひ教えてくださいね!