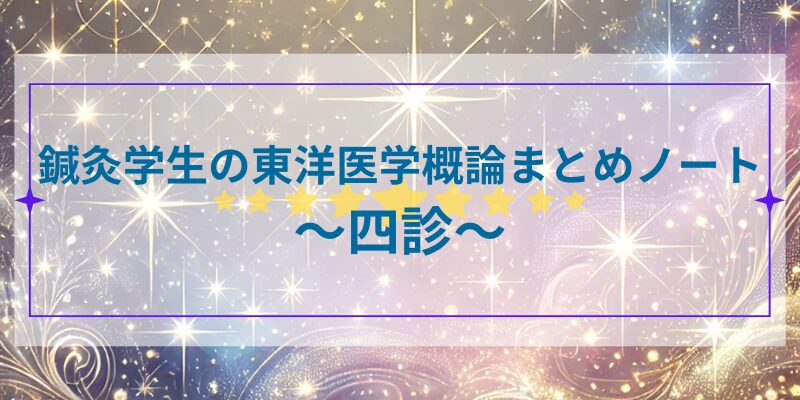🌟四診とは?東洋医学の基本診察法をマスターしよう
東洋医学において病の本質を見極めるための診察法、それが四診です。
これは「望診・聞診・問診・切診」の4つの診察技法から成り、視覚・聴覚・嗅覚・対話・触覚など、患者の全身を多角的に観察することで病態を把握します。
臨床における正確な証の判断や、中医学・経絡治療・鍼灸施術の根拠となるため、鍼灸師にとって必須のスキルです。
望診(ぼうしん):
「神技」とも称され、患者の顔色・皮膚・舌・体格・表情などを目で観察して病態を判断します。
聞診(ぶんしん):
「聖技」とも言われ、声の調子・呼吸音・体臭・口臭などを通して内臓の状態や邪気の性質を見極めます。
問診(もんしん):
「工技」と呼ばれ、患者の自覚症状・生活習慣・発症の経過・痛みの部位などを丁寧に聞き取り、八綱弁証などの基礎資料を得ます。
切診(せっしん):
「巧技」として、脈診・腹診・圧痛・皮膚温・経絡の緊張などを手で触れて確認し、証を確定していく重要な工程です。
🌟望診:視覚で見抜く東洋医学的病証判断
望診は、東洋医学における基本的な診察法であり、患者の皮膚の色、顔色、舌の状態、体格、動作などを視覚で観察することによって病態を読み解きます。
舌診(舌の色・形・苔)は、証を見極めるうえで非常に重要です。
望診を行う際には、明るい自然光の下で患者の全体像をよく観察することが大切です。
顔色、皮膚の艶、眼の輝き、舌の状態など、患者から発せられる「外見のサイン」は、五臓六腑の状態や気血津液の変化を反映しています。
舌診では、舌の色や苔の状態から陰陽・寒熱・虚実を総合的に把握します。
皮膚の色から診る五臓の変化
- 青色:肝の病、寒証、血瘀を示す
- 赤色:心の病、熱証を示す
- 黄色:脾の病、虚証、湿熱を示す
- 白色:肺の病、虚証、寒証を示す
- 黒色:腎の病、寒証、血瘀、痛証を示す
顔面の部位と五臓の関係
- 左頬:肝
- 額:心
- 鼻:脾
- 右頬:肺
- 顎:腎
舌診:舌の部位ごとの対応臓腑
- 舌尖部:心・肺
- 舌辺部:肝・胆
- 舌中部:脾・胃
- 舌根部:腎
舌色の変化と病証の読み方
- 淡紅:健康な舌、表証
- 淡:血虚、寒証
- 紅:実熱、陰虚による熱証
- 紫:血瘀
- 瘀斑・瘀点:血瘀
舌形の特徴からみる体質と病態
- 胖大舌:陽虚、痰湿の停滞
- 痩薄舌:気血不足、陰虚
- 裂紋舌:気血不足、陰虚
- 歯痕舌(胖大あり):陽虚、痰湿
- 歯痕舌(胖大なし):気虚
- 点刺舌:熱が盛んな証
- 舌下脈絡怒張:血瘀
舌苔の種類と証の解釈
- 薄白苔・薄苔:健康、表証、病状が軽い
- 厚白苔:寒証
- 黄苔:熱証
- 厚苔:痰湿、食滞
- 少苔:陰虚
- 膩苔:痰湿の停滞、食滞
五色(青・赤・黄・白・黒)と五臓(肝・心・脾・肺・腎)の関連性は、東洋医学の理論体系を理解するうえで重要です。
国家試験でも「舌色や苔の状態」「顔色の変化」に関する出題が毎年見られます。
たとえば、「舌色が紫で舌下脈絡が怒張している場合、何を疑うか?」という問題では、血瘀が正答となります。
学生の皆さんには、観察項目を五臓別・色別・部位別に整理して覚えるのがコツです。
また、臨床では舌診・顔色・皮膚の状態などを「セット」で見ることで、より的確な証の判断ができるようになります。
舌診は体内の状態を鏡のように反映する診断法です。国家試験でも出題されやすく、臨床現場では証決定の決め手となることも多いため、観察ポイントをしっかり押さえましょう。
🌟問診:対話から読み解く八綱弁証の極意
問診は、東洋医学の四診の中で患者との対話を通じて情報を得る診察法です。
自覚症状・発症の経緯・部位・性質・時間帯などを聞き取り、証の見極めに不可欠な材料を集めます。
とくに八綱病証(陰陽・表裏・寒熱・虚実)の分類は、東洋医学の診断枠組みの基礎となります。
八綱病証:4つの軸から構成される基本弁証
- 陰証:裏証・寒証・虚証に傾く状態
- 陽証:表証・熱証・実証に傾く状態
- 表証:悪寒・発熱・咽頭部違和感・脈浮など、外感の初期
- 裏証:病が深部に入り、消化器・泌尿器系の症状が多い
- 寒証:冷えると悪化、温めると軽減/顔色蒼白・舌苔白・脈遅
- 熱証:温めると悪化、冷やすと軽減/発熱・口渇・舌苔黄・脈数
- 虚証:体力低下・気血不足・慢性症状/自汗・倦怠・息切れ・喜按
- 実証:外邪の侵入・実熱・炎症性/無汗・拒按・疼痛増強・滑脈
半表半裏証は、寒熱往来や胸脇苦満、口苦などが特徴で、少陽病に多く見られます。
証の組み合わせパターンと特徴
- 陰虚:潮熱・盗汗・五心煩熱・舌紅・舌苔少・脈細数
- 陽虚:冷え・無力・下痢・顔色白・舌淡・脈沈細
- 陰盛:寒邪の亢進による寒証の強化
- 陽盛:実熱が旺盛で症状が強く表れる
- 寒熱錯雑:冷えとほてりが同時に存在/更年期などに多い
- 虚実錯雑:慢性疾患で虚のなかに実が混在する状態
疼痛部位と経絡の関係
| 部位 | 経絡 |
|---|---|
| 後頭部~項背部 | 太陽経:風寒外邪の侵襲に多い |
| 前額部~眉間 | 陽明経:胃経の影響を受けやすい |
| 側頭部 | 少陽経:肝胆の疏泄障害に関連 |
| 頭頂部 | 厥陰経:肝血不足や上熱に起因 |
痛みの性質で証を見分ける
| 痛みの種類 | 説明 | 関連証 |
|---|---|---|
| 拒按 | 押すと痛みが増す | 実証 |
| 喜按 | 押すと楽になる | 虚証 |
| 刺痛 | 鋭く刺すような痛み | 瘀血 |
| 冷痛 | 冷えを伴う痛み、温めると軽減 | 寒証・陽虚 |
| 酸痛 | だるさを伴う痛み | 気血不足・湿邪 |
| 遊走痛 | 部位が移動する | 気滞・風邪 |
| 夜間痛 | 夜に増悪 | 瘀血・寒邪 |
問診は「言葉の舌診」とも言えます。
丁寧な聴き取りは、患者の訴えに潜む証のヒントを明確にします。
八綱の整理に慣れ、臨床でも国家試験でも使えるようにしておきましょう。
🌟聞診:音と匂いで読み解く内臓のサイン
聞診(ぶんしん)は、東洋医学の四診のひとつで、患者の声・呼吸・咳・においなどを通して身体の内側の状態を察知する方法です。
聞診は聴覚・嗅覚を使って判断する診察法であり、「聖技」とも称されます。
声や音の質、発生部位、タイミングに注目することで、臓腑の虚実・寒熱・気機の乱れなどがわかります。
声や呼吸に表れる病証
- 短気(たんき):息切れや浅い呼吸。
⇒ 気虚、特に肺気虚に見られ、労作後に悪化しやすい。 - 少気(しょうき):話す声が弱々しく、呼吸も浅い。
⇒ 慢性的な虚証(気血不足)を示唆。 - 喀痰(かくたん):音が濁っている場合は痰湿、乾いた咳は燥邪や陰虚。
これらの呼吸や声の変化は肺・腎・脾の虚弱によって現れることが多く、慢性疾患では重要な所見となります。
胃気上逆に関連する音と症状
- 嘔吐(おうと):食物や水を戻す。
⇒ 胃気上逆の典型。
【虚寒】:冷え・水様嘔吐、【実熱】:酸味の強い嘔吐。 - 曖気(あいき):いわゆる「げっぷ」。
⇒ 胃気上逆による、肝気犯胃・食滞・中気不足。 - 吃逆(きつぎゃく):しゃっくり。
⇒ 横隔膜の痙攣で、胃気の逆流に由来。
【虚寒】:冷えが原因、【実熱】:炎症性の刺激。
胃気上逆は、肝・胃・脾の気機不調によって生じる代表的な現象です。
患者の訴えに耳を傾け、そのタイミングや内容物から証の判断材料を得ることができます。
においや音による気機の乱れのサイン
- 失気(しっき):放屁。
⇒ 脾気虚による運化障害、または肝鬱気滞による腸の蠕動失調が原因。 - 口臭:胃熱・食滞・歯根炎などにより強くなる。
- 体臭・尿臭:湿熱・中焦の不調を反映することがある。
聞診では、患者本人が気づいていない異常音やにおいを手がかりに、内臓機能や気血の異常を探ります。
とくに胃気上逆と肺の虚は頻出で、国試では「短気と少気の違い」や「曖気・吃逆の証分類」が問われやすいです。
🌟切診
切診(せっしん)は、患者の身体に実際に触れて病状を判断する東洋医学の診察法です。
四診の中でも最も物理的に接触を伴うため、実感的な情報を得やすいのが特徴です。主に腹診と脈診が中心となり、それぞれに細かな診断指標があります。
腹診:五臓の位置と特徴
腹部の触診は、五臓の反応点や張り・抵抗・圧痛などを手掛かりにします。
東洋医学では「五臓の状態は腹部に現れる」とされ、それぞれの臓器に対応する部位が明確に定められています。
| 臓腑 | 腹部での位置 | 主な反応 |
|---|---|---|
| 肝 | 臍の左 | 胸脇苦満、筋張り、怒りの感情反応 |
| 心 | 臍の上 | 動悸、心下痞鞭など |
| 脾 | 臍部 | 軟弱、無力、按じて痛む |
| 肺 | 臍の右 | 浅い呼吸、咳、皮膚の冷感 |
| 腎 | 臍の下 | 虚寒、冷え、無力感 |
腹証と所見
臨床では以下のような腹部所見がよく見られます。それぞれの反応は病因・病理の手がかりとなります。
| 所見 | 特徴 | 関連病態 |
|---|---|---|
| 心下痞鞭 | 心下部が詰まった感+硬さ | 心・胃の病、胃気の不降 |
| 胸脇苦満 | 肋骨下の張りと圧痛 | 肝気鬱結、少陽病 |
| 小腹不仁 | 下腹部に力がなく知覚鈍麻 | 腎虚、精の不足 |
| 小腹急結 | 左下腹部の硬結・圧痛 | 瘀血、血の停滞 |
| 裏急 | 腹直筋の異常な緊張 | 虚労、気の失調 |
脈診の基本
脈診では手首の寸口(そんこう)を三指で触れ、表裏・寒熱・虚実などを読み取ります。触れる位置は以下のとおりです。
| 部位 | 対応臓腑 |
|---|---|
| 寸(手首側) | 肺・心 |
| 関(中央) | 脾・肝 |
| 尺(肘側) | 腎・膀胱 |

代表的な脈状一覧
| 脈状 | 特徴 | 関連病証 |
|---|---|---|
| 浮脈 | 軽く当てて強く、押すと弱い | 表証・虚証 |
| 沈脈 | 深く押して感じる | 裏証 |
| 遅脈 | 1呼吸に3拍以下 | 寒証 |
| 数脈 | 1呼吸に6拍以上 | 熱証 |
| 虚脈 | 力なく、按じても返ってこない | 虚証 |
| 実脈 | 力強く押し返す | 実証 |
| 滑脈 | 丸く滑らかで流れるよう | 痰湿・妊娠 |
| 濇脈 | 渋り、途切れるよう | 血瘀・血虚 |
| 弦脈 | ピンと張った弦のよう | 肝気鬱結・痛証 |
| 緊脈 | 縄を引っ張るように緊張 | 寒邪・痛証 |
| 濡脈 | 柔らかく、按じると消える | 湿証・気虚 |
| 弱脈 | 沈んで弱く、按じると絶えそう | 気血両虚 |
脈診は技術的にも奥深く、三部九候といった古典的な概念も活用されます。
臨床では複数の脈状が同時に現れることもあるため、全体の症状と照らし合わせながら総合的に判断しましょう。
🌟まとめ
四診法は「観て、聴いて、聞いて、触る」という基本的な人間の感覚をフルに使って、患者の状態を全体的にとらえる診断法です。
現代医学の検査データでは捉えきれない、微妙な体調の変化や体質も読み取れる点が魅力です。
東洋医学の臨床力を高めるためには、四診をバランスよく用いる練習と、実際の症例を多く経験することが大切です。
🌟四診を学びたい方におすすめのアイテム
四診の理解を深め、日々の臨床や学習に活かしたい方へ。鍼灸学生・東洋医学ファン必見のアイテムをご紹介します。
🌟四診を学ぶのにおすすめの教材
📘『東洋医学の教科書』
初心者にもわかりやすく、望診・舌診・脈診の基本を丁寧に解説。図解が豊富で理解が深まります。
📚 臨床中医実践弁証トレーニング
八綱弁証・舌・脈・問診を系統的に学べる良書。
教科書の補助や国家試験対策にも役立ちます。