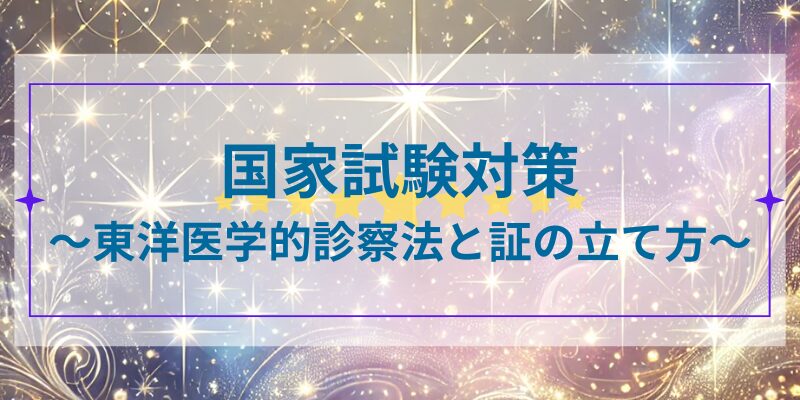🌟痛みの性質
東洋医学では、痛みの訴えを単に「痛い」として一括りにせず、その性質・感覚・部位・持続時間などをもとに、体内の状態を読み解いていきます。
これは「証を立てる」上で極めて重要な判断材料となり、問診や舌診・脈診と並ぶ四診の一部を担います。
国家試験では、「痛みの名称とその病因・病理との組み合わせ」が頻出します。
以下の表では、代表的な痛みの性質と、それに対応する病因をまとめ、その下で具体的な病証とのつながりを解説していきます。
| 脹痛 | 脹った感じ、膨満感を伴う痛み | 気滞 |
| 刺痛 | キリで刺したような痛み | 血瘀 |
| 酸痛 | だるい痛み | 虚証、湿証 |
| 重痛 | 重く感じる痛み | 湿証 |
| 冷痛 | 冷えを伴う痛み | 寒証(実寒、虚寒) |
| 灼痛 | 灼熱感を伴う痛み | 熱証(実熱、虚熱) |
| 絞痛 | 絞扼感や疝痛 | 寒証、血瘀、結石 |
| 隠痛 | 我慢できる持続性の鈍痛 | 虚証 |
| 掣痛 | 引っ張られるような痛み | 肝の病証 |
| 空痛 | 疼痛部位に空虚感を伴う | 気血精髄の不足 |
以下、それぞれの痛みについて、臨床での判断のポイントと共に解説します。
- 脹痛(ちょうつう):お腹の張り感や、胸のつかえ感として現れることが多く、感情の抑圧(肝鬱)やストレスによる気の巡りの悪さが主因。「気滞」証に属し、疏肝理気の治法が選ばれます。
- 刺痛(しつつう):位置が固定し、夜間に悪化する刺すような痛みは「血瘀(けつお)」を示唆。瘀血による経絡の阻滞が原因とされ、活血化瘀が基本方針です。
- 酸痛(さんつう):筋肉や関節がだるく重い感覚。虚証や湿証に多く、気血の不足や脾虚による痰湿の停滞が背景にあります。
- 重痛(じゅうつう):身体が鉛のように重く、特に下肢に多い。湿邪による停滞が主な原因で、「利湿」や「健脾」などの治療法が使われます。
- 冷痛(れいつう):寒冷によって悪化し、温めると改善する痛み。寒邪の侵入(外感)や陽虚による体内の冷え(内因)によって発生します。温補や散寒法が必要。
- 灼痛(しゃくつう):焼けるような熱感を伴い、炎症や発熱などの実熱証、または陰虚による虚熱証でも出現。清熱または滋陰清熱が治療指針。
- 絞痛(こうつう):絞られるような激しい痛み。腎結石や疝気に近い感覚で、寒邪による気血の停滞や、瘀血・実邪の存在が示唆されます。
- 隠痛(いんつう):はっきりしない鈍痛で、慢性的・持続的。気血不足や陽気の虚弱が原因となるため、補気補血や温補法を選びます。
- 掣痛(せいつう):肝経に沿って放散するような痛み。肝風内動や肝気鬱結に関連し、特に女性の月経痛や緊張による症状に現れやすい。
- 空痛(くうつう):空虚感が伴う痛みで、精・血・気の深刻な不足がある場合に起きる。慢性疾患や高齢者によく見られ、滋補肝腎・填精益髄の治療が用いられます。
このように、同じ「痛み」でも東洋医学では非常に繊細に分類され、それぞれに対応した治法があります。
臨床だけでなく国家試験でもこの分類がそのまま問われることが多いため、用語と病因をセットで覚えておきましょう。
🌟脈状
東洋医学における診察法の中でも、脈診は非常に重要な位置を占めています。
脈を診ることで、気血の状態・陰陽の偏り・邪の有無・臓腑の虚実などを把握することができ、「証の立て方」に直結する情報が得られます。
国家試験では、脈状の名称とその特徴、証との関係、さらに五臓・五行との関連を問う問題が頻出です。まずは基本的な分類とその組み合わせを表で確認しましょう。
| 祖脈 | 浮・沈・遅・数・虚・実 |
| 八脈 | 浮・沈・遅・数・弦・緊・伏・結 |
| 七表脈(陽脈) | 浮・芤・滑・実・弦・緊・洪 |
| 八裏脈(陰脈) | 沈・緩・濇・濡・遅・伏・微・弱 |
| 九道脈 | 長・短・細・虚・動・牢・結・促・代 |
各分類にはそれぞれ特徴があり、現れる脈状から体内の状態を推察できます。
例えば「浮脈」は体表近くで触れ、表証や陽盛を、「沈脈」は深く沈み、裏証や陰証を示します。
「弦脈」はピンと張った弓のような脈で、肝胆の病変や気滞などに対応します。
また、以下の表では「五臓・五行・季節」との関連性をまとめたものです。
これは四時脈(季節脈)と呼ばれ、国家試験でも問われやすい分野です。
| 肝 | 春 | 弦脈 |
| 心 | 夏 | 洪脈 |
| 脾 | 長夏 | 代脈 |
| 肺 | 秋 | 毛脈 |
| 腎 | 冬 | 石脈 |
これらの脈は、生理的に季節と呼応して強くなる傾向があり、たとえば春には「弦脈」が触れやすく、これは肝気の昂ぶりと連動しています。
また、病的に見られる場合には、該当する五臓の異常を示すことがあります。
他にも臨床で重要なのが、「虚里の脈」です。これは左乳下(心尖部)で触れる拍動のことで、心陽・真気の盛衰を示すとされています。
動悸や息切れを訴える患者で虚里の脈が弱いとき、元気の衰え(元気虚)や心陽虚などの証を考える必要があります。
- 虚里の脈:左乳下に感じる動悸。心気の強弱を示す。
以下、代表的な脈状と対応する証の例をまとめます:
- 浮脈:表証、外感風寒、風熱など
- 沈脈:裏証、寒邪内陥、気滞
- 遅脈:寒証、陽虚
- 数脈:熱証、陰虚
- 滑脈:痰湿、実熱、妊娠
- 濇脈:血虚、血瘀
- 弦脈:肝病、痛証、痰飲
- 緊脈:寒証、痛証
- 微脈:気血両虚、陽虚
これらを理解しておくことで、脈診だけでもおおよその「証」を立てる助けとなります。
国家試験では「○○脈はどんな証を示すか」「脈と五臓・季節の組み合わせ」などの形で出題されますので、パターンごとに押さえておきましょう。
🌟六部定位
東洋医学の脈診の中でも、とくに臓腑の状態をより細かく見極めるために用いられるのが「六部定位(ろくぶじょうい)」です。
これは両手の寸口・関上・尺中という3つの脈位をそれぞれ左右で診る方法で、合計6カ所の脈を通じて、六つの臓腑系統を評価するという診断法です。
この六部定位法は、古典である『難経』にその基礎が述べられており、現在の中医学でも広く用いられています。
特に臓腑ごとの病変の有無や、虚実・寒熱・気血の偏りを判断する上で有効です。
| 寸口 | 関上 | 尺中 | |
| 右手 | 肺・大腸 | 脾・胃 | 心包・三焦 |
| 左手 | 心・小腸 | 肝・胆 | 腎・膀胱 |
この表は国家試験でもよく出題される「六部定位」の基本です。
左右の手それぞれに3つの脈位があり、寸口は上焦、関上は中焦、尺中は下焦に対応しているとされます。
以下に左右の部位ごとの対応関係を詳しく見ていきましょう。
- 右手・寸口:肺・大腸に対応。呼吸器系や免疫・皮膚疾患を示唆します。
- 右手・関上:脾・胃に対応。消化吸収や脾虚の兆候を捉えます。
- 右手・尺中:心包・三焦に対応。心神の不安や気機の調節を反映します。
- 左手・寸口:心・小腸に対応。循環器や神志活動に関連する異常が表れます。
- 左手・関上:肝・胆に対応。情志・血流・疏泄作用のバランスを見る部位です。
- 左手・尺中:腎・膀胱に対応。生命力や下焦の冷え・浮腫などに関係します。
特に重要なのは、左右差の診断です。
左手は「血・陰」に関係し、右手は「気・陽」に関係するとされ、同じ臓腑の異常でも、左右で触れる脈の違いからより深い診断が可能になります。
例えば、右手関上の脈が弱く濡脈なら「脾陽虚」や「脾気虚」の可能性があり、左手関上で弦脈なら「肝気鬱結」や「肝陽上亢」を疑います。
こうした組み合わせで複合的に「証」を立てるのが東洋医学の魅力でもあり、実力が試される場面です。
国家試験では、「寸・関・尺の部位に対応する臓腑」を問う定番の問題があり、語呂合わせで覚える受験生も多いです。
たとえば「肺脾包/心肝腎」と縦読みで覚えると、右手・左手の上中下焦が整理しやすくなります。
また臨床では、触診の際に力加減を調節することも重要です。
寸口は軽く触れる「浮診」、関上は中程度、尺中はやや深く圧をかける「沈診」によって正確に状態を読み取ります。
これも六部定位の理解には欠かせません。
六部定位を正確に把握しておくことで、患者さんの体調の傾向を立体的に捉えられます。
これは国家試験だけでなく、実際の鍼灸臨床でも非常に有用な診断技術です。
🌟難経腹診
腹診(ふくしん)は東洋医学における重要な切診法の一つであり、腹部に現れる異常を通して五臓六腑の状態を推察します。
中でも『難経』に記された腹診法は、臍(へそ)を中心に五臓の病変を診断するための古典的診断法として、現在の鍼灸臨床や国家試験対策でも頻繁に登場します。
「難経腹診」と呼ばれるこの診断法では、臍を中心とした五方向の圧痛や硬結の有無、質感などから、対応する臓器の虚実・病証を読み取ります。
以下の表は、その基本的な対応関係をまとめたものです。
| 肝病 | 臍の左に硬結や圧痛 | 胸脇苦満/小腹急結/裏急 |
| 心病 | 臍の上に硬結や圧痛 | 心下痞硬 |
| 脾病 | 臍の周囲に硬結や圧痛 | 小腹急結/裏急 |
| 肺病 | 臍の右に硬結や圧痛 | (記載なし) |
| 腎病 | 臍の下に硬結や圧痛 | 小腹不仁/小腹急結/裏急 |
このように、五臓それぞれに特徴的な腹部の圧痛点が存在するとされ、それを探ることで病変部位を絞り込んでいきます。
特に重要なのは、左右の圧痛の違いや、深さ・質感の差です。
たとえば「硬結」は実証、「虚軟」は虚証を示唆します。
- 肝病:臍の左側に圧痛。胸脇苦満や小腹急結が伴えば「肝鬱気滞」や「肝実」などを示す。
- 心病:臍の上、心下部に圧痛。心下痞硬(みぞおちのつかえ)を伴えば「痰飲」「心気鬱結」など。
- 脾病:臍周囲全体が緊張・圧痛。「脾虚湿盛」や「食積」を示唆する。
- 肺病:臍の右側に圧痛が出るが、関連症状が少なく、国家試験では「記述なし」のまま問われることが多い。
- 腎病:臍の下に圧痛が出現。小腹不仁(冷えや感覚鈍麻)や裏急(下腹部の緊張)が伴えば、腎陽虚や腎精不足を疑う。
また、症状欄に頻出する「小腹急結(しょうふくきゅうけつ)」という表現は、下腹部が突っ張るように硬くなる状態で、肝経や腎経の異常、あるいは瘀血や寒邪の停滞が原因とされます。国家試験では「この腹部所見が示す臓器は?」という形式で問われるため、臍の上下左右の位置関係と対応臓腑を正確に覚えることが得点に直結します。
臨床では、腹診は視診・触診・聴診・打診と組み合わせて用いられ、舌診や脈診とともに総合的な証を導き出すための重要なヒントになります。
特に小児や虚弱者では、脈診が困難な場合もあるため、腹診が判断材料として大きな意味を持つ場面もあります。
なお、腹診における異常は必ずしも単独ではなく、複数臓腑の所見が重なることもあります。
たとえば、臍下と左に圧痛がある場合、腎と肝の両方の関与を示し、「腎虚肝鬱」や「肝腎陰虚」などの複合証を立てるきっかけになります。
このように、『難経』腹診の知識は国家試験でも臨床でも重要な武器になります。
臍を基準に「上=心」「下=腎」「左=肝」「右=肺」「周囲=脾」としっかり整理しておきましょう。
🌟舌診
舌診(ぜっしん)は、東洋医学における望診(ぼうしん)の一つであり、身体の内側の状態を舌の色、形、苔(こけ)などから読み取る重要な診断法です。
舌は「内臓の鏡」とも呼ばれ、特に気血の状態・津液の充実度・寒熱虚実を示す指標とされます。
国家試験では、「舌のどの部位がどの臓腑に対応するか」という基本的な問題が頻出です。
下記の表に、舌の各部位と臓腑の対応関係をまとめました。
| 舌尖部 | 心・肺・上焦 |
| 舌中部 | 脾・胃・中焦 |
| 舌辺部 | 肝・胆・中焦 |
| 舌根部 | 腎・下焦 |
舌を診るときは、舌質(色・形)と舌苔(苔の厚さ・色・湿潤度)を合わせて観察しますが、まずはこの「部位と臓腑の対応」を正しく覚えることが基本です。
特に国家試験では、舌尖が紅い=心火亢進、舌根が紫=腎虚または瘀血など、局所的な所見と臓腑病理との関係が問われます。
- 舌尖部(心・肺・上焦):舌の先端。赤みが強ければ「心火亢進」、尖が裂けている場合は「心血虚」。白っぽければ「肺気虚」や「寒邪侵襲」を示唆します。
- 舌中部(脾・胃・中焦):舌の中央部。苔が厚く黄ければ「胃熱」、白く湿っていれば「脾陽虚」や「湿邪困脾」の可能性があります。
- 舌辺部(肝・胆・中焦):舌の両側。紅く腫れていれば「肝火」、歯痕があれば「肝血虚」や「脾虚による水湿停滞」が考えられます。
- 舌根部(腎・下焦):舌の奥。色が黒っぽい・苔が剥がれていれば「腎陰虚」や「腎精虚損」、白く湿れば「腎陽虚」や「寒湿」の傾向です。
舌診は視覚的な診断法なので、言語化しにくい所見を明確にする力があります。
また、他の診察法(脈診・腹診・問診)と組み合わせることで、より確実な「証の立案」が可能になります。
国家試験対策としては、以下の3点を重点的におさえましょう:
- 部位と臓腑の対応関係(上焦=舌尖、中焦=舌中・辺、下焦=舌根)
- 舌質の色:淡=虚、紅=熱、紫=瘀血
- 苔の厚薄:厚=実、薄=虚、無=陰虚や津液不足
臨床では、風邪や発熱時に舌尖部が赤くなったり、慢性胃腸障害で舌中央部に苔が付着したりと、症状との一致を確認する機会も多く、患者の主観に頼らず「目で見て判断できる」数少ない診察法の一つです。
さらに、舌診は患者自身にも伝えやすいため、セルフチェックとしても活用できます。
「舌が赤いから胃熱があるかも」「苔がべったりしてるから湿が溜まっているかも」といった形で、健康意識の向上にもつながる優れた指標です。
このように、舌診は東洋医学の中でも簡便かつ効果的な診断手法です。
「どこが赤いか・苔はどこにあるか・どんな質感か」を丁寧に見ていくことで、証を立てるための確かな手がかりとなります。
🌟鍼灸国家試験過去問
第1回-104
問診と関連する組合せはどれか。
- 呼 ─── 笑 ─── 歌
- 酸 ─── 苦 ─── 甘
- 臊─── 焦 ─── 香
- 青 ─── 赤 ─── 黄
第1回-105
八裏の脈はどれか。
- 結脈
- 緊脈
- 濡脈
- 滑脈
第1回-106
冷え症で他覚的にも冷えが認められる状態を何というか。
- 傷寒
- 厥冷
- 悪風
- 悪寒
第1回-107
六部定位の脈診部位と臓腑との組合せで正しいのはどれか。
- 左の寸口 ─── 心包・三焦
- 右の尺中 ─── 腎・膀胱
- 左の関上 ─── 脾・胃
- 右の寸口 ─── 肺・大腸
第1回-108
聞診で用いる感覚はどれか。
- 視覚
- 触覚
- 嗅覚
- 味覚
第2回-105
脈について正しい記述はどれか。
- 弦脈、緊脈は陰脈である。
- 人迎気口脈診は経絡病証を診る。
- 陰脈、陽脈は粗脈である。
- 左手の関上の脈は肝・胆を診る。
第2回-106
難経の腹診において臍の下で診る病はどれか。
- 脾の病
- 肝の病
- 腎の病
- 心の病
第3回-105
難経による五臓と腹診部位との組合せで正しいのはどれか。 (
- 腎 ─── 臍の右側
- 肺 ─── 心下部
- 心 ─── 中胃部
- 肝 ─── 臍の左側
第3回-106
腹証で正しい組合せはどれか。
- 心下痞硬 ─── 脾
- 胸脇苦満 ─── 肝
- 小腹不仁 ─── 瘀血
- 小腹急結 ─── 腎
第3回-109
実熱証で診られる脈状はどれか。
- 数
- 細
- 虚
- 沈
第4回-105
舌診部位と臓腑との組合せで正しいのはどれか。
- 舌尖部 ─── 腎
- 舌根部 ─── 心
- 舌辺部 ─── 肺
- 舌中部 ─── 脾
第4回-106
切経による実の反応はどれか。
- 陥下
- 不仁
- 緊張
- 冷感
第4回-107
六部定位脈診で左手関上の部位を沈めて診る臓腑はどれか。
- 胃
- 肝
- 腎
- 胆
第5回-104
左乳下で触れる脈はどれか。
- 虚里の脈
- 腎間の動悸
- 胃の気の脈
- 虎口三関の脈
第5回-105
胸脇苦満を示すのはどの臓の病か。
- 腎
- 肝
- 肺
- 脾
第5回-106
六部定位脈診の部位と臓腑との組合せで正しいのはどれか。
- 右の寸口 ─── 心・小腸
- 左の寸口 ─── 肺・大腸
- 右の関上 ─── 肝・胆
- 左の尺中 ─── 腎・膀胱
第5回-107
問診で診るのはどれか。
- 悪寒
- 体臭
- 体形
- 脈状
第6回-104
瘀血の腹証はどれか。
- 小腹急結
- 心下痞硬
- 小腹不仁
- 胸脇苦満
第6回-107
七表の脈でないのはどれか。
- 弦脈
- 実脈
- 遅脈
- 浮脈
第6回-109
神技(望診)で診るのはどれか。
- 顔色
- 筋硬結
- 関節痛
- 呼吸音
第6回-111
六部定位脈診で肝の臓の脈状はどこで診るか。
- 右手関上
- 左手関上
- 左手寸口
- 右手尺中
第7回-105
六部定位脈診で右尺中で診る臓腑はどれか。
- 心と小腸
- 心包と三焦
- 腎と膀胱
- 肝と胆
第7回-106
珠をころがしたような脈はどれか。
- 緩脈
- 滑脈
- 洪脈
- 弦脈
第7回-107
腎を診る舌診部位はどれか。
- 舌根
- 舌辺
- 舌中央
- 舌尖
第8回-105
弱々しく細く指に感じられる脈状で虚証にみられるのはどれか。
- 濡脈
- 弦脈
- 洪脈
- 滑脈
第8回-106
聞診で診るのはどれか。
- 五香
- 五味
- 五悪
- 五主
第8回-107
小腹不仁を示す臓の病はどれか。
- 肝
- 心
- 腎
- 脾
第8回-108
脈について誤っている記述はどれか。
- 四季に応じる脈には弦脈がある。
- 八裏の脈には結脈がある。
- 祖脈には数脈がある。
- 七表の脈には実脈がある。
第9回-104
腹診で誤っている記述はどれか。
- 天枢穴では大腸の異常を診る。
- 五臓診では肝の状態は臍の左側で診る。
- 上実下虚の腹は脾実腎虚にみられる。
- 胸脇苦満は心実証でみられる。
第9回-105
九道の脈はどれか。
- 浮脈
- 弦脈
- 細脈
- 遅脈
第9回-107
脈についての記述で誤っているのはどれか。
- 四季の移り変わりに応じて変動する。
- 虚里の動で腎の働きを診る。
- 祖脈は脈状の基本である。
- 臍下丹田の動悸で先天の原気を診る。
第10回-105
胸脇苦満を呈する臓はどれか。
- 肺
- 肝
- 心
- 腎
第10回-106
四季と脈状との組合せで誤っているのはどれか。
- 秋 ─── 毛脈
- 冬 ─── 石脈
- 春 ─── 緩脈
- 夏 ─── 洪脈
第10回-107
六部定位脈診で腎を診る方法はどれか。
- 左の関上を沈めて診る。
- 左の尺中を沈めて診る。
- 右の寸口を浮かせて診る。
- 右の関上を浮かせて診る。
第10回-108
六部定位脈診で左手関上の沈が虚している場合、難経六十九難に基づく治療穴で適切なのはどれか。
- 曲泉と陰谷
- 労宮と大都
- 太淵と太白
- 復溜と経渠
第11回-107
陰虚証の症状でないのはどれか。
- 盗汗
- 潮熱
- 手足のほてり
- 自汗
第12回-105
虚証の症状で適切でないのはどれか。
- 下痢
- 短気
- 自汗
- 拒按
第13回-104
五心煩熱がみられるのはどれか。
- 血虚
- 気虚
- 陰虚
- 陽虚
第13回-106
六部定位脈診において左関上で診る臓腑はどれか。
- 脾と胃
- 肺と大腸
- 心包と三焦
- 肝と胆
第14回-99
聞診で診るのはどれか。
- 五主
- 五香
- 五味
- 五液
第14回-100
舌診で舌尖部に配当されるのはどれか。
- 心
- 脾
- 腎
- 肝
第14回-102
胃熱による症状はどれか。
- 梅核気
- 五更泄瀉
- 心下痞
- 消穀善飢
第14回-104
半表半裏証でみられないのはどれか。
- 悪風
- 胸脇苦満
- 往来寒熱
- 口が苦い
第15回-100
陽虚の症状で適切でないのはどれか。
- 自汗
- 小便不利
- 四肢厥冷
- 畏寒
第16回-98
顔面と舌の五臓配当で正しい組合せはどれか。
- 左の頬 ―――― 舌中
- 鼻 ―――――― 舌尖
- 右の頬 ―――― 舌辺
- オトガイ ─── 舌根
第16回-100
虚証にみられないのはどれか。
- 盗汗
- 酸痛
- 喜温
- 黄苔
第17回-98
熱証にみられないのはどれか。
- 口渇
- 月経先期
- 小便自利
- 鼾声
第17回-101
八裏の脈はどれか。
- 代脈
- 短脈
- 緊脈
- 伏脈
第17回-104
「咽喉の閉塞感、怒りっぽい、抑うつ、胸脇苦満」 最も考えられる脈状はどれか。
- 結脈
- 弦脈
- 濡脈
- 濇脈
第18回-100
痛みの性質と病証との組合せで誤っているのはどれか。
- 刺痛 ─── 血瘀
- 重痛 ─── 湿証
- 隠痛 ─── 気滞
- 酸痛 ─── 虚証
第18回-101
季節と脈状との組合せで正しいのはどれか。
- 春 ─── 緩脈
- 秋 ─── 石脈
- 冬 ─── 毛脈
- 夏 ─── 洪脈
第18回-102
目のかすみ、めまい、脇部の隠痛および手足のふるえを呈する病証で最も考えられる舌質はどれか。
- 淡白舌
- 淡紅舌
- 紫舌
- 紅舌
第19回-98
「55歳の女性。皮下出血しやすく、皮膚はかさつき、腹が脹る。月経時に血塊を伴う。」 この患者の舌証として正しいのはどれか。
- 胖舌
- 燥苔
- 灰苔
- 紫舌
第19回-100
六経病証の頭痛分類で正しい組合せはどれか。
- 前頭部 ─── 太陽経頭痛
- 側頭部 ─── 陽明経頭痛
- 後頭部 ─── 少陽経頭痛
- 頭頂部 ─── 厥陰経頭痛
第19回-101
所見と病証との組合せで正しいのはどれか。
- 口苦 ───── 脾陽虚証
- 口淡 ───── 脾気虚証
- 消穀善飢 ─── 脾気虚証
- 厭食 ───── 胃寒証
第19回-104
六部定位脈診で左手尺中の沈が虚している場合、難経六十九難に基づく配穴で適切な組合せはどれか。
- 中衝 ─── 大敦
- 尺沢 ─── 陰谷
- 経渠 ─── 復溜
- 陰谷 ─── 曲泉
第20回-94
所見と病証との組合せで正しいのはどれか。
- 拒按 ─── 陽虚証
- 隠痛 ─── 陰実証
- 潮熱 ─── 陽実証
- 盗汗 ─── 陰虚証
第20回-96
食滞について誤っている記述はどれか。
- 消渇が起こる。
- 大便に酸臭がある。
- 呑酸がある。
- 食を嫌う。
第20回-98
一定の時刻に発熱する特徴をもつのはどれか。
- 但熱不寒
- 往来寒熱
- 潮熱
- 壮熱
第20回-100
「45歳の男性。首や肩のこりが強く、寝汗をよくかき熟睡できない。便が硬く排便しづらい。」 この患者の舌の所見と脈状との組合せで正しいのはどれか。
- 淡舌 ─── 弦脈
- 紅舌 ─── 細脈
- 痩舌 ─── 滑脈
- 胖舌 ─── 結脈
第20回-101
季肋部で診る腹証はどれか。
- 小腹急結
- 胸脇苦満
- 裏急
- 心下痞鞭
第20回-103
「頭痛、首と肩がこる、手足の関節が痛む、厚着をしても寒い、微熱、薄白苔、緊脈。」 この患者の症状として正しいのはどれか。
- 食欲不振
- 無汗
- 口渇
- 泄瀉
第21回-99
胃気の上逆でみられるのはどれか。
- 鼾
- 欠
- 喘
- 吃逆
第21回-103
陰虚による舌質の色はどれか。
- 紫舌
- 淡白舌
- 紅舌
- 淡紅舌
第21回-104
だるい痛みはどれか。
- 刺痛
- 隠痛
- 酸痛
- 脹痛
第21回-105
虚証でみられるのはどれか。
- 細脈
- 緊脈
- 洪脈
- 滑脈
第22回-100
統血作用の失調でみられるのはどれか。
- 陽萎
- 崩漏
- 帯下
- 秘結
第22回-103
心・心包の病証で多くみられるのはどれか。
- 心下痞鞭
- 裏急
- 小腹急結
- 胸脇苦満
第23回-91
臓腑の働きと五華の組合せで正しいのはどれか。
- 神を蔵する ――― 毛
- 精を蔵する ――― 爪
- 営を蔵する ――― 唇
- 血を蔵する ――― 面色
第23回-95
嘈雑がみられる病証はどれか。
- 食滞
- 胃の実熱
- 胃の虚熱
- 脾胃の湿熱
第23回-100
「56歳の男性。主訴は食欲不振。腹部の痞えや膨満感、重痛を伴う。口が粘る、口苦、臭いの強い下痢がみられる。」 本患者の病証でみられる脈状はどれか。
- 滑脈
- 濇脈
- 細脈
- 結脈
第24回-98
陰虚にみられる舌苔はどれか。
- 少苔
- 膩苔
- 潤苔
- 厚苔
第24回-99
次の文で示す患者の腹診所見はどれか。 「75歳の女性。半年前から膝に力が入らない。姿勢は前かがみで、1回の尿量が少なく、足がむくむ。」
- 小腹不仁
- 胸脇苦満
- 少(小)腹急結
- 虚里の動
第25回-97
脈診で左手関上「浮」に配当される臓腑の募穴はどれか。
- 関元
- 章門
- 日月
- 石門
第25回-98
次の文で示す患者の病証でみられる舌象はどれか。 「43歳の男性。主訴は頭痛。めまい、目赤、胸脇苦満を伴う。最近、仕事上のストレスを抱えている。」
- 紅舌
- 紫舌
- 青舌
- 淡白舌
第25回-100
「31歳の女性。主訴は頭痛と肩こり。月経は不定期で月経時に頭痛が憎悪し、下腹部痛も出現する。月経血に血塊がみられ、舌下静脈の怒張もみられる。」 本患者の痛みの特徴はどれか。
- 痛む部位が移動する。
- 夜間に痛みが増悪する。
- 冷やすと疼痛が軽減する。
- だるい感じの痛みが現れる。
第25回-101
「31歳の女性。主訴は頭痛と肩こり。月経は不定期で月経時に頭痛が憎悪し、下腹部痛も出現する。月経血に血塊がみられ、舌下静脈の怒張もみられる。」 本患者の病証でみられる脈状はどれか。
- 浮いていて細軟の脈
- 絹糸のように細くて力があり、按じて左右に移る脈
- 弾力に富み、琴の弦を按じるような脈
- ざらざらとして渋滞したような脈
第26回-99
次の文で示す患者の病証でみられる脈診所見はどれか。 「52歳の男性。主訴は腰痛。不眠や手足のほてりを伴う。仕事の疲れがたまると眩暈や盗汗が起こる。」
- 弦脈
- 滑脈
- 細脈
- 緊脈
第26回-100
六部定位に配当される脈診部位と絡穴部位の組合せで正しいのはどれか。
- 右寸口 ――― 尺側手根屈筋腱の橈側縁、手関節掌側横紋の上方1寸
- 左関上 ――― 長母指外転筋腱と短母指伸筋腱の間、手関節掌側横紋の上方1寸5分
- 右関上 ――― 前脛骨筋の外縁、外果尖の上方8寸
- 左尺中 ――― 長掌筋腱と橈側手根屈筋腱の間、手関節掌側横紋の上方2寸
第27回-93
胆経の病でみられるのはどれか。
- 嘆息
- 喘息
- 噴嚏
- 吃逆
第27回-95
次の文で示す患者の病証で最もみられる脈状はどれか。 「45歳の女性。主訴は膝痛。10日前に転倒して膝を打撲した。現在も膝内側が腫れて痛み、夜間も痛む。」
- 洪脈
- 滑脈
- 濡脈
- 濇脈
第27回-97
舌診で気陰両虚の所見はどれか。
- 舌の色が青紫色である。
- 舌苔が剥落している。
- 舌体が腫れて大きい。
- 舌下静脈の怒張がある。
六部定位脈診で左手尺中の沈の部が虚している場合、難経六十九難に基づく治療穴の部位はどれか。
- 膝後内側、半腱様筋腱の外縁、膝窩横紋上
- 足内側、第1中足指節関節内側の近位陥凹部、赤白肉際
- 下腿後内側、アキレス腱の前縁、内果尖の上方2寸
- 足の第1指、末節骨外側、爪甲角の近位外方1分
第28回-96
次の文で示す患者の病証で最もみられる汗の状態はどれか。 「36歳の男性。主訴は咳嗽。水様の鼻汁を伴い、息切れ、倦怠感も訴える。脈は弱。」
- 大汗
- 絶汗
- 自汗
- 盗汗
第28回-99
次の文で示す患者の病証で最もみられる舌所見はどれか。 「54歳の女性。主訴は肩こり。2週間前に感冒にかかり咳が強く出た。現在も透明な鼻汁が出て痰が多い。」
- 膩苔
- 黄苔
- 剥落苔
- 燥苔
第29回-93
陰虚にみられる舌苔はどれか。
- 少苔
- 潤苔
- 厚苔
- 膩苔
第29回-103
次の文で示す患者の病証で最もみられる症状はどれか。 「42歳の女性。主訴は月経周期の乱れ。子どもの面倒をみながらの在宅勤務でイライラすることが多い。」
- 短気
- 太息
- 呵欠
- 噴嚔
第29回-105
六部定位脈診で右手関上の沈の部が虚している場合、難経六十九難に基づく治療穴はどれか。
- 曲泉
- 労宮
- 中渚
- 商丘
第30回-102
次の文で示す患者の病証で最もみられる脈状はどれか。 「43歳の男性。主訴は便秘。1週間前に風邪を引き、その後、口渇が強くなり発汗も多くなった。午後3時から5時くらいまで体温が高くなる。」
- 緩脈
- 濡脈
- 弦脈
- 洪脈
第31回-103
汗と脈状の組合せで正しいのはどれか。
- 大汗 ――― 滑脈
- 無汗 ――― 濇脈
- 手足心汗 ――― 細脈
- 戦汗 ――― 結脈
第31回-104
次の文で示す症例の腹診所見はどれか。 「44歳の女性。主訴は頭痛。半年前に転職し、上司との人間関係がうまくいかず気が滅入る。頭部に刺すような痛みがあり、顔のシミが目立つようになってきた。」
- 小腹不仁
- 腹裏拘急
- 心下痞鞭
- 少腹急結
第31回-105
六部定位脈診で左手関上の沈の部が実している場合、難経六十九難に基づく治療穴はどれか。
- 陽輔
- 少府
- 陰谷
- 経渠
🌟まとめ:東洋医学的診察で「証」を立てる力を身につけよう
本記事では、東洋医学における診察法と「証の立て方」について、国家試験対策の視点から5つの重要なテーマを学んできました。
具体的には以下のような内容でした。
- 🌸痛みの性質:10種類の痛みの分類と、それぞれの関連証(気滞・血瘀・寒熱・虚実など)を整理。
- 🌸脈状:祖脈・八脈・七表脈・八裏脈・九道脈といった分類と、季節・五臓との関係を学習。
- 🌸六部定位:左右の寸・関・尺の脈位と臓腑の対応を明確に把握。脈診の診断力を高める要素。
- 🌸難経腹診:臍を中心とした腹部の圧痛点から、五臓の病変を推測する古典的診断法。
- 🌸舌診:舌の部位・色・苔を観察し、上中下焦および寒熱・虚実を判断する視診の柱。
これらはすべて「四診法(望・聞・問・切)」の中に位置づけられる技術であり、それぞれ単独で使うのではなく、複合的に組み合わせて初めて正確な「証」が立てられるというのが東洋医学の大きな特徴です。
国家試験では、知識を単に覚えるだけでなく、「どの所見がどの臓腑と関連するか?」「どの証に分類されるか?」といった臨床的思考力が求められる問題が出題されます。
例えば、舌尖が赤く・脈が数で・胸がチクチクと痛むような場合、それらを総合して「心火亢進・血瘀」のような証を導くことができるようになることが理想です。
また、実際の臨床では、こうした所見に加え、患者の訴え・生活背景・気候や体質なども含めた多角的な視点から診断を行うことが求められます。
日々の学習においては、「分類→覚える→使ってみる」というサイクルを意識し、実践的な知識として定着させていきましょう。
模擬問題や過去問演習と組み合わせながら、繰り返し復習することが得点アップへの近道です。
東洋医学は、臨床の中で活きる「生きた知識」です。
国家試験を通過点として、卒後も使える技術として磨き上げていきましょう。