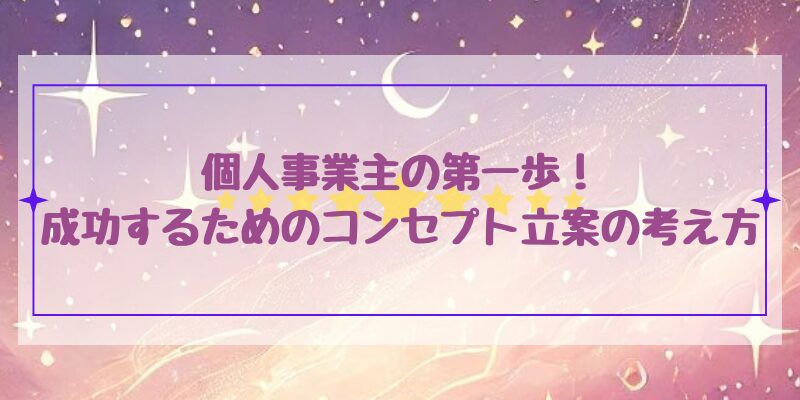こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
個人事業主として「開業する」と決めたとき、多くの人が最初に手に取るのは開業関連の書籍ではないでしょうか。
鍼灸院や整体院、エステサロンやリラクゼーションサロンなど、ジャンルごとに出版されている開業本は数多くあります。
ところが、実際に読んでみると、「集客方法」や「メニュー作成」「店舗内装」「SNS運用」など、どれも似たような内容ばかり。
具体的な開業の準備フローや、資金面、行政手続き、地域ニーズを踏まえた事業設計の手順について、わかりやすく書かれた本はなかなか見つかりませんでした。
それに、内容の大半は著者の体験談ベースで、「私はこうやって上手くいきました」という話が多いのです。
読んでいて刺激にはなりますが、それがそのまま自分に当てはまるわけではありません。
地域も違えば対象も違うし、資金も人脈もスキルもそれぞれ。
むしろ、同じことをマネしてもうまくいかないリスクのほうが高いのではないかと感じました。
やはり、「自分の軸」を持つこと。
それが開業において一番大切なのだと感じます。
そんなとき、具体的なステップや思考の道筋が書かれている実用的な一冊と出会いました。
それがこちらです。
↑「はじめての鍼灸マッサージ治療院 開業ベーシックマニュアル」医道の日本社刊です。
この本には、ただの成功体験やマインド論だけでなく、実際に「どこから始めるべきか」「どう進めればよいか」という開業プロセスが丁寧に書かれています。
しかも、鍼灸院に特化しているので、無駄がなく現実的な視点で読めるのも魅力。
「開業ってギャンブルじゃないの?」と思っていたKagayaですが、この本を読むことで「計画があれば、成功の確率は上がる」ということが腑に落ちました。
現在はこの書籍をもとに、Kagaya自身のコンセプト立案、開業スタイル、ターゲット分析を行っています。
本記事では、その実践内容を具体的に紹介していきます。
これから開業を考えている方の参考になれば嬉しいです!
🌟開業するまでの手順
鍼灸院やサロンの開業を目指すとき、どこから手を付けていいのかわからないという方は多いのではないでしょうか。
Kagayaも最初は、「開業=物件を借りてお店を出すこと」としか考えていませんでした。
ですが実際には、開業には順序と計画があり、順番を間違えると無駄な出費や方向性のブレにつながってしまうこともあります。
ここでは、Kagaya自身が「開業ベーシックマニュアル」を参考にしながら整理した、一般的な開業までの流れをご紹介します。
そして、そのプロセスをどう自分のビジョンに落とし込んだかも共有します。
- コンセプトを考える
まずは「どんなサービスを、誰に、なぜ届けたいのか」を明確にすることが最優先です。これがすべての軸になります。Kagayaは、重症心身障がい児(者)とその家族を支えることを主軸に、「看護×鍼灸×療育」を組み合わせた訪問型サービスを構想中です。 - 開業スタイルを選ぶ
物件を借りるか、自宅の一部を使うか、訪問専門にするか。Kagayaは開業資金を抑えるため、まずは訪問専門+シェアサロン併用という形でスタートする予定です。 - 立地を考える
実店舗型であればターゲット層にとって通いやすい場所か、バリアフリー対応かなどが大切。訪問型でも、訪問範囲(市内何km圏など)をあらかじめ決めておくと行動しやすくなります。 - 物件を探す
店舗型の場合、立地・家賃・駐車場・バリアフリー・周辺環境などを総合的にチェック。Kagayaの場合、将来的にシェアサロン以外に借りるとすれば、特別支援学校に近く、車イス対応の1階物件が必須条件になります。 - 資金の調達
開業資金には内装費・備品・広告・保険なども含まれます。助成金や補助金の活用も検討しましょう。Kagayaは学生時代から毎月3万円を貯金して開業資金に充てています。 - 内装準備
店舗開業時は、内装のテイストがターゲットに合っているかも重要です。訪問型であれば、持参するツールや雰囲気作りのアイテム(例:お灸セット、アロマ、スヌーズレン用ライトなど)を整えておくと良いでしょう。 - 備品の調達
鍼灸器具や衛生用品、ユニフォーム、施術ベッドなどが必要になります。Kagayaは訪問対応のため、持ち運びやすさと清潔感を重視して選ぶ予定です。 - 集客方法を考える
ブログやSNS、地域の福祉事業者へのチラシ配布、マルシェ出店など、自分に合ったやり方を選ぶことが大切です。Kagayaは障がい児関連施設や保護者への口コミ・紹介を重視しています。 - 各種届出の提出
開業届(税務署)、保健所への申請、個人事業主としての屋号登録などが必要になります。訪問看護や鍼灸保険を扱う場合は、さらに関係機関との調整も必要です。
このように、開業までには多くの工程がありますが、順序立てて考えていけば大丈夫です。
そして何より、「自分の生活スタイルと合っているか」「お客様と心地よい関係が築けるか」を常に意識することが、長く続けられる開業の鍵だと思います。
Kagayaも、上記の流れを参考にしながら、自分にしかできないスタイルを形にしていきたいと思っています。
🌟コンセプトの必要性
「開業する」と決めたとき、多くの人がまず考えるのは「どこでやろうか」「何をやろうか」「どうやって集客しようか」という具体的な手段かもしれません。
でも実は、それらの前に絶対に固めておくべきものがあります。
それが「コンセプト」です。
コンセプトとは、あなたがこれから始めるサービスの軸・土台・核となるものです。
「誰に、どんな価値を、どうやって提供するのか」というビジネスの“根っこ”を決める作業です。
このコンセプトが曖昧だと、どんなに立派なチラシを作っても、SNSでバズっても、結局“何をしている人なのか分からない”状態になります。
そして集まってきたお客様のニーズと提供するサービスがズレてしまい、リピートもされにくく、事業が続かない原因になってしまうのです。
Kagaya自身も、「鍼灸師として開業したい」と思ってからしばらくの間、自分の中での方向性が定まりませんでした。
「美容鍼もできる」「リハビリもやりたい」「メンタルケアも気になる」など、やりたいことが多すぎて、逆にブレてしまっていたんです。
でも、自分の過去の経験や得意分野、関心のある対象と真剣に向き合った結果、「重症心身障がい児(者)とその家族を支える」という核にたどり着きました。
そこからすべての構想が整理され、行動もスムーズになりました。
このように、コンセプトは「どんなチラシを作るか」よりも、「どんなサービスをやるのか」を決めるための指針であり、ぶれない土台です。
SNS投稿やチラシの内容、料金設定、営業エリア、サービス時間など、すべての判断基準はこのコンセプトに立ち返ることになります。
たとえば「ストレス社会で頑張る女性を癒す」ことがコンセプトなら、ターゲットは働く女性になり、夜間営業が有効だったり、アロマや美容鍼の導入が必要になったりします。
一方、「重症児を育てる家族をサポートする」がコンセプトなら、訪問型・昼間対応・看護スキルの強みなどが求められてきます。
このように、すべての選択がコンセプトによって導かれていくのです。
そしてこの作業は、短時間で済ませるものではなく、何度も見直し、育てていくものです。
時には修正することもあるし、お客様の反応によってブラッシュアップされることもあります。
最初から完璧を目指す必要はありません。
でも、だからこそ最初の一歩として、自分なりの「コンセプト」を言語化してみることが何よりも大事です。
Kagayaは、自分のコンセプトが定まったことで、やるべきことが絞れ、サービスの中身や届けたい人が明確になってきました。
これから本格的に動き出す準備が整った感覚があります。
ぜひあなたも、「開業したい」と思ったその瞬間から、「何を軸にしてこの仕事をやりたいのか?」と向き合ってみてください。
🌟コンセプトを決めるためのチェックリスト
前章でお伝えしたように、コンセプトは事業の軸です。しかし、いざ「自分らしいコンセプトを考えよう」と思っても、どう考えればよいのか分からない方も多いはず。
そこでKagayaが参考にしたのが、以下の5つのチェックポイント。これは、自分の想いや現実的な条件と照らし合わせて、ブレないコンセプトを組み立てるための指針になります。
- 事業主として自分のやりたい方向性とマッチしているか
- ターゲットとする顧客が想定できるか
- 開業スタイルや立地があらかじめ決まっている場合、現実的に可能か
- 予算があらかじめ決まっている場合、現実的に可能か
- 複数のコンセプトを掛け合わせていないか、盛りすぎていないか
それぞれ、もう少し具体的に掘り下げてみましょう。
① やりたい方向性とマッチしているか
これは単なる「興味」だけでなく、「情熱を持って長く続けられるかどうか」が問われるポイントです。Kagayaの場合、「重症心身障がい児(者)に対して、看護と鍼灸で支援したい」という強い思いが根底にありました。ブレそうになったときは、必ずここに立ち返るようにしています。
② 顧客が具体的にイメージできるか
“誰に届けたいのか”を想定することで、サービス内容や広告戦略が変わります。例えばKagayaは、「平日の日中、自宅で重度障がいの子を介護しているお母さん」を想定しています。その方が「安心して休息できる時間をつくる」ことがサービスの目的です。
③ 開業スタイルや立地の現実性
たとえば「店舗を借りて重症児を受け入れたい」と思っても、バリアフリーの1階物件が近隣に少ないと、現実的ではないかもしれません。Kagayaは、最初は自宅を拠点に訪問中心で動き、必要があればシェアサロンを活用するというスタイルを選びました。
④ 予算の制限内で可能か
初期投資を抑えたいなら、広告にお金をかけずSNSと口コミを中心にするとか、訪問型にしてテナント費をゼロにするといった工夫が必要です。Kagayaも「できるだけリスクを減らしたい」と思い、学生時代から月3万円ずつ貯金して資金準備をしています。
⑤ コンセプトが盛り過ぎていないか
「美容鍼もやりたいし、精神疾患ケアも興味あるし…」と多くを詰め込みすぎると、結局何の専門なのか分からなくなります。特に開業初期は「絞る勇気」が必要。Kagayaも、まずは重症児とその家族支援に集中し、必要ならその後に別の柱を加えていく方針にしました。
この5つの視点でチェックしていくと、「やりたいこと」と「できること」のバランスが整理され、コンセプトがより現実的で実行しやすいものになります。
ぜひ皆さんも、ノートやメモアプリにこの5つを並べて、自分自身に問いかけてみてください。
🌟事業主として自分のやりたい方向性とマッチしているか
開業において最初に確認したいのは、「自分が本当にやりたいこと」と「これから始める事業の方向性」が一致しているかどうかです。
たとえばNICUで新生児を看たいと思っていたのに、介護施設に就職してしまったような“ミスマッチ”が起こると、どんなに環境が整っていてもモチベーションが続かず、結果的に辞めてしまう原因になります。
Kagayaが目指す方向性は明確です。
「重症心身障がい児(者)専門の鍼灸ケア+看護+療育支援」。
さらにそれを、自費訪問や移動支援、卒後の夕方ケアといった柔軟なスタイルで届けることをコンセプトとしています。
一見、やりたい方向と開業内容はマッチしているように思えますが、本当にその道が自分にとって最適なのか?を見つめ直すために、ここでは「SWOT分析」という手法を用いて、内面と外部環境の両面から検討してみましょう。
SWOT分析で「ズレ」を見極める
SWOT分析とは、「S:強み」「W:弱み」「O:機会」「T:脅威」の4つの視点から自分と市場を客観的に整理する方法です。
これを活用することで、やりたいことと社会的ニーズの交差点を見出し、ズレや無理のない開業が可能になります。
S(強み)
まずは自分の持っている資格や経験、人柄や特技など、自信を持てる要素を書き出します。
- 看護師、養護教諭、普通自動車免許あり
- 鍼灸師の資格取得予定
- 重症児の介助・訪問看護・放課後デイ・学校看護経験
- 片道10km以上自転車で移動可能
- ハンドメイド・裁縫が得意
W(弱み)
苦手意識やリスク要因、事業を行う上で気がかりなことを書き出します。
- 高齢者・男性への対応に不安
- 大きな車の運転や同じ建物内での長時間勤務が苦手
- 保険診療の人員要件を満たす人脈がない
- 実費サービスで顧客がつくか不安
O(機会)
社会的背景や時流の中で追い風になりそうなことを整理します。
- 医療の発達で障がい児の出生率が上昇
- 重症児支援の需要に対して専門機関が不足
- 鍼灸は拘縮・神経系の改善に有効
- 制度外の支援の余白が多い
T(脅威)
事業展開の妨げになる制度や環境上のリスクを明確にします。
- 障がい児支援の多くは公費で完結しており、実費サービスは選ばれにくい
このように整理することで、「やりたいこと」と「できること」と「求められていること」の三つの重なる領域を確認できます。
そこに“あなたにしかできない開業スタイル”が浮かび上がるはずです。
逆に、この分析で「自分の強みが活かせない」「社会的ニーズと噛み合わない」と感じた場合は、コンセプトの再考や準備の見直しが必要です。
開業は自己満足ではなく、社会との接点をどう創るかがカギなのです。
「SWOT分析」は開業前の不安を客観的に整理するツールとして非常に有効です。
紙とペンでぜひ一度、実際に書き出してみてください。
🌟6W2Hによるコンセプトの考え方
開業にあたり、「自分がどのようなサービスを、誰に、どこで、なぜ提供したいのか?」という全体像を明確にすることが大切です。
その際に役立つフレームワークが「6W2H」です。これは「Who(誰が)」「Whom(誰に)」「Where(どこで)」「What(何を)」「Why(なぜ)」「When(いつ)」「How-to(どのように)」「How-much(いくらで)」という8つの視点から、事業のコンセプトを具体的に可視化していく方法です。
Who(誰が)
まずは自分自身の肩書きや保有資格を整理しましょう。
- 看護師国家資格あり
- 養護教諭の免許状あり
- 鍼灸師国家資格取得予定
- 特別支援学校・放課後等デイでの実務経験あり
このように多職種の視点を持つことが、サービスの差別化や信頼性につながります。
Whom(誰に)
ターゲットは誰なのかを明確にします。
- 0歳から成人までの重症心身障がい児(者)とその家族
- 自費でも専門的な見守りやケアを求める家庭
具体的に想像できるほど、発信や広告の方向性がぶれません。
Where(どこで)
- 東京都小平市を拠点とした訪問サービス
- 自宅事業所(兼事務所)を拠点に半径5〜10km圏内
訪問形式により、移動が困難な方にも対応可能なスタイルを目指します。
What(何を)
どんなサービスを提供するのかを整理します。
- 見守り+鍼灸+療育的ケア(運動・散歩・絵本など)
- 保護者の時間確保を目的としたレスパイトケア的役割
- 鍼灸による拘縮予防・神経刺激・自律神経調整
単なる「鍼灸」ではなく、「看護的な視点」を掛け合わせることで強みになります。
Why(なぜ)
- 雇用に縛られず、自由なスタイルで支援したい
- 制度に縛られないことで本当に必要な支援を実現したい
- 鍼灸師として治療的アプローチを、看護師として生活支援を両立したい
この「Why=原動力」は、事業の継続や発信時の核になります。
When(いつ)
- 開業予定日:2025年4月1日
- 営業時間:平日16:00〜20:00、木曜定休、その他応相談
スモールスタートで始めることで無理なく軌道に乗せやすくなります。
How-to(どのように)
サービス提供方法、集客手段、競合との差別化などを具体化します。
- 自費訪問型+シェアサロン活用型
- レンタルスタジオや貸スペースでの柔軟対応
- 児童発達支援・放デイなど既存支援者への営業
- 保護者コミュニティや口コミを通じて広げる
地域密着+専門性という独自のブランディングが集客の軸になります。
How-much(いくらで)
価格設定は信頼感や継続性に直結します。明確かつ安心できる価格帯を検討しましょう。
- 訪問看護に準じた1時間あたり5,000円前後
- 保険診療ではなく自費で明朗会計を提示
地域相場・対象者の経済背景を踏まえた継続可能な価格設定が重要です。
この「6W2H」によって、自分のやりたいことが現実的かどうか、どこに工夫の余地があるかが見えてきます。開業コンセプトを構築するうえで、ぜひ時間をかけて書き出してみてください。
🌟英雄神話によるコンセプトの考え方
開業ストーリーを言語化する際、ハリウッド映画やビジネス講演でも活用される「英雄神話(ヒーローズ・ジャーニー)」という型があります。
これは、平凡な主人公がある日事件に巻き込まれ、苦難や試練を経て成長し、最後には使命感と共に社会に貢献するという物語構造です。
この考え方を応用して、自分自身の開業動機やストーリーを言語化しておくと、ブログ・HP・営業資料・プロフィール作成にとても役立ちます。
「あなたから受けたい」と思われる“共感ストーリー”の構築にもなります。
平凡な日常
Kagayaはもともと服飾大学を卒業したのですが、当時は就職難で業界での道が開けず、進路変更を余儀なくされました。
将来への不安から、安定職である看護師を目指して看護学校に進学。
ですが、学生時代から「本当に自分がやりたいことはこれなのか?」という疑問が拭えないまま、なんとなく医療の道に進みました。
困難と違和感
病院勤務を始めると、さらにその違和感は大きくなりました。
夜勤が辛い、職場の人間関係がストレス、同じ場所で8時間動けない、自分のやりたい看護とは違う——。
どこかで“自分の人生なのに、誰かに操られているような感覚”がありました。
結果として2〜3年ごとに職場を転々とする「ジプシーナース」状態になっていきました。
きっかけと出会い
そんな中で、「このままでは心も身体も壊れる」と感じたとき、知人の勧めで初めて鍼灸治療を受けました。
長年悩んでいた胃の張りが、一度の施術でスッと軽くなったのです。
西洋医学では“異常なし”とされてきた不調が、東洋医学では改善された。
その体験が衝撃的でした。
この出来事をきっかけに、「自分もこの技術で人を癒したい」と思うようになり、開業権のある鍼灸師になることを決意しました。
成長の道のり
その後、常勤看護師を辞め、時給2,000円の非常勤ナースとして働きながら鍼灸学校に入学。
クラスメイトには理学療法士、柔整師、美容師、社会人経験者が多く、多様な価値観や志に刺激を受けながら学びを深めています。
自分自身の体験や違和感が、今では“使命”となりつつあります。
クライマックス=開業決意
そして今、「重症心身障がい児(者)」を対象とした専門のケアを行うべく、訪問型の自費サービスを立ち上げようと準備を進めています。
保護者が安心して働けるように、そして休息をとれるように——。
医療・福祉の隙間を埋める新しいケアスタイルとして、看護+鍼灸+療育というハイブリッドな支援を提供したいと思っています。
継続の信念
Kagayaは、この活動を“長く続けること”を大切にしています。
制度の狭間に置かれた家族のために、丁寧なケアと信頼関係を積み重ね、必要とされる存在になっていきたい。
子どもたちや家族が「また来てほしい」と言ってくれることが、何よりの喜びです。
社会的ミッション
ゆくゆくは、同じ志をもつ仲間とチームを組み、地域全体のケア力を底上げしたいと考えています。
重症児・者の支援体制を拡充し、社会から孤立しない「地域まるごとケア」の実現へ。
小さな一歩かもしれませんが、私のこの開業がその第一歩となれば幸いです。
「きらぼし」という屋号には、小さくても光を放つ存在になりたいという想いを込めています。
🌟ターゲットとする顧客が想定できるか
開業するうえで「どんなお客様に来てほしいのか?」を明確にすることは非常に重要です。
これはコンセプトと同じくらい大事な部分で、ターゲットが定まらないとサービス設計や宣伝方法、料金体系まで全部がぼやけてしまいます。
Kagayaの場合、「重症心身障がい児(者)とその保護者」を明確にターゲットとしています。
年齢でいえば0歳から40代以上まで幅があり、障がいの程度も個別性が高いですが、共通しているのは日常的に強い医療的ケアや見守りが必要な人ということです。
では、なぜこの層をターゲットにしようと思ったのか?
それはKagayaが看護師として、訪問看護・放課後等デイ・特別支援学校などで働くなかで、重症心身障がい児(者)とその家族が抱える社会的な困難を目の当たりにしてきたからです。
例えば、子どもに24時間付きっきりでいなければならず、外出もままならないお母さん。
医療的ケアや介助を行える支援が限られていて、レスパイト先が見つからないケース。
成長とともに体重が増え、家族だけでは介助が困難になる場面も増えていきます。
そうした方々に対して、医療資格を持った自費訪問のスタイルで、「療育+鍼灸+看護」という複合的なケアを届けることができたら…というのがKagayaの出発点です。
また、開業時に重要なのが「ターゲットの人物像(ペルソナ)」をイメージすることです。
Kagayaのペルソナの一例を挙げると、以下のような方です:
- 小平市・東村山エリア在住の30代~40代の母親
- 高校卒業後の医療的ケア児の保護者
- 日中ひとりで介護しており、少しでも休める時間が欲しい
- 訪問看護は頼んでいるが、療育的なケアが足りないと感じている
- リラクゼーションや美容より「生活を維持できる支援」を求めている
このように、ターゲット像が具体的になるほど、サービス内容や営業方法、ブログ記事の内容までブレずに設計できます。
また、集客方法もターゲット次第で変わります。
Kagayaのように“障がい児(者)の保護者”を想定している場合、SNS広告よりも、相談支援専門員・放課後デイ・特別支援学校への連携の方が信頼と実績につながりやすくなります。
さらに、保護者向けの勉強会やマルシェでの無料体験、病院・施設での情報交換会なども接点づくりとして有効です。
開業当初は「ターゲットを広くしておこう」と思いがちですが、絞った方がむしろ伝わるし、選ばれるようになります。
必要があればあとから広げればいいのです。
あなたが提供したいのは“誰の、どんな悩みに応えるサービス”ですか? それを一言で言えるようになったとき、あなたの事業は大きく前進します。
🌟開業スタイルや立地があらかじめ決まっている場合は、現実的に可能かどうか
Kagayaの場合、「まずは自宅を拠点として訪問サービスからスタートし、徐々に資金が貯まったらテナントを借りて拡大していく」という流れを想定しています。
このような“段階的に広げていく”開業スタイルは、リスクを抑えつつ継続しやすい方法として多くの個人事業主にも支持されています。
しかし実際に物件を探してみると、思っていたよりもハードルが高い現実に直面しました。
特に、Kagayaが対象とする「重症心身障がい児(者)」は車イスユーザーであることが多いため、物件には次のような条件が必須になります。
- 1階、またはバリアフリー対応のエレベーター付き物件であること
- スロープや自動ドアなど、車イスでの出入りが可能な設計であること
- 近隣に駐車場があること(訪問車両・利用者家族の送迎にも対応できる)
- 小平特別支援学校、村山特別支援学校の送迎圏内であること
こういった条件を満たす物件は非常に少なく、見つけたとしても賃料が高く、初期費用が重くのしかかってきます。
実際に、不動産ポータルや街中で空き物件を探してみると、良さそうな立地の物件はすでに「チョコザップ」などのフランチャイズ店舗に入れ替わっていることもしばしば。住宅街でもジムが成り立つ時代だとは思いつつ、「本当にこの地域で?」と疑問を感じる場所もあります。
そんな中で新たに知ったのが「シェアサロン」という選択肢です。
これは施術ベッド1台分のスペースを時間単位・日単位で借りて使えるスタイルで、初期費用をぐっと抑えられます。
訪問専門としてスタートし、必要なときだけシェアサロンで対面対応するという流れなら、
- 固定費を最小限に抑えながらも
- 「自宅に来られるのは抵抗がある」という層にも対応できる
- 地域でのプレゼンス(存在感)も出しやすい
という3つのメリットがあります。
さらに、「シェアサロン × 訪問サービス」の組み合わせは、看護師・鍼灸師としてのWライセンスを最大限に活かす構成でもあります。
現在の結論としては、自宅を事業拠点として訪問をベースに活動しつつ、必要に応じてシェアサロンを活用する柔軟なスタイルで始めていく方針です。
将来的に地域にニーズがあると実感したタイミングで、改めてバリアフリー対応のテナント開設を検討します。
その時に備え、不動産情報のチェックは日々続けていこうと思っています。
現実的な条件を把握しながら、夢と現実のバランスをとることが、開業スタイルの構築にはとても重要です。
🌟予算があらかじめ決まっている場合は現実的に可能かどうか
Kagayaは開業にあたり、「人生のストレスを減らし、将来的に安定した収入を得ること」を大きな目標としています。
ですが、それを達成するには、最初のステップである「開業資金」の現実ときちんと向き合う必要があります。
個人事業主になるということは、会社員としての保証や安定を自ら手放すことでもあります。
たとえるなら、「飼い猫」が「野良猫」になるようなもの。
守られた環境から飛び出すには大きな覚悟が必要で、自由の裏側には不安や責任も伴います。
とはいえ、完全な野良猫として生きていくのは現実的に厳しい。
理想は、会社員としての安定を維持しつつ、自分らしい働き方を実現する「半分飼い猫・半分野良猫」な状態。
つまり、副業的なスタートで個人事業を徐々に育てていくことが、自分にとっての最適解だと考えています。
そのため、開業スタイルとしては「店舗を持たない訪問型サービス」を基本にしています。
テナント契約や内装費にかかる初期費用が不要になり、運転資金のリスクを大幅に減らせるからです。
加えて、鍼灸師としての開業に必要な機材や物品は、最小限で始めることが可能です。
- お灸・鍼などの施術道具(初期費用:2〜5万円程度)
- 折りたたみ式施術ベッド(約1〜2万円)
- 名刺やチラシなどの広報ツール(1万円以内)
- 保険適応施術をする場合は、受領委任契約や書類関係の整備
これらを踏まえ、学生時代から毎月3万円ずつ積み立てをして、卒業と同時に開業に踏み切る予定です。
年間36万円の貯金を2年間続ければ、約70万円。これだけでも初期費用としては十分にスタート可能な金額です。
もちろん想定外の出費は必ずあります。
そのため、固定費の少ない訪問型+必要に応じたシェアサロン利用というスタイルで、無理なく段階的にスケールアップしていく戦略をとります。
また、完全に独立してしまうと収入がゼロになるリスクもあるため、週数回のアルバイトやパート看護師の仕事を継続しつつ、副業として事業を始めていく「ハイブリッド型」の働き方を選んでいます。
このように、
- 開業スタイルの工夫(訪問+シェアサロン)
- 予算管理とコツコツ貯金
- 副業・兼業によるリスク分散
という3本柱で、できる限り低リスク・低予算で、無理のないスタートを目指しています。
大切なのは「勢いだけで始める」のではなく、「自分にとって現実的な予算内で可能か」を冷静に見極めること。
個人事業はマラソンのようなもの。
走り続けられる体力(資金力)を確保しつつ、最初の一歩を踏み出す準備を、今まさに整えています。
🌟複数のコンセプトを掛け合わせるのはOKだが、盛り過ぎてブレていないか
開業を考える上で、「やりたいこと」はいくつもあります。
Kagayaが目指しているのは、重症心身症がい児(者)のための看護×療育×鍼灸を組み合わせたサービスです。
これは、今まであまりなかった新しいアプローチであり、非常に意義のある仕事だと感じています。
その一方で、興味のある分野は他にもあります。
- 脊髄損傷のある方への鍼灸+リハビリ
- 看護×鍼灸によるメンタルアプローチ
- 障がい児の母親のための美容鍼
どれも魅力的で、すべてを取り入れたいと思ってしまいますが、1人でできることには限りがあります。
特に開業初期は「ターゲット」や「サービス」を欲張り過ぎないことがとても重要です。
たとえば、美容鍼。客単価が1万円を超えることもあるため、収益性は高いと言われています。
しかしそれには、高級感ある空間づくりや「お姫様気分」を味わってもらうような接客が求められます。
それを自分の性格やスタイルで無理なく実現できるか?と考えると、現時点では「ちょっと違うかな」と思っています。
また、メンタル面で悩みを抱える方への鍼灸も興味があります。
看護師資格があることで、信頼性は得られるかもしれませんが、それによって深刻な精神疾患を抱えた方の相談が増えるリスクもあります。
Kagayaは、繊細で感受性の強い方にとっては少しガサツに見えるかもしれない性格です。
実際、そういう部分が原因で距離を置かれてしまう可能性もあるでしょう。
「できること」と「やりたいこと」は違います。最初から何でもかんでも取り入れると、軸がぶれてしまい、結局どれも中途半端になってしまいます。
ですが、自分の飽きっぽい性格も理解しています。
「自分には合わない」と思ったらスパッとやめてしまうこともあります。
だからこそ、いくつかの方向性にトライしながら、「自分が楽しく続けられるか」「ニーズに応えられるか」を見極めていくスタンスが、自分には合っているのかもしれません。
いまのところ、メインで提供するサービスは次の3つに絞っています。
- 重症心身症がい児(者)への鍼灸+看護
- 保護者のための癒し(必要に応じて美容鍼)
- 訪問型のサポート+必要に応じたシェアサロン活用
これらを中心に、「無理のない範囲で挑戦しながら、事業として育てていく」スタイルを目指します。
最初は小さく始め、将来的に必要があれば徐々に拡張していく。
そんな成長型の事業コンセプトが、いまの自分にはちょうどいいのかもしれません。
そして何より大切なのは、「自分にとってストレスが少なく、長く続けられる」こと。
事業の柱を増やすのは悪いことではありませんが、その全てがブレずに結びついているかを常に意識するようにします。
🌟まとめ
今回、改めて自分のコンセプトを言語化し、整理してみました。
「看護×療育×鍼灸」という軸を中心に、どのように重症心身症がい児(者)とそのご家族を支援していくか。
やりたいことは明確になってきましたが、まだまだ模索中の部分も多く、正直なところブレていると感じる場面もあります。
たとえば、メンタルケアや美容鍼、脊髄損傷へのアプローチなど、興味のある分野はたくさんあります。
その中で「自分が本当にやりたいこと」「無理なく続けられること」「地域のニーズに応えられること」を選び、コンセプトに落とし込んでいく必要があると感じました。
また、技術面でも知識面でも、まだまだ勉強が必要です。
鍼灸や看護の専門知識はもちろん、療育の理論、発達支援の知見、そして個人事業主としての経営スキルも学んでいかなければなりません。
そのため、開業に向けて今から少しずつ準備を進めています。
鍼灸学校を卒業する頃には、「自分のやるべきこと」「できること」「求められていること」の重なる場所をしっかり見極めて、一本筋の通ったコンセプトを持っていたいと思います。
そして、将来的にはただの施術者としてではなく、看護師としての視点・療育者としての視点・鍼灸師としての技術を統合した、「自分にしかできないサポート」を提供していきたいのです。
訪問×シェアサロンというスタイルも、自分にとっては無理がなく、自由度の高い働き方だと実感しています。
必要に応じて現場を変えられる柔軟性は、重症心身症がい児(者)とそのご家族にとっても安心材料になるのではないかと思います。
今後も情報収集や実地経験を積みながら、自分のコンセプトをブラッシュアップしていきます。
修正・方向転換を恐れず、むしろ「試行錯誤できる今この時間」を大切にしながら進んでいきたいです。
開業とはゴールではなくスタート。
だからこそ、準備段階での思考の深さが、その後の事業の軸になります。
卒業後すぐに開業届を出せるように、今できることから着実に取り組んでいきます。
🌟開業準備におすすめのアフィリエイト商品
「鍼灸×看護×療育」の開業を目指すKagayaが実際に役立つと感じた、開業コンセプト構築や事業準備にぴったりの書籍をご紹介します。
📘 はじめての鍼灸マッサージ治療院 開業ベーシックマニュアル
鍼灸師としての開業を基礎から学べる一冊。保険制度・届出・経営の基礎など、初心者にもわかりやすく解説されています。
✔ こんな人におすすめ:
- 卒業後すぐに開業を考えている方
- 保険請求や法的な手続きが不安な方
- 経営の基本をしっかり押さえたい方
📘 ひとりビジネスの教科書
ひとりで仕事を始めたい人のための心構えや仕組みづくり、集客の基本をまとめた入門書。副業スタートにもぴったり。
✔ こんな人におすすめ:
- 副業や複業スタイルでスタートしたい
- 小さく始めて徐々に広げていきたい
- ブレない軸を持ちたい方