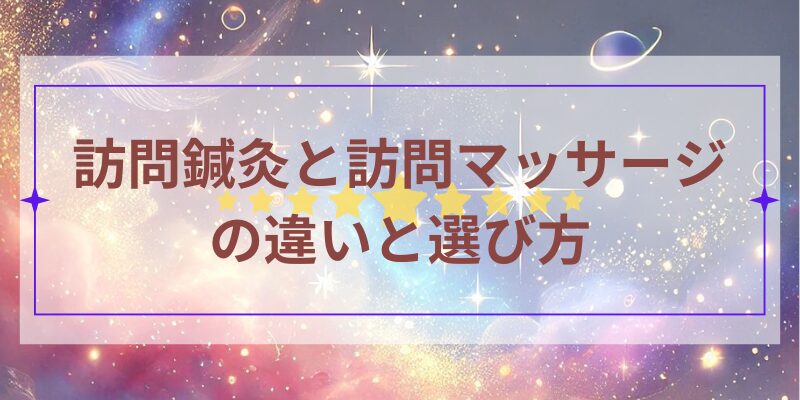こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
「訪問鍼灸と訪問マッサージ、どう違うの?」「どちらを選べばいいかわからない」という質問は、地域で活動していると本当によくいただきます。
どちらもご自宅や施設に施術者が訪問してサービスを受けられる便利な仕組みですが、その目的や対象となる症状、利用できる保険制度には明確な違いがあります。
正しく理解して選ぶことで、身体の状態や生活スタイルに合ったケアが受けやすくなり、日々の生活がぐっと楽になります。
たとえば、脳梗塞の後遺症で手足のしびれやこわばりがある方は、鍼灸で神経や筋肉に直接アプローチするのが有効なこともあります。
一方、長く寝たきり生活が続いて関節が固まってしまった方には、訪問マッサージで筋肉や関節を少しずつほぐし、可動域を広げる方が適していることもあります。
つまり「どちらが優れている」ではなく、「今の症状や目的にどちらが合うか」が大切なのです。
また、費用の面でも違いがあります。
訪問鍼灸は「神経痛・リウマチ・五十肩・腰痛症」など限られた疾患で医師の同意書が必要ですが、訪問マッサージは「歩行困難」「関節拘縮」などでマッサージが医学的に必要と認められれば保険が適用されます。
どちらも1〜3割負担で利用できるため、実際の費用は1回あたり数百円〜1,500円程度に収まるケースが多いです。
自費で受けると数千円〜1万円以上かかることを考えると、保険を使えるかどうかは大きなポイントになります。
この記事では、地域で実際に訪問施術を行っている私自身の経験を踏まえながら、訪問鍼灸と訪問マッサージの違い、保険の仕組み、向き不向き、そして選び方のコツをまとめました。
さらに『きらぼし』での実際の活用例も紹介しますので、迷っている方の参考になればうれしいです。
この記事でわかること
- 訪問鍼灸と訪問マッサージの基本的な違い
- 保険適用条件と費用の目安
- それぞれに向いている症状やケース
- 併用するメリット
- 『きらぼし』の訪問鍼灸活用例
🌟訪問鍼灸とは
訪問鍼灸とは、国家資格であるはり師・きゅう師がご自宅や施設に訪問し、鍼(はり)や灸(きゅう)を用いて施術を行うサービスです。
病院や治療院に通うことが難しい方でも、自宅にいながら専門的なケアを受けられるのが大きな特徴です。
特に、慢性的な痛みやしびれ、自律神経の不調など、薬だけでは改善が難しい症状に対して力を発揮します。
鍼灸では、東洋医学の「気・血・水」のバランスを整える考え方と、西洋医学的な神経・筋肉・血流の働きを踏まえたアプローチの両面から施術を行います。
たとえば鍼を用いると、筋肉の緊張をやわらげると同時に、神経に作用して痛みを軽減する効果が期待されます。
さらに、脳内でエンドルフィンやセロトニンといった物質が分泌され、自然な鎮痛やリラックス効果が得られることも研究で明らかになっています。
灸は温熱によって血流を促し、免疫力や代謝の改善を助けます。
訪問鍼灸が対象となるケースには、さまざまなものがあります。
代表的なものとしては、脳血管障害後遺症による片麻痺やしびれ、パーキンソン病による筋緊張や震え、呼吸や嚥下機能の低下、不眠や自律神経失調、冷えや便秘などの慢性症状です。
これらは日常生活に大きな影響を及ぼしますが、鍼灸によって症状がやわらぎ、生活の質が改善される方も少なくありません。
また訪問鍼灸の強みは、施術の強さや方法をきめ細かく調整できることです。
痛みに敏感な方や感覚過敏のある方には、ごく細い鍼や刺さない鍼(てい鍼)を用いることも可能ですし、温熱が心地よい方には灸を中心に施術するなど、一人ひとりの体質や好みに合わせたオーダーメイドの対応が可能です。
そのため、子どもから高齢者まで幅広い年代の方に安全に利用していただけます。
実際の訪問の現場では、施術だけでなく生活支援につながる工夫も行います。
たとえば夜眠れない方には、鍼灸と合わせて睡眠環境のアドバイスをすることで、夜間の覚醒が減ったケースもあります。
また、片麻痺の方に対しては、鍼灸で筋緊張をゆるめてからリハビリを行うことで、動作がしやすくなり訓練効果が高まるといった相乗効果もあります。
このように訪問鍼灸は、「痛みの軽減」や「体調の改善」だけでなく、「生活のしやすさ」を支える包括的なケアとして役立つものです。
単なる治療ではなく、日常生活を安心して過ごすためのサポートとして位置づけられるのが、訪問鍼灸の魅力といえるでしょう。
- 国家資格:はり師・きゅう師
- 施術内容:鍼・灸で痛みやしびれ、自律神経、内臓機能などの調整
- 対象例:神経痛、脳血管障害後遺症、パーキンソン病、筋緊張、呼吸・嚥下機能の補助、不眠など
- 特徴:刺激量や方法を細かく調整でき、幅広い症状に対応可能
🌟訪問マッサージとは
訪問マッサージとは、国家資格であるあん摩マッサージ指圧師がご自宅や施設に訪問して施術を行うサービスです。
マッサージと聞くと「リラクゼーション」のイメージが強いかもしれませんが、医療保険を用いた訪問マッサージは、医学的に必要とされる機能改善や維持を目的としています。
筋肉をもみほぐしたり、関節を動かしたりする手技を通して、血流の促進や関節可動域の改善を図ることが大きな特徴です。
対象となるのは、主に筋萎縮や関節の拘縮、寝たきりによる関節のこわばり、むくみ(浮腫)などです。
たとえば、脳血管障害後のリハビリが不十分で腕や足が固まってしまったケースや、慢性的な車椅子生活で足のむくみが強いケースなどでは、訪問マッサージによって筋肉をやわらげ、血流を改善し、日常生活動作(ADL)の維持につなげることができます。
訪問マッサージの魅力は、直接手で触れることによる安心感やリラクゼーション効果です。
触覚刺激は心地よさをもたらし、自律神経を整えてリラックスを促す働きがあります。
特に高齢の方や、認知症を抱える方にとって、誰かにやさしく触れてもらうこと自体が心理的な安定や生活の質の向上につながります。
また、関節の可動域を広げる効果も大きな特徴です。
硬くなった関節を少しずつ動かしていくことで、着替えや立ち上がり、歩行などの動作がしやすくなります。
さらに血流改善は床ずれ(褥瘡)の予防や冷え性の緩和にも役立ちます。
単なる慰安ではなく、生活を支えるための医学的な機能訓練として活用されているのが訪問マッサージです。
ただし、訪問マッサージには得意分野と限界があります。
たとえば強い神経痛や不眠、自律神経の乱れといった症状は、鍼灸の方が適している場合もあります。
逆に「関節が固まってきた」「歩行に不安がある」といった悩みにはマッサージが効果的です。
つまり、訪問マッサージは「身体を動かしやすくするサポート」に重点が置かれており、痛みや自律神経症状への直接的な効果はやや限定的といえるでしょう。
実際の現場では、訪問マッサージを続けることで「以前より立ち上がりが楽になった」「浮腫が軽減して靴が履きやすくなった」といった変化を感じる方が多くいます。
特に長期間の寝たきり生活を余儀なくされている方にとって、マッサージは筋肉や関節を刺激し、二次的な合併症を防ぐ大切な役割を果たします。
このように訪問マッサージは、身体を動かしやすくする・血流を促進する・安心感を与えるという3つの柱を通して、利用者の生活を支える存在です。
単なるリラクゼーションにとどまらず、在宅医療や介護の現場で重要なケアとして活用されているのです。
- 国家資格:あん摩マッサージ指圧師
- 施術内容:手技で筋肉・関節をほぐし、血流促進や関節可動域改善
- 対象例:筋萎縮、拘縮、関節のこわばり、浮腫など
- 特徴:触覚刺激でリラックス効果が得やすい/関節の動きやすさをサポート
🌟保険適用条件と費用の違い
訪問鍼灸と訪問マッサージは、どちらも健康保険を利用できる在宅サービスですが、保険が適用されるためには条件があります。
共通するのは、医師の診察を受けて「この方には鍼灸(またはマッサージ)が医学的に必要である」と判断されること。
これを証明するのが医師の同意書です。
つまり、勝手に保険で施術ができるわけではなく、医師の管理下にあることが大前提となります。
訪問鍼灸の場合、対象となるのは「神経痛・リウマチ・頸肩腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症」など、厚生労働省で定められた疾患に限られています。
これらは慢性化しやすく、薬物治療だけでは十分に改善しにくいことが多いため、鍼灸による補完的な治療が認められているのです。
訪問マッサージの場合は、疾患名よりも身体機能の状態が重視されます。
「歩行が困難である」「関節の拘縮が強くて自力で動かせない」「筋肉が萎縮している」といった状況で、マッサージによる血流改善や関節運動が医学的に必要と医師が判断すれば、同意書が発行されます。
つまり、機能訓練や生活動作の維持・改善を目的とした利用が中心になります。
気になる自己負担額は、どちらも健康保険の1〜3割が適用されるため、1回あたり数百円〜1,500円程度で利用できることがほとんどです。
経済的な負担が軽いため、定期的に継続しやすい点は大きなメリットです。
実際に週2〜3回の利用をされる方も多く、通院の手間や交通費を考えると、費用面での安心感は大きいといえます。
一方で、自費で利用する場合は相場が大きく異なります。
訪問鍼灸は40〜60分で6,000〜12,000円程度、訪問マッサージは5,000〜10,000円程度が目安となり、さらに訪問距離によって加算される場合があります。
保険が使えないケースや、対象外の症状で施術を希望する場合は、この自費料金での利用となります。
たとえば「美容鍼」「リラクゼーション目的のマッサージ」などは自費扱いです。
ここで大切なのは、「自分の症状は保険適用になるのか?」を確認することです。
訪問鍼灸の場合は、対象疾患が限られているため、同意書を出してもらえないこともあります。
一方で訪問マッサージは「動かせない」「歩けない」など身体機能の低下が明らかなケースでは同意が得られやすいです。
迷ったときは、かかりつけの医師や、実際に施術を行う鍼灸師・マッサージ師に相談してみるのが安心です。
このように、訪問鍼灸と訪問マッサージは保険適用の条件・対象疾患・費用感に違いがあり、それぞれの特徴を理解することで自分に合った選び方がしやすくなります。
費用の負担だけでなく、症状の改善をどのように目指したいかを考えて選ぶことが大切です。
| 項目 | 訪問鍼灸 | 訪問マッサージ |
|---|---|---|
| 保険適用条件 | 医師の同意書+対象疾患(神経痛・リウマチ・頸肩腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症) | 医師の同意書+歩行困難や関節拘縮などで医療上マッサージが必要 |
| 自己負担額 | 1〜3割(数百円〜1,500円程度/回) | 1〜3割(数百円〜1,500円程度/回) |
| 自費相場 | 40〜60分:6,000〜12,000円+距離加算 | 40〜60分:5,000〜10,000円+距離加算 |
🌟どんなときにどちらが向いている?
訪問鍼灸と訪問マッサージは「在宅で受けられる施術」という点では共通していますが、得意とする分野や適している症状は異なります。
選び方に迷ったときには、自分や家族が今どんな症状で困っているのか、生活の中で何を改善したいのかを整理してみるとよいでしょう。
以下に、それぞれの施術が向いているケースを具体的にまとめました。
訪問鍼灸が向いているケース
- 痛みやしびれが強く、薬だけでは十分に抑えられない場合
- 不眠・便秘・冷え・動悸など、自律神経の乱れを伴う症状がある場合
- 「肩こりも腰痛もある」「痛みと睡眠障害が同時にある」など複数の症状をまとめてケアしたい場合
- パーキンソン病や脳梗塞後遺症など、神経系の不調を抱えている場合
- 感覚過敏や心身の緊張が強く、刺激量を細かく調整してもらいたい場合
鍼灸は、神経や自律神経に直接作用しやすいため、しびれや痛み、不眠など多彩な症状に対応できるのが特徴です。
「全身をトータルで整えたい」「体質改善を目指したい」と考える方に向いています。
訪問マッサージが向いているケース
- 筋肉の緊張や関節の拘縮が主な悩みである場合
- リハビリや関節の可動域訓練を中心に受けたい場合
- 「動かしやすさ」を重視して生活動作を改善したい場合
- むくみ(浮腫)が強く、循環を促したい場合
- リラクゼーション効果を重視し、心身の安らぎを得たい場合
訪問マッサージは、筋肉や関節に働きかけて「動きやすさ」をサポートすることが得意です。
触覚刺激によるリラックス効果も得やすく、日常生活の快適さや介護負担の軽減につながりやすいケアです。
つまり、「痛みや自律神経の不調を和らげたい」なら訪問鍼灸、「筋肉や関節を動かしやすくしたい」なら訪問マッサージと考えるとイメージしやすいでしょう。
もちろん、両方を組み合わせて利用することも可能で、それぞれの強みを活かすことでより高い効果を期待できます。
迷ったときには、症状を優先順位づけしてみてください。
たとえば「夜眠れないほど痛みがある」場合はまず鍼灸で痛みや自律神経の調整を行い、その後マッサージで関節の可動域を広げるといった流れも考えられます。
反対に「まずは固まった関節を動かしたい」という方はマッサージから始め、必要に応じて鍼灸を取り入れるのも良い方法です。
🌟併用するメリット
訪問鍼灸と訪問マッサージは、どちらか一方だけでも十分に効果を感じられることがありますが、両方を併用することで相乗効果が期待できます。
鍼灸は神経や自律神経にアプローチして痛みやしびれ、不眠などをやわらげるのが得意であり、マッサージは筋肉や関節に働きかけて「動かしやすさ」を改善するのが得意です。
つまり、この2つを組み合わせることで、体をより包括的にケアできるのです。
たとえば、脳梗塞の後遺症で片麻痺があり、痛みと関節拘縮の両方に悩む方の場合、鍼灸で痛みを軽減したあとにマッサージで関節の可動域を広げると、リハビリでの成果が高まりやすくなります。
逆に、マッサージで全身をリラックスさせてから鍼灸を行うと、鍼の刺激を受け入れやすくなり、効果が増すケースもあります。
また、施術方法が一つに偏らないため、患者さんが「飽きにくい」「続けやすい」というメリットもあります。
在宅ケアでは継続することがとても大切ですが、同じ施術だけでは「効いているのか分からない」「単調に感じる」とモチベーションが下がってしまうことも少なくありません。
鍼灸とマッサージを組み合わせることで刺激にバリエーションが生まれ、楽しみながら続けられるのです。
さらに大きな利点は、症状に合わせて施術の割合を柔軟に調整できる点です。
たとえば、痛みが強いときは鍼灸を中心に、動かしやすさを優先したいときはマッサージを多めに、といったように、その日の体調や症状の変化に応じたオーダーメイドのケアが可能になります。
この柔軟さこそが、併用の最大の強みです。
実際の現場では「鍼灸で夜眠れるようになった」「マッサージで日常動作が楽になった」といった声を同時にいただくことが多くあります。
どちらか一方ではカバーしきれない症状を補い合うことで、生活全体の質(QOL)が高まるのです。
- 鍼灸で痛みや神経症状を軽減 → マッサージで可動域拡大・筋緊張緩和
- 施術刺激のバリエーションが増え、飽きにくい
- 症状や体調に合わせて施術割合を柔軟に調整可能
- 総合的にQOL(生活の質)を高めやすい
🌟『きらぼし』の訪問鍼灸活用例
ここでは、実際に『きらぼし』で訪問鍼灸を行った事例をご紹介します。
訪問鍼灸の魅力は、その方の生活環境や症状に合わせて柔軟に施術を組み立てられることにあります。
単に痛みを和らげるだけではなく、ご本人やご家族の「こうなりたい」という希望を叶えるために、リハビリや訪問マッサージ、生活環境の工夫とも組み合わせながら支援を行っています。
事例1:脳梗塞後遺症で片麻痺があり、強い痛みと筋緊張に悩むケース。
まず鍼灸で肩や腕のしびれ・痛みを軽減し、緊張した筋肉をゆるめました。
その後、訪問リハビリやマッサージと連携して関節可動域を広げ、動きやすさを確保することで、日常生活の中で「立ち上がりやすい」「衣服の着脱が楽になった」といった変化が見られました。
鍼灸と他職種の支援を組み合わせることで、機能回復と生活改善の両立が可能となった好例です。
事例2:重度障がい児で感覚過敏と睡眠障害を抱えていたケース。
鍼灸施術だけでは緊張が強く、不安定になりやすかったため、施術環境に工夫を取り入れました。
具体的には、スヌーズレン空間(光・音・香り・触覚をやさしく刺激する多感覚環境)を整えた上で鍼灸を実施。
結果としてお子さんがリラックスしやすくなり、夜間の覚醒が減少しました。
ご家族からは「夜眠れるようになり、親の負担も減った」と喜びの声をいただきました。
事例3:在宅療養中の高齢者で、慢性的な腰痛と食欲不振を訴えるケース。
鍼灸で腰部の血流を促し、胃腸機能を整えるツボを刺激したところ、腰痛が軽減するとともに「食事が進むようになった」との変化がありました。
マッサージやリハビリと連動することで、体調だけでなく生活意欲の改善にもつながった例です。
このように、『きらぼし』の訪問鍼灸は単独の施術にとどまらず、訪問マッサージやリハビリ、さらにはスヌーズレンのような感覚統合的アプローチとも組み合わせながら活用されています。
利用者さんやご家族の「こうなりたい」に寄り添い、一緒に生活の質を高めていけるのが訪問鍼灸の強みです。
📩 ご相談・初回のご案内はこちらから
🌟まとめ|違いを知って最適なケアを選ぶ
訪問鍼灸と訪問マッサージは一見似ているサービスですが、得意分野やアプローチの仕方に明確な違いがあります。
鍼灸は「痛み」「しびれ」「不眠や冷えなど自律神経の乱れ」に強く、身体の内外を同時に整えることができます。
一方でマッサージは「筋肉のこわばり」「関節の拘縮」「むくみ」といった機能的な問題に対して有効で、動きやすさやリラクゼーション効果を得やすい施術です。
つまり、「どちらが優れているか」ではなく「いま自分に必要なケアはどちらか」という視点で考えることが大切です。
例えば、「痛みが強く夜眠れない」という方には訪問鍼灸が適しており、「関節が固まって動かしにくい」という方には訪問マッサージが合っています。
そして「どちらの症状もある」「幅広くケアしたい」という場合には、併用することで相乗効果を得ることができます。
また、在宅で受けられるという点も大きなメリットです。
通院の負担が減り、ご家族も安心して見守ることができます。
特に高齢の方や障がいをお持ちのお子さんにとって、生活の場で安心して受けられるケアは、心身の安定につながります。
鍼灸やマッサージは単なる治療ではなく、生活を支える重要なサポートとして役立つのです。
『きらぼし』では、鍼灸とマッサージの両方の特徴を理解した上で、ご本人やご家族の希望に沿った施術プランをご提案しています。
必要に応じてリハビリやスヌーズレン的環境調整も組み合わせ、「その方らしい生活」を取り戻すお手伝いをしています。
訪問鍼灸と訪問マッサージの違いを理解し、自分やご家族にとって最適なケアを選ぶことは、これからの生活の質を大きく左右します。
ぜひ専門家に相談しながら、無理なく続けられる方法を見つけてください。
そして、もし迷われたときには、『きらぼし』にご相談いただければ、一緒に最適な方法を考えていきましょう。
📩 ご相談・初回のご案内はこちらから
あわせて読みたい