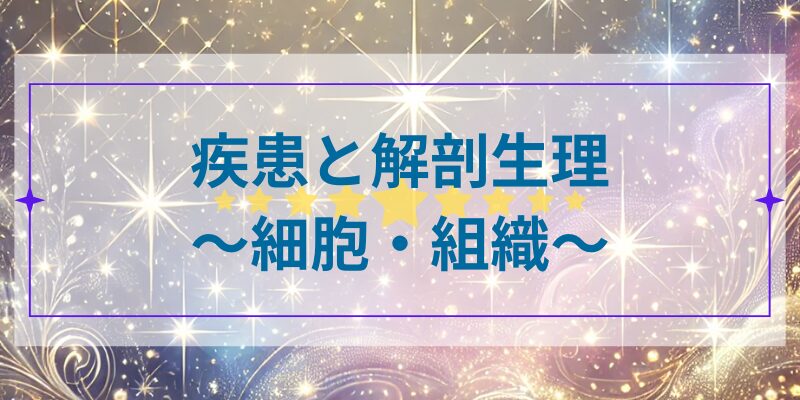🌟バイタルサイン=生命徴候
バイタルサインとは、「生命徴候」とも訳され、人間が生きていることを示す基本的な生理指標のことをいいます。
医療・看護の現場では、状態観察や異常の早期発見、急変の兆候を読み取るうえで非常に重要な情報源となります。
バイタルサインは主に、体温・脈拍・呼吸・血圧・意識レベルの5つを基本項目として含みます。
以下、それぞれについて詳しく説明していきます。
🔶体温(Temperature)
体温の基準値は一般的に36.0〜37.0℃とされていますが、個人差や測定部位によって若干異なります。
日内変動や月経周期、運動、ストレスなどでも変化します。
高すぎても低すぎても体の機能が正常に働かなくなるため、常に適正な体温が保たれることが重要です。
体温測定は、腋窩・口腔・直腸などの部位で行われ、一般的には腋窩温が最も低く、直腸温が最も高いという特徴があります。
🔶脈拍(Pulse)
脈拍数の基準値は成人で65〜85回/分が目安です。
拍動は心拍数にほぼ一致し、循環器系の状態を反映します。
- 頻脈:100回/分以上(例:発熱、貧血、脱水、甲状腺機能亢進症など)
- 徐脈:60回/分以下(例:アスリート、迷走神経反射、薬物の影響、甲状腺機能低下など)
また、脈拍のリズムの乱れ(不整脈)がある場合は、心房細動や期外収縮などの疾患の兆候である可能性があるため注意が必要です。
🔶血圧(Blood Pressure)
正常な血圧はおおむね120/80mmHg未満とされます。
上の数値(収縮期血圧)は心臓が収縮して血液を押し出すときの圧力、下の数値(拡張期血圧)は心臓が拡張しているときの圧力を示します。
- 高血圧:140/90mmHg以上
- 低血圧:100mmHg以下(明確な下限値はなく、症状の有無で判断)
血圧は姿勢、時間帯、精神的な緊張などによって変化するため、家庭血圧と診察室血圧の違い(白衣高血圧・仮面高血圧)にも注意が必要です。
🔶呼吸(Respiration)
正常な呼吸数は成人で16〜20回/分です。
呼吸の異常は、肺や心臓、脳などの異常のサインであることが多く、呼吸数・リズム・深さ・音などを観察することで異常を早期に発見できます。
例えば、頻呼吸は発熱や心不全、徐呼吸は脳圧亢進や薬物中毒などが疑われます。
また、チェーンストークス呼吸やクスマウル呼吸など、特徴的な呼吸様式は重篤な疾患に結びつくことがあるため、熟知しておくことが求められます。
🔶意識レベル(Consciousness)
意識は、脳機能の指標として非常に重要なバイタルサインの一つです。
覚醒状態、見当識、言動の整合性などを観察し、JCS(Japan Coma Scale)やGCS(Glasgow Coma Scale)などの指標を用いて評価します。
急な意識変容は、低血糖・脳卒中・感染症・薬物中毒などが原因として考えられ、迅速な対応が求められます。
観察するだけでなく、前後の変化や本人の既往歴にも着目することが重要です。
🔶バイタルサインの観察の意義
バイタルサインの変化は、病態の進行や改善の指標となるため、看護師・鍼灸師・介護職などの現場職にとっては欠かせない観察項目です。
患者の小さな変化を見逃さず、状態の悪化を防ぐためにも、定期的かつ正確な測定と記録が必要です。
とくに高齢者や慢性疾患をもつ方は、バイタルが日常から逸脱しても自覚症状が乏しいことがあるため、数値と全体像を組み合わせた総合判断力が求められます。
鍼灸24回-52
成人のバイタルサインで異常所見はどれか。
- 体温36.5℃
- 血圧110/70mmHg
- 呼吸数18回/分
- 脈拍110回/分
鍼灸1回-63
WHOの高血圧分類で境界域の拡張期血圧はどれか。
- 80〜89mmHg
- 90〜94mmHg
- 95〜99mmHg
- 100〜104mmHg
按マ指国家試験過去問
按マ指11回-69
バイタルサインはどれか。
- 体重
- 体温
- 尿量
- 顔色
按マ指1回- 73
生命徴候(バイタルサイ ン)に含まれないのはど れか。
- 意識状態
- 自発呼吸
- 排便
- 血圧
按マ指4回-65
生命徴候(バイタルサイ ン)の検査項目として 誤っているのはどれか。
- 体温
- 脈拍数
- 呼吸数
- 瞳孔対光反射
按マ指7回-74
生命徴候に含まれないのはどれか。
- 呼吸
- 脈拍
- 体温
- 意識
按マ指13回-72
バイタルサインに含まれないにはどれか。
- 尿量
- 呼吸
- 体温
- 脈拍
按マ指16回-61
生命徴候に含まれないのはどれか。
- 体温
- 脈拍
- 呼吸
- 瞳孔径
按マ指26回-50
健康成人のバイタルサインで異常値はどれか。
- 脈拍48回/分
- 体温36.2℃
- 血圧110/60mmHg
- 呼吸数16回/分
按マ指30回-45
健康成人のバイタルサインで異常値はどれか。
- 体温36.9℃
- 呼吸数25回/分
- 脈拍数85回/分
- 収縮期血圧100mmHg
🌟死の徴候
死の徴候とは、人の生命活動が完全に停止したことを確認するための医学的な所見です。
看護・医療・介護の現場では、死の判定、死後変化の理解、脳死や植物状態の区別が極めて重要です。
とくに救急対応や終末期ケア、臓器提供の判断にも関わるため、正確な知識が求められます。
🔶死の三徴候と医学的判定
一般に医療現場で「死を確認する」ためには、以下の3つの徴候がすべて認められる必要があります。
- 脈拍停止(心停止)
- 呼吸停止
- 瞳孔反射の消失(散大・固定)
これらは、心肺機能の不可逆的停止を確認するもので、心電図や心音、血圧計、呼吸音、瞳孔反射テストなどを用いて判断されます。
心肺蘇生を行っても回復が見込めないと判断された場合、医師によって死亡が宣告されます。
🔶死後の身体的変化(死後変化)
死後には時間経過とともに、以下のような身体的変化が現れます。
これらは法医学的にも重要で、死亡推定時刻の手がかりにもなります。
- 死冷:体温の低下。死後1時間で約1℃低下するとされる。
- 死斑:重力により血液が沈下して皮膚に紫色の斑点が出る。
- 死後硬直:筋肉が硬直する現象。通常2~3時間後に始まり、12時間程度で全身に及ぶ。
- 血液凝固:循環が停止し、血液が凝固し始める。
- 自己融解(自家融解):細胞が自己分解し、腐敗が始まる。
これらの死後変化を理解することは、終末期看護や死亡確認時の処置、家族への説明にも役立ちます。
🔶脳死の定義と判定基準
脳死とは、大脳・小脳・脳幹を含む脳全体の機能が不可逆的に停止した状態を指します。
心臓がまだ拍動している場合でも、脳が完全に機能を失っていれば、法律上の「死」として扱われることがあります(臓器提供など)。
- 脳死判定の除外条件:低体温、急性薬物中毒、生後12週未満の乳児など
以下の5つの基準をすべて満たすことが脳死判定の条件となります。
- 深昏睡(完全な意識消失)
- 瞳孔固定(散大し、光を当てても縮瞳しない)
- 脳幹反射の消失(対光反射、角膜反射、咽頭反射など)
- 平坦な脳波(脳の電気活動が見られない)
- 自発呼吸の停止(人工呼吸器で維持)
これらを1回目に確認した後、6時間後に再度判定を行い、両方の判定が一致した場合に「脳死」と認定されます。
🔶植物状態との違い
植物状態(遷延性意識障害)は、広範な大脳の損傷によって、意識や運動機能が失われた状態を指します。
ただし、脳幹の機能は保たれており、自発呼吸や心拍は維持されているのが特徴です。
この状態では、瞳孔反射や脳幹反射は残存し、脳波も平坦ではないため、脳死とは明確に区別されます。
臓器提供の対象にはなりません。
臨床現場では、脳死=死であるのに対し、植物状態=生存である点が大きな違いです。
倫理的・法律的な対応も異なるため、状況ごとに慎重な判断と説明が必要です。
以上が、死の徴候に関する基礎知識です。
国家試験では、脳死の判定基準や死後の変化、植物状態との違いについてよく問われるため、用語の意味と違いを正確に押さえておきましょう。
鍼灸16回-59
死の三徴候に含まれないはどれか。
- 体温低下
- 呼吸停止
- 対光反射消失
- 心停止
鍼灸19回-48
植物状態について正しい記述はどれか。
- 脳死状態である。
- 人工呼吸器が必要である。
- 意思䛾疎通ができる。
- 脳幹の機能は保たれて いる。
鍼灸26回-40
植物状態を引き起こす障害部位はどれか。
- 大脳
- 中脳
- 延髄
- 脊髄
鍼灸10回-51
ヒトの植物状態として適切でない記述はどれか。
- 自発呼吸がある。
- 経管栄養が必要である。
- 大脳の高次機能が失われている。
- 脳波が平坦化している。
鍼灸22回-47
臓器の移植に関する法律における脳死判定で誤っているのはどれか。
- 移植医が判定する。
- 急性薬物中毒による深昏睡は除外される。
- 自発呼吸は停止している。
- 判定は2回行う。
按マ指国家試験過去問
按マ指23回-40
心臓死の判定に必要なのはどれか。
- 体温の低下
- 死後硬直
- 瞳孔反射の消失
- 死斑の出現
按マ指6回-58
死の判定に含まれない因子はどれか。
- 心拍動
- 眼球運動
- 呼吸運動
- 中枢神経機能
按マ指28回-40
心臓死の判定項目でないのはどれか。
- 瞳孔反射の消失
- 脈拍の停止
- 呼吸運動の途絶
- 体温の低下
🌟体温測定
体温の測定は、バイタルサインの基本項目のひとつであり、体の状態や病態の把握において非常に重要な指標です。
体温は日内変動や環境の影響を受けやすいため、正確な測定方法や測定部位の違いを理解しておくことが、臨床判断やケアの質を高めるうえで欠かせません。
体温は、視床下部の体温中枢によって一定に調整されています。
人の体温は個人差があり、また測定する部位によっても温度が異なります。
そのため、「どこで測った体温なのか」を明確にすることが重要です。
🔶体温の高さの順序
- 直腸温 > 口腔温 > 腋窩温(高い順)
同じ人の体温でも、測定部位によって差があります。
- 直腸温:最も正確で高めに出る(中心体温)。医療機関や乳児での測定に用いられる。
- 口腔温:中間の値。会話や飲食の影響を受けやすいため、前後30分間は避ける。
- 腋窩温:一般的な家庭で最も用いられるが、周囲温度や姿勢による誤差が大きい。
国家試験では、「体温が高く出る順」や「どの部位が中核体温に近いか」などが問われることが多く、基本として覚えておく必要があります。
🔶測定方法と注意点
体温測定では、正確な値を得るためにいくつかの注意点があります。
- 腋窩温:汗を拭き取り、センサーが皮膚にしっかり接触するようにする。測定中は腕を体側に密着させる。
- 口腔温:飲食や喫煙直後は避ける。舌の裏側にセンサーが当たるようにする。
- 直腸温:体温変動が少なく中核温に近いため、集中治療室や小児科でよく用いられる。感染予防や個人差への配慮が必要。
また、測定する時間帯によっても体温には日内変動があり、早朝が最も低く、夕方が高くなる傾向があります。そのため、発熱や異常の判断には、基準体温との比較や経時的観察が重要です。
🔶発熱と低体温の区別
体温測定においては、ただ測るだけでなく、その値の意味を解釈する力も求められます。
たとえば、37.5℃以上を発熱と判断することが多いですが、個人差や活動量によっても変わるため、普段の平熱を把握しておくことが大切です。
- 微熱:37.0〜37.9℃程度。ウイルス感染や疲労でも見られる。
- 高熱:38.0℃以上。細菌感染やインフルエンザなどが疑われる。
- 低体温:35.0℃以下。高齢者、甲状腺機能低下、出血、栄養障害などが原因。
とくに高齢者では平熱が低い傾向にあり、「37℃未満の発熱」でも体調不良や重篤な疾患の可能性があるため注意が必要です。
🔶現場で役立つ体温の見方
実際の臨床や在宅看護の場では、体温だけで判断せず、脈拍・呼吸・血圧などの他のバイタルサインと併せて総合的に観察します。
たとえば、発熱時に頻脈や呼吸促迫があれば感染症を疑い、熱がないのに意識レベルが低下している場合は低体温や脳血管障害を考えるべきです。
体温測定は誰でも行える一方で、結果の意味をどう読み取るかが国家試験や現場で問われる力です。
正しい知識と観察力を持ち、患者の変化にいち早く気づけるようにしておきましょう。
鍼灸2回-67
腋窩温と直腸温との比較で正しい記述はどれか。
- 腋窩温が約2℃低い。
- 腋窩温が約1℃低い。
- 直腸温が約1℃低い。
- 直腸温が約2℃低い。
按マ死指国家試験過去問
按マ指4回-66
体温測定でも最も高値を示す部位はどれか。
- 直腸
- 口腔
- 腋窩
- 前額
按マ指21回-68
体温について正しいのはどれか。
- 卵胞期より黄体期が高い。
- 口内温より腋窩温が高い。
- 午後より午前中が高い。
- 小児より成人が高い。
按マ指8回-52
体温について正しいのはどれか。
- 夜間は日中より高い。
- 月経前は月経後より低い。
- 腋窩温は直腸温より低い。
- 甲状腺機能低下症で上昇する。
🌟発熱の症状・熱型
発熱(fever)とは、体温が恒常性の調節範囲を超えて上昇する状態を指します。
体温は免疫系と密接に関係しており、感染症、炎症、腫瘍、免疫異常などによって体温中枢がリセットされることで発熱が起こります。
発熱の状態にはさまざまなパターンがあり、熱型と呼ばれる分類が用いられます。
熱型の違いを見極めることで、病態の推定や鑑別診断の手がかりになります。
以下に代表的な熱型とその特徴、関連疾患をまとめます。
| 熱型 | 特徴 | 代表疾患 |
|---|---|---|
| 稽留熱 | 高熱が持続し、日内変動が1℃以内 | 腸チフス、肺炎、髄膜炎 |
| 弛張熱 | 高熱が持続し、日内変動が1℃以上 | 敗血症、腸膿瘍、膠原病 |
| 間欠熱 | 日内で1℃以上の変動があり、低い時は正常体温まで下がる | 膿瘍、マラリアなど |
| 波状熱 | 発熱期と無熱期を不規則に繰り返す | ホジキン病、マラリア |
| 周期熱 | 周期的に発熱と解熱を繰り返す | マラリア、ステロイド熱 |
| 低体温 | 体温が35.0℃以下に低下した状態 | 甲状腺機能低下症、出血、重篤疾患など |
🔶熱型の臨床的な意味
熱型を把握することは、単なる体温の変化を超えて、疾患の背景や進行度、治療反応を読み取るうえで非常に重要です。
たとえば、稽留熱は強い炎症反応を伴う感染症に多く見られ、弛張熱は免疫反応が波のように続く膠原病に特徴的です。
また、間欠熱は細菌性膿瘍やマラリアなど、感染が波状に広がるような病態で認められることが多く、解熱と再発熱を繰り返す患者には注意が必要です。
🔶低体温も重要なサイン
低体温(hypothermia)もまた重要な身体サインのひとつです。
体温が35.0℃以下に低下すると、酵素反応や代謝が低下し、意識障害や循環不全を引き起こす可能性があります。
- 甲状腺機能低下症:代謝が低下し、恒常的な低体温となる。
- 大量出血:ショック状態による末梢循環障害で体温が維持できなくなる。
- 慢性消耗性疾患:癌、栄養不良、高齢者の終末期などでも低体温がみられる。
発熱ばかりに注目が集まりがちですが、低体温は重篤な疾患の初期サインや終末期の兆候であることもあるため、冷たく感じる皮膚や測定値の異常に気づくことが大切です。
🔶熱型と国家試験対策のポイント
国家試験では、各熱型の定義と代表疾患の組み合わせが頻出です。
たとえば、「稽留熱を示す疾患はどれか?」や「周期熱が見られるのは?」という形式で出題されるため、表で覚えるだけでなく、病態とセットでイメージするのがおすすめです。
また、低体温に関する知識も、甲状腺疾患や出血性ショックなどとの関連でよく問われます。
「発熱=病気」と短絡的に考えず、「熱がない、または下がっている状態」も異常として判断できるようにしましょう。
発熱パターンを通して、患者の全体像や経過、必要なケアを想像できるようになることが、現場でも試験でも役立ちます。
鍼灸15回-54
発熱時にみられないのはどれか。
- 悪寒
- チアノーゼ
- 頭痛
- 関節痛
鍼灸16回-56
発熱がみられないのはどれか。
- 結核
- 甲状腺機能低下症
- 皮膚筋炎
- 肺癌
按マ指国家試験過去問
按マ指21回-61
発熱がみられやすいのはどれか。
- アジソン病
- 悪性貧血
- パーキンソン病
- 全身性エリテマトーデス
按マ指7回-63
発熱を疑わせる症状で適切でないのはどれか。
- 発汗
- 頻脈
- 悪寒
- 起坐呼吸
按マ指28回-54
高熱が持続し、日内変動が1℃以内なのはどれか。
- 間欠熱
- 弛張熱
- 稽留熱
- 周期熱
按マ指11回-71
熱型において最低でも37℃以上で日内変動が1℃以上なのはどれか。
- 稽留熱
- 弛張熱
- 間欠熱
- 波状熱
按マ指25回-54
体温が持続的に高く、日内変動が1℃以上の熱型はどれか。
- 稽留熱
- 弛張熱
- 間欠熱
- 周期熱
按マ指17回-68
高熱期と平熱期が交互にみられ、日差が1℃以上あるのはどれか。
- 稽留熱
- 弛張熱
- 間欠熱
- 波状熱
27 按マ指 52
体温の日内変動が1℃以上で最低体温が平熱まで下がるのはどれか。
- 間欠熱
- 稽留熱
- 弛張熱
- 波状熱
按マ指9回-65
熱型と疾患との組合せで正しいのはどれか。
- 弛張熱---マラリア
- 稽留熱---粟粒結核
- 間欠熱---敗血症
- 波状熱---化膿性疾患
🌟頻脈・徐脈
脈拍数は、心臓の拍動を反映しており、頻脈(tachycardia)と徐脈(bradycardia)はバイタルサインのなかでも重要な異常のサインです。
成人の安静時脈拍は通常60~100回/分の範囲内に収まります。
この基準を超えて速くなったり遅くなったりしている場合、さまざまな疾患や生理的変化を疑う必要があります。
🔶頻脈(100回/分以上)
頻脈とは、心拍数が100回/分以上となる状態を指します。
運動時や発熱、ストレスなどの生理的反応として起こることもありますが、病的頻脈では以下のような原因が考えられます。
- 貧血:酸素供給の低下により代償的に心拍が増加
- 心不全:心拍出量を保つために心拍数が上昇
- 甲状腺機能亢進症(バセドウ病):代謝亢進に伴う交感神経の活性化
- 大量出血:循環血液量の低下による代償的頻脈
- 褐色細胞腫:副腎髄質からのカテコールアミン過剰分泌による
これらの疾患では、頻脈+他の症状(例:発汗、動悸、めまいなど)が合併して現れることが多く、心電図や血液検査による精査が必要になります。
🔶徐脈(60回/分以下)
徐脈は、心拍数が60回/分未満となる状態を指します。
高齢者やアスリートでは生理的な徐脈がみられることもありますが、病的な徐脈では以下のような原因が挙げられます。
- 甲状腺機能低下症:代謝全体の低下により心拍数が減少
- 脳圧亢進:頭蓋内圧上昇に伴い、反射的な徐脈(クッシング反射)を呈する
- 黄疸:重度の肝機能障害によって迷走神経の影響が強くなることがある
- アダムス・ストーク症候群:一過性の心停止により意識消失を伴う徐脈発作
- 完全房室ブロック:房室間の刺激伝導が断たれ、心房と心室の拍動が独立して徐脈となる
徐脈によって、脳への血流低下が生じると、めまい、失神、意識消失などの症状が起こります。
とくにアダムス・ストーク症候群や完全房室ブロックでは、ペースメーカーの適応が検討されることもあります。
🔶頻脈・徐脈の見分けと国家試験対策
国家試験では、「頻脈や徐脈をきたす疾患の組み合わせ」を問う問題が頻出です。
たとえば、「頻脈の原因として誤っているものを選べ」や「徐脈をきたす内分泌疾患はどれか?」といった出題が想定されます。
また、心拍数だけでなく、リズム異常(不整脈)との鑑別も重要であり、「頻脈性不整脈(心房細動、上室性頻拍など)」と「徐脈性不整脈(房室ブロックなど)」の理解も必要です。
臨床現場では、バイタル測定時に異常な脈拍数を見つけたら、必ず他のバイタル(血圧・呼吸・意識)とともに全体像を把握することが求められます。
薬剤の影響(β遮断薬など)も見逃してはならないポイントです。
頻脈・徐脈は、単なる数字の異常ではなく、体の異変を知らせるアラームです。
原因を突き止める力と、適切な初期対応が現場力につながります。
鍼灸25回-50
脈拍について正しいのはどれか。
- 鉄欠乏性貧血では徐脈を呈する。
- うっ血性心不全では頻脈を呈する。
- 甲状腺機能低下症では頻脈を呈する。
- 出血性ショックでは徐脈を呈する。
鍼灸28回-52
脈拍について正しいのはどれか。
- 貧血では頻脈を呈する。
- 頭蓋内圧亢進時は頻脈を呈する。
- 甲状腺機能亢進症では徐脈を呈する。
- うっ血性心不全では徐脈を呈する。
鍼灸2回-57
頻脈となる疾患はどれか。
- 心ブロック
- 脳圧亢進
- バセドウ病
- 洞不全症候群
鍼灸19回-56
頻脈がみられるのはどれか。
- 鉄欠乏性貧血
- 糖尿病
- バージャー病
- 甲状腺機能低下症
鍼灸18回-61
徐脈がみられるのはどれか。
- バセドウ病
- 発熱
- 貧血
- アダムス・ストークス症候群
鍼灸7回-61
橈骨動脈の脈拍について正しいのはどれか。
- 示指で触診する。
- 右より左が大きい。
- 大動脈炎症候群では右が大きい。
- ショック時には触れにくくなる。
按マ指国家試験過去問
按マ指21回-65
安静時の脈拍数で正しい記述はどれか。
- 成人では80/分以上を頻脈という。
- 成人では60/分以下を徐脈という。
- 乳幼児は約40/分である。
- 鍛錬されたスポーツマンでは100/分以上ある。
按マ指20回-60
頻脈がみられるのはどれか。
- 脳圧亢進
- 粘液水腫
- 褐色細胞腫
- 完全房室ブロック
按マ指29回-44
頻脈がみられるのはどれか。
- 脳圧亢進
- 粘液水腫
- 褐色細胞腫
- パーキンソン病
按マ指4回-67
頻脈とならないのはどれか。
- 発熱
- 運動
- 精神的緊張
- 睡眠
按マ指10回-75
徐脈をきたすのはどれか。
- 完全房室ブロック
- 期外収縮
- 奇脈 交
- 互脈
按マ指30回-44
徐脈がみられるのはどれか。
- うっ血性心不全
- 甲状腺機能亢進症
- 出血性ショック
- 頭蓋内圧亢進
🌟脈拍リズムの異常
脈拍リズムの異常は、心臓の電気的な刺激伝導系に異常がある場合や、外的要因によって心拍が規則的でなくなる状態を指します。
これを総称して不整脈(arrhythmia)と呼びます。
不整脈には生理的なものから重篤な疾患を示唆する病的なものまで幅広く存在し、臨床での判断力が問われる重要な観察項目です。
ここでは、国家試験でよく出題される代表的な不整脈の種類と特徴、関係する疾患について、表とともに解説していきます。
| 名称 | 特徴 | 関連疾患・備考 |
|---|---|---|
| 洞性不整脈 | 吸気時に脈が速く、呼気時に遅くなる。 呼吸性不整脈とも呼ばれ、若年者に多い。 | 生理的現象で病的意義なし |
| 期外収縮 | 正常のリズムより早く心拍が現れる異常な脈。 早期に来る異所性興奮による。 | 心疾患、 ジギタリス中毒 |
| 絶対性不整脈 | 脈の間隔・強さ・大きさが全く不規則。 心房細動に典型的。 | 僧帽弁膜症、 虚血性心疾患、 甲状腺機能亢進症、 脳塞栓 |
| 心ブロック | 刺激伝導路の障害により、心房から心室への伝導が遅延・遮断される。 | 完全房室ブロックでは徐脈 |
| 交互脈 | 脈拍の強さが1拍ごとに変化する。 | 左室機能不全、心筋障害 |
| 奇脈 | 吸気時に脈拍が減弱または消失する。 | 心タンポナーデ、収縮性心膜炎など |
🔶代表的な不整脈の解説
① 洞性不整脈:自律神経の働きによって起こる呼吸性の脈拍変動です。小児や若年者に多く、生理的で問題ないものです。吸気時に心拍数が増加し、呼気時に減少します。検査中に気づいても病的意義はないと判断されます。
② 期外収縮:通常の心拍リズムに割り込むように早期の心拍が現れます。心房性・心室性の2種類があり、ジギタリス中毒や心疾患で出現しやすいです。患者は「胸がドキッとする」「一瞬止まった感じがする」などと訴えることがあります。
③ 絶対性不整脈:全く不規則な脈で、一定の間隔や強さがないのが特徴です。代表的な原因は心房細動で、血栓形成→脳塞栓のリスクが高くなります。高齢者や弁膜症、甲状腺機能亢進症などが背景にあることも多く、抗凝固療法が行われることもあります。
④ 心ブロック:刺激伝導系の異常により、心房から心室への信号が伝わらなくなる病態です。完全房室ブロックでは心室が独立して拍動し、著しい徐脈を起こします。重度の場合はペースメーカーの適応です。
⑤ 交互脈:脈の強さが交互に変わるのが特徴で、左室の収縮力が不安定な場合にみられます。心筋症や心不全など心筋障害の存在を示唆します。
⑥ 奇脈:吸気時に脈が弱くなったり、触れなくなったりする現象です。心タンポナーデや収縮性心膜炎などの疾患で起こり、緊急性が高い兆候です。
🔶国家試験対策ポイント
国家試験では、「心房細動=絶対性不整脈」「ジギタリス中毒=期外収縮」「奇脈=心タンポナーデ」など、不整脈の種類と原因疾患の組み合わせがよく出題されます。
また、心電図所見との対応(例:心房細動ではP波が見られない、心ブロックではPQ延長や脱落)が問われることもあるため、病態とメカニズムをセットで理解しておくことが得点に直結します。
不整脈は一見すると難しそうですが、名称と症状・原因をひとつずつ整理すれば確実に覚えられます。
臨床現場でも遭遇頻度の高い内容ですので、試験対策のうちにしっかり理解しておきましょう。
鍼灸3回-58
脈拍のリズムについて正しい記述はどれか。
- 期外収縮とは脈が1拍欠けるものをいう。
- 心房細動は絶対性不整脈を示す。
- 完全房室ブロックでは脈が速くなる。
- 洞性不整脈と呼吸のリズ ムと無関係である。
鍼灸30回-61
不整脈で予後が最も良いのはどれか。
- 心室細動
- 心房細動
- 上室性期外収縮
- Ⅲ度房室ブロック
鍼灸9回-74
心房細動に合併しやすい脳血管障害はどれか。
- 脳血栓症
- 脳塞栓症
- 脳出血
- くも膜下出血
鍼灸4回-81
脳梗塞を起こしやすい不整脈はどれか。
- 心房細動
- 心室細動
- 期外収縮
- 房室ブロック
按マ指国家試験過去問
按マ指13回-84
脈拍異常とその原因との組合せで誤っているのはどれか。
- 呼吸性不整脈---洞性不整脈
- 絶対性不整脈---心房細動
- 脈拍欠損---期外収縮
- 奇脈---房室ブロック
按マ指14回-70
心房細動の合併症はどれか。
- 脳塞栓
- 脳血栓
- 脳出血
- 脳腫瘍
按マ指6回-86
心房細動と関係の深い疾患はどれか。
- 脳腫瘍
- 脳膜炎
- 脳塞栓
- 脳出血
🌟血圧について
血圧(Blood Pressure)は、心臓が血液を全身に送り出すときに血管壁にかかる圧力のことです。
血圧の測定は、循環機能の評価や疾患の早期発見・経過観察に欠かせない指標であり、国家試験でも必ず出題される重要項目です。
🔶血圧の測定方法
| 測定方法 | 説明 |
|---|---|
| 触診法 | 橈骨動脈の拍動を触れて測定する方法。 最高血圧のみ把握でき、聴診法よりやや低めに出る。 |
| 聴診法 | 血圧計と聴診器を用いてスワン音を確認する方法。 第1点=最高血圧、第5点=最低血圧。 |
| 正しい姿勢 | 座位または仰臥位で、前腕を心臓と同じ高さに置く。測定前の安静も重要。 |
とくに国家試験では、スワン音の第1点と第5点がそれぞれ何を示すかがよく問われるので、「第1点=収縮期血圧」「第5点=拡張期血圧」という基本をしっかり押さえましょう。
- コロトコフ音(スワンの第1〜5点)
- 第1点:音が聞こえ始める(最高血圧)
- 第2点:雑音が現れる
- 第3点:高調で清明な音になる
- 第4点:音が急に弱まる
- 第5点:音が完全に消失する(最低血圧)
🔶高血圧とその原因
高血圧(Hypertension)とは、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の状態を指します。
原因には以下のような分類があります。
| 分類 | 代表的な原因 |
|---|---|
| 腎性 | 慢性腎炎、糖尿病性腎症など |
| 内分泌性 | 褐色細胞腫、クッシング症候群、原発性アルドステロン症 |
| 神経性 | 頭蓋内圧亢進など |
| 心血管性 | 大動脈弁閉鎖不全症など |
- 仮面高血圧:家庭血圧は高いが診察室では正常
- 白衣高血圧:診察室でのみ高く、家庭では正常
これらの高血圧タイプは、家庭での血圧測定が診断に重要な役割を果たします。
持続的な高血圧は、脳卒中・心不全・腎不全などのリスクとなるため、早期の発見と管理が重要です。
🔶低血圧とその原因
低血圧(Hypotension)は、明確な数値基準はありませんが、一般に収縮期血圧が100mmHg以下またはそれに伴って症状(立ちくらみ・意識消失・倦怠感など)がある場合を指します。以下のような病態で生じます。
- 大出血:循環血液量の減少により血圧が維持できなくなる
- 脱水:体液量の減少により低血圧に
- 心筋梗塞:心拍出量の低下による
- 敗血症:血管拡張と循環障害
- 急性腎不全:ナトリウム・水分保持不能により
- シモンズ病:下垂体機能低下により、全身代謝が低下
🔶脈圧とは?
脈圧は、収縮期血圧(最高血圧)と拡張期血圧(最低血圧)の差を指します。
正常は40〜60mmHg前後です。
- 広い脈圧:大動脈弁閉鎖不全症など
- 狭い脈圧:心拍出量が低下した状態(ショックなど)
脈圧の異常も、疾患の鑑別に役立つサインのひとつです。
とくに脈圧が著しく狭い場合には、循環不全が疑われ、早期の対応が必要です。
血圧は単なる数字の変化ではなく、心臓・血管・ホルモン・腎臓などの総合的な働きのバロメーターです。
国家試験では原因疾患との関連性や測定方法の知識が問われるため、しっかり整理しておきましょう。
鍼灸23回-53
血圧について正しいのはどれか。
- 血圧を測定する際は前腕を強く屈曲する。
- 低血圧は動脈硬化の危険因子である。
- 血圧は心臓の拡張期に最高となる。
- 収縮期血圧と拡張期血圧の差を脈圧という。
鍼灸29回-46
血圧について正しいのはどれか。
- 心臓は拡張期に最高となる。
- 脈圧は収縮期血圧と拡張期血圧の差である。
- 触診法で拡張期血圧が測定できる。
- 圧迫帯は肘関節に巻く。
鍼灸20回-55
血圧について正しい記述はどれか。
- 平均血圧は収縮期血圧と拡張期血圧の和は1/2 である。
- 触診法での聴診法より高く測定される。
- 仮面高血圧患者での家庭血圧が診察室血圧より高い。
- 白衣高血圧は若年者に多い。
鍼灸8回-61
随時血圧測定で誤っている記述はどれか。
- 坐位で測定する。
- 収縮期血圧はスワン第5点で判定する。
- 収縮期血圧䛿は触診法で測定できる。
- 収縮期血圧は触診法よりも聴診法で高値を示す。
鍼灸11回-60
血圧測定で誤っている記述はどれか。
- 触診法は聴診法より測定値が高くなる。
- 血圧は通常上腕で測定する。
- 大動脈弁閉鎖不全症では拡張期血圧をスワン4 点で判定する。
- 触診法では収縮期血圧のみ測定できる。
鍼灸14回-138
「本態性高血圧で降圧薬を服用している78歳の男性。夜間頻尿を主訴とし て来院。手足のほてり、 腰の重だるさがみられ、 舌診では舌質紅・無苔、 脈診では浮で無力を呈し た。随時血圧測定では収縮期血圧148mmHg、拡張期血圧84mmHgであった。」この文で示す患者について、随時血圧の測定で誤っているのはどれか。
- 上腕を心臓の高さにして 測定する。
- 仰臥位で測定する。
- スワンの第1点を収縮期血圧とする。
- マンシェットの圧を1秒間に2mmHg程度で下げて いく。
鍼灸12回-78
高血圧症の臨床所見でみられないのはどれか。
- 蛋白尿
- 心肥大
- 血中ナトリウム上昇
- 眼底細動脈狭窄
鍼灸7回-76
高血圧がみられない疾患はどれか。
- 原発性アルドステロン症
- クッシング症候群
- アジソン病
- 褐色細胞腫
鍼灸2回-70
二次性高血圧の原因とならない疾患はどれか。
- 褐色細胞腫
- アルドステロン症
- アジソン病
- バセドウ病
鍼灸11回-54
二次性高血圧症に関与しない疾患はどれか。
- 急性糸球体腎炎
- 甲状腺機能亢進症
- 急性肝炎
- 褐色細胞腫
鍼灸2回-137
境界域高血圧症患者の生活指導で誤っているのはどれか。
- 安静
- 禁煙
- 禁酒
- 減塩食
鍼灸14回-139
「本態性高血圧で降圧薬を服用している78歳の男性。夜間頻尿を主訴とし て来院。手足のほてり、 腰の重だるさがみられ、 舌診では舌質紅・無苔、 脈診では浮で無力を呈し た。随時血圧測定での収縮期血圧148mmHg、拡張期血圧84mmHgで あった。」この文で示す患者について、本症例は高血圧の治療を放置した 場合、臓器障害がみられにくいのはどれか。
- 心臓
- 腎臓
- 肝臓
- 脳
鍼灸12回-77
低血圧がみられる疾患はどれか。
- クッシング症候群
- コン症候群
- シモンズ病
- レイノー病
按マ指国家試験過去問
按マ指4回-68
健常者の血圧について正しい記述はどれか。
- 右手より左手の方が高い。
- 臥位と立位では異なる。
- 拡張期血圧が収縮期血圧より高い。
- 上肢と下肢では差がな い。
按マ指3回-65
血圧について正しい記述はどれか。
- 最高血圧とは拡張期圧をいう。
- 単に血圧といえば静脈内圧をいう。
- 触診法では収縮期圧を測定する。
- 左右の手の血圧の差を脈圧という。
按マ指2回-66
血圧について正しい記述はどれか。
- 触診法では最低血圧はわからない。
- 収縮期血圧と最低血圧とは同じである。
- 個人の血圧は一日中一定である。
- 拡張期血圧は血管が最も拡張した時の血圧である。
按マ指1回-75
血圧について正しいのはどれか。
- 最低血圧は静脈の血圧をいう。
- 最高血圧は心室の拡張期の血圧である。
- 上肢と下肢とで血圧値は同一である。
- 最高血圧と最低血圧との差を脈圧という
按マ指24回-52
血圧測定に関して正しいのはどれか。
- マンシェットは肘窩を中心に巻く。
- 触診法で拡張期血圧が測定できる。
- 脈圧の収縮期血圧と拡張期血圧の差である。
- 収縮期血圧はスワン第5 点で判断する。
按マ指6回-70
聴診法による血圧測定で収縮期血圧に相当するのはどれか。
- 音が聴こえ始める点
- 音が最も大きく聴こえる点
- 突然音が小さくなる点
- 音が完全に消失する点
按マ指13回-71
随時血圧測定で誤っている記述はどれか。
- 坐位で測定する。
- 圧迫帯は中心が心臓の高さで測定する。
- 圧迫帯の減圧は1心拍に約6mmHgとする。
- 収縮期血圧はスワン第1 点で判定する。
按マ指25回-68
高血圧症について正しいのはどれか。
- 多くは頭痛を主訴とする。
- 原因の90%以上は遺伝的要因である。
- 食事療法ではカリウム摂取を制限する。
- 罹患率は年齢とともに増加する。
按マ指1回-81
高血圧で誤っているのはどれか。
- 本態性と症候性とがある。
- 非遺伝性である。
- 食塩摂取により悪化する。
- 動脈硬化を増悪する。
按マ指6回-65
高血圧を伴う疾患はどれか。
- 膀胱腫瘍
- 前立腺肥大
- 睾丸腫瘍
- 腎硬化症
按マ指11回-83
高血圧がみられる疾患はどれか。
- シモンズ病
- 原発性アルドステロン症
- アジソン病
- 粘液水腫
按マ指18回-86
二次性高血圧の原因となる疾患はどれか。
- ギラン・バレー症候群
- ダンピング症候群
- 上大静脈症候群
- 大動脈炎症候群
按マ指24回-68
二次性高血圧の原因となる疾患はどれか。
- 褐色細胞腫
- バージャー病
- ラムゼイハント症候群
- 上大静脈症候群
按マ指5回-147
高血圧症で施術の対象として適切なのはどれか。
- 本態性のもの
- 心臓疾患によるもの
- 腎臓疾患によるもの
- 内分泌疾患によるもの
🌟呼吸について
呼吸は、酸素と二酸化炭素のガス交換を行う生命維持の基本機能のひとつであり、呼吸の回数・リズム・深さ・努力呼吸の有無などを観察することで、呼吸器・循環器・中枢神経系の異常を早期に捉えることができます。
国家試験でも頻出となる異常呼吸のパターンやその原因疾患について、以下の表に詳しくまとめます。
| 異常呼吸の名称 | 特徴 | 関連疾患・状態 |
|---|---|---|
| 頻呼吸 | 呼吸回数の増加 | 心不全、肺炎、髄膜炎、尿毒症、発熱 |
| 徐呼吸 | 呼吸回数の減少 | 脳圧亢進、気管支閉塞、モルヒネ中毒 |
| 起坐呼吸 | 仰臥位で呼吸困難が増悪し、座位で軽快 | 心不全(特に肺うっ血時) |
| チェーンストークス呼吸 | 徐々に深くなる呼吸と無呼吸を周期的に繰り返す | 心・腎・脳疾患、薬物中毒 |
| クスマウル呼吸 | 深く速い規則的な呼吸(代謝性アシドーシスの代償) | 糖尿病性昏睡、尿毒症 |
| ビオー呼吸 | 短く速い呼吸の後、突然の無呼吸を繰り返す | 脳圧亢進 |
| 口すぼめ呼吸 | 呼気時に口をすぼめて呼気抵抗を減らす | COPD、肺気腫 |
| 呼気性呼吸困難 | 呼気時に強い努力が必要になる | 気管支喘息 |
| 吸気性呼吸困難 | 吸気時に呼吸困難が強くなる | 上気道閉塞(鼻閉・異物など) |
| 混合性呼吸困難 | 吸気・呼気ともに困難 | 肺炎、胸膜炎、心不全 |
| 心臓喘息 | 夜間の発作性呼吸困難。肺うっ血が原因 | 左心不全(夜間悪化) |
| 過換気(過呼吸) | 呼吸数・深さの異常増加 | 激しい運動、過度のストレス、過呼吸症候群 |
🔶呼吸異常の観察ポイント
呼吸異常を見つけた場合は、単に「苦しそう」と判断するのではなく、いつ・どんな姿勢で・どのようなリズムや深さかを具体的に記録することが重要です。
- 呼吸数:成人では16~20回/分が基準
- 呼吸のリズム:整っているか、不規則か
- 呼吸補助筋の使用:肩をすくめる、鼻翼の動き
- 呼吸音:副雑音(ぜい鳴、捻髪音)など
これらを踏まえて観察することで、呼吸器疾患・循環不全・中枢神経障害の早期発見や、適切な医療介入につながります。
🔶国家試験対策のポイント
国家試験では、クスマウル呼吸=糖尿病性昏睡、チェーンストークス呼吸=心不全や脳障害など、呼吸異常と疾患の組み合わせがよく出題されます。
用語の意味だけでなく、背景病態と結び付けて覚えるようにしましょう。
また、起坐呼吸・心臓喘息・過換気症候群など、臨床現場での看護対応が求められるパターンも問われます。
異常呼吸に気づいた際の対応として、体位変換・酸素投与・医師への報告なども重要です。
呼吸の観察は、患者の生命に直結する情報を得る窓口です。
見逃さない観察力と、判断力、即応力が求められます。
鍼灸1回-66
呼吸困難について正しいのはどれか。
- 右心不全では生じることはない。
- 心臓喘息は肺うっ血による。
- 過換気症候群は左心不全による。
- 夜間発作性呼吸困難は心不全とは関係がない。
鍼灸8回-74
呼吸とその原因との組合せで誤っているのはどれか。
- 頻呼吸---脳圧亢進
- クスマウル大呼吸---糖尿病性アシドーシス
- 起坐呼吸---心不全
- チェーン・ストークス呼吸---尿毒症
鍼灸22回-52
糖尿病性昏睡時にみられるのはどれか。
- チェーン・ストークス呼吸
- クスマウル呼吸
- ビオー呼吸
- 口すぼめ呼吸
あマ指国家試験過去問
按マ指16回-67
呼気時に呼吸困難を呈するのはどれか。
- 気管支喘息
- 肺線維症
- 鼻閉
- 異物による上気道閉塞
按マ指11回-65
呼吸困難の所見でないのはどれか。
- 呼吸補助筋を使う。
- 意識障害がある。
- 息切れがする。
- 起坐位で楽になる。
按マ指2回-69
呼吸困難の成因と疾患との組合せで誤っているのはどれか。
- 気管支喘息---呼吸筋性
- 左心不全---心臓性
- 尿毒症---代謝性
- 頭蓋内庄亢進症---神経性
按マ指16回-100
呼吸困難の程度を表わす分類はどれか。
- ヒュー・ジョーンズ
- スタインブロッカー
- ウェクスラー
- ブルンストローム
按マ指21回-74
「45歳の男性。労作時の呼吸困難、咳嗽、喀痰を 主訴に来院した。胸部は聴診で呼吸音は減弱し、 視診上、口すぼめ呼吸がみられ、呼吸機能検査で1秒率の低下を認めた。」この症状の原因はどれか。
- 気胸
- 肺気腫
- 肺水腫
- 間質性肺炎
按マ指8回-89
リズムの異常を伴う呼吸はどれか。
- 頻呼吸
- 徐呼吸
- 過呼吸
- ビオー呼吸
按マ指13回-73
呼吸異常と疾患との組合せで正しいのはどれか。
- チェーン・ストークス呼吸---糖尿病性アシドーシ ス
- 起坐呼吸---うっ血性心不全
- クスマウル大呼吸---気管支喘息
- 下顎呼吸---過換気症候群
按マ指29回-45
呼吸異常と疾患の組合せで正しいのはどれか。
- 起坐呼吸---うっ血性心不全
- 下顎呼吸---気管支喘息
- クスマウル大呼吸---過換気症候群
- チェーン・ストークス呼吸---糖尿病性ケトアシドーシス
按マ指11回-75
最も危険な状態を示す呼吸はどれか。
- チェーン・ストークス呼吸
- クスマウル呼吸
- あえぎ呼吸
- 睡眠時無呼吸
按マ指15回-58
徐呼吸がみられるのはどれか。
- 脳圧亢進
- 発熱
- 肺炎
- 心不全
按マ指5回-71
気管支喘息発作時の呼吸で誤っているのはどれか。
- 呼吸数の増加
- 吸気の延長
- 起坐位
- 喘鳴
按マ指6回-71
気管支喘息発作時の呼吸困難で楽な体位はどれか。
- 仰臥位
- 起坐位
- 側臥位
- 腹臥位
🌟まとめ|バイタルサインは「命の声」
バイタルサインは、患者の状態変化を最も早く、最も確実に捉えるための重要な観察項目です。
体温・脈拍・呼吸・血圧・意識、それぞれが「生命維持に必要な機能の反映」であり、異常を見逃さないことが、迅速な対応と重篤化の回避につながります。
今回の記事では、各バイタルサインについて次のような内容を整理しました:
- 体温:測定部位の違い、発熱と低体温の区別、熱型の種類と関連疾患
- 脈拍:頻脈・徐脈の原因疾患、脈のリズム異常(心房細動、期外収縮など)
- 血圧:測定法(触診法・聴診法)、高血圧・低血圧の分類と病因、脈圧の意味
- 呼吸:異常呼吸の種類(クスマウル・チェーンストークスなど)と関連病態
- 意識:死の三徴候・脳死と植物状態の違い、JCSやGCSなどの評価指標
これらの知識は、国家試験で必ず出題される定番分野です。
特に以下のような出題パターンが多く見られます:
- 「この疾患で予想されるバイタルの変化はどれか?」
- 「熱型と代表疾患の組み合わせとして正しいのは?」
- 「コロトコフ音の第1点は何を示すか?」
- 「心房細動の特徴的な脈拍は?」
- 「クスマウル呼吸が見られるのはどの病態か?」
ただ丸暗記するのではなく、病態生理とセットで理解し、なぜその異常が出るのかを考えることが合格への近道です。
そして、実習や臨床現場ではこの知識を使って「患者さんの命のサインを読み取る力」になります。
「体温が上がってるから風邪かな?」ではなく、「なぜこの人は発熱しているのか?」「その熱型は何を示しているのか?」と考えられることが医療者に求められる視点です。
最後に、バイタルサインを測るという行為は単なる数値の記録ではなく、「いま、患者がどう生きているか」を知ることでもあります。
常に観察力と判断力を養い、患者に寄り添える力を磨いていきましょう。
次の記事では「ショック」「意識障害」「循環の観察」など、より実践的な症状アセスメントへと進んでいきます。
バイタルサインの知識を土台として、さらにステップアップしていきましょう。