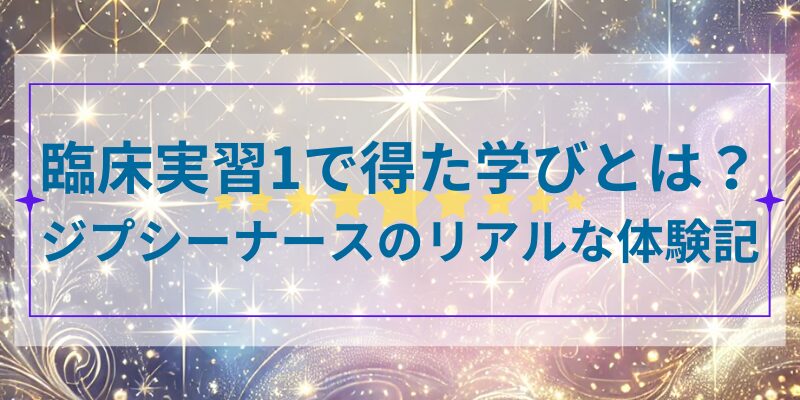🌟鍼灸と看護、臨床実習のギャップに驚いた話
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
今回は、鍼灸学生としての「臨床実習1」で感じたことを、看護学生時代の過酷な実習と比較しながら、率直に綴ってみたいと思います。
率直に言うと──鍼灸の臨床実習、びっくりするほどラクです。
もちろん、ラク=学びがないというわけではありません。
でも、精神的にも肉体的にも「看護実習の地獄」をくぐり抜けてきた私にとっては、あまりにも対照的な世界でした。
看護学生時代の実習は、本当に過酷でした。
1クール3週間、内科・外科・精神科など各領域をローテーションしながら、1週間目で情報収集、2〜3週目で看護計画の立案・実施・評価──。
しかも、実習先では常に「緊張」や「不安」にさらされます。
指導者との関係、看護師の目、患者とのコミュニケーション……そして、なにより大変だったのが、看護記録の量です。
たった1人の患者さんに対して、3~4cmにもなる分厚い記録冊子を作成。
深夜までパソコンに向かい、翌朝はまた病院へ。
記録地獄とは、まさにあのことです。
それに比べると、鍼灸実習は「天国」と感じてしまうほど穏やかです。
基本は見学スタイルで、指導教員のもとで医療面接から施術までの一連の流れを観察します。
1グループ5〜6人で交代しながら臨床現場に入るため、学生一人にかかる負担はかなり少なめです。
しかも、終わった後にレポートや記録を出す義務は(少なくともKagayaの学校では)ほぼありません。
夜もぐっすり眠れますし、精神的に追い詰められるようなプレッシャーもありません。
「これでいいの?」と思ってしまうほど、拍子抜けするくらいでした。
もちろん、実習内容が「軽い」わけではありません。
見学といっても、学ぶべきことは山ほどあります。
ただ、看護実習のように「実践して評価される」という構造が少ないため、受け身の姿勢でもある程度こなせてしまうのが現実です。
実際の臨床で扱う患者さんの訴えは、肩こりや腰痛などの整形外科的症状が中心です。
教員の鍼手技はとても勉強になりますが、正直なところ──私はそこに強い関心を持てていません。
Kagayaが本当に興味を持っているのは、脊髄損傷やパーキンソン病など、神経系の難治性疾患、あるいは障がい児のような特別なニーズを抱える方への鍼灸的アプローチです。
しかし、残念ながら学校付属の鍼灸院には、そういった方が来院することはほぼありません。
バリアフリーではない治療院の構造(階段など)も一因ですし、学校の地域的な特性もあると思います。
「もっと多様な症例に出会いたい」「障がいを持つ方への鍼灸を学びたい」と思っても、それは臨床実習1では叶わないのが現実でした。
それでも──臨床実習を通して見えてきたこと、気づいたこと、感じたことはたくさんあります。
次章からは、実際にどんな学びがあったのか、振り返ってみたいと思います。
🌟臨床実習1の学習目標と現場での「気づき」
臨床実習は、鍼灸学生にとって臨床力を育てるための大切なプロセスです。
学校によってカリキュラムは多少異なると思いますが、私の通う学校では「臨床実習1~4」まで段階的に構成されています。
その中でも、臨床実習1は「見学実習」が中心。
つまり、自分で施術を行うのではなく、主に教員の施術や問診を観察しながら、臨床の流れ・空気感・患者対応の所作を体得していく段階です。
実習の初回オリエンテーションでは、以下のように説明されました。
「見学を通して、臨床に携わる者としての態度・習慣を身につける。また、将来必要となる臨床能力を見学から学び、“気づき”を得ることが目的です」
つまり、「ただ見る」のではなく「観察して学ぶ」姿勢が求められているということです。
一見ラクに見える見学実習ですが、観察の質がそのまま学びの深さに直結します。
実際には、指導教員の裁量によっては少しだけ「実践」の場もあります。
たとえば──
- 患者さんの医療面接を横で見ながら記録を取る
- 教員の指導のもと、1〜2穴だけ鍼を刺させてもらう
- 治療後の声かけやベッド整備を任される
完全な受け身ではなく、患者さんとの距離を少しずつ近づけていくステップでもあります。
とはいえ、まだ2年生の段階では学生主体で治療計画を立てたり、東洋医学的診断を行うことはありません。
あくまでも「臨床現場を感じ、流れをつかむ」ための準備段階です。
実習中は、患者さんの表情や言葉のニュアンス、教員の判断基準、刺鍼のリズムや力加減など、あらゆる情報が学びのヒントになります。
特に印象に残ったのは、「患者さんとの空気の作り方」。
教員の中には、初対面にもかかわらず、患者さんの緊張をすっと解くような話し方をされる方もいて、「こういうのが“臨床力”なんだな」と、目の前で見て実感しました。
教科書で学んだ“接遇”では表現しきれない、実際の場でしか感じられない「温度」がある。
臨床実習1の価値は、まさにそこにあると思います。
そしてもうひとつ大きかったのは、「自分がどんな鍼灸師になりたいのか」を少しずつ意識するようになったことです。
鍼灸師の数だけ、スタイルがある。手技も考え方も十人十色。見学を重ねるほど、自分の目指す方向が少しずつ明確になっていく──そんな感覚が芽生えた実習でもありました。
次の実習では、もう少し能動的に関われるようになるそうです。それに備えて、今できることを丁寧に積み重ねていきたいと思っています。
🌟医療面接から見えてきた課題
臨床実習の中でも、印象的だったのが「医療面接」でした。
Kagayaは看護師としてのバックグラウンドがあるので、情報収集の大切さは身をもって知っています。
看護学生時代には、患者さんからの情報をもとに看護計画を立案するため、日々コミュニケーションに頭を悩ませていました。
主訴・生活歴・家族背景・服薬状況など、かなり広範囲にわたって聞き取る必要があります。
一方、鍼灸の臨床実習で初めて「医療面接」という言葉を耳にした時は、少し違和感がありました。
「あれ?これって看護でやってた“情報収集”のことだよね?」と。
でも、実際に臨床での医療面接を見学・体験するうちに、治療者としての目的が違うことに気づいてきました。
鍼灸における医療面接は、単に情報を集めるだけでなく、「どこに、なぜ、どう鍼を打つか」という治療方針に直結する大事な過程なのです。
患者さんを治療室に案内し、着替えを促すところからすでに“観察”は始まっています。
姿勢、歩き方、声のトーン──すべてが診断のヒントになります。
医療面接が始まると、主訴を丁寧に聞き取っていきます。
たとえば痛みひとつとっても、表現は人それぞれです。
「ジンジンする」「ズキズキ」「重だるい」など言葉の違いに注目しながら、患者さんと共通認識を持つために確認を重ねることが大切です。
ただ、実習中に驚いたことがありました。
一応「初診」という設定で面接を行っていたのに、教員は生活習慣だけを聞き、職業や既往歴・現病歴はほとんど確認していなかったのです。
「え?そこ、聞かなくて大丈夫?」と正直モヤモヤしました。
看護の現場では、職業病の可能性や感染症リスク、アレルギー有無の確認は必須項目です。
鍼灸においても、鍼の金属や使用するアルコールにアレルギー反応を起こす人は一定数います。
そのリスクを把握せずに施術することは、治療者として無責任だと感じます。
訪問看護で使うフェイスシートにも、「利用目的」や「ご本人・ご家族の希望」を記入する欄があります。
学生の頃はその意味がよく分からなかったのですが、今になってとても重要だと痛感しています。
特に鍼灸やマッサージのような自由診療の場合、「慰安目的」なのか「治療目的」なのかを明確にしないと、トラブルの原因になります。
患者さんの中には「癒されたいだけ」の人もいれば、「本気で治したい」と思っている人もいます。
後者であれば本治・漂治の考え方を説明し、継続的な来院を促す必要がありますし、前者であれば強い刺激はむしろ逆効果になるかもしれません。
実際、訪問看護の現場でも、「マッサージが下手」と怒られたことがあります。
看護師や理学療法士に対して、あたかも“リラクゼーションサービス”のような期待を抱いているケースです。
その人の目的と、こちらの提供するケアがずれていれば、信頼関係は一気に崩れます。だからこそ──。
「患者さんがどんな未来を望んでいるのか」
それを丁寧に聞き取ることが、医療面接の本質だと感じました。
もしも、その人の望むことと自分ができることが明らかにズレているのであれば、思いきってお断りするのも誠実な選択かもしれません。
治療者の価値観を押しつけるのではなく、「その人の物語」にそっと寄り添う姿勢──それが、Kagayaの目指す医療面接のあり方です。
🌟鍼事故の防止について|安全な施術のために必要なこと
鍼灸は基本的に安全な医療です。
しかし、「人が手で行う施術」である以上、絶対に事故が起きないとは言い切れません。
「鍼は怖くない」「副作用がない」というイメージもありますが、それは“正しい方法で使った場合”に限った話です。
看護師として医療現場に長く身を置いてきたKagayaにとって、「リスク管理」は当たり前の感覚でした。
しかし、鍼灸の現場においても同様に、事故防止のために意識すべきことは多くあります。
ここでは、臨床実習を通じて気づいた鍼灸のリスクとその対策について、体験を交えてまとめてみます。
鍼刺し事故|感染のリスクをゼロにするには
医療従事者にとって、「針刺し事故」は職業上の大きなリスクのひとつです。
看護師時代、採血や点滴で使用する針の取り扱いについては、研修でも厳しく指導を受けました。
Kagayaは10年以上看護師として働く中で、針刺し事故を起こしたことはありませんが、周囲で一度だけ実際に起きたケースを目の当たりにしました。
緊張と焦りが重なった一瞬のミスでした。
鍼灸師も鍼を扱う以上、このリスクとは常に隣り合わせです。
ディスポ鍼(使い捨て鍼)の使用が主流ですが、それでも使用前・使用後の管理、刺入・抜鍼の手順には細心の注意が必要です。
臓器・神経損傷と気胸のリスク
鍼は体表から深部へと刺入する治療法です。
だからこそ、臓器や神経への損傷リスクがゼロではありません。
中でも特に注意したいのが「気胸」。
肺に鍼が刺さってしまい、呼吸困難や命に関わる事故に発展することもあります。
極細の鍼で起きるなんて信じられないと思うかもしれませんが、実際に死亡事例も報告されています。
また、置鍼中に鍼の上にタオルや毛布をかけてしまうと、その重みで鍼が深く刺さりすぎる危険もあります。
ほんの小さなミスでも重大事故に繋がりかねないので、施術環境への配慮も不可欠です。
加えて、内出血も避けては通れません。
どんなに経験豊富な鍼灸師でも、一定の確率で起こります。
だからこそ、患者さんに事前にリスクを説明し、施術後はきちんと止血対応を行うことが、信頼関係の維持につながります。
鍼の抜き忘れ|ヒヤリ・ハットの典型例
鍼灸院で最も多いインシデントが「鍼の抜き忘れ」だといわれています。
特に「ルート治療」など、多数の鍼を使用する場合は、1本の確認漏れが大きな事故に直結します。
Kagayaは、使用する鍼の本数をできるだけ最小限に抑え、管理しやすくすることを心がけています。
1本1本の鍼の意味を明確にして使いたいという思いもありますし、コスト面でも大切な工夫です。
実際、必要以上の鍼を使っても効果が上がるとは限りません。
信頼してくれていた患者さんでも、鍼の抜き忘れ1つで一気に関係が崩れてしまいます。
自分で管理できない手技は、最初から選ばない。
それが、事故を防ぐ一番の方法かもしれません。
ドーゼオーバー|刺激の“やりすぎ”で悪化することも
「ドーゼオーバー」とは、刺激のしすぎによって身体が逆に悪化してしまう現象です。
刺激量は人によって異なります。
年齢、体質、精神状態、その日の体調によっても受け取り方がまるで違うのです。
実は以前、知人から「母親が鍼灸治療をやめたら、歩けるようになった」と聞いたことがあります。
当時は「鍼灸って怖い」と思ってしまいました。
でも今思えば、その鍼灸師が刺激量を調整できていなかったのかもしれません。
もしくは、悪化させて通院させようとする悪質なケースだったのかも……。
鍼灸は「痛みを与える治療」ではありません。
説明もなく、ただ強い刺激を与えるだけの施術は避けるべきです。
お灸による火傷と火災リスク
かつては“痕をつけてこそ効く”というような灸法もありましたが、現代ではそんなやり方は通用しません。
火傷によるトラブルはすぐに訴訟問題に発展します。
Kagayaは、自分の足でお灸練習をしていたとき、調子に乗って火傷を作ってしまったことがあります。
根性焼きのような跡ができてしまい、自分でも驚きました……。
火の扱いには十分注意しなければいけません。
火種の消し忘れや、お灸中の患者さんの動きが火事につながる可能性もあります。
ちなみに、その火傷は鍼灸で治しました(笑)。
でも、患者さんに同じ経験をさせないよう、火灸の施術では慎重すぎるくらいでちょうどいいと思っています。
🌟まとめ|ジプシーナースとして、これからも“現場で学ぶ”
臨床実習1を振り返って感じるのは、「見学」だけでも、得られる気づきや学びは想像以上に多かったということです。
確かに、まだ2年生の段階では、学生主体で施術することはほとんどありません。
基本は指導教員の医療面接や鍼手技を見学するスタイルで、こちらから積極的に動く機会は限られています。
でも、患者さんの言葉、表情、教員の視線や鍼のリズム──そのすべてが臨床の“教材”であり、「こんなふうに治療するんだ」というリアルな現場感を肌で感じられる貴重な経験でした。
実際に学校の治療院に来院されるのは、首・肩・腰の痛みやこりを訴える患者さんがほとんど。
筋肉疲労や姿勢性の不調が多く、症状も比較的わかりやすいため、学生でも治療を組み立てやすいというメリットはあります。
一方で、Kagayaが本当に学びたい「脊髄損傷の後遺症」「発達障がい児へのアプローチ」「慢性神経疾患に対する鍼灸」などのケースには、現場でまだ出会えていません。
もちろん、学校の立地やバリアフリーの問題、そもそもの患者層の特性もあり、現時点でそういった症例に触れられないのは仕方のないことだとも感じています。
それでも、多様な教員の治療スタイルや考え方を間近で見られたことは、非常に大きな学びでした。
東洋医学をどう捉えるか、経穴をどう選ぶか、声かけや触診の手の置き方まで──治療者ごとに違う“答え”があることを知りました。
臨床実習1は、いわば“未来の自分”を探すための第一歩。
まだ完成形にはほど遠いけれど、「こんな鍼灸師になりたい」「これは真似したい」「これは違うかも」という直感的な気づきがたくさんありました。
次のステップとなる臨床実習2では、いよいよ学生主体で医療面接を行うようです。
少しずつ自分の言葉で患者さんと関わり、自分の判断で鍼の一本を選ぶ──その段階が始まると思うと、今から少し緊張もしています。
でも、看護師として現場に立ってきた経験があるからこそ、Kagayaは“対話の中にある答え”を見つける力には自信があります。
鍼灸を単なる“技術”として学ぶのではなく、患者さんの人生やストーリーに寄り添う“道具”として扱えるようになりたい──。
それが、ジプシーナースKagayaとしての目標です。
このブログを読んでいる鍼灸学生の方、あるいは医療者を目指している方がいれば、どうか焦らず、「今、自分にできること」に集中してみてください。
どんなに小さな一歩でも、続けることで必ず“臨床力”は育っていきます。
そして──
学びは、いつも現場にある。
これからも、患者さんとともに、実習の現場で学び続けていきたいと思います。
🌟臨床実習に役立つおすすめ教材3選
臨床実習を通して感じたのは、「自分で予習・復習することの大切さ」です。
教員の動きや経穴の配置を見て学ぶだけでなく、自宅でも理解を深める工夫をすることで、実習の充実度は大きく変わります。
ここでは、Kagaya自身が活用している&同級生に勧めている、臨床実習にぴったりの教材やツールを3つご紹介します。
いずれもAmazonなどで確実に購入でき、実習中の理解をグッと深めてくれるアイテムです。
📌 経穴図ポスター
自宅の壁に貼って眺めるだけでも、経絡の流れや経穴の位置が自然と頭に入ります。
特に、実習で本治・漂治を学び始めたタイミングで役立ちました。
📘鍼灸国家試験 過去問題集
実習中に出てきたキーワードや病証を、そのまま過去問で確認。
臨床での学びと国家試験対策がリンクし、記憶の定着にも◎。紙でも電子版でも入手可能です。
🩺フィジカルアセスメント ポケットガイド
「患者さんのここを見てるの、何のためだろう?」と思ったときの確認用に超便利。
看護師経験のあるKagayaには馴染み深い1冊ですが、鍼灸学生にもおすすめです。
実習で得た学びを深めるには、現場+教材のハイブリッドが最強です。
ぜひ自分に合ったツールを取り入れて、理解を「体得」に変えていってくださいね。