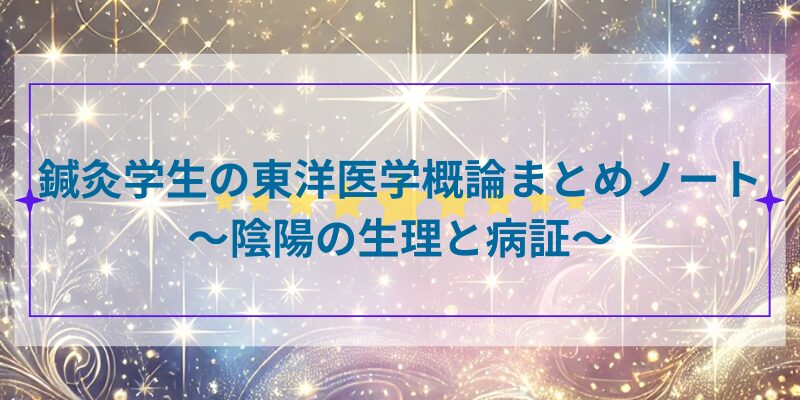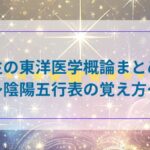こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
今回は、鍼灸学生として東洋医学を学ぶ中で、最初にぶつかる「陰陽」の考え方について、Kagaya自身のまとめノートをシェアします。
「陰陽って難しい」「漢字ばかりでわかりにくい」と感じている方に、なるべくイメージしやすく伝わるように、基本用語と病証をセットで整理しました。
これから東洋医学を学ぶ方にも、復習したい方にも、おすすめの内容です。
🌟陰陽の生理とは?|基本用語をわかりやすく整理
陰陽の「生理」とは、それぞれが担う働きのことを意味します。
まずは東洋医学でよく使われるキーワードと一緒に、ざっくり整理してみました。
- 血・津液・静(=陰):
滋潤作用(からだを潤す)と寧静作用(落ち着かせる)を担う - 気(=陽):
温煦作用(温める)と推動作用(動かす)を担う - 陰虚:
陰が不足し、潤いや静けさを保てない状態(虚熱の症状が出やすい) - 陰盛:
陰が過剰で、冷えが強く現れる状態 - 陽虚:
陽が不足して、体を温める力や活動する力が弱くなった状態 - 陽盛:
陽が過剰になり、熱っぽさや興奮などの実熱症状が出る状態 - 滋潤作用:
血や津液による潤いと滋養のはたらき - 寧静作用:
からだやこころの動きを穏やかにするブレーキの役割 - 温煦作用:
全身を温め、寒さから守るはたらき - 推動作用:
血や津液、臓腑のはたらきを動かす原動力 - 虚(きょ):
からだに必要な精気が不足している状態 - 実(じつ):
邪気(病因)が旺盛、または不要なものが溜まっている状態 - 本(ほん):
病の根本的な原因・病態 - 標(ひょう):
表に現れる症状や二次的な反応
最初は言葉に圧倒されますが、「陰=冷やす・潤す・落ち着かせる」「陽=温める・動かす」とざっくり捉えると理解しやすくなりました。
Kagayaも授業で出てくるたびに「また知らない漢字…」と格闘していましたが、今は臨床でこの考え方がとても役立つと実感しています。
🌟陰陽の病証|4タイプを症状から理解しよう
東洋医学では、陰陽のバランスが崩れた状態を「病証」としてとらえます。
ここでは、鍼灸の授業でも頻出の「陰虚・陰盛・陽虚・陽盛」という4つのパターンについて、それぞれの特徴や見分け方を症状ベースでまとめてみました。
🔥陰虚|潤い不足でほてりや虚熱が出る
陰の機能が低下することで、体を冷やしたり潤したりする力が不足し、結果的に熱がこもったような症状(虚熱)が出ます。
- 虚熱(からだの奥の熱)
- 熱感は局所的(のぼせ、手足のほてりなど)
- 頬の紅潮、盗汗(寝汗)、体が痩せていく
- 舌質:赤い 舌苔:少ない 脈:細くて速い
❄️陰盛|冷えが強く出る寒実タイプ
寒の邪気が体に多すぎると、「陰が盛んな状態」となり、冷えがつらく感じられるようになります。
- 寒気が強く、四肢の冷え・顔面蒼白
- 腹痛・下痢・小便が透明で多い
- 気虚をともなう場合:疲れやすさ・自汗・息切れ・食欲不振
- 脈:弱く沈んでいる
❄️陽虚|温める力が弱くて冷えや疲れが出る
陽の機能(温める力)が不足しているために、慢性的な冷えや体のだるさが起こります。
- 寒がり・四肢の冷え・顔色が白い
- 下痢・尿が多くて透明
- 痛み(冷えると悪化)・疲れやすい
- 舌質:淡い 舌苔:湿っている 脈:遅くて弱い
🔥陽盛|熱が過剰で広範囲に症状が出る
陽が過剰になると、体にこもるような強い熱(実熱)があちこちに現れます。
- 全身的な発熱・顔の紅潮・口渇・冷たい飲み物を好む
- 多弁・怒りっぽい・便秘・尿が少なく濃い
- 舌質:赤く 舌苔:黄色 脈:速くて力強い
こうして並べてみると、同じ「熱」や「冷え」の症状でも、その背景にある陰陽の状態によってアプローチが異なることがよくわかります。
Kagaya自身も、授業や実習で「なんでこの症状が出てるんだろう?」と悩んだときに、この4つの視点に立ち返るとスッキリ整理できるようになりました。
🌟陰証と陽証の見分け方|東洋医学的な観察ポイント
陰陽の病証を見分けるときには、症状だけでなく、舌の色や声の調子、脈の強さなど、五感を使った観察がとても重要になります。
ここでは「陰証」と「陽証」の違いを表にまとめてみました。
実際の臨床や勉強のときに、照らし合わせて使えるようにしてあります。
| 観察項目 | 陰証の特徴 | 陽証の特徴 |
|---|---|---|
| 顔色 | 明るく紅潮(血色良い) ※黄疸は明るい黄色 | 暗く黒ずむ・紫色がかる ※黄疸は暗黄色 |
| 舌の色 | 淡い〜明るい赤 | 赤みが強く青紫を帯びる |
| 尿の色 | 濃く、短いことが多い | 淡く、長い・多い |
| 腫れの色 | 赤く腫れる | 色の変化少ない/青暗色 |
| 腫れの質 | 適度に硬い | 極端に硬い/軟らかすぎる |
| 腫れの形 | 高く盛り上がる | 平坦・凹み気味 |
| 浮腫(むくみ) | 押して戻る(弾力あり) | 押すと凹んで戻らない |
| 声の特徴 | 大きな声、話が多い | 声が弱く、話したがらない |
| 痛みの感じ方 | 押すと悪化する | さする・押すと楽になる |
| 脈の様子 | 力強く、速い | 力弱く、遅い |
| 病気の性質 | 急性が多い | 慢性が多い |
こうして一覧で見ると、陰証は「内側が充実・実熱寄り」、陽証は「虚・冷え傾向」というイメージがつかみやすくなります。
Kagayaも実際の臨床で、声の調子や顔色、むくみの状態を見るだけでも、どちらに傾いているかがなんとなくつかめるようになりました。
患者さんとのやり取りの中で、五感を総動員して観察する力を養っていくことが、東洋医学を使いこなす第一歩です。
▼あわせて読みたい:五行論とセットで学ぶと、さらに理解が深まります。
🌟参考文献|Kagayaおすすめの東洋医学入門書
ここでは、Kagayaが鍼灸学校に入学する前に読んでいた本や、授業の理解を助けてくれた入門書をご紹介します。
はじめは漢字だらけで「何が書いてあるのか…」と正直くじけそうになりましたが、授業と並行して読むうちに「こういうことか!」と少しずつ理解できるようになりました。
今では「授業の補助資料」としても「独学で東洋医学を始めたい人」にとっても、とても役立つ本だと感じています。
『中医学の仕組みがわかる基礎講義』
講義形式で話が進むスタイルで、読みやすく図も豊富。「システマチックな思考」が苦手な人でも理解しやすい構成になっています。
『オールカラー版 基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書』
視覚的にとても分かりやすく、全ページフルカラー。初学者にやさしい1冊です。学校の課題やテスト対策にも活躍しました。
『最新カラー図解 東洋医学 基本としくみ』
図解中心で、流れをつかみやすい構成です。短時間で要点を押さえたい方におすすめ。
どれも東洋医学を学ぶうえで、「基礎づくり」にぴったりの1冊です。内容の重なりもあるので、まず1冊選んで手にとってみてくださいね。