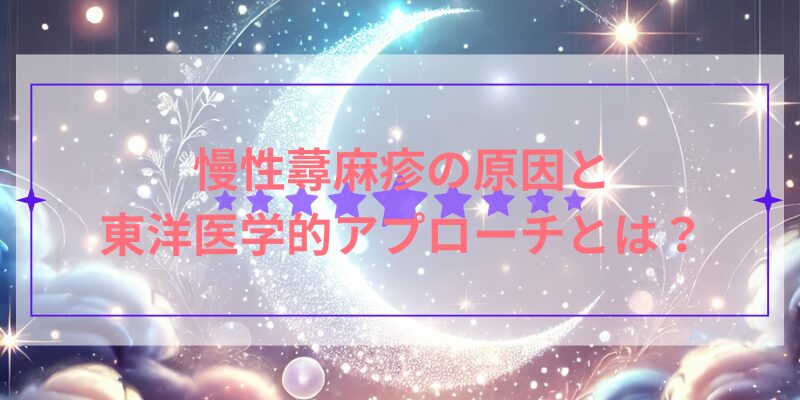こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
国家試験が終わった直後から、ほぼ毎日のように蕁麻疹(じんましん)が出るようになりました。
最初は「疲れやストレスのせいかな?」と軽く考えていたのですが、日に日に発疹の範囲が広がっていき、かゆみも強くなる一方。
しかも、症状が出る時間帯や条件が一定せず、朝起きた時や夕方、食事のあとなど、予測がつかないため生活の中で常に不安がつきまとっていました。
Kagayaはこれまで病院での勤務経験から、皮膚症状に対して西洋医学の治療の流れを理解していたので、「どうせ抗ヒスタミン薬を出されるだけだし…」という気持ちもあり、しばらくは様子を見ていました。
しかし、かゆみで夜中に目が覚める日が増え、集中力や体力にも影響が出てきたため、「これは放置できない」と感じ、皮膚科を受診することにしました。
皮膚科専門の病院は数が限られており、予約もすぐには取れず、やっと行けた日も待ち時間は2時間以上。
診察前にすでに疲れ切ってしまいました。
診断は「慢性蕁麻疹」。
原因は特定できないとのことでした。
日常的に出る発疹は、食事や環境、ストレスなど様々な要因が複雑に関与しており、検査では明確な引き金が見つからないケースが多いそうです。
Kagayaの場合も、食後に症状が出やすかったため「食物アレルギーですか?」と尋ねましたが、特定の食品に限定されていないため否定されました。
医師からは「重篤なアナフィラキシーでなければ、生活の中で気をつける程度でいい」との説明を受けました。
さらに、「身体が温まって血流が良くなると蕁麻疹が出やすいので、冷やすと良い」とアドバイスされました。
ですが、Kagayaはもともと冷え性で、体を冷やすと胃腸の不調や肩こりが悪化しやすいため、「冷やせ」という指示には少し抵抗がありました。
診察中、医師自身も「自分も慢性蕁麻疹で10年以上薬でコントロールしている」と話しており、「体質だから仕方ない」との言葉も…。
その瞬間、「医師なら体質改善しろよ!」と思うのと同時に、「西洋医学は症状を抑えることは得意でも、体質そのものを変えるのは不得手なのだな」と痛感しました。
もちろん、薬で炎症やかゆみを抑え、掻き壊しや色素沈着を防ぐことは非常に重要です。
しかし、それだけでは再発を繰り返すリスクは残ります。
そこでKagayaは、東洋医学の視点に立ち返りました。
東洋医学では、こうした「原因不明」とされる慢性蕁麻疹にも、必ず体質的な背景や生活習慣の偏りがあると考えます。
皮膚に現れた症状は、内臓の働きや血流、自律神経、免疫の状態を映し出すサイン。
たとえば冷えや湿気の滞り、胃腸機能の低下、ストレスによる「気」の巡りの停滞など、複数の要因が絡み合って症状が長引いているケースが多いのです。
Kagayaは施術の中で、耳や舌、脈、腹部の状態からこうしたサインを読み取り、体質に応じた鍼灸施術や養生法を提案します。
症状を一時的に抑えるだけでなく、再発しにくい体質に整える――それが東洋医学の強みであり、きらぼしでのケアの軸でもあります。
慢性蕁麻疹に悩む方には、「症状がある=必ず原因がある」という視点で、自分の体からのメッセージを受け止めてほしいと思っています。
そして、その原因に寄り添い、日常生活に落とし込めるケアを一緒に続けていくことで、きっと症状のない日常に近づけるはずです。
🌟西洋医学でみる慢性蕁麻疹のメカニズム
西洋医学では、蕁麻疹は肥満細胞(マスト細胞)や好塩基球といった免疫細胞が活性化し、そこからヒスタミンやロイコトリエン、プロスタグランジン、サイトカインなどの化学伝達物質が放出されることで発症します。
これらは皮膚の浅い血管を拡張させ、血管の透過性を高め、血漿成分が周囲に漏れ出します。
その結果、皮膚には膨疹(ぷくっと盛り上がった発疹)が現れ、強いかゆみを伴うのです。
急性型の蕁麻疹は食物(エビ・カニなど)や薬剤(抗生物質、解熱鎮痛薬など)、感染症(風邪、胃腸炎など)が原因で出現することが多く、原因除去と薬物治療で速やかに改善します。
一方で慢性蕁麻疹(chronic spontaneous urticaria:CSU)は、6週間以上ほぼ毎日のように発疹が出現し、検査でも明確な原因が特定できないことが多いのが特徴です。
このため「原因不明」とされがちですが、実際にはいくつかの発症メカニズムが関与していると考えられています。
🔬原因とされるメカニズム
- 免疫異常(自己免疫型):IgG抗体がIgE受容体(FcεRI)やIgE自体に結合し、肥満細胞を直接刺激。これによりヒスタミンが放出され、炎症反応が持続します。慢性蕁麻疹患者の約3〜4割に自己免疫型が関与すると報告されています。
- 自律神経の乱れ:交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、皮膚血管の収縮・拡張が不安定に。これが肥満細胞を刺激し、発疹を誘発。特にストレスや生活リズムの乱れが背景にあることが多いです。
- 腸内環境の悪化:腸管バリア機能が低下し(リーキーガット症候群)、食物抗原や細菌由来物質が血中へ侵入。免疫が過剰に反応して全身の過敏状態をつくります。善玉菌減少や腸内細菌バランスの乱れも影響します。
- 物理的刺激:温熱、寒冷、圧迫、摩擦、発汗、日光などの非アレルギー性刺激が直接肥満細胞を活性化させます。これらは「物理性蕁麻疹」として分類されることもあります。
さらに、感染症の既往、甲状腺自己抗体の存在、ホルモン変動なども慢性蕁麻疹の発症や悪化に関与することが報告されています。
これらの要因が単独で作用することもあれば、複数が重なって症状を長引かせるケースもあります。
診断は主に問診(発疹の出現パターン、持続時間、生活との関係)、身体所見(皮膚の状態や誘発テスト)、血液検査(炎症反応、甲状腺機能、自己抗体、アレルギー関連項目)などで行われます。
特定の原因が疑われる場合は食物負荷試験や除去試験、皮膚プリックテストなどを行うこともありますが、慢性型では特定に至らないことが多いです。
治療の基本は第二世代抗ヒスタミン薬の定期内服で、効果が不十分な場合は用量増量や薬剤変更、H2ブロッカーやロイコトリエン拮抗薬の併用が検討されます。難治例ではオマリズマブ(抗IgE抗体)、シクロスポリンなどの免疫抑制薬、生物学的製剤が選択肢になります。
これらの治療は、発疹と痒みを抑え、生活の質(QOL)を改善することを目的としています。
ただし、西洋医学的治療はあくまで「症状をコントロールすること」が中心で、発症しにくい体質に変えることまでは得意ではありません。
薬で炎症を抑えることは大切ですが、背景にある免疫や自律神経、腸内環境の乱れを整えるには、生活習慣や食事、ストレスケアなどの併用が不可欠です。
そこで、Kagayaは西洋医学の利点を活かしながら、東洋医学の体質改善アプローチを組み合わせることで、慢性蕁麻疹の根本改善を目指しています。
🌟東洋医学でみる慢性蕁麻疹のメカニズム
東洋医学では、慢性蕁麻疹は単なる皮膚のアレルギー反応ではなく、体内の気・血・水の巡りの乱れや、外から侵入する「風(ふう)」「湿(しつ)」「熱(ねつ)」などの邪気が皮膚に影響して発症すると考えます。
皮膚は「肺」の機能と密接に関わり、肺は外界からの刺激や病邪に対する防御を司ります。
また、消化吸収を担う「脾胃」や、情動や自律神経バランスと関係する「肝」、体の根本的なエネルギーを蓄える「腎」も、蕁麻疹の発症や悪化に関与します。
したがって、東洋医学では皮膚の状態だけでなく、全身の機能バランスを包括的に診ていきます。
🍃主なパターンと体質分類
- 風熱(ふうねつ)型:赤みが強く、熱感を伴い、発疹が急に広がるのが特徴。春先や初夏など、気温が上がる時期や、辛い物・アルコール摂取後に悪化しやすい。治法は清熱・疏風で、代表的な経穴は曲池、合谷、風池など。漢方では消風散、銀翹散などを用いることが多い。
- 風寒(ふうかん)型:発疹が白っぽく、寒冷刺激や冷たい風に当たることで悪化。冬場や冷房環境での発症が目立つ。温陽・発汗が必要で、大椎、風門、足三里などを温灸で温めると良い。漢方では麻黄附子細辛湯などが用いられる。
- 湿熱(しつねつ)型:皮膚がベタつき、汗っかきで、むくみや軟便、下痢傾向を伴うことが多い。梅雨や湿度の高い時期に悪化しやすい。利湿・健脾を目的に陰陵泉、脾兪、中脘などを使う。漢方では竜胆瀉肝湯や茵蔯蒿湯が選ばれることがある。
- 血虚風燥(けっきょふうそう)型:乾燥肌で粉を吹くような質感があり、かゆみが夜間に悪化する。慢性的な栄養不足、月経過多、出産後、更年期など血不足の状態で出やすい。補血・潤燥のため三陰交、血海、膈兪などを使い、漢方では当帰飲子や四物湯などが有名。
これらのタイプは単独で出ることもあれば、風熱+湿熱、血虚+風燥など複合的に絡み合うことも少なくありません。
そのため、東洋医学では問診・舌診・脈診・腹診などの診察法を組み合わせて「弁証(べんしょう)」し、その人の今の状態に最も合う治療方針を立てます。
例えば、舌が赤く苔が黄色ければ熱が優勢、苔が厚く湿っていれば湿邪が強いと判断します。
治療は、鍼灸で経絡の流れを整え、余分な熱や湿を取り除き、必要な気血を補うことを目的とします。
加えて、漢方薬で内側から体質を変え、食事や生活習慣の改善(養生)で再発を防ぎます。
例えば風熱型の人には、冷却性のある野菜や果物を適度に取り入れ、辛い物や油っこい物を控えるよう指導します。
湿熱型の人には、甘い物や乳製品、アルコールの摂取を控え、利尿作用のある食材(ハトムギ、冬瓜など)を取り入れると効果的です。
血虚風燥型には、鉄分やたんぱく質、ビタミンB群を含む食材(赤身肉、卵、ほうれん草など)をバランスよく摂るよう勧めます。
このように、東洋医学では症状の表面的な部分だけでなく、背景にある全身のバランスを見直すことで、根本的な体質改善を目指します。
慢性蕁麻疹に悩む方にとって、このアプローチは「再発を防ぎ、症状が出にくい体をつくる」ための重要な道筋となります。
🌟自律神経との関係は?
慢性蕁麻疹は「夜になると特にかゆくなる」「お風呂あがりや布団に入った時に出やすい」です。
これは、副交感神経が優位になるタイミング(リラックス時・就寝前など)に、皮膚の血管が拡張し、血流が増えることで、ヒスタミンがより強く作用するためと考えられます。
しかし背景をさらに掘り下げると、多くの場合、日中は交感神経優位のストレス状態が長時間続いていることが分かります。
仕事や育児、環境の変化、将来への不安など、精神的・身体的負荷がかかると、交感神経は過剰に働きっぱなしになり、夜に副交感神経へ急激に切り替わることで、皮膚の過敏反応が一気に表面化します。
つまり、慢性蕁麻疹は「副交感神経のせい」ではなく、日中の交感神経優位と夜間の副交感神経優位のギャップが大きすぎることが、症状悪化のカギとなっているのです。
この急激な自律神経の変動は、肥満細胞からのヒスタミン過剰放出を誘発し、皮膚のかゆみや膨疹を繰り返します。
東洋医学では、この状態を「肝気鬱結(かんきうっけつ)=ストレスや感情の抑圧で気の巡りが滞る」や「脾虚湿盛(ひきょしつせい)=胃腸機能の低下で体内に湿がたまる」といった概念で捉えます。
肝は自律神経や情動と深く関わり、気の巡りを調整する役割がありますが、ストレスによって肝気が滞ると、全身の巡りが悪くなり、皮膚症状が現れやすくなります。
また、脾は消化吸収と水分代謝を司るため、機能が低下すると「湿」が停滞し、これが皮膚の痒みや腫れを助長します。
このように、西洋医学では自律神経とヒスタミン反応の関係として説明される部分を、東洋医学では「気・血・水」の流れや「臓腑の機能低下」という視点から解釈します。
そしてどちらの視点からも共通するのは、自律神経の安定が慢性蕁麻疹の改善に欠かせないということです。
きらぼしの施術では、自律神経を整えるために耳ツボ、腹部や背部の経穴刺激を組み合わせ、心身両面からのバランス調整を行います。
また、在宅ケアでは生活リズムや呼吸法、食事の工夫についても一緒に見直すことで、日中と夜間の自律神経の切り替えをスムーズにし、蕁麻疹が出にくい身体づくりをサポートします。
🌟蕁麻疹改善のためにやるべきこと
慢性蕁麻疹の改善には、薬だけでなく日常生活での「体質改善」が重要です。
皮膚の防御力を高め、免疫バランスを整えるためには、皮膚バリアの保護、腸内環境の改善、そして生活習慣の見直しが三本柱となります。
下記の表は、実際にKagayaが臨床やセルフケア指導で推奨している方法をまとめたものです。
| 項目 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 皮膚バリアケア | セラミド配合の保湿剤を朝晩使用/肌にやさしい綿素材の衣類/低刺激の洗剤に変更 |
| 腸内環境改善 | 発酵食品(味噌・納豆・ぬか漬け)/食物繊維(ごぼう・海藻)/オリゴ糖や乳酸菌のサプリ |
| 生活習慣 | 睡眠の質を上げる/ストレスケア(深呼吸・ヨガ・お灸)/便通の見直し |
① 皮膚バリアケア
皮膚は「外界からのバリア」であり、アレルゲンや刺激物質の侵入を防ぐ第一の防御ラインです。特に慢性蕁麻疹では、皮膚の保湿不足や刺激によって症状が悪化しやすくなります。セラミド配合の保湿剤は角質層に潤いを与え、バリア機能を修復します。また、化学繊維よりも綿素材の衣類を選ぶことで摩擦や静電気による刺激を減らせます。洗剤は無添加・低刺激タイプに切り替えることも重要です。
② 腸内環境改善
腸は免疫細胞の約7割が存在する「免疫の司令塔」です。腸内環境が乱れると免疫反応が過敏になり、蕁麻疹やアレルギー症状が悪化します。味噌や納豆、ぬか漬けなどの発酵食品は腸内の善玉菌を増やし、免疫バランスを整えます。さらに、ごぼう・海藻などの水溶性食物繊維は腸内で発酵し、短鎖脂肪酸を産生して腸粘膜を保護します。加えて、オリゴ糖や乳酸菌サプリを補助的に取り入れると効果的です。
③ 生活習慣の見直し
自律神経の乱れは慢性蕁麻疹の大きな要因です。質の高い睡眠は免疫の過剰反応を抑え、皮膚の修復力を高めます。就寝前のスマホ使用を控え、照明を暖色系に変えるだけでも入眠がスムーズになります。また、深呼吸やヨガ、お灸などのリラックス法は副交感神経を整え、ストレスによる交感神経優位状態を和らげます。便通の乱れも腸内環境を悪化させるため、朝の水分補給や軽い運動も取り入れましょう。
これら3つのアプローチは単独ではなく、組み合わせて行うことで相乗効果を発揮します。
きらぼしの施術では、鍼灸や耳ツボで自律神経と免疫のバランスを整えると同時に、こうした生活習慣改善のアドバイスも行い、日常から症状をコントロールできる体質作りをサポートします。
🌟きらぼしでできる慢性蕁麻疹ケア
1. 鍼灸で自律神経と免疫のバランスを整える
蕁麻疹の発症には、自律神経の乱れや免疫の過剰反応が深く関わっています。きらぼしでは、かゆみや炎症を和らげる経穴(合谷・曲池・足三里など)を使いながら、全身のバランスを調整します。
2. 腸内環境を整える生活アドバイス
免疫の7割は腸に存在すると言われます。腸が乱れると皮膚にも影響が出やすくなります。施術では、食事内容や生活習慣についても一緒に確認し、発酵食品や食物繊維の取り入れ方、腸に負担をかけない調理法など、日常で実践できる改善策を提案します。
3. ストレスケアとリラックス法の提案
精神的ストレスは交感神経を優位にし、蕁麻疹を悪化させる引き金になります。きらぼしでは、鍼灸施術と合わせて、自宅でできる深呼吸法、お灸、軽いストレッチ、香りや音による五感刺激など、リラックス法をお伝えしています。
4. 皮膚バリアを守るケア
外的刺激から皮膚を守るために、保湿剤の選び方や塗布のタイミング、衣類・洗剤の選び方などもサポートします。とくに敏感肌や小さなお子さんの場合は、家庭でできるやさしいスキンケア方法もお伝えします。
きらぼしの特徴は、「施術だけでなく生活の改善まで伴走する」ことです。
症状を抑えるだけでなく、「出にくい体質」に変えていくことを目指します。
訪問ケアでは、ご自宅の環境を実際に拝見しながら生活動線や環境調整のアドバイスも可能です。
シェアサロン利用時には、落ち着いた空間でじっくりと施術を受けていただけます。
もし慢性蕁麻疹にお悩みで、「薬だけに頼らず体質から整えたい」と感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの生活や体質に合わせたオーダーメイドケアで、少しずつでも快適な毎日を取り戻すお手伝いをいたします。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら
🌟まとめ:慢性蕁麻疹と上手に付き合うために
慢性蕁麻疹は、薬で一時的にかゆみや発疹を抑えられても、根本から改善するには時間がかかることが多い症状です。
そのため、「治す」だけを目標にするよりも、まずは上手に付き合いながら再発しにくい体質づくりを意識することが大切です。
東洋医学では、蕁麻疹の背景に「風・湿・熱・血虚」などの体質的要因があると考えます。
これらはストレスや生活習慣の乱れ、腸内環境の悪化、皮膚バリア機能の低下などともつながっています。
つまり、日常生活を整えることが、そのまま症状の改善にもつながるのです。
日々できることとしては、以下の3つが柱になります。
- 皮膚を守る習慣:低刺激のスキンケア、保湿の徹底、衣類や洗剤の見直し
- 腸を整える食生活:発酵食品や食物繊維の摂取、加工食品・添加物の控えめ
- 自律神経と免疫の安定:質の良い睡眠、深呼吸やお灸などのリラックス習慣
もちろん、これらを完璧にこなす必要はありません。
「今日は保湿をしっかりやった」「発酵食品を一品追加した」など、小さな一歩を積み重ねるだけでも、身体は確実に変化していきます。
きらぼしでは、訪問・サロンの両方で慢性蕁麻疹の体質改善サポートを行っています。
施術だけでなく、生活の工夫や食事、ストレスケアまで含めて伴走するのが私たちの強みです。
慢性蕁麻疹は「ただ我慢するしかない症状」ではありません。
正しい知識と日々のセルフケア、そして必要な時にプロの手を借りることで、症状の頻度や強さを減らし、心地よい肌と暮らしを取り戻すことができます。
もし今、蕁麻疹に悩んでいるなら、「これ以上ひどくならないために」ではなく、「もっと快適な毎日を手に入れるために」行動を始めてみませんか?
きらぼしは、あなたの肌と心を守るパートナーとして、一歩ずつ寄り添っていきます。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら
🌟きらぼしおすすめ:慢性蕁麻疹ケアグッズ3選
本文でお伝えした「皮膚・腸・自律神経」をサポートする定番アイテムです。
Kagayaが指導現場で使い勝手が良かったもののジャンル例を挙げます。
セラミド配合保湿クリーム:入浴後5分以内に全身へ。バリア回復の要。
乳酸菌:腸の善玉菌を増やし、免疫の過敏反応を穏やかに。
お灸(せんねん灸):神門・足三里・三陰交などに。過度に熱くしないのがコツ。