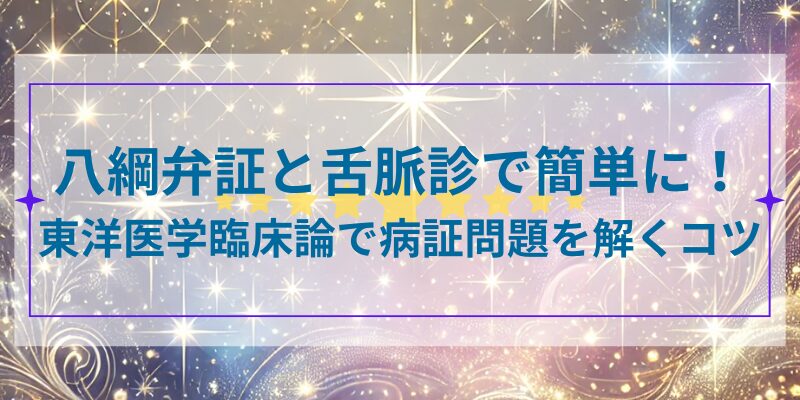🌟八綱病証とは?~東洋医学における基本病証の整理~
東洋医学における「八綱病証(はっこうびょうしょう)」とは、病の状態や特徴を分類する基本的な考え方で、診断・弁証・治療の大きな指標となる枠組みです。
八綱とは「表・裏」「寒・熱」「虚・実」「陰・陽」の4組の対概念からなり、それぞれが病の位置・性質・勢い・全体傾向を示します。
例えば、病が体表にあるか内部にあるかを「表裏」で判断し、寒い症状か熱い症状かを「寒熱」で判断します。
正気(せいき)の強さと邪気の強さのバランスを「虚実」で評価し、最終的な全体傾向を「陰陽」に統括して診断・治療を行います。
これらの八綱は、古代中国医学の臨床経験から体系化された診断フレームであり、現代の中医学や鍼灸学の基礎にも位置づけられています。
以下では各分類ごとに具体的な特徴や症状、代表的な証型をわかりやすく整理していきます。
- 表、裏(病位=病が存在する部位)
- 寒、熱(病性=病の性質)
- 虚、実(病勢=正気と邪気の盛衰)
- 陰、陽(陰=裏、寒、虚/陽=表、熱、実)
八綱病証について正しい記述はどれか。
- 表裏は八綱を統括する。
- 寒熱は疾病の性質を示す。
- 虚実は病位の深浅を示す。
- 陰陽は正邪の盛衰を示す。
八綱のうち病証を総括するのはどれか。
- 陰陽
- 表裏
- 虚実
- 寒熱
「頭痛、首と肩がこる、手足の関節が痛む、厚着をしても寒い、微熱、薄白苔、緊脈。」 最も考えられる病証はどれか。
- 裏寒
- 表熱
- 裏熱
- 表寒
八綱病証で、急な発熱と強い悪寒、関節痛があるのはどれか。
- 表寒証
- 裏熱証
- 表熱証
- 裏寒証
🌟表裏(病位)
東洋医学における「表裏(ひょうり)」とは、病が体のどの部位に存在しているかを示す分類であり、八綱弁証の第一段階となる病位診断です。
表証は体の表層部、裏証は体の内部に病邪が存在している状態を指します。
また、表でも裏でもない中間の状態を「半表半裏(はんぴょうはんり)」と呼びます。
病がどこにあるかを見極めることで、治療の方向性(発汗か、清熱か、補益かなど)が大きく変わるため、極めて重要な判断材料となります。
表証
- 特徴
- 病態が体表(皮毛・筋肉・経絡)にとどまる
- 風寒・風熱などの外感邪気が主な原因
- 外感病の初期に多くみられる
- 発症が急で進行が速く、短期間で変化する
- 主な症状
- 悪寒、発熱、頭痛、身体痛
- 鼻汁、くしゃみ、咽の違和感
- 項強(うなじのこわばり)、悪風
- 脈緊、または浮
半表半裏
- 特徴
- 邪気が表から裏へと移行する途中段階
- 正邪の闘争が体の中間(胸脇あたり)で起こっている
- 少陽病に特徴的な病位
- 主な症状
- 寒熱が交互に現れる(寒熱往来)
- 胸脇苦満(みぞおち〜脇が張るように苦しい)
- 口苦、喉の渇き、目眩(めまい)
- 脈弦(弓のように張る)
裏証
- 特徴
- 病邪が臓腑や深部に侵入した状態
- 主に内因(七情・飲食不節・労倦など)により発生
- 発症が緩やかで、病期が長く慢性化しやすい
- 主な症状
- 腹痛、便秘または下痢、食欲不振
- 舌苔の変化(厚膩・白膩・黄膩)
- 舌質の変化、脈沈
八綱病証で病位を診るのはどれか。
- 表裏
- 虚実
- 陰陽
- 寒熱
八綱病証で病位を問うのはどれか。
- 陰陽
- 寒熱
- 表裏
- 虚実
八綱病証で病位を示すのはどれか。
- 寒熱
- 虚実
- 表裏
- 陰陽
八綱病証のうちで病位が臓腑にあるのを示すのはどれか。
- 寒証
- 虚証
- 裏証
- 陽証
八綱病証で表証の症状はどれか。
- 胸脇苦満
- 食欲不振
- 慢性便秘
- 悪寒
八綱病証で表証の症状でないのはどれか。
- 浮脈
- 悪寒
- 下痢
- 発汗
半表半裏証でみられないのはどれか。
- 口が苦い
- 往来寒熱
- 胸脇苦満
- 悪風
🌟寒熱(病性)
寒熱は、東洋医学における病の「性質(病性)」を判断するための重要な概念です。
寒証(かんしょう)は「冷え」や「虚弱」などの陰性の病態、熱証(ねっしょう)は「炎症」や「興奮」などの陽性の病態を指します。
また、寒と熱が同時に存在する「寒熱錯雑証(かんねつさくざつしょう)」という複雑な状態もあり、適切な弁証が必要となります。
以下ではそれぞれの証の特徴・原因・症状を詳しく解説します。
寒証
- 特徴
- 寒冷の外邪(陰邪)の感受による外因性寒証
- または体内の陽気不足による内因性寒証(陽虚)
- 主な症状
- 悪寒、寒がり、温めると楽になる
- 顔面蒼白、口淡無味、声が小さい
- 四肢の冷え、下痢、清長尿
- 舌質は淡、舌苔は白
- 脈は遅、または沈細
- 治法:温陽散寒・補気救陽
熱証
- 特徴
- 陽邪の感受による外因性熱証(実熱)
- または陰液の消耗による内因性熱証(虚熱)
- 主な症状
- 発熱、口渇、汗多、暑がり
- 顔面紅潮、目の充血、いらだち
- 便秘、尿黄、舌紅、苔黄
- 脈数、または滑数
- 治法:清熱瀉火・養陰清熱
寒熱錯雑証
- 特徴:寒証と熱証が同時に存在する複雑な病態
- 例:
- 上熱下寒(例:顔が火照るが下肢は冷たい)
- 寒熱往来(少陽病の特徴)
- 脾胃虚寒+肝鬱化火による混在
- 治法:和解少陽・寒熱調和・標本兼治
八網病証で疾病の性質を示すのはどれか。
- 陰陽
- 寒熱
- 虚実
- 表裏
八綱で病の性質を示すのはどれか。
- 表裏
- 虚実
- 寒熱
- 陰陽
寒証でないのはどれか。
- 遅脈
- 小便は少なく赤い。
- 温かいものを好む。
- 手足の厥冷
熱証にみられないのはどれか。
- 口渇
- 月経先期
- 小便自利
- 鼾声
熱証の特徴でないのはどれか。
- 口渇
- 発汗
- 動悸
- 下痢
🌟虚実(病勢)
虚実(きょじつ)は、病気の「勢い=病勢(びょうせい)」を判断する指標であり、正気(せいき)と邪気(じゃき)の盛衰バランスを表しています。
東洋医学では「虚は補い、実は瀉する(補虚瀉実)」という治療原則があり、弁証論治の核となる概念です。
虚証とは、体内の正気が不足している状態を指し、主に慢性・消耗性の病に多く見られます。
実証は、邪気が旺盛な状態で、症状が激しく現れる急性疾患に多くみられます。
さらに、両方が同時に存在する複雑なタイプを「虚実挟雑証(きょじつきょうざつしょう)」といいます。
以下でそれぞれの証型について詳しく見ていきましょう。
虚証
- 特徴
- 正気(気・血・津液・精・陰陽)が不足
- 身体の機能が低下し、反応が鈍い
- 慢性疾患・術後・高齢者・虚弱体質などに多い
- 主な症状
- 倦怠感、疲れやすい、自汗(動かなくても汗が出る)
- 顔色が淡白、声に力がない
- 喜按(お腹を押されると楽)、脈は虚・弱・細・無力
- 舌質は淡・舌苔薄
- 治法:補気・補血・補陰・補陽など
実証
- 特徴
- 邪気(風・寒・湿・痰・瘀血など)が体内に旺盛に存在
- 身体は正気がしっかりしているため、症状が激しい
- 主な症状
- 発熱、胸腹部の脹痛・拒按(押すと嫌がる)
- 無汗、便秘、尿が少ない・黄色い
- 顔面紅潮、煩躁、脈は有力・弦・滑など
- 舌苔は厚く、黄色や膩苔が見られる
- 治法:清熱・理気・瀉下・化痰など
虚実挟雑証
- 特徴:虚証と実証が同時に存在する混在型
- 例:
- 肝陽亢進(肝実+腎虚)
- 心腎不交(心火旺+腎陰虚)
- 脾虚湿盛(脾虚による水湿の停滞)
- 治法:標本同治(急な症状を抑えつつ、体質を根本から整える)
八綱病証で病勢を示すのはどれか。
- 表裏
- 陰陽
- 虚実
- 寒熱
正邪の盛衰を診るのはどれか。
- 燥湿
- 虚実
- 寒熱
- 表裏
正邪の盛衰を示すのはどれか。
- 陰陽
- 虚実
- 表裏
- 寒熱
正邪の盛衰を示すのはどれか。
- 寒熱
- 虚実
- 表裏
- 陰陽
八綱で正気と邪気の盛衰を示すのはどれか。
- 陰陽
- 虚実
- 寒熱
- 表裏
正気の不足や衰えた状態はどれか。
- 表証
- 実証
- 虚証
- 裏証
「55歳の女性。1か月前から大腿部・下腿部の後側にだるい痛みがあり、その部位を押さえると痛みは和らぎ、気持ちが良い。」 本患者の八綱病証で適切なのはどれか。
- 虚証
- 表証
- 陽証
- 熱証
八綱病証で実証はどれか。
- 疼痛部を押すと痛みが増強する。
- 長期間微熱が続いている。
- 小便の回数が多い。
- 鈍痛が持続している。
八綱病証で実証はどれか。
- よく汗をかく。
- 便秘している。
- 体に力が入らない。
- 呼吸が浅い。
病証において虚実挟雑証でないのはどれか。
- 脾虚湿盛
- 心腎不交
- 肝陽上亢
- 風熱犯肺
🌟六経病(三陰三陽病証)
六経病(ろっけいびょう)とは、『傷寒論』に基づく古典的な弁証法で、外感病(風寒の邪)が体に侵入した際の経過や病位・病性を三陰三陽の六つに分類して示したものです。
この分類は、太陽・少陽・陽明(陽経)と、太陰・少陰・厥陰(陰経)の6つの経に対応し、病の進行や特徴を診断しやすくするための指標です。
各経に現れる症状の違いを把握することで、病の深さ・重さ・変化を見極めることができます。
六経分類早見表
| 経名 | 分類・病位 | 主な特徴・症状 |
|---|---|---|
| 太陽経 | 表証・外感初期 | 悪寒・発熱・頭痛・項強・脈浮 →風寒が体表に侵入し、衛気と戦っている段階 |
| 少陽経 | 半表半裏証 | 寒熱往来・胸脇苦満・口苦・目眩・脈弦 →邪気が表裏の中間で停滞、進退しにくい |
| 陽明経 | 裏実熱証 | 高熱・大汗・激しい口渇・便秘・潮熱・譫言・脈洪大 →陽熱が裏に入り腑(胃腸)で盛んになった状態 |
| 太陰経 | 裏虚寒証 | 食欲不振・水様便・腹満・四肢冷・脈緩遅 →脾陽虚により寒湿が生じ、消化機能低下 |
| 少陰経 | 裏虚証(寒または熱) | 寒タイプ:四肢厥冷・疲労・下痢・無欲・脈沈細 熱タイプ:心煩・不眠・口渇・尿少・舌紅・脈細数 |
| 厥陰経 | 陰陽錯雑・病の末期 | 寒熱錯雑・胸部不快・口渇・嘔吐・下痢・四肢厥冷 →エネルギーの枯渇、上熱下寒の重篤状態 |
六経弁証は、現在の診療現場ではそのまま用いられることは少なくなっていますが、病の進行プロセス・体力の強弱・邪気の位置などを理解するための教育的な基盤として重宝されています。
特に、傷寒・インフルエンザなどの外感病の弁証においては、今も有用な指標です。
六経病証について正しい組合せはどれか。
- 少陰経病 ─── 難聴が起こる。
- 厥陰経病 ─── 腰背が強ばる。
- 少陽経病 ─── 陰嚢が縮む。
- 太陰経病 ─── 咽頭が渇く。
三陰三陽病と症状の組合せで正しいのはどれか。
- 太陰病 ─── 便秘
- 少陰病 ─── 臥床を好む
- 陽明病 ─── めまい
- 少陽病 ─── 項のこわばり
三陰三陽六病位と体幹の部位との組合せで誤っているのはどれか。
- 太陽 ─── 背面の表
- 厥陰 ─── 側面の裏
- 太陰 ─── 背面の裏
- 陽明 ─── 腹面の表
三陰三陽病証で往来寒熱、胸脇苦満が現れるのはどれか。
- 少陽病
- 太陰病
- 少陰病
- 太陽病
六経弁証の少陽病証でみられるのはどれか。
- 悪風
- 高熱
- 下痢
- 口苦
六経病証で病邪が最後に達するのはどれか。
- 太陰経
- 厥陰経
- 少陽経
- 陽明経
次の文で示す傷寒論の六経病証はどれか。 「胸中の灼熱様の痛み、激しい口渇、空腹だが飲食ができない、四肢厥冷、嘔吐、下痢。」
- 厥陰病
- 太陽病
- 少陰病
- 陽明病
🌟難経六十九難(なんぎょう ろくじゅうきゅうなん)
『難経』とは、東洋医学の古典である『黄帝内経(こうていだいけい)』の要点や矛盾点を補足・解説する目的で編纂された注釈書です。
その中でも第六十九難では、五行説に基づいた治療の基本的な考え方として「母子関係による補寫法」が示されています。
これは病気の性質が「虚証」か「実証」かによって、治療の方向性(補う or 瀉する)をどの臓に向けて行うべきかを説明しており、五臓六腑の相生・相剋関係を活用した理論です。
シンプルながら応用の幅が広く、弁証論治の基礎中の基礎とも言える重要な内容です。
難経六十九難の原則
- 虚すればその母を補う
→ 本臓(病んでいる臓)が虚しているときは、その母にあたる臓を補うことで間接的に力をつける。- 例:肝が虚すれば「母」である腎を補う(腎生肝)
- 実すればその子を寫す
→ 本臓が実(過剰)であれば、子にあたる臓を瀉して力を分散させ、過剰を緩和する。- 例:肝が実すれば「子」である心を瀉す(肝生心)
この考え方のベースにあるのは、五行の「相生関係(木→火→土→金→水→木…)」です。
五臓の母子関係
- 肝(木)→「母」:腎(水)、 「子」:心(火)
- 心(火)→「母」:肝(木)、 「子」:脾(土)
- 脾(土)→「母」:心(火)、 「子」:肺(金)
- 肺(金)→「母」:脾(土)、 「子」:腎(水)
- 腎(水)→「母」:肺(金)、 「子」:肝(木)
このように、症状だけにとらわれず、「本臓・母・子」の関係性に注目して治療を行うことが、より根本的な改善を導きます。
臨床では「母子補瀉法」と呼ばれ、現代でも経絡治療や漢方処方の組み立てに応用されています。

難経六十九難の治療法則で原穴を選穴するのはどれか。
- 肺虚証
- 肝虚証
- 腎虚証
- 脾虚証
難経六十九難の治療法則で肝虚証の治療穴はどれか。
- 曲泉
- 中封
- 大敦
- 太衝
難経六十九難で心が虚しているとき、補の治療で最も適切な経穴はどれか。
- 少府
- 少衝
- 少商
- 少沢
難経六十九難の法則で脾虚証に補法を行う経穴はどれか。
- 曲泉
- 復溜
- 至陰
- 大都
難経六十九難による治療では肺が虚している時、これを補するのに最も適している経穴はどれか。
- 公孫
- 列缺
- 二間
- 太白
難経六十九難の治療で大敦穴に瀉法を行った。実していた経絡はどれか。
- 腎経
- 心経
- 脾経
- 肺経
難経六十九難で太淵と太白に補法を行うのはどれか。
- 肝虚証
- 脾虚証
- 心虚証
- 肺虚証
難経六十九難で経渠穴と商丘穴とに瀉法を行うのはどれか。
- 肝実証
- 腎実証
- 肺実証
- 脾実証
難経六十九難による補法で正しい組合せはどれか。
- 肺虚 ─── 大敦、魚際
- 脾虚 ─── 隠白、然谷
- 肝虚 ─── 中封、湧泉
- 腎虚 ─── 経渠、復溜
難経六十九難により瀉法で正しい組合せはどれか。
- 肺実証 ─── 商丘、経渠
- 脾実証 ─── 行間、少府
- 心実証 ─── 神門、太白
- 肝実証 ─── 尺沢、陰谷
難経六十九難に基づく腎虚証の治療穴の部位はどれか。
- 太谿の上方3寸でアキレス腱の前
- 太淵の上方1寸で橈骨動脈の拍動部
- 膝窩横紋の内端で半腱様筋腱と半膜様筋腱の間
- 神門の上方1寸5分で尺側手根屈筋腱の橈側
難経六十九難により腎虚の補法を行う選穴部位はどれか。
- 上腕二頭筋腱外方の陥凹部、肘窩横紋上
- 太渓の上方2寸で、アキレス腱と長指屈筋との間
- 手関節前面横紋上で、橈骨動脈拍動部
- 足内側、舟状骨粗面の下方、赤白肉際
次の文で示す経脈病証に対し、難経六十九難の治療法則を考慮して施術を行う場合、最も適切な経穴はどれか。 「顔色が黒ずむ、呼吸が苦しく咳がでる、立ちくらみ、食欲がない、寝ることを好んで起きたがらない。」
- 曲泉
- 経渠
- 大都
- 太渓
次の文で示す症状に対し、難経六十九難に基づく適切な治療穴はどれか。 「食欲がなく、腹部膨満感、下痢があり、手足に無力感がある。」
- 手掌、第5中手指節関節の近位端と同じ高さ、第4・第5中手骨間
- 足関節後内側、内果尖とアキレス腱の間の陥凹部
- 足内側、第1中足指節関節の近位陥凹部、赤白肉際
- 前腕、橈骨下端の橈側で外側に最も突出した部位と橈骨動脈の間、手関節掌側横紋の上方1寸
難経六十九難で肝実証に行間穴とともに瀉法を行う経穴はどれか。
- 中封
- 少府
- 然谷
- 大敦
肝実証で難経六十九難に基づく治療穴はどれか。
- 曲泉
- 行間
- 大敦
- 太衝
🌟六部定位脈診(ろくぶじょうい みゃくしん)
六部定位脈診とは、東洋医学における診察法「脈診(みゃくしん)」の基本的な形式のひとつです。
両手の寸口(手首の脈を触れる場所)で脈を三か所ずつ計六か所診る方法で、「左寸・関・尺」「右寸・関・尺」の計6部を観察して、それぞれに対応する臓腑や病位を判断します。
この脈診法は『難経』や『傷寒論』などの古典に基づいており、体内の五臓六腑・経絡・気血の状態を把握する重要な方法として、現在でも中医学や鍼灸臨床で幅広く用いられています。
六部脈診の部位と臓腑の対応
| 側 | 部位 | 主に対応する臓腑 |
|---|---|---|
| 左手 | 寸口(親指側) | 心・小腸 |
| 関上(中央) | 肝・胆 | |
| 尺中(肘側) | 腎(陰)・膀胱・生殖器 | |
| 右手 | 寸口(親指側) | 肺・大腸 |
| 関上(中央) | 脾・胃 | |
| 尺中(肘側) | 腎(陽)・三焦・命門 |
脈診では、これらの部位で脈の速さ・強さ・深さ・質感などを観察し、気血の巡りや陰陽の偏り、病邪の性質などを判断します。
例えば:
- 浮脈:病位が表にある、風寒・風熱などの外感
- 沈脈:病位が裏にある、内臓の病、寒湿
- 数脈:熱証、陽盛
- 遅脈:寒証、陽虚
- 弦脈:肝胆の異常、ストレス、気滞
- 滑脈:痰湿、食滞、妊娠
- 濇脈:血虚、瘀血
なお、六部脈診はあくまで「定位」診断の補助であり、四診(望・聞・問・切)全体の情報とあわせて弁証することが重要です。
特に現代では、脈だけで臓腑の病変を断定せず、体全体のバランスや変化を診るという姿勢が重視されています。
鍼灸や漢方治療では、この六部脈診により処方や取穴が決定されることも多く、患者の声なき声を感じ取る重要な診察技術と言えるでしょう。

六部定位脈診で右手関上の沈の部が虚している場合、難経六十九難に基づく治療穴はどれか。
- 曲泉
- 商丘
- 労宮
- 中渚
六部定位脈診で左手尺中の沈が虚している場合、難経六十九難に基づく配穴で適切な組合せはどれか。
- 陰谷 ─── 曲泉
- 尺沢 ─── 陰谷
- 経渠 ─── 復溜
- 中衝 ─── 大敦
六部定位脈診で左手関上の沈が虚している場合、難経六十九難に基づく治療穴で適切なのはどれか。
- 太淵と太白
- 復溜と経渠
- 労宮と大都
- 曲泉と陰谷
六部定位脈診で左手尺中の沈の部が虚している場合、難経六十九難に基づく治療穴の部位はどれか。
- 足内側、第1中足指節関節内側の近位陥凹部、赤白肉際
- 下腿後内側、アキレス腱の前縁、内果尖の上方2寸
- 膝後内側、半腱様筋腱の外縁、膝窩横紋上
- 足の第1指、末節骨外側、爪甲角の近位外方1分
六部定位脈診で左手関上の沈の部が実している場合、難経六十九難に基づく治療穴はどれか。
- 少府
- 陰谷
- 経渠
- 陽輔
🌟八綱病証のまとめ
東洋医学における八綱病証(はちこうびょうしょう)は、「表裏・寒熱・虚実・陰陽」という4つの基本的な枠組みを通じて、あらゆる病態を分類・整理し、治療方針を導くための診断体系です。
国家試験でも毎年のように出題される重要テーマであり、病位・病性・病勢・全体傾向を正確に見極めることが、臨床力・応用力の土台となります。
- 表裏:病の位置(浅い or 深い)を示す
- 寒熱:病の性質(寒邪 or 熱邪)を示す
- 虚実:正気と邪気の強弱を示す
- 陰陽:他の3要素を総合した最終判断
また、これら八綱に加え、「六経病証(太陽〜厥陰)」「難経六十九難」「六部定位脈診」などの診断法を併用することで、より具体的かつ実践的な弁証論治が可能となります。
学習時のポイントとしては、以下の3点が重要です。
- 各病証の定義と主症状を語呂やイメージで覚える
- 実際の臨床場面でどのように使うかを意識する
- 虚実や寒熱が複雑に混在するパターン(虚実錯雑など)にも慣れておく
しっかりと基礎を押さえておくことで、臨床判断のスピードと正確さが格段に上がります。
鍼灸師・東洋医学従事者としての第一歩に欠かせない内容ですので、時間をかけて理解を深めていきましょう。