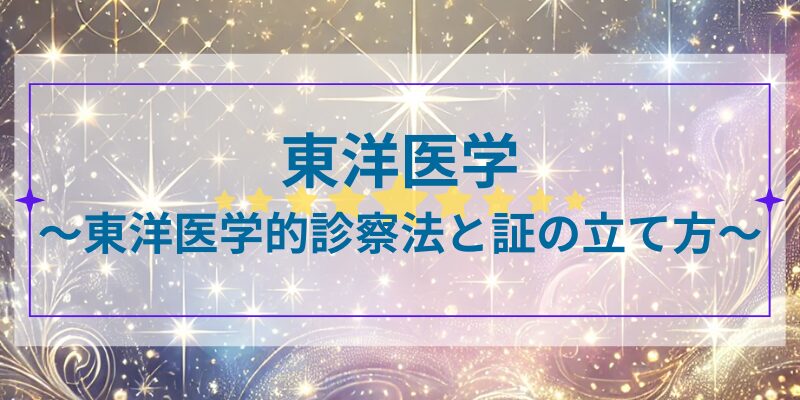🌟四診とは?東洋医学の診察の基礎
東洋医学では、病を診断するうえで「四診法(ししんほう)」と呼ばれる独自の診察法を用います。
これは「望診・聞診・問診・切診」の4つから構成され、それぞれ五感を駆使して患者の状態を把握します。
現代医学のような検査機器に頼らず、人間の感覚を最大限に生かした診断法です。
- 望診(神技):視覚による診察。顔色、皮膚、舌、爪、姿勢、表情などを観察します。
- 聞診(聖技):聴覚と嗅覚による診察。声のトーンやにおいから内臓の状態を読み取ります。
- 問診(工技):対話による診察。症状や生活習慣、既往歴を丁寧に聞き出します。
- 切診(巧技):触覚による診察。脈診や腹診を通じて体内の状態を把握します。
四診によって得られた情報を統合し、「証(しょう)」を立てることで、東洋医学的な治療方針が決定されます。
証とは、患者の体質や病態を示す診断名のようなものであり、たとえば「脾気虚」「肝鬱気滞」などと表現されます。
四診について正しい組合せはどれか。
- 切診 ─── 口臭
- 望診 ─── 舌苔
- 問診 ─── 脈状
- 聞診 ─── 痛み
四診について誤っている組合せはどれか。
- 問診 ─── 食欲
- 望診 ─── 五色
- 聞診 ─── 圧痛
- 切診 ─── 脈状
四診のうち脈の状態を診るのはどれか。
- 望診
- 切診
- 問診
- 聞診
西洋医学の触診に相当するのはどれか。
- 聞診
- 問診
- 望診
- 切診
四診で実の反応はどれか。
- 経脈に沿った陥凹
- 按圧すると軽減する疼痛
- 診察者の指を力強く押し上げる脈
- 力のない声
🌟望診の基本と臨床応用
望診とは、患者の身体全体を視覚的に観察する方法です。
表情、皮膚、舌、体格、動作、姿勢など、多岐にわたる情報を得ることができます。
特に顔色や舌の状態は、気血津液や五臓六腑の状態を反映しているため、重視されます。
まず、全体的な印象を観察します。
目に力があり、顔に艶と潤いがある場合は「神」が充実しており、回復の見込みがあるとされます。
一方、顔色がどんよりし、目の輝きが乏しい場合は、予後不良の可能性があります。
- 光沢があって、明るく潤っている場合は予後良好
- 光沢がなく、艶がなくなっている場合は予後不良
| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 |
| 五色 | 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 |
| 五華 | 爪 | 面・色 | 唇 | 毛 | 髪 |
| 五体 | 筋 | 血脈 | 肌肉 | 皮 | 骨 |
| 五官 | 目 | 舌 | 口 | 鼻 | 耳 |
- 三余
- 血余:髪
- 骨余:歯
- 筋余:爪
このように、観察した部位や色からどの臓が関係しているかを読み取ります。
また、「三余」と呼ばれる爪・歯・髪の異常も病変の手がかりになります(筋余=爪、骨余=歯、血余=髪)。
舌診も望診の一種として非常に重要です。
舌体の色や形、苔の状態は、寒熱や気血のバランス、臓腑の異常を反映します。
舌尖の紅は心火、舌辺の紅は肝火、舌全体が淡い場合は気血不足を示します。
舌診
- 舌質
- 舌体の色や形
- 気血の盛衰や寒熱などが反映
- 舌苔
- 舌色:寒熱の状態
- 舌質:水液の盛衰、病邪の性質
- 淡→虚証
- 白→寒証
- 紅、黄→熱証
- 紫、暗→瘀血、寒邪
- 胖、歯根→脾の虚
- 舌辺紅→肝
- 紅舌、少苔→陰虚
| 舌の部位 | 臓腑 |
| 舌根 | 腎 |
| 舌中 | 脾・胃 |
| 舌辺 | 肝・胆 |
| 舌尖 | 心・肺 |
| 色 | 状態 |
| 淡紅 | 正常、表証 |
| 淡白 | 気血不足、寒証 |
| 紅 | 実熱、陰虚による熱証 |
| 青 | 実寒、陽虚、寒凝血瘀 |
| 紫 | 血瘀 |
このように望診では、病の兆候をいかに早期に捉え、全体像を読み解くかが重要です。
神技(望診)で診るのはどれか。
- 顔色
- 筋硬結
- 呼吸音
- 関節痛
糖尿病患者に対する四診とその内容の組合わせで正しいのはどれか。
- 望診──健康診断の結果をみせてもらった。
- 聞診──1か月間の食生活の状況を聞いた。
- 問診──息に甘い香りを感じた。
- 切診──足背動脈の減弱を認めた。
望診で得られる所見はどれか。
- 寒熱
- 五音
- 脈状
- 舌質
舌診で舌尖部に配当されるのはどれか。
- 肝
- 脾
- 心
- 腎
腎を診る舌診部位はどれか。
- 舌辺
- 舌中央
- 舌尖
- 舌根
舌診部位と臓腑の組合せで正しいのはどれか。
- 舌根部 ─── 肺
- 舌辺部 ─── 腎
- 舌尖部 ─── 心
- 舌中部 ─── 肝
舌診部位と臓腑との組合せで正しいのはどれか。
- 舌根部 ─── 心
- 舌辺部 ─── 肺
- 舌中部 ─── 脾
- 舌尖部 ─── 腎
顔面と舌の五臓配当で正しい組合せはどれか。
- 右の頬 ―――― 舌辺
- 鼻 ―――――― 舌尖
- 左の頬 ―――― 舌中
- オトガイ ─── 舌根
陰虚による舌質の色はどれか。
- 紅舌
- 淡紅舌
- 紫舌
- 淡白舌
次の文で示す患者の病証でみられる舌象はどれか。 「43歳の男性。主訴は頭痛。めまい、目赤、胸脇苦満を伴う。最近、仕事上のストレスを抱えている。」
- 紅舌
- 淡白舌
- 紫舌
- 青舌
目のかすみ、めまい、脇部の隠痛および手足のふるえを呈する病証で最も考えられる舌質はどれか。
- 紅舌
- 紫舌
- 淡紅舌
- 淡白舌
「55歳の女性。皮下出血しやすく、皮膚はかさつき、腹が脹る。月経時に血塊を伴う。」 この患者の舌証として正しいのはどれか。
- 胖舌
- 灰苔
- 紫舌
- 燥苔
「45歳の男性。首や肩のこりが強く、寝汗をよくかき熟睡できない。便が硬く排便しづらい。」 この患者の舌の所見と脈状との組合せで正しいのはどれか。
- 紅舌 ─── 細脈
- 胖舌 ─── 結脈
- 痩舌 ─── 滑脈
- 淡舌 ─── 弦脈
陰虚にみられる舌苔はどれか。
- 膩苔
- 潤苔
- 厚苔
- 少苔
陰虚にみられる舌苔はどれか。
- 膩苔
- 厚苔
- 潤苔
- 少苔
舌診で気陰両虚の所見はどれか。
- 舌の色が青紫色である。
- 舌下静脈の怒張がある。
- 舌苔が剥落している。
- 舌体が腫れて大きい。
次の文で示す患者の病証で最もみられる舌所見はどれか。 「54歳の女性。主訴は肩こり。2週間前に感冒にかかり咳が強く出た。現在も透明な鼻汁が出て痰が多い。」
- 剥落苔
- 膩苔
- 黄苔
- 燥苔
🌟聞診の重要性と診断ポイント
聞診(ぶんしん)は、聴覚と嗅覚を使って患者の病態を診る東洋医学の診察法です。
現代の医学における「聴診」とは異なり、患者の声や呼吸、体臭・口臭など、身体から発せられる自然な情報を重視します。
聞診は患者との距離を縮め、症状の裏にある本質的な変化を見抜く重要な手段です。
- 聴覚
- 音声、呼吸音、咳、あえぎ、うめき、言葉の力強さやかすれ具合
- 嗅覚
- 体臭、口臭、排泄物や分泌物のにおい
たとえば、呼吸が浅く弱々しい場合は肺の気虚や腎陽虚が、反対に声が大きく激しい咳であれば、外感風熱や肺実証などが疑われます。
| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 |
| 五音 | 角 | 微 | 宮 | 商 | 羽 |
| 五声 | 呼 | 笑 | 歌 | 哭 | 呻 |
| 五臭 | 羶(臊) | 焦 | 香 | 腥 | 腐 |
聞診で用いる感覚はどれか。
- 味覚
- 触覚
- 視覚
- 嗅覚
聞診で診るのはどれか。
- 排泄物の色
- 悪寒発熱
- 声の変化
- 脈状
聞診で診るのはどれか。
- 耳鳴がする。
- 顔色が青い。
- 圧痛、硬結がある。
- 声に力がない。
聞診で診るのはどれか。
- よくしゃべる。
- 眠れない。
- 食欲がない。
- 耳鳴りがする。
聞診で診るのはどれか。
- 意識状態
- 舌の色
- 体温
- 口臭
聞診で診るのはどれか。
- 五香
- 五味
- 五主
- 五液
聞診で診るのはどれか。
- 五悪
- 五香
- 五主
- 五味
患者の体臭を診るのはどれか。
- 望診
- 聞診
- 問診
- 切診
五香を診るのはどれか。
- 望診
- 聞診
- 切診
- 問診
嗅覚によって診る方法はどれか。
- 問診
- 望診
- 切診
- 聞診
次の文で示す患者の病証で最もみられる症状はどれか。 「42歳の女性。主訴は月経周期の乱れ。子どもの面倒をみながらの在宅勤務でイライラすることが多い。」
- 太息
- 短気
- 噴嚔
- 呵欠
🌟問診のポイントと見極め方
問診(もんしん)は、東洋医学の診察の中でも患者との対話を通じて情報を得る重要なプロセスです。
患者自身の主観的な訴えに耳を傾け、生活背景や体質、発症の経緯を丁寧に聞き取ることで、証を組み立てるための核心に迫ります。
五臓六腑の状態は外見からは見えませんが、言葉や症状の訴えにヒントが隠れています。
以下のような観点から丁寧に質問を重ねていくことが、的確な証の立案へとつながります。
- 寒熱を問う(寒がり・ほてり・発熱・悪寒など)
- 飲食を問う(食欲・口渇・好み・消化不良・便通の変化)
- 睡眠を問う(寝つき、眠りの深さ、夢、夜間覚醒)
- 二便を問う(大便・小便の回数、性状、色、臭い)
- 情志を問う(精神状態、ストレス、不安、怒り、憂うつなど)
たとえば、「夕方に足がむくむ」「寝汗をかく」「夢を多く見る」「怒りっぽい」などの訴えは、単なる主観的な現象に見えても、それぞれが五臓の虚実や気血の乱れを表している可能性があります。
問診では、患者の言葉をそのまま受け止めるだけでなく、その背景にある原因や病理を「弁証論治」の視点から読み解く洞察力が求められます。
問診と関連する組合せはどれか。
- 青 ─── 赤 ─── 黄
- 臊─── 焦 ─── 香
- 酸 ─── 苦 ─── 甘
- 呼 ─── 笑 ─── 歌
問診事項はどれか。
- 甘い香りがする。
- 陥下がある。
- 顔色が赤い。
- 便秘している。
問診事項はどれか。
- 表情
- 体臭
- 睡眠
- 脈
問診で診るのはどれか。
- 声に張りがある。
- 甘いものを好む。
- 顔色が赤い。
- 脈が速い。
問診で診るのはどれか。
- 脈状
- 体臭
- 体形
- 悪寒
痛みの性質と証の関係
東洋医学では、痛みの種類や性質から体内の病理状態を推察します。
どのような刺激で痛みが変化するか、痛みの表現がどうかによって、虚実、寒熱、表裏の弁証が行えるからです。
以下は代表的な分類と臨床的な意味です。
- 喜按(あんを好む) → 虚証に多い
- 拒按(触られるのを嫌う) → 実証に多い
| 名称 | 特徴 | 原因 |
| 重痛 | 重だるい痛み | 湿邪による気血の運行停滞 |
| 酸痛 | だるさを伴う鈍い痛み | 気血不足、湿邪、虚証 |
| 隠痛 | 我慢できる程度のはっきりしない痛み | 虚証(特に寒・血虚) |
問診で「どのような痛みですか?」と聞く際には、言葉の表現だけでなく、表情や押圧への反応にも注意します。
軽く押されて気持ちよさそうなら虚証、強く押すと嫌がるなら実証であることが多いです。
実痛はどれか。
- 冷やすと心地良い。
- 痛みは鈍く持続性である。
- 押えると気持ちが良い。
- 温めると痛みは和らぐ。
虚の痛みはどれか。
- 冷やすと快い。
- 赤く腫れて痛む。
- 押さえると痛みが増す。
- 温めると気持ちがよい。
だるい痛みはどれか。
- 隠痛
- 刺痛
- 酸痛
- 脹痛
はっきりとしない持続的な痛みはどれか。
- 掣痛
- 脹痛
- 重痛
- 隠痛
シクシクとした持続的な痛みはどれか。
- 脹痛
- 重痛
- 隠痛
- 刺痛
外邪と疼痛の組合せで正しいのはどれか。
- 熱邪 ─── 掣痛
- 湿邪 ─── 酸痛
- 寒邪 ─── 重痛
- 風邪 ─── 灼痛
痛みの性質と病証との組合せで誤っているのはどれか。
- 酸痛 ─── 虚証
- 刺痛 ─── 血瘀
- 重痛 ─── 湿証
- 隠痛 ─── 気滞
「31歳の女性。主訴は頭痛と肩こり。月経は不定期で月経時に頭痛が憎悪し、下腹部痛も出現する。月経血に血塊がみられ、舌下静脈の怒張もみられる。」 本患者の痛みの特徴はどれか。
- 夜間に痛みが増悪する。
- だるい感じの痛みが現れる。
- 痛む部位が移動する。
- 冷やすと疼痛が軽減する。
頭痛の部位と経絡の関係
東洋医学では、頭痛の起こる部位から関連する経絡(けいらく)を推察し、治療方針を決定します。
それぞれの経絡に沿った部位の痛みは、関連する臓腑の変調や外邪の侵入によるものであると考えられます。
経絡と頭痛部位
| 名称 | 意味 |
| 陽明経 | 前額部〜眉間にかけての頭痛 |
| 太陽経 | 後頭部〜項背部にかけての頭痛 |
| 少陽経 | 側頭部(こめかみ周辺)の頭痛 |
| 厥陰経 | 頭頂部(百会)にかけての頭痛 |
例えば、パソコン作業やスマホの長時間使用で前頭部が痛む場合、陽明経に属する経穴(例:印堂、攅竹、陽白など)へのアプローチが有効です。
また、風寒やストレスなどでこめかみや後頭部に痛みが出る場合は、太陽経・少陽経の流注を意識して治療点を選ぶと良いでしょう。
六経病証の頭痛分類で正しい組合せはどれか。
- 前頭部 ─── 太陽経頭痛
- 後頭部 ─── 少陽経頭痛
- 頭頂部 ─── 厥陰経頭痛
- 側頭部 ─── 陽明経頭痛
頭痛の部位と分類との組合せで正しいのはどれか。
- 頭頂部 ――― 厥陰経頭痛
- 前頭部 ――― 太陽経頭痛
- 側頭部 ――― 陽明経頭痛
- 後頭部 ――― 少陽経頭痛
その他
食滞について誤っている記述はどれか。
- 呑酸がある。
- 大便に酸臭がある。
- 消渇が起こる。
- 食を嫌う。
所見と病証との組合せで正しいのはどれか。
- 口淡 ───── 脾気虚証
- 口苦 ───── 脾陽虚証
- 消穀善飢 ─── 脾気虚証
- 厭食 ───── 胃寒証
一定の時刻に発熱する特徴をもつのはどれか。
- 往来寒熱
- 但熱不寒
- 壮熱
- 潮熱
「頭痛、首と肩がこる、手足の関節が痛む、厚着をしても寒い、微熱、薄白苔、緊脈。」 この患者の症状として正しいのはどれか。
- 無汗
- 泄瀉
- 口渇
- 食欲不振
次の文で示す患者の病証で最もみられる汗の状態はどれか。 「36歳の男性。主訴は咳嗽。水様の鼻汁を伴い、息切れ、倦怠感も訴える。脈は弱。」
- 盗汗
- 大汗
- 絶汗
- 自汗
陽がたかぶり、津液が蒸化されて発汗し、手足のほてりが出るのはどれか。
- 盗汗
- 戦汗
- 自汗
- 大汗
統血作用の失調でみられるのはどれか。
- 崩漏
- 秘結
- 帯下
- 陽萎
冷え症で他覚的にも冷えが認められる状態を何というか。
- 悪風
- 悪寒
- 傷寒
- 厥冷
🌟切診
切診(せっしん)とは、実際に体に触れて得られる情報をもとに病態を把握する診察法です。
東洋医学においては脈診・腹診・経穴圧痛・経絡の緊張や虚実などを調べ、体の内側の変調を読み取ります。
切診の分類
- 脈診:手首の橈骨動脈上で脈の強さ・速さ・質などを診る
- 腹診:腹部の冷え、圧痛、拍動、抵抗感などを診る
- 経穴診:ツボや経絡の圧痛、陥凹、硬結などを調べる
- 寒熱虚実:触れた際の温度、質感、張り具合から弁別する
特に腹診は、日本鍼灸において独自の発展を遂げた重要な診察法で、長野式や経絡治療など多くの流派で重視されています。
| 所見 | 考えられる状態 |
| 拍動亢進 | 肝陽上亢、瘀血など |
| 圧痛 | 実証・気滞・瘀血・炎症 |
| 陥凹(かんおう) | 気虚・血虚・寒証 |
| 硬結 | 湿痰・瘀血・冷え |
触れて冷たく感じる部位は寒証、温かく腫れている部位は熱証の可能性があります。
これらの情報をもとに、施術点の選定や治療方針を立てていきます。
切診で診るのはどれか。
- 眩暈
- 咳嗽
- 陥下
- 舌苔
切診事項はどれか。
- よくしゃべる。
- 硬結がある。
- 食欲がない。
- 顔色が悪い。
切経で按圧によって診るのはどれか。
- 硬結
- 皮膚のざらつき
- 皮膚温
- 知覚鈍麻
圧痛を診るのはどれか。
- 切診
- 聞診
- 望診
- 問診
切経で虚の反応はどれか。
- 熱感
- 不仁
- 拒按
- 緊張
切経で虚の所見はどれか。
- 緊張
- 硬結
- 不仁
- 拒按
切経による実の反応はどれか。
- 不仁
- 冷感
- 陥下
- 緊張
経穴の切経で「実」の所見はどれか。
- 湿潤
- 陥下
- 緊張
- 不仁
切経で実の反応はどれか。
- 熱感
- 陥下
- 不仁
- 皮膚のざらつき
切診でないのはどれか。
- 舌診
- 切経
- 腹診
- 脈診
腹診
| 肝病 | 臍の左 |
| 心病 | 臍の上 |
| 脾病 | 臍のあたり |
| 肺病 | 臍の右 |
| 腎病 | 臍の下 |
| 心下痞硬 | 心下部の自覚的つかえ、他覚的に硬い 心、心包の腹証 |
| 胸脇苦満 | 季肋下部に充満感がある 肝の腹証 |
| 小腹不仁 (臍下不仁) | 下腹部に力なく、フワフワして知覚鈍麻がある 腎虚の腹証 |
| 少腹急結 (小腹急結) | 左下腹部に抵抗感、硬結 瘀血の腹証 |
| 裏急 (腹裏拘急) | 腹直筋の異常なつっぱり 虚労にみられる |
腹診の所見は、東洋医学的な臓腑の偏りや気血の状態を把握する手がかりとなります。
触診による感触を「虚」「実」「寒」「熱」といった四証に照らし合わせ、治療方針の決定に役立てます。
平人の腹はどれか。
- 下腹部に抵抗がある。
- 上腹部が平らである。
- 心下部に痞えがある。
- 季肋下部に充満感がある。
腹診で誤っている記述はどれか。
- 上実下虚の腹は脾実腎虚にみられる。
- 天枢穴では大腸の異常を診る。
- 五臓診では肝の状態は臍の左側で診る。
- 胸脇苦満は心実証でみられる。
腹診において腹部中央で診る臓はどれか。
- 腎
- 脾
- 肝
- 肺
難経の腹診において臍の下で診る病はどれか。
- 腎の病
- 脾の病
- 心の病
- 肝の病
五臓の腹診で肺の臓を診る部位はどれか。
- 臍の左
- 臍の下
- 臍の右
- 臍の上
腹診で腎の臓はどこで診るか。
- 臍の左
- 臍の右
- 臍の上
- 臍の下
腎虚の腹証はどれか。
- 小腹不仁
- 小腹急結
- 心下痞鞭(硬)
- 胸脇苦満
腎虚の腹証はどれか。
- 心下痞鞭
- 胸脇苦満
- 小腹不仁
- 小腹急結
腎虚でみられる腹証はどれか。
- 心下痞鞭
- 胸脇苦満
- 少腹急結
- 小腹不仁
難経による五臓と腹診部位との組合せで正しいのはどれか。
- 肺 ─── 心下部
- 心 ─── 中胃部
- 肝 ─── 臍の左側
- 腎 ─── 臍の右側
腹証で正しい組合せはどれか。
- 心下痞硬 ─── 脾
- 小腹急結 ─── 腎
- 小腹不仁 ─── 瘀血
- 胸脇苦満 ─── 肝
胸脇苦満を示すのはどの臓の病か。
- 腎
- 肝
- 肺
- 脾
胸脇苦満を呈する臓はどれか。
- 腎
- 心
- 肝
- 肺
季肋部で診る腹証はどれか。
- 小腹急結
- 胸脇苦満
- 心下痞硬
- 臍下不仁
季肋部で診る腹証はどれか。
- 心下痞鞭
- 胸脇苦満
- 小腹急結
- 裏急
小腹不仁を示す臓の病はどれか。
- 脾
- 肝
- 心
- 腎
小腹不仁はどこで診るか。
- 肋骨下部
- 下腹部
- 臍部
- 心窩部
小腹不仁について誤っているのはどれか。
- 小腹の知覚麻痺
- 小腹の動悸
- 腎虚の腹証
- 小腹の無力空虚
心・心包の病証で多くみられるのはどれか。
- 胸脇苦満
- 裏急
- 小腹急結
- 心下痞鞭
腹証で瘀血を診る部位はどれか。
- 季肋部
- 臍部
- 心窩部
- 左腸骨窩
瘀血の腹証はどれか。
- 小腹急結
- 胸脇苦満
- 小腹不仁
- 心下痞硬
瘀血の腹証はどれか。
- 胸脇苦満
- 小腹急結
- 心下痞硬
- 小腹不仁
瘀血でみられる腹診所見はどれか。
- 小腹不仁
- 腹裏拘急
- 胸脇苦満
- 少腹急結
虚労の際にみられる腹証はどれか。
- 心下痞硬
- 腹裏拘急
- 胸脇苦満
- 少腹急結
虚労でみられる腹証はどれか。
- 心下痞鞭
- 胸脇苦満
- 少腹急結
- 裏急
次の文で示す腹証はどれか。 「季肋下部に充満感があり、肋骨弓の下縁に指を入れようとすると抵抗、圧痛がある。」
- 胸脇苦満
- 小腹不仁
- 心下痞硬
- 小腹急結
次の文で示す症例の腹診所見はどれか。 「44歳の女性。主訴は頭痛。半年前に転職し、上司との人間関係がうまくいかず気が滅入る。頭部に刺すような痛みがあり、顔のシミが目立つようになってきた。」
- 小腹不仁
- 腹裏拘急
- 心下痞鞭
- 少腹急結
次の文で示す患者の腹診所見はどれか。 「75歳の女性。半年前から膝に力が入らない。姿勢は前かがみで、1回の尿量が少なく、足がむくむ。」
- 胸脇苦満
- 虚里の動
- 少(小)腹急結
- 小腹不仁
脈診
🌿 脈診は、患者の生命力や臓腑の状態を把握する東洋医学の基本技法です。
寸口(手首)で左右それぞれ三部に分けて、浅深・強弱・速さなどを確認します。
| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 |
| 五季 | 春 | 夏 | 長夏 | 秋 | 冬 |
| 五脈 | 弦 | 洪 | 代 | 毛 | 石 |
脈状の分類は祖脈・表脈・裏脈・病脈に大別され、それぞれの性状に応じて病因・病位・虚実寒熱などを推定します。
| 祖脈 | 浮・沈・遅・数・虚・実 |
| 七表の脈 | 緊・実・浮・洪・弦・滑・芤 |
| 八裏の脈 | 微・弱・遅・緩・伏・沈・濡・濇 |
| 九道の脈 | 結・虚・長・動・細・短・牢・促・代 |
代表的な脈象とその病証
| 名称 | 特徴 | 病証 |
| 浮脈 | 軽く触れて打つ | 表証・虚証 |
| 沈脈 | 深く按じて触れる | 裏証 |
| 遅脈 | 脈がゆっくり | 寒証 |
| 数脈 | 脈が速い | 熱証 |
| 虚脈 | 力なく触れる | 虚証 |
| 実脈 | 力強く跳ね返す | 実証 |
| 滑脈 | 玉が転がるような感触 | 痰湿・食滞 |
| 濇脈 | ザラつき・停滞感あり | 血瘀 |
| 弦脈 | 弦に触れたような緊張感 | 肝胆病・痛証 |
| 緊脈 | 縄のように張る | 実寒・痛証 |
| 細脈 | 脈幅が細く、はっきり触れる | 血虚 |
| 洪脈 | 大きく広がるような脈 | 熱盛 |
| 結脈 | 不整で時々途切れる | 寒証・血瘀 |
| 緩脈 | ゆったりとした脈 | 湿証・脾虚 |
| 濡脈 | 柔らかく、細く、浮く | 湿証・虚証 |
脈状の組み合わせで弁証する例:
- 沈・遅・緊 → 寒証
- 浮・数 → 熱証
- 虚・細 → 虚証・血虚
- 滑・濡 → 湿証
- 濇・結 → 血瘀
- 弦・緊 → 肝胆病・痛証
脈について正しい記述はどれか。
- 人迎気口脈診は経絡病証を診る。
- 陰脈、陽脈は粗脈である。
- 左手の関上の脈は肝・胆を診る。
- 弦脈、緊脈は陰脈である。
脈について誤っている記述はどれか。
- 祖脈には数脈がある。
- 四季に応じる脈には弦脈がある。
- 八裏の脈には結脈がある。
- 七表の脈には実脈がある。
脈についての記述で誤っているのはどれか。
- 虚里の動で腎の働きを診る。
- 臍下丹田の動悸で先天の原気を診る。
- 四季の移り変わりに応じて変動する。
- 祖脈は脈状の基本である。
左乳下で触れる脈はどれか。
- 腎間の動悸
- 虚里の脈
- 胃の気の脈
- 虎口三関の脈
実熱証で診られる脈状はどれか。
- 虚
- 数
- 沈
- 細
虚証でみられるのはどれか。
- 滑脈
- 緊脈
- 細脈
- 洪脈
力がなく細い脈の状態を何というか。
- 虚脈
- 浮脈
- 実脈
- 数脈
珠をころがしたような脈はどれか。
- 弦脈
- 洪脈
- 滑脈
- 緩脈
弱々しく細く指に感じられる脈状で虚証にみられるのはどれか。
- 滑脈
- 弦脈
- 洪脈
- 濡脈
「咽喉の閉塞感、怒りっぽい、抑うつ、胸脇苦満」 最も考えられる脈状はどれか。
- 濇脈
- 濡脈
- 結脈
- 弦脈
七表の脈でないのはどれか。
- 弦脈
- 実脈
- 遅脈
- 浮脈
八裏の脈はどれか。
- 濡脈
- 緊脈
- 結脈
- 滑脈
八裏の脈はどれか。
- 短脈
- 緊脈
- 伏脈
- 代脈
九道の脈はどれか。
- 細脈
- 浮脈
- 弦脈
- 遅脈
四季と脈状との組合せで誤っているのはどれか。
- 春 ─── 緩脈
- 秋 ─── 毛脈
- 冬 ─── 石脈
- 夏 ─── 洪脈
季節と脈状との組合せで正しいのはどれか。
- 冬 ─── 毛脈
- 秋 ─── 石脈
- 春 ─── 緩脈
- 夏 ─── 洪脈
「56歳の男性。主訴は食欲不振。腹部の痞えや膨満感、重痛を伴う。口が粘る、口苦、臭いの強い下痢がみられる。」 本患者の病証でみられる脈状はどれか。
- 濇脈
- 滑脈
- 結脈
- 細脈
次の文で示す患者の病証でみられる脈診所見はどれか。 「52歳の男性。主訴は腰痛。不眠や手足のほてりを伴う。仕事の疲れがたまると眩暈や盗汗が起こる。」
- 細脈
- 弦脈
- 緊脈
- 滑脈
「31歳の女性。主訴は頭痛と肩こり。月経は不定期で月経時に頭痛が憎悪し、下腹部痛も出現する。月経血に血塊がみられ、舌下静脈の怒張もみられる。」 本患者の病証でみられる脈状はどれか。
- 絹糸のように細くて力があり、按じて左右に移る脈
- 弾力に富み、琴の弦を按じるような脈
- ざらざらとして渋滞したような脈
- 浮いていて細軟の脈
次の文で示す患者の病証で最もみられる脈状はどれか。 「43歳の男性。主訴は便秘。1週間前に風邪を引き、その後、口渇が強くなり発汗も多くなった。午後3時から5時くらいまで体温が高くなる。」
- 弦脈
- 濡脈
- 緩脈
- 洪脈
次の文で示す患者の病証で最もみられる脈状はどれか。 「45歳の女性。主訴は膝痛。10日前に転倒して膝を打撲した。現在も膝内側が腫れて痛み、夜間も痛む。」
- 洪脈
- 濇脈
- 滑脈
- 濡脈
汗と脈状の組合せで正しいのはどれか。
- 手足心汗 ――― 細脈
- 大汗 ――― 滑脈
- 無汗 ――― 濇脈
- 戦汗 ――― 結脈
祖脈に含まれるのはどれか。
- 数脈
- 長脈
- 細脈
- 弱脈
祖脈でないのはどれか。
- 数脈
- 遅脈
- 浮脈
- 大脈
脈診で脈状をみるのはどれか。
- 六部定位脈
- 人迎脈口
- 祖脈
- 三部九候
季肋部に充満感があり、按圧すると抵抗や圧痛がある場合の脈状はどれか。
- 促脈
- 洪脈
- 濡脈
- 弦脈
一呼吸に六動以上の脈はどれか。
- 数脈
- 浮脈
- 沈脈
- 実脈