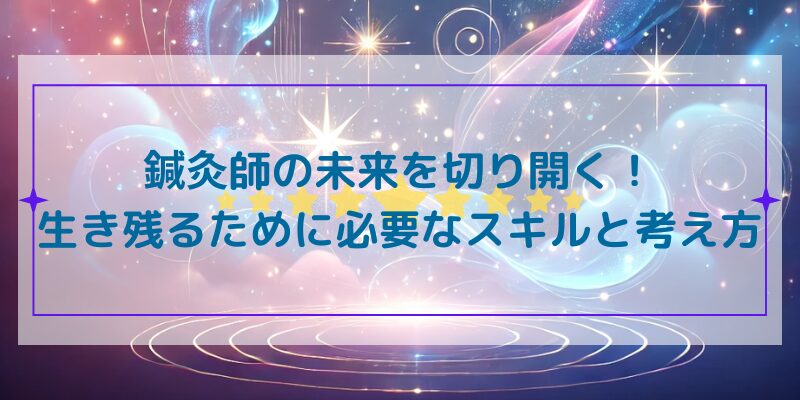🌟鍼灸師として生き残れる人はどんな人?国家資格だけでは足りない理由
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
『葬送のフリーレン』という漫画をご存じですか?
その中に出てくるゼーリエというキャラクターの言葉が、国家資格を目指す私たちにも通じるな~と思ったのです。
「一級魔法使いになった自分の姿が想像できているかどうか」
これは、ただのフィクションの中のセリフではなく、本質をついた問いです。
鍼灸師を目指す学生にとっても、「国家資格を取った後に、鍼灸師としてどんな姿で働いているのか」を具体的に想像できるかどうかは、とても重要な要素だと思います。
国家試験に合格することは、ゴールではありません。
むしろスタートラインです。
しかし、実際にはこのスタートラインに立った人たちのうち、3年後にも鍼灸師を続けている人は、クラスで1~2人程度だとも言われています。
それだけ離職率が高いという現実があります。
なぜ、せっかく3年間も勉強して国家資格まで取ったのに、鍼灸師を続けられない人が多いのでしょうか?
国家試験に受かるための努力はもちろん大切です。
でも、その後に待っているのは「技術職」+「対人支援職」+「経営感覚」まで求められる、なかなかシビアな世界です。
資格を取ることよりも、資格を取った後にどう生き残っていくかのほうが、ずっと大切なテーマなのです。
Kagayaもまだ国家試験には合格していませんが、「鍼灸師としてどんな風に仕事しているか」は常に具体的に想像しています。
患者さんの声を聴き、触れて、寄り添う。
看護師の経験も活かして、ただ「ツボを取る」だけじゃない、一人ひとりに合わせたケアを提供していく姿です。
この記事では、そんなKagayaの目線で「なぜ鍼灸師として続けられない人が多いのか?」を掘り下げ、鍼灸師として生き残るために必要なスキルや考え方について、現実ベースでお話ししていきたいと思います。
鍼灸の道をこれから進もうとしている方、すでに悩みながら現場で働いている方、ぜひ最後まで読んでみてください。
きっと、あなたの未来に役立つヒントがあるはずです。
🌟給料や待遇が悪い現実をどう乗り越えるか?
鍼灸師の国家資格を取得した多くの人は、まずどこかの鍼灸院や整骨院に就職するという道を選ぶと思います。
しかし、実際に働き始めて感じるのは、「給料が思っていたより安い」「福利厚生が整っていない」「労働時間が長い」などの待遇面での不満ではないでしょうか?
鍼灸師は医師のように診療報酬点数が高いわけでもなく、保険治療に頼った経営をしているところでは、1回あたりの施術料が1,600円程度と、かなり低単価です。
1日10人診ても16,000円。それをスタッフ全員に払えるほどの利益が出るかと言えば、現実はかなり厳しいです。
実際に私が見聞きした事例では、「1時間に1人を丁寧に治療しても、10人をマッサージのように流しても、時給はほぼ変わらない」というケースがほとんどです。
つまり、現場でどれだけ頑張っても、その成果が給料には反映されにくい構造になっているのです。
特に保険診療を行っている鍼灸院では、オーナーが利益のほとんどを管理しており、雇われている鍼灸師には最低賃金に近い給与しか払われないという例も少なくありません。
訪問看護の業界も似ています。
1件あたり8,000円以上の報酬が発生していても、実際に訪問している看護師の取り分は時給換算で2,000円程度。
差額の6,000円はどこに消えているのでしょうか。
これは別に制度が悪いのではなく、中間に入っている事業者・管理者が大きな割合を取っているという現実があります。
しかし、鍼灸師は医師の指示がなくても開業できる数少ない国家資格です。
つまり「待遇が悪い」と感じるならば、自分で独立して働くことができるという強みがあるのです。
もちろん、開業には準備や覚悟が必要です。
でも、自分の裁量で報酬を決められるというのは、他の医療系国家資格にはない魅力です。
もし今、雇用されている中で「搾取されている」と感じているならば、働き方を見直してみましょう。
例えば、以下のような選択肢があります。
- 歩合制・出来高制の働き方に変える
- 業務委託契約にして、働いた分だけ報酬を得る
- 副業として自費鍼灸や出張施術を始めてみる
- 少しずつ顧客をつけてから小規模開業にシフトする
待遇に不満を持ちながらも、じっと我慢して働き続けるのはもったいないです。
今の時代、副業や自費施術、訪問ケア、SNS集客など、自分の価値を直接お客様に届ける方法はたくさんあります。
誰かのルールの中で働いて「搾取される」働き方から、自分で報酬を生み出す働き方へ。
それが、鍼灸師として生き残る第一歩だと、Kagayaは思っています。
🌟人間関係のストレスにどう向き合うか?
鍼灸師として働いていると、技術だけでなく「人間関係」という壁にぶつかることも少なくありません。
どの業界にもいえることかもしれませんが、鍼灸師の世界にも独特の人間模様があります。
たとえば、自分こそが一番うまいと信じて疑わないような自信家タイプ。
実力があるのは良いことなのですが、そういった人ほど、後輩や同僚に対して横柄な態度を取ってしまうことも。
これはあくまでもKagayaの個人的な経験や主観も含みますが、患者さんに対して横柄な態度をとる鍼灸師は、同僚や部下にもきつく当たる傾向があると感じています。
人間関係の悪化は、職場の雰囲気を悪くし、モチベーションや精神面にも大きな影響を与えます。
さらに、患者さんの感情を受けすぎてしまうタイプの鍼灸師も、心身のバランスを崩しやすいです。
特に、「感受性が高い人」「共感しやすい人」ほど、患者さんの悲しみや不安を自分のことのように背負ってしまいがちです。
一方、Kagayaは看護師としても働いてきましたが、医療業界は鍼灸業界よりもはるかに過酷な人間関係が存在します。
医師から怒鳴られ、先輩看護師からの圧を受け、患者さんやご家族からのクレームにさらされる…
「かわいらしく見えるベテラン看護師」でも、実は鋼のメンタルを持っているのが現実です。
しかし、そんな中でも長く続けていける人は、「感情を自分の中で整理する力」「適切な距離感を保つ技術」「冷静に状況を見る視点」を持っています。
これは鍼灸師にもまったく同じことが言えるのではないでしょうか。
人と関わる仕事=感情労働です。
その中で自分の心を守りながら働くには、スキルとして「感情のコントロール」を学ぶ必要があります。
また、どうしても合わない職場環境に悩んでいるなら、「環境を変える」ことも選択肢です。
たとえば以下のような工夫が考えられます。
- 少人数制の鍼灸院に転職する
- フリーランスや委託契約として働く
- 訪問鍼灸など、対人関係が限定される働き方を選ぶ
- SNSやLINEなど、オンラインでのカウンセリング・相談業務を組み合わせる
大切なのは、人間関係は完全に避けられないが、選ぶことはできるということです。
そして、他人の感情に巻き込まれずに「自分の軸」を持つこと。
これは学校では教えてくれないけれど、長く続けていくために欠かせないスキルです。
感情労働に飲まれない自分づくりを、少しずつでも始めていきましょう。
🌟卒後教育が不十分?「見て学べ」の限界と自分で学ぶ力
国家資格を取ったからといって、いきなり一人前のプロとして働けるわけではありません。
医療従事者全般にいえることですが、実践力や臨床力は、資格取得後に現場でどのように育てられるかによって大きく変わってきます。
たとえば、看護師や理学療法士などは、多くの病院や施設で新人研修制度やプリセプター制度などが整備されています。
段階的な研修プログラムに沿って、知識や技術、倫理観、接遇まで丁寧に指導される環境が一般的です。
しかし、鍼灸師の世界はそうではありません。
多くの鍼灸院や整骨院では、「見て覚える」「盗んで学ぶ」という文化が今も根強く残っており、体系化された卒後教育制度が整っていないのが現状です。
つまり、職場によって教え方・考え方・技術のスタンダードがバラバラで、「育つかどうかは運次第」になってしまうのです。
Kagayaが看護師として働いていた現場では、新人指導マニュアルやシミュレーション研修などが整備されており、「これは看護教育の進化だな」と感じていました。
一方で、鍼灸の臨床実習では「見て覚える」スタイルが色濃く残っていて、若干のカルチャーショックを受けたのを覚えています。
もちろん、勉強意欲が高く、吸収力のある人であれば、そのような環境でも成長していけるかもしれません。
しかし、教える文化のない職場で、安い給料で雑用ばかりやらされるような環境では、技術も自信も育たず、早々に辞めてしまう人が後を絶ちません。
では、どうすればいいのでしょうか?
答えはひとつ。
自分で学ぶ場所を選び、自分で学び続けることです。
今は、大学の鍼灸研究室、認定講習、オンライン勉強会、臨床セミナー、YouTubeなど、卒後に学び続ける方法はたくさんあります。
「この治療法を極めたい」「○○症状に強い鍼灸師になりたい」という目標があるなら、それに合った学び場を自分で探し、投資する必要があります。
そして、「現場で育たない」のであれば、開業しながら学ぶという選択肢もあります。
たとえばKagayaは、将来的に訪問鍼灸や療育、スヌーズレンといった要素を取り入れた形での開業を視野に入れています。
だからこそ、今のうちから経営や福祉制度、心理支援などの分野にも学びを広げて、卒後のステップアップに備えています。
「誰かに教えてもらうのを待つ」のではなく、「自分の人生は自分で設計して学び続ける」。
これが、鍼灸師として長く続けていくために必要なマインドだと、Kagayaは思います。
🌟まとめ:鍼灸師として生き残るために、自分の未来を選ぼう
ここまで、「鍼灸師として生き残るにはどうすればいいのか?」というテーマでお話してきました。
結論から言えば、自分で働き方を選べることこそ、鍼灸師という国家資格の最大の強みです。
確かに、雇用されることで一定の安定や安全は得られます。
でもその裏には、搾取構造や人間関係、育たない環境といった「辞めたくなる要素」も潜んでいます。
だからこそ、Kagayaは思います。
「開業できる資格を持っているなら、自分で開業して、自分で生き残る方法を作ったほうがいい」と。
実際に、美容スクールをちょっと通っただけの人でも、今の時代は開業できます。
それに比べて、3年間真面目に通い、国家試験を突破して、「厚生労働省公認」の資格を手にした鍼灸師が「私には無理」と思ってしまう必要はないはずです。
もちろん、開業にはリスクもあり、経営や集客、収支管理など、学ばなければならないことはたくさんあります。
でもそれらは、すべて後から学べばいいのです。
技術と経営は別物だからこそ、技術に加えて「経営脳」も少しずつ育てていけば、自分のペースで続ける道が見えてきます。
誰もが「年収1,000万プレイヤー」や「雑誌に載るカリスマ鍼灸師」になる必要はありません。
大切なのは、自分の強みやライフスタイルに合った形で、鍼灸師を続けること。
鍼灸以外のスキル(看護・介護・心理・教育・発信など)と組み合わせれば、独自の価値を生み出すこともできます。
それに、医師の指示がなければ動けない看護師や薬剤師とは違って、鍼灸師は自分で事業を起こせる自由度の高い資格です。
つまり、鍼灸師は「儲からない」のではなく、儲からない働き方を選んでいるだけなのかもしれません。
Kagayaは、鍼灸師になった自分の姿がハッキリと想像できます。
だから、どんなに道が険しくても、「続けられない理由」は見つかりません。
あなたも、今の環境に悩んでいるなら、自分の未来を「選ぶ」勇気を持ってみてください。
きっと、今まで見えていなかった道が開けてくるはずです。
🌟鍼灸師人生を支える!おすすめ実用書3選
Kagayaが自信を持っておすすめする、現役でも役立つ実用書を3冊ご紹介します。
どれも情報が確かで、すぐに活用できる内容です。
①『はじめての鍼灸マッサージ治療院 開業ベーシックマニュアル』
② みんなの臓活 - 五臓をのぞき、活かす - (美人開花シリーズ)
③ "超初心者用・鍼灸院治療マニュアル: 即効性のあるテクニック