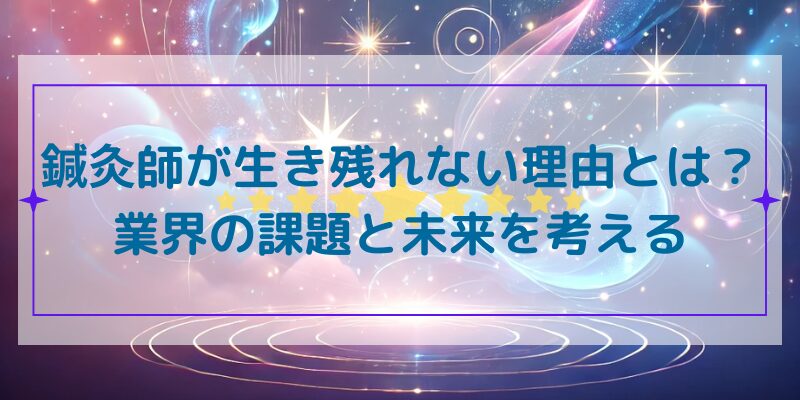🌟鍼灸師はなぜ離職率が高いのか?
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
いよいよ鍼灸学生も3年生になり、国家試験の勉強も本格化していますが、同時に「卒業後どうするか」という現実にも向き合わなければなりません。
最近、学校で担任の先生との面談がありました。
話の流れで当然のように「卒業後はどうするの?」と質問されました。
Kagayaは、現在の仕事を継続しつつ、卒業後は個人事業主として自分のスタイルで鍼灸院を立ち上げる予定です。
開業といっても、最初は副業に近い形になるかもしれませんが、自分のペースでやっていこうと思っています。
ただ、面談自体は驚くほどあっさりと終わってしまい、「あれ?この学校って、就職率とかそんなに重視してないのかな?」と少し拍子抜けしました。
思い返せば、看護学生時代は全く違いました。
学校行事として国立病院機構の病院をバスで巡るツアーに参加したこともありましたし、就職願書の管理も学校が行っていました。
一方、鍼灸の世界では先生たちが「どうせ開業するんだから、卒業してすぐ始めた方がいいよ」と軽く言う程度。
それだけ鍼灸師=開業が前提という文化が根づいているのかもしれません。
でも現実問題として、卒業してすぐに開業といっても、知識や経験、人脈も不十分なままでは経営はなかなか難しいのが実情です。
だから副業的に始める人が多いのでしょう。
やはり、鍼灸業界は看護業界とは大きく性質が異なります。
最近では、ネット上で「鍼灸師はやめた方がいい」「食べていけない」「ブラックだ」という意見を見かけることが多くなりました。
たしかに、そのような声にも一理あるのかもしれません。
でも、Kagayaから言わせれば「いやいや、看護師もやめた方がいいよ!」と正直に思うこともあります。
実際、Kagaya自身も看護師として働く中で身体を壊してしまった経験があります。
「看護師=高収入」というイメージもありますが、独身女性が一人で生きていける程度であって、決して贅沢はできません。
むしろ、介護福祉士の方が条件によっては看護師より稼いでいることもあるのです。
結局のところ、どの業界でも「働き方次第」だと思います。
資格や肩書だけでは安定も幸せも得られないというのが現実です。
しかし現実には、鍼灸師は卒業後2~3年で離職してしまう人が非常に多いと言われています。
それはなぜか?何が原因で鍼灸師を辞めてしまうのか?
Kagayaはこれまでの経験や情報をもとに、鍼灸業界に存在するいくつかの構造的な課題に気づきました。
🌟「先生」呼び文化がもたらす業界の弊害
鍼灸学生として勉強していると、東洋医学の機器や教材を扱う業者さんとやり取りする機会があります。
あるとき、東洋医学的な体表観察ができる検査機器について問い合わせをしたところ、電話口で開口一番、「Kagaya先生のお電話でしょうか?」と呼ばれました。
思わず「は?先生じゃねーし!」とツッコミかけましたが、相手は真面目にそう呼んでいる様子。
高齢の患者さんが看護師や理学療法士に対しても「先生」と呼ぶことはありますが、営業マンがこちらを「先生」と呼ぶのは正直びっくりしました。
まあ、面倒なのでそのまま「はい」と受け入れましたが、正直なところ違和感は拭えません。
昔、学校で働いていたときは子どもたちにとっては「大人=先生」だから「先生」と呼ばれるのは自然なことかもしれません。
しかし、職業名に「先生」が付くかどうかって、そんなに大事なんでしょうか?
その後、鍼灸師向けのセミナーに参加したとき、さらに驚くことがありました。
なんと、参加者同士で「○○先生、今日はお疲れさまでした」とお互いに呼び合っているではありませんか。
えっ?鍼灸師同士で「先生」呼びするのが普通なの?と困惑。
確かにセミナーのポスターにも「講師○○先生」と書いてありました。
医師が「先生」と呼ばれるのは納得ですし、学校教員も当然「先生」です。
でも、鍼灸師同士で「先生」と呼び合うってどうなんでしょうか?
しかも、それが業界全体に広まっている雰囲気。。
そんなに偉いのでしょうか、鍼灸師。。
少なくとも看護師同士で「先生」と呼び合うことは絶対にありません。
呼んだら怒られるし、むしろ嫌がられます。
理学療法士や作業療法士、介護福祉士などのリハビリ職でも、仲間内で「先生」なんて呼び合っていません。
たぶん、これは鍼灸師だけじゃなく、柔道整復師や按摩マッサージ指圧師など、いわゆる「医師ではない治療家」系の職種で見られる慣習なのかもしれません。
Kagayaにとっては、これは業界の勘違い文化のひとつに見えます。
「先生」と呼ばせることで、責任や自覚を促すためだという意見もありますが、本当にそうでしょうか?
そもそも、責任や自覚は呼び名ではなく、態度と行動で示すものです。
看護師なんて命に関わる現場で動いているのに、「先生」なんて呼ばれません。
それでも職業人としての責任感は鍼灸師の比ではないと思っています。
実際、「うちは先生呼びルールだから」といった職場もあるようで、そうした文化が鍼灸師の勘違いや自己過信を生み、最終的には医療事故にもつながりかねないと感じています。
一度、施術ミスや事故を起こした鍼灸師は、精神的に大きなダメージを受けます。
過信によるミスは、取り返しがつかないケースもありますし、再起にも強いサポートが必要です。
だからこそ、Kagayaは「先生」と呼ばれるよりも、地道に技術を磨き、患者さんと向き合うことの方が大切だと思っています。
医療職の一員として、謙虚な姿勢を忘れてはいけません。
ちなみに、数日だけ働いたことのある整体院でも、同じような「先生」文化がありました。
「自分は特別な存在だ」と思っているスタッフがいて、やっぱりどこか違和感が拭えませんでした。
鍼灸師の社会的地位を上げるには、「先生」と呼ばれることではなく、実力と信頼を積み重ねること。
それが最終的には業界の健全化にもつながるのではないかとKagayaは感じています。
🌟鍼灸学校と業界に共通する教育体制の問題点
鍼灸学校には一応、臨床実習の授業があります。
Kagayaの学校でも、6人程度のグループで順番に問診・施術・記録を行う形式で実施されています。
しかし、実際に自分が担当する機会は限られており、担当でないときは見学に回るだけです。
もちろん見て学ぶこともありますが、体験としては圧倒的に足りないと感じています。
このまま学校を卒業してすぐに開業していいのか…と思うと、正直、不安しかありません。
一方で、看護学生の臨床実習はとてもハードです。
1クール3週間の実習を何度も繰り返し、実際の現場で患者さんと深く関わりながら、命に関わる責任感を肌で学びます。
そして卒業しても、1年目の看護師は学生の延長のように扱われ、プリセプター制度のもとで先輩に付きながら学び続けます。
もちろん「先生」なんて呼ばれることはありませんし、誰もが一人前とは見てくれません。
やっと一人前と見られるのは、早くても3年目以降。
優れた教育体制を整えた病院では、「ラダー制度」や「OJT」を活用して、段階的に知識や技術、倫理観を育てています。
しかし、鍼灸師業界にはそうした卒後教育の仕組みがほとんど存在しません。
一部には大学病院での研修制度や、卒後セミナーの案内があるものの、鍼灸院そのものに新人教育を行う意識が乏しく、「明日から治療してね」と即戦力扱いされることも珍しくありません。
新人教育といっても、それはあくまで「技術指導」レベルであって、職業倫理や医療人としての振る舞いまで教えてくれる現場はごくわずかです。
いくら鍼の打ち方を教わっても、患者さんへの言葉遣いや接し方、感染管理、情報の取り扱いなどを学ばなければ、臨床の現場では通用しません。
これは看護師としての経験から痛感していることです。
実際、Kagayaはこれまでいくつかの職場を見てきましたが、人が定着しないところほど「技術だけで何とかしよう」としていて、人間教育やフォローアップが欠けている印象を受けました。
そして、業界によっては「先生」呼びの文化によって、「できる風」を装ってしまい、現実とのギャップに苦しむ新人もいます。
誰もがいきなり一人前にはなれないのに、そう振る舞わざるを得ない…
そのプレッシャーが鍼灸師の離職理由の一つになっているのではないでしょうか?
これからは、単なる「見て覚えろ」「背中を見て学べ」という昭和的な教育スタイルではなく、対話的な育成と段階的なスキル習得が求められている時代です。
新人鍼灸師が安心して経験を積み、医療人として自信を持てるような業界になってほしいと、心から願っています。
🌟ブラック治療院と低賃金のリアル
Kagayaは“ジプシーナース”なので、転職した翌日から求人情報をチェックするのが日課です。
看護師としても、そしてこれから鍼灸師としても、自分に合った職場を探すためにはアンテナを張り続けなければなりません。
世間では「看護師=高給取り」というイメージがありますが、現実はそんなに甘くありません。
Kagayaも実感していますが、独身女性が一人で生きていける程度の収入がやっとです。
時給で言えば、訪問看護や夜勤ありの施設勤務でも2,000円前後が上限。
デイサービスや老人ホームでは、時給1,300円〜1,800円が相場。
これで「高収入」といわれることに、モヤっとすることもあります。
そして、もっと驚くのが鍼灸師の求人。
ハローワークや求人サイトで条件を見ていると、「これ、学生バイトより安いんじゃない?」という待遇も多くて、思わず「鼻くそ給料かよ」と声が出てしまいます。
もちろん、保険診療をメインにしている治療院なのか、自費診療中心なのかによっても違いはありますが、全体的に報酬単価がとにかく安い。
保険が適用される鍼灸治療でも、初検料や訪問加算、往療料などを含めてせいぜい4,000〜5,000円前後。
そこから治療院の家賃・光熱費・人件費・備品代などを差し引けば、残るのはわずかな利益です。
経営を維持するためには、とにかく新患を常に獲得し続ける必要があります。
長時間開院し、土日も営業し、SNSで集客し、クーポン配布してリピーター確保…。
これを毎日続けるのはかなりの消耗戦です。
さらに問題なのが、ブラックな労働環境が蔓延していること。
労働基準法を無視した労働時間、休憩も取れない現場、残業代がつかない職場…枚挙にいとまがありません。
雇い主側も監査や社会保険料の負担を避けるため、「個人事業主扱い」にして雇用契約を結ばないケースも。
名目上は“業務委託”なので、労働者としての権利が守られません。
結果として、社会保険には加入できず、雇用保険や労災もなし。
病気やケガをしても休めない、不安定な働き方が常態化しています。
20代前半の学生や若手鍼灸師は、こうした仕組みを知らないまま、安い給料で酷使されて燃え尽きてしまう。
一方で、ある程度社会経験のある人は、この業界の異常さに気づき、早々に離れていきます。
そして最終的には、鍼灸の資格を活かすことなく、資格不要のマッサージ業界やエステ業界に流れていく…。
そんな残念な構図が出来上がっています。
鍼灸師という国家資格があっても、現場環境や報酬体系がこれでは夢を描けません。
だからこそ、鍼灸師自身が働き方や収入のあり方を見直し、より健全な道を模索していく必要があると強く感じています。
🌟鍼灸師として生き残るために必要なこと
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
これまでの章でお伝えしてきたように、鍼灸業界には「先生」呼び文化や新人教育の欠如、劣悪な労働環境など、さまざまな課題が存在します。
離職率が高いのも無理はありません。
でも、Kagayaはあえてこの世界に足を踏み入れました。
そして今も鍼灸師として「自分に合った働き方は何か?」を日々模索しながら進んでいます。
人材が定着する職場の特徴は、技術や給与だけではなく、教育体制の充実と人間関係の良さです。
技術は後からいくらでも習得できますが、職業人としてのマナーや倫理観、医療人としての自覚は、適切な指導と時間がなければ育ちません。
これを職場側が理解しているかどうかが大きな分かれ道になります。
これは介護や看護の現場でも同じで、人が定着する施設や病院には共通して明確な育成体制があります。
優秀な人材が育つ場所には、育てる文化があるのです。
一方で、鍼灸師は開業権があるため、誰にも頼らず1人でも仕事ができます。
治療院が軌道に乗れば、次は人を雇いたいと考えるようになるかもしれません。
でも現実には、教育に時間や人手を割く余裕はなく、即戦力を求めてしまうのが実情です。
その結果、「先生」と呼ばせて“できるふり”をさせるような文化が根づき、誰もが本当の意味で育たない環境になってしまっているのではないでしょうか。
師弟制度もなく、かつてのような「背中を見て学べ」という時代でもありません。
今の時代に求められるのは、対話と支援のある教育。
段階的に自信とスキルをつけていける仕組みが必要です。
社会経験の浅い若い鍼灸師たちが、いきなりブラックな職場に放り込まれて消耗してしまうことがないように。
業界全体が変わっていく必要があります。
Kagaya自身も、自分の働き方・生き方に合った鍼灸スタイルを少しずつ形にしているところです。
訪問型やシェアサロン型、小児や障がい児者への鍼灸など、ニッチだけど必要とされる分野を見つけて挑戦しています。
鍼灸師として生き残るには、業界の闇を知ったうえで、自分に合う環境・やり方・人とのつながりを選んでいくことが大切です。
情報を鵜呑みにせず、自分の目で見て、耳で聞いて、感じたことを信じていいと思います。
これから鍼灸師を目指す方、今まさに迷っている方、すでに現場で苦しんでいる方にとって、この体験と気づきが少しでも参考になれば嬉しいです。
鍼灸師の未来は、まだまだこれからです。
あなたがどんな鍼灸師になるかは、あなた自身が決められます。
🌟鍼灸師として生き残るために役立つおすすめ書籍・ツール
ここでは、Kagayaもおすすめしたい、開業準備・実践スキル・日々の帳簿管理に役立つ商品を3つご紹介します。どれも実際に販売されている信頼できるアイテムです。
📘 はじめての鍼灸マッサージ治療院 開業ベーシックマニュアル
鍼灸師・マッサージ師のための開業・経営マニュアル決定版!
保健所届出、受領委任制度、自費診療の集客まで、開業前に知っておきたい内容が網羅されています。
おすすめの人:開業を検討中の方、副業スタートを考えている方
使い方:開業前の手続きチェックリストとして活用できます。
📗 日本人が書いた中医鍼灸実践マニュアル 上巻
臨床で使える中医理論と治療の組み立て方が学べる実践書!
証の立て方・経穴の選び方・四診の活用など、明日から使える知識がぎっしり詰まった一冊です。
おすすめの人:東洋医学を深く学びたい人、自費診療の幅を広げたい人
使い方:日々の施術に迷ったときの辞書代わりに。
📒 コクヨ ノート式帳簿 A5 売上帳 チ‑52
経理が苦手でも続けやすい、手書きの帳簿ノート。
売上・支出・メモを日付ごとに記録できるA5サイズ。紙派の個人事業主に大人気。
おすすめの人:クラウド会計が苦手な人、副業から始めたい人
使い方:毎日の売上や経費を手書きで記録して確定申告に備えましょう。