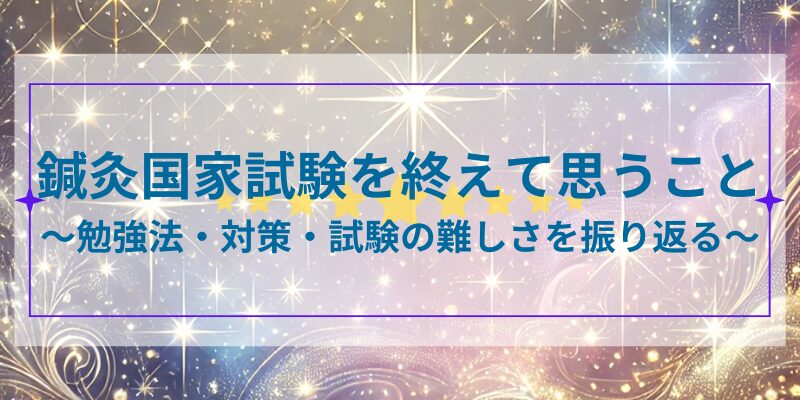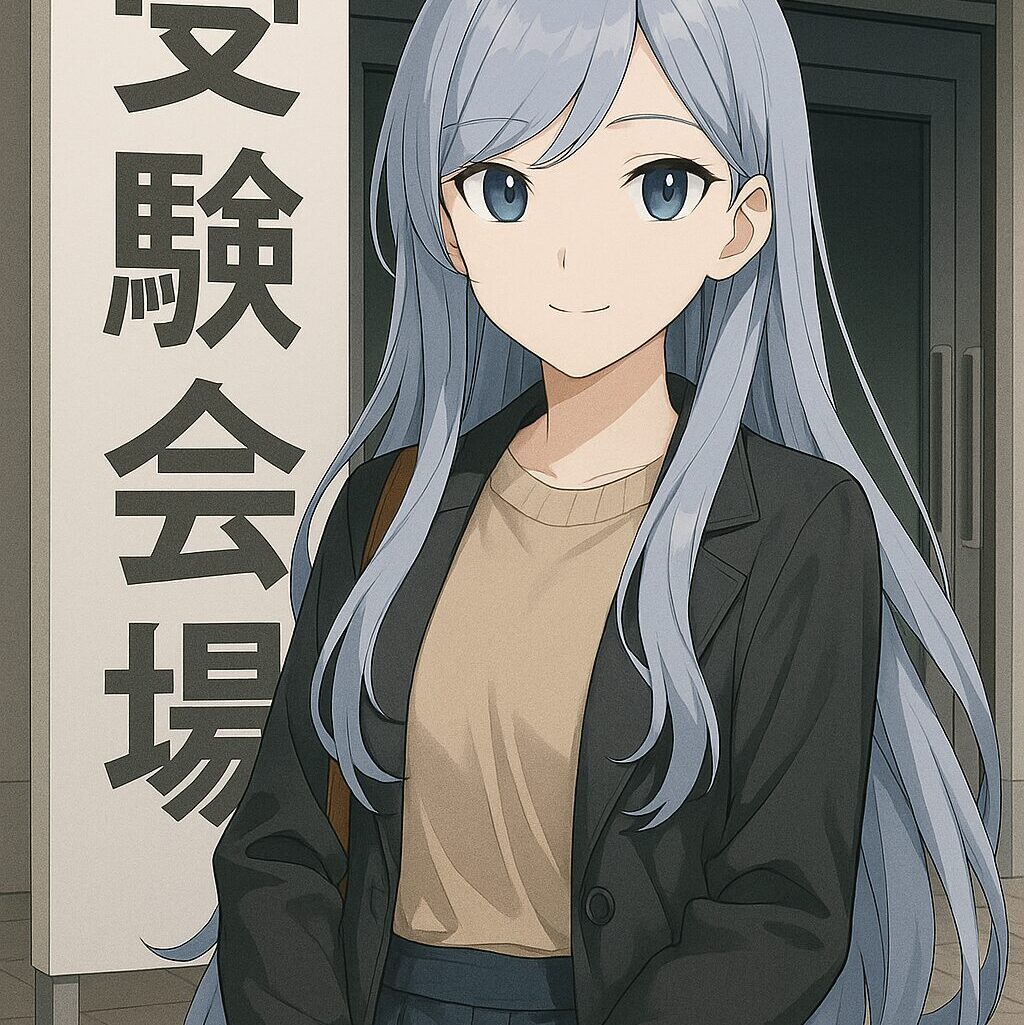
🌟鍼灸国家試験を終えて思うこと
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
2月23日、世間では3連休という中、第33回はり師・きゅう師国家試験が全国で実施されました。
看護師としてすでに医療現場に立っていたKagayaですが、改めて受けた鍼灸国家試験。
自己採点の結果は、ギリギリ合格ラインに引っかかった……というところ。
難しかったのか、簡単だったのか正直わかりません。
というのも、過去問では見たことのない言い回しや業界特有の表現が散見され、選択肢に妙に迷わされた印象が強かったからです。
とりあえず、今は合格発表を待つのみ。試験勉強に費やしていた時間は、これから開業に向けての事業計画書づくりにシフトしていきます。
Kagaya式ライフは、切り替えが命!
とはいえ、鍼灸の試験勉強で覚えた経絡や経穴の名称は、早くも記憶の奥底へ…。
正直、もう覚えていられる余裕はありません。
「覚えること」と「臨床で活かせること」はまったくの別物です。
「国家試験で高得点を取ったから、臨床ができるか?」と聞かれたら、答えはNOです。
現場で通用するかどうかは、知識の量ではなく、それをどう使うか、そして患者さんにどう寄り添えるかに尽きるとKagayaは思っています。
そもそも、学校の先生たちは国家試験で満点取った人たちでしょうか? そういう人たちでも「教えるのが上手」かどうかはまた別の話ですよね。
つまり、点数=実力とは限らないということ。
なのでKagayaは、あえて「最低限の勉強で合格する」ことを目指しました。
時間も体力も限られている社会人受験生にとって、満点は不要。
6割ちょっとで合格できる国家試験に対して、100%の努力を費やすのは非効率。
これは、あくまで割り切った戦略です。
試験前日、先生から「あん摩マッサージ指圧師の国家試験問題は、鍼灸と内容が重なる部分が多い」と聞いて、さっそく解いてみたのですが……出題内容にモヤっとする部分もちらほら。
パーキンソン病の症状はどれか。
1.体幹失調
2.前屈姿勢
3.動揺性歩行
4.アテトーゼ
この選択肢、解剖生理やリハビリの現場を知っている人間からすると「ん?」と思うものばかり。2の「前屈姿勢」が正解なんでしょうが、「前傾姿勢」じゃないの?って思いませんか?
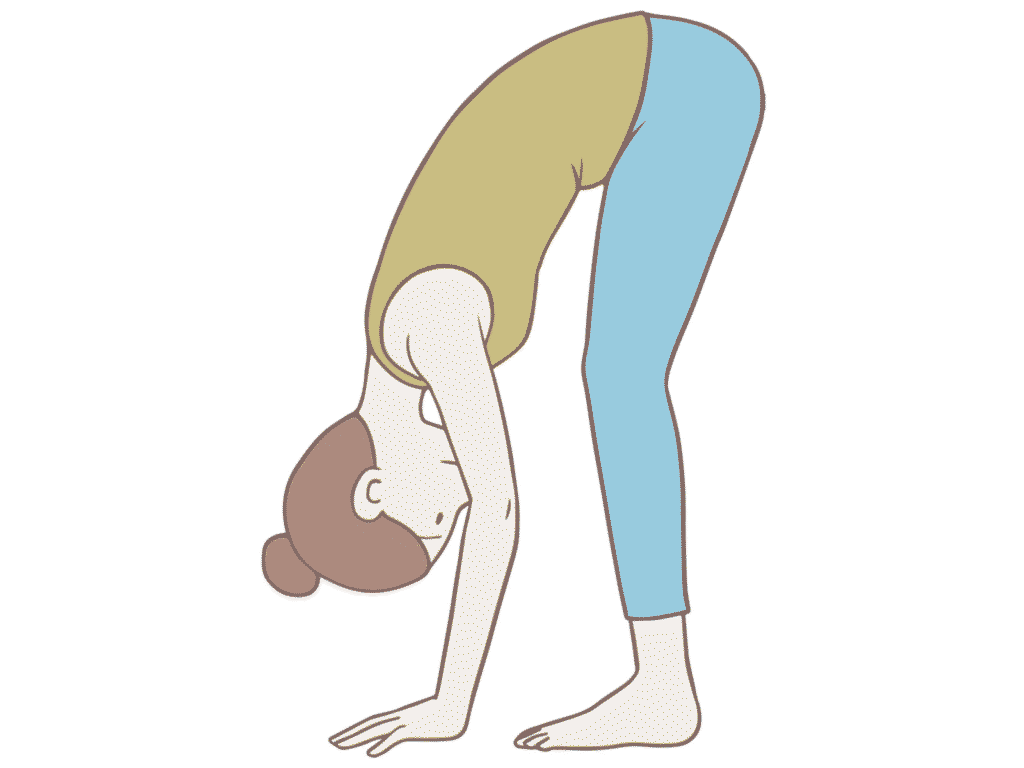
↑これが前屈姿勢でしょ?
「前屈姿勢」といった記録を看護記録で見たこともなく、どこか納得できない表現でした。
次の症例で、患者に自由に文章を書かせたときにみられる所見として最も
適切なのはどれか。
「68 歳の男性。利き手の静止時振戦、上肢の歯車様筋強剛、歩行時のすくみ足がみられる。」
1.吃 書
2.書 痙
3.小字症
4.自発書字障害
この問題の正解は「3. 小字症」。
パーキンソン病の特徴的な症状である「文字がだんだん小さくなる現象」ですが、現場で見た印象とは異なることも。
Kagaya自身、パーキンソン病の方を何人も担当してきましたが、「文字が小さい」というより「文字が読めない」「筆圧が不安定」という印象が強く、国試的な正解と、臨床のリアルとの乖離を感じました。
「正解」を導き出すためには、医療業界の“試験用語”に合わせた言語調整が必要なのです。現場経験があるからこそ引っかかってしまう、そんなトラップも国家試験には潜んでいます。
だからこそ、「鍼灸師業界の言葉で、鍼灸師の問題に答える訓練」が必要なんです。
つまり、試験に合格するための言語感覚を“翻訳”する能力。
そんな葛藤と戦いながら、Kagayaが選んだのは「無駄を省いた最低限の勉強法」。このあと、具体的な勉強法について詳しく紹介していきます。
🌟Kagaya式・ギリギリ合格を狙う現実的な勉強方法
何を目指して国家試験に挑むのかは、人それぞれだと思います。
高得点を狙いたい人は、それにふさわしい努力をすればよいし、Kagayaのように「とにかく合格したい!」という人は、それに合った戦略を立てるべきだと思います。
ネットで見かける「首席合格しました!」「何百点取りました!」という人の勉強法は、正直なところ、あまり参考になりません。
「教科書を全部読みました」「経絡経穴を歌で覚えました」「1日8時間以上勉強しました」……。
いや、それができるなら、最初からやってるよ!という感じですよね。
Kagayaは再試験も経験しましたが、それでも合格できたので、今回は「ギリギリでも合格できる」勉強法を、正直にお伝えします。
まず、Kagayaが目指したのは「自分に合ったやり方を見つけること」。
10年以上前の学生時代にやっていたような方法では通用しないと感じていたので、文明の利器に頼ることにしました。
例えば、移動時間やスキマ時間に使える便利なアプリがあります。
第21回〜第30回の過去問が収録されていて、教科別・難易度別・年代別に設定して問題を解くことができます。
解説も丁寧で、言葉の意味もフォローしてくれているので、初心者にもわかりやすいです。
最新の問題が収録されていないのが少し難点ですが、移動中やちょっとした空き時間に過去問をサクサク解けるのは大きなメリット。
こちらは第1回から最新までの過去問が揃っていて、あマ指の国家試験問題にも対応しています。
科目別・年度別で探せて、とにかく手軽に問題演習できます。
解説はないですが、「とにかく問題数をこなしたい!」という人にはピッタリです。
Kagayaはこの2つを使って、毎日の生活に少しずつ勉強を組み込むようにしていました。
それなりに勉強しても再試になったこともありましたが、その経験も含めて、「自分に合った勉強法を見つける」のが何よりも大事だと感じました。
結果的には、看護師国家試験のときよりも嬉しかったです。
なぜなら、今回は本当に「人生で一番勉強した」と言えるから。
この章を読んでいるあなたが、Kagayaのように「完璧じゃなくても合格したい」と思っているなら、ぜひ一度、自分に合った方法を探してみてくださいね。
🌟Kagayaの購入した参考資料
看護のレビューブックみたいな本です。
ほとんど活用しなかったです。
鍼灸学生ならほとんどの人が持っている国試黒本は2冊で不便。
快速マスターで十分です。
鍼灸ハンドブックも見やすいです。
一通り全教科の復習にはこのシリーズで十分です。
ゆるゴロ経穴学は絵がかわいくて、わかりやすくまとめられています。
この本はわりと使いました。
経穴マップは全く使いませんでした。
覚える気ないから。。
これは一番使いました。
国家試験対策は何よりも過去問です。
過去問だけでは不十分ですが、傾向や出される確率の統計を取ることができます。
この本もわりと使いました。
解剖生理をカンタンに復習することができます。
図や例えがあるのでわかりやすいです。
色々と本を買いましたが、国家試験過去問とゆるゴロ経穴学だけで十分かなと思います。
🌟出題傾向を制す!相手と自分を知る作戦勝ちの国家試験
国家試験とは、単なる暗記勝負ではありません。
あくまで「出題者の意図を読み、自分の弱点と強みを把握する」ことが勝負の分かれ目です。
「彼を知りて己を知れば百戦して殆うからず」──これは有名な孫子の兵法の一節です。
国家試験に挑むとき、まさにこの言葉の通り「相手=国家試験の傾向」「自分=自分の得意不得意や性格」を理解することが、最もコスパよく合格点に届く戦略になります。
例えば、過去問を見ると、同じテーマが言い回しを変えて何度も出題されていることに気づきます。
「視診とは何か?」「交感神経と副交感神経の働きの違い」「五臓六腑の病証の特徴」など、定番ネタがたくさんあります。
つまり、出題側のパターンを知れば、すでに「出そうな場所」には目星をつけることができるのです。
逆に、「出るかどうかわからないけど、出たら差がつく」ような超マニアックな内容に時間をかけすぎると、本来取れるはずの1点を失ってしまうかもしれません。
Kagaya自身も「勉強のトリアージ(優先順位付け)」をしながら学習を進めていました。
国家試験は全170問。
合格基準は102点。つまり68問も落としていいということ。
これは逆にいえば、「捨て科目」や「捨て問題」を決めてよいということでもあります。
Kagayaは東洋医学系の過去問で50点をキープできるよう意識し、西洋医学系で+10点以上を稼ぐ作戦にしました。
また、「暗記」よりも「出題者の意図を読む」意識で過去問を見直すことで、単なる記憶作業ではなく、応用問題にも対応しやすくなります。
たとえば、「脈診の手順」に関する問題が出た場合、「答えを丸暗記」ではなく、「脈診がなぜ必要なのか」「どの目的で先に診るのか」まで考えておくと、初見の選択肢にも対応できます。
そして何より大事なのは、「どのように国家試験を制するか」という視点です。
知識量ではなく、作戦です。
「やることリスト」「やらないことリスト」を作って、取れるところから順に埋めていく。
それだけでも合格率は大きく変わってきます。
あなたは今、自分の得意・不得意を把握していますか? 敵である国家試験の傾向を知っていますか? 効率よく勝ち抜く戦略を、次章で一緒に考えていきましょう!
🌟試験前日にやること
国家試験の前日──
「あと1日しかない…」と焦る気持ち、よくわかります。
でも、ここまで頑張ってきたあなたに必要なのは、新しい知識を詰め込むことではなく、心と体を整えることです。
試験前日にやってよかったこと、やらなくてよかったことを、実際の体験を交えてお伝えします。
🛁 無理せず、温泉でリラックス
「ここまで頑張った!」と自分をねぎらう意味でも、温泉やお風呂で体をゆるめるのはおすすめです。
ゆっくりと湯船に浸かって、呼吸を整えるだけで副交感神経が優位になり、ぐっすり眠れる土台が整います。
🐥 インコの体調が最優先?
Kagayaの場合、試験前日は自分よりもインコの体調が気になって、鳥専門の動物病院に行きました(笑)
「国家試験なのに、何やってるんだろう」と思いつつ、不安のタネを取り除く行動こそが自分を整える一番の近道だと感じました。
📝 あマ指の問題を解いてみた
その日の夕方はあん摩マッサージ指圧師国家試験の問題がアップされていたので、軽く目を通して解いてみました。
東洋医学系の問題が、鍼灸の国家試験よりわかりやすく感じたのが印象的でした。
あくまで気分転換レベルで、「これが出るかも」と深読みせず、軽く確認程度にしておくのがポイントです。
😴 とにかく、早めに寝る!
「今さらあがいても仕方ない」──これは本当です。
国家試験で一番怖いのは、前日詰め込みすぎて当日頭が回らないこと。
人間の脳は、寝ている間に記憶を整理するといわれています。
前日に詰め込むより、早めに寝た方が脳の働きは良くなるのです。
🌙 前日の過ごし方まとめ
- 勉強は“軽く確認”する程度でOK
- 新しいことには手を出さない
- 不安要素は前日にクリアしておく(例:持ち物、健康、ペット)
- リラックスしてよく眠る
試験本番で120%の力を出すためには、前日の「整え」が9割です。
🌟試験当日
いよいよ国家試験当日。
これまで積み重ねてきた努力の集大成を発揮する日です。
この章では、Kagayaが実際に体験した当日の様子と、受験生へのアドバイスを交えてお届けします。
⏰ 目覚ましは3個セット!
試験当日の朝は、万が一寝坊してはいけないと、目覚ましを3個セットしました。
夜中に何度も目が覚めてしまいましたが、これは試験あるある。
緊張していても、無理に睡眠時間を気にしないことが大切です。
🍚 朝ごはんは「猫まんま」で胃を守る
Kagayaはお腹を壊したくなかったので、市販のインスタント味噌汁+ご飯で「猫まんま」を作って食べました。
刺激物や乳製品、油ものなどは避けて、腸にやさしい食事を選ぶのがベターです。
🏫 会場入り~スマホは茶封筒へ?
試験会場にはスムーズに到着。
場所の下見をしておいたので、落ち着いて行動できました。
驚いたのがスマホの管理方法。
なんと電源を切って茶封筒に入れて、机の上に置くというスタイル!
電子機器をバッグの中にしまうのではなく、見える化で管理するのが最近のカンニング対策のようです。
📝 午前終了→昼休憩の過ごし方
午前中は無事に終了。
出題傾向は予想通りで、変に焦ることはありませんでした。
昼休みは、パンと温かいお茶で軽く食事。
「ここだけ覚えろノート」を見直しながら、静かに集中力を維持していました。
他の受験生が友達としゃべっているのを聞くと、不安になることもありますが、自分のペースを守ることが大切です。
😖 午後の試験と「痛みを制する」鍼灸テク
午後開始。
緊張のせいか、お腹が痛くなってきたのです。
もしかして、お昼のパンが悪かった?それとも、単なる試験ストレス?
そんなときKagayaは、合谷(ごうこく)と内関(ないかん)を刺激して、なんとか痛みを乗り越えました。
「痛みには痛みを持って制す!」──鍼灸の知識が、こんなところで役立つとは。
問題を解き終えた後にマークシートへ写すスタイルだったので、集中力と我慢の勝負でした。
🚻 トイレ事情とアフター自己採点
意外だったのが、試験中のトイレが思ったより自由に行けたこと。
実際、途中で席を立つ人もちらほらいて、「あ、行けるんだ」と安心しました。
試験後は、戦友たちと一緒に自己採点。
正答が合っていても不安、間違えていても開き直る。
そんな一喜一憂の時間も、もう大切な思い出です。
結果はどうであれ、この日まで頑張ってきた自分に誇りを持ってください。
🌟まとめ
国家試験は「資格を取るためのゲーム」だと割り切ることが、Kagayaが行き着いた結論です。
たしかに、臨床で役立つ内容が問われることもありますが、多くの問題は「覚えるだけ」「受験テクニック勝負」のように感じました。
学校の先生からは「現場で活きる知識だよ」と言われ続けましたが、正直なところ、看護師の現場では学校で習ったことよりも、現場での経験や応用力がものを言うのが現実でした。
それと同じで、鍼灸師としても、本当に必要な知識は現場に出てから、自分で選び直して学ぶことになると思っています。
実際の試験問題では、ツボの名前や取穴部位を問うのではなく、わざわざ筋肉名や神経名を使って出題される問題が多く、かえって混乱することもありました。
もっと現実的な内容──たとえば「この動作で痛みが出るのはどの筋肉か?」「この症状にはどの経穴が効果的か?」などの臨床に直結する問題が増えてほしいと、心から思います。
Kagayaは、もう覚えるのが嫌すぎて、ChatGPTで予想問題を作ってもらったり、出題傾向を分析して確率論で勉強範囲を絞るという荒業まで駆使していました(笑)
「そんな時間あるなら、経絡覚えろよ」と思う方もいるかもしれませんが、限られた時間で勝ちに行くために“自分の得意戦術”を見つけることが大切なんです。
結果的に、筋、骨格、神経、経絡が弱くても、他で点を稼げば合格はできると実感しました。
血液生化学検査の結果で異常値はどれか。
1.血糖 40 mg/dL
2.総コレステロール 180 mg/dL
3.中性脂肪 100 mg/dL
4.尿酸 5 mg/dL
動脈血における酸素飽和度の正常値はどれか。
1.約 67 %
2.約 77 %
3.約 87 %
4.約 97 %
↑この問題を間違えたら、看護師辞めるしかないと思った(笑)。
最近の国家試験では、こうした“正常・異常の数値”を問う問題が明らかに増えています。
だからこそ、ムダなプライドや理想論は全部トイレに流して、本当に大切なことだけを拾っていく柔軟さが必要だと感じました。
試験が終わってみれば、「これからが鍼灸師としての本当の勉強の始まり」──。
なのに、「鍼灸国家試験ってカンタンでしょ?」とか言ってくる人がいたら、もう…本当に腹立つ!
昔と今じゃ、出題範囲も傾向も違うんじゃい!
──というわけで、これが私Kagayaのリアルな国家試験体験でした。