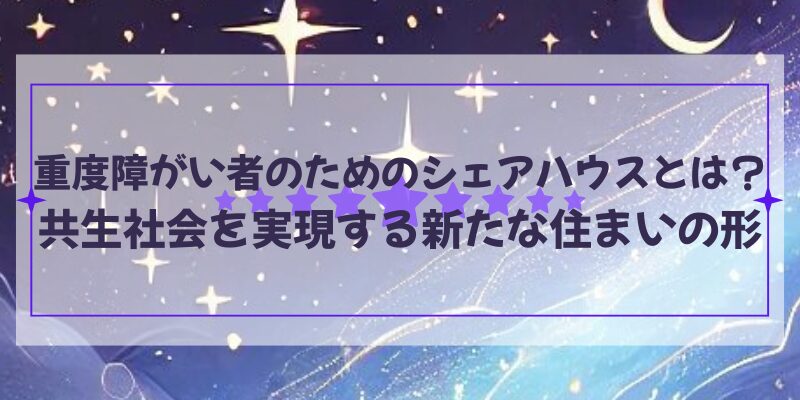こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
最近、Yahoo!ニュースなどで「障がい児の保護者が自ら放課後等デイサービスを立ち上げた」あるいは「自分の子のためにグループホームを開設した」といった記事を見かけることがあります。
こうした親の熱意や行動力には、同じ福祉や医療の現場で働く者として本当に頭が下がります。
ただ、実際に運営していくとなるとそう簡単ではありません。
資金調達はできたとしても、施設運営に必要な人材、特にケアスタッフや看護師の確保はとても難しいのが現状です。
「お金は出すけど、誰が見るの?」という問題に、多くの家庭や団体が直面しています。
また、親が子のために作った施設をそのまま運営・介護まで担ってしまうと、他の入居者やその家族が気を遣ってしまう状況も生まれやすいです。
とくに福祉の場では、「みんなが平等に安心して過ごせる空間」であることが大切。
そのバランスは意外と難しいものです。
現在、知的障がいや精神障がいの方向けの福祉施設は全国的に整備が進んでいますが、医療的ケアを必要とする重度障がい者のための施設はまだまだ不足しています。
特に24時間体制で医療・看護・介護のサポートが必要な方にとって、入居できる選択肢は限られています。
今でこそ、医療的ケア児も毎日放課後等デイサービスを利用するのが当たり前になりつつありますが、ほんの15年前まではそんなことは考えられませんでした。
当時は、ようやく特別支援学校に通えるようになったというレベル。
放課後等デイサービス自体も、医療的ケア児の受け入れは困難でした。
現在では、そのような子どもたちが中学・高校を卒業すると「生活介護」という福祉サービスに移行し、そこでも毎日の通所がスタンダードになっています。
そして、高校卒業後に「自立」の一歩として、親元を離れてグループホームへ入居する事例も少しずつ増えてきました。
ただし、ここでも問題になるのが「医療的ケアへの対応」。
吸引や経管栄養などを必要とする方を受け入れられるグループホームや入所施設は非常に少なく、保護者の多くが進路や住まいについて不安を抱えています。
そのような背景の中で、注目されているのが「医療的ケア対応シェアハウス」という新しい住まいの形です。
「施設」ではなく「住宅」として、自宅のように暮らしながら必要なケアだけを外部から導入するスタイル。
この柔軟な仕組みが、重度障がい者とその家族にとって希望となりつつあります。
今回の記事では、この「重度障がい者のためのシェアハウス」について、Kagayaなりの視点から、現実と課題、そして可能性について掘り下げてみたいと思います。
🌟シェアハウスについて
「シェアハウス」と聞くと、若者が集まって楽しく共同生活をするというイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
一般的には、一戸建てや広めのマンションの中にそれぞれの個室があり、リビングやキッチン、トイレ、浴室などを共用で使用する賃貸住宅の形態を指します。
一人暮らしと比べて、家賃や光熱費を分担できるため、経済的にもメリットが大きいのが特徴です。
特に東京や大阪など家賃が高騰しがちな都市部では、シェアハウスの選択肢が増えており、若年層だけでなく外国人や単身赴任者にも利用されています。
シェアハウスの魅力は、単に「安く住める」だけではありません。
似たような価値観やライフスタイルを持つ人たちが集まって住むことで、人とのつながりや安心感が生まれやすく、孤独感の解消にもつながります。
もちろん、人と暮らすことがストレスになるタイプの方にとっては、向き不向きもあるでしょう。
最近では、運営者が明確なコンセプトを掲げている「テーマ型シェアハウス」も増えています。
たとえば、毎週金曜日には入居者以外の人も参加できるイベントを開催するような交流型シェアハウスや、菜園付きのエコライフ型、語学学習や起業家支援に特化したものまで、実に多様です。
中でも注目されているのが、「社会的マイノリティ」や「弱者」とされる立場の人たちを受け入れる支援型シェアハウスの存在です。
たとえば、シングルマザー向けや、精神疾患のある人を対象とした安心安全な住まい、LGBTQ+フレンドリーなシェアハウス、高齢者や認知症の方を受け入れる住宅なども登場しています。
また、表現活動を行う人たち向けに特化したアトリエ付きのシェアハウスもあり、美大生やアーティストが共同で制作活動を行うスペースとして機能しています。
実際、油絵専攻の学生に部屋を貸したくないという大家さんがいるという話もありますが、そうした偏見を取り払う居場所の提供は、まちづくりや福祉の観点からも意義深いと感じます。
Kagayaの地元である小平市も、美術大学がある関係で芸術に縁のある町です。
アートと福祉が交わるシェアハウスがこの町に生まれたら素敵だな…と夢を描くこともあります。
このように、シェアハウスは単なる「節約のための共同生活」ではなく、人と人がつながりながら支え合い、自分らしく暮らすための新しい住まい方の一つとして、多様な展開を見せています。
🌟グループホームについて
ここでは「グループホーム」について、介護保険法に基づく「認知症高齢者グループホーム」ではなく、障害者総合支援法に基づく「障がい者グループホーム」を中心に解説していきます。
グループホームは、家庭での生活が難しい障がいのある方が、地域の中で自立的な暮らしを営むための福祉サービスの一つです。
入居者は職員の支援を受けながら、食事・入浴・掃除・金銭管理などの支援を受けつつ、可能な限り自立した生活を目指します。
「家」でありながら「支援施設」でもあるグループホームは、制度上の定義や基準に則って運営されており、障がい者本人やその家族にとって、将来を見据えた大切な選択肢のひとつとなっています。
グループホームの種類
障がい者グループホームには、入居者の障がいの程度や支援内容に応じて、いくつかの種類があります。
それぞれの型には特徴があり、適切な支援のあり方が異なります。
以下に主要な4つのタイプをご紹介します。
介護サービス包括型
日常生活において一定の介護が必要な方を対象としたタイプです。食事・入浴・排泄などの基本的な介助をホームの職員が直接提供します。日中は就労継続支援B型や生活介護など、外部の福祉サービスを利用する方が多く、夜間や休日の生活支援を中心としています。
外部サービス利用型
介護の必要性が比較的軽度な方を対象とし、入浴・食事・排泄などの介護は外部の事業者と委託契約を結び、訪問介護などを組み合わせて対応します。生活支援の範囲が明確に分かれており、より柔軟に構成されるのが特徴です。
日中活動サービス支援型
日中も含めた常時支援が必要な方に対応したタイプです。生活介護などの通所が困難な方が対象となり、グループホーム内で日中活動や支援を受けられるよう、職員が常駐しています。重度障がいのある方や高齢化した入居者にとっては非常に重要な支援体制です。
サテライト型
グループホームの本体施設とは別に、近隣のアパートやマンションに1人暮らしのような形で暮らすタイプです。日常的な支援は必要最小限にとどめ、自立度の高い方が対象です。必要時には本体職員に連絡して支援を受けられるため、「半自立」の練習にも向いています。
グループホームの設置基準
グループホームは、障害者総合支援法に基づく福祉サービスであるため、開設・運営には一定の法的基準や条件を満たす必要があります。
たとえば、居室面積、トイレ・浴室の設置基準、職員の配置人数、避難経路、消防設備など、詳細な項目が自治体ごとに定められています。
また、入居できる人にも条件があります。原則として、18歳以上で障害支援区分が「区分3以上」、あるいは50歳以上で区分2以上が必要です。
また、一定の地域生活能力や医療的安定性が求められることもあります。
これらのルールは、入居者の安全・安心を守るためには重要ですが、一方で運営側にとっては柔軟性を持たせづらい制度の縛りにもなっています。
たとえば、医療的ケアが必要な重度障がいの方が対象になると、看護師配置や夜勤体制が必要となり、運営コストが跳ね上がるため、受け入れに消極的な施設も少なくありません。
このように、制度としてのグループホームは整備が進んでいる一方で、重度障がいのある方が「終の住処」として暮らせる場所としては、まだまだ課題が多いのが現実です。
🌟重度障がいのシェアハウスビジネスについて
最近、重度障がいのある方を対象とした「シェアハウス」という新しい形態の住まいが少しずつ登場しはじめています。
障がい者向けの施設といえば、グループホームや入所施設が一般的でした。
しかし、それとは異なる「シェアハウス」という選択肢が注目されているのはなぜなのか?
そして、重度障がいの方を対象としたシェアハウスは、果たしてビジネスとして成立するのか?いくつもの疑問が浮かびます。
医療的ケアや24時間の介護体制が必要な方を受け入れる住環境には、多くの課題があります。
まず前提として、重度障がい者が安心して暮らせる設備を整え、常時サポートできるスタッフを確保し、医療・看護との連携を図らなければならないため、運営コストは非常に高くなります。
採算をどうとるのか、これは非常に現実的な問題です。
実際にいくつかの医療的ケア対応型シェアハウスを運営している企業のサイトを見てみました:
これらの事業を見ると、いわゆる「シェアハウス」に訪問介護や訪問看護の事業所を紐づけて、サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)と似た構造をとっていることが多いです。
つまり、住宅そのものでは利益を出さず、そこで必要となる福祉サービスや医療支援によって採算をとる「芋づる式ビジネス」と言えるでしょう。
このような構造は、医療的ケアが必要な高齢者向け住宅と非常に似ています。
対象が高齢者から障がい者に切り替わっただけ、という印象もあります。
ただし、違う点は「障がい者福祉制度」の仕組みが高齢者福祉よりも複雑で、制度上の制限も多いため、単純な転用はできません。
そして、重度障がい者の受け入れとなると、人員配置や医療連携、介護報酬の取り扱いなど、非常に繊細な運営が求められます。
正直なところ、これを“儲かるビジネス”として成り立たせるのはかなり難しいのが現実です。
ではなぜ、こうしたシェアハウス事業に取り組む企業が存在するのでしょうか。
それはやはり、志のある事業者による「社会的な使命感」や「本人らしい暮らしを叶える住まいづくり」への挑戦に他なりません。
実際、営利を追い求めるだけでは成立しない領域であるため、想いのある運営者や地域医療・福祉との連携、そしてご家族の協力が不可欠です。
補助金や助成金を活用しつつ、収益だけに偏らないバランス感覚が求められます。
Kagaya自身も、こうした重度障がい者のシェアハウスを見て感じたのは、「ただの住宅ビジネスではない」ということ。
そこにはケアする側の覚悟と、暮らす本人たちの「生き方」を支える覚悟が問われている気がします。
単にシェアハウスという仕組みを導入すれば良いという話ではなく、支援体制や人材確保、地域との関係づくりなど、継続可能な仕組みをどう築くかが鍵となるのです。
🌟シェアハウス運営を選ぶ理由
グループホームと比較したとき、なぜあえて「シェアハウス」という形を選ぶ人がいるのでしょうか?
そこには、制度に縛られない柔軟性や、本人にとっての「終の棲家」を実現したいという切実な願いが込められているように思います。
まず、グループホームは障害者総合支援法に基づく福祉サービスであり、国や自治体からの補助金が出るため、家賃・光熱費・食費を含めても月額70,000円前後と、入居者の自己負担はかなり抑えられます。
しかし、その反面、設置基準や入居条件が細かく決まっており、年齢や障害支援区分によっては「入れない」「続けて住めない」などの制限が発生します。
たとえば、年齢とともに要介護度が上がり、入退院を繰り返すようになると、グループホームでは対応できずに退去を迫られるケースもあります。
一方、シェアハウスは福祉制度に基づく「施設」ではなく、あくまで「住宅」です。
一般住宅と同じ扱いになるため、制度上の設置基準や入居者の条件は存在しません。
運営者の裁量によって入居対象を柔軟に設定することができます。
つまり、「誰が、どのような支援を受けながら、どこで暮らすか」を自分たちで決められるという大きな自由があるのです。
これこそが、シェアハウスを選ぶ最大の理由であり、制度の枠を超えて「自分らしく生きる場」としての価値が生まれます。
もちろん、制度外であるということは、国からの補助金が出ない=費用はすべて自費負担という意味でもあります。
家賃、光熱費、食費、消耗品(オムツや入浴用品など)など、入居にかかる月額費用はだいたい70,000~90,000円程度が相場のようです。
これは、サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)と比べるとかなりリーズナブルです。
サ高住の場合、家賃だけで月20万円を超えることも珍しくありません。
それに介護サービスを追加すると、さらに費用は増えていきます。
それでも、Kagayaのような福祉職の給与でその金額を払うのは正直つらいところです。
Kagaya自身、「自分が入るとしたら月20万円の生活費は無理…」と思ってしまいます。
にもかかわらず、実際のサ高住では「高額なのに自由がない」「まるで施設のようだ」という声も少なくありません。
その点、シェアハウスには「監獄のような制約」はなく、運営者が入居者と対話しながら一緒に住環境を作ることができます。
介護や看護が必要になっても、訪問サービスを活用しながら柔軟に支援を受け続けることができます。
また、グループホームはあくまで「中間的な施設」として捉えられ、「いずれは次の施設に移る」ことが前提となることもあります。
しかし、シェアハウスはそのまま終の棲家(ついのすみか)となる可能性があるのです。
「親の亡き後の住まいをどうするか?」という課題は、多くの保護者が共通して抱える不安です。
その答えのひとつとして、制度に頼らず「本当に本人らしい暮らし」を目指す住まいとして、シェアハウスが選ばれているのかもしれません。
🌟自費サービス提供の需要
グループホームに比べて、制度上の制約が少なく自由度が高いシェアハウスですが、重度障がい者が入居するとなると、24時間365日の介護・医療的サポートが必要になります。
たとえば、吸引・経管栄養・見守り・排泄介助・体位変換・入浴介助など、生活のあらゆる場面で支援が必要な方も少なくありません。
そのため、重度訪問介護の利用を組み合わせるケースが多くなります。
ただし、重度訪問介護や訪問看護といった公的サービスでは、支援内容に明確な制限があるため、必ずしも希望通りの生活スタイルを叶えられるとは限りません。
たとえば、
- 好きな時間に外出したい
- アートや音楽など趣味を楽しみたい
- イベントやレクリエーションに参加したい
- 買い物やお散歩に付き添ってほしい
こうした「生活の質(QOL)」を高める活動に、公的支援だけで十分対応するのは難しいのが現実です。
ここで必要となるのが、自費サービスの導入です。
たとえば、以下のようなニーズに応えるサービスは、今後ますます求められていくと考えられます。
- シェアハウス入居者の散歩・外出・通院への同行支援
- 家族に代わって行う買い物代行や日用品管理
- 音楽療法・アートセッションなどの余暇活動支援
- 旅行・外泊・墓参りなどの長時間外出の付き添い
- 専門性の高いリラクゼーションや個別ケア(耳鍼、YNSAなど)
グループホームは「施設」としての制限が多く、こうした個別性の高いサービスを柔軟に取り入れることは難しい側面があります。
しかし、シェアハウスは「住宅」なので、入居者や運営者の意向に応じて、どこまで・どのような支援を導入するかを自由に設計できます。
とはいえ、すべてを無料・無償でまかなうのは現実的ではありません。
「できること」の幅が広がる代わりに、「自費での利用」が前提になる場面も増えるでしょう。
つまり、シェアハウスを運営する側としても、外部の専門職や事業者と連携しながら、付加価値のある有料サービスを展開していく必要があるのです。
入居者と対話しながら「これがあったらいいね」という声を拾い、新たなサービスを立ち上げていくことで、暮らしの質を向上させていくことができます。
Kagaya自身も、自費訪問鍼灸・耳介療法・リラクゼーションケアなど、重度障がいの方の生活支援につながる個別ケアを提供してきました。
これからの時代は、こうした民間ケアの力も活かしながら、共生のかたちを育てていく必要があると感じています。
シェアハウス運営者と専門職が協働し、「制度外の自由なケア」の可能性を広げていく。
そこに、新しい支援のかたちとビジネスの可能性があるのではないでしょうか。
🌟まとめ
ここまで、重度障がい者向けのシェアハウスについて、制度的背景やグループホームとの違い、運営の実際、自費サービスの可能性に至るまで幅広く見てきました。
重度障がい者といっても、支援のあり方は一人ひとり異なります。
たとえば、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や高位頸髄損傷のように、身体の自由は制限されていても、意思疎通が可能な方にとっては、施設感のない「家」としてのシェアハウスは、とても大きな意味を持ちます。
一方で、重度の知的障がいや重症心身障がい児(者)の場合、本人が「どこで、誰と、どう暮らしたいか」を表現することが難しいケースもあります。
そのようなとき、本人の意思をどう尊重するかという課題が浮かび上がります。
決して「シェアハウスが良い」「施設が悪い」といった二元論ではなく、誰にとって、どんな暮らしが“その人らしい”のかを、家族や支援者、専門職が一緒に考えていく姿勢が求められるのです。
これは医療の場で語られる「生命倫理」と同じように重いテーマでもあり、この記事ではあえて深くは触れませんが、支援に関わるすべての人が考え続けなければならない視点でもあります。
現状として、グループホームや入所施設の空きが少なく、入りたくても入れないという課題は全国的に共通しています。
そんな中で、シェアハウスという「住まい方の選択肢」があることは、非常に大きな意義があります。
シェアハウスは、一時的な利用も可能ですし、最期まで暮らす「終の棲家」とすることもできます。
制度の枠に縛られず、本当に必要な人に、必要な支援を提供できるという意味で、可能性に満ちた仕組みです。
ただし、そこに「ビジネスとしての利益」を求めすぎると、本来の目的から大きく逸れてしまう危険もあります。
「障がい者をターゲットにした金儲けビジネス」になってしまわないよう、倫理観と誠実さをもって運営する姿勢が何よりも大切です。
これからの時代は、多様な支援スタイルが共存する社会、いわば「共生社会」の実現が求められています。
重度障がい者が住み慣れた地域で、安心して最期まで暮らせる。
その一助として、シェアハウスという住まい方がもっと広がってほしいとKagayaは願っています。
そしてその支援の輪の中に、私たち看護師や鍼灸師、介護職、地域の人々、家族みんなが関わることができれば、「施設」でも「家」でもない、本当の居場所がきっと生まれてくるはずです。