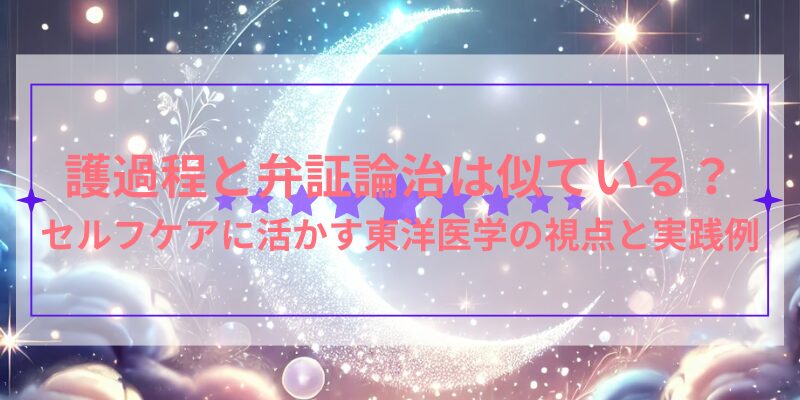こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
鍼灸の専門学校に通いはじめた頃から、Kagayaの中にはずっと「既視感」のようなものがありました。
それは、東洋医学の基本となる「弁証論治(べんしょうろんち)」という考え方に触れたとき──
「あれ?これはまるで看護過程と同じじゃない?」
そう感じたのが始まりです。
看護の世界では、「対象となる人」を疾患や数値だけで判断するのではなく、その人の暮らし、価値観、背景、さらにはその人らしさまで含めてトータルで捉える視点が求められます。
「その人らしさを支えるケア」とは何かを常に考え、5つのステップ(情報収集、アセスメント、計画立案、実施、評価)を通じて、最適な看護を模索し続ける──これが看護過程です。
一方、東洋医学にも「その人をまるごと診る」という視点があります。
単に「腰が痛い」「眠れない」などの症状だけを切り取るのではなく、なぜその症状が今のタイミングで現れているのか?
体のどこに偏りがあるのか?
気・血・水の流れや臓腑の働き、感情、食事、生活習慣までを含めて「全体のバランス」を読み解き、原因と対策を導き出します。
この一連の流れは、まさに西洋医学における看護過程にそっくりです。
実際に、私が訪問看護の現場で関わる患者さんの多くは、病名だけでは語りきれない多面的な困りごとを抱えています。
・夜に眠れないけれど、病院では「異常なし」と言われた
・なんとなく疲れやすいけれど、誰にも理解されない
・食欲や気分に波があり、自分でも原因がわからない
そんなとき、私は看護師として「生活や環境の変化」「ストレス」「服薬歴」などの情報を丁寧に拾い集めます。
そして同時に、鍼灸師としての目で「舌の状態」「耳の反応点」「腹部の冷えや緊張」などを観察し、東洋医学的に弁証(病態の分析)を行います。
看護と東洋医学は、まったく別の領域に見えて、実は「人をみる軸」が非常によく似ています。
この2つの視点を組み合わせることで、Kagayaは今、自分自身のセルフケアにも大きな手応えを感じています。
そして何より、この視点を持つことで、患者さん自身が「自分の体に気づける力」を取り戻していく瞬間に、たくさん立ち会ってきました。
本記事では、そんなKagaya自身の体験や実践例を交えながら、看護と東洋医学の共通点、セルフケアへの応用方法をやさしく解説していきます。
「なんとなく調子が悪いけど、どう向き合ったらいいかわからない」
「看護や介護に携わっているけれど、自分自身のケアが後回しになっている」
そんな方にも、少しでもヒントや安心を届けられたら嬉しいです。
🩺 看護過程と弁証論治──実はとてもよく似ている
看護の現場では、患者さんの症状だけでなく、その人の背景や生活スタイル、価値観までも含めて理解する「看護過程」が基本となっています。
この看護過程は、「情報収集 → アセスメント → 計画立案 → 実施 → 評価」という5つのステップで構成されており、一連の流れの中で“その人にとって最も適した看護”を探っていく実践的なプロセスです。
一方、東洋医学では、「四診(望・聞・問・切)」を通じて得た情報をもとに「弁証論治」を行います。
「弁証」とは、患者さんの体に起きている症状を整理・分析し、どのようなバランスの乱れがあるのかを判断する過程。
そして「論治」とは、その乱れに対して、どのように整えていくかという治療方針を立てることです。
この「情報を集める → 状態を判断する → その人に合ったケアを考える」という流れは、まさに看護過程と共通しています。
たとえば、ある訪問先でこんな訴えがありました。
「最近、夜中に何度も目が覚めてしまって…頭がずっと重いんです」
看護師としてのKagayaは、まず睡眠環境、生活リズム、ストレスの有無、日中の活動量、服薬状況などを丁寧にヒアリング(アセスメント)します。
交感神経優位による自律神経の乱れや、女性ホルモンの変動、加齢による睡眠の質の低下など、西洋医学的な背景も念頭に置きながら情報を集めていきます。
一方で、鍼灸師としてのKagayaは、東洋医学の視点からその方の舌を診て(舌診)、耳の状態を観察(耳診)しました。
舌は全体的に白く、むくみがあり、歯の痕(歯痕)が目立ちました。また、耳の「腎区」と呼ばれるエリアにやや膨らみと冷感が見られました。
これらの所見から、「脾腎陽虚(ひじんようきょ)」という状態──つまり、消化吸収やエネルギーを作る機能(脾)と、生命力の源である腎のエネルギー(腎陽)が弱まっている状態であると判断しました。
そこで、冷えの改善を目的に、三陰交・関元・腎兪といったツボにお灸を提案。
さらに、冷たい飲食の制限や、湯船にしっかり浸かることなど、生活面での見直しもアドバイスしました。
数日後、その方から「ぐっすり眠れるようになって、朝の頭の重さも消えました」と笑顔で報告をいただきました。
このように、看護と東洋医学はアプローチや用語こそ違えど、「目の前の人をまるごと理解しようとする姿勢」は共通しています。
単なる症状や検査値の変化ではなく、「なぜ今それが起こっているのか?」を多角的に見つめ、その人が自分らしく過ごせる方向に導く──これは、どちらの視点にも共通する“人間中心のケア”です。
Kagayaにとって、東洋医学は「補助的な選択肢」ではありません。
むしろ、看護をより深くするためのもう一つの言語だと感じています。
だからこそ、これからもKagayaは看護の知識と東洋医学の技術を融合させ、その人にとって自然で無理のないケアを探求し続けていきたいと思っています。
🌟 なぜ体がしんどいのか?──現代人の不調の背景
「ぐっすり寝たはずなのに疲れがとれない」「理由もなく体がだるい」「頭がずっと重くてスッキリしない」「なんとなく気分が沈みがち」
こうした“明確な病名はつかないけれど、確実にしんどい”状態のご相談が、Kagayaの訪問ケアやLINE相談でもここ数年、特に増えています。
しかも、それは特定の年代や性別に限ったことではありません。
20代の学生さん、働き盛りの会社員、子育て中のママさん、高齢の方まで──年齢も背景もバラバラなのに、共通して「なんとなく元気が出ない」「疲れがとれない」と訴えられるのです。
以下のような症状、あなたにも思い当たることはありませんか?
- 寝ても疲れがとれない/朝スッキリ起きられない
- 頭がずっと重い/集中力が続かない
- 胃腸の調子が不安定/食欲に波がある
- 生理前になると感情の起伏が激しくなる
- 常にイライラ/不安感/焦りがある
これらの症状は、単なる「年齢のせい」「気のせい」「疲れてるだけ」では片づけられないものです。
実際には、心と体の両面で“エネルギーの消耗”が続いている状態だと考えられます。
たとえば、朝から晩までスマホやパソコンを使い続ける生活。
仕事や家事、育児、介護…あらゆるプレッシャーに囲まれながらも、なかなか「休む」ことができず、自分のケアは後回しになりがちです。
こうして交感神経(興奮モード)が優位な状態が続くと、体は常に戦闘態勢のようになり、夜になってもリラックスできず眠りが浅くなる──このような悪循環に陥ってしまいます。
また、ストレスや情報過多によって、「本当の疲れ」に気づく感覚そのものが鈍くなっていることも多いのです。
「気づかないうちに無理していた」「これくらい大丈夫とがんばっていた」
その結果、ある日突然、心身がブレーキをかけてくる──
それが、上記のような「なんとなく不調」のサインとして現れるのです。
東洋医学では、こうした状態を「未病(みびょう)」と呼びます。
病気とは診断されていないけれど、すでに健康な状態からは外れている──
この未病の段階で、体の声に気づき、ケアを始められるかどうかが、未来の健康を大きく左右します。
とくに、慢性的なだるさ・頭の重さ・胃腸の不調・冷え・PMSなどがある方は、「いつものこと」と放置せず、心身のバランスを整えるきっかけとして捉えてみてください。
このあとから、東洋医学と西洋医学の両視点から「不調の原因」を紐解いていきます。
ご自身の体に、もっとやさしくなれるヒントが見つかりますように。
西洋医学的視点
「なんとなくしんどい」「疲れが抜けない」といった不定愁訴に対し、西洋医学では主に自律神経の乱れやホルモンバランスの変動、そして慢性的なストレスが背景にあると考えられています。
自律神経には、「交感神経(活動・緊張モード)」と「副交感神経(リラックス・休息モード)」があり、この2つが状況に応じてバランスよく働くことで、私たちの体は一定のリズムと安定を保っています。
しかし現代社会では、仕事や家事、育児、人間関係、SNS疲れなどによって、心も体も慢性的に“交感神経優位”の状態が続きがちです。
特に以下のような生活習慣は、自律神経の乱れを助長します:
- 長時間のスマホ・パソコン使用(脳が休まらない)
- 寝る直前までの画面閲覧や情報摂取
- 不規則な生活・睡眠時間のばらつき
- 栄養バランスの乱れや食事の不規則化
- 運動不足・日光不足(セロトニン分泌の低下)
こうした生活が続くと、自律神経の切り替えがうまくできなくなり、“ずっと戦闘モード”のような状態が続きます。
その結果、体に以下のような変化が起こります:
- 眠っても深く眠れず、脳が休まらない
- 胃腸の働きが鈍り、食欲や排便に不調が現れる
- 免疫力が下がり、風邪をひきやすくなる
- 代謝が落ちて疲れやすくなる
- 女性では生理周期の乱れやPMSが悪化する
こうした状態が続くことで、「自律神経失調症」「過敏性腸症候群(IBS)」「慢性疲労症候群」「月経前症候群(PMS)」などの診断がつくケースも増えてきました。
中でも、自律神経失調症は検査では“異常なし”なのに、本人はつらい症状を感じているというジレンマを抱えやすく、対処に悩む方が多いのが特徴です。
また、ストレスホルモンである「コルチゾール」や、睡眠ホルモン「メラトニン」、女性ホルモンのエストロゲン・プロゲステロンなど、ホルモン分泌のリズムが崩れることも不調の原因になります。
実際、ストレスが多いときや生活が乱れているときに、「肌が荒れる」「眠れない」「気分が落ち込む」「冷えやすくなる」など、複数の症状が同時に起こるのはこのためです。
西洋医学ではこうした症状に対して、睡眠薬、抗不安薬、胃腸薬、ホルモン剤などによる薬物治療が一般的ですが、根本的な回復には「生活のリズムを整えること」「ストレス源への気づき」が不可欠です。
特に自律神経の乱れは、早い段階で気づいて対処できれば、薬に頼らず自然に回復できることも多くあります。
次の章では、東洋医学がどのようにこうした不調を捉え、どうアプローチしていくのかを解説していきます。
東洋医学的視点
西洋医学では“自律神経の乱れ”や“ホルモン変動”として説明されるような不調──その根本的なバランスの乱れを、東洋医学では「気・血・水(き・けつ・すい)」の流れとして捉えます。
「気」はエネルギーそのもの、「血」は体を栄養し潤すもの、そして「水(津液)」は体液として体内の機能を支える要素です。
この3つがスムーズに流れ、偏りなく循環しているとき、人は健康な状態にあります。
しかし、以下のような生活習慣やストレスが続くと、気・血・水のバランスが崩れ、さまざまな症状として現れます:
- 睡眠不足・疲労の蓄積 → 気虚(ききょ)=エネルギー不足
- 過度なストレス → 気滞(きたい)=気の巡りが悪くなる
- 栄養不足や消化力の低下 → 血虚(けっきょ)=貧血・不眠・集中力低下
- 冷え・水分過多・代謝の低下 → 水滞(すいたい)=むくみ・頭重感・めまい
つまり、現代人に多い「だるさ」「ぼんやりする」「むくみやすい」「気分が晴れない」といった不調は、気血水のどれか、あるいは複数の滞りがあるサインともいえます。
さらに東洋医学では、五臓六腑の働きに着目し、「肝」「脾」「腎」などがストレスや食生活、感情と深く関わっていると考えます。
特に不調と関連しやすいのが、以下の2つ:
- 肝(かん):気の巡りを調整。怒り・イライラ・生理痛・PMSと関係
- 脾(ひ):消化吸収を司る。疲れやすい・下痢・むくみ・食欲不振
たとえば、「月経前になると情緒が不安定になる」「疲れるとすぐ胃腸にくる」という方は、肝の働きが強まりすぎて脾を抑制している(肝脾不和)という弁証が考えられます。
また、慢性的なストレスや過労が続くと、腎の精(生命力)が消耗し、やる気が出ない・足腰がだるい・不眠傾向・老化の加速などに繋がる場合もあります。
このように、東洋医学では症状の「表面」ではなく、その背後にある「内側の流れの偏り」や「五臓の連携」に注目します。
そして、診断(弁証)によってツボを選び、灸や鍼、生活習慣の見直しによって、滞っていた流れを“元の状態に戻す”ことを目的とします。
たとえ検査で異常が出なくても、「なんとなく調子が悪い」という時点で、東洋医学的にはすでにバランスが乱れている状態。
未病の段階で気づき、整えることが、体と心を守る最もやさしい方法なのです。
「冷えやすい」「頭が重い」「生理前につらい」「むくみやすい」──それらはすべて、あなたの体からのSOS。
薬に頼る前に、生活を少し整えるだけでも、改善できるケースはたくさんあります。
東洋医学の視点をセルフケアに活かして、まずはご自身の「今の状態」に気づくところから、はじめてみませんか?
✅ セルフチェックリスト
「病院に行くほどじゃないけど、なんとなくつらい…」
そんな状態を抱えていませんか?
体調不良や不定愁訴が続くとき、多くの方が「年のせいかな」「気の持ちようかも」と思って我慢したり、無意識に見過ごしたりしています。
けれど東洋医学では、こうした状態を「未病(みびょう)」と呼び、病気になる前の段階をとても大切に考えます。
未病とは「病気ではないけれど、健康ともいえないグレーゾーン」のこと。
この段階で体のサインに気づき、早めにケアを始めることで、不調の進行を防ぎ、自然な回復を促すことができます。
Kagayaは、訪問ケアやセルフケア相談の現場で、東洋医学の「気・血・水」のバランスを見立てる際に、このチェックリストを活用しています。
下記の項目に3つ以上あてはまる場合、気血水の巡りに偏りがある可能性があり、自律神経や内臓の働きにも負担がかかっているかもしれません。
- 朝起きても疲れが抜けない/目覚めが悪い
- 便秘または下痢を繰り返す(特にストレスで悪化)
- PMS(月経前症候群)が重く、情緒が乱れやすい
- 寝つきが悪く、夜中に目が覚める・夢をよく見る
- 不安感や焦燥感が強く、リラックスできない
- 頭が重い・スッキリしない日が多い
- 手足が冷えやすく、むくみやすい
- 胃腸が弱く、食欲に波がある/食後に疲れる
- 生理痛・排卵痛・周期の乱れが気になる
- 風邪をひきやすく、治りにくい
いかがでしたか?
これらの症状は、「なんとなくの不調」では済まされない、体からの大切なメッセージかもしれません。
たとえば:
- 気虚(ききょ): 疲れが抜けない・元気が出ない
- 気滞(きたい): イライラ・のどのつかえ・生理前の情緒不安定
- 血虚(けっきょ): 不眠・目のかすみ・集中力低下
- 水滞(すいたい): むくみ・冷え・頭重感・めまい
こうしたアンバランスが複数重なることで、心と体の調和が崩れていきます。
西洋医学の検査では「異常なし」と言われるけれど、どうにも不快…という方にこそ、日常的に“自分でチェックする習慣”がとても役立ちます。
特別な道具も知識もいりません。
まずはこのチェックリストを定期的に振り返り、「最近どうかな?」と自分に問いかけるところから始めてみてください。
小さな違和感に気づき、整える力を育てること。それが、東洋医学がめざす“未病ケア”の第一歩です。
次章では、こうした不調のサインにどう向き合い、整えていくのか──Kagaya式のセルフケアをご紹介していきます。
💡 Kagaya式セルフケアのすすめ
なんとなく体が重い日、寝ても疲れがとれない朝、気分が落ち込みがちな時──あなたは、どんなふうにその不調に対応していますか?
市販の薬を飲んでやり過ごす、マッサージや整体に頼る、あるいは「そのうち治るだろう」と我慢してしまう…。
それも、もちろんひとつの選択肢です。
けれどKagayaは、こう考えています。
「自分で自分を整える力=セルフケア」こそが、毎日の健康を支える最も根本的で持続可能な方法ではないかと。
東洋医学には、数千年の歴史のなかで培われた「自分で自分の体と向き合う知恵」がたくさんあります。
たとえば、舌を鏡で見ること、耳のかたちや色を観察すること、心地よいと感じるツボにお灸をすること、冷えや疲れを防ぐための生活習慣を整えること…。
どれも難しい技術や知識がなくても、今日からすぐに始められることばかりです。
実際、Kagayaが訪問施術でお会いする方の多くが、「少し自分に目を向けるだけで、体が変わる」ことを実感されています。
最初は「舌って見る意味あるの?」「耳にツボなんてあるの?」と半信半疑でも、数日続けていくうちに、「今日は疲れてるから、無理しないでおこう」といった“自分をケアする判断力”が育っていきます。
それは、まるで小さな羅針盤のように、体調の波から自分を守ってくれるのです。
とくに現代の私たちは、外の情報に振り回され、自分の感覚が置き去りになりやすい時代に生きています。
だからこそ、自分の体の声を“感じる力”を育て、日常の中でこまめにケアしていくことが大切です。
この章では、Kagayaが日頃から患者さんにお伝えしている、シンプルで実践的なセルフケア方法を4つご紹介します。
- 耳診(じしん):ストレスや冷えのサインを耳でキャッチ
- 舌診(ぜっしん):舌の色・形・苔で体の状態をチェック
- お灸:冷え・疲れ・不眠に効果的なセルフケア法
- 生活習慣アドバイス:体内リズムを整える習慣づくり
どれも、特別な道具や技術は必要ありません。
むしろ「気づいて、見て、触れて、感じる」──この自然な行為こそが、心と体をゆるめる力になるのです。
ご自身の体に対して、ほんの少しの「優しい関心」を向けてみてください。
その気づきが、不調の連鎖を断ち切る第一歩になります。
それでは、次の章から一つずつ、実践方法を詳しくご紹介していきます。
耳診(じしん)で見るサイン
東洋医学では「耳は全身の縮図」といわれるほど、重要な観察ポイントです。
耳介(じかい)には五臓六腑や脳神経、自律神経の状態を反映するツボや反射区が集中しており、
“耳を見れば今の体調がわかる”といっても過言ではありません。
Kagayaは、訪問施術の際にも必ず耳をチェックし、その日の不調や体調の変化を読み取る手がかりとしています。
たとえば、以下のようなサインはとても重要です。
- 耳が赤くなっている:交感神経が過緊張。イライラ・焦り・不眠傾向があるサイン
- 耳が冷たく、むくみがある:「腎」の働きの低下、水滞傾向。冷え・排尿トラブル・むくみ体質の可能性
- 耳のシワ・乾燥・しぼみ:血虚、陰虚傾向。疲れやすい・肌がカサつく・月経トラブルが出やすい
- 左右差がある:一方の耳だけ赤み・むくみが強い場合は、片側の不調(肩こり・神経痛など)を示唆
また、耳の上部にある「神門(しんもん)」というツボは、自律神経の調整に関わる重要ポイント。
強いストレスや緊張、不安感が続くと、この部分が赤くなったり、腫れぼったくなったりします。
「最近イライラが続くな…」「眠りが浅いかも」と感じたとき、ぜひ鏡で耳を見てみてください。
そんな時は、以下の簡単なセルフケアがおすすめです。
- 両耳を軽くつまんで上下左右に引っ張る(5回ずつ)
- 耳全体を手のひらで包み、じんわり温める
- 神門あたりを親指でやさしく円を描くようにマッサージ
これらはすべて、リラックス神経(副交感神経)を優位にする働きがあり、深い呼吸や眠りにもつながります。
特別な器具や薬は必要ありません。
「耳をやさしく触れる」という行為そのものが、自分をねぎらうひとときになるのです。
さらに体調管理に活用したい方は、耳つぼシールやマグレイン(粒鍼)を活用するのも効果的です。
たとえば、以下のような用途があります。
- 神門(ストレス・不安・イライラ)
- 胃点(胃の疲れ・食べすぎ)
- 内分泌点(ホルモンバランス・PMS)
薬に頼りすぎず、自分で不調の波をととのえていける感覚。
それが、Kagaya式セルフケアの第一歩です。
次の章では、東洋医学でよく使われる「舌診(ぜっしん)」についてご紹介します。
舌診(ぜっしん)でわかる体の中の状態
「舌は体の鏡」とも言われるほど、東洋医学では大切な診察ポイントです。
私たちの体は、不調があると肌や目、声など様々なところにサインを出しますが、その中でも特に変化が出やすいのが「舌(ぜつ)」です。
舌診では、舌の色・形・苔(こけ)の状態・潤いの有無などを総合的に観察し、内臓の状態・エネルギー(気血)の流れ・水分バランスなどを判断します。
とくに次のような舌の特徴は、Kagayaが訪問ケアやセルフケア指導の際にチェックしている代表的なパターンです。
- 淡い舌+縁に歯の跡(歯痕舌): 脾の弱り、エネルギー不足(気虚)。疲れやすい、むくみやすい傾向。
- 厚く白い舌苔: 体内に冷えや水分が停滞している状態。水滞や痰湿のサイン。
- 舌の先が赤い: 心の熱が強い(心熱)。不安・不眠・イライラ・興奮しやすい。
- 舌苔が薄く剥がれている: 胃腸のエネルギー(気・津液)の消耗。乾燥・のぼせ・陰虚傾向。
- 舌が赤黒い・紫っぽい: 血の巡りが悪い(瘀血)。肩こり・月経痛・冷え・慢性疲労の可能性。
これらの変化は、「病院の検査では異常なし」と言われるけど不調が続く…といった「未病(みびょう)」のサインとして、とても有効です。
Kagaya自身も、朝起きたら必ず「舌を鏡でチェックする」習慣をつけています。
「今日はやたらと舌苔がべったりしているな…」という日は、冷たいものや甘いものを控えめにして、温かいおかゆや味噌汁を中心に。
「舌先が赤くてピリピリしている」と感じた日は、心を落ち着ける時間をとって、深呼吸や軽い運動、アロマなどを意識的に取り入れます。
このように、舌の変化を毎日の体調管理のバロメーターとして使うことができるのです。
とくに朝は、まだ食事や歯磨きの影響を受けていないため、舌の本来の状態が観察しやすいタイミング。
以下のように、ぜひ舌診を日々の習慣に取り入れてみてください。
- 朝起きてすぐ、鏡の前で舌を見る
- スマホで記録して比較する(連続観察がおすすめ)
- 気になる変化があれば、食事や生活の調整を
東洋医学の視点を持つと、「今日は無理をしない方がいい」「冷え対策を強化しよう」「ストレスをケアしよう」など、自分にやさしく寄り添う判断ができるようになります。
あなたもぜひ、舌という“体からの声”に耳を傾けてみてください。
次の章では、家庭で簡単にできるお灸(きゅう)ケアについてご紹介します。
お灸(セルフケア用)
「なんだか疲れが抜けない…」「冷えやだるさが続いている…」そんなとき、Kagayaがいちばんにおすすめするのがセルフ灸です。
お灸は、東洋医学で古くから用いられてきたセルフケアの代表格。
ツボ(経穴)に温熱刺激を与えることで、気血の巡りを整え、自然治癒力を高める働きがあります。
とくに「火を使うのが不安…」「初心者でよく分からない…」という方には、煙が少なく火傷しにくい『せんねん灸オフ』シリーズなどの温灸タイプがおすすめです。
Kagayaの訪問施術でも、ご家族の方と一緒に使い方をお伝えしたり、お灸の配置を相談しながら行う場面がよくあります。
自分でツボにお灸をすることで、「自分をいたわる時間」が自然と生まれます。
🌿 よく使うおすすめツボ3選
- 三陰交(さんいんこう): 内くるぶしから指4本分上。冷え、生理不順、むくみ、不眠など女性に多いお悩みに。
- 足三里(あしさんり): 膝のお皿の下、外側に指4本分。胃腸の疲れ、体力低下、足のだるさなどに。
- 関元(かんげん): おへそから指3~4本分下。下腹部の冷え、元気の不足、気血の強化に。
この3つのツボは、「とにかく迷ったらここから」という万能ツボ。1日1カ所だけでも、継続することでじんわりと体が変わっていくのを感じられる方が多いです。
🔥 セルフお灸のコツと注意点
- 入浴前後は避け、リラックスできる時間帯に
- 最初は週に2~3回からスタート
- 火の取り扱いに注意し、火災報知器の下では使わない
- 同じ場所に何度も繰り返さず、皮膚の状態を見ながら
- やけどやかぶれがある場合はすぐ中止を
「今日は冷えるな」「ちょっと疲れがたまってるな」そんなとき、温かいお灸の刺激は、心も体もゆるめてくれます。
Kagayaの訪問でも、「毎日続けたら手足がぽかぽかしてきた」「よく眠れるようになった」「便秘が改善した」という声をよくいただきます。
難しい技術や高価な道具は必要ありません。
やさしく、あたたかく、体に寄り添う──それが東洋医学のセルフケアの魅力です。
次の章では、生活習慣の中で意識できるちょっとしたケア方法をご紹介します。
生活アドバイス
からだを整えるには、「何をするか」だけでなく「どう暮らすか」がとても大切。
東洋医学では、五臓六腑の働きは生活習慣によって影響を受けると考えられています。
たとえば夜更かしが続くと「肝血」が不足したり、冷たいものばかり摂ると「脾胃」が弱ったり…。
日々のちょっとした癖や習慣が、知らず知らずのうちに不調を呼び込んでいることもあるのです。
Kagayaは、訪問施術やLINE相談でお話を聞く中で、次のようなアドバイスをよくお伝えしています。
🌿 Kagayaがすすめる日常ケア5選
- 午後のカフェインを控える:交感神経の興奮が夜まで残り、眠りが浅くなる原因に。午後は麦茶やハーブティーなどカフェインレスに切り替えるのがおすすめです。
- 冷たい飲み物を避け、白湯をこまめに:脾胃(消化器系)は冷えに弱い臓腑。常温~ぬるめの白湯をゆっくり飲むことで、内臓をやさしく温めることができます。
- 夜は湯船に10分以上つかる:交感神経優位で一日中がんばっていた体を、副交感神経へゆっくりシフト。湯船につかることで血流が促され、心身の緊張がほどけていきます。
- スマホ・PCは就寝1時間前にオフ:ブルーライトは脳の覚醒を促し、自律神経の乱れにつながります。照明も少し暗めにして、睡眠ホルモン(メラトニン)が自然に出る環境を整えましょう。
- 朝日を浴び、軽いストレッチからスタート:東洋医学では「朝は陽気が生まれる時間帯」。光を浴びて背伸びをするだけでも、体内時計が整い、気の巡りがよくなります。
どれも特別なことではなく、今日からすぐに取り入れられることばかり。
ですが、この「日常の小さな積み重ね」こそが、本当の体質改善や健康維持に大きく影響するのです。
東洋医学には「未病(みびょう)」という考え方があります。
これは「病気になる前の不調のサインを整えていく」というもの。
「不調まではいかないけど、なんだか最近調子が出ない…」というときこそ、生活を見直すタイミングです。
Kagayaのケアでも、施術よりも毎日の習慣が整ったときのほうが改善が早いという方がたくさんいらっしゃいます。
焦らなくて大丈夫です。まずは、できそうなことをひとつだけでも。
あなたの毎日が、少しずつ整っていきますように。
🛒 おすすめセルフケア商品
ここでは、Kagayaが実際に愛用しているセルフケアアイテムを3つご紹介します。
どれも訪問施術の現場や、セルフケア講座のなかで「これは取り入れやすい!」と好評をいただいているものばかり。
「ついスマホを見ながら寝落ちしてしまう」「自分のことは後回しになりがち」──そんな忙しい方でも、1日10分で気軽にできるケアばかりです。
東洋医学で大切にされている“気・血・水”の巡りを整えながら、自分自身の内側にやさしく意識を向けてみましょう。
1. めぐリズム 蒸気でホットアイマスク
夜勤明けや長時間のパソコン作業で目が疲れたとき、Kagayaが愛用しているアイテムです。
袋を開けるだけで発熱が始まり、じんわりとした蒸気が目の奥まで届いて、10分ほどでふわっと緊張がゆるみます。
東洋医学では、「目は肝に通ず」と言われており、目の疲れは肝血の不足やストレス過多のサインと考えられます。
目を温めることは肝のケアにもつながり、PMSやイライラが強い時期にもおすすめです。
とくに寝る前に使うことで、副交感神経が優位になり、自然と眠りやすくなります。
2. せんねん灸オフ 伊吹
「お灸は初めてで不安…」という方に一番おすすめしているのが、煙が少なくて扱いやすい温灸タイプの「せんねん灸オフ 伊吹」です。
Kagaya自身も毎晩のように足三里・三陰交に使用しており、足元がポカポカして眠りにつきやすくなります。
お腹の冷え、足のむくみ、気の巡りが滞っているときなど、1日1個のお灸でも体が変わっていくのを実感できます。
3. アロマディフューザー&柑橘系精油
PMSや不安感、ストレスが強いときに、Kagayaがよく使うのがベルガモットやオレンジの精油。
柑橘系の香りは「肝の気」をめぐらせる作用があり、東洋医学的にも理気(りき)=気を巡らせるケアになります。
ネブライザー式のアロマディフューザーは水を使わず精油本来の香りを楽しめるので、より効果的。
就寝前の5分だけでも、気持ちがすっと落ち着きます。
嗅覚は脳の深部に直接届く感覚。五感の中で最も早く「安心」を届けてくれる手段のひとつです。
🏠 Kagayaの訪問ケア/シェアサロン施術について
Kagayaは、東京都小平市を拠点に「鍼灸+看護」の視点を活かした訪問ケアサービスを行っています。
ご高齢の方や障がいのあるお子さま、持病で通院が困難な方など、外出が難しい方にこそ「その人らしいケア」を届けたい──。
そんな想いから、ご自宅でゆっくりとお話を伺いながら、生活に寄り添った施術を行っています。
💡 訪問ケアの特徴
- 小平市・東村山・東大和・東久留米・国分寺・立川エリアに対応
- 鍼灸師・看護師のダブルライセンスで安心のケア
- 東洋医学+看護の視点から「心身まるごと」にアプローチ
- 医療的ケア児や在宅療養中の方にも対応可能
- ご家族の不安にも寄り添う看護的支援
訪問時には、耳・舌・腹部などの状態を丁寧に確認し、東洋医学的な見立て(四診)に基づいた施術を行います。
鍼や灸が難しい場合は、てい鍼や温熱・経絡マッサージを用い、できるだけ負担の少ない方法で整えていきます。
また、訪問先の状況に合わせてベッド上での施術や、座位・車いすのままでも対応可能です。
🩺 訪問ケアの対象となる方
- 症状を丁寧にみてほしい方/他の治療法で改善しなかった方
- 医療的ケアが必要なお子さんも対応可能(胃ろう・気管切開など)
- 心身の発達に課題のあるお子さん(発達障がい・重症心身障がい)
- 外出が困難な方や、ご高齢の方の在宅サポート
- 育児や介護で通院が難しい方のメンテナンス
「自宅に来てもらえるだけで、安心できた」「施術だけでなく、生活面のアドバイスがありがたい」──そんなお声を多くいただいています。
🌿 小平市内のシェアサロン施術
また、通院が可能な方には、小平市・東久留米市内のシェアサロンにて耳つぼセッション/舌診+体質カウンセリングをご提供しています。
カウンセリング+施術を組み合わせることで、気の滞りや冷え、消化器の不調、生理前後の不調(PMS・PMDD)などにも対応。
安心できる空間で、ゆっくりとご自身の体と向き合う時間をお届けします。
施術内容は、お悩みに応じて以下を組み合わせてご提案しています:
- 耳つぼ貼付(パイオネックス・粒)
- 温灸(せんねん灸)による気血の巡り改善
- 舌・腹・耳からの体質カウンセリング
- 必要に応じて養生アドバイスや食事提案
とくにストレス・疲労・PMS・睡眠トラブル・便秘・冷えなどでお悩みの方におすすめです。
どちらの施術でも、無理なことは一切いたしません。
お話をしながら、ご自身のペースでゆったりと受けていただけます。
「どんなことをするのか不安」「まずは相談だけでも…」という方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら