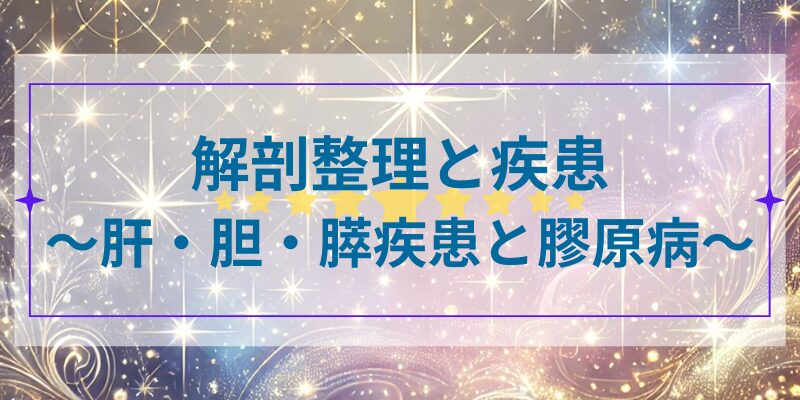肝臓
- 栄養が含まれる血液がたくさん運ばれる
- 前面
- 横隔膜の下にある
- 肝鎌状間膜⇒右葉と左葉を分ける膜
- 右葉⇒厚くて大きい
- 左葉⇒薄くて小さい
- 底面
- 底面を臓側面という
- 肝門⇒血管などが出入りする
- 肝門を通る管
- 肝静脈→下大静脈→心臓→全身
- 門脈
- 栄養が豊富に含まれる
- 静脈血が集められる
- 上腸間膜静脈
- 小腸、上行結腸
- 横行結腸
- 下腸間膜静脈
- 横行結腸、下行結腸
- S上結腸、上部直腸
- 脾静脈
- 胃、膵臓
- 脾臓
- 固有肝動脈
- 酸素などの栄養を含む
- 動脈血が集められる
- 大動脈弓→胸部大動脈→腹部大動脈→腹腔動脈(左胃動脈、脾動脈)→総肝動脈(胃十二指腸動脈)
- 肝管
- 肝臓で作られた胆汁が送り出されるところ
- 胆嚢は一時的に胆汁を蓄えるところ
- 肝管→総胆管(⇔胆嚢管)→十二指腸乳頭→小腸
- 出入りする血管
- 肝臓を養う動脈と栄養を豊富に含む静脈
- 類洞(洞様毛細管)
- 肝細胞索の間にある毛細血管で肝静脈に流れる
- 栄養血管
- 肝細胞に酸素などの栄養を与えている
- 肝臓に入ると小葉間動脈に枝分かれする
- 肝血流の30%を占める
- 固有肝動脈⇒小葉間動脈⇒類洞⇒中心静脈⇒肝静脈⇒下大静脈
- 機能血管
- 栄養を運んで代謝という肝臓の機能に関わる
- 肝臓に入ると小葉間静脈に枝分かれする
- 肝血流の70%を占める
- 門脈⇒小葉間静脈⇒類洞⇒中心静脈⇒肝静脈⇒下大静脈
- 肝臓の基本単位
- 肝臓は直径1mmほどの肝小葉の集合体
- グリソン鞘
- 小葉間動脈
- 小葉間静脈
- 小葉間胆管
- 肝小葉の細胞
- 肝細胞が中心静脈を中央に放射状に並ぶ
- 肝細胞
- 胆汁を作る
- 1つの肝小葉に50万個の存在する
- 中心静脈に向かって放射状に並ぶ列を肝細胞索という
- 肝細胞索は板状の肝細胞板を作る
- クッパ―細胞
- 類洞の壁に存在する
- 肝臓に入った異物を分解して処理する
- マクロファージの一種
- 星細胞
- ディッセ腔に存在⇒類洞と肝細胞の間
- ビタミンA貯蔵細胞ともいう
糖代謝
- 代謝
- 三大栄養素⇒ATP(アデノシン三リン酸)⇒加水分解(アデノシン二リン酸)⇒エネルギー発生
- 糖代謝の流れ
- 小腸⇒糖質をグルコースなどの単糖類に変換
- 門脈⇒肝臓へ運ばれる
- 肝臓⇒多くの単糖類をグルコースに変換し血液中に放出
- グルコースは全身の細胞でATPとして利用される
- 単糖類
- グルコース
- フルクトース
- ガラクトース
- 血糖値
- 肝臓は血糖値の調節をしている
- 血糖値が十分な時は肝臓でグルコース同士をくっつけてグリコーゲンとして肝細胞にためる
- 血糖値が低い(低血糖)時はグリコーゲンを分解してグルコースを血中に放出する
- 血糖値が異常に下がったとき
- 血糖値低下
- 筋肉
- エネルギーを得るためにピルビン酸を分解する
- 乳酸が肝臓に運ばれる
- 筋肉のタンパク質を分解してアミノ酸をつくる
- アミノ酸が肝臓に運ばれる
- エネルギーを得るためにピルビン酸を分解する
- 脂肪組織
- エネルギー源となるトリグリセリドを分解する
- グリセリンが肝臓に運ばれる
- エネルギー源となるトリグリセリドを分解する
- 運ばれた物質から肝臓はグルコースをつくる
- 糖新生⇒糖質以外の物質からグルコースを合成すること
タンパク質代謝
- タンパク質を分解して身体に必要なものを合成する
- 必須アミノ酸
- 体内で合成できない
- 食事などで外から摂り入れる必要がある
- タンパク質は小腸でアミノ酸に分解される
- 非必須アミノ酸
- 体内で合成できる
- 必須アミノ酸やグルコースから作られる
- 肝臓はアミノ酸を全身に供給して、細胞でタンパク質を合成している
- 血漿タンパク質⇒肝臓が作っている
- アルブミン
- 血管内に水を引き付ける働きがある
- 水に溶けにくい物質の輸送をおこなう
- フィブリノゲン(血液凝固因子)
- 止血のために血液凝固をおこす
- アルブミン
- 古くなったタンパク質の処理
- アミノ酸に分解される
- アミノ酸は新しいタンパク質が合成されるときに再利用されたり(リボソーム)、分解されエネルギー源として利用される
- エネルギーを取り出す時に発生したアンモニアは肝臓で無害な尿素に変換される
- 尿素は血流にのって腎臓にいき、尿中に排泄される
脂質代謝
- 脂質代謝
- 乳化させる
- 脂質+胆汁=乳化(ミセル化)
- 胆汁に含まれる胆汁酸によって脂質を膵液になじみやすくする
- 脂質+膵リパーセ
- 膵液中に脂質を分解する消化酵素と脂質がなじみにくい
- ミセルを形成して水に溶けやすくする
- 脂質
- トリグリセリド
- 脂質で一番多い
- 中性脂肪にあたる
- グリセリンに3つの脂肪酸が結合している
- トリグリセリドの分解
- 膵リパーセによって分解され、脂肪酸が1つになってモノグリセリドになる
- 脂肪酸とモノグリセリドが小腸上皮で吸収されたあとにトリグリセリド(脂質)に再合成し、リンパ管へ行く
- リン脂質
- 細胞膜をつくる
- リン酸は親水基にあたる
- コレステロール
- 細胞膜をつくる
- ステロイドホルモンをつくる
- 胆汁をつくる
- トリグリセリド
- 脂質の運搬
- 消化管からきたものが肝臓で加工されて全身に運ばれる
ビリルビン代謝
- ビリルビン
- 古い赤血球を使用してつくられる胆汁成分
- 間接ビリルビンは肝臓で変化する
- 120日経過した古い赤血球⇒硬くなって変形できない
- 脾臓のマクロファージ⇒古くなった赤血球を食べて分解する
- ヘモグロビンの分解
- ヘム
- 鉄
- 脾臓で貯蔵
- トランスフェリンによって骨髄や肝臓に運ばれる
- ビリルビン
- 間接ビリルビン
- ヘムから分解されたばかりのビリルビン
- 水に溶けにくく血液中を移動できない
- 間接ビリルビン
- 鉄
- グロビン(タンパク質)
- アミノ酸として再利用
- ヘム
- 直接ビリルビン⇒直接ビリルビン
- 脾臓⇒間接ビリルビンをアルブミンが運ぶ
- 肝小葉(小葉間静脈を通る)
- 類洞で直接ビリルビンはアルブミンと分かれて肝細胞へ行く
- 肝細胞にいるグルクロン酸とグルクロン酸抱合する
- 水に溶けやすい直接ビリルビンになり、胆汁の中に出されて毛細胆管に分泌
- 胆汁の流れ⇒胆嚢で蓄えられて食物がくると一気に分泌
- 胆汁は左右の肝管を通り肝臓の外へ出る
- 総胆管、胆嚢管を通り、胆嚢に一時的に蓄えられて濃縮
- 食べ物が十二指腸を通過するときコレシストキニンの作用で胆嚢が収縮
- 胆汁は胆嚢管を通って十二指腸に分泌される
- 胆汁の成分⇒水、胆汁酸、直接ビリルビン、コレステロール
- 胆汁の中にある胆汁酸が脂肪の吸収を助ける
- 胆汁の成分⇒水、胆汁酸、直接ビリルビン、コレステロール
肝•胆•膵の問題
腸管とその構造との組合せで正しいのはどれか。
- 空腸 ───── 腸腺
- 回腸 ───── 腹膜垂
- 十二指腸 ─── 腸間膜
- 横行結腸 ─── 腸絨毛
間膜と付着部との組合せで正しいのはどれか。
- 肝冠状間膜 ─── 横隔膜
- 大網 ────── 空腸
- 腸間膜 ───── 腎臓
- 小網 ────── 脾臓
正しいのはどれか。
- 肝静脈は上大静脈に開口する。
- 膵管は肝管と合流し大十二指腸乳頭に開口する。
- グリソン鞘には動脈・静脈・胆管の三つ組が見られる。
- 胆汁は胆嚢で産生される。
正しい記述はどれか。
- 門脈は肝門に入る。
- 胃の角切痕は大弯にある。
- 腹膜垂は小腸にみられる。
- 大腸には内腔に輪状ヒダがある。
肝臓について正しい記述はどれか。
- 栄養血管は門脈である。
- 右葉と左葉とは同じ大きさである。
- 肝静脈は直接下大静脈に注ぐ。
- 全面を腹膜で包まれる。
肝臓について正しいのはどれか。
- 肝静脈は肝門を通る。
- 実質はグリソン鞘により肝小葉に分けられる。
- 右葉よりも左葉の方が大きい。
- 肝鎌状間膜は方形葉と尾状葉の間にある。
肝臓の血管系について正しい記述はどれか。
- 中心静脈は小葉間静脈へ注ぐ。
- 門脈には動脈血が流れる。
- 肝静脈は肝門を通る。
- 洞様毛細血管(類洞)は中心静脈へ注ぐ。
肝臓について正しい記述はどれか。
- 肝静脈は肝門から出る。
- 肝鎌状間膜は方形葉の右側に位置する。
- 中心静脈は小葉間静脈へ注ぐ。
- 胎生期の静脈管は臍静脈血を下大静脈に導く。
肝機能で正しいのはどれか。
- セクレチンの合成
- ガストリンの分泌
- グリコーゲンの合成
- ムチンの分泌
肝臓の働きについて誤っているのはどれか。
- 胆汁の生成
- ガンマグロブリンの合成
- アルブミンの合成
- コレステロールの生成
胆汁の流路で誤っている記述はどれか。
- 総胆管は十二指腸に開口する。
- 総胆管は胃の前を通る。
- 肝管と胆嚢管とが合流して総胆管となる。
- 肝管は肝門を通る。
胆汁の流れが一方向でないのはどれか。
- 胆嚢管
- 肝管
- 総胆管
- 小葉間胆管
胆汁酸の作用はどれか。
- 蛋白質分解
- 糖質分解
- ビリルビン生成
- 脂肪乳化
腸管からの吸収に際して胆汁酸と共にミセルを形成するのはどれか。
- アミノ酸
- 電解質
- ブドウ糖
- 脂肪酸
胆汁について誤っている記述はどれか。
- 胆汁色素はビリルビンである。
- 消化酵素を含む。
- 胆汁酸を含む。
- 十二指腸に排出される。
胆汁について誤っている記述はどれか。
- 肝臓で産生される。
- 脂肪の消化・吸収に働く。
- 分泌は迷走神経によって調節される。
- 消化酵素を含んでいる。
低蛋白血症時に起こらないのはどれか。
- 血液凝固の促進
- 浮腫
- 易感染性
- 細胞へのアミノ酸供給の減少
脂肪の消化に関与しないのはどれか。
- リパーゼ分泌
- 乳化作用
- アミラーゼ分泌
- 胆汁分泌
解糖系で生成される高エネルギー化合物はどれか。
- ピルビン酸
- 乳酸
- グリコーゲン
- ATP
解糖について正しい記述はどれか。
- 炭酸ガスが発生する。
- ミトコンドリアの中で起こる。
- ブドウ糖の加水分解の過程である。
- 無酸素的に起こる。
健常成人の体内で合成されないのはどれか。
- トリプトファン
- グリコーゲン
- トリグリセリド
- コレステロール
脂質について正しい記述はどれか。
- 脂肪酸は主に解糖系で代謝される。
- 脂質は蛋白質と結合した形で血液中を運搬される。
- コレステロールはサイロキシンの前駆物質である。
- 中性脂肪は1分子のグリセロールと5分子の脂肪酸からなる。
脂質について正しい記述はどれか。
- 酵素で分解されて脂肪酸とグリセリンになる。
- 水溶性物質である。
- グリセリンはβ酸化されてATPを産生する。
- 細胞膜を構成する材料とならない。
脂質について正しいのはどれか。
- リン脂質はヘモグロビンの構成成分である。
- コレステロールはコルチゾールの前駆物質である。
- 脂肪酸の多くは水溶性物質である。
- 中性脂肪は1分子のグリセロールと2分子の脂肪酸からなる。
グルコースについて正しいのはどれか。
- 蛋白質の合成に利用される。
- グリセロールから合成される。
- 多糖類である。
- ミトコンドリアで分解される。
コレステロールについて正しいのはどれか。
- 膵臓で合成される。
- 皮下脂肪の主成分である。
- 単純脂質である。
- 細胞膜に含まれる。
1分子のグルコースから最も多くのATPを合成するのはどれか。
- ローマン反応
- クエン酸回路
- 電子伝達系
- 解糖系
ATPに含まれるのはどれか。
- チミン
- アクチン
- リン酸
- デオキシリボース
糖新生の材料になるのはどれか。
- グリコーゲン
- マルトース
- アミノ酸
- ガラクトース
解糖について正しいのはどれか。
- クエン酸が生成される。
- 酸素を必要とする。
- 細胞質内で行われる。
- 電子伝達系に比べATP産性能が高い。
血糖について誤っているのはどれか。
- グリコーゲンとして貯えられる。
- エネルギー源となる。
- 食欲に関係する。
- グルカゴンの作用により減少する。
ペプチド結合を有する物質はどれか。
- 蛋白質
- ビタミン
- 脂質
- 炭水化物
蛋白質について正しいのはどれか。
- 細胞膜には含まれない。
- 4種類のアミノ酸からなる。
- 細胞の主要な構成成分である。
- β酸化により代謝される。
ウイルス性肝炎
- 共通症状
- 全身倦怠感
- 食欲不振
- 黄疸
- 肝腫大
- A型
- 経口感染
- 生ガキなどの生鮮魚介類の摂取
- 治癒しやすい
- 発熱の前駆症状
- 集団発生を起こすことがある
- IgMーHA抗体陽性
- B型
- 血液感染(針刺し事故)
- 性感染
- 母子感染(垂直感染)
- 劇症化しやすい
- DNAウイルス
- 自覚症状がほとんどない
- 感染した場合は抗HB免疫グロブリン投与
- HBs抗原陽性(感染状態)
- HBe抗原陽性(感染力が強い)
- C型
- 血液感染(輸血)
- 慢性化しやすい
- ワクチン予防ができない
- HCV-RNAが陽性
- D型
- 血液感染
- E型
- 経口感染
- イノシシなど獣肉の生食
肝硬変
- 肝臓全体が線維化する病態
- 線維化
- 細胞が減る
- 機能低下、不全
- 構造が崩れる
- 血行障害
- 縮む
- 肝臓が小さくなる
- 細胞が減る
- 進行過程
- C型肝炎
- 慢性肝炎
- 線維化が始まる
- クモ状血管拡張
- 手掌紅斑
- 代償期
- 特異的な症状を伴わない
- 非代償期
- 門脈圧亢進症
- 門脈血の流れが障害される⇒門脈圧が亢進し、症状が出る
- 食道静脈瘤
- 胃静脈瘤
- 痔核
- メズサの頭
- 脾腫
- 汎血球減少症、貧血
- 腹水、浮腫
- 肝機能不全
- 門脈圧亢進症
- 肝機能低下
- 糖代謝
- 食後高血糖、空腹時低血糖
- タンパク質代謝
- アルブミン
- 低アルブミン血症(浮腫、腹水)
- フィブリノゲン
- プロトロンビン時間延長(出血傾向)
- アルブミン
- コレステロール合成
- 低コレステロール血症
- エストロゲン分解
- 手掌紅斑
- クモ状血管腫
- 女性化乳房、睾丸縮小
- ビリルビン代謝
- 黄疸
- アンモニア解毒作用
- 肝性脳症
- 糖代謝
膵癌
- 好発
- 高齢男性
- 危険因子
- 糖尿病
- 慢性膵炎
- 喫煙
- アルコール
- 発生部位
- 膵頭部癌が最も多い
- 膵管上皮に発生
- 特徴
- 膵頭部癌は比較的早期に閉塞性黄疸が現れる
- 内分泌腫瘍はまれ
- 腫瘍マーカー
- CA19-9
膵炎
- 腺房細胞の自己消化が起こる疾患
- 急性膵炎
- 原因
- アルコール
- 症状
- 上腹部痛
- 背部痛
- 悪心、嘔吐
- 座位前屈で軽減する背部痛(仰臥位で増強)
- 検査
- 血清、尿中のアミラーゼ上昇
- リパーゼ上昇
- 原因
- 慢性膵炎
- 代償期
- 急性膵炎の症状⇔症状がない時を繰り返す
- 非代償期
- 線維化が進行し、自己消化もおこらず、腹痛もない
- 脂肪下痢
- 二次性糖尿病
- 石灰化現象(膵石)
- 代償期
胆石症
- 好発
- 40歳代肥満女性
- 原因
- 胆嚢の急激な収縮(空腹時の暴食、高脂肪食の摂取)
- 夜間に多い
- 組成
- 胆汁中のコレステロールやビリルビン、カルシウム
- 症状
- 胆石発作
- 心窩部から右季肋部に強い痛み(疝痛)
- 右肩に放散
- 黄疸
- 診断
- アルカリフォスファターゼ(ALP)上昇
- 高ビリルビン血症
- γ-GTP上昇
肝・単・膵の疾患問題
疾患と痛みが放散する部位との組合せで誤っているのはどれか。
- 尿管結石 ───── 鼡径部
- 胆石症 ────── 右肩
- 狭心症 ────── 左肩
- 十二指腸潰瘍 ─── 右肩
疾患と検査との組合せで誤っているのはどれか。
- 胆石症 ──── 超音波検査
- 大腸癌 ──── 便潜血反応
- 肝癌 ───── CT検査
- 急性膵炎 ─── 内視鏡検査
疾患と危険因子との組合せで正しいのはどれか。
- 肝細胞癌 ─── ウイルス感染
- 喉頭癌 ──── 細菌感染
- 肺癌 ───── 飲酒
- 大腸癌 ──── 高繊維食摂取
ウイルス性肝炎と感染経路の組合せで正しいのはどれか。
- B型 ─── 性行為
- C型 ─── 獣肉摂取
- A型 ─── 血液への暴露
- E型 ─── 生鮮魚介類摂取
ウイルス性肝炎と感染経路の組合せで正しいのはどれか。
- C型 ――― 血液への曝露
- B型 ――― 獣肉摂取
- E型 ――― 生鮮魚介類の摂取
- A型 ――― 性行為
疾患と症状の組合せで正しいのはどれか。
- 慢性膵炎 ―――――― 便秘
- 過敏性腸症候群 ――― 血便
- 肝硬変 ――――――― 女性化乳房
- 急性胆囊炎 ――――― 左季肋部痛
正しいのはどれか。
- 急性膵炎では血清アミラーゼ値が下降する。
- B型肝炎は血液を介して感染する。
- 胆石は水に溶解しやすい。
- A型肝炎は細菌の感染による。
肝炎について正しい記述はどれか。
- C型肝炎は慢性化しやすい。
- A型肝炎は慢性化しやすい。
- A型肝炎は輸血で起こりやすい。
- 急性B型肝炎は慢性化しやすい。
肝炎の感染経路で正しいのはどれか。
- C型肝炎は生鮮魚介類の摂取で感染する。
- A型肝炎は血液で感染する。
- E型肝炎は母子感染する。
- B型肝炎は性行為で感染する。
最も治りやすい肝炎はどれか。
- A型肝炎
- 劇症肝炎
- B型肝炎
- C型肝炎
A型肝炎について誤っているのはどれか。
- 劇症化しやすい。
- 経口感染する。
- ワクチンにより予防できる。
- 集団発生を起こす。
B型肝炎について正しい記述はどれか。
- 垂直感染がみられる。
- 慢性肝炎からは肝硬変に進展しにくい。
- 成人の初感染は慢性化しやすい。
- HBe抗原陽性では感染力が弱い。
C型急性肝炎について正しい記述はどれか。
- 高熱がみられる。
- 経口感染である。
- 劇症化はまれである。
- 慢性化はない。
C型肝炎で適切でない記述はどれか。
- 肝硬変に移行しやすい。
- 経口感染する。
- 食欲不振がある。
- 肝腫大がある。
ウイルス性肝炎で生の貝類の摂取により最も感染しやすいのはどれか。
- E型
- A型
- C型
- B型
経口感染するウイルス性肝炎はどれか。
- E型
- C型
- D型
- B型
ウイルス性肝炎に関して正しい記述はどれか。
- B型はDNAウイルスによる。
- C型はワクチンで予防できる。
- A型は輸血で感染する。
- E型は慢性化しやすい。
急性ウイルス性肝炎で正しいのはどれか。
- C型肝炎では劇症化することが多い。
- B型肝炎では垂直感染はみられない。
- A型肝炎では発熱がよくみられる。
- E型肝炎では生鮮魚介類摂取が原因となることが多い。
「施術後、患者の血液のついた鍼を廃棄する時に誤って施術者の指に刺さった。」 鍼刺し事故後、感染率が最も高いのはどれか。
- 成人T細胞白血病
- C型肝炎
- HIV感染症
- B型肝炎
「施術後、患者の血液のついた鍼を廃棄する時に誤って施術者の指に刺さった。」 HBウイルス陽性患者であった場合の対応で最も適切なのはどれか。
- 抗HB免疫グロブリン投与
- HBワクチン投与
- 穿刺部位のアルコール消毒
- 抗生物質の投与
肝硬変で誤っているのはどれか。
- 手掌紅斑を生じる。
- 肝が肥大する。
- 腹水を生じる。
- 食道静脈瘤を生じる。
肝硬変の症状でないのはどれか。
- 皮膚線条
- メズサの頭
- クモ状血管腫
- 手掌紅斑
非代償性肝硬変でみられる血液検査所見はどれか。
- 血小板減少
- アルブミン値上昇
- プロトロンビン時間短縮
- 総ビリルビン値低下
肝性昏睡にみられない症状はどれか。
- 下肢対麻痺
- はばたき振戦
- アンモニア口臭
- 傾眠傾向
膵管上皮由来の膵臓癌でみられないのはどれか。
- CEA陽性
- 黄疸
- 背部痛
- 低血糖
慢性膵炎で正しい記述はどれか。
- 便秘が多い。
- 病初期より糖尿病が発症する。
- 腹部超音波検査で石灰化像がみられる。
- 胆石によるものが多い。
急性膵炎で最も多いのはどれか。
- 胆石性膵炎
- 薬剤性膵炎
- 自己免疫性膵炎
- アルコール性膵炎
急性膵炎で誤っている記述はどれか。
- 激烈な心窩部痛がある。
- 尿中アミラーゼ値が上昇する。
- 飲酒家に多い。
- 血清アミラーゼ値が下降する。
急性膵炎の原因で最も多いのはどれか。
- 膵癌
- アルコール多飲
- 胆石
- 脂質異常症
膵癌について誤っている記述はどれか。
- 膵腺房細胞から発生することが多い。
- 血清腫瘍マーカーとしてCA19-9を用いる。
- 膵頭部癌では閉塞性黄疸をきたしやすい。
- 高齢の男性に多い。
膵癌について正しいのはどれか。
- 膵尾部癌では早期に症状が現れる。
- CA19-9は診断的価値が高い。
- 内分泌腫瘍が多い。
- 膵体部に好発する。
膵臓癌で適切でない記述はどれか。
- 血清アミラーゼ値が低下する。
- 食欲不振がある。
- 体重減少がある。
- 心窩部痛を起こしやすい。
膵癌のリスクファクターでないのはどれか。
- 慢性膵炎
- 高血圧
- 喫煙
- 糖尿病
胆石症で適切でないのはどれか。
- コレステロール結石
- ビリルビン結石
- 黄疸
- アルカリフォスファターゼ値低下
胆嚢癌について正しいのはどれか。
- 左季肋部痛が多い。
- AFPの上昇がみられる。
- 女性に多い。
- 胆石の合併は少ない。
40歳の肥満女性。右季肋部の疝痛と発熱、黄疸が認められた。最も考えられるのはどれか。
- 肝硬変
- 腎結石
- 膵尾部癌
- 総胆管結石
汎血球減少がみられるのはどれか。
- 肝硬変
- 関節リウマチ
- 溶血性貧血
- 重症筋無力症
「施術後、患者の血液のついた鍼を廃棄する時に誤って施術者の指に刺さった。」 誤刺および感染を回避する方法として適切でないのはどれか。
- 単回(1回)使用毫鍼を使用する。
- 手指の消毒には20%(体積百分率)イソプロピルアルコールを用いる。
- 施術には指サックを使用する。 使用後の鍼は感染性廃棄物として専用容器に捨てる。
- 使用後の鍼は感染性廃棄物として専用容器に捨てる。
肋骨脊柱角に叩打痛がみられるのはどれか。
- 慢性胃炎
- 腎盂腎炎
- 急性肝炎
- 慢性膵炎
「60歳の男性。軽度呼吸困難で来院。腹部膨隆と女性化乳房とがみられ、上部消化管内視鏡検査で食道・胃静脈瘤を認める。血液検査で血小板と白血球に減少が認められ、C型肝炎ウイルス陽性であった。」 この疾患で血小板減少をきたす原因となる病変臓器はどれか。
- 腎臓
- 肺
- 脾臓
- 肝臓
「60歳の男性。軽度呼吸困難で来院。腹部膨隆と女性化乳房とがみられ、上部消化管内視鏡検査で食道・胃静脈瘤を認める。血液検査で血小板と白血球に減少が認められ、C型肝炎ウイルス陽性であった。」 この疾患に合併する悪性腫瘍の早期発見に有用な腫瘍マーカーはどれか。
- CEA
- AFP
- PSA
- CA19-9
「55歳の女性。夕食にてんぷらを摂取後、悪心、嘔吐、右季肋部痛が出現し、救急外来を受診した。血液検査データで白血球数19,500/μl、CRP高値、赤沈亢進を認めた。」本患者で予測される所見はどれか。
- 打診で肋骨脊柱角に叩打痛がある。
- 聴診で血管雑音が聴取される。
- 触診で筋性防御がみられる。
- 視診で皮膚線条がみられる。
「55歳の女性。夕食にてんぷらを摂取後、悪心、嘔吐、右季肋部痛が出現し、救急外来を受診した。血液検査データで白血球数19,500/μl、CRP高値、赤沈亢進を認めた。」本患者でまず行う検査はどれか。
- 血管造影検査
- 腹部超音波検査
- PET(ポジトロンCT)検査
- 消化管内視鏡検査
「50歳の男性。大酒家である。軽度の意識障害で受診した。眼球の黄染、胸部のクモ状血管拡張と著明な腹水がみられた。また、上肢の不規則な運動が認められた。」 本症例でみられる上肢の所見はどれか。
- 振戦
- けいれん
- アテトーゼ
- バリスム
「50歳の男性。大酒家である。軽度の意識障害で受診した。眼球の黄染、胸部のクモ状血管拡張と著明な腹水がみられた。また、上肢の不規則な運動が認められた。」 本疾患でよくみられる合併症はどれか。
- 食道静脈瘤
- 大動脈瘤
- 大腸憩室炎
- マロリー・ワイス症候群
脂肪肝に関係ないのはどれか。
- 肝硬変
- 胆嚢ポリープ
- 肥満
- 糖尿病
「35歳の女性看護師。皮膚の黄染、全身倦怠感にて受診。針刺しの既往がある。肝炎ウイルスマーカーでは、HCV抗体陽性、HCV-RNA陽性で、他は陰性であった。」 本疾患について正しいのはどれか。
- 慢性化の頻度が高い。
- ワクチン予防が可能である。
- 生ガキの摂取で起こる。
- 劇症肝炎へ進展しやすい。
「35歳の女性看護師。皮膚の黄染、全身倦怠感にて受診。針刺しの既往がある。肝炎ウイルスマーカーでは、HCV抗体陽性、HCV-RNA陽性で、他は陰性であった。」 本疾患に合併する悪性腫瘍で上昇する腫瘍マーカーはどれか。
- CA125
- CEA
- AFP
- SCC
予防接種が有効な感染症はどれか。
- C型肝炎
- 腸チフス
- 猩紅熱
- 百日咳
「55歳の女性。2か月前から背部の鈍痛が続いていたが放置していた。発熱はないが、食欲不振、体重減少、倦怠感がある。」 最も疑われる疾患はどれか。
- 腎盂腎炎
- 子宮筋腫
- 膵臓癌
- 尿路結石
「55歳の女性。2か月前から背部の鈍痛が続いていたが放置していた。発熱はないが、食欲不振、体重減少、倦怠感がある。」 行うべき検査で最も適切なのはどれか。
- 尿沈渣
- 血液像(白血球分画)
- 腹部超音波検査
- 腹部エックス線検査
膠原病
- 全身の膠原繊維にフィブリノイド変性による病変が見られる疾患群の総称
- 共通症状
- 発熱
- 関節痛
- 筋肉痛
- 全身倦怠感
- 易疲労性
- 体重減少
- 検査
- 血中自己抗体の出現
- 赤沈亢進
- CRP陽性
関節リウマチ
- 女性に多く、関節を主病証として全身の支持組織を多発性におかす慢性の炎症性疾患
- 関節症状
- 滑膜の異常⇒朝のこわばり
- 関節痛⇒対称性関節腫脹
- 近位指節間関節
- 多発性の関節炎
- 関節の破壊
- 変形
- スワンネック変形
- ボタン穴変形
- 尺側偏位
- 強直
- 関節外症状
- 皮下結節
- 間質性肺炎(肺線維症)
- 血液・血清検査
- 血液炎症所見
- 赤血球減少(貧血)
- 自己抗体
- リウマトイド因子
- 抗CCP抗体(抗環状シトルリン化ペプチド)
膠原病の特徴的な症状
- 全身性エリテマトーデス
- 蝶形紅斑
- 口腔、鼻腔潰瘍
- 痙攣
- 脱毛
- 日光過敏症
- 全身性硬化症
- レイノー現象
- 皮膚硬化
- ソーセージ様手指
- 皮膚筋炎
- ヘリオトロープ疹
- ゴットロン徴候
- ベーチェット病
- 口腔内アフタ性潰瘍
- ぶどう膜炎
- 外陰部潰瘍
全身性エリテマトーデス(SLE)
- 20~40代の女性に好発し、多彩な自己抗体と免疫複合体沈着による全身多臓器病変を特徴とし、増悪と寛解を繰り返す慢性炎症性疾患
- 症状
- 皮膚粘膜症状
- 蝶形紅斑
- 口腔、鼻腔潰瘍
- 脱毛
- 日光過敏症
- 関節症状
- 臓器症状
- 腎臓(ループス腎炎)
- 神経(痙攣)
- 肺
- 皮膚粘膜症状
- 自己抗体
- 抗核抗体
- 抗DNA抗体
- 抗Sm抗体
- リウマトイド因子
- 検査
- 白血球減少
- 貧血
- 血小板減少
- 補体価低下
- 高γグロブリン
- LE細胞減少
ベーチェット病
- 4つの主症状の他、全身の諸臓器に急性炎症発作を繰り返しながら慢性の経過をたどる難治性疾患
- 20~40代に好発
- 性差なし
- 4つの症状
- 口腔内アフタ性潰瘍
- ブドウ膜炎
- 外陰部潰瘍
- 皮膚症状(結節性紅斑、毛嚢炎)
- HLA検査
- HLA-B51の陽性率が高い
全身性硬化症(強皮症)
- 皮膚硬化と血管病変(レイノー現象、小血管障害)を特徴とし、全身の結合組織に炎症と変性が起こる慢性炎症性疾患
- 女性に多い
- 食道病変(逆流性食道炎)
- 肺病変(肺線維症)
- 症状
- 皮膚硬化⇒ソーセージ様手指
- 血管病変⇒レイノー現象
- 血清免疫検査
- 抗ScI-70抗体陽性
- 抗核抗体陽性
- 高γ-グロブリン血症
多発性筋炎・皮膚筋炎
- 横紋筋を広範に障害する慢性炎症性筋疾患で、近位筋群の筋力低下を主張とする
- 筋症状
- 近位筋群の対称性筋力低下
- 皮膚症状
- 紅斑性皮疹⇒ヘリオトロープ疹、ゴットロン徴候
- 悪性腫瘍を合併しやすい
膠原病問題
疾患と症状との組合せで正しいのはどれか。
- ベーチェット病 ─── 口腔内アフタ性潰瘍
- 悪性リンパ腫 ──── レイノー現象
- 再生不良性貧血 ─── ハンター舌炎
- 皮膚筋炎 ────── 陰部潰瘍
疾患と検査結果との組合せで適切なのはどれか。
- 全身性硬化症 ─── HLA-B51陽性
- 関節リウマチ ─── CRP値上昇
- 悪性貧血 ───── ビタミンB6欠乏
- 悪性リンパ腫 ─── フィラデルフィア染色体陽性
疾患と検査所見との組合せで誤っているのはどれか。
- 慢性関節リウマチ ────── LE細胞現象陽性
- 痛風 ──────────── 血清尿酸値上昇
- 全身性エリテマトーデス ─── 抗核抗体陽性
- 動脈硬化症 ───────── 総コレステロール値上昇
疾患と症状との組合せで正しいのはどれか。
- 全身性エリテマトーデス ─── ヘリオトロープ疹
- 全身性硬化症 ──────── ブドウ膜炎
- 皮膚筋炎 ────────── 仮面様顔貌
- ベーチェット病 ─────── 陰部潰瘍
膠原病でないのはどれか。
- 痛風
- 皮膚筋炎
- 全身性エリテマトーデス
- 慢性関節リウマチ
全身性エリテマトーデスについて正しい記述はどれか。
- 補体値は高値となる。
- 末梢白血球数は減少する。
- 血清γ-グロブリン値は低下する。
- LA-B51が陽性である。
全身性エリテマトーデスについて正しいのはどれか。
- 血清補体価上昇を認める。
- 白血球数減少がみられる。
- 関節変形がみられる。
- 高齢女性に発症頻度が高い。
全身性エリテマトーデスについて正しい記述はどれか。
- 陰部潰瘍がみられる。
- 増悪と寛解を繰り返す。
- 白血球が増加する。
- 男性に多い。
SLE(全身性エリテマトーデス)について誤っているのはどれか。
- 寛解と再燃増悪とを繰り返す。
- 慢性炎症性疾患である。
- 中年で発症することが多い。
- 赤沈促進がみられる。
全身性エリテマトーデスの症状で適切でないのはどれか。
- 蝶形紅斑
- レイノー現象
- ホルネル徴候
- 関節痛
全身性エリトマトーデスでみられないのはどれか。
- 脱毛
- 口腔粘膜潰瘍
- 皮下結節
- けいれん
全身性エリテマトーデスで誤っている記述はどれか。
- 関節痛がみられる。
- 蝶形紅斑が特徴的である。
- 高脂血症を合併する。
- 20~40歳代の女性に好発する。
全身性エリテマトーデスについて誤っているのはどれか。
- 白血球が増加する。
- 女性に多い。
- 抗核抗体が陽性である。
- 蝶形紅斑を認める。
関節リウマチについて正しいのはどれか。
- 遠位指節間関節の腫脹を認めることが多い。
- 男性に多い。
- 対称性の関節腫脹を認めることが多い。
- 関節のこわばりは夕方に多い。
関節リウマチの関節内初期病変部位はどれか。
- 靱帯
- 骨
- 関節軟骨
- 滑膜
関節リウマチでみられないのはどれか。
- スワンネック変形
- ボタン穴変形
- 尺側偏位
- デュピュイトレン拘縮
関節リウマチと関係ないのはどれか。
- 関節血腫
- 朝のこわばり
- 関節の強直
- 対称性関節腫脹
関節リウマチに合併しない変形はどれか。
- マレット変形
- 尺側偏位
- スワンネック変形
- ボタン穴変形
関節リウマチの血液検査所見で誤っているのはどれか。
- 血小板数減少
- 赤沈値促進
- CRP陽性
- 赤血球数減少
関節リウマチの関節外症状として適切でないのはどれか。
- 間質性肺炎
- 陰部潰瘍
- 皮下結節
- 血管炎
ベーチェット病について正しい記述はどれか。
- 外陰部は正常である。
- 高齢者に多く発症する。
- 眼の症状はない。
- アフタ性潰瘍ができる。
ベーチェット病の特徴的な症状でないのはどれか。
- 陰部潰瘍
- 口腔内アフタ性潰瘍
- ブドウ膜炎
- 中耳炎
ベーチェット病について正しい記述はどれか。
- 高齢者に多い。
- 病的骨折がみられる。
- ビタミンB12の不足が原因である。
- ブドウ膜炎がみられる。
全身性硬化症(強皮症)でみられるのはどれか。
- 出血傾向
- ブドウ膜炎
- リンパ節腫脹
- 肺線維症
皮膚筋炎でみられるのはどれか。
- コプリック斑
- ヘリオトロープ疹
- ソーセージ様手指
- スワンネック変形
汎血球減少がみられるのはどれか。
- 重症筋無力症
- 肝硬変
- 関節リウマチ
- 溶血性貧血
関節疾患について正しいのはどれか。
- 変形性関節症は退行変性である。
- 関節拘縮の原因は関節包内の骨・軟骨にある。
- 関節リウマチの原因は細菌である。
- 関節強直の原因は関節包外の軟部組織にある。
「58歳の女性。数年前から左手の第4指の近位指節間関節の腫脹に気がついた。特に疼痛はなかったが、今年になって右手の第4指近位指節間関節の腫脹もみられるようになった。」本患者の治療で有効なのはどれか。
- 非ステロイド系抗炎症薬
- カルシトニン
- ビタミンB6
- ビタミンD製剤
「48歳の女性。2年前、左手のこわばりがみられ、その後、近位指節間関節から始まる左指の関節痛と腫れが生じ、さらに右指の関節も痛みだした。現在では、両側の手・膝関節にも関節炎がみられる。光過敏や嚥下障害はない。」 本疾患で陽性となるのはどれか。
- リウマトイド因子
- 抗トポイソメラーゼI抗体(抗Scl-70抗体)
- LE細胞
- 抗Jo-1抗体
「48歳の女性。2年前、左手のこわばりがみられ、その後、近位指節間関節から始まる左指の関節痛と腫れが生じ、さらに右指の関節も痛みだした。現在では、両側の手・膝関節にも関節炎がみられる。光過敏や嚥下障害はない。」 本疾患でよくみられるのはどれか。
- プシャール結節
- ハンマー指
- ヘバーデン結節
- Z型変形
「40歳の女性。数年前より手指のこわばりを自覚していた。最近、症状の増悪と手指の関節痛、腫脹が認められ来院した。冷たいものに触ると手指が白くなることがある。検査では抗トポイソメラーゼI抗体(抗Scl-70)が陽性であった。」 本症例の手指の所見はどれか。
- スプーン状爪
- レイノー現象
- ばち指
- ゴットロン徴候
「40歳の女性。数年前より手指のこわばりを自覚していた。最近、症状の増悪と手指の関節痛、腫脹が認められ来院した。冷たいものに触ると手指が白くなることがある。検査では抗トポイソメラーゼI抗体(抗Scl-70)が陽性であった。」 本疾患の合併症として最も多いのはどれか。
- ネフローゼ症候群
- 逆流性食道炎
- シェーグレン症候群
- ブドウ膜炎