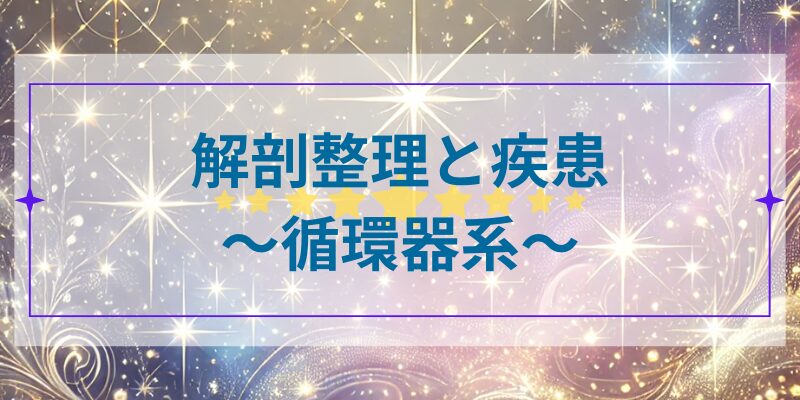血液
血管の構造
- 血管壁の3構造
- 内膜:単層扁平上皮
- 中膜:平滑筋や弾性線維
- 外膜:線維性結合組織
- 動脈
- 厚い中膜をもつ
- 太い動脈は弾性線維が多い
- 細い動脈は平滑筋線維が多い
- 静脈
- 中膜が薄く、弾性線維、平滑筋繊維が少ない
- 動脈と伴走
- 逆流を防ぐ静脈弁がある
- 毛細血管
- 1層の内皮細胞+基底膜
- 平滑筋と弾性線維がない
- 血液-組織間の物質交換を行う
- 終動脈
- 脳、心臓、肺、脾臓、腎臓にみられる
- 血管の構造
- 弾性血管:大動脈
- 抵抗血管:細動脈
- 容量血管:静脈
- 交換血管:毛細血管
血液の成分と働き
- 成分⇒血漿と細胞成分でできている
- 血漿55%
- 血清
- フィブリノゲン
- 細胞成分45%
- 赤血球
- 白血球
- 血小板
- 血漿55%
- 赤血球の始まり⇒造血幹細胞が分化してできる
- 腎臓から分泌されるエリスロポエチンにより産生促進される
- 肝臓や脾臓で破壊される
- 多量のヘモグロビンを含有する
- 酸素が多いところ⇒酸素と結びつく(酸素化ヘモグロビン)
- 酸素が少ないところ⇒酸素と離れる(還元ヘモグロビン)
- ヘモグロビンにより酸素の運搬、二酸化炭素の運搬、p Hの調節を行う
- ヘモグロビンは分解されるとビリルビンになる
- さらに腸内でウロビリノーゲンになる
- 二酸化炭素運搬は重炭酸イオンにより行われる
- 赤血球への分化
- 骨髄
- 造血幹細胞⇒骨髄内で盛んに分裂する
- 赤芽球⇒細胞核を放出して捨てる(脱核)
- 血管
- 網状赤血球⇒網状赤血球は血管内に移動
- 赤血球⇒1~2日で赤血球に成熟
- 骨髄
- ヘマトクリット値と赤血球沈降速度
- ヘマトクリット値
- 全血液容積に占める赤血球容積の割合のこと
- 貧血で低下、脱水で上昇
- 赤血球沈降速度
- 血液凝固阻害剤を入れた血液内で赤血球がしずむ速度
- 上昇
- 結核などの感染症
- リウマチなどの膠原病
- 悪性腫瘍
- 貧血
- 低下
- 多血症
- 肝疾患
- ヘマトクリット値
- 溶血の原因
- 低張液、細菌毒素、血液型不適合輸血、超音波などの物理的刺激、表面活性物質などの科学的刺激
- 血漿タンパク
- アルブミン:膠質浸透圧の維持、血漿タンパクで最も多い
- グロブリン:免疫細胞に関与
- フィブリノゲン:血液凝固作用に関与
血液型
| 血液型 | 凝集原(抗原) | 凝集素(抗体) |
| A型 | A | β |
| B型 | B | α |
| AB型 | A、B | なし |
| O型 | なし | α、β |
母親の血液型がRh -、父親の血液型がRh +の場合、胎児の血液型はRh +となる確率が高い
Rh +の第1子は通常無事に出産するが、第2子(Rh+)を妊娠した時、胎児の赤血球凝集反応を起こし、流産や死産を招くことが多い
心臓
心臓について
- 心臓の特徴⇒胸のやや左寄り中央
- 心臓の役目⇒全身に血液を送るポンプ
- 平均心拍数:約70回/分
- 安静時1回心拍出量:約70ml(ヤクルトの量)
- 心臓の外形⇒心軸が心底部から左前下方の心尖部に走ってる
- 右心耳
- 左心耳⇒大動脈と肺動脈の基部を抱くようにある耳たぶ上の突起物を心耳という
- 心尖部⇒心臓の下部にあるとがったところ
- 心底部(心基部)⇒心臓の上部で血管に出入りする
- 心臓の構造⇒心臓の壁は心内膜、心筋層、心外膜の3層からなる
- 心内膜⇒心臓の1番内側にある膜
- 心筋層⇒心内膜の外がにある筋肉
- 心外膜⇒心臓の外側をおおう膜
- 心膜腔⇒心外膜と壁側心膜の間のすき間
- 心膜液によって満たされ、摩擦を防いでいる
- 壁側心膜⇒心外膜が折り返され外側の膜
- 線維性心膜⇒全体を包む線維性の結合組織
- 心臓弁:僧帽弁(左)のみ二尖弁
- 右房室弁⇒右房室口にあり、三尖弁という
- 左房室弁⇒左房室弁にあり、二尖弁、僧帽弁という
- 大動脈弁⇒左心室の大動脈口にあり、3つの半月弁からなる
- 肺動脈弁⇒右心室の肺動脈口にあり、3つの半月弁からなる
- 肺動脈口は大動脈口の前方にある
- 冠状動脈⇒心臓が自分自身に栄養や酸素を届ける血管
- 上行大動脈
- 左冠状動脈⇒大動脈の基部の左側から心臓の前面に出て後ろにまわる
- 回旋枝⇒左冠状動脈から分かれ、左心房と左心室の間をめぐる血管
- 前下行枝⇒左冠状動脈から分かれて心室の前壁に向かう血管
- 右冠状動脈⇒大動脈の基部から右側から心臓の前面に出て後ろにまわる
- 後下行枝⇒右冠状動脈が心尖部に分かれた血管
- 冠状動脈の流れ
- 冠状動脈が運ぶ動脈血には酸素と栄養がたっぷりある
- 心臓の細胞に酸素と栄養を与えた後、静脈血になる
- 静脈血は冠状静脈を通って、冠状静脈洞に集められる
- 最後は右心房に注がれ、右心室から肺に送られて酸素を受け取る
- 心筋の特徴
- 興奮を伝導するのは特殊心筋
- 収縮するのは固有心筋
- 心筋は機能的合胞体であり、横紋筋であり、不随意筋である
- 心筋収縮にはC a2+が必要
- スターリングの法則に従い(静脈還流量が増加し、心筋が進展されると、心筋の収縮力が増加する)
血液循環
- 心臓内の血液の流れ⇒右心系と左心系に分かれる
- 肺に送る右心系
- 酸素が少ない静脈血が右心房、右心室に戻り肺へ送られる
- 全身に送る左心系
- 酸素が多い動脈血が左心房から左心室、全身へ送られる
- 肺に送る右心系
- 体内の血液の流れ⇒体循環と肺循環を交互にめぐる
心周期
心周期
- 心周期⇒収縮と弛緩のサイクルと弁の動き
- 拍動
- 収縮期⇒心室がギュッと収縮して動脈へ血液を送り出す時
- 拡張期⇒血液が心房を通ってゆるっと弛緩した心室に戻る時
- 拍動
- 等容性収縮期⇒駆出期⇒等容性弛緩期⇒充満期
- 等容性収縮期(収縮期)
- Ⅰ音:三尖弁と僧帽弁(房室弁)が閉じる音
- 心室に血液が溜まる
- 心室内圧<動脈圧
- 駆出期(収縮期)
- 動脈弁開く
- 心室から動脈へ流れる
- 心室内圧>動脈圧
- 等容性弛緩期(拡張期)
- Ⅱ音:肺動脈弁と大動脈弁(動脈弁)が閉じる音
- 静脈から心房へ流れる
- 次のポンプの準備
- 心室内圧<動脈圧
- 充満期(拡張期)
- 房室弁開く
- 心房から心室へ流れる
- 心房内圧>心室内圧
- 心房収縮期
- 房室弁開く
- 心房から心室へ流れる
- 残りの1/3の血液をギュッと絞り出す
- 心房内圧>心室内圧
- 等容性収縮期(収縮期)
血圧
- 血圧⇒血液が内側から動脈壁を押す圧力
- 心臓の仕事量⇒心拍出量は1回拍出量と心拍数で決まる
- 1回拍出量を変える要因
- 心収縮力⇒心臓が収縮する強さ
- 循環血液量⇒全身をめぐっている血液量
- 心拍数を変える要因
- 緊張
- 運動
- 末梢血管抵抗を変える要因
- 血管の内腔の大きさ
- 広い⇒流れやすい(血圧低下)
- 狭い⇒流れにく(血圧上昇)
- 血管壁の弾性
- ゆるゆる⇒流れやすい(血圧低下)
- カチカチ⇒流れにく(血圧上昇)
- 血液の粘性
- サラサラ⇒流れやすい(血圧低下)
- ドロドロ⇒流れにくい(血圧上昇)
- 血管の内腔の大きさ
- スターリングの法則
- 循環血液量が増えると、心臓に戻ってくる血液量である静脈還元量も増えて、心臓は引き伸ばされる
- その反動で心収縮力は増加する
刺激伝導系
- 洞房結節の興奮⇒自律神経で心拍数増減
- 自動能⇒心臓は神経が切断されてもしばらくの間は、自動的に拍動を続ける
- 自律神経
- 交感神経⇒交感神経の活動が活発になると心拍数が増える
- 心拍数増加(頻脈)
- 副交感神経⇒副交感神経の活動が活発になると心拍数が減る
- 心拍数減少(徐脈)
- 交感神経⇒交感神経の活動が活発になると心拍数が増える
- 自律神経
- 自動能⇒心臓は神経が切断されてもしばらくの間は、自動的に拍動を続ける
- 特殊心筋と刺激伝導系⇒全体が調和して心臓が(リズミカルに)動く仕組み
- 心臓はリズミカルに拍動する能力を持っている
- 心筋には心臓の拍動のリズムを決める特殊心筋と、全身に血液を送り出すポンプの働きをする固有心筋がある
- 特殊心筋の中の洞房結節が最初の心臓の収縮・拡張のリズムを引きおこす
- 洞房結節の発した興奮は心房筋と房室結節に伝わる
- 房室結節に伝わった興奮は、ヒス束を通って右脚と左脚、プルキンエ線維に伝えられる
- 特殊心筋から刺激を受けて心臓の大部分を占める固有心筋が収縮する
- 心房の収縮と弛緩、心室の収縮と弛緩が正しく周期的に繰り返されて血液は拍出される
- 洞房結節⇒房室結節⇒ヒス束(房室束)⇒右脚、左脚⇒プルキンエ線維を通って心室全体に興奮が伝わる
- 洞房結節
- 上大静脈の開口部に位置する
- 房室結節
- 洞房結節の興奮を心室に伝える心筋線維で右心房の下壁にある
- ヒス束(房室束)
- 心房と心室を連絡する
- 線維三角を貫通する
- 右脚、左脚
- ヒス束から始まって心室中隔を走行する
- プルキンエ線維
- 心内膜下を細かく分岐しながら網目状に走る
- 心室全体に興奮を伝える
- 心電図
- P波:心房興奮
- QRS波:心室興奮開始
- ST波:心室全体が興奮している時間に相当
- T波:心室の興奮消退の過程(再分極)
- 心筋の興奮異常や刺激伝導系の異常:PQ間隔、QRS群の変化
- 心室筋障害:T波の変化
胎児循環
- 胎児循環⇒胎盤が未発達な肺と肝臓の働きを引き受け、特有のバイパスがある
- 胎盤
- 胎児と母体の血液は直接混ざらない
- 母体と胎児が酸素や栄養と二酸化炭素や老廃物の交感をおこなう
- 臍静脈
- 静脈だけど酸素が多い
- 胎盤で受け取った動脈血を胎児の体内におくる血管
- 静脈管
- すでに母体で栄養が代謝されているから肝臓をとおらない
- 臍静脈から分かれた血管
- 肝臓を通らず下大静脈に注ぐ
- 卵円孔
- 血液に酸素がいっぱいで肺をとおらなくてもいい
- 心房中隔にある穴
- 右心房から左心房へ直接血液を送る
- 動脈管
- 胎児期においてみられる肺動脈と大動脈をつなぐ血管
- 右心房を通った血液を大動脈へバイパスする
- 臍動脈
- 動脈だけど酸素が少ない
- 左右の内腸骨動脈へ注がれた静脈血を胎盤に送る血管
- 胎盤
- 胎児循環の流れ⇒胎盤で始まり胎盤で終わる
- 胎盤から送られた動脈血が臍静脈を通って胎児の体内へ入る
- 静脈管を通り、肝臓を通らずに下大静脈に注ぐ⇒静脈血と混ざる
- 右心房から卵円孔を通って左心室へ行く⇒一部は右心室へ
- 左心房から左心室へ行く
- 大動脈を通って上半身に優先的に送られる⇒一部は頭部へ
- 上大静脈を通って右心房に戻る
- 右心室に流れた血液は肺動脈へ行く
- 動脈管、下行大静脈を通り、内臓や下半身へ行く
- 多くの静脈血は内腸骨動脈から臍動脈を通って胎児に送られる
- 新生児循環
- 新生児循環の特徴⇒新生児とは生後28日未満の赤ちゃん
- 肺呼吸が開始されて肺循環が開始する
- 胎盤がなくなる
- 臍静脈⇒肝円索
- 静脈管⇒静脈管索
- 臍動脈⇒臍動脈索
- 動脈管⇒動脈管索
- 卵円孔⇒卵円窩
- 新生児循環の特徴⇒新生児とは生後28日未満の赤ちゃん
循環器系の問題
血管について正しい記述はどれか。
- 下肢の動脈には弁がある。
- 動脈の中膜には発達した平滑筋がある。
- 毛細血管内皮は単層立方上皮である。
- 静脈は動脈に比べて壁が厚い。
血管の構造について正しい記述はどれか。
- 心臓に近い大血管では弾性線維よりも平滑筋線維が多い。
- 毛細血管には平滑筋が含まれる。
- 顔面の静脈は弁が豊富である。
- 門脈の構造は静脈と同じである。
正しいのはどれか。
- 冠状動脈は直接、右心房から分岐する。
- 右心房と右心室との間には二尖弁がある。
- 心臓の刺激伝導系は特殊心筋により構成される。
- 心臓は胸膜という二重の膜で包まれている。
心臓の血管系について正しい記述はどれか。
- 冠状静脈が分布する。
- 静脈血は上大静脈へ注ぐ。
- 冠状動脈は胸大動脈から分枝する。
- 左冠状動脈は心臓の前壁を養う。
心臓について正しい記述はどれか。
- 心尖は第2肋間の高さに位置する。
- 洞房結節は上大静脈の開口部に位置する。
- 心臓の静脈血は上大静脈に注ぐ。
- 右房室弁は僧帽弁という。
心臓について正しいのはどれか。
- 冠状静脈洞は右心房に開口する。
- 乳頭筋の収縮で房室弁が開く。
- プルキンエ線維は線維三角を貫く。
- 心内膜と心外膜の間が心膜腔である。
心臓について正しいのはどれか。
- 心外膜は漿膜の壁側板である。
- 心臓は後縦隔に位置する。
- 房室結節は心房を収縮させる。
- 大心臓静脈は冠状溝を走行する。
心臓について正しいのはどれか。
- 洞房結節は右心房壁にある。
- 後室間枝は左冠状動脈の枝である。
- 大動脈口は肺動脈口の前方にある。
- 腱索は半月弁に付着する。
心臓について誤っている記述はどれか。
- 洞房結節は右心房壁にある。
- 大動脈の起始部は左心房の後方にある。
- 線維輪は心房と心室との間にある。
- 冠状溝は心房と心室との境界にある。
冠状静脈洞が注ぐ部位はどれか。
- 下大静脈
- 左心房
- 上大静脈
- 右心房
心房の内部にみられるのはどれか。
- 乳頭筋
- 卵円窩
- 腱索
- 肉柱
心臓の動脈弁はどれか。
- 二尖弁
- 半月弁
- 僧帽弁
- 三尖弁
刺激伝導系について正しい記述はどれか。
- 房室結節は右心室にある。
- ヒス束は線維三角を通る。
- プルキンエ線維は心外膜下を走行する。
- 神経線維により構成される。
心臓の後室間枝と一緒に走行する静脈はどれか。
- 中心臓静脈
- 冠状静脈洞
- 前心臓静脈
- 大心臓静脈
心臓の刺激伝導系について正しいのはどれか。
- 刺激は房室結節からヒス束へと伝わる。
- プルキンエ線維の活動が心房を収縮させる。
- 房室結節は自動能をもたない。
- 固有心筋からなる。
脾臓に血液を送る動脈はどれか。
- 上腸間膜動脈
- 腹腔動脈
- 下腸間膜動脈
- 腰動脈
動脈とその分布域との組合せで正しいのはどれか。
- 腹腔動脈 ───── 胃
- 腎動脈 ────── 精巣
- 下腸間膜動脈 ─── 卵巣
- 上腸間膜動脈 ─── 直腸
肺の栄養動脈を分枝するのはどれか。
- 胸大動脈
- 総頸動脈
- 肺動脈
- 腋窩動脈
十二指腸を栄養する動脈はどれか。
- 脾動脈
- 下腸間膜動脈
- 総腸骨動脈
- 上腸間膜動脈
腹腔動脈の枝でないのはどれか。
- 固有肝動脈
- 脾動脈
- 下腸間膜動脈
- 右胃動脈
骨盤内臓器を栄養するのはどれか。
- 上腸間膜動脈
- 下腸間膜動脈
- 内腸骨動脈
- 外腸骨動脈
冠状動脈を分枝するのはどれか。
- 胸大動脈
- 肺動脈
- 大動脈弓
- 上行大動脈
腹大動脈の枝のうち対をなすのはどれか。
- 下腸間膜動脈
- 腹腔動脈
- 上腸間膜動脈
- 腎動脈
動脈と分布域との組合せで誤っているのはどれか。
- 上腸間膜動脈 ─── 空腸
- 腹腔動脈 ───── 脾臓
- 下腸間膜動脈 ─── 上行結腸
- 気管支動脈 ──── 肺臓
胸腹部の動脈について正しい記述はどれか。
- 気管支動脈は上行大動脈から分枝する。
- 上腸間膜動脈は直腸に分布する。
- 卵巣動脈は腹大動脈から分枝する。
- 腹腔動脈は回腸に分布する。
腹大動脈から起こる枝について正しい記述はどれか。
- 下腸間膜動脈は回腸を養う。
- 腎動脈は第4腰椎の高さで起こる。
- 精巣動脈は鼡径靱帯の深層を通る。
- 腹腔動脈は脾臓を養う。
内腸骨動脈の枝はどれか。
- 卵巣動脈
- 上殿動脈
- 上直腸動脈
- 内側大腿回旋動脈
外頸動脈の枝はどれか。
- 眼動脈
- 顎動脈
- 下甲状腺動脈
- 椎骨動脈
赤血球の産生を促進する因子はどれか。
- ビリルビン
- エリスロポイエチン
- フィブリン
- トロンビン
血漿中のアルブミンについて誤っている記述はどれか。
- 血漿の浸透圧維持に関与する。
- 細胞へのアミノ酸供給源である。
- 抗体として働く。
- 血漿中に最も多く含まれる蛋白質である。
ビリルビンについて誤っているのはどれか。
- ヘモグロビンの分解産物である。
- 血漿蛋白である。
- 胆汁成分である。
- 腸内でウロビリノーゲンになる。
赤血球の破壊で生じるのはどれか。
- フィブリノーゲン
- ウロビリノーゲン
- グロブリン
- プラスミノーゲン
体内に二酸化炭素が蓄積した場合に起こるのはどれか。
- 呼吸性アルカローシス
- 代謝性アルカローシス
- 代謝性アシドーシス
- 呼吸性アシドーシス
血漿蛋白について正しい記述はどれか。
- アルブミンが最も多い。
- γ-グロブリンは血液凝固に関与する。
- フィブリノーゲンはホルモンを運搬する。
- α-グロブリンは抗体として働く。
血液中の酸素分圧低下時に起こらないのはどれか。
- 頸動脈小体からの求心性活動の亢進
- エリスロポイエチンの分泌
- 酸素化ヘモグロビンの増加
- 赤血球の増加
赤血球沈降速度について誤っている記述はどれか。
- 血漿の粘性に左右される。
- 化膿性疾患で低くなる。
- 成人男性の正常1時間値は10mm以下である。
- 赤血球増多症で低くなる。
血液中を二酸化炭素が運搬される際の存在様式で最も多いのはどれか。
- ヘモグロビンと結合
- 血漿蛋白と結合
- 遊離二酸化炭素として溶解
- 重炭酸イオンとして溶解
血漿の膠質浸透圧の維持に必要な蛋白質はどれか。
- トロンビン
- アルブミン
- フィブリン
- グロブリン
血液への添加で溶血を起こすのはどれか。
- 蒸留水
- トロンビン
- ナトリウムイオン
- カルシウムイオン
貧血の要因でないのはどれか。
- 胃の全切除
- 高地への移住
- 栄養不足
- 脾臓の機能亢進
二酸化炭素運搬に関わる主要な血液成分はどれか。
- アルブミン
- 水
- 重炭酸イオン
- ヘモグロビン
血液凝固に関与するのはどれか。
- ビタミンK
- ビタミンD
- ビタミンE
- ビタミンC
血液凝固因子はどれか。
- フィブリノゲン
- γ-グロブリン
- アルブミン
- ヘパリン
線維素溶解に働く物質はどれか。
- アルブミン
- カルシウム
- プラスミン
- トロンビン
凝集素をもたない血液型はどれか。
- A型
- B型
- O型
- AB型
妊娠を繰り返すにつれて母体の抗Rh抗体産生が起こりやすくなる組合せはどれか。
- Rh+型の女性 ─── Rh+型の男性
- Rh-型の女性 ─── Rh-型の男性
- Rh+型の女性 ─── Rh-型の男性
- Rh-型の女性 ─── Rh+型の男性
肺循環について正しい記述はどれか。
- 肺動脈は動脈血を運ぶ。
- 体循環の動脈圧より低い。
- 肺静脈は右心房に血液を運ぶ。
- 大循環とも呼ばれる。
正常成人の安静時1回心拍出量で正しいのはどれか。
- 約150ml
- 約300ml
- 約30ml
- 約70ml
心臓でスターリングの法則を示す記述はどれか。
- 左心室から流出する血液が多くなると心拍数が増える。
- 左心室から流出する血液が多くなると心拍出量が増える。
- 右心房に流入する血液が多くなると心拍出量が増える。
- 右心房に流入する血液が多くなると心拍数が増える。
心周期における等容性収縮期について正しい記述はどれか。
- 心室内容積が増加する。
- 大動脈弁が閉じている。
- 心室内圧は動脈圧より高い。
- 心室内に血液が流入する。
第1心音が発生する心周期の時期はどれか。
- 収縮期の終わり
- 拡張期の終わり
- 拡張期の始め
- 収縮期の始め
心電図のQRS波が表す過程はどれか。
- 心房の興奮消退
- 心室の興奮消退
- 心室の興奮
- 心房の興奮
心臓迷走神経について誤っている記述はどれか。
- 洞房結節に分布する。
- 房室弁の開閉を調節する。
- 延髄に起始する。
- 活動が高まると徐脈となる。
心臓のスターリングの法則で正しい記述はどれか。
- 流入血液量が少ないほど心拍数は増える。
- 心筋が伸展されるほど収縮力は高まる。
- 流入血液量が少ないほど収縮力は高まる。
- 心筋が伸展されるほど心拍数は増える。
心臓のスターリングの法則で正しい記述はどれか。
- 心筋は太さに応じた収縮力を発生する。
- 心筋は伸展の度合いに応じた収縮力を発生する。
- 心筋は長さと無関係に一定の収縮力を発生する。
- 心筋は静脈環流量が少ない程大きな収縮力を発生する。
毎分心拍出量が増える直接の原因とならないのはどれか。
- 静脈環流量の増加
- 心拍数の増加
- 一回心拍出量の増加
- 血圧の上昇
心筋の特徴で誤っている記述はどれか。
- 自律神経支配を受ける。
- 強縮する。
- 絶対不応期は骨格筋より長い。
- 自動性をもつ。
心周期で房室弁が開放しているのはどれか。
- 駆出期
- 等容性収縮期
- 等容性弛緩期
- 充満期
心周期の中で房室弁が開放しているのはどれか。
- 充満期
- 等容性弛緩期
- 等容性収縮期
- 駆出期
心臓の働きについて誤っている記述はどれか。
- 摘出した心臓は一定時間拍動する。
- 心臓の収縮に自律神経の働きは不可欠である。
- 刺激伝導系の興奮は特殊心筋線維によって伝えられる。
- ペースメーカー細胞は一定リズムで興奮する。
心臓の刺激伝導系について誤っている記述はどれか。
- 洞房結節にペースメーカー細胞がある。
- 固有心筋からなる。
- ヒス束の興奮は右脚・左脚に伝わる。
- 房室結節は右心房にある。
心周期で心房内圧が心室内圧より高い時期はどれか。
- 等容性収縮期
- 駆出期
- 等容性弛緩期
- 充満期
心周期における等容性収縮期について誤ってる記述はどれか。
- 心室内圧は大動脈圧より高い。
- 心室内圧は増加する。
- 第1心音の発生時期と一致する。
- 大動脈弁は閉じている。
徐脈がみられるのはどれか。
- 発熱時
- 運動時
- 精神的興奮時
- 頸動脈洞圧迫時
心房から心室への伝導時間を表す心電図成分はどれか。
- PP間隔
- PQ時間
- QT時間
- RR間隔
心周期で心室内圧が動脈圧より高い時期はどれか。
- 駆出期
- 等容性収縮期
- 充満期
- 等容性弛緩期
血管について正しいのはどれか。
- 静脈弁は血液の逆流を防ぐ。
- 歩行時には静脈還流量が低下する。
- 動脈は静脈より血管抵抗が小さい。
- 動脈は静脈より多くの血液を貯留する。
血圧を上昇させる要因はどれか。
- 圧受容器活動の亢進
- 迷走神経活動の亢進
- 抵抗血管の拡張
- 心拍出量の増加
抵抗血管はどれか。
- 大動脈
- 大静脈
- 細静脈
- 細動脈
平均血圧について正しい記述はどれか。
- 収縮期血圧から脈圧の1/3を引く。
- 拡張期血圧に脈圧の1/2を加える。 1日の血圧変動を平均する。
- 拡張期血圧に脈圧の1/3を加える。
静脈還流を促す因子でないのはどれか。
- 骨格筋の収縮によるポンプ作用
- 吸息時の胸腔内圧低下
- 右心房内圧の上昇
- 静脈弁による逆流防止
静脈還流が促進される要因でないのはどれか。
- 歩行運動
- 呼息
- 静脈の弁
- 心房内圧の低下
血漿の膠質浸透圧の維持に必要な蛋白質はどれか。
- トロンビン
- フィブリン
- アルブミン
- グロブリン
健康成人において血圧低下を起こすのはどれか。
- 心収縮力の増大
- 細動脈の拡張
- レニン分泌の増加
- 血中ナトリウム濃度の上昇
減少すると血圧が上昇するのはどれか。
- 循環血液量
- 血中カテコールアミン
- 血管断面積
- 血液の粘性
血圧を下げる要因はどれか。
- 血液粘性の上昇
- 血管壁弾性の低下
- 血管平滑筋の弛緩
- 血液量の増加
血管について正しいのはどれか。
- 歩行時には静脈還流量が低下する。
- 動脈は静脈より血管抵抗が小さい。
- 静脈弁は血液の逆流を防ぐ。
- 動脈は静脈より多くの血液を貯留する。
脳循環の特徴で正しい記述はどれか。
- 毛細血管には血液-脳関門がある。
- 心拍出量の約30%を占める。
- 脳動脈は二酸化炭素の増加で収縮する。
- 脳血流量は絶えず大きく変動している。
圧受容器の興奮で起こらないのはどれか。
- 心拍数の低下
- 心拍出量の減少
- 迷走神経活動の低下
- 抵抗血管の拡張
循環系における圧受容器反射について誤っている記述はどれか。
- 受容器は頸動脈洞や大動脈弓の血管壁にある。
- 遠心路は交感神経および迷走神経である。
- 反射中枢は脊髄にある。
- 短時間(秒単位)で作動する。
大動脈弓の圧受容器が刺激された時に起こる反応はどれか。
- 心拍数の増加
- 血圧の低下
- 呼吸運動の促進
- 消化管運動の抑制
血液量をモニターしているのは主にどの受容器か。
- 大動脈弓圧受容器
- 大動脈小体化学受容器
- 心肺部圧受容器
- 頸動脈洞圧受容器
肺循環について正しい記述はどれか。
- 肺静脈は右心房に血液を運ぶ。
- 大循環とも呼ばれる。
- 肺動脈は動脈血を運ぶ。
- 体循環の動脈圧より低い。
血管拡張作用をもつのはどれか。
- セロトニン
- アンジオテンシンⅡ
- エンドセリン
- 二酸化炭素
心不全
- 心拍出量が低下する
- 心臓に血液が溜まる=心臓に血液を戻せなくなる
- 心臓のひとつ前の臓器に異常が起こる
- 左心不全⇒左心室のポンプ機能が障害されて発生する病態
- 左心室・左心房に血液が溜まる
- 肺から心臓に血液が移動できなくなる
- 肺に血流が溜まる(肺うっ血)
- 肺うっ血⇒肺水腫
- 労作時呼吸苦
- 夜間呼吸困難⇒起坐呼吸
- 頻脈
- 咳嗽、喘鳴
- チアノーゼ
- 尿量低下
- ピンク色泡沫状の痰
- 右心不全⇒右心室の本譜機能が障害されて発生する病態
- 右心室・右心房に血液が溜まる
- 肝臓や全身から心臓に血液が移動できなくなる
- 肝臓に血液が溜まる(肝腫大)
- 全身に浮腫が見られる(特に下腿)
- 上下大動脈のうっ血
- 食欲低下
- 倦怠感
- 頚静脈怒張
- 腹水、胸水
虚血性心疾患
- 冠動脈が狭くなり、心筋に酸素と栄養が行きわたらない状態
- 狭心症
- 冠動脈が狭窄し胸痛が生じたもの
- 心臓の動きは正常
- 安静のみで数分から15分程度で胸痛は消失する
- ニトログリセリン舌下投与
- 胸痛
- 前胸部圧迫感、絞扼感(労作時・興奮時・食事時)
- 異型狭心症は夜中から明け方に出現
- ST低下(異型狭心症はST上昇)
- 心筋梗塞
- 冠動脈が閉塞し心筋壊死になったもの
- 急性期に発熱が起こることがある
- 安静やニトログリセリンは効果なし
- ST上昇⇒異常Q波⇒冠性T派
- 労作性狭心症(安定狭心症)⇒安静狭心症(不安定狭心症)⇒心筋梗塞
- 細胞内の物質が細胞外に出る⇒炎症が起こる(白血球増加、血沈亢進、CRP陽性)
- 筋の破壊⇒ミオグロビン、CK、心筋トロポニンT上昇
- 細胞の破壊⇒AST(GOT)、LDH上昇
- 心不全状態⇒脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)増加
弁膜症
- リウマチ熱感染、心内膜炎が原因
- 心房の拡大は心房細動を起こしやすい
- 心室は筋が厚いため肥大しやすい
- 症状は左心不全に症状にみられる
- 心収縮と心雑音
- 収縮期
- 狭窄部を血流が流れる際の乱流で雑音が発生
- 拡張期
- 閉じるべき弁が閉じない際の逆流により雑音が発生
- 収縮期
- 僧帽弁狭窄症の心雑音
- 僧帽弁が開かなければならない時期に開かない
- 拡張期(充満期)
- 左房から左室への流入が障害される
- 弁に強い力がかかり無理やり開かれる⇒僧帽弁解放音(オープニングスナップ)
- 大量の血液が一気に通る⇒ランブル音
- 女性に多い
- 僧帽弁が開かなければならない時期に開かない
- 僧帽弁閉鎖不全症の心雑音
- 僧帽弁が閉じず、逆流がみられる
- 収縮期
- 左室から左房へ逆流が生じる
- 逆流性収縮期雑音
- 男性に多い
- 僧帽弁が閉じず、逆流がみられる
- 大動脈弁狭窄症の心雑音
- 大動脈弁が開かなければならに時期に開かない
- 収縮期(駆出期)
- 左室から大動脈への流出が障害される
- 駆出性収縮期雑音
- 大動脈弁が開かなければならに時期に開かない
- 大動脈弁閉鎖不全症の心雑音
- 大動脈弁が閉じず、逆流がみられる
- 拡張期
- 大動脈から左室へ逆流が生じる
- 逆流性拡張期雑音
- 1回拍出量増⇒逆流のため拡張期血圧減⇒脈圧増大
- 大動脈弁が閉じず、逆流がみられる
循環器疾患問題
疾患と検査結果との組合せで適切なのはどれか。
- 悪性リンパ腫 ─── フィラデルフィア染色体陽性
- 関節リウマチ ─── CRP値上昇
- 悪性貧血 ───── ビタミンB6欠乏
- 全身性硬化症 ─── HLA-B51陽性
疾患と原因との組合せで誤っているのはどれか。
- 成人T細胞白血病 ─── ウイルス
- 痛風 ───────── 高尿酸血症
- 血友病 ──────── 血小板減少
- 粘液水腫 ─────── 甲状腺機能低下
疾患と診察所見の組合せでよくみられるのはどれか。
- 巨赤芽球性貧血 ――― 関節内出血
- 鉄欠乏性貧血 ―――― 歯肉出血
- 腎性貧血 ―――――― 血尿
- 再生不良性貧血 ――― 鼻出血
血液疾患と原因との組合せで誤っているのはどれか。
- 白血病 ────── 放射線被曝
- 鉄欠乏性貧血 ─── 子宮筋腫
- 血友病 ────── 凝固因子欠乏
- 悪性貧血 ───── ウイルス感染
血液疾患と検査所見との組合わせで誤っているのはどれか。
- 本態性血小板減少性紫斑病 ─── ルンベル・レーデ試験陽性
- 慢性白血病 ────────── 血小板増加
- 急性白血病 ────────── 白血病裂孔
- 血友病 ──────────── プロトロンビン時間延長
血液疾患と症状との組合せで最も関連の低いのはどれか。
- 血友病 ───────── 関節内出血
- 白血病 ───────── 発熱
- 悪性リンパ腫 ────── 貧血
- 血小板減少性紫斑病 ─── リンパ節腫大
血液疾患と症状の組合せで正しいのはどれか。
- 急性白血病 ───── 出血傾向
- 悪性リンパ腫 ──── 舌炎
- 再生不良性貧血 ─── リンパ節腫脹
- 鉄欠乏性貧血 ──── 末梢神経障害
貧血とその原因との組合せで誤っているのはどれか。
- 再生不良性貧血 ───── 骨髄の低形成
- 鉄欠乏性貧血 ────── 慢性出血
- 悪性貧血 ──────── 赤血球の崩壊亢進
- 遺伝性球状赤血球症 ─── 赤血球の浸透圧抵抗減弱
貧血について誤っている組合せはどれか。
- 再生不良性貧血 ─── 汎血球減少
- 悪性貧血 ────── ビタミンB12欠乏
- 溶血性貧血 ───── 黄疸
- 鉄欠乏性貧血 ──── 大球性正色素性赤血球
血液疾患について誤っているのはどれか。
- 血友病では第8凝固因子が欠乏している。
- 悪性貧血はビタミンB1の欠乏により生じる。
- 急性白血病では白血球が急激に無制限に増殖する。
- 鉄欠乏性貧血はヘモグロビン産生量の減少により生じる。
血小板が減少する貧血はどれか。
- 再生不良性貧血
- 鉄欠乏性貧血
- 悪性貧血
- 溶血性貧血
骨髄移植の適応となる疾患はどれか。
- 白血病
- 悪性貧血
- 血友病
- エイズ
急性糸球体腎炎の症状で正しいのはどれか。
- 細菌尿
- 多尿
- 糖尿
- 血尿
急性白血病の症状で誤っているのはどれか。
- 貧血
- 血小板増多
- 出血傾向
- 白血球増多
血小板が減少する疾患はどれか。
- 慢性白血病
- 再生不良性貧血
- 鉄欠乏性貧血
- 血友病
脾腫をきたさない疾患はどれか。
- 悪性リンパ腫
- 血友病
- 慢性骨髄性白血病
- 自己免疫性溶血性貧血
二次性変形性関節症の原因とならないのはどれか。
- 先天性股関節脱臼
- ペルテス病
- 血友病
- 重症筋無力症
鉄欠乏性貧血の症状でないのはどれか。
- 頻脈
- スプーン状爪
- 舌乳頭萎縮
- チアノーゼ
血友病について誤っているのはどれか。
- 血小板数減少
- 遺伝性疾患
- 凝固時間延長
- 毛細管抵抗正常
鉄欠乏性貧血の原因として適切でないのはどれか。
- 過多月経
- 大腸癌
- 妊娠
- 痛風
鉄欠乏性貧血について適切でない記述はどれか。
- 血清フェリチン値は減少する。
- ビタミン剤の投与が有効である。
- 息切れ・動悸の訴えがある。
- 妊娠時に起こりやすい。
特発性血小板減少性紫斑病の症状で適切でないのはどれか。
- 鼻出血
- 関節内血腫
- 皮膚の点状出血
- 歯肉出血
血友病について正しい記述はどれか。
- 免疫抑制薬を投与する。
- 女性に多い。
- 血小板数の減少がみられる。
- 関節内血腫がみられる。
鉄欠乏性貧血について正しい記述はどれか。
- 総鉄結合能が減少する。
- フェリチンが減少する。
- 男性に多くみられる。
- ハンター舌炎がみられる。
汎血球減少がみられるのはどれか。
- 関節リウマチ
- 肝硬変
- 溶血性貧血
- 重症筋無力症
悪性貧血について正しいのはどれか。
- 正球性貧血を呈する。
- 抗内因子抗体が陽性となる。
- 伴性劣性遺伝である。
- ビタミンB1投与が有効である。
汎血球減少症をきたすのはどれか。
- 再生不良性貧血
- 腎性貧血
- 溶血性貧血
- 鉄欠乏性貧血
感染症に罹患しやすいのはどれか。
- 遺伝性球状赤血球症
- 血友病
- 悪性リンパ腫
- 鉄欠乏性貧血
悪性リンパ腫について誤っているのはどれか。
- 化学療法が有効である。
- 発熱がみられる。
- 有痛性のリンパ節腫脹がみられる。
- CRPが陽性となる。
白血病についてウイルスが原因で日本の西南地方に多いのはどれか。
- 急性リンパ性白血病
- 成人T細胞白血病
- 慢性骨髄性白血病
- 急性骨髄性白血病
自己免疫機序が関与しないのはどれか。
- 悪性貧血
- 溶血性貧血
- 鉄欠乏性貧血
- 再生不良性貧血
小球性低色素性貧血をきたすのはどれか。
- 巨赤芽球性貧血
- 溶血性貧血
- 再生不良性貧血
- 鉄欠乏性貧血
汎血球減少症をきたすのはどれか。
- 溶血性貧血
- 再生不良性貧血
- 鉄欠乏性貧血
- 腎性貧血
鉄欠乏性貧血について正しいのはどれか。
- 葉酸の欠乏が原因となる。
- 小球性貧血がみられる。
- 骨髄は低形成である。
- 血清フェリチンは増加する。
「52歳の男性。3週間前から倦怠感と微熱がある。舌炎は認めないが、鼻血や歯茎の出血、皮下出血斑がみられる。」 最も考えられる疾患はどれか。
- 悪性貧血
- 溶血性貧血
- 血友病
- 急性白血病
「52歳の男性。3週間前から倦怠感と微熱がある。舌炎は認めないが、鼻血や歯茎の出血、皮下出血斑がみられる。」 診断に必要な血液検査項目で最も適切なのはどれか。
- 血液像
- 第Ⅷ凝固因子
- ビリルビン
- 葉酸
疾患と痛みが放散する部位との組合せで誤っているのはどれか。
- 尿管結石 ───── 鼡径部
- 胆石症 ────── 右肩
- 十二指腸潰瘍 ─── 右肩
- 狭心症 ────── 左肩
疾患と臨床所見との組み合わせで誤っているのはどれか。
- 気管支拡張症 ──── 血痰
- 自然気胸 ────── 呼吸困難
- 狭心症 ─────── 胸痛は30分以上持続
- 解離性大動脈瘤 ─── 背部の激痛
循環器疾患と臨床所見との組合せで誤っているのはどれか。
- 心臓喘息 ────── 夜間呼吸困難
- 心タンポナーデ ─── 血圧低下
- 右心不全 ────── 下腿浮腫
- 左心不全 ────── 肝腫大
動脈疾患とその症状との組合せで誤っているのはどれか。
- レイノー病 ────── 間欠性跛行
- 閉塞性動脈硬化症 ─── 虚血性潰瘍
- 大動脈炎症候群 ──── 橈骨動脈拍動減弱
- 解離性大動脈瘤 ──── 体幹部激痛
心臓弁膜症と聴診所見との組合せで正しいのはどれか。
- 僧帽弁閉鎖不全症 ─── 頸動脈雑音
- 大動脈弁狭窄症 ──── ランブル
- 僧帽弁狭窄症 ───── 収縮期雑音
- 大動脈弁閉鎖不全 ─── 拡張期雑音
心臓弁膜疾患と症状との組合せで誤っているのはどれか。
- 大動脈弁閉鎖不全症 ─── 拡張期血圧上昇
- 僧帽弁狭窄症 ────── 起座呼吸
- 大動脈弁狭窄症 ───── 失神発作
- 僧帽弁閉鎖不全症 ──── 易疲労性
大動脈弁狭窄症で誤っているのはどれか。
- 拡張期雑音
- 肺うっ血
- 左室肥大
- 心拍出量低下
大動脈弁狭窄症でみられるのはどれか。
- オープニングスナップ
- 大脈
- 遅脈
- 収縮中期のクリック音
心筋梗塞について正しいのはどれか。
- 血清GPT上昇
- 心電図異常Q波
- ニトログリセリンが有効
- 白血球減少
僧帽弁狭窄症について正しいのはどれか。
- 心房細動の合併が多い。
- 先天性が多い。
- 左房圧は低下する。
- 心拍出量は増加する。
心筋梗塞の診断上有用でない酵素はどれか。
- GOT
- GPT
- LDH
- CK
心筋梗塞で誤っているのはどれか。
- AST(GOT)高値
- 赤血球数増加
- CRP陽性
- 心電図異常Q波
急性心筋梗塞の所見で誤っているのはどれか。
- 軽度または中等度の発熱
- 白血球減少
- GOTの上昇
- 赤沈促進
急性心筋梗塞の検査項目で最も有用性が高いのはどれか。
- トロポニンT
- ALP
- 赤血球数
- コリンエステラーゼ
心筋梗塞の心電図変化で誤っているのはどれか。
- ST上昇
- PQ時間短縮
- 冠性T波
- 異常Q波
心電図で異常Q波が出現する疾患はどれか。
- 慢性収縮性心膜炎
- 心筋梗塞
- 急性心膜炎
- 狭心症
閉塞性肥大型心筋症でみられるのはどれか。
- 胸部大動脈瘤
- 肺動脈弁狭窄症
- 大動脈圧上昇
- 突然死
拡張型心筋症で誤っている記述はどれか。
- 心筋の生検が診断の決め手となる。
- 胸部レントゲンは診断上有用である。
- 原因は不明である。
- 心電図で特徴的所見がある。
心不全について正しいのはどれか。
- 左心不全では下肢の浮腫は顕著である。
- 血中ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)値が低下する。
- 心拍出量が低下する。
- 左心不全では臥位で症状が軽快する。
心不全の徴候でないのはどれか。
- 腹水
- 肝臓腫大
- 起立性低血圧
- 頚静脈拡張
心不全患者の処置で誤っているのはどれか。
- 水分の摂取量を減らす。
- 食塩の摂取量を増す。
- 上半身を高くする。
- 身体を保温する。
狭心症について正しいのはどれか。
- 発作時の治療に抗血小板薬が用いられる。
- 異型狭心症は日中に起こりやすい。
- 心エコー検査で心臓の動きは正常である。
- 狭心痛は大動脈壁の内膜に生じた亀裂に血液が流入することで生じる。
階段を上がる時、前胸部に圧迫感が生じ、数分の安静で軽快するという症状を訴えた場合、最も考えられる疾患はどれか。
- 労作時狭心症
- 異型狭心症
- 心筋梗塞
- 安静時狭心症
虚血性心疾患の危険因子(リスク要因)はどれか。
- 高脂血症
- 高尿酸血症
- 不整脈
- 蛋白尿
狭心症について正しいのはどれか。
- 心電図ではP波の変化が特徴である。
- 冠攣縮型による狭心症は日中に起こりやすい。
- 不安定狭心症は心筋梗塞へ移行しにくい。
- 発作時にはニトログリセリンが有効である。
狭心症で異常を示さない検査はどれか。
- 運動負荷心電図
- 安静時心電図
- 冠状動脈造影
- 血中GOT
労作性狭心症発作の特徴でない記述はどれか。
- 安静によって軽快する。
- ニトログリセリンが有効である。
- 食事によっても誘発される。
- 持続時間は30分以上である。
労作性狭心症と急性心筋梗塞で、最も違いが明確なのはどれか。
- 胸痛の持続時間
- 放散痛の部位
- 呼吸困難の程度
- 症状出現の時刻
心電図では診断できない病態はどれか。
- 心臓弁膜症
- 狭心症
- 心房細動
- 期外収縮
動脈硬化症を増悪しない血中因子はどれか。
- 総コレステロール
- 中性脂肪
- HDLコレステロール
- LDLコレステロール
二次性高血圧の原因とならない疾患はどれか。
- アジソン病
- アルドステロン症
- バセドウ病
- 褐色細胞腫
僧帽弁狭窄症について正しい記述はどれか。
- 心房細動を起こしやすい。
- 肺うっ血を生じることは少ない。
- 左心室の拡張を伴う。
- 梅毒によるものが多い。
僧帽弁狭窄症について正しいのはどれか。
- 心房細動の合併が多い。
- 先天性が多い。
- 男性に多い。
- 心拍出量が増加する。
ファロー四徴症で認められないのはどれか。
- 肺動脈狭窄
- 大動脈騎乗
- 大血管転位
- 右室肥大
心房中隔欠損症で誤っている記述はどれか。
- 肺血流量が体血流量より少ない。
- 欠損は卵円孔型が多い。
- 肺動脈領域に収縮期雑音を聴取する。
- 右房の拡大がみられる。
「78歳の男性。5年前に高血圧を指摘されたが、自覚症状がないため放置していた。早朝、安静時に突然強い胸背部痛が出現し、救急搬送された。その際に胸部エックス線検査で上縦隔の著明な拡大を認めたが、心電図上有意な変化はみられなかった。」 本疾患の診断のため、直ちに施行すべき検査はどれか。
- 気管支内視鏡
- 運動負荷心筋シンチ
- 24時間ホルター心電図
- 胸腹部造影CT
「78歳の男性。5年前に高血圧を指摘されたが、自覚症状がないため放置していた。早朝、安静時に突然強い胸背部痛が出現し、救急搬送された。その際に胸部エックス線検査で上縦隔の著明な拡大を認めたが、心電図上有意な変化はみられなかった。」 本疾患による合併症はどれか。
- 大動脈弁狭窄症
- 気胸
- 心タンポナーデ
- 間質性肺炎
「71歳の女性。1週間前から労作時の胸痛を自覚していたが、安静で症状は軽減したため放置していた。しかし、昨日より安静時でも胸痛が起こるようになり、救急受診した。」本疾患の危険因子として最も重要なのはどれか。
- 低血圧
- 低HDL血症
- 低アルブミン血症
- 低血糖
「71歳の女性。1週間前から労作時の胸痛を自覚していたが、安静で症状は軽減したため放置していた。しかし、昨日より安静時でも胸痛が起こるようになり、救急受診した。」本疾患の合併症としてよくみられるのはどれか。
- 気胸
- 心室性期外収縮
- 心房中隔欠損症
- 僧帽弁狭窄症
「20歳の女性。呼吸困難、全身倦怠感の精査のため受診。胸部レントゲン写真で心拡大と肺うっ血を認めた。心エコー検査では左室内腔は著明に拡大し、心室中隔と左室後壁は薄くなっていた。」 本疾患の所見で適切なのはどれか。
- 頸静脈怒張
- 肺動脈圧低下
- 尿量増加
- 左房径縮小
「20歳の女性。呼吸困難、全身倦怠感の精査のため受診。胸部レントゲン写真で心拡大と肺うっ血を認めた。心エコー検査では左室内腔は著明に拡大し、心室中隔と左室後壁は薄くなっていた。」 本疾患に最も有用な血液検査項目はどれか。
- アルカリフォスファターゼ
- ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド
- ロイシンアミノペプチダーゼ
- リパーゼ
心房細動について正しいのはどれか。
- 心電図では異常Q波の出現が特徴である。
- 僧帽弁狭窄症は原因となる。
- くも膜下出血の発症リスクとなる。
- 若年者で罹患率が高い。
不整脈で予後が最も良いのはどれか。
- 心室細動
- Ⅲ度房室ブロック
- 心房細動
- 上室性期外収縮
心電図検査でST低下の際に疑われるのはどれか。
- 洞不全症候群
- 狭心症
- 心室粗動
- 心房細動
右心不全によくみられる身体所見はどれか。
- 下肢の浮腫
- 肺うっ血
- 頻呼吸
- 四肢チアノーゼ