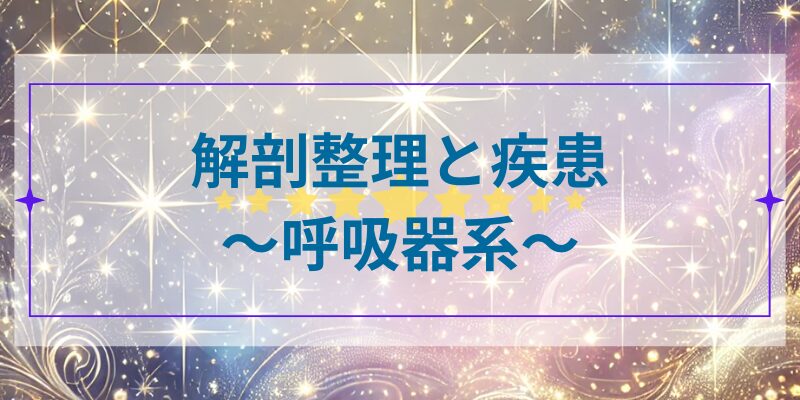呼吸器系
- 空気の通り道、気道と肺
- 上気道
- 鼻腔
- 空気の加湿と加温
- 空気中のごみの除去
- 上咽頭(咽頭鼻部)
- 頭蓋骨から口蓋までの高さ
- 中咽頭(咽頭口部)
- 口蓋から舌骨の高さ
- 下咽頭(咽頭喉頭部)
- 舌骨から輪状軟骨の高さ
- 咽頭
- 咽頭と気管をつなぐ
- 声帯がある
- 鼻腔
- 下気道
- 気管
- 喉頭の下に続き、第5胸椎の高さで左右の気管支に分かれる
- 気管支
- 細器官支
- 気管
- 肺胞の構造
- ブドウの房のような形
- 空気の出入りする肺胞の周りを毛細血管が取り囲む
- 肺胞+毛細血管⇒酸素と二酸化炭素を交換
- 外呼吸と内呼吸
- ガス交換
- 外呼吸⇒肺胞と血液でガス交換
- 内呼吸⇒血液と組織でガス交換
- 酸素を含んだ空気が気道から肺へ移動
- 肺胞から血液に酸素が移動してガス交換
- 赤血球によって酸素が移動
- 血液と組織の間で酸素と二酸化炭素がガス交換
- 血液から肺胞に二酸化炭素が移動してガス交換
- 二酸化炭素を含んだ空気が呼気として肺⇒外へ
- ガス交換
- 気管支
- 左右の気管支は葉気管支へ分かれる
- 右気管支
- 太くて短い
- 垂直に近い傾斜
- 3本ある
- 左気管
- 細くて長い
- 水平に近い傾斜
- 2本ある
- 肺葉
- 右⇒3葉、左2葉
- 肺理尖部
- 肺上面
- 鎖骨の上方
- 2~3cmまで達する
- 肺門
- 気管支や血管が肺に出入りすることろ
- 肺底部
- 肺の下面
- 横隔膜に上に位置する
- 裂
- 肺の表面にある深い溝
- 肺葉を仕切る
- 心切痕
- 左の肺にある心臓でへこんでいるところ
- 右肺
- 肺門
- 右肺動脈
- 左肺静脈
- 気管支
- 肺門
- 胸膜
- 肺の働きを支える二重の膜
- 臓側胸膜
- 肺の表面を覆っている胸膜
- 壁側胸膜
- 臓側胸膜が肺門で折り返してつながる胸膜
- 胸膜腔
- 臓側胸膜と壁側胸膜の間
- 正常で5~10cc程度の胸水(胸膜液)で満たされている
- 臓側胸膜
- 肺の働きを支える二重の膜
- 胸郭
- 胸骨で作られる空間
- 胸椎12個
- 肋骨12対
- 胸郭上口
- 第1胸椎と第1肋骨と胸骨で囲まれた上の縁
- 胸骨1個
- 胸骨柄
- 胸骨体
- 剣状突起
- 胸骨で作られる空間
- 胸壁
- 胸郭の壁を胸壁をいう
- 縦隔
- 左右の肺に挟まれた部分
- 気管
- 気管支
- 心臓
- 心臓に出入りする血管
- 大動脈
- 肺動脈
- 肺静脈
- 上大動脈
- 奇静脈
- 胸腺
- 胸管
- 食道
- 神経
- 迷走神経
- 横隔神経
呼吸運動
- 化学受容器
- 体内を循環する血液の状態を知るセンサー
- 血中内の状態に反応して呼吸中枢に情報を送る
- 酸素分圧の低下↓
- 二酸化炭素分圧の上昇↑
- pHの上下降
- 3つの化学受容器
- 末梢化学受容器
- 酸素分圧の低下に反応
- 頸動脈小体⇒内頚動脈と外頸動脈の分岐部
- 舌咽神経
- 大動脈小体⇒大動脈弓にある
- 迷走神経
- 頸動脈小体⇒内頚動脈と外頸動脈の分岐部
- 酸素分圧の低下に反応
- 中枢化学受容器
- 延髄の腹部にある
- 二酸化炭素分圧上昇
- pHの低下
- 末梢化学受容器
- 呼吸中枢
- 呼吸の指令を出す司令塔
- 呼吸中枢
- 化学受容器から情報を受けて「呼吸」命令を出す
- 横隔膜
- 頚髄から出る横隔神経が指令を伝達し、横隔膜が収縮
- 外肋間筋
- 胸髄から出る肋間神経が指令を伝達し、外肋間筋が収縮
- 胸腔が広がる
- 胸腔内圧低下
- 肺が膨張
- 空気が肺に入る
- 呼気と吸気
- 肋間筋と横隔膜の共同作業
- 吸気
- 肋間神経の活動が亢進して外肋間筋は収縮
- 横隔神経の活動が亢進して横隔膜は収縮
- 胸腔の容積は増大し、胸腔内圧が低下(陰圧が強まる)して肺が膨らんで吸気する
- 呼気
- 肋間神経の活動が低下して外肋間筋は弛緩
- 横隔神経の活動が低下して横隔膜は弛緩
- 胸腔の容積は減少し、胸腔内圧が上昇(陰圧が弱まる)して肺がしぼんで呼気する
- 努力呼吸時の筋肉
- 意識的により多くの筋肉を使う呼吸
- 吸息筋
- 息を深く吸った時に収縮する筋肉
- 主吸息筋⇒横隔膜、外肋間筋
- 呼吸補助筋⇒胸鎖乳突筋、斜角筋、小円筋
- 呼息筋
- 息を強く吐いた時に収縮する筋肉
- 内肋間筋、腹直筋、腹横筋、腹斜筋
酸塩基平衡
- 血液の中で酸と塩基がバランス(平衡)をとって最適なpHになっている
- 酸(酸性)⇒水に溶けて水素イオンを生じる物質
- 塩基(アルカリ性)⇒水に溶けて水素イオンを受け取る物質
- 平衡⇒バランスが取れている
- 中性=pH7
- 胃酸⇒酸性
- 膵液⇒アルカリ性
- 血液⇒pH7.4(弱アルカリ性)
- アシデミア、アシドーシス⇒血液が酸性(pH<7.35)になる状態、病態、変化
- アルカレミア、アルカローシス⇒血液がアルカリ性(pH>7.35)になる状態、病態、変化
- 肺と腎臓で水素イオン量を調節できる
- 肺の機能
- 肺は空気中の酸素を体内に取り入れ、体内の二酸化酸素を外に出す働きがある
- 肺機能が低下すると二酸化炭素を外に出しづらくなり、体内に溜まってしまう
- 血液中に二酸化炭素が溜まると水素イオンが増加する
- 血液中の水素イオンが増加してアシドーシスになる
- 呼吸性アシドーシス
- 肺は呼吸量を増やし二酸化炭素を減少させようとすることで、アシドーシスを改善しようとする(代償作用)
- 腎臓の機能
- 腎臓は血液中の水素イオンを尿中へ排泄し、重炭酸イオンを再吸収する働きがある
- 腎臓の機能が低下すると水素イオンの排泄が低下し、重炭酸イオンの再吸収が障害される
- 血液中の水素イオンが増加してアシドーシスとなる
- 代謝性アシドーシス
- 肺の機能
- 肺と腎臓の代償作用
- 肺機能障害のときの腎臓
- 重炭酸イオンの再吸収力を高める
- 水素イオンの排出量を高める
- 水素イオンを体外に出し、肺に代わって下がったpHを上げる
- 腎機能障害のときの肺
- 二酸化炭素をたくさん排出し、腎臓に代わってpHを上げる
- 肺による代償作用は速度が速く、腎臓による代償作用は速度が遅い
- 肺機能障害のときの腎臓
酸素解離曲線
- 酸素分圧
- 血液中にある酸素の分圧の高さ
- 酸素が多いと酸素分圧が高い
- 酸素分圧が低い所ではヘモグロビンは酸素を離しやすい
- 酸素分圧が高い所ではヘモグロビンは酸素と結合しやすい
- ガス交換のしくみ
- 外呼吸
- 肺胞からの酸素とヘモグロビンがほとんど結合している
- 細胞、組織に酸素を渡すヘモグロビン
- 内呼吸
- 細胞、組織
- 肺胞が酸素を血液に渡して二酸化炭素を受け取る
- 血液中の二酸化炭素の大部分は、赤血球内で重炭酸イオンに変換されて運ばれる
- 外呼吸
- 酸素分圧が同じでも酸素を放出する原因
- 二酸化炭素分圧上昇
- pHの低下(水素イオンの上昇)
- 温度の上昇
スパイログラム
- スパイログラム⇒呼吸機能検査で描かれたグラフ
- 最大吸気位⇒思いっきり息を吸った時の基準点
- 安静吸気位⇒安静状態で息を吸った時の基準点
- 安静呼気位⇒安静状態で息を吐いた時の基準点
- 最大呼気位⇒思いっきり息を吐いた時の基準点
- 一回換気量⇒安静吸気位ー安静呼気位
- 約500ml
- 安静状態での呼吸量
- 肺胞換気量⇒1回換気量ー死腔量
- 死腔はガス交換に関わらない容積のこと
- 約350ml
- 予備吸気量⇒最大吸気位ー安静吸気位
- 安静状態で息を吸った状態からさらに吸う
- 2~3ℓ
- 予備呼気量⇒安静呼気位ー最大呼気位
- 安静呼気位からさらに吐き出せる空気量
- 約1ℓ
- 残気量⇒息を吐いた時に残った空気量
- 1~1.5ℓ
- 最大吸気量⇒1回換気量+予備吸気量
- 機能的残気量⇒予備呼気量+残気量
- 肺活量⇒1回換気量+予備吸気量+予備呼気量
- 思いっきり息を吸った状態で自力で吐き出すことができる最大の空気量
- 男性⇒3~4ℓ
- 女性⇒2~3ℓ
- 全排気量⇒1回換気量+予備吸気量+予備呼気量+残気量
- 気道と肺に入っているすべての空気量(肺活量+残気量)
努力呼吸
- 呼吸音の種類
- 正常呼吸音
- 気管呼吸音
- 気管支呼吸音
- 肺胞呼吸音
- 副雑音
- ラ音
- 連続性ラ音
- 低音性
- 高音性
- 断続性ラ音
- 水泡音
- 捻髪音
- 連続性ラ音
- その他
- 胸膜摩擦音
- ラ音
- 正常呼吸音
- 呼吸音減弱
- 気胸
- 胸膜が破れて胸膜腔に空気が入り、肺がしぼむ
- 胸水貯留
- 胸水が過剰にたまり、呼吸困難になる
- 気胸
- 副雑音の種類
- 連続性ラ音⇒一定時間以上持続するラ音
- 低音性⇒いびき音(ロンカイ)
- COPD
- 気管支拡張症
- 気道異物
- 高音性⇒笛音、笛声音(ウィーズ)
- 気管支喘息
- 閉塞性換気障害
- 低音性⇒いびき音(ロンカイ)
- 断続性ラ音⇒断続的に短いラ音
- 水泡音⇒コースクラックル
- 肺水腫
- 肺炎
- 捻髪音⇒ファインクラックル
- 間質性肺炎
- 肺線維症
- 水泡音⇒コースクラックル
- 胸膜摩擦音⇒胸膜の表面がザラザラになり、2つの胸膜がこすれあう音
- 胸膜炎
- 連続性ラ音⇒一定時間以上持続するラ音
呼吸器系の問題
左右の肺について正しい記述はどれか。
- 右には心切痕がある。
- 右は上大静脈に接する。
- 左には水平裂がある。
- 左が右より容積が大きい。
肺について正しい記述はどれか。
- 肺門は縦隔に面する。
- 右2葉、左3葉からなる。
- 臓側胸膜は肺尖で壁側胸膜に移行する。
- 胸膜腔は滑液で満たされる。
肺門を通るのはどれか。
- 横隔神経
- 気管
- 胸管
- 気管支動脈
肺について誤っている記述はどれか。
- 右肺には水平裂がみられる。
- 肺尖は鎖骨上方へ突出する。
- 胸膜腔は滑液で満たされる。
- 肺の表面は臓側胸膜で包まれる。
肺について誤っている記述はどれか。
- 肺静脈は右心房に入る。
- 表面は臓側胸膜で覆われる。
- ガス交換は肺胞壁において行われる。
- 左肺は2葉に分かれる。
縦隔内に存在しない器官はどれか。
- 食道
- 胸大動脈
- 心臓
- 肺
胸部の器官について後縦隔にあるのはどれか。
- 胸腺
- 食道
- 心臓
- 大動脈弓
気管について正しい記述はどれか。
- 後壁は脊柱に接している。
- 粘膜上皮は重層扁平上皮である。
- 前方を大動脈弓が横切る。
- 気管筋は骨格筋である。
気管について正しい記述はどれか。
- 第2胸椎の高さで左右の気管支に分岐する。
- 輪状軟骨の下縁に始まる。
- 軟骨が全周を取り囲む。
- 食道の後方にある。
気管について誤っている記述はどれか。
- 内面は粘膜で覆われる。
- 喉頭の下方に続く。
- 気管軟骨は馬蹄形をしている。
- 食道の後方に位置する。
気管支について正しい記述はどれか。
- 気管支壁は肺動脈によって栄養される。
- 左気管支は3本の葉気管支に分かれる。
- 右気管支は左よりも垂直に近く傾斜する。
- 気管分岐部は第1胸椎の高さである。
呼吸器について正しい記述はどれか。
- 左肺には水平裂がみられる。
- 気管膜性部は食道に接する。
- 声帯筋は平滑筋である。
- 上顎洞は上鼻道に開口する。
誤っている記述はどれか。
- 胸骨角の部位に第3肋骨が付く。
- 胸郭の下縁を通る水平面には第2-3腰椎間の椎間板がある。
- 輪状軟骨は第6頸椎の高さにある。
- ヤコビー線は第4-5腰椎の棘突起間を通る。
声帯筋が付着するのはどれか。
- 輪状軟骨
- 気管軟骨
- 喉頭蓋軟骨
- 披裂軟骨
喉頭を構成する軟骨で対をなすのはどれか。
- 甲状軟骨
- 披裂軟骨
- 輪状軟骨
- 喉頭蓋軟骨
喉頭の軟骨のうち対をなすのはどれか。
- 甲状軟骨
- 輪状軟骨
- 披裂軟骨
- 喉頭蓋軟骨
声帯靭帯が付着するのはどれか。
- 輪状軟骨
- 喉頭蓋軟骨
- 小角軟骨
- 甲状軟骨
声帯について誤っている記述はどれか。
- 声帯は輪状軟骨に付く。
- 声帯筋は迷走神経により支配される。
- 声帯と声帯裂とを合せて声門という。
- 左右の声帯の間を声帯裂という。
喉頭について誤っている記述はどれか。
- 披裂軟骨は対をなす。
- 声帯靭帯は輪状軟骨に付く。
- 喉頭隆起は甲状軟骨にある。
- 甲状軟骨は輪状軟骨と関節する。
食道について正しいのはどれか。
- 粘膜上皮は多列線毛上皮からなる。
- 第3頸椎の高さで始まる。
- 食道下部の筋層は横紋筋である。
- 縦隔を通る。
呼吸調節で正しいのはどれか。
- 血液のpHが低下すると呼吸運動が抑制される。
- 吸息で肺が伸展すると呼息が抑制される。
- 動脈血酸素分圧が低下すると呼吸運動が抑制される。
- 延髄の呼吸中枢には呼息中枢と吸息中枢とがある。
呼吸について正しい記述はどれか。
- 吸気時に胸腔内圧が更に陰圧となる。
- 肺活量は最大の吸気量である。
- 安静呼気時に残気量はゼロになる。
- 1回換気量は呼気量と残気量との和である。
血液の酸塩基平衡を保つのに重要なイオンはどれか。
- カリウムイオン
- マグネシウムイオン
- 重炭酸イオン
- カルシウムイオン
血液の酸塩基平衡の保持に重要なイオンはどれか。
- 重炭酸イオン
- カルシウムイオン
- マグネシウムイオン
- カリウムイオン
呼吸の化学受容器反射を起こすのはどれか。
- 動脈血中の酸素分圧増加
- 静脈血中の炭酸ガス分圧増加
- 動脈血中の炭酸ガス分圧増加
- 静脈血中の酸素分圧増加
呼吸調節におけるヘーリング・ブロイエル反射について正しい記述はどれか。
- 受容器は圧受容器である。
- 求心路は交感神経である。
- 反射中枢は視床にある。
- 吸息中枢が抑制される。
ヘーリング・ブロイエル反射(肺迷走神経反射)で正しいのはどれか。
- 吸息を抑制する反射
- 咳を起こす反射
- あくびを誘発する反射
- 呼息を抑制する反射
ヘーリング・ブロイエル反射について正しいのはどれか。
- 反射中枢は視床下部にある。
- 求心路は交感神経である。
- 受容器は圧受容器である。
- 吸息中枢が抑制される。
気道を拡張させるのはどれか。
- 副交感神経活動の亢進
- 気管支平滑筋の収縮
- 気管線毛運動の亢進
- 交感神経活動の亢進
吸気時の胸腔内圧について正しい記述はどれか。
- 大気圧より高い。
- 肺胞気圧より高い。
- 大気圧より低い。
- 肺胞気圧に等しい。
体内に二酸化炭素が蓄積した場合に起こるのはどれか。
- 呼吸性アルカローシス
- 呼吸性アシドーシス
- 代謝性アシドーシス
- 代謝性アルカローシス
健康成人の呼吸について誤っている記述はどれか。
- 一回換気量は約500mlである。
- 肺活量は最大の換気量である。
- 機能的残気量は予備呼気量と残気量との差である。
- 予備呼気量は約1000mlである。
呼吸の反射性調節について正しい組合せはどれか。
- 動脈血二酸化炭素分圧の低下 ────── 呼吸促進
- 肺伸展受容器の興奮 ────────── 呼息抑制
- 動脈血酸素分圧の低下 ───────── 呼吸促進
- 脳脊髄液中の水素イオン濃度の上昇 ─── 呼吸抑制
酸素分圧が最も高いのはどれか。
- 静脈血
- リンパ液
- 動脈血
- 肺胞気
正常時の呼吸調節で誤っている記述はどれか。
- 呼吸中枢は延髄にある。
- 血液のpHが低下すると呼吸運動は促進する。
- 動脈血酸素分圧が低下すると呼吸運動が抑制される。
- 吸息で肺が伸展すると吸息は抑制される。
血液のガス運搬について正しい記述はどれか。
- 酸素は主に水酸基として運ばれる。
- 二酸化炭素は主に重炭酸イオンとして運ばれる。
- 肺での酸素の移動は主にろ過による。
- 組織での二酸化炭素の移動は主に能動輸送による。
呼吸について誤っている記述はどれか。
- 肺胞の酸素分圧は動脈血の酸素分圧より低い。
- 腹式呼吸の吸気時に横隔膜は収縮する。
- 胸腔内圧は陰圧である。
- ヘモグロビンと酸素の結合能は炭酸ガス分圧が低い程高まる。
分時肺胞換気量に関与しないのはどれか。
- 呼吸数
- 残気量
- 1回換気量
- 死腔量
正常呼吸と浅くて速い呼吸とを比べ変化しないのはどれか。
- 予備吸気量
- 分時肺胞換気量
- 1回換気量
- 死腔量
血液中を二酸化炭素が運搬される際の存在様式で最も多いのはどれか。
- 遊離二酸化炭素として溶解
- 血漿蛋白と結合
- 重炭酸イオンとして溶解
- ヘモグロビンと結合
安静時の肺気量で最も少ないのはどれか。
- 1回換気量
- 死腔量
- 残気量
- 肺胞換気量
呼吸促進が起こるのはどれか。
- 肺伸展受容器の興奮
- 大動脈小体の興奮
- 動脈血酸素分圧の上昇
- 脳脊髄液水素イオン濃度の低下
肺における体液の酸塩基平衡に関与するのはどれか。
- 水分の排泄
- 窒素の吸収
- 酸素の吸収
- 二酸化炭素の排泄
肺活量を表す式として正しいのはどれか。
- 肺活量 = 予備吸気量 + 予備呼気量
- 肺活量 = 1回換気量 + 予備呼気量
- 肺活量 = 1回換気量 + 予備吸気量 + 予備呼気量
- 肺活量 = 1回換気量 + 予備吸気量
頸動脈小体を刺激するのはどれか。
- 動脈圧の上昇
- 血液のpH上昇
- 血液量の減少
- 血液の酸素ガス分圧減少
過換気で起こるのはどれか。
- 血漿重炭酸イオン濃度の増加
- 動脈血酸素分圧の低下
- 動脈血二酸化炭素分圧の上昇
- 血漿水素イオン濃度の減少
呼息時に起こるのはどれか。
- 胸腔内圧が上昇する。
- 横隔膜が水平になる。
- 肋骨が挙上する。
- 外肋間筋が収縮する。
異常呼吸で、深い呼吸が規則正しく続くのはどれか。
- クスマウル呼吸
- チェーン・ストークス呼吸
- 起坐呼吸
- ビオー呼吸
安静吸息時に起こる現象はどれか。
- 腹筋の収縮
- 胸郭の縮小
- 胸腔内圧の上昇
- 外肋間筋の収縮
呼吸運動を促進するのはどれか。
- 血中酸素分圧の増加
- 体温の低下
- 血中水素イオン濃度の減少
- 大動脈小体の興奮
肺結核(肺抗酸菌)
- 結核菌を吸い込むことで空気感染する呼吸器感染症
- 2類感染症
- 診断されたら届け出が必要
- 日本は他の先進国と比べて患者数が多い
- 初感染発病(一次結核)
- 細胞性免疫により多くは自然治癒する
- 一部の菌が残存して免疫力低下
- 既感染発病(二次結核)
- ほとんどの人は生涯発病しない
- エイズや糖尿病など免疫が低下する疾患を合併していると再発率は高くなる
- 症状
- 咳嗽
- 喀痰
- 微熱
- 盗汗(寝汗)
- 血痰
- 倦怠感
- 診断
- 胸部X線写真
- ツベルクリン反応
- 血痰培養
- 抗原特異的インターフェロンγ遊離試験(クオンティフェロン検査)
- 治療
- 4剤を2か月⇒2剤を4か月を規則正しく服用する
- 多剤耐性結核菌の出題問題あり
- ワクチン
- BCG
- マスク着用の推奨
- 医療者⇒N95マスク
- 患者⇒サージカルマスク
慢性閉塞性呼吸器疾患(COPD)
- 肺気腫
- 肺胞中隔が破壊される疾患
- 中隔にある血管、弾性繊維がなくなる
- ガス交換ができない⇒低酸素血症、高炭酸ガス血症
- 弾性収縮力低下⇒肺が過膨張=樽状胸、呼吸音減弱
- 慢性気管支炎
- 気道で炎症が起こる疾患
- 喫煙などにより炎症が起こる
- 気道分泌物が増加
- 湿性咳嗽
- COPDは気道が狭くなり「息が吐き出しにくい」
- 労作時の呼吸困難⇒労作時呼吸苦、呼気延長
- 1秒率低下
- 残気量の増加
- 原因
- 喫煙
- 病態生理
- 終末細気管支よりも末梢での気腔の不可逆的な拡大をきたした疾患
- 明らかな線維化を伴わない
- 合併症
- 呼吸不全状態の際、高濃度酸素の投与によりCO2ナルコーシスを合併する
- 胸部X線検査
- 肺野の透過性亢進
- 横隔膜低位
- 1秒率低下=閉塞性疾患
間質性肺炎(肺線維症)
- 肺胞壁に炎症、線維化、肥厚をきたす拘束性呼吸器疾患
- ガスの拡散障害(拡散の低下)
- 酸素の取り込みが低下(低酸素血症)
- 二酸化炭素は影響を受けない
- 肺の軟らかさ(コンプライアンス)の低下
- 肺活量の低下
肺癌
- 気管支上皮から発生する癌
- 特徴
- 喫煙(受動喫煙も)が危険因子
- 死亡数は男性が多い
- 骨転移しやすい
- 全身症状
- 発熱
- 倦怠感
- 体重減少
- バチ状指
- 胸水
| 分類 | 特徴 | 局所症状 |
| 小細胞癌 | 最も悪性 | 咳嗽、喀痰、血痰、喘鳴 |
| 扁平上皮癌 | 喫煙との関係性が高い | 咳嗽、喀痰、血痰、喘鳴 |
| 腺癌 | 最多 | 早期は無症状 |
| 大細胞癌 | 早期は無症状 |
- パンコースト腫瘍特有症状
- 腕神経叢、脈管⇒上肢の症状
- 頸部の交感神経⇒ホルネル症候群(眼瞼下垂、無汗症、縮瞳)
- 浸潤、圧迫による症状
- 反回神経に浸潤⇒嗄声
- 上大静脈圧迫⇒上大静脈症候群(頸部静脈怒張、顔面浮腫)
- 壁側胸膜浸潤⇒胸痛
- 食道圧迫⇒嚥下困難
- 気管圧迫⇒呼吸困難
- 診断
- 胸部X線検査
- 胸部CT検査
- 血痰検査
- 確定診断⇒気管支ファイバースコープ
- 転移有無⇒CT検査、MRI検査、超音波検査、PET-CT検査、全身骨シンチグラフィー
肺炎
- 大部分が細菌が原因で、肺実質に化膿性炎症を起こす疾患
- 肺炎球菌が最多
- 発熱、悪寒
- 血液炎症所見がみられる
- 血沈亢進
- 白血球増加(好中球増加)
- CRP陽性
- 肺胞腔、肺胞上皮に炎症
- 咳嗽
- 喀痰
- 息苦しさ
- 加齢とともに死亡率が上がる
- 65歳以上の高齢者には肺炎球菌ワクチンが推奨されている
- マイコプラズマ肺炎
- 原因
- 細菌(マイコプラズマ・ニューモニエ)
- 好発
- 40歳未満の若年者
- 特徴
- 潜伏期間は2~3週間
- 周期的な流行がある
- 症状
- 39℃近い高熱
- 乾性咳嗽が多い(空咳、夜間眠れないほどの咳)
- 消化器症状
- 原因
気管支喘息
- 気道の炎症により「気道の狭窄と気管支腺の過分泌」をおこす疾患
- 好酸球、リンパ球を主体とした炎症
- 閉塞性障害(1秒率低下)
- 咳嗽、息苦しさ、喘鳴
- 笛声音
- 低酸素血症
- 起坐呼吸
- 疫学
- 若年者に多く、増加傾向
- 死亡数は高齢者に多いが、年々減少傾向
- 特徴
- 日中より夜間にひどい場合が多い
- 就寝時よりも就寝後深夜から明け方に発作が出現する
- 治療はステロイド吸入薬が中心
- 本疾患はコントロールする疾患であり治癒しない
気胸
- 若く背の高い痩せ型男性に好発し、突然の強い胸痛がおこる疾患
- 自然気胸は再発しやすい
- 空咳(刺激性の咳)もみられる
- 緊張性気胸は緊急処置が必要
過換気症候群
- 心因的素因が関与し、若年女性に多い
- 過換気発作30分~1時間程度で消失する
- 動脈血中の二酸化炭素分圧が低下⇒呼吸困難、動悸、頻脈、胸痛
- 呼吸性アルカローシス⇒手足のしびれ
- 低カルシウム血症⇒テタニー
- 脳血管収縮
- 脳血流低下⇒めまい、失神
呼吸器系疾患
呼吸機能検査所見と疾患の組合せで正しいのはどれか。
- 気道過敏性亢進 ――― 心臓性喘息
- 閉塞性障害 ――――― 肺結核後遺症
- 拡散能低下 ――――― 特発性肺線維症
- 拘束性障害 ――――― 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
呼吸器感染症について正しいのはどれか。
- 感冒の原因は主に細菌感染である。
- 非結核性抗酸菌は人から人へ感染する。
- 肺炎治療で菌の耐性化が問題となっている。
- 肺結核の治療は抗菌薬の単剤治療である。
呼吸器感染症について正しいのはどれか。
- インターフェロンγ遊離試験は非結核性抗酸菌症で陽性となる。
- 65歳以上の高齢者には肺炎球菌ワクチンが推奨されている。
- 上気道炎の治療は主に抗菌薬である。
- 日本の結核患者数は先進国の中では少ない。
呼吸器疾患について正しいのはどれか。
- COPDは安静時の呼吸困難が特徴的である。
- 自然気胸は胸痛を伴う。
- 肺線維症は閉塞性換気障害をきたす。
- 気管支喘息による死亡者数は増加している。
かぜ症候群について正しいのはどれか。
- 初期から呼吸音に異常がみられる。
- 主な感染経路は空気感染である。
- ほとんどがウイルス感染である。
- 抗菌薬を主に用いる。
肺結核について正しいのはどれか。
- 発熱することはない。
- 肺炎球菌の感染により発症する。
- 胸部エックス線検査は診断に有用である。
- ステロイドホルモンが治療に有効である。
肺結核について正しいのはどれか。
- 抗結核薬は単剤で用いる。
- 医療者はサージカルマスク着用が推奨される。
- 主な感染経路は飛沫感染である。
- 結核と診断したら直ちに届け出る。
肺結核について正しいのはどれか。
- 一次結核症の頻度が高い。
- クオンティフェロン法は診断に用いられる。
- 糖尿病合併患者では再発率が低い。
- 接触感染の頻度が高い。
肺結核の診断に用いられないのはどれか。
- 喀痰検査
- 胸部エックス線検査
- ツベルクリン反応
- BCG
非結核性抗酸菌症について正しいのはどれか。
- 人から人へ感染する。
- 難治性である。
- 男性に多い。
- 肺切除の対象とはならない。
肺結核を疑う症状で適切でないのはどれか。
- 微熱
- 喀痰
- 咳嗽
- 胸痛
気胸を疑う必要のある疾患はどれか。
- めまい
- 呼吸数減少
- 嘔気
- 刺激性の咳
気胸について正しい記述はどれか。
- 緊張性気胸は緊急処置が必要となる。
- 突然嗄声が出現する。
- 肥満は危険因子である。
- 自然気胸は成人女性に多い。
自然気胸について正しいのはどれか。
- 女性に多い。
- 緊張性気胸となることはない。
- 胸痛をきたすことが多い。
- 肥満者が多い。
原発性自然気胸について誤っているのはどれか。
- 肥満者に多い。
- 喫煙者に多い。
- 再発率が高い。
- 若年者に多い。
肋間神経ブロック後に突然の咳、胸痛、呼吸困難を生じた。最も考えられるのはどれか。
- 気管支喘息発作
- 気胸
- 解離性大動脈瘤破裂
- 急性心筋梗塞
肺線維症でみられないのはどれか。
- 肺活量減少
- 胸痛
- 息切れ
- 乾性咳嗽
特発性肺線維症をきたす危険因子でないのはどれか。
- 感染
- 喫煙
- 薬剤
- 過食
特発性肺線維症について誤っている記述はどれか。
- 細菌性肺炎に含まれる。
- 肺胞隔壁に炎症・線維化をきたす。
- 60歳代に多い。
- 重篤な呼吸障害を生じる。
COPDについて正しいのはどれか。
- 安静時の呼吸困難が特徴である。
- 増悪予防にはインフルエンザワクチン接種は有効である。
- 拘束性換気障害を呈する。
- 女性に多い。
COPDについて正しいのはどれか。
- 発作時に気管支狭窄音を伴う。
- 労作時の呼吸困難が特徴である。
- 肺機能検査では拘束性換気障害が特徴である。
- 肺拡散能(DLCO)は正常である。
COPDで正しいのはどれか。
- 安静時の呼吸困難が特徴である。
- 肺機能検査では閉塞性障害が特徴である。
- 喫煙は関与しない。
- 発作時に気管支狭窄音を伴う。
肺気腫について正しい記述はどれか。
- 肺胞の胞隔に線維化をきたす。
- CO2ナルコーシスをきたす。
- 肺機能検査で残気量が減少する。
- 呼気は短縮する。
慢性気管支炎で誤っている記述はどれか。
- 喫煙により悪化する。
- 気道抵抗が増加する。
- 湿性ラ音が聴取される。
- 高熱を伴う。
肺気腫について正しいのはどれか。
- 漏斗胸がみられる。
- 残気量が減少する。
- 吸気が延長する。
- 呼吸音が減弱する。
肺気腫の発症に最も関与する疾患はどれか。
- 肺癌
- 慢性気管支炎
- 気胸
- 胸膜炎
肺気腫の原因として適切でないのはどれか。
- 肺癌
- 加齢
- 喫煙
- 慢性気管支炎
肺気腫の病変部位でないのはどれか。
- 肺胞
- 呼吸細気管支
- 気管支
- 終末細気管支
肺気腫について誤っている記述はどれか。
- 動脈血酸素分圧が上昇する。
- 肺野のエックス線透過性が亢進する。
- ビール樽状胸郭を示す。
- 1秒率が低下する。
慢性気管支炎について誤っている記述はどれか。
- 治療として禁煙が重要である。
- 主な症状は湿性の咳嗽である。
- 閉塞性呼吸器疾患である。
- 1か月以上持続する気管支炎をいう。
慢性気管支炎について正しい記述はどれか。
- 乾性の咳嗽を認める。
- 喫煙が発病の原因となる。
- 拘束性呼吸器疾患である。
- 若年者に多い。
肺炎について正しいのはどれか。
- マイコプラズマ肺炎では湿性咳嗽が多い。
- 肺炎球菌ワクチンの接種が推奨されている。
- 原因はウイルス感染が多い。
- 若年者は高齢者と比較して死亡する危険性が高い。
急性肺炎の検査所見で誤っているのはどれか。
- 好中球増多
- 赤沈亢進
- CRP陽性
- 血小板増多
細菌性肺炎で変化しないのはどれか。
- CRP値
- 白血球数
- 赤血球沈降速度
- 赤血球数
マイコプラズマ肺炎で正しい記述はどれか。
- 水痘様の発疹が出る。
- 頑固な咳を伴う。
- ウイルス性の疾患である。
- 成人に感染しない。
マイコプラズマ肺炎で正しい記述はどれか。
- 乾性咳が多い。
- 潜伏期は2~3日である。
- 消化器症状はみられない。
- 老年者に頻度が高い。
急性間質性肺炎について正しい記述はどれか。
- 若年者に多い。
- 細菌感染が原因である。
- 肺コンプライアンスが低下する。
- 予後は比較的良好である。
肺抗酸菌症について正しいのはどれか。
- 非結核性抗酸菌症も結核と同様に隔離する必要がある。
- 咳が4週間以上持続している場合は肺結核を考慮する。
- 抗結核薬は1剤を投与する。
- 結核患者は届け出る必要はない。
肺癌について正しいのはどれか。
- 骨転移はまれである。
- 小細胞癌が最も多い。
- 受動喫煙は危険因子である。
- 死亡数は女性が多い。
肺癌と関係ないのはどれか。
- ホルネル症候群
- 上大静脈症候群
- 嗄声
- ギラン・バレー症候群
肺癌の隣接臓器への浸潤による症状でないのはどれか。
- 嚥下障害
- 嗄声
- 頸部静脈怒張
- 散瞳
肺癌の検査法で適切でないのはどれか。
- PET(ポジトロンCT)検査
- 超音波検査
- MRI検査
- CT検査
肺癌の診断に有用でないのはどれか。
- 喀痰検査
- 肺CT検査
- 気管支ファイバースコピー
- スパイログラフィー
原発性肺癌が頸部交感神経節に浸潤した場合にみられるのはどれか。
- 眼裂狭小
- うっ血乳頭
- 女性化乳房
- 血痰
肺癌の所見と浸潤部位との組合せで誤っているのはどれか。
- 縮瞳 ───── 迷走神経
- 嗄声 ───── 反回神経
- 呼吸困難 ─── 気管支
- 顔面浮腫 ─── 上大静脈
肺癌患者にみられる所見と浸潤部位の組合せで正しいのはどれか。
- 嗄声 ――――― 反回神経
- 腰痛 ――――― 横隔神経
- 縮瞳 ――――― 上大静脈
- 顔面浮腫 ――― 交感神経
肺癌患者にみられる所見と浸潤部位の組合せで正しいのはどれか。
- 顔面浮腫 ――― 上大静脈
- 縮瞳 ――――― 反回神経
- 嗄声 ――――― 交感神経
- 腰痛 ――――― 横隔神経
気管支喘息について正しい記述はどれか。
- 低酸素血症をきたしやすい。
- 人工呼吸は禁忌である。
- 予後は良好である。
- 若年者より老人に多い。
成人の気管支喘息について正しいのはどれか。
- 拘束性換気障害をきたす。
- 発作は昼間に起こりやすい。
- 吸入ステロイド薬が治療の中心である。
- 血液検査では好塩基球が増加する。
成人の気管支喘息について正しいのはどれか。
- 患者数は減少傾向にある。
- 治療は吸入ステロイド薬が中心である。
- 治癒率は50%である。
- 症状は昼間に起こりやすい。
気管支喘息について誤っている記述はどれか。
- 肺機能検査では拘束性障害を示す。
- 気道の狭窄を呈する。
- 気道の炎症がみられる。
- 発作時は咳嗽・息苦しさがみられる。
「67歳の女性。胸部エックス線写真で右上肺野の末梢側に2cm大の結節影があり、気管支内視鏡検査で肺癌と診断された。」 最も可能性が高い組織型はどれか。
- 小細胞癌
- 扁平上皮癌
- 大細胞癌
- 腺癌
「67歳の女性。胸部エックス線写真で右上肺野の末梢側に2cm大の結節影があり、気管支内視鏡検査で肺癌と診断された。」 遠隔転移を調べる上で必要な検査はどれか。
- 冠動脈造影
- 脳造影MRI
- 呼吸機能
- 心エコー
「35歳の男性。発熱、乾性咳嗽および呼吸困難で入院。胸部エックス線写真で両側の中・下肺野にびまん性すりガラス状陰影を認め、喀痰細胞診でニューモシスチス肺炎と診断された。」 この患者で陽性と考えられるのはどれか。
- 単純ヘルペスウイルス
- ヒト免疫不全ウイルス
- 成人T細胞白血病ウイルスⅠ型
- ライノウイルス
「35歳の男性。発熱、乾性咳嗽および呼吸困難で入院。胸部エックス線写真で両側の中・下肺野にびまん性すりガラス状陰影を認め、喀痰細胞診でニューモシスチス肺炎と診断された。」 本疾患で減少するのはどれか。
- Tリンパ球
- Bリンパ球
- 単球
- 好中球
体位ドレナージが有効な疾患はどれか。
- 気管支喘息
- 気管支拡張症
- 肺水腫
- 肺気腫
小児のピーナッツによる気道異物で誤っているのはどれか。
- 呼吸困難を呈する。
- 咳嗽が消失したら排出されたと考える。
- 一瞬の吸気とともに吸い込まれる。
- 肺炎を起こしやすい。