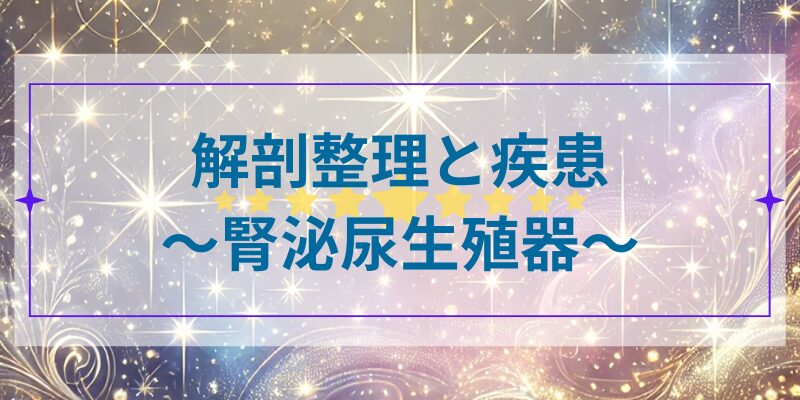腎臓の構造
- 約130g左右にある
- 第12胸椎~第3腰椎の間
- 右の腎臓の方がやや低い(肝臓が上にあるため)
- 腹膜の後ろにある
- 腎臓につながる血管
- 腎動脈は右が長い
- 腎静脈は左が長い
- 腎臓の役目⇒血液から尿を作る
- 動脈血が腎動脈を通って腎臓に送られる
- 腎臓を流れる腎血流量は心拍出量の約4/1、約1.2ℓ/分
- 糸球体で血液から原尿を作る
- 腎臓の糸球体でろ過された原尿は、尿細管で再吸収、分泌されて尿が作られる
- 腎臓から出た尿は尿細管を通って排出される
- 動脈血が腎動脈を通って腎臓に送られる
- 腎臓の構造⇒生成された尿は腎盂に集まる
- 腎被膜⇒線維性の膜
- 腎皮質⇒表層の部分
- 腎柱⇒腎錐体の間に挟まれた腎皮質
- 腎髄質⇒深部の部分で10個ほどの腎錐体からなる
- 腎乳頭⇒腎錐体の先にある乳頭管が開口する
- 腎葉⇒1つの腎錐体とその周りの腎皮質
- 腎杯⇒腎皮質から尿へ送る
- 腎門⇒尿管と血管が出入りする
- 腎盂⇒作られた尿が集められる
- 尿管⇒尿は腎皮質と腎髄質で作られて尿管を流れる
- 動脈血の流れ⇒糸球体でろ過される
- 心臓から動脈血が送られる
- 腎動脈から区域動脈
- 葉間動脈
- 弓状動脈
- 小葉間動脈⇒輸入細動脈⇒糸球体⇒輸出細動脈
- 糸球体⇒ボウマン嚢で血漿成分をろ過して原尿をつくる
- 輸入細動脈
- 糸球体(ボウマン嚢)
- 糸球体の表面に小さな穴があいている
- 血圧によって穴から水分や小さい分子が出される
- 水
- 尿素
- グルコース
- クレアチニン
- 糸球体をおおうボウマン嚢にろ過された物質が溜まる⇒原尿
- 輸出動脈
- 小さな穴を通れない大きい分子は流れていく
- 赤血球
- タンパク質
- 小さな穴を通れない大きい分子は流れていく
- 静脈血の流れ⇒不要なものが減った血液が腎を流れ去る
- 尿細管周囲毛細血管
- 小葉間静脈
- 弓状静脈
- 葉間静脈
- 区域静脈
- 腎静脈
- 下大静脈
- 静脈血として心臓に戻る
- ろ過のしくみ⇒ボウマン嚢の圧力がかかわる
- 腎小体+尿細管=ネフロン
- 糸球体
- ボウマン嚢
- ボウマン嚢は糸球体によって押し付けられている
- ボウマン嚢と糸球体の接地面をろ過膜
- ろ過膜
- 血管内皮細胞
- 基底膜
- 足細胞突起
- ろ過膜に関わる力
- 糸球体血圧⇒ろ過を助ける
- 血漿成分が血管から出ていく圧力
- 血漿の膠質浸透圧⇒ろ過を邪魔する
- 血液中のタンパク質や水を引き込む力
- ボウマン嚢内圧⇒ろ過を邪魔する
- ボウマン嚢が糸球体に加える圧力
- 有効ろ過圧=糸球体内圧ー血漿の膠質浸透圧ーボウマン嚢内圧
- どのくらいの圧力がろ過に有効なのかをあらわしたもの
- 糸球体血圧⇒ろ過を助ける
- 腎小体+尿細管=ネフロン
腎臓の機能
- 尿の生成⇒糸球体でいったん濾されて、再吸収された残りの尿
- 腎小体(糸球体+ボウマン嚢)で原尿が作られる
- 原尿が近位尿細管、ヘンレループ、遠位能細管を通る(原尿から尿が作られる)
- 集合管でさらに水分が再吸収される
- 腎小体+尿細管=ネフロン
- 尿の流れ⇒尿細管から腎盂、尿管、膀胱へ
- 尿細管
- 集合管
- 腎乳頭
- 腎杯
- 腎盂
- 尿管
- 膀胱
- 尿道
- 畜尿
- 膀胱三角
- 尿道×2
- 内尿道口
- 再吸収と分泌
- 輸入細動脈を流れてきた血液が糸球体でろ過されて原尿になる
- ボウマン嚢⇒原尿
- 糸球体でろ過されたが、身体に必要な栄養素は再吸収して体内に戻す
- 近位尿細管⇒重要な物質の大部分が吸収される
- 再吸収
- 水、ナトリウムイオン、カリウムイオン、重炭酸イオン、グルコース、アミノ酸、ビタミン
- 分泌
- 水素イオン、アンモニア、パラアミノ馬尿酸
- ヘンレループ
- 再吸収
- 水、ナトリウムイオン、カリウムイオン、塩素イオン
- 分泌
- 尿素
- 再吸収
- 再吸収
- 糸球体でろ過されなかった、身体に不要なものは分泌して体外にすてる
- 遠位尿細管
- 再吸収
- 水、ナトリウムイオン、カリウムイオン、塩素イオン、重炭酸イオン
- 分泌
- 水素イオン、カリウムイオン
- 再吸収
- 再吸収と分泌を繰り返しながら尿は生成され、腎臓から尿管を通って膀胱へ溜められる
- 集合管
- 再吸収
- 水、ナトリウムイオン、重炭酸イオン、尿素
- 分泌
- 水素イオン、カリウムイオン
- 再吸収
- 集合管
- 遠位尿細管
- 尿
- クレアチニンはろ過だけされて尿細管で再吸収も分泌もされない
- 近位尿細管⇒重要な物質の大部分が吸収される
- 輸入細動脈を流れてきた血液が糸球体でろ過されて原尿になる
- ろ過⇒糸球体ろ過量(GFR)の低下
- 尿細管分泌・再吸収⇒電解質異常
- ビタミンD3の活性化⇒カルシウム吸収障害⇒低カルシウム血症
- エリスロポエチン分泌⇒貧血
畜尿・排尿
- 畜尿と排尿⇒尿を溜めて必要時に排泄
- かかわる3つの筋肉
- 内尿道括約筋
- 平滑筋
- 外尿道括約筋
- 横紋筋
- 排尿筋
- 膀胱の壁をつくる3層の筋肉
- 膀胱平滑筋、膀胱収縮筋
- 内尿道括約筋
- かかわる5つの神経
- 大脳皮質⇒畜尿か排尿かの指令をだす
- 排尿中枢⇒脳幹の橋にある
- 交感神経⇒胸腰髄にある
- 副交感神経⇒仙髄にある
- オヌフ核⇒仙髄にある
- 畜尿のしくみ⇒膀胱の筋肉を緩め尿をためる
- 骨盤神経の求心路が興奮し、交感神経中枢とオヌフ核が興奮する⇒膀胱壁の伸展が刺激
- 下腹神経が興奮して膀胱の排尿筋が弛緩して、内尿道括約筋が収縮する⇒尿を溜めるように緩み、出ないように閉める
- 陰部神経が興奮して外尿道括約筋が収縮⇒漏れないようにさらに閉める
- 骨盤神経の興奮は大脳皮質にも伝わる⇒尿意を感じる
- 排尿のしくみ⇒膀胱の筋肉を収縮して尿を出す
- 骨盤神経の求心路の活動が活発になって尿意が高まる⇒尿を出そうという意思が生じる
- 大脳から尿を出す指示が出て橋にある排尿中枢が活動する⇒下位の神経に伝える
- 排尿がおこる
- 排尿反射
- 下腹神経が抑制、骨盤神経が興奮⇒排尿筋が収縮
- 骨盤神経が興奮⇒内肛門括約筋が弛緩
- 陰部神経が抑制⇒外肛門括約筋が弛緩
- 排尿反射
| 神経 | 畜尿 | 排尿 |
| 下腹神経 | 興奮 膀胱の弛緩 内尿道括約筋収縮 | 低下 内・外尿道括約筋弛緩 |
| 陰部神経 | 興奮 外肛門括約筋収縮 | 低下 内・外尿道括約筋弛緩 |
| 骨盤神経 | 興奮 膀胱が収縮 |
クレアチニンクリアランス
- クレアチニン⇒再吸収されない物質
- 尿細管で再吸収・分泌がほとんどされない
- 糸球体ろ過量の指標になる
- 肝臓
- クレアチン
- アミノ酸のを原料にクレアチニンがつくられる
- 血液に放出される
- クレアチン
- 筋肉
- クレアチンリン酸
- クレアチニンが筋肉に流れる
- リン酸と結合してクレアチリン酸になる
- クレアチンリン酸
- 腎臓
- 血清クレアチニン
- クレアチリン酸がエネルギー産生で使われて、その過程でクレアチニンができる
- 血清クレアチニン
- クレアチニン
- 血清クレアチニンが糸球体に運ばれる
- ろ過されて尿中に出される
- 肝臓
- クレアチニンクリアランス⇒腎臓の排泄能力の指標
- 血清クレアチニン濃度
- 血液中にクレアチニンがどのくらい含まれているのか
- 尿中クレアチニン濃度
- 尿中にクレアチニンがどのくらい含まれているのか
- 腎機能低下
- クレアチニンクリアランス低↓
- 血清クレアチニン高↑
- 尿崩症
- 尿量増↑
- 血清クレアチニン低↓
- 肝機能障害
- クレアチン生成低↓
- 血清クレアチニン低↓
- 血清クレアチニン濃度
BUN(血中尿素窒素)
- 腎機能の指標
- 尿素には窒素が含まれる
- 腎臓でろ過されて排出される老廃物
- 腎機能が低下するとBUNが上昇する
- 尿素の発生から排泄されるまでの流れ
- 体内でアミノ酸が分解される
- 摂取したタンパク質が消化酵素によってアミノ酸に分解される
- 体内で古くなったタンパク質がアミノ酸に分解される
- アミノ酸が分解されるときに有害なアンモニアが発生する
- アンモニアが肝臓へ運ばれる
- 肝臓の代謝機能によってアンモニアは無害な尿素に変換する⇒解毒作用
- 下大静脈から心臓に運ばれて、血液によって全身をめぐる
- 尿素が腎臓へ運ばれる
- 腎動脈から腎臓に運ばれる
- 糸球体でろ過されて約50%の尿素は体外に排泄される
- 体内でアミノ酸が分解される
- BUNが高くなる要因
- 腎機能障害
- 糸球体ろ過量減↓
- 尿素が排泄されずに血中の尿素が増↑
- 糸球体ろ過量減↓
- タンパク質の多量摂取
- アミノ酸分解増↑
- アンモニア増↑
- 血中尿素増↑
- アミノ酸分解増↑
- 消化管出血
- 消化管が出血することで組織が分解される
- タンパク質が分解される
- アンモニア増↑
- 血中尿素増↑
- 消化管が出血することで組織が分解される
- 甲状腺機能亢進症
- タンパク質の異化作用が促進
- タンパク質を分解してアミノ酸をエネルギーにする
- アンモニア増↑
- 血中尿素増↑
- タンパク質の異化作用が促進
- 脱水
- 体内の水分を増やそうとする
- 尿量減↓と水の再吸収量が増↑
- 血中尿素増↑
- 体内の水分を増やそうとする
- 腎機能障害
- BUNが低くなる要因
- タンパク質摂取不足
- タンパク質摂取量減↓
- アンモニア減↓
- 血中尿素減↓
- 肝不全
- 肝不全で肝機能低下
- アンモニアを代謝できず血中尿素減↓
- 肝不全で肝機能低下
- 尿崩症
- 尿崩症で尿量増↑
- 体外へ排泄される尿素増↑
- 血中尿素減↓
- 尿崩症で尿量増↑
- タンパク質摂取不足
生殖器の構造
- 女性
- 子宮壁の構造
- 子宮内膜⇒受精卵の着床が行われる
- 子宮筋層
- 子宮外膜
- 卵巣周期⇒卵巣に起こる周期的な変化
- 月経周期⇒子宮内膜に起こる周期的な変化
- 子宮壁の構造
- 男性
- 精嚢、前立腺、尿道球腺からの分泌液を精漿という
- 精巣
- 鶉卵くらいの重さ
- 楕円球の形をしている
- 精子をつくる
- 前立腺
- 栗の実ほどの大きさ
- 真ん中を尿道が通る
- 陰茎
- スポンジ状の組織である陰茎海綿体と尿道海綿体が並んでいる
- 勃起時
- 副交感神経の働きで動脈が拡張して陰茎海綿体に血液が充満し、交感神経の働きで射精する
妊娠と分娩
- 受精
- 卵子が排卵されたとき、性行為がおこなわれて膣内に精子が入る
- 一部の精子が鞭毛運動によって子宮頸癌、子宮腔内を通って卵管膨大部にたどり着く
- 減数分裂が途中である二次卵母細胞(卵子)に精子がやってくる
- 1個の卵子が卵細胞膜と融合すると顆粒膜細胞と透明帯が反応してほかの精子が入るのを防ぐ
- 精子が侵入した二次卵母細胞は減数分裂を再開し、精子と卵子の核が合体して受精卵になる
- 着床
- 受精卵は分裂しながら子宮内膜へ移動する⇒卵割
- 細胞の間に液が溜まって内腔に液腔が生じる⇒胞胚
- 大きくなるのを邪魔していた透明帯から胞胚が外に出てくる⇒孵化
- 受精から1週間くらいで胞胚は子宮内膜に侵入する⇒着色
- 妊娠成立
腎臓の問題
泌尿器系について誤っている記述はどれか。
- 尿道は膀胱の後壁から始まる。
- 腎乳頭は髄質にある。
- 腎小体は糸球体とボーマン嚢からなる。
- 膀胱は恥骨結合のすぐ後方にある。
泌尿器について誤っている記述はどれか。
- 尿管は膀胱の後壁を貫く。
- 腎杯は腎乳頭を包む。
- 腎乳頭と腎葉の数は同一である。
- 男性の尿道は前立腺の後ろを通る。
腎臓について正しい記述はどれか。
- 弓状動脈は皮質と髄質との間を走る。
- 遠位尿細管は腎杯に注ぐ。
- 集合管はネフロンに含まれる。
- ボーマン嚢は結合組織からなる。
腎臓について正しいのはどれか。
- 足細胞は糸球体表面を取り囲んでいる。
- 集合管はネフロンを構成する。
- 腎小体は髄質に散在する。
- 腎柱の先端を腎乳頭という。
腎臓について誤っているのはどれか。
- 傍糸球体細胞からアルドステロンが分泌される。
- 右腎は左腎より低い。
- 脂肪被膜で包まれる。
- 腎小体は糸球体とボーマン嚢からなる。
腎臓について誤っている記述はどれか。
- 集合管の粘膜上皮は移行上皮である。
- 腎小体は皮質に存在する。
- 近位尿細管はボーマン嚢に起始する。
- ヘンレループは髄質に存在する。
腎小体について誤っている記述はどれか。
- ネフロンを構成する。
- 腎小体の一端から尿管が続く。
- 糸球体に出入りする血管は動脈である。
- 腎臓の皮質に存在する。
腎小体について誤っているのはどれか。
- 腎臓の皮質に存在する。
- 尿細管とあわせてネフロンと呼ぶ。
- 糸球体とボーマン嚢からなる。
- 血管極から輸出細静脈が出る。
ネフロン(腎単位)について誤っているのはどれか。
- ボーマン嚢は糸球体を包んでいる。
- 糸球体は毛細血管で形成される。
- 緻密斑は遠位尿細管の一部に形成される。
- 遠位尿細管はボーマン嚢の尿管極から始まる。
尿が流れる方向について正しいのはどれか。
- 尿道から膀胱へ
- 腎盂から腎杯へ
- 膀胱から尿管へ
- 尿細管から集合管へ
尿管について誤っている記述はどれか。
- 腎門に起始する。
- 膀胱後下面に開口する。
- 総腸骨動脈と交叉する。
- 腹膜に包まれる。
尿道について誤っている記述はどれか。
- 男性尿道は前立腺を貫く。
- 女性尿道は腟の後壁に接する。
- 男の外尿道口は陰茎亀頭にある。
- 尿道括約筋は横紋筋である。
尿道について誤っている記述はどれか。
- 男性の尿道は尿道海綿体の中を走る。
- 尿道上皮は粘膜上皮である。
- 尿道括約筋は平滑筋である。
- 女性の尿道は腟前庭に開口する。
尿道について誤っている記述はどれか。
- 内尿道口に始まる。
- 尿道括約筋は横紋筋である。
- 女性のほうが短い。
- 陰茎海綿体内を貫く。
膀胱について正しいのはどれか。
- 全体が腹膜で覆われる。
- 膀胱頂に尿管が開口する。
- 骨盤内臓神経が分布する。
- 坐骨の後方にある。
膀胱について誤っている記述はどれか。
- 男女共に後方には直腸が接する。
- 膀胱の筋は自律神経に支配される。
- 恥骨結合の後方に位置する。
- 尿管口は膀胱三角の頂点をなす。
女性の膀胱について誤っているのはどれか。
- 底部に尿管が開く。
- 内面は移行上皮で覆われる。
- 直腸と子宮との間に位置する。
- 小骨盤腔に位置する。
男性尿道の隔膜部に最も近いのはどれか。
- 膀胱
- 肛門
- 精巣
- 尿道球腺
健康成人の尿細管に分泌される物質はどれか。
- 蛋白質
- ブドウ糖
- 赤血球
- アンモニア
腎糸球体でろ過されるのはどれか。
- アルブミン
- グルコース
- 白血球
- 赤血球
尿細管で分泌される物質はどれか。
- ブドウ糖
- ナトリウムイオン
- アンモニア
- アミノ酸
腎臓の尿細管で分泌されないのはどれか。
- 水素イオン
- 尿素
- 重炭酸イオン
- カリウムイオン
尿細管で起こる現象のうち体液の浸透圧を下げる要因はどれか。
- 水の再吸収
- ナトリウムイオンの再吸収
- 水素イオンの分泌
- ブドウ糖の再吸収
腎臓の酸・塩基平衡の保持作用で最も重要なのはどれか。
- 重炭酸イオンの排泄
- 水素イオンの排泄
- ナトリウムイオンの再吸収
- カリウムイオンの再吸収
安静時の腎血流量は心拍出量の約何%か。
- 5%
- 10%
- 50%
- 25%
健常成人で腎臓に流入する血漿のうち糸球体でろ過される割合はどれか。
- 40%
- 80%
- 20%
- 60%
糸球体におけるろ過に関与しない圧はどれか。
- 糸球体における血圧
- 血漿の膠質浸透圧
- 尿管内圧
- ボーマン嚢内圧
腎臓による体液の調節について正しい記述はどれか。
- ろ液の水分の 99%は尿細管で再吸収される。
- バゾプレッシンは尿量を増加させる。
- アルドステロンは水素イオンの再吸収を高める。
- レニン・アンジオテンシン系はバゾプレッシンの分泌を促進する。
排尿時に起こるのはどれか。
- 内尿道括約筋の収縮
- 膀胱支配の下腹神経活動の増加
- 外尿道括約筋の収縮
- 膀胱支配の骨盤神経活動の増加
尿量を増やすのはどれか。
- 大動脈弓圧受容器活動の低下
- 細胞外液量の増加
- バソプレッシン分泌の増加
- 血液の浸透圧の上昇
糸球体におけるろ過に関与しないのはどれか。
- 膀胱内圧
- 血漿の膠質浸透圧
- ボーマン嚢内圧
- 糸球体の血圧
排尿反射について誤っている記述はどれか。
- 中枢は脳幹にある。
- 求心路は骨盤神経である。
- 蓄尿時に陰部神経の活動は低下する。
- 排尿時に下腹神経の活動は低下する。
健常成人のクリアランス値で最も小さいのはどれか。
- グルコース
- 尿酸
- クレアチニン
- 尿素
尿量が減少する要因はどれか。
- 有効ろ過圧の上昇
- 血漿浸透圧の上昇
- 腎血漿流量の増加
- 糸球体血圧の上昇
尿量を増やすのはどれか。
- 血漿浸透圧の上昇
- 心肺部圧受容器活動の亢進
- 循環血液量の減少
- バソプレシン分泌の増加
意識的に排便を抑えるのはどれか。
- 下腹神経の抑制
- 骨盤神経の興奮
- 横隔神経の興奮
- 陰部神経の興奮
体液の調節について誤っている記述はどれか。
- レニン・アンジオテンシン系は細胞外液量の増加で活性化される。
- バゾプレッシンは尿量を低下させる。
- アルドステロンはナトリウムイオンの再吸収を促進させる。
- 細胞外液の浸透圧の変化は視床下部で検出される。
蓄尿時に興奮が高まらないのはどれか。
- 膀胱平滑筋支配の下腹神経
- 外尿道括約筋支配の陰部神経
- 膀胱平滑筋支配の骨盤神経
- 内尿道括約筋支配の下腹神経
集合管において水の再吸収を促すホルモンはどれか。
- 心房性ナトリウム利尿ペプチド
- バゾプレッシン
- パラソルモン
- アドレナリン
ある物質Sのクリアランスを求める際の指標として必要でないのはどれか。
- 物質Sの尿中濃度
- 1分間あたりの腎血流量
- 1分間あたりの尿量
- 物質Sの血漿濃度
糸球体におけるろ過の原動力はどれか。
- ボーマン嚢内液の膠質浸透圧
- 糸球体血圧
- 血漿膠質浸透圧
- ボーマン嚢内圧
糸球体ろ過量を増加させるのはどれか。
- 糸球体血圧の上昇
- 血漿膠質浸透圧の上昇
- 尿管内圧の上昇
- ボーマン嚢内圧の上昇
糸球体ろ過量を増加させるのはどれか。
- 血中アルブミン濃度の上昇
- 腎血流量の低下
- 尿管内圧の上昇
- 糸球体血圧の上昇
糸球体における有効ろ過圧の計算式で正しいのはどれか。
- 糸球体血圧-血漿膠質浸透圧+ボーマン嚢内圧
- 糸球体血圧+血漿膠質浸透圧+ボーマン嚢内圧
- 糸球体血圧+血漿膠質浸透圧-ボーマン嚢内圧
- 糸球体血圧-血漿膠質浸透圧-ボーマン嚢内圧
排尿時に起こるのはどれか。
- 膀胱壁の平滑筋が弛緩する。
- 下腹神経活動が亢進する。
- 陰部神経活動が低下する。
- 外尿道括約筋が収縮する。
生殖器の問題
正しいのはどれか。
- 前立腺は男女ともに尿道起始部にみられる。
- 腟壁にはよく発達した粘液腺が分布している。
- 陰茎には1対の陰茎海綿体がみられる。
- 尿道球腺は腟前庭に開口する。
誤っているのはどれか。
- 卵巣動脈は内腸骨動脈から分岐する。
- 精巣は後腹壁で形成され陰嚢中へ下降する。
- 精巣挙筋は内腹斜筋の続きである。
- 卵管の自由端は腹膜腔に開口している。
精巣で男性ホルモンを分泌する細胞はどれか。
- ライディヒの間細胞
- 精母細胞
- 精子細胞
- セルトリ細胞
女性生殖器について誤っている記述はどれか。
- 卵管は腹膜腔に開口する。
- 子宮内膜は粘膜で構成される。
- 卵巣は腹膜に包まれている。
- 腟口は外尿道口の前方にある。
生殖器について誤っている記述はどれか。
- 子宮円索は子宮を支持する。
- 精索は精嚢を支持する。
- 精巣は陰嚢中に位置する。
- 卵巣は骨盤腔に位置する。
前立腺の開口部があるのはどれか。
- 尿道
- 尿管
- 膀胱
- 精管
鼠径管を通らないのはどれか。
- 卵管
- 精管
- 精巣挙筋
- 子宮円索
精子を産生する部位はどれか。
- 精巣上体
- 曲精細管
- 精管
- 精巣網
子宮に直接つながっていないのはどれか。
- 卵巣
- 子宮円索
- 子宮広間膜
- 卵管
卵管について誤っている記述はどれか。
- 膨大部で受精が行われる。
- 子宮広間膜の上縁に沿って走る。
- 外側端で内腔は腹腔に開く。
- 上皮は重層扁平上皮である。
成人において内腔が腹膜腔に直接開口しているのはどれか。
- 精管
- 子宮
- 精巣鞘膜腔
- 卵管
前立腺について誤っている記述はどれか。
- 腹膜に覆われている。
- 導管は尿道に開口する。
- 膀胱の下に位置する。
- 腺組織の間に平滑筋が含まれる。
子宮について正しい記述はどれか。
- 膀胱の後方に位置する。
- 子宮頸部は卵管につながる。
- 子宮底で膣につながる。
- 子宮筋層は横紋筋からなる。
卵管上皮はどれか。
- 単層扁平上皮
- 移行上皮
- 単層立方上皮
- 線毛上皮
鼠径管を通らないのはどれか。
- 精巣動脈
- 精管
- 卵巣動脈
- 子宮円索
男性生殖器について誤っている記述はどれか。
- 精管は膀胱に開口する。
- 尿道球腺は左右1対ある。
- 精索は鼠径靱帯の上を通る。
- 陰嚢の正中部には縫線がみられる。
発生について正しいのはどれか。
- 着床は胚盤胞の段階で起こる。
- 受精は子宮内で起こる。
- 受精後4週目以降を胎児と呼ぶ。
- 胎児の臍動脈と母体の子宮動脈はつながっている。
男性生殖器とその位置の組合せで正しいのはどれか。
- 尿道球腺 ――― 骨盤隔膜
- 射精管 ―――― 尿道球
- 精管 ――――― 大腿輪
- 精巣上体 ――― 陰嚢
男性生殖器について正しいのはどれか。
- 射精管は陰茎を貫いている。
- 精巣上体は陰嚢内にある。
- 精子は精嚢に蓄えられる。
- セルトリ細胞は男性ホルモンを分泌する。
発生について正しいのはどれか。
- 着床は桑実胚の段階で起こる。
- 真皮は中胚葉から分化する。
- 精子と卵子は腟内で受精する。
- 胎盤では母体と胎児の血液が混ざり合う。
精巣で男性ホルモンを分泌するのはどれか。
- セルトリ細胞
- 精母細胞
- 精祖細胞
- ライディッヒ細胞(間細胞)
内胚葉から分化するのはどれか。
- 骨組織
- 表皮
- 骨格筋
- 小腸上皮
中胚葉から分化する細胞はどれか。
- 視細胞
- 肺胞上皮細胞
- 赤血球
- 神経細胞
外胚葉由来の上皮組織を有するのはどれか。
- 気管
- 網膜
- 卵管
- 胸膜
外胚葉から分化するのはどれか。
- 上皮組織
- 神経組織
- 結合組織
- 筋組織
発生学的に正しい組合せはどれか。
- 肝細胞 ─── 中胚葉
- 真皮 ──── 外胚葉
- 網膜 ──── 外胚葉
- 涙腺 ──── 内胚葉
内胚葉から分化するのはどれか。
- 表皮
- 赤血球
- 平滑筋
- 小腸上皮
内分泌腺について誤っている記述はどれか。
- 下垂体前葉は神経性下垂体と呼ばれる。
- 膵臓の内分泌細胞で一番多いのはβ細胞である。
- 上皮小体は甲状腺の背面にある。
- 副腎髄質は外胚葉に由来する。
体表構造について中胚葉に由来するのはどれか。
- 真皮
- 毛
- 表皮
- 爪
甲状腺について正しいのはどれか。
- 上甲状腺動脈は外頸動脈の枝である。
- 下甲状腺静脈は鎖骨下静脈に流入する。
- 傍濾胞細胞から出るホルモンは血中カルシウム濃度を上げる。
- 中胚葉に由来する。
皮膚について正しいのはどれか。
- 毛幹は皮膚内部に埋まっている。
- エクリン汗腺は足底にはない。
- 真皮は中胚葉に由来する。
- 表皮は多列円柱上皮でできている。
発生について正しいのはどれか。
- 真皮は中胚葉から分化する。
- 胎盤では母体と胎児の血液が混ざり合う。
- 着床は桑実胚の段階で起こる。
- 精子と卵子は腟内で受精する。
小腸について正しいのはどれか。
- 上皮は内胚葉から分化する。
- 半月ヒダがある。
- 回腸には腸間膜がない。
- 十二指腸空腸曲は腰椎の右にある。
排卵後に血中濃度が急速に高まるホルモンはどれか。
- プロゲステロン
- エストロゲン
- 黄体形成ホルモン
- 卵胞刺激ホルモン
射乳反射を起こすホルモンはどれか。
- エストロゲン
- オキシトシン
- グルカゴン
- プロゲステロン
出生後数年間で成人の重量水準に達する器官はどれか。
- 脳
- 心臓
- 腎臓
- 肝臓
黄体ホルモンの作用で誤っている記述はどれか。
- 基礎体温を上げる。
- 受精卵の着床を容易にする。
- 乳腺の発育を促す。
- 排卵を促す。
ホルモンとその作用との組合せで誤っているのはどれか。
- 黄体形成ホルモン ─── 排卵の誘発
- オキシトシン ───── 子宮筋の弛緩
- エストロゲン ───── 卵胞の発育
- プロゲステロン ──── 妊娠の維持
性周期について誤っている記述はどれか。
- プロゲステロンは排卵後に分泌が増加する。
- エストロゲンは子宮内膜を肥厚させる。
- 排卵に先立って黄体形成ホルモンの分泌が急激に増加する。
- 黄体は着床が起こると退化する。
女性の性周期においてプロゲステロンの分泌が最も亢進する時期はどれか。
- 分泌期
- 卵胞期
- 排卵期
- 月経期
妊娠中に分泌が抑制されるホルモンはどれか。
- プロゲステロン
- エストロゲン
- プロラクチン
- 黄体形成ホルモン
着床が起こるのはどの時期か。
- 排卵期
- 卵胞期
- 分泌期
- 増殖期
排卵を誘発するホルモンはどれか。
- プロゲステロン
- プロラクチン
- 黄体形成ホルモン
- オキシトシン
出産時の子宮収縮にかかわるホルモンはどれか。
- プロゲステロン
- 黄体形成ホルモン
- エストロゲン
- オキシトシン
授乳中に分泌が抑制されるのはどれか。
- 成長ホルモン
- ソマトスタチン
- プロラクチン
- 性腺刺激ホルモン
性周期について正しいのはどれか。
- 子宮内膜の分泌期には卵胞が成熟する。
- 排卵に先立って黄体ホルモンの分泌が急激に増加する。
- 卵胞ホルモンの作用により子宮内膜が増殖する。
- 子宮内膜の増殖期が終了すると月経期となる。
生理的老化の特徴で正しい記述はどれか。
- 環境変化に対する適応能力はよく保たれる。
- 各機能が同じ速度で低下する。
- 個体差が大きい。
- 安静時機能の低下が著しい。
加齢に伴い低下するのはどれか。
- 肺活量
- 副甲状腺ホルモン分泌
- 血糖値
- 血圧
加齢に伴い増加するのはどれか。
- 副腎皮質ホルモン分泌
- 重心動揺
- 肺活量
- 神経伝導速度
加齢による低下がみられないのはどれか。
- 視力
- 副甲状腺ホルモン分泌
- 腎血流量
- 最大換気能力
腎不全
- 糸球体ろ過量が低下する
- 尿量が減る⇒乏尿、無尿
- 老廃物が溜まる⇒尿毒症、代謝性アシドーシス
- 細胞外液量増加⇒浮腫
- 急性腎不全⇒腎機能の急激な悪化
- 何らかの原因で急激にネフロンのGFRが低下
- 原因が改善すれば治る可能性がある
- 循環血液量低下
- 腎前性
- ショック
- 下痢
- 脱水
- 出血
- 嘔吐
- 火傷
- 心不全
- 敗血症
- 腎性
- ミオグロビン尿症
- 急速進行性糸球体腎炎
- 腎後性
- 両側尿管閉塞
- 尿管結石
- 前立腺癌
- 腎前性
- 慢性腎不全⇒腎機能のゆるやかな低下と悪化
- 糸球体ろ過量低下により老廃物が出せない
- 腎機能の悪化が3か月以上続く
- 血中で高値になるもの
- K(高カリウム血症)
- P(高リン血症)⇒カルシウム吸収量低下⇒低カルシウム血症⇒二次性副甲状腺機能亢進症
- BUN(血中尿素窒素)
- 血清クレアチニン
- 腎機能低下による異常
- 正球正色素性貧血
- 体液量増加
- 高血圧
- 浮腫
- 心不全徴候
- 低ナトリウム血症
- 原因疾患
- 糖尿病性腎症
- 慢性糸球体腎炎
- 腎硬化症
- IgA腎症
- 膜性腎症
急性糸球体腎炎
- A群β溶血連鎖球菌の感染後に発症する血尿をきたす疾患
- 3~10歳の男児に起こりやすい
- 溶連菌に感染
- 溶連菌が体内に侵襲し、抗体と結合して免疫複合体になる
- 溶連菌にて咽頭炎や扁桃炎がおこる
- Ⅲ型アレルギー発生
- 腎臓に運ばれた免疫複合体が糸球体にひっかかって沈着する
- Ⅲ型アレルギーが発生して白血球や補体が活性化する(補体が使われて補体価低下)
- 糸球体障害
- 免疫反応で炎症が発生することで、糸球体の細胞が障害される
- 糸球体毛細血管が押しつぶされて毛細血管が閉塞
- 糸球体ろ過量減↓
- 体内に水が貯留
- 浮腫
- 高血圧
- 乏尿
- 炎症によりろ過膜がボロボロ
- 血尿
- タンパク尿
- 糸球体毛細血管が押しつぶされて毛細血管が閉塞
- 免疫反応で炎症が発生することで、糸球体の細胞が障害される
ネフローゼ症候群
- 何らかの原因によりタンパク尿が出ることで起こる疾患
- 高血圧にはならない
- 原因疾患
- ループス腎炎
- 糖尿病
- 病態
- タンパク尿
- 低アルブミン血症
- 浮腫
- 高脂血症、高コレステロール
腎盂腎炎
- 細菌の上行感染による腎盂・腎杯・腎間質に炎症が起こる疾患
- 急性腎盂腎炎
- 症状
- 3徴候⇒発熱、腰痛、膿尿
- 肋骨脊柱隔の叩打痛
- 腎機能は正常
- 尿検査
- 尿中白血病増加
- 細菌尿
- タンパク尿
- 血液検査
- 全身炎症所見を伴う
- 発熱
- CRP陽性
- 血沈亢進
- 症状
- 慢性腎盂腎炎
- 尿路の器質的疾患
- 無症状だが、腎機能が徐々に低下
前立腺肥大と前立腺癌
- 高齢者に多い
- 症状
- 夜間頻尿
- 残尿感
- 飲酒による急性尿閉
- 尿失禁
- 直腸指診
- 前立腺の腫脹(表面が滑らかで弾性硬~軟)
- 前立腺癌
- 直腸指診で硬い腫瘤を触知
- 骨転移しやすい
- PSA
泌尿器系疾患
疾患と痛みが放散する部位との組合せで誤っているのはどれか。
- 狭心症 ────── 左肩
- 胆石症 ────── 右肩
- 十二指腸潰瘍 ─── 右肩
- 尿管結石 ───── 鼡径部
症状と疾患との組合せで誤っているのはどれか。
- 多尿 ─── 尿崩症
- 頻尿 ─── 膀胱炎
- 無尿 ─── 前立腺肥大症
- 血尿 ─── 腎結石症
腎疾患と所見との組合せで正しいのはどれか。
- 慢性腎不全 ────── 低リン血症
- 急性腎不全 ────── 代謝性アシドーシス
- 急性糸球体腎炎 ──── 低血圧
- ネフローゼ症候群 ─── 低コレステロール血症
腎疾患と所見の組合せで正しいのはどれか。
- 慢性腎不全 ―――――― 高リン血症
- 急性腎不全 ―――――― 代謝性アルカローシス
- ネフローゼ症候群 ――― 低コレステロール血症
- 急性糸球体腎炎 ―――― 低血圧
排尿異常で適切でない記述はどれか。
- 前立腺肥大では尿閉になりやすい。
- 膀胱炎では頻尿になりやすい。
- 尿管結石では多尿になりやすい。
- 神経因性膀胱では切迫性尿失禁になりやすい。
肋骨脊柱角に叩打痛がみられるのはどれか。
- 慢性胃炎
- 腎盂腎炎
- 慢性膵炎
- 急性肝炎
側腹部の疝痛と血尿とがみられる疾患はどれか。
- 急性腎炎
- 膀胱腫瘍
- 膀胱炎
- 尿路結石症
腎疾患で高血圧を特徴としないのはどれか。
- 慢性糸球体腎炎
- 腎硬化症
- 急性糸球体腎炎
- ネフローゼ症候群
慢性腎不全でみられるのはどれか。
- 血清尿素窒素低値
- 多血症
- 低リン血症
- 高血圧症
慢性腎不全でみられるのはどれか。
- 低カリウム血症
- 高カルシウム血症
- 高ナトリウム血症
- 高リン血症
慢性腎不全の検査所見で誤っているのはどれか。
- 糸球体ろ過値(GFR)の上昇
- 正球性正色素性貧血
- 血清クレアチニン値の上昇
- 高カリウム血症
慢性腎不全で高値を示すのはどれか。
- 血中カルシウム
- 糸球体ろ過値
- 血中エリスロポイエチン
- 血中カリウム
慢性腎不全で低値を示す検査値はどれか。
- 血清尿素窒素
- 血清尿酸
- 血清カリウム
- クレアチニンクリアランス
腎前性急性腎不全の病因はどれか。
- ミオグロビン尿症
- 尿管結石
- 糸球体腎炎
- 脱水
腎前性急性腎不全の病因はどれか。
- 前立腺癌
- 急性糸球体腎炎
- 広範囲熱傷
- ミオグロビン尿症
腎前性腎不全の病因はどれか。
- 急性腎炎症候群
- 後腹膜腫瘍
- 出血性ショック
- 前立腺癌
慢性腎不全で適切でない検査所見はどれか。
- 血清尿素窒素高値
- 血清クレアチニン高値
- 代謝性アシドーシス
- 尿濃縮力増加
急性糸球体腎炎の症状で正しいのはどれか。
- 糖尿
- 多尿
- 細菌尿
- 血尿
急性糸球体腎炎について正しい記述はどれか。
- 先行感染から数か月後に発症する。
- 発症直後は高蛋白食を与える。
- 血清補体価は高値となる。
- 溶血性連鎖球菌感染が原因となる。
急性糸球体腎炎について正しいのはどれか。
- 高齢者に多い。
- 血清補体価は上昇する。
- 予後は良好である。
- 細菌尿がみられる。
急性腎盂腎炎の尿所見で適切でないのはどれか。
- 脂肪円柱
- 白血球円柱
- 細菌尿
- 蛋白尿
腎盂腎炎を起こしにくいのはどれか。
- 尿崩症
- 馬蹄腎
- 膀胱尿管逆流現象
- 尿路結石
ネフローゼ症候群にみられないのはどれか。
- 高蛋白血症
- 浮腫
- 高脂血症
- 高度の蛋白尿
ネフローゼ症候群の特徴でないのはどれか。
- 低蛋白血症
- ミオグロビン尿症
- 高脂血症
- 全身浮腫
ネフローゼ症候群をきたす疾患はどれか。
- 腎盂腎炎
- 間質性腎炎
- ループス腎炎
- 膀胱炎
ネフローゼ症候群の診断基準に含まれるのはどれか。
- 高蛋白血症
- 尿糖
- 高LDLコレステロール血症
- 排尿痛
下垂体性尿崩症について誤っている記述はどれか。
- 続発性尿崩症の頻度が高い。
- 多飲となる。
- バゾプレッシンの分泌が低下している。
- 高血糖を認める。
前立腺肥大症について正しいのはどれか。
- 蛋白尿がみられる。
- 夜間頻尿がみられる。
- 下腹痛を伴うことが多い。
- 若年者に多い。
前立腺肥大症について正しいのはどれか。
- 直腸指診では石のように硬く触れる。
- 蛋白尿がみられる。
- 夜間頻尿がみられる。
- 骨転移がみられる。
尿路結石の再発予防に有用なのはどれか。
- 尿酸排泄促進薬内服
- ホウレンソウ摂取
- 水分摂取
- 柑橘類摂取
急性膀胱炎について正しいのはどれか。
- 排尿後の痛みが多い。
- 水分はあまり摂らない方がよい。
- 男性に多い。
- 原因菌は黄色ブドウ球菌が多い。
「50歳の男性。主訴は下肢の浮腫。血液検査は総蛋白5.2g/dl、アルブミン2.5g/dl、総コレステロール280mg/dl。尿検査は尿糖3+、尿蛋白4+であった。」 下肢浮腫の触診部位で最も適切なのはどれか。
- 外果
- 内果
- アキレス腱
- 脛骨前面
「50歳の男性。主訴は下肢の浮腫。血液検査は総蛋白5.2g/dl、アルブミン2.5g/dl、総コレステロール280mg/dl。尿検査は尿糖3+、尿蛋白4+であった。」 本症例でみられる浮腫の主な原因はどれか。
- リンパ液のうっ滞
- 血漿膠質浸透圧の低下
- 静水圧の上昇
- 血管透過性亢進
「72歳の女性。頻尿と尿意切迫感を主訴に来院した。尿一般検査と尿細菌検査に異常はなかった。腹部超音波検査で残尿はみられなかった。」 考えられる疾患はどれか。
- 腎盂腎炎
- 急性膀胱炎
- 過活動膀胱
- 腎結石
「72歳の女性。頻尿と尿意切迫感を主訴に来院した。尿一般検査と尿細菌検査に異常はなかった。腹部超音波検査で残尿はみられなかった。」 生活指導について適切なのはどれか。
- 坐位時間を長くする。
- 骨盤底筋訓練を行う。
- 水分摂取を控える。
- 尿意を感じたらすぐに排尿する。