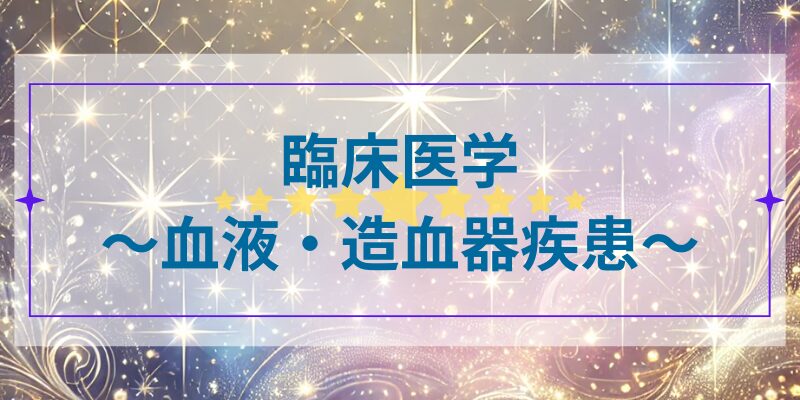🌟黄疸とは?~ビリルビン代謝と分類のポイント~
黄疸(おうだん)は、皮膚や眼球結膜が黄色く変色する症状で、血中ビリルビン濃度の異常な上昇(高ビリルビン血症)が原因です。
通常、血清ビリルビン値が約2mg/dLを超えると黄染が目立ってきます。
黄疸の分類やビリルビンの代謝機序を理解することで、疾患の鑑別や臨床対応に役立ちます。
🔬赤血球の寿命と崩壊
- 赤血球の寿命は約120日で、古くなった赤血球は脾臓・肝臓・骨髄で分解されます。
- 赤血球内のヘモグロビンは代謝され、最終的にビリルビンへと変化します。
脾臓について正しい記述はどれか。
- 右上腹部にある
- 肝臓の次に大きな臓器である
- 血小板を産生する
- 古い赤血球を破壊する
溶血を起こすのはどれか。
- 赤血球と好中球との混合
- 蒸留水の添加
- 血小板の減少
- 血液凝固因子の除去
血液への添加で溶血を起こすのはどれか。
- ナトリウムイオン
- 蒸留水
- カルシウムイオン
- トロンビン
赤血球に由来しない色素はどれか。
- ヘモジデリン
- ヘマトイジン
- ビリルビン
- メラニン
誤っている組合せはどれか。
1.痛風---尿酸
2.黄疸---ビリルビン
3.アミロイドーシス---へモジデリン
4.ゴーシェ病---類脂質
🧪ビリルビンの代謝と分類
- 赤血球由来のヘモグロビンは代謝され間接型ビリルビン(脂溶性)となり、肝臓へ運ばれます。
- 肝細胞でグルクロン酸と抱合され、直接型ビリルビン(水溶性)へと変換されます。
- 直接型ビリルビンは胆汁として腸管へ分泌され、腸内細菌の働きでウロビリノゲンやステルコビリンへと変化します。
- 一部のウロビリノゲンは再吸収され尿中に排泄されます。
ビリルビンについて誤っているのはどれか。
- 胆汁成分である。
- 血漿蛋白である。
- 腸内でウロビリノゲンになる。
- ヘモグロビンの分解産物である。
胆汁について正しいのはどれか。
- 胆囊で産生される。
- ビリルビンを含む。
- 消化酵素を含む。
- 脂肪分の多い食事により分泌が低下する。
赤血球の破壊で生じるのはどれか。
- グロブリン
- フィブリノーゲン
- ウロビリノゲン
- プラスミノーゲン
健常成人の胃液に含まれないのはどれか。
- 塩酸
- ムチン
- ペプシン
- ビリルビン
肝臓の働きで誤っているのはどれか。
- 血液凝固因子を産生する。
- 血液中の有害物質を無害化する。
- ブドウ糖からグリコーゲンを合成する。
- ビリルビンをウロビリノゲンにする。
📊黄疸の分類と原因
- 黄疸は主に以下の3つに分類されます:
- 肝前性黄疸:赤血球崩壊の亢進(例:溶血)
- 肝細胞性黄疸:肝臓内の抱合・排泄障害(例:肝炎、肝硬変)
- 肝後性黄疸:胆道閉塞による排泄障害(例:総胆管結石、胆管癌)
- 黄疸の鑑別では、直接型・間接型ビリルビンの比率が重要な手がかりになります。
🩸肝前性黄疸の特徴
赤血球が過剰に破壊されると、肝臓で処理できる量を超えて間接ビリルビンが増加します。
- 溶血性黄疸:
- 自己免疫性溶血性貧血、輸血ミスマッチ、遺伝性球状赤血球症
- 全身性エリテマトーデス(SLE)などの膠原病
- 新生児黄疸:肝機能が未熟なため一時的に間接ビリルビンが増加
- 核黄疸:重症新生児黄疸が中枢神経に影響(感音性難聴・知的障害)
- 胎児性溶血性疾患:Rh不適合妊娠による母子間溶血
脾腫をきたす疾患はどれか。
- 血友病
- 溶血性貧血
- 鉄欠乏性貧血
- 再生不良性貧血
血中間接ビリルビンが高値となるのはどれか。
- 溶血性黄疸
- 急性肝炎
- 閉塞性黄疸
- 薬剤性肝障害
貧血黄疸がみられるのはどれか。
- 溶血性貧血
- 巨赤芽球性貧血
- 鉄欠乏性貧血
- 再生不良性貧血
黄疸をきたす疾患はどれか。
- 糖尿病
- 慢性心不全
- 脂質異常症
- 溶血性貧血
間接ビリルビンの増加する貧血はどれか。
- 溶血性貧血
- 巨赤芽球性貧血
- 鉄欠乏性貧血
- 再生不良性貧血
黄疸をきたす疾患で尿中ビリルビンが上昇しないのはどれか。
- 胆石症
- 膵臓癌
- 急性肝炎
- 溶血性貧血
赤血球型不適合輸血に特徴的な副作用はどれか。
- 急性溶血反応
- 急性発熱反応
- 移植片対宿主病
- 肝炎ウイルス感染
溶血性黄疸の原因として最も適切なのはどれか。
- 肝炎
- 胆石
- 血液型不適合輸血
- 先天性胆道閉塞症
溶血性黄疸はどれか。
- 新生児黄疸
- C型肝炎による黄疸
- 胆石症による黄疸
- 膵頭部癌による黄疸
🧬肝細胞性黄疸の病態
- 肝細胞が障害されると、ビリルビンの抱合や胆汁排泄がうまく行われず、直接型ビリルビンが血中に逆流します。
- 原因:
- 急性・慢性肝炎
- 肝硬変による肝機能低下
- 肝癌など肝実質の病変
- しばしば低コレステロール血症も伴います。
肝硬変のときにみられる顔色で正しいのはどれか。
- 蒼白
- 紅潮
- チアノーゼ
- 黄疸
🚫肝後性黄疸と閉塞性黄疸
- 胆道が閉塞すると、胆汁に排出されるはずの直接型ビリルビンが血中に逆流します。
- 代表疾患:
- 総胆管結石
- 胆管癌
- 先天性胆道閉塞症
- 膵頭部癌
- 随伴症状として肝腫大・高コレステロール血症・γ-GTP上昇を伴います。
γ-GTPの上昇がみられる疾患はどれか。
- 食道炎
- 胃炎
- 溶血性貧血
- 閉塞性黄疸
40歳の肥満女性。右季肋部の疼痛と発熱、黄疸が認められた。最も考えられるのはどれか。
- 膵尾部癌
- 総胆管結石
- 腎結石
- 肝硬変
🧾直接型・間接型ビリルビンの臨床鑑別
- 高間接型ビリルビン血症:
- 溶血性黄疸、新生児黄疸など
- 尿中にビリルビンは出現しない
- 高直接型ビリルビン血症:
- 肝炎、肝硬変、胆道閉塞など
- 尿中にビリルビンが排泄される
「60歳の女性。主訴は黄疸。発熱と腹痛は認めない。貧血と間接ビリルビンの上昇が認められ、腹部超音波検査では脾腫と胆石を認めた。」黄疸の原因として最も考えられるのはどれか。
- 胆石嵌頓
- 肝細胞破壊
- 赤血球寿命短縮
- 側腹血行路形成
鍼刺激の影響をみるとき、尿中ウロビリン体量が指標となる臓器はどれか。
- 肺
- 心臓
- 膵臓
- 肝臓
黄疸の発生原因として適切でないのはどれか。
- 胆嚢内結石
- 膵頭部癌
- ウイルス性肝炎
- 不適合輸血
黄疸をきたさない疾患はどれか。
- 急性肝炎
- 脂肪肝
- 胆石症
- 溶血性貧血
十二指腸潰瘍の症状でないのはどれか。
- 黄疸
- 吐血
- 下血
- 空腹時痛
「60歳の女性。主訴は黄疸。発熱と腹痛は認めない。貧血と間接ビリルビンの上昇が認められ、腹部超音波検査では脾腫と胆石を認めた。」黄疸の診察部位として正しいのはどれか。
- 眼瞼結膜
- 眼球結膜
- 口腔粘膜
- 舌
🌟貧血の種類と特徴~国家試験に出るポイントをおさえよう~
貧血とは、全身の組織へ酸素を運ぶ赤血球の量が減少した状態を指し、原因や病態によって分類されます。
国家試験では、再生不良性貧血・鉄欠乏性貧血・巨赤芽球性貧血の3つの代表的な疾患が頻出です。
📘国家試験で狙われるポイント
- 再生不良性貧血:汎血球減少+骨髄低形成
- 鉄欠乏性貧血:小球性低色素性+出血・吸収障害
- 巨赤芽球性貧血:B12欠乏+内因子+ハンター舌
🔍まずは基本:貧血の主な症状と原因疾患
- 症状
- 心拍数上昇(頻脈、動悸)
- 呼吸数上昇(息切れ)
- 皮膚・粘膜の蒼白
- 全身倦怠感、疲れやすさ
- 貧血の背景となる疾患
- 出血性疾患(消化管出血など)
- 悪性腫瘍
- 白血病・悪性リンパ腫
- 膠原病(全身性エリテマトーデスなど)
貧血で正しいのはどれか。
- 徐脈となる。
- 眼球結膜が充血する。
- 鉄欠乏は原因の一つである。
- 血液データの赤血球数で診断される。
貧血を疑う症状はどれか。
- 徐脈
- 顔面蒼白
- 振戦
- 多尿
不足すると貧血になるのはどれか。
- 塩分
- 鉄分
- 脂質
- 糖質
貧血の症状でないのはどれか。
- 動悸
- 息切れ
- 易疲労性
- 顔面紅潮
貧血をきたす疾患はどれか。
- パーキンソン病
- 高血圧症
- 全身性エリテマトーデス
- 高脂血症
貧血の要因でないのはどれか。
- 胃の全切除
- 栄養不足
- 高地への移住
- 脾臓の機能亢進
貧血について誤っている組合せはどれか。
- 鉄欠乏性貧血---大球性正色素性赤血球
- 悪性貧血---ビタミンB12欠乏
- 再生不良性貧血---汎血球減少
- 溶血性貧血---黄疸
貧血について誤っている組合せはどれか。
- 悪性貧血---ビタミンB12欠乏
- 鉄欠乏性貧血---総鉄結合能低下
- 溶血性貧血---黄疸
- 再生不良性貧血---骨髄の造血細胞減少
貧血とその原因との組合せで誤っているのはどれか。
- 鉄欠乏性貧血---慢性出血
- 悪性貧血---赤血球の崩壊亢進
- 遺伝性球状赤血球症---赤血球の浸透圧抵抗減弱
- 再生不良性貧血---骨髄の低形成
貧血とその原因との組合せで誤っているのはどれか。
- 悪性貧血---ビタミンC欠乏
- 鉄欠乏性貧血---月経過多症
- 再生不良性貧血---原爆症
- 溶血性貧血---Rh血液型不適合
貧血と病態との組合せで誤っているのはどれか。
- 鉄欠乏性貧血---骨髄赤芽球増加
- 悪性貧血---ビタミンB6欠乏
- 溶血性貧血---脾腫
- 再生不良性貧血---白血球減少
貧血の治療で誤っている組合せはどれか。
- 悪性貧血---ビタミンC
- 再生不良性貧血---骨髄移植
- 腎性貧血---エリスロポイエチン
- 自己免疫性溶血性貧血---脾臓摘出術
貧血について誤っている組合せはどれか。
- 鉄欠乏性貧血---血清フェリチン増加
- 巨赤芽球性貧血---ビタミンB12欠乏
- 溶血性貧血---脾腫
- 再生不良性貧血---汎血球減少
疾患と所見の組合せで正しいのはどれか。
- 鉄欠乏性貧血---スプーン状爪
- 急性白血病---関節内血腫
- 特発性血小板減少性紫斑病---脾腫
- 血友病---リンパ節腫大
疾患と症状の組合せで正しいのはどれか。
- 溶血性貧血---ばち指
- 鉄欠乏性貧血---スプーン状爪
- 巨赤芽球性貧血---黄疸
- 再生不良性貧血---ハンター舌炎
疾患と診察所見の組合せでよくみられるのはどれか。
- 鉄欠乏性貧血---歯肉出血
- 巨赤芽球性貧血---関節内出血
- 腎性貧血---血尿
- 再生不良性貧血---鼻出血
血液疾患で誤っている組合せはどれか。
- 鉄欠乏性貧血---スプーン様爪変形
- 悪性貧血---ビタミンB2欠乏
- 再生不良性貧血---末梢血汎血球減少
- 紫斑病---血小板異常
血液疾患と原因との組合せで誤っているのはどれか。
- 血友病---凝固因子欠損
- 溶血性貧血---血液型不適合
- 鉄欠乏性貧血---骨髄機能障害
- 悪性貧血---ビタミンB12欠乏
血液疾患と原因との組合せで誤っているのはどれか。
- 血友病---凝固因子欠乏
- 悪性貧血---ウイルス感染
- 白血病---放射線被曝
- 鉄欠乏性貧血---子宮筋腫
血液疾患について誤っているのはどれか。
- 鉄欠乏性貧血はヘモグロビン産生量の減少により生じる。
- 悪性貧血はビタミンB1の欠乏により生じる。
- 急性白血病では白血球が急激に無制限に増殖する。
- 血友病では第8凝固因子が欠乏している。
ビタミンとその欠乏症との組合せで誤っているのはどれか。
- ビタミンA---夜盲症
- ビタミンB1---脚気
- ビタミンC---悪性貧血
- ビタミンD---骨軟化症
🩸再生不良性貧血の特徴
- 骨髄の低形成(多能性造血幹細胞の減少)
- 赤血球・白血球・血小板のすべてが減少(汎血球減少)
- 症状:貧血・易感染・出血傾向
- 治療には骨髄移植や免疫抑制療法など
再生不良性貧血
- 骨髄の低形成
- 骨髄の造血幹細胞(多能性幹細胞)減少
- 赤血球、白血球、血小板の数が減少
- 汎血球減少症
- 貧血症状
- 易感染
- 出血傾向
- 骨髄移植
易感染性をきたすのはどれか。
- 鉄欠乏性貧血
- 溶血性貧血
- 腎性貧血
- 再生不良性貧血
多能性幹細胞の障害によるのはどれか。
- 鉄欠乏性貧血
- 溶血性貧血
- 腎性貧血
- 再生不良性貧血
汎血球減少症をきたすのはどれか。
- 腎性貧血
- 溶血性貧血
- 鉄欠乏性貧血
- 再生不良性貧血
汎血球減少症をきたすのはどれか。
- 鉄欠乏性貧血
- 腎性貧血
- 溶血性貧血
- 再生不良性貧血
血小板が減少する疾患はどれか。
- 鉄欠乏性貧血
- 血友病
- 再生不良性貧血
- 慢性白血病
加齢に伴う病変と最も関連の低いのはどれか。
- 脳血管障害
- 骨粗鬆症
- 再生不良性貧血
- 嚥下性肺炎
🩸鉄欠乏性貧血の特徴
- 小球性低色素性貧血
- 慢性出血(月経過多、子宮筋腫、痔核、大腸がん など)
- 妊娠や胃切除後、鉄吸収障害なども原因
- 検査所見:血清鉄↓、フェリチン↓、総鉄結合能↑
- 特徴的な症状:スプーン状爪、舌乳頭萎縮
鉄欠乏性貧血について正しい記述はどれか。
- 男性に多くみられる。
- ハンター舌炎がみられる。
- フェリチンが減少する。
- 総鉄結合能が減少する。
鉄欠乏性貧血について正しいのはどれか。
- 大球性貧血である。
- 正色素性貧血である。
- 総鉄結合能は低下する。
- 鉄剤投与によって網状赤血球は増加する。
鉄欠乏性貧血について正しいのはどれか。
- 男性に多い。
- スプーン状爪がみられる。
- 大球性貧血となる。
- 血清フェリチンは増加する。
鉄欠乏性貧血について適切でない記述はどれか。
- 息切れ・動悸の訴えがある。
- 妊娠時に起こりやすい。
- ビタミン剤の投与が有効である。
- 血清フェリチン値は減少する。
鉄欠乏性貧血について誤っているのはどれか。
- 女性に多い。
- 大球性貧血である。
- 貧血の中で最も頻度が高い。
- 血清フェリチン値は低下する。
鉄欠乏性貧血の原因として適切でないのはどれか。
- 大腸癌
- 過多月経
- 妊娠
- 痛風
鉄欠乏性貧血の症状でないのはどれか。
- スプーン状爪
- 舌乳頭萎縮
- チアノーゼ
- 頻脈
鉄欠乏性貧血をきたさないのはどれか。
- 胃切除後
- 子宮筋腫
- 高脂血症
- 痔核
低色素性貧血はどれか。
- 鉄欠乏性貧血
- 巨赤芽球性貧血
- 溶血性貧血
- 再生不良性貧血
出血傾向がみられない疾患はどれか。
- 急性骨髄性白血病
- 鉄欠乏性貧血
- 壊血病
- 肝硬変
スプーン状爪のみられるのはどれか。
- 細菌性食中毒
- 糸球体腎炎
- 血友病
- 鉄欠乏性貧血
自己免疫機序が関与しないのはどれか。
- 悪性貧血
- 溶血性貧血
- 鉄欠乏性貧血
- 再生不良性貧血
小球性低色素性貧血を呈するのはどれか。
- 鉄欠乏性貧血
- 巨赤芽球性貧血
- 溶血性貧血
- 再生不良性貧血
小球性低色素性貧血をきたすのはどれか。
- 溶血性貧血
- 鉄欠乏性貧血
- 再生不良性貧血
- 巨赤芽球性貧血
小球性低色素性貧血を呈するのはどれか。
- 鉄欠乏性貧血
- 巨赤芽球性貧血
- 溶血性貧血
- 再生不良性貧血
頻脈がみられるのはどれか。
- 鉄欠乏性貧血
- 糖尿病
- バージャー病
- 甲状腺機能低下症
喫煙者に起こりやすい健康障害で誤っているのはどれか。
- 肺癌
- 慢性気管支炎
- 鉄欠乏性貧血
- 冠動脈疾患
「48歳の女性。1年前から月経血量が増え、労作時に息切れするようになった。手術歴はない。眼瞼結膜は蒼白である。出血傾向、黄疸、浮腫はない。」この文で示す症例について、最も考えられる疾患はどれか。
- 再生不良性貧血
- 鉄欠乏性貧血
- 溶血性貧血
- 悪性貧血
「48歳の女性。1年前から月経血量が増え、労作時に息切れするようになった。手術歴はない。眼瞼結膜は蒼白である。出血傾向、黄疸、浮腫はない。」この文で示す症例について、最もみられる所見はどれか。
- 手掌紅斑
- ばち指
- スプーン状爪
- クモ状血管腫
鉄欠乏性貧血について正しいのはどれか。
- 葉酸の欠乏が原因となる。
- 血清フェリチンは増加する。
- 小球性貧血がみられる。
- 骨髄は低形成である。
鉄欠乏性貧血でみられるのはどれか。
- 紫斑
- 脾腫
- 汎血球減少
- スプーン状爪
鉄欠乏性貧血の症状で適切でないのはどれか。
- 顔面蒼白
- 易疲労性
- 徐脈
- 息切れ
「45歳の女性。2か月前から易疲労感、動悸、息切れ、体重減少が出現した。血液検査では、血中ヘモグロビンと平均赤血球容積は低値であった。」薬物治療にて症状は改善した。今後食事で特に摂取すべきものはどれか。
- 赤身の肉類
- 豆腐
- 緑黄色野菜
- 海藻
🩸巨赤芽球性貧血(悪性貧血)の特徴
- ビタミンB12欠乏や葉酸不足が原因
- 胃切除後(3〜5年)に内因子欠乏 → B12吸収障害
- 抗内因子抗体陽性 → 自己免疫性
- 大球性正色素性貧血
- ハンター舌(舌の赤くツルツルした萎縮)が特徴的
悪性貧血について正しいのはどれか。
- 伴性劣性遺伝である。
- 抗内因子抗体が陽性となる。
- 正球性貧血を呈する。
- ビタミンB1投与が有効である。
ハンター舌炎がみられるのはどれか。
- 溶血性貧血
- 鉄欠乏性貧血
- 巨赤芽球性貧血
- 再生不良性貧血
「55歳の女性。息切れ、動悸、めまいを主訴に来院した。45歳で胃全摘手術の既往がある。血液検査では大球性正色素性貧血を認めた。」本疾患でみられるのはどれか。
- 黄疸
- スプーン状爪
- 脾腫
- ハンター舌炎
ビタミンB12欠乏による疾患はどれか。
- 骨軟化症
- ウェルニッケ脳症
- 巨赤芽球性貧血
- 脂漏性皮層炎
「55歳の女性。息切れ、動悸、めまいを主訴に来院した。45歳で胃全摘手術の既往がある。血液検査では大球性正色素性貧血を認めた。」本疾患の原因はどれか。
- ビタミンA欠乏
- ビタミンB6欠乏
- ビタミンB12欠乏
- ビタミンK欠乏
「70歳の男性。胃全摘手術後3年。労作時息切れを訴えるようになった。眼瞼結膜は蒼白である。出血傾向、黄疸、浮腫はない。鉄剤は投与されている。」適切な治療はどれか。
- ビタミンC経口投与
- ビタミンB12筋肉注射
- 濃厚赤血球輸血
- 副腎皮質ステロイド経口投与
「70歳の男性。胃全摘手術後3年。労作時息切れを訴えるようになった。眼瞼結膜は蒼白である。出血傾向、黄疸、浮腫はない。鉄剤は投与されている。」最も考えられる検査所見はどれか。
- 小球性低色素性貧血
- 大球性正色素性貧血
- 正球性正色素性貧血
- 汎血球減少
関節リウマチで起こりにくいのはどれか。
- 出血傾向
- 朝のこわばり
- 対称性関節腫脹
- 赤沈値亢進
慢性白血病で誤っているのはどれか。
- 骨髄性とリンパ性とがある。
- 肝腫と脾腫がともにみられる。
- 出血傾向がみられる。
- 予後は不良である。
🌟血小板と血液凝固因子
血小板の特徴と役割
- 血小板(platelet)は、骨髄中の巨核球からちぎれてできる細胞片で、核を持たない。
- 大きさは直径2〜3μm、血液1μLあたり15〜25万個程度が存在。
- 寿命は約8〜10日間で、主に脾臓で破壊される。
- 止血作用を担い、傷ついた血管をふさぐように凝集・粘着・放出を行う。
- 灸刺激、特に透熱灸は、血小板の凝集能を高めるという報告もあり、東洋医学的観点からも注目されている。
血小板異常による疾患
- 血小板減少症(出血傾向):
- 造血障害:再生不良性貧血、巨赤芽球性貧血、急性白血病など
- 脾臓での破壊亢進:肝硬変、脾機能亢進
- 自己免疫疾患:特発性血小板減少性紫斑病(ITP)
- アレルギー:アレルギー性紫斑病
- 血小板増多症(血栓傾向):
- 慢性骨髄性白血病、関節リウマチ、感染症、鉄欠乏性貧血など
血液の細胞成分とその機能との組合せで正しいのはどれか。
- 赤血球---抗体産生
- リンパ球---血液凝固
- 好中球---酸素運搬
- 血小板---止血
健康成人の血小板について誤っている記述はどれか。
- 血液1mm3中に約15〜40万個ある。
- 骨髄幹細胞から分化する。
- 止血作用がある。
- 有核細胞である。
血小板について誤っている記述はどれか。
- 直径は2〜5μmである。
- 寿命は約10日である。
- 核をもつ。
- 血液凝固に関与する。
血小板が減少する疾患はどれか。
- 鉄欠乏性貧血
- 血友病
- 再生不良性貧血
- 慢性白血病
透熱灸による局所炎症反応で正しいのはどれか。
- 皮膚血流量減少
- 血管透過性抑制
- 血小板凝集能亢進
- マスト細胞活性抑制
血栓形成の誘因はどれか。
- 血流速度の上昇
- 内皮細胞の障害
- 血液粘度の低下
- 線溶系の亢進
血友病について誤っているのはどれか。
- 遺伝性疾患
- 血小板数減少
- 毛細管抵抗正常
- 凝固時間延長
非代償性肝硬変でみられる血液検査所見はどれか。
- 総ビリルビン値低下
- 血小板減少
- プロトロンビン時間短縮
- アルブミン値上昇
関節リウマチの血液検査所見で誤っているのはどれか。
- 赤血球数減少
- CRP陽性
- 血小板数減少
- 赤沈値促進
急性白血病の症状で誤っているのはどれか。
- 貧血
- 出血傾向
- 白血球増多
- 血小板増多
急性肺炎の検査所見で誤っているのはどれか。
- 赤沈亢進
- CRP陽性
- 好中球増多
- 血小板増多
浮腫の成因として最も関連の低いのはどれか。
- 血小板減少症
- 低アルブミン血症
- うっ血性心不全
- ネフローゼ症候群
「60歳の男性。軽度呼吸困難で来院。腹部膨隆と女性化乳房とがみられ、上部消化管内視鏡検査で食道・胃静脈瘤を認める。血液検査で血小板と白血球に減少が認められ、C型肝炎ウイルス陽性であった。」この疾患で血小板減少をきたす原因となる病変臓器はどれか。
- 肺
- 肝臓
- 脾臓
- 腎臓
「52歳の男性。3週間前から倦怠感と微熱がある。舌炎は認めないが、鼻血や歯茎の出血、皮下出血斑がみられる。」最も考えられる疾患はどれか。
- 急性白血病
- 悪性貧血
- 溶血性貧血
- 血友病
止血と血液凝固のメカニズム
- 止血は2段階で行われる。
- 一次止血: 血小板の粘着・凝集により一次血栓形成
- 二次止血: 血液凝固因子によりフィブリン血栓を形成
- これにより血管損傷部が安定的に塞がれる。
止血作用をもつ血液成分はどれか。
1.赤血球
2.血小板
3.リンパ球
4.単球
血液凝固因子とその関連
- プロトロンビン:肝臓で産生。
→ 肝障害(肝炎・肝硬変・肝がん)でプロトロンビン時間(PT)が延長 - トロンビン:プロトロンビンが変化してでき、フィブリノゲンをフィブリンに変換する酵素
- フィブリノゲン:肝臓由来。過剰で線維素性炎を起こすことがある
- フィブリン:最終的に血栓を形成する不溶性タンパク
- その他因子:カルシウムイオン(Ca²⁺)、ビタミンK(合成に必要)など
血液凝固に関与する血漿蛋白はどれか。
- ヘパリン
- フィブリノーゲン
- アルブミン
- プラスミン
血液を凝固させる物質はどれか。
- プラスミン
- ヘパリン
- アルブミン
- プロトロンビン
血液凝固因子はどれか。
- ヘパリン
- ビタミンB12
- ウロキナーゼ
- カルシウムイオン
血液凝固因子はどれか。
- ヘパリン
- アルブミン
- フィブリノゲン
- γ-グロブリン
血液凝固に関与するのはどれか。
- ビタミンC
- ビタミンD
- ビタミンE
- ビタミンK
線維素溶解に働く物質はどれか。
- プラスミン
- トロンビン
- アルブミン
- カルシウム
血液凝固に関与しないのはどれか。
- トロンボプラスチン
- プロトロンビン
- プラスミン
- カルシウムイオン
フィブリノーゲンをフィブリンに変えるのはどれか。
- トロンビン
- プラスミン
- ヘパリン
- トロンボキナーゼ
フィブリノゲンの滲出が特徴的なのはどれか。
- 壊疽性炎
- 化膿性炎
- 漿液性炎
- 線維素性炎
透熱灸による血液凝固・線維素溶解系の亢進に関与しないのはどれか。
- プラスミン
- サブスタンスP
- プロトロンビン
- カルシウム
線溶系:血栓を溶かす仕組み
- プラスミン:フィブリンを分解する酵素
- フィブリン血栓を溶かし、血流再開を図る(線溶系)
- バランスが崩れると、出血傾向または血栓症に至る
線維素溶解に働く物質はどれか。
- プラスミン
- トロンビン
- 葉酸
- ビタミンK
🌟出血傾向の疾患とその特徴
出血傾向とは、出血しやすく止血しにくい状態を指します。
通常、止血は血管、血小板、凝固因子、線溶系のバランスによって保たれていますが、これらのいずれかに異常があると、日常生活に支障をきたすほどの出血が起こりやすくなります。
ここでは、国家試験に頻出の代表的な出血性疾患を整理していきましょう。
出血傾向の原因となるのはどれか。
- 総蛋白の減少
- 白血球の減少
- 血小板の減少
- 血糖の減少
出血傾向の原因でないのはどれか。
- 血糖値の異常
- 血小板の異常
- 血液凝固因子の異常
- 血管壁の異常
出血傾向がみられない疾患はどれか。
- 急性骨髄性白血病
- 鉄欠乏性貧血
- 壊血病
- 肝硬変
出血性素因をきたすのはどれか。
- ビタミンA欠乏症
- ビタミンB欠乏
- ビタミンD欠乏
- ビタミンK欠乏症
出血性素因について正しいのはどれか。
- 一次血栓はフィブリンで構成される。
- 血液凝固反応にはビタミンCが重要である。
- 血友病は男性には認められない。
- 特発性血小板減少性紫斑病は自己免疫疾患である。
出血性素因について誤っている記述はどれか。
- 血小板増加により起こる
- いったん出血すると止血しにくい
- 皮下に紫斑をつくりやすい
- わずかな外力で出血する
出血性素因について誤っている記述はどれか。
- 血小板増加により起こる
- いったん出血すると止血しにくい
- 皮下に紫斑をつくりやすい
- わずかな外力で出血する
ビタミンK欠乏が関与するのはどれか。
- 口内炎
- 骨軟化
- 血管脆弱
- 出血傾向
ビタミンK欠乏が関与するのはどれか。
- 口内炎
- 骨軟化
- 血管脆弱
- 出血傾向
ビタミンK欠乏によるのはどれか。
- 口角炎
- 精神症状
- 骨軟化症
- 鼻出血
WHOの「鍼の基礎教育と安全性に関するガイドライン(1999年)」で鍼治療を避けるべき状態としているのはどれか。
- 出血性の疾患
- 歯科の術後痛
- 手術後の嘔吐
- つわり
「52歳の男性。3週間前から倦怠感と微熱がある。舌炎は認めないが、鼻血や歯茎の出血、皮下出血斑がみられる。」診断に必要な血液検査項目で最も適切なのはどれか。
- 葉酸
- 血液像
- 第Ⅷ凝固因子
- ビリルビン
紫斑病(しはんびょう)
- 紫斑:皮膚や粘膜にあらわれる出血斑(赤紫色)。
- 突発性血小板減少性紫斑病(ITP):
- 自己免疫によって血小板が破壊される。
- 成人女性に多い。
- 鼻出血、歯肉出血、月経過多、皮膚の紫斑。
- 血小板数低下、出血時間延長。
- アレルギー性紫斑病(血管性):
- 小児に多い、血管壁がアレルギー反応で障害される。
- 下肢の点状紫斑、腹痛、関節痛、腎障害など。
皮下出血がみられる疾患はどれか。
- 紫斑病
- 関節リウマチ
- 肺気腫
- 過敏性腸症候群
特発性血小板減少性紫斑病の症状で適切でないのはどれか。
- 鼻出血
- 関節内血腫
- 歯肉出血
- 皮膚の点状出血
壊血病(かいけつびょう)
- 原因:ビタミンC欠乏によってコラーゲン合成が不全となり、血管壁が脆弱になる。
- 症状:歯肉出血、皮下出血、関節痛、創傷治癒の遅延。
- 対象者:高齢者、偏食、アルコール依存症、飢餓状態など。
血栓を起こしやすい疾患でないのはどれか。
- 壊血病
- 悪性腫瘍
- 敗血症
- 熱傷
血友病(けつゆうびょう)
- 原因:第VIII因子(血友病A)または第IX因子(血友病B)の欠乏。
- 遺伝形式:伴性劣性遺伝(X染色体上)、男子のみに発症。
- 症状:
- 関節内出血(関節血腫)が特徴。
- 打撲後の筋肉内出血、抜歯後止血困難。
- 検査所見:
- 凝固時間延長
- プロトロンビン時間(PT)正常
- フィブリノゲン正常
- 血小板数正常
血友病について正しい記述はどれか。
- 関節内血腫がみられる。
- 血小板数の減少がみられる。
- 免疫抑制薬を投与する。
- 女性に多い。
血友病について誤っている記述はどれか。
- 遺伝性疾患である。
- 男性に多い。
- 出血傾向がある。
- 凝固因子の内服が必要である。
血友病について誤っているのはどれか。
- 遺伝性疾患
- 血小板数減少
- 毛細管抵抗正常
- 凝固時間延長
伴性遺伝をする先天性疾患はどれか。
- ダウン症候群
- ターナー症候群
- マルファン症候群
- 血友病
女性の全身に紫斑が発生した時に考えられる疾病として適切でないのはどれか。
- 突発性血小板減少性紫斑病
- 血友病
- 敗血症
- アレルギー性紫斑病
血栓を起こしやすい疾患として誤っているのはどれか。
- 動脈瘤
- 血友病
- 動脈硬化症
- 血管炎
鍼治療の絶対禁忌はどれか。
- 血友病
- 慢性閉塞性肺疾患
- 三叉神経痛
- 慢性胃炎
男性に発症しやすいのはどれか。
- 血友病
- 大腸腺腫症
- エドワーズ症候群
- マルファン症候群
WHOでは鍼治療の適応といえる疾患として41疾患をあげているが、そのなかに含まれないのはどれか。
- 胃酸過多症
- メニエール病
- 頸腕症候群
- 血友病
脾腫をきたさない疾患はどれか。
- 慢性骨髄性白血病
- 悪性リンパ腫
- 自己免疫性溶血性貧血
- 血友病
遺伝性疾患はどれか。
- 血友病
- 鉄欠乏性貧血
- 特発性血小板減少性紫斑病
- シェーンライン・ヘノッホ紫斑病
遺伝性疾患はどれか。
- 顆粒球減少症
- ホジキン病
- 血友病
- 血管性紫斑病
🌟血栓・塞栓・梗塞とは?~類似する3つの病態の違いを理解しよう~
「血栓」「塞栓」「梗塞」はいずれも血流障害によって起こる疾患ですが、原因や病態のプロセスが異なります。
国家試験でも頻出のこの3つの概念は、混同しやすいため明確に整理しておく必要があります。
それぞれの違いを理解して、臨床での判断や問題選択のポイントに役立てましょう。
血栓(thrombus)
- 定義:血管内で血液成分が凝固して塊になった状態。
- 主な構成:血小板+フィブリン+赤血球など。
- 原因因子(Virchowの三要素):
- ①血管壁の障害(例:動脈硬化、糖尿病、血管炎)
- ②血流の異常(例:心房細動、静脈瘤、長期臥床)
- ③血液凝固能の亢進(例:脱水、悪性腫瘍、DIC)
- 検査所見:Dダイマー陽性(血栓の分解産物)
- 代表疾患:深部静脈血栓症(DVT)、脳血栓、心筋梗塞など
血栓症を生じやすい疾患はどれか。
- 肝硬変
- 糖尿病
- 再生不良性貧血
- ビタミンC欠乏症
血栓を起こしやすい疾患でないのはどれか。
- 壊血病
- 悪性腫瘍
- 敗血症
- 熱傷
血栓形成の誘因はどれか。
- 血流速度の上昇
- 内皮細胞の障害
- 血液粘度の低下
- 線溶系の亢進
血栓を形成する条件として適切でないのはどれか。
- 血管壁の障害
- 血流速度の低下
- 血液粘度の増加
- 血液量の増加
血栓形成を促進する条件として正しいのはどれか。
- 血流速度の上昇
- 血管壁の損傷
- 血小板の減少
- 血液粘稠度の低下
血栓を起こしやすい疾患として誤っているのはどれか。
- 動脈瘤
- 血友病
- 動脈硬化症
- 血管炎
大腿動脈の血栓症に際して下肢の示す所見で適切でないのはどれか。
- 膝窩に脈を触れない。
- チアノーゼを呈する。
- 皮膚温は低下している。
- 周径が小さくなっている。
栓子の発生原因と、それによって起こる塞栓症の発生部位との組合せで誤っているのはどれか。
- 大腿静脈血栓---肝臓
- 腹部大動脈瘤内血栓---足指
- 下肢複雑骨折---肺
- 潜水病---脳
急性炎症の際、好中球が血管外に遊走するのに必要な要件でないのはどれか。
- 細胞接着分子の活性化
- 血栓の形成
- 血流の減速
- サイトカインの放出
循環障害について誤っている記述はどれか。
- 充血は動脈から過剰の血液が流れ込んだ状態である。
- うっ血は静脈血の流出が妨げられて起こる。
- 血栓症は血管外で血液が凝固する現象である。
- 梗塞は終末動脈の閉塞により生じる。
「68歳の女性。国際線の機内で左下腿が次第に腫脹してきた。熱感や冷感はない。左ふくらはぎに把握痛がある。」最も考えられるのはどれか。
- 心不全
- 急性腎不全
- コンパートメント症候群
- 深部静脈血栓症
「78歳の女性。大腿骨頸部骨折の術後3日間ベッド上安静であったが、突然胸痛、呼吸困難が出現した。胸部単純エックス線写真でうっ血所見はなく、肺野の透過性増大がみられた。血性クレアチニンキナーゼ値は正常、D-ダイマー値上昇が認められた。」本疾患の危険因子として最も重要なのはどれか。
- 脱水
- 貧血
- 運動
- 徐脈
「78歳の女性。大腿骨頸部骨折の術後3日間ベッド上安静であったが、突然胸痛、呼吸困難が出現した。胸部単純エックス線写真でうっ血所見はなく、肺野の透過性増大がみられた。血性クレアチニンキナーゼ値は正常、D-ダイマー値上昇が認められた。」本疾患の発症を予測するのに最も有用な検査はどれか。
- ホルター心電図
- 負荷心筋シンチグラフィ
- 頸動脈超音波検査
- 下肢静脈超音波検査
塞栓(embolus)
- 定義:血流にのって運ばれた異物(固体・液体・気体)が血管内腔を塞いでしまうこと。
- 主な種類:
- ①血栓塞栓:最も頻度が高い(例:心房細動→脳梗塞)
- ②脂肪塞栓:長管骨骨折後に起こりやすい
- ③空気・ガス塞栓:減圧症(潜水病)や手術ミスなど
- ④羊水塞栓:分娩時の急変に注意
- 移動経路の例:
- 心疾患 → 脳動脈 → 脳梗塞
- 下肢静脈 → 肺動脈 → 肺塞栓
- 大動脈 → 末梢動脈 → 足趾壊死
最も頻度の高い塞栓はどれか。
- 腫瘍
- 血栓
- 空気
- 脂肪
塞栓の原因で最も頻度の高いのはどれか。
- 血栓
- 骨髄
- 脂肪
- 腫瘍
塞栓症について誤っている組合せはどれか。
- 心弁膜症---脳の血栓性塞栓
- 外傷性複雑骨折---肺の脂肪性塞栓
- スキューバダイビング---脳のガス塞栓
- 大腿静脈血栓---肝臓の血栓性塞栓
塞栓症について誤っている記述はどれか。
- 血液に溶解しない物質が小血管に閉塞した状態である。
- 最も多いのは脂肪塞栓症である。
- 動脈性塞栓症は脳に生じやすい。
- 局所の変性壊死の原因になる。
奇異塞栓がみられるのはどれか。
- 心室性期外収縮
- 心房中隔欠損症
- 大動脈弁狭窄症
- 感染性心内膜炎
脳塞栓について正しいのはどれか。
- 緩徐に発症する。
- 激しい頭痛を伴う。
- 心房細動に合併する。
- 高血圧はリスクファクターである。
脳塞栓について正しいのはどれか。
- 緩徐に発症する。
- 心房細動に合併する。
- 高血圧はリスクファクターである。
- 激しい頭痛を伴う。
心房細動の合併症はどれか。
- 脳塞栓
- 脳血栓
- 脳出血
- 脳腫瘍
心房細動に合併しやすい脳血管障害はどれか。
- 脳血栓症
- 脳塞栓症
- 脳出血
- くも膜下出血
心房細動と関係の深い疾患はどれか。
- 脳腫瘍
- 脳膜炎
- 脳塞栓
- 脳出血
「72歳の男性。以前より発作性心房細動を指摘されていた。事務作業中に倒れたが、呼びかけには何とか返答できた。右上下肢は全く動かず、頭痛、嘔吐はなかった。」最も考えられるのはどれか。
- くも膜下出血
- 脳血栓
- 脳塞栓
- 一過性脳虚血発作
「68歳の女性。国際線の機内で左下腿が次第に腫脹してきた。熱感や冷感はない。左ふくらはぎに把握痛がある。」その後、胸痛と呼吸困難が出現してきた。最も考えられるのはどれか。
- 肺塞栓症
- 脳梗塞
- 心筋梗塞
- 閉塞性動脈硬化症
肺の脂肪塞栓症の原因とならないのはどれか。
- 早期胎盤剥離
- 大腿骨骨折
- 肥満体の腹部手術
- 交通事故による挫滅
左冠動脈閉塞による急性心筋梗塞で死亡した。肺にみられる変化として適切でないのはどれか。
- 出血
- 塞栓
- 水腫
- うっ血
梗塞(infarction)
- 定義:血管が完全に閉塞し、酸素・栄養が届かなくなることで起こる組織の壊死。
- 種類:
- ①貧血性梗塞:心臓・脾臓・腎臓・脳(白色梗塞)
- ②出血性梗塞:肺・腸など二重血流をもつ臓器(赤色梗塞)
- 特徴:
- 脳や脊髄では融解壊死が起こる
- 多発性脳梗塞は認知症やパーキンソニズムの原因となる
- 肺梗塞では咳嗽、血痰、呼吸困難が出現
梗塞について正しいのはどれか。
- 組織間隙に過剰な水分が貯留した状態
- 動脈から過剰な血液が流れ込んだ状態
- 血管内で血液が凝固した状態
- 終末動脈が閉塞し、その支配組織に壊死が生じた状態
出血性梗塞を最も起こしやすい臓器はどれか。
- 脳
- 肺
- 心臓
- 腎臓
出血性梗塞を最も起こしやすい臓器はどれか。
- 脳
- 脾臓
- 小腸
- 腎臓
出血性梗塞を最も起こしやすいのはどれか。
- 心臓
- 小腸
- 脾臓
- 腎臓
出血性梗塞を最も起こしやすい臓器はどれか。
- 腎臓
- 小腸
- 心臓
- 脾臓
出血性梗塞を最も起こしやすいのはどれか。
- 肺
- 心臓
- 腎臓
- 脾臓
貧血性梗塞を起こしやすい臓器でないのはどれか。
- 心臓
- 肺
- 腎臓
- 脳
梗塞の種類と罹患臓器の組み合わせで正しいのはどれか。
- 出血性梗塞---心臓
- 出血性梗塞---腎臓
- 貧血性梗塞---肺
- 貧血性梗塞---脾臓
融解壊死がよくみられる疾患はどれか。
- 心筋梗塞
- 脳梗塞
- 腎梗塞
- 肺壊疽
融解壊死が最も生じやすい疾患はどれか。
- 腎梗塞
- 脳梗塞
- 脾梗塞
- 心筋梗塞
脳梗塞の原因疾患はどれか。
- 脳腫瘍
- 脳血栓
- 脳炎
- 結核性髄膜炎
脳梗塞を起こしやすい不整脈はどれか。
- 心房細動
- 心室細動
- 期外収縮
- 房室ブロック
🌟動脈硬化の種類と進行メカニズム
動脈硬化は、血管の内壁が厚くなり弾力性を失うことで血流が悪化し、さまざまな心血管疾患のリスクを高める状態を指します。
とくに中年以降に多く見られ、高血圧・脳梗塞・心筋梗塞などの重大な病気の原因となるため、国家試験でも頻出のテーマです。
アテローム性動脈硬化
- 最も一般的なタイプで、大動脈・冠動脈・頸動脈に好発
- 血管内皮の損傷→マクロファージの侵入→LDLコレステロールの沈着→アテローム(粥腫)形成という流れで進行
- アテロームが破綻すると、血小板凝集・血栓形成→心筋梗塞・脳梗塞へ
脂質異常症との関係
- アテローム性動脈硬化の主因は脂質異常症
- 以下のような血中脂質異常がリスクを高める:
- 高トリグリセリド血症(中性脂肪↑)
- 高LDLコレステロール血症(悪玉コレステロール↑)
- 低HDLコレステロール血症(善玉コレステロール↓)
- 脂質異常が続くと、血管内皮障害や酸化LDLが進行し、アテローム形成に拍車をかける
血圧・血栓との関係
- 動脈硬化の進行に伴い、血管の柔軟性が低下→血圧が上昇
- 高血圧は血管壁の損傷を助長し、動脈硬化の悪循環に
- 動脈硬化部位は血小板の粘着が促進され、血栓が形成されやすい状態
- Dダイマーの上昇など、血栓形成の指標もチェックポイント
動脈硬化は生活習慣病の一環としてとらえる必要があります。
高脂血症・糖尿病・喫煙・ストレスなどの改善が、動脈硬化の進行予防に直結します。
国家試験対策では、アテローム形成の流れ、脂質異常との関係、血圧との関連、そして血栓形成にいたるまでの一連の病態生理をしっかり理解しておきましょう。
動脈硬化症を増悪しない血中因子はどれか。
- 総コレステロール
- 中性脂肪
- HDLコレステロール
- LDLコレステロール
血中脂質で基準値を下回ると動脈硬化のリスクが高くなるのはどれか。
- 中性脂肪
- 総コレステロール
- LDLコレステロール
- HDLコレステロール
動脈硬化と関連が少ないのはどれか。
- 肝硬変
- 腎硬化症
- 脳梗塞
- 心筋梗塞
動脈粥状硬化症の誘因として適切でないのはどれか。
- 高脂血症
- 多血症
- 糖尿病
- 高血圧症
血圧を上昇させる要因はどれか。
- 血液粘度の減少
- 血管壁の弾力性の低下
- 迷走神経遠心性活動の亢進
- 圧受容器からの求心性活動の亢進
脂質代謝異常に基づく疾患はどれか。
- アテローム硬化症
- アミロイドーシス
- 痛風
- 尿毒症
関連の少ない組合せはどれか。
- 狭心症---敗血症
- 動脈瘤---梅毒
- 川崎病---血管炎
- 多臓器不全---ショック
脂質代謝異常に起因する疾患はどれか。
- 粥状動脈硬化症
- 糖尿病
- アミロイドーシス
- 痛風
心電図が診断上有用でない疾患はどれか。
- 解離性大動脈瘤
- 期外収縮
- 狭心症
- 心筋梗塞
触診で発見できないのはどれか。
- リンパ節腫脹
- 胸部大動脈瘤
- 肝臓の腫大
- 腹部の腫瘤
血管雑音を聴取するのはどれか。
- 高血圧
- 狭心症
- 心筋梗塞
- 腹部大動脈瘤
坐骨神経痛をきたしにくい疾患はどれか。
- 悪性腫瘍の骨転移
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 帯状疱疹
- 閉塞性動脈硬化症
動脈硬化の部位とその症状との組合せで誤っているのはどれか。
- 内頸動脈---間欠跛行
- 冠動脈---胸痛
- 腎動脈---高血圧
- 大腿動脈---冷感
腰背部痛の原因で生命の危険をきたすのはどれか。
- 腰部脊柱管狭窄症
- 子宮内膜症
- 尿管結石
- 解離性大動脈瘤
「60歳の男性。糖尿病発症から15年経過、現在腎機能は正常。収縮期血圧は180mmHg、拡張期血圧は90mmHgである。」最近下肢の冷感が出現している。最も優先度の高いスクリーニング検査はどれか。
- 心電図
- 頸動脈超音波検査
- 足背動脈拍動の確認
- 両側アキレス腱反射
「78歳の男性。5年前に高血圧を指摘されたが、自覚症状がないため放置していた。早朝、安静時に突然強い胸背部痛が出現し、救急搬送された。その際に胸部エックス線検査で上縦隔の著明な拡大を認めたが、心電図上有意な変化はみられなかった。」この文で示す症例について、診断のため、直ちに施行すべき検査はどれか。
- 24時間ホルター心電図
- 運動負荷心筋シンチ
- 胸腹部造影CT
- 気管支内視鏡
「78歳の男性。5年前に高血圧を指摘されたが、自覚症状がないため放置していた。早朝、安静時に突然強い胸背部痛が出現し、救急搬送された。その際に胸部エックス線検査で上縦隔の著明な拡大を認めたが、心電図上有意な変化はみられなかった。」この文で示す疾患による合併症はどれか。
- 気胸
- 間質性肺炎
- 大動脈弁狭窄症
- 心タンポナーデ
疾患とその治療との組合せで誤っているのはどれか。
- 関節リウマチ---パラフィン浴
- 肩関節周囲炎---ホットパック
- 総腓骨神経麻痺---低周波療法
- 閉塞性動脈硬化症---寒冷療法
下肢の切断原因で近年特に増加しているのはどれか。
- 腫瘍
- 交通外傷
- 血管障害
- 労働災害
心臓リハビリテーションにおける運動療法の禁忌はどれか。
- 心移植後
- 冠動脈形成術後
- 不安定狭心症
- 末梢動脈閉塞性疾患
次の文で示す患者の病態に対する施術目的で最も適切なのはどれか。「76歳の男性。主訴は右下肢痛。間欠性跛行があり、足背動脈及び後脛骨動脈の触知が困難である。下肢の知覚や深部反射に異常はない。」
- 腰部の神経根への圧迫の改善
- 腰部の筋緊張改善
- 下肢の末梢循環改善
- 下肢の筋力増強
次の文で示す患者について、「65歳の男性。主訴は左下肢痛。平地を200mほど歩くと足が痛み、歩けなくなる。しばらく休むとまた歩くことができる。検査所見では左下肢動脈拍動減弱、ケンプ徴候陰性、膝蓋腱反射正常である。」本症例でみられるのはどれ
か。
- 前傾姿勢で休息すると楽になる。
- 痛みは髄節性である。
- 下腿の知覚が鈍い。
- 下肢の冷感がある。
「67歳の男性。BMI30。糖尿病で加療中。200m程歩くと右下腿に痛みが生じるが、休むと軽減し、再び歩くことができる。前屈みで痛みに変化がなかった。」本症にみられるのはどれか。
- 足背動脈拍動消失
- ケンプ徴候陽性
- アキレス腱反射亢進
- トレンデレンブルグ徴候陽性
「70歳の男性。3か月前から歩行によって右下腿後面に締めつけられるような痛みが出現する。休息すると、姿勢にかかわらず痛みが軽減する。SLRテスト陰性、知覚検査異常なし。」最も考えられる疾患はどれか。
- 腰部脊柱管狭窄症
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 閉塞性動脈硬化症
- 糖尿病性ニューロパチー
「70歳の男性。3か月前から歩行によって右下腿後面に締めつけられるような痛みが出現する。休息すると、姿勢にかかわらず痛みが軽減する。SLRテスト陰性、知覚検査異常なし。」この患者の病態に対する施術目的で最も適切なのはどれか。
- 下肢の末梢循環改善
- 下肢の筋力増強
- 腰部の神経根圧迫の改善
- 腰部の筋緊張改善
次の文で示す症例で、患側にみられる所見はどれか。「68歳の男性。最近右足の冷えが強く、5分程度の歩行で右ふくらはぎが痛み、歩行困難となる。一定時間の休息で再び歩けるようになるが、休息姿勢に特徴はない。喫煙習慣があり、血圧が高いが、血糖値は正常である。」
- 後脛骨動脈拍動減弱
- トンプソンテスト陽性
- ボンネットテスト陽性
- アキレス反射減弱
「65歳の男性。1か月前から右足の冷えと歩行中の痛みが出るようになった。休むと痛みが軽減し、再び歩くことができる。ただし、前屈み姿勢により痛みは変化しなかった。痛みの部位はふくらはぎと足底。動脈の触診では膝窩動脈の拍動を確認できたが、右側
下腿の動脈拍動は減弱。」歩行中の痛みを起こす原因はどれか。
- L5神経根の刺激
- 筋肉の虚血
- 末梢神経の炎症
- 筋肉の内圧上昇
「65歳の男性。1か月前から右足の冷えと歩行中の痛みが出るようになった。休むと痛みが軽減し、再び歩くことができる。ただし、前屈み姿勢により痛みは変化しなかった。痛みの部位はふくらはぎと足底。動脈の触診では膝窩動脈の拍動を確認できたが、右側
下腿の動脈拍動は減弱。」拍動の減弱を呈する動脈に向けた刺鍼で、足の冷えと痛みを治療するのに適切な経穴はどれか。
- 衝門
- 委中
- 太渓
- 太衝
次の文で示す症例について、問いに答えよ。「71歳の男性。100mの歩行で左下腿後面に絞扼痛が出現、休息で軽快。仰臥位で両下肢を挙上させ30秒足趾を屈伸させると患側足底部が白くなる。SLRテスト陰性。」身体診察で患側下肢にみられる所見はどれか。
- ケンプ徴候陽性
- 足底部の触覚鈍麻
- アキレス腱反射減弱
- 足背動脈拍動減弱
次の文で示す症例について、問いに答えよ。「71歳の男性。100mの歩行で左下腿後面に絞扼痛が出現、休息で軽快。仰臥位で両下肢を挙上させ30秒足趾を屈伸させると患側足底部が白くなる。SLRテスト陰性。」本症例で、症状のある筋の支配神経近傍に刺鍼し、低周波鍼通電療法を行う場合、最も適切な経穴はどれか。
- 陰廉
- 委中
- 足三里
- 陽陵泉
🌟その他の動脈疾患
動脈疾患といえば動脈硬化が最も代表的ですが、それ以外にも特定の血管に炎症が起こったり、末梢循環に障害を及ぼすような疾患が存在します。
ここでは、国家試験でも頻出の「大動脈炎症候群(高安病)」「レイノー現象」について、それぞれの原因・好発年齢・特徴・関連疾患をまとめます。
いずれの疾患も、動脈の機能障害によって身体に大きな影響を及ぼす点で共通しています。
特に国家試験では「若年女性に多い動脈疾患」や「三相反応」「膠原病との関連」などが問われやすいポイントとなっています。
大動脈炎症候群(高安病・脈なし病)
- 概要:大動脈およびその主要分枝に炎症が起こり、血管壁が肥厚・狭窄・閉塞して血流障害をきたす疾患。
- 別名:高安病、脈なし病(特に橈骨動脈の脈が触れなくなることから)
- 原因:明確な原因は不明だが、自己免疫疾患の一種と考えられている。
- 好発年齢・性別:若年女性に好発(10〜30歳代の女性に多い)
- 好発部位:右総頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈、大動脈弓部
- 症状:
- 橈骨動脈が触れなくなる(左右差あり)
- 血圧が測れない・左右差が生じる
- めまい、視力障害、頭痛、手のしびれなどの虚血症状
- 合併症:腎動脈が狭窄すると腎血流低下 → レニン分泌増加 → 二次性高血圧を引き起こす
- 検査所見:
- 血液検査:炎症反応(CRP・赤沈)上昇
- 画像検査:血管造影、CT・MRIで血管狭窄や閉塞を確認
- 治療:ステロイド治療、免疫抑制剤。重症例では血管形成術やバイパス手術を行うことも。
心疾患で関連の少ない組合せはどれか。
- 心室中隔欠損---左心室肥大
- 心不全---肺水腫
- 狭心症---冠動脈硬化症
- 心筋炎---高安病(脈なし病)
感染が原因でない疾患はどれか。
- 化膿性骨髄炎
- 大動脈炎症候群
- ひょう疽
- よう
二次性高血圧の原因となる疾患はどれか。
- ギラン・バレー症候群
- ダンピング症候群
- 上大静脈症候群
- 大動脈炎症候群
レイノー現象(Raynaud's phenomenon)
- 寒冷やストレスなどの刺激で末梢血管が収縮し、血流が一時的に遮断される現象
- 交感神経の異常が関与する
- 三相反応が典型的(蒼白 → チアノーゼ → 紅潮)
- 指先の冷感・しびれ・痛みを伴う
分類:
- レイノー病(一次性)
- 基礎疾患なし
- 20歳前後の女性に多く、良性経過
- レイノー症候群(二次性)
- 原因疾患あり
- 以下のような疾患に関連
- 膠原病(強皮症、SLEなど)
- 閉塞性動脈疾患(ASO、バージャー病)
- 振動病(建設機械・キーパンチャーなど)
- 神経疾患(胸郭出口症候群・手根管症候群)
レイノー現象がみられる疾患はどれか。
- 肥大型心筋症
- 気管支喘息
- クローン病
- 全身性硬化症
レイノー現象がみられるのはどれか。
- 原発性アルドステロン症
- アジソン病
- 全身性硬化症(強皮症)
- パーキンソン病
レイノー現象に対する局所施術部位として適切なのはどれか。
- 頭部
- 手部
- 腹部
- 背部
「38歳の女性。3年前に全身性硬化症と診断され、皮膚の硬化がみられる。レイノー現象の改善を目的に鍼治療を行うことになった。」鍼治療の効果を評価する方法として最も適切なのはどれか。
- サーモグラフィ
- 単純エックス線
- 筋電図
- 脳波
「38歳の女性。3年前に全身性硬化症と診断され、皮膚の硬化がみられる。レイノー現象の改善を目的に鍼治療を行うことになった。」レイノー現象の改善を目的とした局所への治療穴として適切なのはどれか。
- 血海
- 中渚
- 正営
- 建里
「35歳の女性。4年前からレイノー現象が出現し、最近では朝のこわばり、皮膚の硬化もみられるようになった。抗Scl-70抗体陽性。」本疾患でみられる所見はどれか。
- ボタン穴変形
- 鷲手
- ヘバーデン結節
- ソーセージ様指
「35歳の女性。4年前からレイノー現象が出現し、最近では朝のこわばり、皮膚の硬化もみられるようになった。抗Scl-70抗体陽性。」レイノー現象に対して局所への低周波鍼通電療法を行う部位で最も適切なのはどれか。
- 譩譆と魂門
- 浮郄と合陽
- 液門と三間
- 承光と絡却
レイノー現象を呈する患者の局所へ低周波鍼通電療法を行う場合、最も適切なのはどれか。
- 八邪
- 四華
- 闌尾
- 四神聡
動脈疾患について誤っている組合せはどれか。
- 閉塞性動脈硬化症---虚血性潰瘍
- 解離性大動脈瘤---背部痛
- 大動脈炎症候群---橈骨動脈拍動減弱
- レイノー病---間欠跛行
動脈疾患とその症状との組合せで誤っているのはどれか。
- 解離性大動脈瘤---体幹部激痛
- 閉塞性動脈硬化症---虚血性潰瘍
- レイノー病---間欠性跛行
- 大動脈炎症候群---橈骨動脈拍動減弱
神経性貧血をきたす疾患はどれか。
- レイノー病
- 心筋梗塞
- バージャー病
- 結節性多発性動脈炎
ペインクリニックの対象となる疾患はどれか。
- 胆石症
- 狭心症
- レイノー病
- 大動脈瘤
疾患と症状との組合せで正しいのはどれか。
- 関節リウマチ---日光過敏症
- 皮膚筋炎---蝶形紅斑
- 強皮症---レイノー現象
- ベーチェット病---スワンネック変形
40歳の女性。数年前より手指のこわばりを自覚していた。最近、症状の増悪と手指の関節痛、腫脹が認められ来院した。冷たいものに触れると手指が白くなることがある。検査では抗トポイソメラーゼⅠ抗体(抗Scl-70)が陽性であった。本症状の手指の所見はどれか。
- ゴットロン徴候
- ばち指
- レイノー現象
- スプーン状爪
「26歳の女性。なで肩で痩せている。主訴は右上肢全体の持続的なだるさ。反射は正常、スパーリングテスト、エデンテスト、ライトテストは陰性、アドソンテストは陽性。」進行した際の症状として最も適切なのはどれか。
- レイノー現象
- 筋トーヌス亢進
- 筋線維束性れん縮
- 手指巧緻運動障害
「35歳の男性。手足のしびれとレイノー現象がある。長く歩くと足部が痛くなるが、少し休むと軽減。下腿の静脈に圧痛や硬結、細絡がある。舌質は紫、脈は沈を認める。」病態鑑別上、優先して聴取すべきなのはどれか。
- 運動
- 食事
- 飲酒
- 喫煙
🌟白血病
白血病は、白血球が腫瘍化し無制限に増殖することで骨髄や全身に影響を及ぼす造血器の悪性腫瘍です。
白血病細胞が正常な造血を阻害し、貧血、感染、出血傾向などを引き起こします。
発症年齢や進行速度、細胞の分化段階によりいくつかのタイプに分類され、国家試験でも頻出の重要テーマです。
白血病の分類と特徴
- 急性白血病
- 骨髄での造血細胞の分化が障害され、未熟な白血病細胞(芽球)が急激に増殖
- 急性骨髄性白血病(AML):骨髄系前駆細胞が腫瘍化。小児~高齢者まで幅広く発症
- 急性リンパ性白血病(ALL):リンパ系前駆細胞が腫瘍化。小児に多く、最多の小児白血病
- 慢性白血病
- 成熟した腫瘍性白血球がゆっくりと増加
- 慢性骨髄性白血病(CML):フィラデルフィア染色体が特徴。中年期以降に好発
- 著しい白血球増多があるが、白血病裂孔(blast crisis)は初期にはみられない
- 慢性リンパ性白血病(CLL):成熟したB細胞が腫瘍化。高齢者に多く、進行は緩徐
- 成人T細胞白血病(ATL)
- 原因はHTLV-1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型)の感染
- 日本では南西諸島や九州地方に多く、中高年男性に多い
- リンパ節腫脹、皮膚病変、高Ca血症などを伴いやすい
主な症状と所見
- 貧血:赤血球減少による全身倦怠感、息切れ、動悸
- 易感染・発熱:好中球減少による
- 出血傾向:血小板減少により鼻出血、皮下出血、歯肉出血など
- 中枢神経症状:白血病細胞が髄膜へ浸潤すると頭痛・嘔吐・けいれん
- 肝腫大・脾腫・リンパ節腫大:白血病細胞の浸潤により
白血病は早期発見・早期治療が重要です。診断には血液検査、骨髄検査(骨髄穿刺・生検)、染色体検査などが用いられます。
治療は化学療法(抗がん剤)、放射線療法、造血幹細胞移植(骨髄移植)などがあり、病型と病期に応じたアプローチが選択されます。
国家試験では、「急性と慢性の違い」「小児と成人の好発疾患」「フィラデルフィア染色体」「三徴候(貧血・出血・感染)」などがよく問われるポイントです。
過去問と組み合わせて復習しておきましょう。
白血病について最も適切なのはどれか。
- 成人T細胞白血病はウイルス感染が原因である。
- 慢性骨髄性白血病では遺伝子変異が認められない。
- 急性骨髄性白血病ではフィラデルフィア染色体が陽性となる。
- 急性骨髄性白血病の治療は骨髄移植が第一選択である。
白血病の症状でないのはどれか。
- 振戦
- 発熱
- 皮下出血
- リンパ節腫脹
白血病についてウイルスが原因で日本の西南地方に多いのはどれか。
- 成人T細胞白血病
- 慢性骨髄性白血病
- 急性骨髄性白血病
- 急性リンパ性白血病
血中の白血球数が増加する疾患はどれか。
- 悪性貧血
- 急性白血病
- 全身性エリテマトーデス
- 血友病
急性骨髄性白血病について正しいのはどれか。
- 幼若芽球が増殖する。
- 小児に多くみられる。
- 細菌感染が関係する。
- ミエロペルオキシダーゼ染色は陰性である。
急性白血病の症状で誤っているのはどれか。
- 貧血
- 出血傾向
- 白血球増多
- 血小板増多
急性白血病でみられないのはどれか。
- 皮下出血
- 脾腫
- 病的骨折
- 発熱
慢性骨髄性白血病について正しいのはどれか。
- 脾臓は萎縮する。
- 10~20歳代に多い。
- 白血球数は正常である。
- 急性転化を起こさせないことが重要である。
慢性白血病で誤っているのはどれか。
- 骨髄性とリンパ性とがある。
- 肝腫と脾腫がともにみられる。
- 出血傾向がみられる。
- 予後は不良である。
慢性骨髄性白血病について誤っている記述はどれか。
- Bリンパ球が腫瘍化したものである。
- 脾腫がみられる。
- フィラデルフィア染色体が陽性である。
- 4.骨髄移植が行われる。
悪性腫瘍に属するのはどれか。
- 白血病
- 軟骨腫
- 脂肪腫
- 神経鞘腫
我が国の最近の小児の悪性腫瘍で年間発生数が最も多いのはどれか。
- 骨肉腫
- 神経芽腫
- 肝芽腫
- 白血病
ウイルスが原因となる腫瘍はどれか。
- ウィルムス腫瘍
- 成人T細胞白血病
- 移行上皮癌
- ユーイング肉腫
骨髄移植の適応となる疾患はどれか。
- 悪性貧血
- 白血病
- 血友病
- エイズ
「52歳の男性。3週間前から倦怠感と微熱がある。舌炎は認めないが、鼻血や歯茎の出血、皮下出血斑がみられる。」最も考えられる疾患はどれか。
- 急性白血病
- 悪性貧血
- 溶血性貧血
- 血友病
血液疾患とその症状について正しい組合せはどれか。
- 鉄欠乏性貧血---紫斑
- 悪性リンパ腫---ハンター舌炎
- 白血病---出血傾向
- 再生不良性貧血---リンパ節腫脹
血液疾患と症状の組合せで正しいのはどれか。
- 鉄欠乏性貧血---末梢神経障害
- 悪性リンパ腫---舌炎
- 急性白血病---出血傾向
- 再生不良性貧血---リンパ節腫脹
🌟まとめ|出血傾向・白血病を含む血液疾患のポイント
この記事では、国家試験で頻出の血液・造血器疾患について解説しました。
血小板や凝固因子に関わる出血傾向、血栓・塞栓症、動脈疾患(動脈硬化・大動脈炎症候群・レイノー現象)、そして白血病の各分類と症状に焦点を当て、重要なキーワードを整理しました。
以下のポイントを復習しておくと、国家試験対策として有効です。
- 血小板と凝固因子の働きと止血機構
- 出血傾向をきたす疾患と症状(紫斑、歯肉出血、関節出血)
- 動脈硬化と脂質異常症の関係
- レイノー病とレイノー症候群の違い
- 白血病の分類(急性/慢性、骨髄性/リンパ性、成人T細胞型)と症状
覚えにくい専門用語も、語呂合わせや表、色分けで視覚的に整理することで記憶に残りやすくなります。