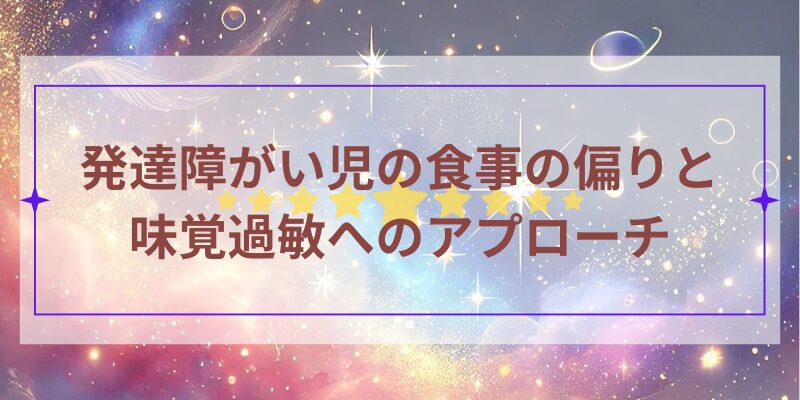こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
「特定の食べ物しか食べない」「新しい食品を一切受け付けない」――これは発達障がい児に比較的多く見られる食事の偏りや味覚過敏の特徴です。
親御さんとしては「栄養バランスが崩れないか」「このまま偏食が続くのではないか」という不安や心配を抱くことも多いでしょう。
さらに、学校や保育園などの集団生活で食事に参加できない場面が増えると、お子さん本人もストレスを感じることがあります。
発達障がい児の食事の偏りや味覚過敏は、単なる「好き嫌い」とは異なり、感覚処理や脳の情報整理の特性が影響しています。
口に入った瞬間の温度や食感、味、匂いなどが過剰に強く感じられる場合、脳が「危険」や「不快」と判断してしまい、拒否反応を引き起こします。
この反応は本人の意思や性格とは無関係であり、むしろ感覚の防御反応として自然に起こるものです。
一方で、感覚が鈍く、特定の味や食感でしか満足感を得られないケースもあります。
例えば、強い味付けやパリパリした食感のスナック菓子ばかりを好むなどがその例です。
いずれの場合も「ただ食べさせればいい」というものではなく、本人が安心して挑戦できる環境づくりと、徐々に感覚を慣らしていくプロセスが欠かせません。
そこで今回は、Kagayaが看護師として培ってきた医療的視点と、鍼灸師としての体験、さらに発達支援や感覚統合のアプローチを組み合わせた方法をお伝えします。
単なる理論だけではなく、訪問支援の現場で実際に効果を感じられた事例も交えてご紹介しますので、ご家庭での実践の参考にしていただければ幸いです。
この記事でわかること
- 発達障がい児の食事の偏りと味覚過敏の特徴
- 家庭でできる工夫とステップアップ方法
- 味覚過敏をやわらげる感覚統合ケア
- 鍼灸を使ったアプローチ
- 『きらぼし』での実際の支援事例
読み進める中で「これはできそう」と思えるポイントから取り入れてみてください。
お子さんにとって食事の時間が少しでも安心で楽しいものになるよう、一歩ずつサポートしていきましょう。
🌟食事の偏りと味覚過敏の特徴
発達障がい児では、五感の中でも特に味覚・嗅覚・触覚に対して敏感または鈍感といった感覚の特性が現れやすく、それが食事の偏りや味覚過敏の原因となります。
大人から見ると単なる「好き嫌い」のように思えることも、実際には脳の感覚処理の特性によって引き起こされている場合が多いのです。
例えば、味覚過敏がある場合は、わずかな酸味や苦味、辛味、香りの強さにも過剰に反応し、舌や口の中で「痛い」「しびれる」「気持ち悪い」といった不快感を感じることがあります。
これらは本人の意思や性格ではなく、脳が危険信号を出している状態です。
一度その食品で不快な経験をすると、「あれは嫌だ」という記憶が強く残り、再び挑戦することが難しくなります。
また、食感のこだわりもよく見られます。
やわらかすぎる食感は「飲み込みにくい」と感じたり、逆に固すぎる食感は「噛むときに痛い」と感じたりします。
ぬるぬる・ねばねばした食品(例:オクラ、納豆、山芋)を避けるお子さんも多く、これも触覚や味覚の過敏さが影響しています。
さらに、見た目や色のこだわりも偏食につながります。
ある色や形に安心感を覚えると、それ以外は拒否することがあります。
例えば「白いご飯だけ」「丸い形のパンだけ」といったパターンです。
食材の色や形が変わると、味が同じでも「別物」と認識されてしまうため、受け入れられなくなるのです。
こうした偏食が続くと、栄養バランスの崩れが起こりやすくなります。
タンパク質やビタミン・ミネラル不足によって免疫力が低下し、風邪をひきやすくなったり、エネルギー不足で疲れやすくなったりします。
また、食物繊維不足による便秘、鉄分不足による集中力低下など、日常生活への影響も大きくなります。
食事時間そのものがストレスになり、家族の雰囲気にも影響するケースも少なくありません。
親御さんが「食べさせなければ」と焦るほど、お子さんはプレッシャーを感じてしまい、食事が「楽しい時間」ではなく「我慢や緊張の時間」になってしまうのです。
この悪循環を断ち切るためには、感覚特性を理解し、それに合わせた環境づくりと支援が必要です。
- 味覚過敏:酸味・苦味・辛味・香りに過剰反応しやすい
- 食感のこだわり:やわらかすぎる/固すぎる/ぬるぬるした食感を避ける
- 見た目・色のこだわり:特定の色・形の食品しか食べない
- 偏食による影響:栄養バランスの崩れ、便秘や疲れやすさ、食事時間のストレス
🌟家庭でできる工夫とステップアップ方法
発達障がい児の食事支援で最も大切なのは、「無理強いせずに安心感を与えること」です。
食事は栄養補給だけでなく、家族とのコミュニケーションや生活習慣の一部として大きな意味を持ちます。
しかし、感覚過敏や偏食があるお子さんにとって、食事の時間はストレスや不安を伴う場面になりやすく、これを和らげるためには環境とアプローチの工夫が不可欠です。
まず、安心できる雰囲気作りが第一歩です。食卓での雰囲気は、食べる意欲に大きく影響します。
大人が「食べなさい」と強く促すと、お子さんは「叱られる場」として食事を避けるようになります。
逆に、「食べられたらラッキー」「今日はここまで食べられたね」とポジティブな声かけを行うことで、食事時間を安全で楽しい経験に変えることができます。
次に、好物からのステップアップを活用します。
完全に新しい食材を出すより、好きな味や食感に似た食品から変化をつける方が成功しやすいです。
例えば、白いご飯が好きなお子さんには、まず雑穀を数粒混ぜてみる、ふりかけを少量かけるなど、味や見た目をほんの少しだけ変える工夫をします。
慣れてきたら、段階的に新しい食材を増やします。
また、単品盛り付けは偏食児に有効です。
食材を混ぜると「何が入っているかわからない」という不安から拒否されやすくなります。
仕切りのあるプレートを使って、見た目で選びやすくすると心理的ハードルが下がります。
新しい食品を導入する際は、匂い→触る→舐める→食べるのステップで進めます。
いきなり口に入れるのではなく、まずは「見る・匂いを嗅ぐ」など感覚的に安全を確認できる時間を設けることで、拒否反応を減らせます。
この過程を数日~数週間かけて繰り返すことで、少しずつ受け入れられる範囲が広がります。
さらに、食事環境の感覚刺激を整えることも重要です。
照明を柔らかくしたり、落ち着く音楽を流したりすることで、自律神経が安定し、食欲が高まりやすくなります。
特に感覚過敏のあるお子さんは、環境音や視覚的刺激に影響を受けやすいため、静かで整った空間作りが効果的です。
- 無理に食べさせず、安心できる雰囲気を作る
- 好物と似た食感・味の食品から少しずつ変化をつける
- 食材を混ぜず、単品で盛り付けて選びやすくする
- 新しい食品は匂い→触る→舐める→食べるの順で段階的に
- 食事中に好きな音楽や照明を使い、安心感を高める
こうした工夫は即効性よりも継続が大切です。
「今日は一口増えた」「匂いを嫌がらなくなった」という小さな変化を見逃さず、本人のペースを尊重してステップアップを続けることが、長期的に偏食改善へつながります。
🌟味覚過敏をやわらげる感覚統合ケア
味覚過敏は、単に「味が苦手」というだけでなく、口腔内の触覚や温度感覚、嗅覚との複雑な連動が関わっています。
発達障がい児の場合、こうした感覚処理が非常に敏感であったり、逆に鈍感であったりするため、食べ物のわずかな変化でも脳が「不快」と判断してしまうことがあります。
その結果、拒否反応や強い警戒心が生まれ、食事の幅が広がらないままになってしまうのです。
この状態を改善するには、感覚統合的なアプローチが効果的です。
感覚統合とは、五感や体の感覚をバランスよく使えるように促すための方法で、遊びや日常動作の中で少しずつ感覚刺激に慣れていくことを目指します。
大切なのは、苦手な刺激をいきなり強く与えるのではなく、「楽しい活動」と結びつけて少しずつ慣らすことです。
例えば、口腔感覚遊びは安全で楽しく取り組める方法です。
ストローで水を吸ったり、シャボン玉を吹いたり、吹き戻し笛で遊んだりすることで、口周りや舌、頬の筋肉を動かし、感覚への順応を促します。
こうした遊びは「食べる」ことに直結しないため、お子さんの心理的負担も少なく、楽しみながら進められます。
また、温度の変化に慣れることも重要です。
冷たい→常温→温かい飲み物の順で体験させると、口腔内の温度感覚が広がり、食べられる食品の幅が増えやすくなります。
特に味覚過敏のあるお子さんは、温度によって味の感じ方が変わるため、同じ食材でも食べやすくなる場合があります。
さらに、嗅覚慣らしは味覚過敏の改善に欠かせません。
嗅覚は味覚と密接に関係しており、香りの刺激に慣れることで食べ物への警戒心が減ります。
好きな香り(例:バニラ、柑橘、ハーブ)から始めて、少しずつ香りの種類や強さを広げると効果的です。
最後に、咀嚼筋マッサージは物理的な緊張をやわらげます。
頬やこめかみをやさしくマッサージすることで筋肉の緊張がほぐれ、噛む・飲み込む動作がスムーズになります。
これは食事前の準備としても有効で、「今から食べる」という体のスイッチを入れる効果もあります。
- 口腔感覚遊び:ストロー遊び、シャボン玉、吹き戻し笛
- 温度の変化に慣れる:冷たい→常温→温かい飲み物の順で体験
- 嗅覚慣らし:好きな香りから徐々に種類を広げる
- 咀嚼筋マッサージ:頬・こめかみをやさしくマッサージして緊張をほぐす
これらの方法は、短期間で劇的な変化を求めるものではなく、数週間から数か月かけて少しずつ変化を促す取り組みです。
お子さんが「楽しい」「安心」と感じられるよう工夫しながら続けることで、味覚過敏が和らぎ、食事への抵抗感が減っていきます。
🌟鍼灸を使ったアプローチ
発達障がい児の食事の偏りや味覚過敏に対しては、鍼灸によるアプローチも有効です。
鍼灸は体のバランスを整え、自律神経や感覚処理の働きを調整することで、食事に向かう際の「緊張」や「拒否感」を和らげるサポートができます。
特に、感覚過敏や偏食の背景には、交感神経が過度に優位な状態や、脳の感覚情報の処理負担が大きい状態が関わっていることが多く、鍼灸はそれらの調整に適しています。
まず代表的なのが、耳ツボ療法です。
耳には全身の臓器や神経に対応する反射区が存在し、その中でも「神門」「内分泌」のツボは、自律神経を整えて精神的な安定を促す効果が期待できます。
神門はリラックス効果が高く、不安や緊張を和らげるサポートに適しています。
内分泌はホルモンバランスや代謝の調整に関与し、全身の調和を保つ役割を持ちます。
これらの耳ツボを軽く刺激することで、食事中の緊張感が和らぎ、受け入れやすくなるケースが多くあります。
次に、頭鍼は脳の感覚処理をスムーズにするアプローチです。
頭皮上の特定ポイントを刺激することで、脳の感覚野や前頭葉に働きかけ、食感や味の情報処理が過敏になりすぎるのを防ぎます。
感覚統合の観点からも、頭鍼によるアプローチは口腔や嗅覚の感覚過敏緩和に効果的と考えられています。
訪問施術では、お子さんの体調やその日の精神状態を確認しながら、刺激量や使用するツボを調整します。
初回は特に弱い刺激から始め、「怖くない」「痛くない」という安心感を持ってもらうことが大切です。
鍼を使用せず、シールタイプのパッチ(円皮鍼)や磁気粒など、低刺激の方法から導入することも可能です。
また、施術前にスヌーズレンや呼吸法で心身をリラックスさせてから行うと効果が高まります。
こうすることで、鍼灸刺激がより受け入れやすくなり、その後の食事も落ち着いた状態で臨めるようになります。
- 耳ツボ(神門・内分泌)で自律神経を整え、食事時の緊張をやわらげる
- 頭鍼で感覚処理をスムーズにする
訪問施術では、お子さんの状態に合わせて刺激量を調整し、「安心して食べられる体と心の準備」を整えます。
鍼灸は薬を使わないため、副作用が少なく、他の療育や感覚統合アプローチとも併用しやすいのが大きな利点です。
🌟まとめ|“食べられる”を少しずつ広げていく
発達障がい児の食事の偏りや味覚過敏は、決して「治さなければならない問題」ではありません。
大切なのは、安心できる環境の中で少しずつ食べられる範囲を広げていくことです。
無理に食べさせようとすると、食事がストレスや恐怖と結びついてしまい、かえって拒否感が強くなることもあります。
逆に、本人のペースを尊重しながら安全な環境で新しい体験を積み重ねると、自然と受け入れられる食品や食感が増えていきます。
今回ご紹介したように、家庭での小さな工夫(盛り付け方や食材のステップアップ)と、感覚統合的な遊び、鍼灸などの専門的なケアを組み合わせることで、お子さんの「食べる力」は少しずつ育っていきます。
味覚や嗅覚、食感への敏感さが和らぐと、食事時間は「我慢する時間」から「楽しむ時間」へと変化します。
これは栄養面だけでなく、心の安定や家族のコミュニケーションにも大きなプラスになります。
『きらぼし』では、小平市周辺を中心に、訪問による食事支援や鍼灸ケアを行っています。
お子さんの感覚特性や日常の様子を丁寧に確認しながら、その日その子に合った方法で支援します。
「家庭では難しい」「専門的な視点から見てもらいたい」という場合は、ぜひ一度ご相談ください。食べることに関する悩みは、ひとりで抱え込まずに、一緒に少しずつ解決していきましょう。
食事は「生きるため」だけでなく、「生きることを楽しむため」の大切な時間です。
少しずつの変化を大事にしながら、安心して食べられる未来を一緒に作っていきましょう。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら
あわせて読みたい