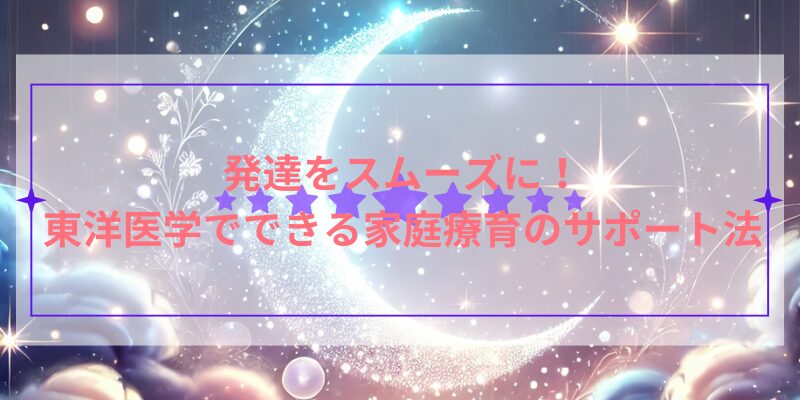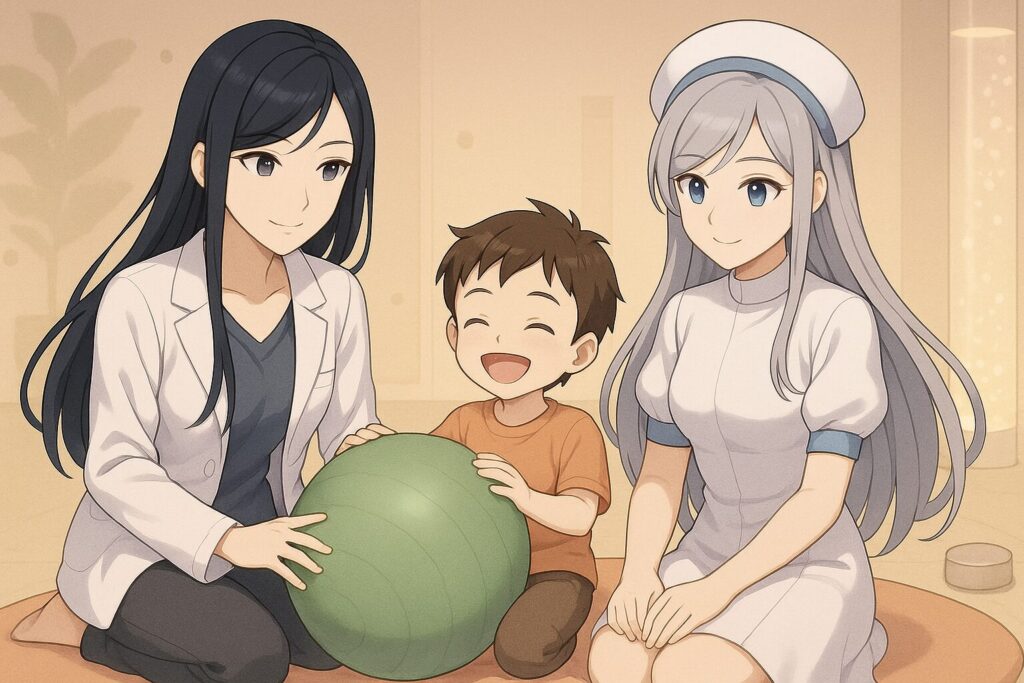
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
このブログにたどり着いてくださった方の中には、日々の育児や療育に真剣に向き合いながら、「うちの子、ちょっと発達がゆっくりかもしれない」「まだ診断はないけれど、なんとなく気になる…」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
Kagayaは、看護師として医療現場に携わりながら、鍼灸師として東洋医学の視点を学び、現在は「訪問鍼灸+看護」という形で地域のご家庭にケアを届ける活動をしています。
その中で感じるのは、医療でも福祉でも手が届かないグレーゾーンの子どもたちと、そのご家族がとても多いということ。
「専門機関に相談したけど、診断名がつくほどではないと言われた」
「発達の遅れが気になるけど、どこに相談していいかわからない」
「保健師さんに言われた発達相談、結局様子見って言われて終わった」
こうした声は、Kagayaが訪問しているご家庭からも多く聞こえてきます。
そして、共通しているのは、お子さんの可能性を信じているからこそ、何かできることはないかと探し続けているということです。
西洋医学的な発達支援ももちろん大切です。
けれど、もう少し広い視点で、お子さんを「こころとからだ」まるごとで捉えてあげられたら、違ったアプローチが見えてくることもあるとKagayaは感じています。
特に、東洋医学の「体質」や「気血水」「五臓」のバランスという視点は、発達の段階でのちょっとした気になるサインを、自然な形で受け止めるヒントになることがあります。
Kagayaは、鍼灸師としての知識だけでなく、看護師としての観察力・生活支援の視点も活かしながら、ご家庭に寄り添うサポートを心がけています。
病院に通うことが難しいご家庭、医療的ケア児を育てるご家庭、そして、「うちの子、ちょっと気になるけど、どこに相談したらいいかわからない…」という方へ。
この記事では、東洋医学の視点から見た「発達のサポート」について、家庭でも実践できるケア方法を交えて、やさしく丁寧にご紹介していきます。
「難しいことはわからないけど、何かできることがあれば知りたい」「発達にいいことを、無理なく日常に取り入れたい」そんな方に向けて、Kagaya自身の現場での経験も交えながら、リアルな視点でお伝えしていきますので、どうぞ最後までお付き合いくださいね。
🌟東洋医学から見る発達の遅れとは?
発達の遅れについて、医療機関に相談すると「脳や神経の未成熟」「感覚統合の問題」「遺伝的要因」「環境因子」などが関与していると説明されることが多いです。
これらはすべて西洋医学の考え方に基づくもので、脳の構造や神経回路の働きを分析し、支援計画を立てていくというアプローチです。
一方、東洋医学では、発達というものを「全体の調和」や「生命の巡り」という視点でとらえます。
体の一部が原因であるというよりは、「からだとこころ全体のバランスが乱れている状態」と考えるのが特徴です。
特に東洋医学では、子どもの発達には以下のような臓腑の働きが密接に関係しているとされます:
- 腎(じん):
生命エネルギーの源とされ、成長・発育・骨・脳の発達をつかさどります。胎児期から乳幼児期の発達には腎の充実が重要とされます。 - 脾(ひ):
飲食物を消化吸収し、それを気血に変える「後天の本」とも呼ばれます。消化機能の未熟さは、体力や免疫力の低下、発語や行動面にも影響すると考えられます。 - 肝(かん):
気の流れや血の巡りを整え、情緒の安定・筋肉や神経の働きをサポートします。ストレスや興奮が強いと「肝の失調」が現れやすくなります。
たとえば、夜泣きがひどい、落ち着きがない、すぐ癇癪を起こす、筋肉のこわばりがある、体が小さい、食が細いなどの症状は、どれもこうした「臓腑バランスの乱れ」として読み解くことができます。
東洋医学では、「心身一如(しんしんいちにょ)」という言葉があります。
これは、こころとからだは分けて考えられるものではなく、互いに影響し合う一つのものという意味です。
子どもの情緒の乱れや発達のズレも、単に脳や神経の問題にとどまらず、全身の気血水の流れや五臓の調和が崩れた結果として現れていることがあるのです。
具体的には、以下のような体質傾向が見られます:
- 腎虚(じんきょ)タイプ:
体力がなく疲れやすい、集中力が続かない、冷えやすい、音や刺激に敏感。 - 脾虚(ひきょ)タイプ:
食が細く、下痢や便秘を繰り返す、風邪をひきやすい、元気が続かない。 - 肝実(かんじつ)タイプ:
怒りっぽい、落ち着きがない、筋肉が硬い、睡眠が浅く寝つきが悪い。
このように、東洋医学では「発達の遅れ=未熟な脳」ではなく、体全体の巡りやバランスの乱れが背景にあると捉え、その子に合ったケアを考えていきます。
「タイプ分けしてラベルを貼る」のではなく、「その子の今の状態を柔軟に見立てる」というのが、東洋医学的アプローチの魅力です。
だからこそ、成長途中で状態が変わっていく子どもたちにとって、非常に親和性の高い見方なのです。
では次に、こうした体質を家庭でどう見分け、どんな対応ができるのか。
次の章では簡単なセルフチェックをご紹介していきます。
🌟家庭でできる!東洋医学のセルフチェック
「うちの子、東洋医学でいうとどんなタイプなのかな?」と思ったことはありませんか?
東洋医学では、体質を見極めることがとても大切です。
病名ではなく「今どのバランスが崩れているか」を見ていくことで、お子さんの特徴や傾向に気づくヒントになります。
以下に、簡単なセルフチェックをご用意しました。当てはまる項目が多いタイプが、今のお子さんの傾向に近いと考えられます。
🌱腎虚タイプ
☑ 寝起きが悪く、朝の支度に時間がかかる
☑ 疲れやすく、外遊びの後すぐに横になりたがる
☑ 大きな音や刺激に対して敏感で怖がりやすい
☑ 集中力が続かず、ぼんやりしていることが多い
☑ 発語がゆっくり、または言葉が出にくい傾向がある
🍚脾虚タイプ
☑ 食が細く、好き嫌いが多い
☑ 下痢や便秘など、消化器系のトラブルが多い
☑ 食後にすぐ眠くなる、またはだるそうにする
☑ 風邪をひきやすく、長引きがち
☑ 口の周りが黄色っぽい、あるいはよだれが多い
🔥肝実タイプ
☑ 落ち着きがなく、じっとしているのが苦手
☑ 感情の波が激しく、突然怒ったり泣いたりする
☑ 興奮すると眠れない、夜更かししがち
☑ 筋肉の緊張が強く、動きがぎこちないことがある
☑ 光や音などの感覚刺激に過敏、または逆に鈍感
いかがでしたか?
このチェックはあくまで目安ですが、当てはまる傾向があれば、日常の過ごし方やケアの方向性を見直すヒントになります。
また、1人の子どもに複数のタイプが混ざっていることも非常に多いです。
例えば、「食が細くて風邪をひきやすい(脾虚)けれど、感情のコントロールが難しい(肝実)」といったパターンもよくあります。
さらに、お子さんの状態は日々変化します。
季節、気温、ストレス、睡眠の質、食事内容など、さまざまな要因でバランスが揺らぐのが当たり前。
だからこそ、「今はちょっと肝が強すぎるかな?」「最近、腎の疲れが出てるかも」といった感覚で、柔軟に見てあげることが大切です。
このように体質を見極めることは、東洋医学的な家庭ケアの第一歩。
ラベリングするためではなく、寄り添うために体質を知るというのがポイントです。
次の章では、こうしたタイプ別にどのようなセルフケアや遊びができるのか、実際にKagayaが訪問支援やサロンで行っている方法を交えてご紹介していきます。
「診断名ではわからないことを知りたい」「子どもに合ったケアを自宅で試してみたい」という方は、ぜひ次も読んでみてくださいね。
🌟Kagaya式セルフケア:五感と経絡を育てる遊び
「遊び=ケア」。
これは、Kagayaが大切にしている考え方です。
大人の感覚で「治療しなければ」「訓練しなければ」と思いがちですが、子どもにとっては楽しい・気持ちいい・面白いが何よりの原動力。
だからこそ、セルフケアも五感を育てる遊びの延長であることが、長く続けるコツだと感じています。
特に発達が気になるお子さんは、感覚の過敏や鈍麻、感覚統合の課題を持っているケースも多いため、「触る・見る・聴く・嗅ぐ・味わう」という感覚刺激がとても重要になります。
以下に、Kagayaが訪問支援や自宅ケアで取り入れている五感刺激のアイデアをご紹介します。
- 🖐 触覚:
・フェルトやガーゼなど手触りの異なる布を触る
・小麦粘土やスライム、寒天での手遊び
・温冷パックやおしぼりの温度変化を感じる - 🎵 聴覚:
・オルゴールやヒーリング音楽
・木のカスタネット、鈴、風鈴などの自然な音
・親子でリズム遊びや歌を歌う - 🌸 嗅覚:
・ラベンダー、ベルガモット、オレンジなどの精油を使用(アロマストーンやティッシュに垂らす)
・調理時に香りを嗅がせる(みそ汁、だし、柑橘類) - 🍴 味覚:
・五味(酸・苦・甘・辛・鹹)を意識した食育
・手づかみ食べで食材の温度や舌触りを感じる
・自分で野菜を切って調理に参加 - 👀 視覚:
・ライトの色を変える、プロジェクターで模様を映す
・スヌーズレン的空間(泡のチューブライト、LED星空)
・視線を追う遊び(シャボン玉、モビールなど)
こうした五感刺激は、子どもの感覚統合を助け、情緒や自律神経を整えることにつながります。
特に触覚と嗅覚は「安心・リラックス」と深く結びついているので、おやすみ前のルーティンに取り入れるのもおすすめです。
さらに、東洋医学的なアプローチとして、ツボ押しや温灸(おんきゅう)もプラスすることで、より深いケアが可能になります。
Kagayaがよく使うツボを3つ紹介します:
- 💡百会(ひゃくえ):
頭のてっぺんにあるツボ。脳の活性化、集中力アップ、情緒の安定に。 - 🌙三陰交(さんいんこう):
内くるぶしから指4本分上。消化、睡眠、ホルモンバランス、免疫力に作用。 - 🌀神門(しんもん/耳ツボ):
耳の上部の内側。交感神経を落ち着け、不安や緊張をやわらげます。
これらはすべておうちで簡単に取り入れられるケアです。
指で優しく押すだけでもOK。
もし可能であれば、せんねん灸のような温灸グッズを使うと、さらにリラックス効果が高まります。
ケアは1回数分で十分。
毎日でなくても、「できる時にできるだけ」の気持ちで取り入れてみてください。
何より大切なのは、子どもと向き合う時間が「心地よいもの」として記憶に残ること。
ケアを通して親子の絆が深まれば、それ自体が発達を後押ししてくれる大きな力になります。
次の章では、Kagayaが実際に使っているおすすめのセルフケアグッズをご紹介します。
「何から始めたらいいかわからない」という方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
🌟おすすめのセルフケアグッズ
ここでは、Kagaya自身が訪問ケアや家庭ケアで実際に活用している、おすすめのセルフケアグッズを3つご紹介します。
どれも子どもが怖がらず、親御さんも使いやすいものを選んでいます。
セルフケアは無理なく継続することが大切なので、「使っていて楽しい」「家族みんなで取り組める」という視点も大切です。
東洋医学に興味はあるけれど、どうやって家庭に取り入れたらいいのかわからない…という方のために、気軽に始められるアイテムを厳選しました。
せんねん灸太陽
ほんのり温かくてやけどしにくい、初心者向けのお灸です。
火を使わないお灸なので、お子さんのケアにも安心して使えます。
🌿おすすめ使用部位:
・百会(頭頂部)→寝つき改善、情緒安定
・三陰交(足首内側)→消化吸収、免疫力アップ
使用感:
Kagayaの訪問先でもよく使うお灸です。火を使わず、子どもが怖がらずに「ポカポカして気持ちいい」と言ってくれることが多いです。
アロマストーン(無印良品)+精油
電気や火を使わないため、寝室でも安心。
嗅覚刺激は情緒の安定や安心感に直結します。
特に寝る前の時間におすすめです。
🌸おすすめ精油:
・ラベンダー…リラックス、入眠サポート
・ベルガモット…気分の落ち込みに
・オレンジスイート…安心感、親子で使いやすい香り
使用感:
石に数滴垂らすだけでふんわり香るので、香りが強すぎないのが好評です。
「眠る前の合図」として定着しているご家庭もあります。
視覚刺激LEDライト(スヌーズレン風)
光や色の変化で視覚をやさしく刺激し、感覚統合と情緒の安定をサポートします。
自宅で簡易的にスヌーズレン空間をつくりたい方に最適。
✨おすすめの使い方:
・就寝前の静かな時間に
・親子で抱っこしながら見る
・BGMと組み合わせてリラックス効果倍増
使用感:
幻想的な光の揺らぎに子どもが自然と引き込まれていきます。
「この光を見たら寝る時間」とルーティン化できるのが嬉しいポイントです。
いずれも「使い方が簡単」で「日常に取り入れやすい」ことを重視して選んでいます。
特別な時間や空間をつくらなくても、日々の暮らしの中に東洋医学の視点を取り入れることは十分可能です。
迷ったら、まずはお灸+アロマから始めてみるのがおすすめ。
体と心のバランスが整い、親子で過ごす時間に深みが出てきます。
次の章では、こうしたセルフケアをもっと深めたい方のために、『きらぼし』で提供している訪問ケアやシェアサロンでのサポート内容をご紹介していきます。
🌟『きらぼし』の訪問ケアでできること
「家庭でできることはやってみたけど、やっぱりプロに一度見てほしい…」「ケアのやり方がこれで合っているか不安」「子どもだけじゃなく、自分も疲れてしまっている…」
そんなときは、ぜひ訪問型ケアサービス『きらぼし』をご活用ください。
Kagayaは、看護師と鍼灸師の両方の国家資格を持ち、病院・訪問看護・療育現場などでの豊富な経験をもとに、ご家庭に合わせたケアを提供しています。
「ただ施術するだけ」ではなく、子どもとご家族が“安心して過ごせる時間”を一緒に作ることを大切にしています。
たとえば、お子さんの発達や体調の状況に合わせて、次のようなサポートを行います:
- 発達がゆっくりなお子さまへの訪問鍼灸+看護ケア
- 耳ツボ(ASP、シールタイプ)や温灸を使ったやさしい刺激ケア
- 五感に働きかけるスヌーズレン的アプローチ(視覚・触覚・音の刺激)
- ご家族へのセルフケア指導・生活アドバイス
- 医療的ケア児への吸引・呼吸管理・見守り(看護師として対応)
施術は、ご自宅の生活スペースの中で行えるように配慮しており、ベッドや布団、お子さんが落ち着く場所でリラックスして受けていただけます。
服を脱がずにできる施術(耳ツボ・お灸・刺さない鍼など)も多く、小さなお子さんや初めての方でも安心です。
また、Kagayaは「家庭全体のケア」という視点を大切にしています。
育児や介護、医療的ケアが続く日々の中で、保護者の方が自分の体と心を後回しにしてしまうことは少なくありません。
でも、お子さんの安定には、ケアをする側の元気が何より大事です。
きらぼしの訪問では、ご家族のお話をじっくり聞きながら、その日その時の状況に合わせて、ケアの内容も柔軟に変えていきます。
「今日はお子さんが落ち着かないから、お母さんの肩だけケアしましょう」「呼吸が浅いから耳ツボを中心にしますね」そんな風に、臨機応変に対応できるのが訪問ケアの良さです。
サービス対象エリアは小平市・東村山・東大和・東久留米・国分寺・立川などの周辺地域。
ご希望に応じてシェアサロン(都内)でのケアにも対応可能です。
定期的なケアはもちろん、「今週だけ」「入園前に調整したい」「グレーゾーンだけどサポートを受けたい」といった一時的なサポート依頼も歓迎しています。
どこに相談したらいいか分からない…そんな時こそ『きらぼし』へ。
まずはお気軽にLINEやお問合せフォームからご連絡ください。
Kagayaが直接ご家庭に伺い、その子、そのご家族にとって“ちょうどいいケア”を一緒に考えていきます。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら
🌟まとめ:あなたの育児に、もう一つの視点を
発達は「比べるもの」ではなく、その子の中にあるリズムや流れに寄り添うものだと、Kagayaは考えています。
たとえ言葉が遅くても、落ち着きがなくても、それは発達の一場面。
「どうしてできないのか?」ではなく、「今どんな状態なのか?」を見つめていくことが、ケアの第一歩です。
今回ご紹介したような東洋医学の視点は、そんなお子さんの状態を優しく受け止めるツールになります。
- 腎・脾・肝などの五臓から体質を読み解く
- 五感刺激を通じて発達と感情に働きかける
- 百会・神門・三陰交などのツボで自律神経を整える
- 家庭でもできるセルフケアで“安心の習慣”を作る
どれも難しいことではありません。
むしろ、「肌に触れる」「一緒に音楽を聴く」「眠る前にお灸をする」など、日々のふれあいの中で自然にできることばかりです。
そして、何より大切にしてほしいのは、「親ががんばりすぎない」こと。
お子さんのことを真剣に考えているからこそ、不安になったり、つい自分を責めてしまったりすることもあると思います。
でも、子どもの発達には、おとなの余裕・安心・あたたかさが何よりの栄養です。
だからこそ、ご家族自身の心とからだも大切にしてほしいのです。
「何かできることはないかな」「家では限界かも」そう思った時は、無理に抱え込まず、どうか『きらぼし』にご相談ください。
Kagayaは、鍼灸師・看護師としての専門性を活かしながら、一緒に悩み、一緒にケアの方法を探していくことを大切にしています。
東洋医学は、診断名のあるなしに関係なく、「今の状態」を丁寧に見ていくことができます。
だからこそ、まだ診断がつかない“グレーゾーン”のお子さんや、軽度発達障害と診断されたお子さんへのケアにも、しっかりと活かせます。
「子どもの発達を整える」のではなく、「その子のリズムに寄り添い、環境を整える」という視点を、ぜひ今日から取り入れてみてください。
『きらぼし』は、そんなご家庭の小さな希望となり、育児にもう一つの安心を添えられる存在でありたいと願っています。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら