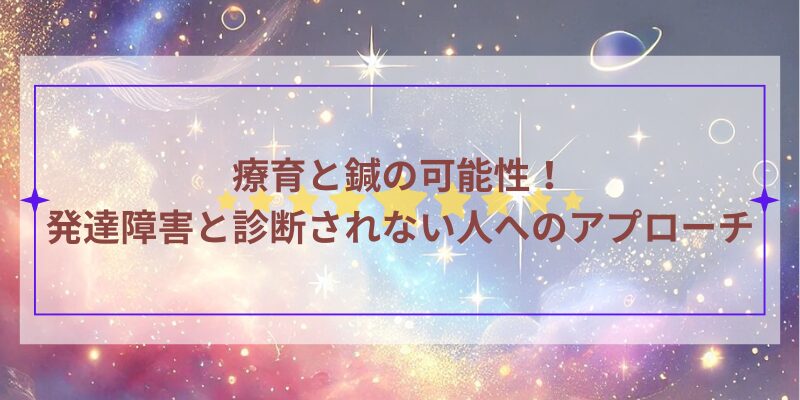こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
最近、「発達障がい」という言葉をよく耳にします。
「早期発見・早期療育」が推奨され、早期介入ができれば、子ども本人も保護者も悩むことが少なくなるといわれています。
けれども、少し集団生活に馴染めない子や、少し手のかかる子がいるだけで、「発達障がいかも?」と早急に判断する保育士や教員も多く見られます。
自分の指導不足を棚に上げて、軽々しく「療育を」と勧めてしまうこともあり、それを言われた保護者は深く傷ついてしまいます。
特に、兄弟に障がいがある「兄弟児」の場合、その傾向は顕著です。
Kagayaの知人にも、クラスで一度ケンカをしただけで療育病院の受診を勧められた方がいました。
「兄弟児はケンカすらできないの?」と、やるせない気持ちになります。
その結果、療育病院を紹介されて受診希望者が増加し、予約が半年〜1年待ちになることもあります。
しかも、やっと受診できたと思ったら「発達障がいではない。しつけの問題です」と片付けられてしまうことも。。
まずは、病院に行く前に、自治体の福祉課・保健センター・子ども家庭支援センターなどに相談してみてください。
専門的な支援や的確なアドバイスを受けることができます。
🌟 発達障がいの基本知識
発達障がいとは、「自閉スペクトラム症(ASD)」「注意欠如・多動症(ADHD)」「学習障害(LD)」などの総称で、脳の機能の偏りにより、言語・行動・学習面で特性が見られる状態です。
行動面・認知面・社会性に特徴が現れ、日常生活や集団生活において困りごとが生じやすくなります。
日本では2005年に「発達障害者支援法」が施行され、まだ比較的新しい枠組みの障がいです。
より詳しく学びたい方は、以下の書籍がおすすめです:
どちらもKagayaが実際に読んでみて「わかりやすい」と感じた本です。
🌟 東洋医学からみる発達障がい
発達障がいという言葉こそ現代のものですが、昔から「脳の働きや精神の不安定さ」による症状として東洋医学ではとらえられてきたと感じています。
🔸 精の不足
生まれつき「精(せい)」が弱い子どもは、やはり成長や発育のリズムがゆっくりだったり、免疫力が弱く風邪をひきやすい傾向にあります。
精の不足により気血の生成も弱まり、身体全体の活力が不足しやすくなります。
🔸 髄海の失調
東洋医学で脳は「髄海(ずいかい)」と呼ばれます。
精が十分でないと髄海が養われず、感覚や運動、精神面に影響が出ます。
発語の遅れや集中力のなさ、情緒の不安定など、Kagayaが現場で見る症状にもよく当てはまります。
さらに、気・血・津液の不足や、内熱・瘀血・痰湿などが髄海に影響すると、記憶力の低下、情緒の乱れ、神経症のような症状が現れることもあります。
🔸 肝鬱気滞(かんうつきたい)
妊娠中の母親のストレス状態が、胎児の気の流れに影響するという考え方もあります。
肝の疏泄作用が乱れると、気が上昇しやすくなり、子どもに多動傾向や情緒不安、他者との関わりの難しさが出やすくなるという特性があります。
このように、東洋医学の視点を取り入れることで、発達障がいの子どもたちの“体質傾向”を把握しやすくなり、より適切なケアにつなげることができます。
🌟 療育と鍼灸の可能性
「発達障がい=療育」という構図がすっかり定着していますが、そもそも療育ってどんなことをするのでしょうか?
療育とは、「治療」と「教育」を組み合わせた支援です。
薬物療法やリハビリテーションといった医療的なアプローチに加えて、学習支援や生活スキルの習得をサポートしていくのが療育の目的です。
つまり、「学びながら身体や心を整える支援」とも言えます。
療育を通して、その子の特性を見極め、苦手な部分に働きかけたり、得意な部分をさらに伸ばしていく。
そしてそれは、子どもだけでなく保護者にも関係することです。
子どもに関わるすべての人が同じ方向を向けるようになると、支援の質がぐっと高まります。
鍼灸師として、Kagayaはこの療育に「鍼」を組み合わせることで、さらに大きな相乗効果が生まれると感じています。
🌟 ご家庭でできるセルフケアの基本
✅ 栄養バランスの良い食事
発達障がいにおいては、脳機能のバランスが整っていないため、できることとできないことの差が大きいのが特徴です。
Kagayaはこれまで、療育現場や訪問看護で多くのご家庭と関わってきましたが、日常生活を整えるだけでも、お子さんの状態が大きく変わることを実感しています。
療育というと「病院や専門施設で行うもの」と思われがちですが、実は日々の積み重ねの中でこそ、育ちの支援は進んでいきます。
勉強や運動だけが療育ではありません。
何かに熱中しすぎて寝食を忘れてしまったり、声かけがないと切り替えが難しいお子さんも多いです。
「生活リズムを整えること」こそが、療育の第一歩です。
✅ 栄養バランスの良い食事
発達障がいのあるお子さんには、偏食傾向が見られることが多いです。
これは単なる「好き嫌い」ではなく、感覚過敏による影響が大きいことも。
たとえば、グラタンは苦手だけど中のジャガイモとチーズは食べられる、生卵は食べられるけれどゆで卵は苦手、いちょう切りのニンジンはダメだけどすりおろせばOK…など、不思議な傾向が見られます。
Kagayaも、工夫しながら少しずつ食べられるものを増やしていく支援を心がけています。
東洋医学では「精(せい)」は食から作られ、それが髄海(脳)を養うと考えられています。
つまり、食事は心と身体の土台です。
偏食が緩和されることで、精神的な安定や行動面での改善がみられることもあります。
✅ 睡眠リズムを整える
寝つきが悪い、夜中に起きてしまうなど、睡眠に関する困りごとも多くの保護者から聞かれます。
睡眠は身体や脳の休息だけでなく、心の安定にも直結します。
発達障がいのあるお子さんは、睡眠を促す「メラトニン」というホルモンの分泌が少ないと言われています。
高齢者の不眠も同じ理由によるものです。
メラトニンを補うサプリやお薬もありますが、まずは自然な生活リズムを整えることが第一です。
朝は7時までに起きて太陽光を浴びる、日中はしっかり活動する、夜は20〜21時に就寝する。
このリズムが、メラトニン分泌を助け、質の良い睡眠をもたらします。
✅ スキンシップで安心感を
スキンシップは「オキシトシン」という愛情ホルモンの分泌を促します。
このホルモンは、触れ合う双方の脳内に分泌され、安心感や愛着を生み出す働きがあります。
保護者との愛着関係がしっかりしていると、不安や情緒の揺れが和らぎ、発達にも良い影響を与えると考えられています。
現在の育児ガイドラインでも、「子どもが満足するまで抱っこする」ことが推奨されており、Kagayaもその考えに共感しています。
シンプルなようでとても大切なスキンシップ。今日から意識してみてください。
🌟 オススメ商品:チェーンブランケット
ラーゴム・ジャパンより
Kagayaが実際に使ってみて、とても良いと感じているのがこの「チェーンブランケット」です。
北欧スウェーデンで生まれた、眠れない・そわそわして落ち着かない方のための“医療用の重み布団”で、特許も取得されています。
スウェーデンでは医療現場でも処方されており、発達障がい、双極性障害、統合失調症、不安障害、PTSD、認知症などの方に有効であるとされています。
Kagayaのまわりでも「子どもがぐっすり眠れるようになった」「不安で泣くことが減った」という声をよく聞きます。
ぜひ、安心できる睡眠環境づくりの一つとして取り入れてみてくださいね。

🌟 発達の“ちぐはぐ”を整える鍼の力
発達障がいに対して、一般的な発達の流れを「定型発達」といいます。
子どもの発達には、「〇歳でこれができるようになる」という一定の目安があります。
でも、発達障がいのある子どもたちは、この順番通りには進まないことがよくあります。
たとえば、「まだうまく走れないのに、自転車には乗れる」といった段階の飛び越えや、「数字の記憶は得意だけど、会話は苦手」など、能力に大きな凸凹(でこぼこ)が見られることがあります。
Kagayaは、こうしたちぐはぐな発達を少しでも滑らかにするために、発達過程に寄り添いながら脳の成長を促すことが大切だと考えています。
そして、ここで注目したいのが 鍼の力 です。
鍼灸は、脳や神経にやさしい刺激を与えるのが得意。刺激を通じて脳の可塑性(かそせい)を高め、学習効果を引き出しやすくすることが期待できます。
つまり、鍼によって脳の準備を整えてから療育を行うことで、よりスムーズに、より効果的に子どもの発達をサポートできる可能性があるのです。
また、東洋医学には古くから「七情の失調(しちじょうのしっちょう)」、つまりメンタルの不調という概念があります。
発達障がいによる問題行動や不安定さの背景には、心のストレスや情緒の乱れが隠れていることも少なくありません。
鍼灸は、こうしたメンタルの不調にも働きかける力があります。
Kagayaの施術では、まずお子さんの“こころ”が落ち着いて、自分らしく療育に取り組める状態をつくることを目指しています。
発達のちぐはぐに悩んでいるご家族にとって、鍼灸は優しく、そして確かな手助けになれるかもしれません。
🌟 診断名よりも大切なこと
今、あなたやご家族が本当に困っていることは何ですか?
「発達障がい」という診断がつかないことが不安なのか。
それとも、人間関係がうまくいかなかったり、感覚過敏や疲れやすさで、日常生活に支障が出ていることがつらいのでしょうか?
Kagayaは、看護師として、鍼灸師として、そしてひとりの支援者として、こう考えています。
たしかに、診断名がつくことで「やっぱりそうだったんだ」と安心する方もいます。
でも実際のところ、診断名がついたからといって、それまでの困りごとが一気に解決するわけではないのです。
発達障がいの診断とは、あくまで症状の“分類”にすぎません。
同じ診断を受けたとしても、感じている困難や特性は人それぞれです。
だからこそ、診断名にこだわりすぎず、目の前にある「困りごと」をどうすれば少しでも軽くできるかに目を向けてほしいと思うのです。
たとえば、認知症も、高次脳機能障害も、精神疾患や知的障がいも、
症状だけを見れば発達障がいとよく似ていて、はっきり区別がつかないこともあります。
とくに高齢者の場合は、そもそも若い頃から知的障がいの傾向があったのか、精神疾患を発症したのか、加齢による認知の低下なのか、判断が難しいケースも多いです。
それでも、その人がどんな人柄なのか、何を大事にして生きているのかを見ていけば、関わり方や支援のヒントは自然と見えてきます。
Kagaya自身は、ちょっと極端かもしれませんが…
高齢者には基本「みんな認知症かもしれない」という視点で関わりますし、
精神疾患のある方には「発達障がいの特性もあるかも」と思いながら対応しています(失礼ですが、ほんとうにそう感じることが多いんです…)。
ただし、Kagayaから無理に「診断を受けたほうがいいですよ」と言うことはありません。
本人が必要と感じていないのに、診断や検査を勧めることはしない主義です。
実際に、発達障がいの専門医の中にも、診断がもたらす社会的な不利益を考慮して、あえて診断名をつけない判断をする方もいます。
結局のところ――
他人がどう言おうと、自分は自分!
たとえ診断がつかなかったとしても、今感じている不調や生きづらさを軽くする方法はたくさんあります。
「診断名」がなくてもいいんです。
“困りごと”を見つめて、できることから整えていくこと。
それが、ほんとうの支援のはじまりだとKagayaは思っています。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら
🌟 少し余談…左利きのKagayaが感じた「障がい」とは
「障がい」とは、乗り越える手段や工夫を見つけたとき、
もしかするとそれは、もはや「障がい」ではなくなるのかもしれません。
実は、Kagayaは左利きです。
左利きにとって、世の中は右利き中心につくられていて、日々の暮らしの中で小さな困難を感じることがあります。
たとえば、自販機や改札の操作パネルは右側にあり、授業でノートを書くと手が汚れたり、右利きの人と隣同士で座ると肘がぶつかってしまうこともあります。
極めつけは「うどん杓子」と呼ばれる給食用の器具でした。
片側だけにギザギザがついていて、右手で使うことを前提に作られています。

給食当番のとき、左手ではうまく使えず、とても苦労した記憶があります。
交代を申し出ても受け入れられず、工夫しながらなんとか乗り越えてきました。
こうした経験から、「障がい」とは一律のものではなく、環境や道具との相性、周囲の理解によって生まれるものでもあると感じています。
もちろん、医学的な定義や診断名も大切ではありますが、私たちが本当に向き合いたいのは、その人が日常の中で感じている「困りごと」や「生きづらさ」ではないでしょうか。
一人ひとりに合わせた支援や、少しの工夫で変わる暮らし。
Kagayaはその「乗り越えるための方法」を、共に探していけたらと思っています。