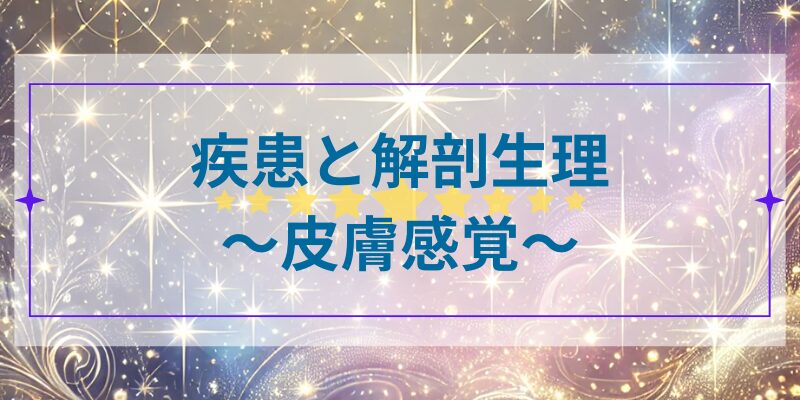🌟皮膚の構造と機能
皮膚の基本構造と感覚機能
皮膚は人体最大の臓器であり、外界と身体の境界を守るバリアとして働くだけでなく、体温調節、感覚受容、免疫防御など多様な役割を果たしています。構造的には、皮膚は大きく3層に分かれています。
- 表皮(epidermis):外胚葉由来の角化した重層扁平上皮で構成され、外界からの刺激や病原体から身体を守る第一線の防御層です。
- 真皮(dermis):中胚葉由来の強靭な結合組織で構成され、豊富な血管と神経が存在し、感覚受容器の多くがここに分布しています。
- 皮下組織(subcutaneous tissue):真皮の下にあり、疎性結合組織と脂肪細胞が主体で、エネルギー貯蔵と断熱機能を担います。
皮膚には以下のような特殊な構造も存在します。
- 毛と爪:表皮由来で、角質構造です。毛根には立毛筋が付着し、交感神経支配で収縮します。
- 皮膚腺:汗腺(エクリン・アポクリン)、脂腺、乳腺があり、いずれも皮膚付属器官です。
感覚受容の面では、皮膚には多様な受容器が点在しています。例えば、メルケル細胞は表皮に存在し、触覚を検出します。マイスナー小体やパチニ小体などは真皮〜皮下組織に存在し、それぞれ速度・加速度など異なる刺激に応答します。
なお、皮膚には以下のような重要事項が国家試験でもよく出題されます:
- メラノサイトは表皮基底層に存在し、メラニンを産生
- 真皮は中胚葉由来で膠原線維に富む強靭な構造
- 自由神経終末は侵害刺激(痛み・温度)を感知
- 手掌には脂腺が存在せず、汗腺は交感神経支配
このように皮膚は、構造・機能・神経支配の観点で整理して理解することが国家試験対策にも、臨床においても非常に重要です。
皮膚について正しい記述はどれか。
- アポクリン汗腺は全身に分布する。
- 手掌には脂腺はみられない。
- 爪は真皮の変形したものである。
- ファーテル・パチニ小体は表皮にある。
皮膚に関して正しい記述はどれか。
- 爪に感覚神経が分布する。
- 表皮に毛細血管が分布する。
- 汗腺に交感神経が分布する。
- 手掌部にアポクリン汗腺が分布する。
皮膚について正しい記述はどれか。
- メラノサイトは角質層に存在する。
- ルフィニ小体は痛覚に関与する。
- 立毛筋は交感神経が支配する。
- アポクリン汗腺は全身の皮膚に分布する。
皮膚について正しいのはどれか。
- 表皮は有棘細胞の分裂によって増殖する。
- パチニ小体は真皮乳頭に存在する。
- 自由神経終末は侵害刺激を受容する。
- 成人の右上肢は総面積の1/5を占める。
皮膚について正しいのはどれか。
- 表皮は多列円柱上皮でできている。
- 真皮は中胚葉に由来する。
- 毛幹は皮膚内部に埋まっている。
- エクリン汗腺は足底にはない。
皮膚について正しいのはどれか。
- 毛幹の下端を毛球という。
- 乳腺は皮膚腺の一種である。
- 表皮は多列円柱上皮である。
- メラノサイトは真皮にある。
皮膚について正しいのはどれか。
- 表皮は多列円柱上皮である。
- 毛は真皮の変形したものである。
- 真皮は外胚葉由来である。
- エクリン汗腺は全身に広く分布する。
皮膚について誤っている記述はどれか。
- 立毛筋は副交感神経の支配を受ける。
- メラノサイトは表皮基底層にある。
- メルケル細胞は表皮の中にある。
- 爪母基は表皮の一部である。
皮膚の各部分について誤っている記述はどれか。
- 表皮は結合組織に富む。
- 真皮は膠原線維に富む。
- 皮下組織は脂肪組織に富む。
- 毛は角質に富む。
皮膚について誤っている記述はどれか。
- 立毛筋は平滑筋である。
- 真皮は強靭な結合組織からなる。
- 表皮は重層扁平上皮である。
- 毛は真皮の変形したものである。
皮膚の構造のうち大量の膠原線維を含むのはどれか。
- 皮脂腺
- 角質層
- 真皮
- 爪
皮膚に脂腺がない部位はどれか。
- 腋窩
- 腰部
- 足底
- 項部
表皮はどの上皮に属するか。
- 多列上皮
- 重層扁平上皮
- 単層円柱上皮
- 移行上皮
皮脂腺が存在しない部位はどれか。
- 頭部
- 手掌
- 腋窩
- 背部
爪を形成する組織はどれか。
- 末節骨
- 表皮
- 皮下組織
- 真皮
毛細血管が分布しないのはどれか。
- 真皮
- 筋膜
- 表皮
- 皮下組織
🌟皮膚感覚と受容器の分類
皮膚に分布する感覚受容器とその分類
皮膚は感覚のセンサーとしての重要な役割を担っており、多様な感覚受容器が特定の刺激に応じて情報を脳に伝達しています。皮膚感覚は主に以下のように分類され、それぞれが異なる受容器と神経線維を通じて伝えられます。
- 触圧覚(接触・圧力)
- 温度覚(冷・温)
- 痛覚(侵害刺激)
- 振動覚(速い変化に反応)
| 種類 | 局在(無毛部) | 局在(有毛部) | 機能 | 順応速度 |
|---|---|---|---|---|
| 圧覚 | メルケル盤 ルフィニ終末 |
触覚盤 ルフィニ終末 |
強度検出器 | 遅い |
| 触覚 | マイスナー小体 | 毛包受容器 | 速度検出器 | 速い |
| 振動覚 | パチニ小体 | パチニ小体 | 加速度検出器 | 非常に速い |
- 温覚:自由神経終末+C線維に接続
- 冷覚:自由神経終末+Aδ線維に接続
- 無感温度:約33℃、熱痛は45℃以上で生じる
- 皮膚の触圧受容器(メルケル、マイスナー、パチニなど)は主にAβ線維に接続
- 粗大な触圧覚は前脊髄視床路を通る
- 精細な触圧覚や深部感覚は後索路を通る
| 線維型 | 感覚器 | 分類 | 髄鞘 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰa | 筋紡錘 | Aα | 有髄 | 拮抗抑制 |
| Ⅰb | 腱紡錘 | Aα | 有髄 | 自原抑制 |
| Ⅱ | 触圧受容器・筋紡錘 | Aβ | 有髄 | 触圧や振動に関与 |
| Ⅲ | 冷・温覚受容器 | Aδ | 有髄 | 鋭い痛み・冷覚 |
| Ⅳ | 温・痛覚受容器 | C | 無髄 | 鈍い痛み・温覚 |
誤っているのはどれか。
- 体性感覚神経を求心路として自律神経を遠心路とする反射を体性-内臓反射という。
- 圧受容器反射による血圧の調整は内臓一体性反射である。
- 体温調節反射には体性-内臓反射の例がみられる。
- 食物が胃に入った時に起こる胃の反射性弛緩は内臓-内臓反射の一例である。
誤っているのはどれか。
- 温覚を伝える神経線維はAβ線維である。
- 温覚は脊髄視床路を通る。
- 温受容器は自由神経終末である。
- 温覚も冷覚も起こさない無感温度は普通33℃前後である。
メルケル盤が刺激されて起こる感覚はどれか。
- 痛覚
- 温覚
- 冷覚
- 触圧覚
灸療法への関与が小さいと考えられる感覚受容器はどれか。
- 圧受容器
- 痛覚受容器
- 温覚受容器
- ポリモーダル受容器
温灸に反応する受容器はどれか。
- パチニ小体
- 自由神経終末
- ルフィニ終末
- マイスナー小体
温度受容器はどれか。
- メルケル盤
- マイスナー小体
- パチニ小体
- 自由神経終末
小児鍼による触圧刺激に対して最も順応の早い受容器はどれか。
- ルフィニ終末
- 毛包受容器
- メルケル盤
- パチニ小体
温覚に関する記述で正しいのはどれか。
- Ⅱ群線維によって伝導される。
- 温受容器は50℃付近で最も強く反応する。
- 温受容器は順応しない。
- 温受容器の形態は自由神経終末である。
温度感覚について正しい記述はどれか。
- 50℃では痛覚を伴う。
- 受容器はルフィニ終末(小体)である。
- 順応しない。
- 伝導路は後索路である。
温熱感覚を伝える求心性線維はどれか。
- Ⅳ群線維
- Ib線維
- Ⅱ群線維
- Ia線維
皮膚感覚について誤っている記述はどれか。
- パチニ小体は振動の受容器である。
- 皮膚の温点は痛点より密度が高い。
- マイスナー小体は触覚の受容器である。
- 侵害刺激の受容器は自由神経終末である。
皮膚の温覚について誤っている記述はどれか。
- 環境の温度に影響される。
- 順応が起こりやすい。
- 温点は痛点より多い。
- 求心性線維はC線維である。
灸の熱刺激を伝える脊髄視床路が通る部位はどれか。
- 側角
- 後索
- 側索
- 前角
透熱灸による熱刺激の伝導路はどれか。
- 後索路
- 外側皮質脊髄路
- 外側脊髄視床路
- 腹側脊髄視床路
灸刺激の伝導路に関与するのはどれか。
- 腹側脊髄視床路
- 延髄網様体
- 後索核
- 内側毛帯
灸刺激の伝導路に関与しないのはどれか。
- 視床
- 後索核
- 脳幹網様体
- C線維
鍼刺激による鈍い響き感覚を伝える脊髄内伝導路はどれか。
- 皮質脊髄路
- 後索路
- 錐体路
- 脊髄視床路
灸による温熱刺激の受容・伝導について正しいのはどれか。
- Ⅱ群線維により伝導される。
- 温度感覚は順応が起こりにくい。
- 腹側脊髄視床路を上行する。
- 熱刺激で開くイオンチャネルが関与する。
灸による温熱刺激の受容・伝導について正しいのはどれか。
- 熱痛情報は脊髄後索を上行する。
- Ⅱ群線維によって伝導される。
- カプサイシン受容体(TRPV1受容体)が応答する。
- 温度感覚は順応が起こりにくい。
灸による温熱刺激の受容・伝導について誤っているのはどれか。
- 脊髄後角の侵害受容ニューロンへ伝達する。
- Ⅳ群線維によって伝導される。
- 熱刺激で開くイオンチャネルが存在する。
- 熱痛情報は脊髄後側索を上行する。
温熱刺激の受容にかかわるのはどれか。
- 自由神経終末
- ルフィニ終末
- メルケル盤
- パチニ小体
知熱灸の熱刺激の伝達に関係するのはどれか。
- 後索路
- 腹側脊髄視床路
- 外側脊髄視床路
- 錐体路
灸刺激情報の伝達に関与しないのはどれか。
- 脳幹網様体
- 脊髄後角
- 延髄オリーブ核
- C線維
灸刺激の伝導に関与するのはどれか。
- 後索核
- 赤核
- Ⅱ群線維
- 脊髄後角
侵害刺激となる温度は約何度以上か。
- 60℃
- 40℃
- 55℃
- 45℃
熱痛覚を引き起こす閾値はどれか。
- 40 ℃
- 55 ℃
- 50 ℃
- 45 ℃
熱により組織の破壊が起こり始める皮膚温はどれか。
- 60 ℃
- 50 ℃
- 30 ℃
- 40 ℃
施灸により蛋白質の変性が起き始める温度はどれか。
- 45℃
- 75℃
- 100℃
- 60℃
温度刺激に関して正しいのはどれか。
- 感覚の順応は起きにくい。
- 20~40℃の間では皮膚温が高いほど閾値が高くなる。
- 熱刺激を受容するⅢ群線維がある。
- 皮膚温が45℃未満の熱刺激では神経性炎症は起こらない。
透熱灸の感覚を伝える神経線維はどれか。
- AδとC
- BとC
- AβとB
- AγとC
施灸による紅斑形成に最も関連の強い神経線維はどれか。
- B
- Aδ
- C
- Aβ
管散術の刺激を伝える神経線維はどれか。
- Aβ
- Aδ
- Aγ
- Aα
刺鍼した際の重だるいひびき感覚を伝える主な神経線維はどれか。
- Ⅰ群
- Ⅳ群
- Ⅲ群
- Ⅱ群
鍉鍼による押圧刺激の情報を伝える神経線維はどれか。
- B
- Aβ
- Aδ
- Aα
施灸による体性-内臓反射の遠心路を構成する神経線維で正しいのはどれか。
- Aα線維
- Aδ線維
- Aβ線維
- C線維
施灸による体性-自律神経反射で交感神経活動の亢進反応でないのはどれか。
- 立毛筋の収縮
- 心拍数の減少
- 皮膚血管の収縮
- 皮脂の分泌亢進
ヘッド帯の出現に関与する反射はどれか。
- 内臓 - 運動反射
- 内臓 - 自律神経反射
- 内臓 - 栄養反射
- 内臓 - 知覚反射
ヘッド帯の出現に関係する反射はどれか。
- 内臓-知覚反射
- 内臓-内臓反射
- 内臓-運動反射
- 内臓-自律神経反射
透熱灸刺激により誘発される反射はどれか。
- 体性内臓反射
- 肺迷走神経反射
- 伸張反射
- 頸動脈洞反射
透熱灸によって誘発される反射はどれか。
- 体性自律反射
- 伸張反射
- へーリング・ブロイエル反射
- 圧反射
足三里穴に施灸して胃の機能が改善したとき、関与したと考えられる反射はどれか。
- 内臓-体性反射
- 体性-自律神経反射
- 軸索反射
- 深部反射
施灸による軸索反射で正しい記述はどれか。
- 近傍の血管は収縮する。
- 反射中枢は脊髄である。
- B線維の興奮による。
- シナプスを経由しない。
刺鍼により起こる軸索反射について正しいのはどれか。
- 血漿が漏出する。
- Aβ線維の興奮によって起こる。
- 反射中枢は脊髄にある。
- 内因性オピオイドが関与する。
圧自律神経反射に関与しないのはどれか。
- 運動神経
- 交感神経
- 汗腺
- 感覚神経
温度覚について正しいのはどれか。
- 2次求心性ニューロンの細胞体は延髄の後索核にある。
- 温受容器の形態は特定の受容器構造をもつ。
- 熱刺激による興奮はⅡ群線維によって伝達される。
- 右下肢の熱刺激の興奮は左の大脳皮質の体性感覚野に伝わる。
体性-内臓反射における遠心路を構成する神経線維はどれか。
- AβとB
- AγとB
- BとC
- BとB
受容器と神経線維との組合せで誤っているのはどれか。
- 腱紡錘 ───── Aγ線維
- 冷覚受容器 ─── Aδ線維
- 圧覚受容器 ─── Aβ線維
- 痛覚受容器 ─── C線維
ゲートコントロール説で正しいのはどれか。
- 発痛促進物質の学説
- 脊髄における鎮痛機序の学説
- 脳内モルヒネ様物質の学説
- 過剰刺激と自律神経との学説
正しいのはどれか。
- 皮膚の痛覚の受容器には低閾値機械受容器とポリモーダル受容器とがある。
- かゆい感じは触覚受容器が強く刺激されて起こる。
- 皮膚の痛覚は主としてB線維群によって伝えられる。
- エンドルフィン類は痛覚の抑制に関与する。
🌟痛覚の分類と鎮痛機構
痛覚の種類と伝導路・鍼鎮痛との関係
痛覚は、身体の異常を知らせる重要な感覚であり、侵害受容器によって検出されます。痛みは以下の3つに分類され、それぞれ異なる特徴と経路を持ちます。
- 表在痛覚:皮膚表面の鋭い痛み。例:針で刺すような痛み。
- 深部痛覚:筋肉・腱・関節などの持続的な鈍い痛み。例:筋肉痛。
- 内臓痛覚:内臓の牽引や伸展、虚血で起こる痛み。例:胃痛、生理痛。
これらの痛みは、主に2種類の受容器を介して感じ取られます。
| 特徴 | 高閾値侵害受容器 | ポリモーダル受容器 |
|---|---|---|
| 刺激反応 | 機械的侵害刺激のみ | すべての侵害刺激 |
| 伝導線維 | Aδ線維(有髄) | C線維(無髄) |
| 痛みの性質 | 鋭く局所的 | 鈍く広範囲 |
| 痛覚の分類 | 主に表在性痛覚 | 表在性・深部痛覚 |
| 伝導路 | 外側脊髄視床路(痛みの主要経路) | |
関連通(放散痛)にも注意が必要です。これは、内臓の侵害刺激が体表の離れた部位に痛みとして感じられる現象です(例:心筋梗塞による左腕の痛み)。
- 一次ニューロン:侵害受容器 → 脊髄後角
- 神経伝達物質:サブスタンスP、CGRP
- 二次ニューロン:交叉して前側索を上行 → 視床、大脳辺縁系へ
- 雀啄(じゃくたく)などの刺激:Aδ線維・C線維 ⇒ 侵害刺激
- 皮膚に触れる程度の圧刺激:Aβ線維 ⇒ 触圧刺激
- 末梢経路:ポリモーダル受容器刺激 ⇒ C線維活性
- 中枢経路:
- 後根 → 後角 → 対側の前側索 → 中脳中心灰白質背側部 → 視床下部外側部 → 弓状核 → 下行性痛覚抑制系
- βエンドルフィン → ドーパミン分泌促進
- 下行性抑制路:
- 脊髄後側索経由で後角に抑制作用
- セロトニン系・ノルアドレナリン系
| モルヒネ様物質 | 受容体 | 拮抗薬 |
|---|---|---|
| エンドルフィン、エンケファリン、ダイノルフィン | オピオイド受容体 | ナロキソン |
鍼鎮痛は、これらの内因性オピオイド系を活性化することで痛覚の伝達をブロックする仕組みがあり、西洋医学的な疼痛管理と東洋医学の融合において重要な知識となります。
内因性オピオイドが関与するのはどれか。
- ナトリウムポンプ
- 下行性抑制系
- レニン・アンジオテンシン系
- TCAサイクル
内因性オピオイドによる鎮痛効果の特徴で正しいのはどれか。
- 発痛物質の生成抑制
- 脊髄後角での疼痛閾値の低下
- ナロキソンによる効果の増強
- 下行性抑制系の賦活
内因性オピオイドの効果を特異的に消失させる物質はどれか。
- ナロキソン
- セロトニン
- ヒスタミン
- ブラジキニン
内因性オピオイドとナロキソンとが結合する受容体はどれか。
- ヒスタミン受容体
- ドパミン受容体
- セロトニン受容体
- モルヒネ受容体
鎮痛に関与する内因性オピオイドはどれか。
- ヒスタミン
- プロスタグランジン
- エンケファリン
- ノルアドレナリン
エンドルフィンの拮抗物質はどれか。
- アセチルコリン
- ナロキソン
- ドーパミン
- セロトニン
内因性発痛物質でないのはどれか。
- ドパミン
- セロトニン
- ブラジキニン
- サブスタンスP
内因性発痛物質でないのはどれか。
- セロトニン
- 水素イオン
- エンケファリン
- ヒスタミン
内因性発痛物質でないのはどれか。
- カリウムイオン
- ブラジキニン
- 水素イオン
- アセチルコリン
内因性発痛物質はどれか。
- エンケファリン
- ブラジキニン
- モルヒネβ
- エンドルフィン
内因性鎮痛物質が作用する受容体はどれか。
- ノルアドレナリン受容体
- オピオイド受容体
- ニコチン様受容体
- ムスカリン様受容体
下行性痛覚抑制系に関係するのはどれか。
- 内側毛帯
- 脊髄灰白質中間質
- 海馬
- 脊髄背側索
発痛に関連しない物質はどれか。
- ソマトスタチン
- セロトニン
- ブラディキニン
- カリウムイオン
痛覚に関する組合せで正しいのはどれか。
- ヒスタミン ───────── 血管収縮
- Aδ(デルタ)神経線維 ─── 鈍痛
- C神経線維 ───────── 刺痛
- ブラジキニン ──────── 発痛物質
鍼治療による鎮痛発現に関与しないのはどれか。
- 内因性オピオイドの産生
- 脳内ドパミンの減少
- 患部の循環改善
- 脊髄膠様質細胞の興奮
鎮痛機構における下行性抑制に関与しないのはどれか。
- ナロキソン
- β-エンドルフィン
- セロトニン
- ノルアドレナリン
下行性抑制系が末梢からの痛覚情報を遮断する部位はどれか。
- 脊髄後角
- 中脳水道周囲灰白質
- 後根神経節
- 延髄大縫線核
下行性痛覚抑制系において、脊髄後角で痛覚を遮断する物質として最も適切なのはどれか。
- ロイコトリエン
- ノルアドレナリン
- ドパミン
- グルタミン酸
下行性痛覚抑制系による鍼鎮痛の特徴について正しいのはどれか。
- 発現までに時間がかかる。
- 効果は刺激周囲に限られる。
- 刺激終了後すぐに消失する。
- 大脳皮質感覚野で起こる。
痛覚に関与しない物質はどれか。
- ヒスタミン
- マグネシウムイオン
- カリウムイオン
- ブラジキニン
鍼鎮痛に関与しないのはどれか。
- オピエート受容体
- カルシトニン
- ポリモーダル受容器
- エンドルフィン
鍼鎮痛の発現に関与するβエンドルフィンを分泌する部位はどれか。
- 中心後回
- 脊髄後角
- 下垂体
- 視床
鍼鎮痛機構に関与しないのはどれか。
- オピオイド物質
- 脊髄膠様質
- ブラジキニン
- 下行性抑制
鍼鎮痛の発現に関与する物質はどれか。
- メラトニン
- トロポミオシン
- アセチルコリン
- セロトニン
鍼の末梢性鎮痛効果に最も関与するのはどれか。
- ムスカリン受容体
- アデノシンA1受容体
- ヒスタミン受容体
- アドレナリン受容体
鍼鎮痛の発現に関与する部位はどれか。
- 歯状核
- 赤核
- 中脳水道周囲灰白質
- 脊髄前角
施灸により局所の鎮痛に作用するのはどれか。
- 交感神経活動の亢進
- 皮膚血流の増加
- ストレス蛋白質の産生
- 筋収縮
🌟自律神経反射と皮膚感覚の関連
皮膚感覚と自律神経反射のつながり
皮膚感覚は単に「触れる・感じる」だけでなく、内臓の働きや情動反応とも深く関連しています。その中心にあるのが「自律神経反射」と呼ばれる神経反応です。これらは求心路と遠心路からなる反射弓を介して、自律的に臓器の機能を調節しています。
自律神経反射には以下の3つの種類があり、それぞれ異なるルートで信号が伝達されます。
- 例:圧受容器反射(血圧調整)
- 求心路:内臓求心性線維(主にC線維)
- 遠心路:交感・副交感などの自律神経線維(B線維、C線維)
血圧や心拍数の調整に関与し、身体の内部環境を自動的に維持します。
- 例:筋性防御(腹膜炎など)、ヘーリング・ブロイエル反射
- 求心路:内臓求心性線維(C線維)
- 遠心路:体性運動神経(Aα線維)
内臓の異常が体表の筋肉に反応を引き起こす仕組みで、腹筋の緊張や収縮などの防御反応が見られます。
- 例:対光反射、輻輳反射、射乳反射など
- 求心路:体性感覚神経(Aβ線維、Aδ線維、C線維)
- 遠心路:自律神経(B線維、C線維)
この反射は皮膚や筋肉などの体性感覚刺激が、内臓の反応を引き起こすもので、鍼灸治療の臨床効果を説明する際にもよく使われます。
- 汗腺には交感神経が分布し、発汗をコントロールしています。
- 立毛筋も交感神経支配で、寒さや恐怖で毛が逆立ちます。
- 皮膚の温度や痛覚刺激が、内臓活動やホルモン分泌にも影響を与えることが知られています。
また、鍼灸治療では、体表(体性)への刺激を通して内臓(自律神経系)の調整を行う「体性-内臓反射」を積極的に活用しています。これは、「経穴刺激により胃腸の動きが改善される」といった反応の背景にある神経生理学的な仕組みです。
このように、皮膚感覚を通して自律神経が働くメカニズムは、東洋医学だけでなく西洋医学でも注目されており、鍼灸の鎮痛・自律神経調整効果の科学的裏付けにもつながっています。
深部痛覚の特徴について誤っている記述はどれか。
- 痛みの感受性には部位差がある。
- 痛みの局在が明瞭な場合が多い。
- 骨格筋の反射性収縮を起こすことが多い。
- 自律神経反射を伴うことが多い。
痛みの識別に関係する伝導路はどれか。
- 後索路
- 脊髄網様体路
- 脊髄小脳路
- 脊髄視床路
痛みの識別に関与する中枢内伝導路はどれか。
- 前脊髄視床路
- 脊髄網様体路
- 新脊髄視床路
- 後索路
痛覚の中枢内伝導路で情動行動、自律神経機能や痛みの制御の調節に関与すると考えられているのはどれか。
- 後索路
- 新脊髄視床路
- 脊髄網様体路
- 前脊髄視床路
体幹部の痛覚の伝導路はどれか。
- 外側脊髄視床路
- 前脊髄小脳路
- 視蓋脊髄路
- 延髄視床路
透熱灸による熱痛覚を伝える伝導路はどれか。
- 腹側脊髄視床路
- 外側脊髄視床路
- 内側毛帯路
- 後索路
脊髄の部位で痛覚を伝える一次求心性ニューロンがシナプスを形成するのはどれか。
- 後索
- 前角
- 前索
- 後角
痛覚の一次性ニューロンが二次性ニューロンに交代する部位はどれか。
- 薄束核
- 脊髄後角
- 楔状束核
- 脊髄前角
痛覚の二次性ニューロンが上行するのはどれか。
- 脊髄前側索
- 内側毛帯
- 脊髄背側索
- 脊髄後索
四肢や体幹からの痛覚情報を伝える三次ニューロンが局在するのはどれか。
- 赤核
- レンズ核
- 視床後外側腹側核
- 尾状核
痛みを伴う熱刺激を伝導するのはどれか。
- Aγ線維
- Aα線維
- Aδ線維
- Aβ線維
ポリモーダル受容器の性質として正しい記述はどれか。
- 非侵害性の受容器である。
- 筋の張力も感受する。
- 機械的、化学的および熱刺激に反応する。
- 伝導速度はAβ帯域である。
鍼刺激による反応でポリモーダル受容器が関与しないのはどれか。
- 鍼のひびきの惹起
- 内因性鎮痛機構の賦括
- サブスタンスPの遊離
- Aβ線維の興奮
鍼刺激によるポリモーダル受容器の興奮を伝える神経線維はどれか。
- Aβ
- C
- B
- Aα
ポリモーダル受容器からの求心性神経線維の特徴で誤っているのはどれか。
- 伝導速度が遅い。
- 細い神経線維である。
- 振動感覚を伝える。
- 疼くような痛みを伝える。
皮膚のポリモーダル受容器からの求心性線維はどれか。
- Aβ線維
- C線維
- B線維
- Aα線維
ポリモーダル受容器が受容した熱痛を主に伝導するのはどれか。
- Aα線維
- Aγ線維
- Aβ線維
- C線維
鈍い痛みを伝える神経線維はどれか。
- Aβ線維
- Aα線維
- B線維
- C線維
透熱灸による熱痛覚を伝える神経線維はどれか。
- Aβ線維
- B線維
- Aα線維
- C線維
痛み情報を伝達するAδ(デルタ)神経線維について正しいのはどれか。
- 刺すような鋭い痛みを伝達する。
- 無髄の神経線維である。
- 局在が不明瞭な痛みを伝達する。
- ルフィニ触覚盤やパチニ小体からの情報を伝達する。
透熱灸による熱痛覚を伝導する求心性神経はどれか。
- Ⅱ群線維
- Ⅳ群線維
- Ib群線維
- Ia群線維
鍼施術の際にⅢ群線維が伝えるのはどれか。
- 鍼の刺入圧
- 押手の上下圧
- 鋭い切皮痛
- 重だるい響き感覚
痛みの受容器はどれか。
- マイスナー小体
- パチニ小体
- 自由神経終末
- ルフィニ終末(小体)
内臓痛について正しい記述はどれか。
- 自律神経症状を伴わない。
- 炎症時には痛みが増強する。
- 関連痛を伴わない。
- 局在が明確である。
内臓痛について誤っているのはどれか。
- Aβ線維により伝達される。
- 脊髄後角の広作動域ニューロンに接続する。
- 関連痛の出現に関与する。
- 痛みの局在が不明瞭である。
関連痛に関与しないのはどれか。
- 内臓性求心路
- 脊髄前角細胞
- 脊髄後角細胞
- 体性求心路
関連痛に直接関与しないのはどれか。
- 侵害受容器
- 外側脊髄視床路
- Ib群求心性線維
- 広作動域ニューロン
痛覚について正しいのはどれか。
- 表在性痛覚はⅡ群線維が伝える。
- 侵害受容器は特定の受容器構造をもつ。
- 深部痛覚はⅣ群線維が伝える。
- ヒスタミンは内因性鎮痛物質である。
痛覚に関する記述で正しいのはどれか。
- 関連痛は皮膚の炎症で生じる。
- 受容器は自由神経終末である。
- 鋭い痛みはC線維で伝えられる。
- 順応しやすい。
皮膚痛覚について誤っている記述はどれか。
- Aδ線維は速い痛みを伝える。
- 順応が起こりやすい。
- 受容器は自由神経終末である。
- C線維は局在の不明瞭な痛みを伝える。
痛覚に関与しないのはどれか。
- 自由神経終末
- 後索路
- 視床
- C線維
痛覚を抑制する生体機構でないのはどれか。
- 脊髄膠様質細胞(SG細胞)
- オピオイドの産生
- 下行性抑制系
- レニン・アンジオテンシン系
痛みについて誤っている記述はどれか。
- 深部痛覚は局在性が明確である。
- エンドルフィンは内因性鎮痛物質である。
- 受容器は自由神経終末である。
- 鋭い痛みと鈍い痛みとがある。
内臓痛の特徴について誤っている記述はどれか。
- 持続性のうずく痛みである。
- 腸間膜を伸展した際に痛みが起こる。
- 局在が明らかである。
- 吐き気を伴うことが多い。
痛覚について誤っている記述はどれか。
- 新脊髄視床路は局在性の乏しい痛みを伝える。
- Aδ線維は早い痛みを伝える。
- 侵害刺激によって屈曲反射が起こる。
- 受容器は自由神経終末である。
痛覚について誤っている記述はどれか。
- 鋭い痛みはAδ線維で伝えられる。
- 脊髄視床路を上行する。
- 順応しやすい。
- 関連痛は内臓炎症時に生じやすい。
無髄神経線維によって伝導される情報はどれか。
- 深部痛覚
- 筋の収縮
- 筋の伸展
- 触覚
🌟皮膚疾患
皮膚疾患について正しいのはどれか。
- 円形脱毛症はウイルス感染が原因である。
- 帯状疱疹は分節性の神経性皮膚炎である。
- 脂漏性湿疹は油脂を取り扱う人に多い。
- 接触性皮膚炎はウイルスとの接触により起こる。
接触性皮膚炎について誤っている記述はどれか。
- I型アレルギー反応である。
- 発赤・腫脹が著しい。
- 原因物質の除去で急性病変は治癒に向かう。
- 原因物質の接触部位に湿疹病変が認められる。
🌟アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎について正しいのはどれか。
- スキンケアが重要である。
- 四肢の伸側に好発する。
- 皮膚のバリア機能が亢進している。
- 主にⅡ型アレルギーが関与する。
アトピー性皮膚炎について正しい記述はどれか。
- 小児の疾患である。
- 有病率は減少傾向にある。
- 環境因子が関与する。
- Ⅱ型アレルギー反応である。
アトピー性皮膚炎について正しいのはどれか。
- 抗核抗体が陽性であることが多い。
- 主にⅡ型アレルギーが関与している。
- 血清IgGが高値であることが多い。
- 気管支喘息を合併することが多い。
アトピー性皮膚炎について誤っているのはどれか。
- 季節により症状が変動しやすい。
- 家系内発症がみられやすい。
- 気管支喘息と合併しやすい。
- Ⅱ型アレルギーである。
誤っている組合せはどれか。
- 風疹 ───────── 胎児奇形
- アトピー性皮膚炎 ─── ビタミンB12欠乏
- 麻疹 ───────── 亜急性硬化性全脳炎
- 水痘 ───────── 帯状疱疹
🌟発疹
胸部の帯状疱疹痛について適切でない施術はどれか。
- 疼痛領域を挟む鍼通電療法
- 疼痛領域を囲む水平刺
- 発疹への直刺
- 罹患神経の高さで脊柱直側の置鍼
次の文で示す患者の病証に対し、適切な治療方針はどれか。
「40歳の男性。エビを食べたところ発疹が現われた。発疹は赤みを帯び膨隆もみられる。舌質は紅。舌苔は黄膩。脈は滑数。」
- 風寒を除く
- 湿熱を除く
- 津液を補う
- 血を補う
次の文で示す患者の病証に対する治療方針で最も適切なのはどれか。
「24歳の男性。主訴は頸から上の痒み。以前からアトピー性皮膚炎による痒みがあったが、症状の変化が激しくなってきた。悪化すると滲出性になる。普段から甘いものを好み、過食すると悪化する。舌苔は白膩、脈は滑。」
- 風寒の邪を除く。
- 運化作用を高め、湿を化す。
- 血を養い、燥を潤す。
- 血熱を除く。
次の文で示す患者の病証に対する治療で最も適切なのはどれか。
「38歳の男性。主訴は鼻閉と鼻汁。鼻汁は黄色く粘りがあり量も多い。日中は頭がぼんやりすることが多く、皮膚掻痒感や嗅覚障害もある。舌質は紅、胖大舌。」
- 太淵に補法を行う。
- 太白に補法を行う。
- 豊隆に瀉法を行う。
- 風門に瀉法を行う。
次の文で示す症例に対して灸治療を行う場合に最も適切な経穴はどれか。
「60歳の女性。主訴は陰部掻痒感。4日前に深酒をした。昨日より右膝内側から大腿部内側のひきつれ感がある。脈は左関上の浮数滑。」
- 脛骨内側面の中央、内果尖の上方5寸
- 脛骨内縁の後際、内果尖の上方3寸
- 腓骨の前方、外果尖の上方5寸
- 前脛骨筋の外縁、外果尖の上方8寸
次の文で示す病証で最も適切なのはどれか。
「58歳の女性。昨夜から陰部掻痒感を自覚。最近イライラすることが多く、飲酒量が増えた。舌辺に黄厚膩苔、脈は左関上の浮数滑を認める。」
- 肝経湿熱
- 胃熱
- 胃陰虚
- 肝陽上亢
次の文で示す患者の病証でみられる舌所見はどれか。
「38歳の男性。就職してからアトピー性皮膚炎を発症。仕事が忙しくなると顔が赤くなりイライラして体を掻きむしってしまう。冷やすと痒みが軽減する。」
- 淡白舌
- 紫舌
- 淡紅舌
- 紅舌
次の文で示す病証に対する治療として最も適切な足の経脈はどれか。
「36歳の男性。主訴は目の疲れと痒み。2日前から右目の内眼角に痒みを自覚し始め、すぐにこすりたくなる。右内眼角部の結膜は軽度充血して、目やにが付きやすい。また、背部のつっぱり感がある。」
- 陽明経
- 厥陰経
- 太陽経
- 少陰経
次の文で示す患者の病証で随伴症状として最もみられるのはどれか。
「10歳の男児。頸部から前胸部にかけて赤い湿疹がみられ、悪化すると痒みが強くなり、じくじくする。舌は紅、黄膩苔、脈は滑数を認める。」
- 手足のけいれん
- 息切れ
- 泥状便
- 悪風
🌟脱毛症
円形脱毛症に対する鍼灸治療で適切でないのはどれか。
- 脱毛部周囲への知熱灸
- 脱毛部への梅花鍼
- 脱毛部への焦灼灸
- 脱毛部周囲への散鍼
50歳の男性。易疲労、腰がだるく手足の厥冷を訴える。顔色はやや黒ずみ、頭髪はうすく聴力の減退がある。治療対象とする病証はどれか。
- 腎虚証
- 肺虚証
- 肝虚証
- 脾虚証
次の文で示す患者の病証に対し、五臓の病に用いる経穴で適切なのはどれか。
「50歳の男性。最近、毛髪が多く抜け落ち、細く柔らかくなった。頭皮は脂が多い。耳鳴りや腰のだるさもある。脈は細数。」
- 太谿
- 太白
- 大陵
- 太淵
次の文で示す患者について、関係する臓腑経脈を考慮して施術する場合、適切な部位はどれか。
「15歳の女子。高校受験によるストレスのため、頭頂部に直径2cmの円形の脱毛部ができた。」
- 前腕内側
- 上腕外側
- 大腿外側
- 下腿内側
🌟まとめと国家試験対策ポイント
皮膚感覚とその周辺知識の総まとめ
ここまで「皮膚の構造」「感覚受容器の種類」「痛覚と鎮痛」「自律神経反射との関係」について解説してきました。国家試験では単発の知識だけでなく、それらを横断的に理解しているかが問われる問題が多く見られます。
以下に試験に出やすい重要ポイントを整理しました。
- 表皮は外胚葉由来の重層扁平上皮
- 真皮は中胚葉由来で膠原線維が豊富な結合組織
- 皮下組織は脂肪に富む疎性結合組織
- 毛・爪・乳腺はすべて表皮由来の皮膚付属器官
- 触圧覚はAβ線維経由、後索路や前脊髄視床路を通る
- 痛覚はAδ線維とC線維が関与し、外側脊髄視床路を上行
- 温度覚は33℃前後が無感温度、45℃以上で熱痛覚
- 鋭い痛みは高閾値侵害受容器とAδ線維による
- 鈍い痛みはポリモーダル受容器とC線維が関与
- 内因性モルヒネ様物質(βエンドルフィンなど)は痛覚抑制に働く
- 拮抗薬ナロキソンはオピオイド受容体を遮断
- 体性-内臓反射:皮膚刺激で内臓機能に影響を与える
- 内臓-体性反射:臓器の異常で筋肉の防御反応が起こる
- 汗腺・立毛筋は交感神経支配