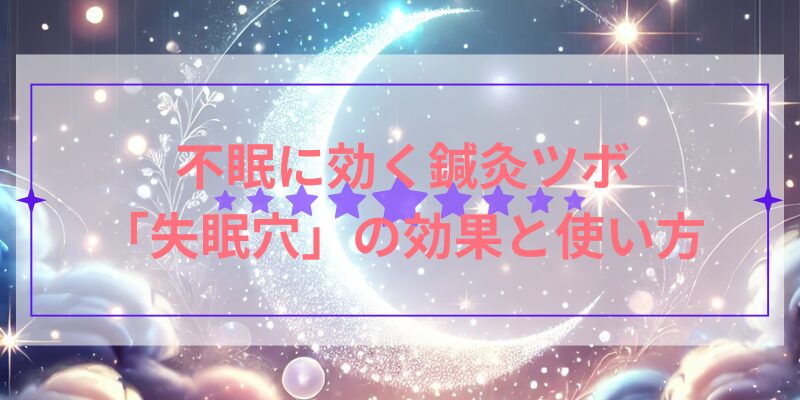こんにちは~。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
「夜、布団に入ってもなかなか寝つけない」「ようやく眠っても夜中に何度も目が覚めてしまう」「日中に眠気が襲ってくるけど、夜は逆に冴えてしまう」──そんな不眠の悩みを抱えていませんか?
不眠の症状は人によってさまざまですが、睡眠の質が下がることで、身体だけでなく心のバランスも崩れてしまいます。
Kagaya自身も、看護師として夜勤をしていた頃に、いわゆる“生活リズムの崩れ”から強い不眠状態を経験しました。
寝たいのに眠れない、朝起きるのがつらい、頭が重い──そんな日々が続くと、自然と気分も落ち込みがちになります。
そんなとき、Kagayaが助けられたのが、東洋医学のセルフケア。
なかでも「失眠(しつみん)」というツボとの出会いは、睡眠の質を整える上でとても大きなヒントとなりました。
「失眠」はその名の通り、“眠りを失った状態”を改善するための特効穴。足の裏側、かかとの真ん中に位置するシンプルなツボですが、正しく使うことで眠りの質にじわじわと変化をもたらしてくれます。
Kagayaは日頃から、訪問ケアの中でも「夜眠れないんです」「薬にはなるべく頼りたくなくて…」という声をよく耳にします。
そんなとき、この失眠穴のケアをお伝えすると、「気持ちよかったです」「ぐっすり眠れました」という感想をいただくことが多いです。
この記事では、東洋医学の考え方や実際の看護・鍼灸現場での経験をふまえながら、「失眠穴」の場所の探し方、押し方、お灸の使い方、注意点まで丁寧に解説していきます。
「夜なかなか眠れない」「できれば自然な方法で改善したい」「薬の副作用が心配」──そんなお悩みを抱える方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
誰でも簡単にできる“やさしいセルフケア”が、あなたの眠りにそっと寄り添いますように。
🌟 失眠(しつみん)ってどんなツボ?

失眠(しつみん)は、足の裏側の「かかとの中央あたり」にある、とてもシンプルながら重要なツボです。
その名前には深い意味が込められています。
「眠りを失う」と書いて“失眠”──つまり、「眠れない状態を改善する」という目的で名付けられたとされ、まさに不眠ケアに特化したようなツボです。
古くから中国の家庭療法や民間療法でも使われており、「夜ぐっすり眠りたいときはかかとを温めると良い」という言い伝えも、この失眠穴の効能に通じています。
Kagayaが訪問ケアやサロン施術で出会った方々の中にも、「なかなか寝つけなくて辛い」「睡眠薬はなるべく減らしたい」という方が少なくありません。
そういった方に、失眠へのお灸をすすめると、「かかとにお灸って、気持ちいいんですね」「朝の目覚めが全然違いました」と驚かれることも。
📍 場所の見つけ方
失眠穴は、足の裏ではなく「足の裏側=足底部とかかとの境目あたり」にあります。
触ってみると、かかとの皮膚の中で少し柔らかくへこんだポイントがあるのがわかります。
- 裸足になって、かかとの真ん中をゆっくり押してみてください。押すとちょっと響く感じがある部分が目安です。
- 片足立ちになると、自然とその部分に圧がかかるので「ここかも」とわかりやすくなります。
- 左右両方にあるため、両かかとに交互にセルフケアするのもOKです。
日中に押して場所を覚えておくと、夜寝る前にすぐに見つけられて便利です。
🩺 東洋医学での意味
東洋医学では、不眠は「陽気(ようき)」が体の上部にこもってしまうことや、「心腎不交(しんじんふこう)」という心と腎のバランスの乱れが原因と考えられています。
特に「腎」は、成長・発育・ホルモン・老化・生殖・睡眠といった生命の根本に関わる大切な臓腑です。
失眠穴は、その腎のエネルギー(腎気)を補い、上にのぼってしまった“余分な陽気”を足元へと沈めてくれると考えられています。
つまり、頭の熱や緊張、不安などが強くて眠れないとき──「頭が冴えて眠れない」「考え事が止まらない」というときに、足のかかとにある失眠を温めることで、気を下げ、眠りに導くというメカニズムです。
西洋医学的に見ても、足底には副交感神経の反射ゾーンが多く集まっており、足裏を温めたり刺激したりすることでリラックス状態をつくりやすくなります。
東西の知恵が一致している点でも、安心してセルフケアに取り入れやすいツボだといえるでしょう。
次の章では、この失眠穴を使って「どのようにお灸を据えると効果的なのか」「押すだけでも効くのか」といった具体的な使い方をご紹介します。
🌙 失眠穴の使い方:お灸がおすすめ
失眠穴は、その位置や役割の特性から、指圧よりも「お灸」による温熱刺激がとても適しているツボです。
足のかかとは皮膚が分厚く、指で強く押してもなかなか深いところまで響きにくいのが特徴。
その点、お灸ならじんわりと奥まで熱が伝わりやすく、刺激の強さも穏やかなので、自宅でのセルフケアにもぴったりです。
🔥 お灸での刺激(おすすめ)
Kagayaが日常的におすすめしているのは、手軽に使える台座灸タイプ。
とくに初心者の方や、火を使うことに抵抗がある方でも扱いやすい製品が多く出ています。
- セルフケアでは「せんねん灸」シリーズが扱いやすく、信頼性も高くて安心です
- 台座灸タイプを使用し、失眠穴に1壮(いっそう)〜3壮を目安に据えます
- 夜、寝る直前にお灸をすることで、副交感神経が優位になり、深いリラックス状態を作れます
- 火を使うのが不安な方は、「火を使わないお灸」や温灸器もおすすめです
とくに「寝つきが悪い」「寝てもすぐ起きてしまう」といったタイプの不眠には、温かさによる刺激が脳を落ち着かせる役割を果たします。
Kagaya自身も、夜勤明けで自律神経が乱れやすいタイミングでは、この失眠穴に「せんねん灸 伊吹」などを据えることで、じんわりとした熱感が足元から心地よく広がり、深くリラックスできました。
以下に、おすすめのお灸製品をご紹介します。
どれもAmazon・楽天・Yahoo!から選べるので、ライフスタイルや好みに合わせて試してみてください。
⚠️ 注意:円皮鍼(えんぴしん)や金粒など貼るタイプの刺激は、かかとは体重がかかる部位のため、歩行時に痛みを感じやすくおすすめできません。失眠穴には、やさしく深部に熱を届けるお灸の方が安全かつ効果的です。
🚨 注意点
失眠穴へのお灸はとても手軽で効果的なセルフケアですが、「安全に」「正しく」使うことが何よりも大切です。
とくに以下のポイントに気をつけて行うことで、安心して心地よく眠りに導くケアが続けられます。
- 🔥 火を使うお灸は、やけどに注意!
お灸は火を使うため、周囲に燃えやすいものがないかを確認し、火傷しないよう肌との距離や熱さの感覚に気を配ってください。 - 👩⚕️ 妊娠中・重度の糖尿病・皮膚疾患がある方は医師に相談を
かかと周辺に潰瘍や湿疹などがある場合や、妊娠初期・不安定期の方は刺激を控えましょう。自己判断で行わず、事前に医師・鍼灸師など専門職へご相談ください。 - 💥 痛み・違和感があればすぐ中止を
お灸が熱すぎて皮膚が赤くなったり、水疱ができそうになった場合はすぐに取り除きましょう。「熱い」と感じた時点で無理せず外してください。
また、失眠穴は足の裏側、つまり体重がかかる部分に位置しています。
そのため、円皮鍼や金粒のような“貼ったまま歩く”タイプのツボ刺激はおすすめできません。
歩行時に強い痛みが出たり、皮膚が傷ついたりするリスクがあるため、夜のリラックスタイムや就寝前に座った状態で「お灸による温熱刺激」を行うのが理想的です。
Kagayaが訪問施術を行う際も、患者さんの体質や皮膚の状態に応じて「お灸の種類」「壮数(刺激量)」「タイミング」を慎重に選ぶようにしています。
セルフケアでも「心地よい」が基本ですので、無理な刺激ややりすぎは禁物です。
とくに高齢の方や感覚が鈍い方、小さなお子さんにお灸をする場合は、必ずそばで見守る人が付き添ってください。
安全第一で行うことが、継続するうえでとても重要なポイントです。
また、お灸を終えた後は「皮膚の様子を見る」ことも忘れずに。
赤み・かゆみ・腫れがないかを確認し、トラブルがあれば使用を中止して様子を見るようにしてください。
大切なのは、「お灸をすること」そのものよりも、それを通して自分の身体とやさしく向き合うこと。
無理なく、続けられる範囲でセルフケアを取り入れていきましょう。
📝 まとめ
今回は、不眠に悩む方へ向けて「失眠(しつみん)穴」のセルフケアをご紹介しました。
足のかかとというシンプルな場所にあるこのツボには、「眠りを失った状態を改善する」という強い意味が込められています。
東洋医学の知恵と現代人のストレス社会が抱える不眠という課題──この2つをつなぐ、まさに“自然な解決策”のひとつです。
失眠穴は、眠れない夜にそっと自分を労わる“お守り”のような存在。
特別な道具や技術がなくても、ツボの場所を覚えて、やさしくお灸を据えるだけで、気持ちが落ち着いてくるのを感じる方はたくさんいらっしゃいます。
「眠れない」「薬にはできれば頼りたくない」──そう思ったときこそ、セルフケアの出番です。
失眠穴のお灸を習慣にすることで、寝つきがよくなったり、夜中に目覚める回数が減ったりと、少しずつ身体が本来のリズムを取り戻していく方もいます。
Kagaya自身も、夜勤後の寝つきの悪さや、自律神経の乱れを感じる日には、足元のお灸で「スイッチを切り替える」ようにしています。
お灸はただ温めるだけでなく、「いま、わたしの体に向き合っている時間」と感じることも大切です。
不眠の原因は、環境、ストレス、体質、ホルモンの乱れなど多岐にわたりますが、どんなケースであっても、まずは“自分の身体をやさしく整える”ことが出発点になります。
セルフケアは、あなた自身があなたの一番の味方になる手段です。
無理のないペースで、できることから一歩ずつ。今夜から、さっそく試してみませんか?
不安や疑問がある方、実際にやってみてよくわからなかったという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
個別にお体の状態や生活に合わせたアドバイスも可能です。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら