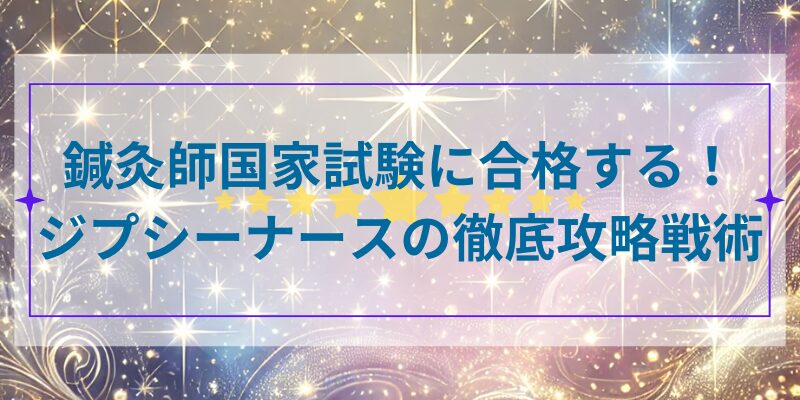🌟ジプシーナースの試験体験と気づき
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
来年の2月、いよいよ鍼灸師国家試験が実施されますね。
看護師国家試験を経験済みのKagayaにとっても、今回はなかなか気合が必要な挑戦になりそうです。
看護師国家試験のときは、正直なところあまり勉強せずに受験しました。
当時は若さゆえの勢いと、基礎学力で何とか切り抜けた感があります。
でも今振り返ると、「よくあんな状態で合格したな…」と、自分でも恐ろしくなります。
若いって本当に怖いもの知らずですね(笑)。
ただ、Kagayaは現役の学生さんより年上だったので、若さだけでは乗り切れない部分もありました。
だからこそ、今の自分にできることを一つずつ、地に足をつけて取り組んでいきたいと思っています。
鍼灸師国家試験は、看護師試験よりも暗記量が圧倒的に多い印象です。
特に経絡経穴や東洋医学の理論は、馴染みがない分だけ苦戦する人も多いはず。
国家試験は全体の60%以上を正解すれば合格できる仕組みですが、それでも内容の濃さには要注意です。
最近では出題数も増えており、現在は170問中102問(60%)の正解で合格ラインとなっています。
言い換えれば、68問までは間違えてもOKということ。
ただし「何を落としていいのか」が分かっていないと危険です。
経絡経穴概論は20問程度出題されますが、正直、361個もの経穴を丸暗記するのは現実的ではありません。
1年生のころからコツコツ覚えるように指導されますが…Kagayaは自信満々に言えます、「忘れる自信がある!」と(笑)。
試験が終われば即効で忘れる、というのもあるあるですよね。
それなら最初から、「全部覚える」という完璧主義は手放して、取れる問題に集中した方が効率的です。
実際、経穴を全部覚えていなくても、問題の解き方を工夫すれば答えられる問題も多いです。
たとえば経穴の位置や主治ではなく、流注や組織の関連から推測できる問題もあります。
また、鍼灸師国家試験は今のところ4択形式。
医師国家試験や看護師国家試験のように「5択」や「全て選べ」問題はありません。
つまり、必ず1つだけ正しい答えがあります。
選択肢を絞り込んでいくだけでも、正解率はグッと上がります。
4択であれば、何も分からなくても25%の確率で正解します。
そこから明らかに違う選択肢を1つ消せば、正解率は33%、2つ消せれば50%、3つ目まで消せれば確定です。
これはれっきとした戦術です。
さらに言うと、過去問と似たような問題は毎年80%以上出題されていると言われています。
まったく同じ問題は出なくても、「見たことあるパターン」の問題が本当に多いです。
だからこそ、過去問を解きながら「どの問題が取りやすいか」「自分はどの分野が得意か」を分析して、効率の良い勉強戦術を立てることが大切なのです。
暗記だけに頼らず、問題を見極める力や選択肢を絞るテクニックを磨くこと。
それが最短で合格に近づくためのポイントだと、Kagayaは考えています。
🌟勉強する優先順位
鍼灸師国家試験は、出題範囲がとても広く、全部をまんべんなく勉強していては時間が足りません。
限られた勉強時間の中で、いかに効率的に得点を重ねるかがカギになります。
たしかに、学校では「361個の経穴をしっかり覚えよう」「五行色体表は完璧に」と教えられますし、それが正攻法であることは間違いありません。
でも、Kagayaの本音を言えば「全部覚えるなんて無理ゲー」です。
経穴は、取穴・主治・経絡など覚える要素が多すぎて、試験のためだけに丸暗記するには膨大な労力がかかります。
五行や陰陽、五臓六腑の表も、理解していないと応用が効かず、解くたびに表をノートに書いて整理しないといけないような問題もあります。
国家試験では、1問あたり約1分のスピードで解く必要があります。
つまり、180問を120分で解くとして、1問あたり40秒。難しい問題に時間をかけすぎると、後半の簡単な問題すら解く時間が足りなくなってしまいます。
ですから、時間のかかる問題は“後回し”または“捨て問”と割り切る勇気も必要です。
完璧主義は合格から遠ざかります。
特に「東洋医学概論」や「経絡経穴概論」のように図解・分析・文章の読み込みが必要な分野は、後半に回してOKです。
これは怠けではありません。
戦略です。
もちろん、東洋医学概論が得意な人なら話は別ですが、「表や五行の関係が出てくると混乱する…」という人は、後回しの選択がむしろ正解だと思います。
国家試験は60%以上取れればいい試験です
。逆に言えば、40%は間違えても合格できます。
カンでマークすれば25%の確率で正解するのだから、苦手な分野は「4つの選択肢からとにかく1つ消す→残った中で最も可能性が高いものを選ぶ」といった対応でも十分通用します。
Kagayaも、東洋医学の抽象的な概念や、経穴の細かな位置には苦手意識があります。
だからこそ「あとで解く」「時間があったらやる」というスタンスで、先に得点源となる問題を片付けるようにしています。
例えば、医学概論・関係法規・公衆衛生学などは暗記中心で短時間で解ける問題が多いため、まずはここで点を稼ぎにいきます。
また、はり理論・きゅう理論も出題数が少なく範囲も狭いため、コスパの良い得点源です。
「東洋医学概論や経絡経穴概論は苦手だけど、後で2~3周できれば何とかなる!」くらいの気持ちで挑むほうが、精神的にも余裕が生まれます。
試験時間の120分をどう配分するかを、日頃の過去問演習からシミュレーションしておくことがポイントです。
つまり、勉強の優先順位を明確にしておけば、どこで点を取って、どこを見送るかの判断がしやすくなります。
「全部をやる」ではなく、「合格するために必要な点数だけを確実に取る」考え方が、最短合格への近道です。
はりきゅう理論
はり理論・きゅう理論は、鍼灸師国家試験の中でも出題範囲が比較的狭く、勉強した分が得点につながりやすい“おいしい科目”です。
各10問ずつ、計20問が出題されるため、合格点(180点中102点)を目指すうえで無視できない得点源になります。
内容としては、刺鍼の技法や鍼の種類、経穴の刺激効果、艾の種類、温灸法の分類、安全管理、禁忌など、実技と理論が融合した内容が中心です。
また、触圧覚や温痛覚といった感覚受容のメカニズムも頻出項目で、これは解剖生理学の神経系ともリンクしています。
この科目の魅力は、「難しい文章読解が不要」「出題パターンが安定している」「臨床でも即活用できる知識が多い」点です。
まさに勉強のコスパが非常に高い分野といえます。
たとえば、鍼先の形状(毫鍼、円鍼など)や刺鍼手技(単刺法、雀啄法、補瀉法)など、選択肢で出てきた瞬間にピンと来るような用語も多いため、ある程度覚えていれば直感的に解ける問題も多いです。
また、実は「はり師」と「きゅう師」はそれぞれ独立した国家資格であり、国家試験もそれぞれに合格しないと両方の免許は得られません。
つまり、「はり師のみ」「きゅう師のみ」という人も現実には存在します。
Kagayaの肌感では、「はり師のみ」の人よりも「きゅう師のみ」の人の方が多い印象があります。
これは、きゅう理論の方が出題が素直で比較的取り組みやすいからかもしれません。
たとえば、艾の種類や台座灸の特徴、温灸の適応と禁忌などは、過去問にほぼ同じ形式で登場することも多く、過去問演習で十分対応可能です。
一方、「はり理論」は鍼尖の形状や刺鍼法、神経線維の分類(Aβ、Aδ、C線維)など、やや専門的な知識や神経学の知識が必要となる場面もあり、やや難易度が高いと感じる人もいるかもしれません。
とはいえ、どちらも範囲が明確であるため、出題ポイントをしっかり絞って対策すれば、確実に点数が取れます。
鍼灸師として臨床に出てからも、「これは取っておいてよかった」と思える知識が詰まっています。
特に、感染対策や衛生管理、安全な施術のためのルールなどは、患者さんの命と健康を預かる施術者にとって重要な責任でもあります。
医療系国家資格を持つ者として、基礎中の基礎ともいえる分野です。
そのため、「点を取るため」だけでなく、「実際に患者さんを診る際の基盤となる知識」として、前向きに取り組んでいくと良いでしょう。
個人的には「はりきゅう理論で確実に15点は取る!」という目標を持つだけで、合格ラインがぐっと近づきます。
また、勉強法としては過去問演習に加えて、図解入りの参考書でビジュアルから覚えるのがおすすめ。
たとえば、鍼尖の形状や艾の燃焼温度などは、写真やイラストを使って覚えると記憶に残りやすいです。
ぜひ「はりきゅう理論」は合格への“おいしい得点源”として、楽しみながら学習していってくださいね。
東洋医学臨床論
東洋医学臨床論は、鍼灸師国家試験の中でもボリュームが大きく、例年24問前後が出題されます。
出題数が多いということは、しっかり対策できれば得点源になり、逆にここを疎かにすると合格が遠のいてしまうということでもあります。
この科目は、名前の通り「東洋医学」の臨床的な応用が問われる分野です。
しかし、実際に出題される問題は純粋な東洋医学の知識だけでは解けません。
体質・証(しょう)の見立て、脈状・舌の状態の判別、経穴の選び方など、東洋的な診断や施術のロジックを理解していることが前提となります。
さらに言えば、西洋医学的な知識も併せて必要になります。
たとえば、糖尿病・高血圧・肝機能障害といった現代病が出題のテーマになることが多く、その病態を西洋医学的に理解した上で、「東洋医学的にみた場合どのように分類するか?」と問われるのです。
つまり、東洋医学臨床論は“すべての教科の集大成”とも言える位置づけです。
解剖学や生理学、病理学の知識をベースにしたうえで、東洋医学独特の視点で再解釈し、臨床につなげる力が求められます。
「肝虚」「脾虚」「陰虚」「気滞」などの弁証概念を理解するには、それぞれの臓腑の役割を把握している必要があります。
そして、その状態を表す舌診・脈診・腹診などを組み合わせて、適切な証を立てる問題が多いです。
また、証に対して適切な経絡・経穴を選べるかも重要です。
たとえば「肝血虚証」と診断されたら、肝経・脾経・腎経をどう活用するか?補法か瀉法か?など、施術の組み立てまで問われることがあります。
一方で、現代医療における治療とのバランスも問われるようになってきており、患者背景(高齢・妊娠・糖尿病など)を考慮した禁忌や注意事項に関する設問も見受けられます。
たとえば「胃腸が弱く疲れやすい」「むくみがある」「めまいがある」などの症状から弁証を導くような問題もあります。
このように、東洋医学臨床論は他の教科と独立して勉強するのではなく、「今まで学んだことをどう臨床で応用するか?」という視点で取り組むと、理解が深まりやすいです。
逆に、各教科の基礎が不十分なまま臨むと、問題文の読解だけでもつまずいてしまう可能性があります。
Kagayaのおすすめとしては、まず解剖・生理・病理の西洋医学系の基礎を固めてから、この臨床論に進むこと。
順番を間違えると「何を聞かれているか分からない…」という状態になります。
また、問題文が長くなりがちなので、読解力とスピードも必要です。
過去問や模試に取り組む際は、問題を読む→証を見立てる→施術方針を立てるという流れを意識しながら練習しましょう。
難易度が高い分、ここで得点できるようになると国家試験全体の得点力がグッと底上げされます。
「全部を完璧に覚えよう」とせず、まずは代表的な証と症状の組み合わせ、代表的な経穴と施術法から押さえていくと、確実にステップアップできます。
まさに「臨床のセンスを問う科目」。
合格後に鍼灸師として即戦力となるための準備が、この科目に詰まっていると感じます。
医学概論・公衆衛生学・関係法規
「医学概論」「公衆衛生学」「関係法規」の3科目は、いずれも暗記中心の科目であり、比較的得点しやすい“落としたくないエリア”です。
出題数も合わせて20問程度あり、確実に合格ラインに近づくためには、ここでしっかり点を稼いでおきたいところです。
まず「医学概論」は、広い意味での医療全般の基礎知識が問われます。
医療倫理、インフォームド・コンセント、チーム医療、医療の質の向上、現代の医療制度などがテーマになりますが、国家試験では年によって出題の傾向に幅があります。
Kagayaの実感としては、授業で深く触れなかったような時事的なキーワードも出題される印象です。
たとえば、第32回では「SDGs(持続可能な開発目標)」が登場しました。
これにはびっくりした人も多かったようですね。
このように、医学概論は「新しい話題を入れてくる科目」でもありますが、満点を取らせるつもりがないのも事実。
みんなが解けない問題は“落としていい問題”と割り切ってOKです。
確実に取れる問題で点を積み上げましょう。
次に「公衆衛生学」。
こちらは予防医学の視点からの出題が多く、一次予防・二次予防・三次予防の分類や、健康指標(有病率、罹患率、死亡率など)、栄養・生活習慣病、環境衛生(上水道・大気汚染など)といった内容が中心です。
知識の整理さえできていれば、設問はストレートなものが多く、過去問で傾向を押さえれば十分対応できます。
とくに「水道水の水質基準で“検出されてはならない”とされているのは?」→「大腸菌」など、いわゆる“サービス問題”も存在します。
最後に「関係法規」。
これは開業予定の方には絶対におさえておきたい科目です。
「あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)」や「医師法」「保健師助産師看護師法」などが出題対象で、条文の暗記が得点に直結します。
たとえば、「はり師・きゅう師が業務を開始できるのはいつか?」という問題の正答は「名簿に登録されたとき」です。
このように、出題パターンが決まっているものが多く、過去問を繰り返せば安定して得点できます。
また、広告の規制(〇〇療法、〇〇効果と謳って良いか)や、施術所開設の要件(届出、構造設備基準など)なども重要。
将来的に自分の鍼灸院を持ちたい方には実務的な意味でも理解しておいて損はありません。
この3科目に共通しているのは、「覚えれば得点できる」というシンプルな構造です。
経穴のように位置や作用を3つ4つ覚えなくてはいけない、という苦しさはありません。
そのため、勉強をスタートする初期段階や、試験直前の詰め込み期にも非常に取り組みやすいです。
得意分野として確実に仕上げておくと、全体の得点を安定させる“土台”になります。
「暗記科目ってつまらない…」と思う人もいるかもしれませんが、逆にいえば「努力がそのまま結果になる」分野。
ゲーム感覚でスピード勝負を楽しんで、取りこぼしのないよう仕上げていきましょう。
解剖生理・病理学
解剖生理学と病理学は、すべての医療系国家試験の土台となる非常に重要な科目です。
鍼灸師国家試験においても例外ではなく、ここをしっかり押さえておくことで、他の科目の理解もぐっと深まります。
よく「看護師だから解剖生理は得意でしょ?」と言われますが、実際にはそう単純な話ではありません。
看護師国家試験では広く浅く出題されますが、鍼灸師国家試験ではより臨床に直結する部位――特に筋骨格系・神経系にフォーカスされることが多く、かなり専門的な知識が求められます。
たとえば、骨格筋の起始・停止、支配神経、反射機構、運動神経・感覚神経の走行などは、鍼灸師にとって施術部位の判断や経穴の選択にも直結する知識です。
また、触圧覚・温痛覚の経路や、Aβ・C線維の特徴といった神経生理学的内容は、はり理論や臨床医学とも深く関わってきます。
つまり、解剖生理・病理は“点が取れる”だけでなく、“他の教科でも使いまわせる”という点で、勉強コスパが非常に高い科目なのです。
逆に、消化器系や呼吸器系、内分泌系などの出題は範囲が広く、毎年どこが出るか読めない部分でもあります。
このあたりは深追いせず、過去問で頻出の病態や器官を中心に最低限押さえるくらいが現実的でしょう。
病理学についても同様です。
すべての疾患を網羅する必要はなく、炎症・壊死・浮腫・腫瘍といった基本的な病変の分類、免疫の基礎、疾患の進行プロセス(急性→慢性)などの理解を軸にすれば、得点しやすくなります。
Kagaya的には、ここをしっかり理解していないと、他の教科が“上滑り”になってしまうと感じます。
まるで、算数の「引き算」が分からないのに「割り算」をやろうとしているようなものです。
基礎が曖昧なまま臨床医学や東洋医学臨床論を解こうとしても、ピンと来ないのは当然なのです。
特に、東洋医学臨床論の弁証問題で出てくる「血虚」「陰虚」「痰湿」などの症状は、病理学的な視点から考えれば整理しやすくなりますし、臨床医学各論で出てくる糖尿病・パーキンソン病・バセドウ病などの理解にも直結します。
国家試験対策としては、まず「正常な構造と機能(解剖・生理)」→「異常や病態の変化(病理)」→「疾患の成立(臨床医学)」という流れを意識して、ストーリーで理解することがポイントです。
図やイラストを活用しながら部位や経路をイメージできるようにすると、記憶の定着率もぐっと上がります。
とくに筋肉や神経は、語呂合わせ+イラストで覚えるのが効果的です。
試験対策だけでなく、将来的な臨床での活用という点でも、解剖生理・病理の知識は絶対に裏切りません。
勉強に苦戦している人こそ、まずこの“人体の基礎”から着実に押さえていきましょう。
臨床医学各論
臨床医学各論は、鍼灸師国家試験においては20問前後出題される重要科目であり、出題の傾向もはっきりしています。
よく出る疾患としては、糖尿病・急性肝炎・関節リウマチ・肺炎・バセドウ病・気胸・パーキンソン病・椎間板ヘルニア・白血病・肝硬変などが挙げられます。
特に、筋骨格系・神経系・内分泌系の疾患は出題頻度が高く、これは鍼灸治療の適応症と重なる部分が多いこととも関係しています。
たとえば、椎間板ヘルニアやパーキンソン病など、鍼灸の現場でよく相談される疾患が試験でも問われるのです。
臨床医学各論を勉強する際には、単に病名を覚えるのではなく、以下の3ステップで整理すると理解が深まりやすくなります。
- ① 病態生理:どの臓器や系統に異常が起きて、何が原因で発症するのか?
- ② 主な症状:どのような症状が現れるか?東洋医学との共通点は?
- ③ 治療法:現代医学での治療法と、鍼灸が対応できる症状や効果は?
たとえば、糖尿病であれば「インスリン分泌低下や抵抗性によって高血糖になる」という病態生理を理解し、症状としては「多飲・多尿・倦怠感・易感染性」などがあり、合併症として網膜症・神経障害・腎症があることを押さえておく必要があります。
また、パーキンソン病であれば、「黒質のドーパミン神経の変性」が原因で、振戦・筋強剛・寡動・姿勢反射障害という四大徴候があり、進行性の神経変性疾患であるということも重要な知識です。
このように、臨床医学各論は単独の知識だけでなく、「解剖生理」「病理学」「公衆衛生学」などと連動させて理解することが、記憶定着と得点の両面で有利になります。
さらに、試験では疾患の特徴だけでなく「禁忌事項」や「医師への紹介基準」が問われることもあります。
たとえば「発熱を伴う関節リウマチの急性悪化」などは、安易に施術を行うことで悪化させてしまうリスクがあるため、実務的な知識としても非常に重要です。
Kagaya的おすすめ勉強法としては、「出題頻度が高い疾患TOP10」をまず固めること。
そこから病態→症状→治療の流れを疾患ごとに整理し、関連する東洋医学的アプローチ(肝腎虚、痰湿、気虚など)を併せて学ぶと、他科目とのつながりも自然に見えてきます。
特に、臨床現場で頻繁に遭遇する疾患は出題されやすいため、「現場感覚」で勉強するのもひとつのコツです。
鍼灸師は医師ではないため、診断はできませんが、見逃してはいけない徴候・紹介が必要なケースは国家試験でもよく問われます。
臨床医学各論を極めることは、単なる試験対策を超えて、将来の安全な施術や患者さんとの信頼関係にも大きくつながる部分です。
自信を持って現場に立てるように、最低限の疾患知識はこの科目でしっかりと身につけておきましょう。
🌟勉強の流れ
鍼灸師国家試験を効率よく突破するためには、「何を」「どの順番で」学ぶかを明確にしておくことが非常に大切です。
バラバラに暗記するのではなく、知識を“流れ”として整理することで、理解力と記憶定着が一気に高まります。
人の体は、「正常な構造と機能」から始まり、「異常=病気が起こる過程」を理解し、最後に「どのように治療・予防していくか」という3段階の視点で学んでいくと、すべての教科がつながって見えてきます。
たとえば、次のような流れで学習するのがおすすめです:
- 一次予防(病気になる前の予防):
「医学概論」「公衆衛生学」「関係法規」
→健康維持・生活習慣・感染予防・制度の理解を通じて病気を防ぐ。 - 二次予防(早期発見・診断):
「解剖学」「生理学」「病理学」「臨床医学総論・各論」
→体の構造・機能がどこでどう壊れるのか、異常のサインを読み取る。 - 三次予防(治療・再発防止・リハビリ):
「東洋医学概論」「経絡経穴概論」「東洋医学臨床論」「リハビリテーション医学」
→治療介入により、患者の生活の質を向上させ、社会復帰を目指す。
この流れの中で、最も基礎となるのが「はり理論」「きゅう理論」です。
まさに看護師国家試験における“必修問題”のような立ち位置で、正答できて当たり前とされる問題が多く出題されます。
また、鍼灸師国家試験では「パーキンソン病」や「関節リウマチ」の問題が非常によく出題されます。
これらは神経系・自己免疫疾患の代表であり、病態・症状・治療法を西洋・東洋の両視点で理解しておく必要があります。
パーキンソン病は黒質のドーパミン神経が障害される指定難病であり、筋固縮・振戦・姿勢反射障害などが主症状です。
関節リウマチは慢性の炎症性疾患で、関節の変形や朝のこわばりなどが特徴。
これらの疾患に対して、鍼灸師が直接的に「治す」ことは難しくても、症状緩和やQOL改善へのアプローチは可能です。
ただし、国家試験では「訪問看護が使いたい放題」や「医療費助成がある」といった制度的な内容は問われません。
出題されるのは、あくまで疾患の病態・症状・東洋医学的解釈・施術の可否などです。
つまり、「試験に出る情報」と「臨床で必要な情報」は必ずしも一致しないということ。
重要なのは、“今必要な知識”を見極めて、効率的に覚えることです。
その意味で、過去問演習は最強の勉強法。
出題傾向をつかむだけでなく、自分の苦手分野を可視化するためにも活用すべきです。
出題パターンを分析し、統計的に頻出テーマを押さえるだけでも、得点力は大きく向上します。
Kagayaのおすすめは、過去問→間違えた箇所を教科書で再確認→要点を自分の言葉でまとめる、というサイクル学習です。
「満点を目指す」のではなく、「確実に60%を超える」ことが合格の条件。
だからこそ、全科目を一律に勉強するより、「取れる問題を落とさない」ことを意識して、戦略的に学習を進めましょう。
🌟問題の解き方テクニック
国家試験には、難易度に応じたランク分けがされているといわれています。
単純な暗記問題から、応用力が問われる問題まで、バランスよく出題されているのが特徴です。
ただし、数学のように「解き方」や「途中経過」を問われることはありません。
正解を選ぶことが求められます。
つまり、どんな解き方をしても、正解を導き出せればそれでOKです。
たとえば「4×3=12」としても、「4+4+4=12」としても、答えが12であれば正解です。
過去32回分の国家試験問題を丸暗記して、60%以上を目指すという作戦もあるかもしれませんが、それでは応用問題に対応できなくなるリスクもあります。
問題を解くテクニックを知っておくことで、時間配分や正答率がぐっと上がります。
たとえば、「確実に正解できる問題」「迷うけど選択肢を2つに絞れる問題」「カンに頼るしかない問題」といった見極めをして、優先順位をつけるのもテクニックのひとつです。
高校受験に向けた中学生が塾で「問題の解き方」を学ぶように、国家試験でも「知識」だけでなく「戦術」や「解法スキル」が合否を左右します。
そして、この手のノウハウは学校ではあまり教えてもらえません。。
だからこそ、自分に合った勉強スタイルとテクニックを見つけて、戦略的に試験に臨むことが大切です。
🌟選択肢がなくても答えられる問題
このタイプの問題は、いわゆる暗記問題です。
問題文を読んだ瞬間に答えが分かる、または選択肢がなくても答えられる問題が多く、確実に得点源となります。
代表的な出題は「医療概論」「公衆衛生学」「関係法規」などの基礎教科に見られます。
考察や応用が求められない分、覚えていれば一瞬で解けるのが特徴です。
以下に、実際によく出題されるパターンの例題を紹介します。
例題①
介護保険制度の保険者はどれか。
市町村
例題②
上水道の水質基準で「検出されないこと」と定められているのはどれか。
大腸菌
例題③
はり師、きゅう師として業務を開始できるのはいつか。
名簿に登録されたとき
このように、選択肢を見なくても即答できる問題は確実に点を取りたいところです。
特に、否定形「〜でないのはどれか?」というタイプでも、正解が分かっていれば消去法で対応できます。
国家試験は60%以上の得点で合格できる試験です。こ
のような問題を確実に正解することで、全体の得点率を底上げすることができます。
絶対に落としたくない問題群と意識して、効率よく暗記していきましょう。
🌟問題文がなくても答えられる問題
国家試験では、選択肢の内容だけで問題の意図を推測できる場合があります。
これは過去問対策を進めていく中で、「あ、このパターンはあの問題だな」と感覚的にわかるようになる瞬間です。
以下のように、選択肢だけでも正誤の判断がつくことがあります。
例① 肺結核に関する選択肢
- 結核患者は届け出る必要はない。
- → 届け出は必要
- 咳が4週間以上持続している場合は肺結核を考慮する。
- → 正しい
- 抗結核薬は1剤を投与する。
- → 多剤療法(3~4剤)
- 非結核性抗酸菌症も結核と同様に隔離する必要がある。
- → 隔離の必要はない
問題文がなくても、「正しいのはどれか?」という問いが想定できます。本来の問題文は、
「肺抗酸菌症について正しいのはどれか。」です。
例② 自然気胸に関する選択肢
- 女性に多い。
- → 男性に多い
- 肥満は危険因子である。
- → ヤセ型が危険因子
- ブラ・ブレブの破裂で起こることが多い。
- → 正しい
- 胸部エックス線検査での診断は困難である。
- → 診断に用いられる
この場合の問題文は、
「自然気胸について正しいのはどれか。」です。
ヒントとなるキーワード(例:「気胸」)を思い出せれば、選択肢の中に必ず1つある正答を見つけることができます。
例③ 尿の症状に関する選択肢
- 排尿痛 → 炎症
- 尿混濁 → 炎症
- 血尿 → 炎症
- 糖尿 → 尿に糖が出る
これらの選択肢から推測される本来の問題文は、
「膀胱炎の症状で適切でないのはどれか。」です。
糖尿は炎症ではなく代謝異常であり、中間外れとなります。
このように、選択肢の内容と知識を照合して、問題文がなくても正解にたどり着ける問題は多く存在します。
過去問演習を重ねる中で、「このタイプの問題はあのテーマだな」と感覚的に掴めるようになると、合格ラインに一気に近づきます。
🌟応用問題の読み解き方
国家試験では、明確な知識だけで解ける「暗記問題」ばかりではありません。
文章量が多く、一見すると難しく感じる応用問題も出題されます。
このような問題は、一文一文に隠れたヒントが散りばめられており、そこから判断材料を拾い集めて答えを導き出す必要があります。
しかし、知識が曖昧なままだと読解に時間がかかり、「結局どれが正解か分からない…」という状態に陥ってしまいます。
ですので、応用問題は「飛ばす勇気」も必要です。
解ける問題から優先し、あとでじっくり考えるのが国家試験での戦略の一つです。
ここでは、東洋医学の応用問題を例に、「どこに注目し、どう読み解くか?」を紹介します。
例① 病証から発展する症状を選ぶ問題
次の文で示す病証が進行した場合、みられやすい症状はどれか。
「39歳の女性。主訴は眼精疲労。長時間のデスクワークで目がかすむ。日頃から眠りが浅く、爪の血色が悪い。舌苔は薄白、脈は細数を帯びてきた。」
- 消渴
- 盗汗
- 厭食
- 諧語
まず「目がかすむ」「爪の血色が悪い」から肝血虚を想定できます。
しかし、選択肢には「肝血虚」という病証はなく、代わりに「盗汗」があります。
注目すべきは「脈が細数」=陰虚のサインであること。
陰虚では「ほてり」「盗汗(寝汗)」「寝つきが悪い」などが出るため、最も適切なのは「盗汗」になります。
このように、病証の読み解きから一歩踏み込んで、証の進展・派生症状まで考えるのが応用問題のポイントです。
例② 治療方針の選択問題
次の文で示す病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。
「49歳の男性。主訴は食欲不振。空腹感はあるが多くは食べられない。胃脘部に我慢できる程度のはっきりしない痛みがある。舌質は紅を認める。」
- 陰液を補う。
- 陽気を補う。
- 気機を除く。
- 湿熱を除く。
空腹感があるのに食べられない、舌質が紅…これは「胃陰虚」と考えられます。
「舌質が紅」→陰液不足による虚熱が示唆されます。
また、胃脘部の「我慢できる痛み」は虚証を示すサイン。
選択肢で「湿熱」は胃の特性「喜潤悪燥」に照らして考えにくく、「陰液を補う」が最も適切な方針です。
応用問題ではこのように、舌・脈・症状のキーワードを根拠に、選択肢を絞っていくことが重要です。
暗記だけでは乗り越えられない問題もありますが、日々の臨床や勉強で「なぜそうなるのか?」という視点をもつことで、読み解き力は確実に伸びます。
🌟まとめ:国家試験を“戦略的”に乗り切る
国家試験対策に悩む皆さんへ。
まず大前提として知っておいてほしいのは、国家試験は合格ラインを超えればOKという試験だということです。
点数で順位が決まるものではなく、60%以上の得点(=102点/170問)で合格ラインを満たせばいいのです。
つまり、単純計算で68問は間違えても合格できる。
これはかなり心が軽くなる考え方ではないでしょうか?
もちろん、すべての内容を完璧に覚えたいという気持ちは尊いです。
でも現実的には、限られた時間の中で「出るところ」「点が取れるところ」から攻略する戦略が必要なのです。
たとえば、東洋医学の「361穴すべてを暗記しなければ合格できない」なんて思い込んでいませんか?
実際には、毎年出題されやすい経穴やパターン、頻出テーマがあります。
出題傾向に基づいて学習範囲を絞り込むことも、立派な受験技術です。
そして何より大切なのは、「問題を解く力」=解法のスキルです。
暗記の量に頼らずとも、文章からヒントを拾い、選択肢を絞ることで解ける問題はたくさんあります。
学校では「満遍なく勉強する」ことが求められるかもしれませんが、国家試験という特殊なゴールに対しては、「割り切る」「優先順位をつける」「得点源に集中する」ことが求められます。
💡戦略的学習のポイント
- 60%以上取れば合格!すべて覚えなくてOK
- 過去問分析で「出る問題」「出ない問題」を分ける
- 暗記よりも「読み解く力」で得点アップ
- 苦手分野より得意分野を強化する方が得点効率が高い
- 満点を目指す必要なし。割り切りが大事!
最後に、少しだけKagayaの想いをシェアさせてください。
Kagayaは鍼灸師として、実際の臨床に立ったときに本当に必要な知識は何か?を日々考えています。
国家試験の点数が高くても、難病や慢性疾患に対応できるとは限りません。
むしろ、臨床での判断力、患者さんの声を聞く力、情報を調べる習慣、そして何より「この人を楽にしてあげたい」と思える心が大切なのです。
国家試験対策は通過点にすぎません。
合格後にどんな鍼灸師・医療人になりたいのか、そのビジョンを忘れずに学び続けてくださいね。
この記事があなたの学習のヒントになれば嬉しいです。応援しています!