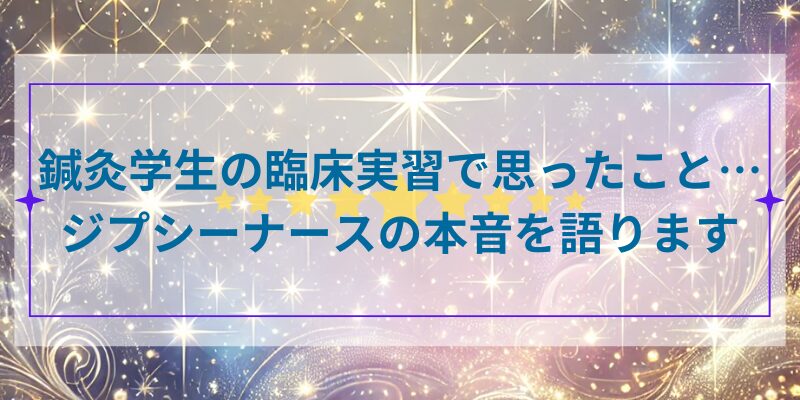🌟看護実習と比べて感じた鍼灸実習の「ゆるさ」
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
気づけば鍼灸学生でいられるのも、あと数ヶ月という時期になってきました。
そろそろ国家試験の勉強に本腰を入れないと…と焦りつつも、なぜか現実逃避のようにブログを書いたり、家のDIYに没頭したりしています。
看護学生のときは、実は国家試験勉強すらまともにやらなかったので、今回も似たような展開になりそうな予感です。
そんな今のKagayaが強く感じているのは、「鍼灸の臨床実習って、本当にこれでいいのかな?」という疑問です。
看護学生時代の臨床実習を思い出すと、あれは本当に過酷でした。
まるで戦場のような日々。
1クールごとに膨大な実習記録を手書きで提出し、看護計画を立て、指導教員に細かくチェックされ、現場の看護師からの洗礼も毎日のように浴びました。
寝不足が続き、記録の誤りを見つけられては怒られることの繰り返しでした。
それに比べると、鍼灸学生の臨床実習は…正直、かなり「ゆるい」と感じています。
もちろん、学校によって違うとは思いますが、少なくともKagayaの通う鍼灸学校では、看護実習に比べて精神的にも肉体的にもラクです。
睡眠時間を確保できていることが何よりの証拠でしょう。
しかし、それは喜ばしいことばかりではありません。
「こんなにラクでいいの?」「本当に現場でやっていけるの?」という不安も同時に湧いてくるのです。
実際、「鍼灸学生 臨床実習 体験記」といったキーワードでネット検索しても、あまり情報がヒットしません。
看護学生の実習体験記は山ほど出てくるのに…。
どんな内容だったとか、どんな患者さんに出会ったとか、実習で苦労したことや学んだこと、記録の書き方まで、看護系ブログには情報が豊富にあります。
一方、鍼灸学生のブログは本当に少なく、見つけても更新が途切れていたり、実習内容が具体的に書かれていなかったり。
もしかしたら、あまりにラクすぎて書くネタにもならないのかもしれません。
Kagaya自身も、教育実習や看護実習を経験してきた中で、最もツラかったのは「記録」でした。
睡眠時間を削って仕上げた記録を朝イチで提出し、直されては再提出。
指導教員のチェックにおびえる日々。
その点、鍼灸の臨床実習にはそうした記録提出がほとんどないので、本当に気がラクなんです。
だからこそ、週6日働きながら学校にも通えているんですよね。
でも…ここでふと立ち止まって考えてしまうのです。
「このままで大丈夫なのかな?」と。
楽であることは確かに助かるけれど、それが将来の不安につながっているのも事実です。
実習の質や量がこの程度で、国家試験に合格してすぐに開業できる鍼灸師になれるのか? 自分自身の成長はどうなのか?
そんなモヤモヤを抱えながら、臨床実習について、今の本音を綴っていきたいと思います。
🌟臨床実習時間の短さについて
鍼灸の臨床実習は、基本的に学校が併設している鍼灸院で行われます。
Kagayaの通っている学校でも、臨床実習3・4としてそれぞれ23コマずつの実習が設けられています。1
回の実習は2コマ連続、つまり3時間かけて行うスタイルです。
この臨床実習では、学生が1人の患者さんに対して問診を取り、治療方針を考え、実際に鍼や灸での施術を行っていきます。
2年生まではほぼ見学中心の実習だったのに対し、3年生ではようやく自分で手を動かす機会が与えられるのです。
しかし、ここで問題なのは「実際に施術する機会が少ない」ということ。
実習は5~6人のグループ制で行われるため、1回の実習で自分がメインとなる機会は限られます。
正味11日間の実習の中で、自分がメインで治療を担当できるのは、なんと2回程度しかありません。
つまり、1年間の実習を通して実際に患者さんに鍼灸治療をするのは4回程度。
これは、どう考えても臨床経験としては圧倒的に少ないと感じています。
もちろん、他の学生の治療を見学したり、ディスカッションに参加したりすることで学びはあります。
しかし、「自分の手で経験を積む」という観点から見ると、あまりにも少なすぎるのではないでしょうか。
たとえば、教育実習では1ヶ月間、小学校や中学校に毎日通い、朝から夕方まで授業の準備・指導・反省を繰り返します。
教員としての技術や姿勢を、現場のリアルな環境の中でじっくり学ぶことができます。
看護実習ではもっと顕著です。
1クールあたり3週間程度の実習を、内科・外科・精神科など複数領域で繰り返し行い、患者1人を受け持ち、その人の生活や病態に寄り添いながら看護を提供していきます。
そうした実習に比べると、鍼灸の臨床実習は本当に短く、回数も少なく、「これで本当に現場でやっていけるのかな?」という不安が正直ぬぐえません。
短時間で1回限りの患者対応という形式では、経験の蓄積が難しいからです。
もちろん、実習以外にも、授業で基礎理論や経穴の取り方、触診の練習を積んでいます。
しかし、机上の学習と、実際の患者さんを前にした施術では、緊張感も判断力も全く違います。
「場数を踏む」という点では、現場に出てナンボの世界なのだと思い知らされます。
実習が少ないからこそ、「卒業後、どうやって経験を積むのか」という課題にも早く向き合う必要があります。
開業していくにも、自信と裏打ちされた経験がなければ、患者さんに安心してもらうことはできません。
そのため、学生のうちから、外部の研修や見学、ボランティア、アルバイトなど、できる限り「実践の場」を探していくことが重要になってくるとKagayaは感じています。
短い臨床実習時間だからこそ、限られた中でどれだけ自分で考えて動けるかが問われる。
そんなふうに前向きに捉えることもできますが、「もう少し実践の機会を増やしてほしいな…」というのが本音でもあります。
🌟臨床実習で学べること・学べないこと
鍼灸の臨床実習は、5~6人のグループに分かれて行われます。
実習では、その日ごとに「メイン」となる学生が1名選ばれ、その学生が実際に患者さん1人を担当し、問診から施術までを行います。
その他のメンバーは見学やサポートという立ち位置です。
実習当日まで、どんな患者さんが来られるのか、どんな主訴があるのかはわかりません。
そのため、準備していけるのはせいぜい「よくある症状(首・肩・腰など)」に対する基礎的な治療法と、経絡経穴の知識、そして徒手検査法程度です。
看護実習では、あらかじめ担当患者の情報(疾患、バイタル、ADLなど)を得て、前日から看護計画を立てたり文献を読んだりして事前学習を重ねます。
しかし、鍼灸の実習ではそれができません。
つまり、「ぶっつけ本番」で対応する力が求められます。
問診しながら、短時間で症状の本質を見抜き、治療方針を立て、鍼の選穴や刺鍼の強さ・方向まで即決しなくてはなりません。
このスピード感と判断力は、ある意味で実践的とも言えますが、初心者の学生にとっては不安も大きく、迷いながらの施術になりがちです。
また、患者さんは実習のたびに異なるため、「継続的に観察・治療をして経過をみる」という学びはほとんどありません。
「この治療法でよかったのか?」「他にできることはなかったか?」と思っても、次回その患者さんに会えるとは限らないのです。
これでは、フィードバックを次に活かす場面も限られ、改善のサイクルがまわしにくいというのが実情です。
Kagayaはこれを「臨床の継続性がない」と感じています。
これは学生教育としては大きな課題かもしれません。
とはいえ、現実の鍼灸院も同様に「一期一会」のケースが多いです。
とくに自由診療である鍼灸院では、患者さんが1回限りで来院をやめてしまうことも珍しくありません。
そのため、1回の施術で「次も来よう」と思ってもらえる結果や体験を提供する必要があります。
こうした「1回の勝負」にかける姿勢を学べるのは、実は鍼灸実習ならではの貴重な学びかもしれません。
しかし一方で、Kagayaが感じてしまうのは「なぜその治療を選んだのか?」という根拠があまり問われないことです。
看護実習では、看護ケアの順序や理由を逐一指導者に突っ込まれます。
「なぜ今、陰部洗浄ではなく清拭なのか?」「この薬の作用を理解しているか?」など、判断の背景を明確に説明することが求められました。
しかし、鍼灸の実習では「なぜそのツボを選んだのか?」「なぜそのタイミングでお灸をするのか?」といった問いがあまり投げかけられません。
学生同士で見ていて、「今それやる?」と突っ込みたくなる場面もありますが、空気を読んで口をつぐんでしまいます。
たとえば、看護実習なら指導者がその場で即、修正指導をしてくれますが、鍼灸実習は「失敗も経験」として見守るスタンスのようです。
それが良いか悪いかは別として、「本当に学びになっているのか?」と疑問に思うこともあります。
最終的には、「患者さんが満足して帰ったかどうか」が評価基準のようになっており、治療というよりはリラクゼーション寄りのサービスになってしまっているような印象も受けます。
患者さんの「気持ちよかった」「スッキリした」といった主観的評価は大切ですが、やはりもう一歩踏み込んで「なぜそう感じたのか」「どうすればより効果が続くのか」といった考察が求められてもよいのでは…と、元・看護学生のKagayaは思ってしまいます。
🌟経験値が足りない
鍼灸学生として臨床実習を経験してきて、Kagayaが今もっとも強く感じているのが「経験値の不足」です。
これは単に「場数が少ない」という話にとどまりません。
鍼灸という手技療法において、身体に触れる回数や刺鍼の経験数は、まさに技術の根幹を支える要素です。
臨床実習3・4を合わせて、Kagayaが触れることのできた患者さんの人数は延べ23人ほど。
実際に鍼を刺したり、お灸を据えたりといった施術をメインで担当したのは、そのうちたった4回程度です。
もちろん、それ以外にも質問をしたり、見学をしたり、手技の補助に入ったりはしましたが、「自分の手で一連の治療を行った」という経験は圧倒的に少ないのが現実です。
メインで施術する機会が少ないということは、刺鍼の深さや角度、皮膚の反応、患者さんの表情の変化など、「実践でしか得られない感覚」が養われにくいということでもあります。
しかも、患者さんの症状は千差万別で、一度きりの治療機会では再現性も持てません。
「前回と比べてどうか」といった経過観察もなく、その場限りの一発勝負。
改善が見られても、「たまたま」だったのか、それとも「治療が功を奏した」のか、検証することが難しいのです。
Kagayaは看護師としての実習も経験しているので、なおさらギャップを感じてしまいます。
看護実習では、患者さんの全体像をつかみ、生活背景や病態、精神面にまで配慮した「看護計画」を立案し、数日間かけて観察とケアを繰り返します。
経験が積み上がっていく実感がありました。
それに比べて鍼灸実習は、あくまでも「点」でしかありません。
「線」にならないのです。
これは制度上やむを得ないことかもしれませんが、実習のたびに「もう少し触れていたかった」「あのツボも使ってみたかった」という未練が残ります。
おそらく、鍼灸学校というのは、あくまでも国家試験に合格するための「知識教育機関」なのでしょう。
実技の精度は、卒業後に各自で研鑽しなさいというスタンス。
これ自体に異を唱えるわけではありませんが、やはり「触れる」経験が足りなすぎるというのは課題です。
正直、「だったら看護の実習も、もう少しラクにしてくれてもよかったんじゃない?」と思ってしまうほど、鍼灸実習との温度差があります。
看護実習では、担当教員が記録指導に朝から晩まで張り付き、学生の細かい記録ミスにも目を光らせ、指導する側も相当な負担です。
でも、それだけ学生に「責任」を持たせてくれていたということでもあります。
責任を持って患者を受け持ち、記録に責任を持ち、発言に責任を持つ。
それが、臨床で働くプロとしての土台を作ってくれました。
鍼灸学校も、もちろん国家資格者を育てる場です。
卒業したらすぐに「開業権」まである。
であれば、せめてもう少しだけでも、「触る・感じる・考える」経験が積めるような実習構成があってもいいのではないかと、思わずにはいられません。
知識は座学で学べても、感覚は現場でしか育たない。
これは、看護も鍼灸も変わらない真実だとKagayaは実感しています。
🌟正常と異常がわからない
看護学生の実習では、「正常と異常の違いがわかるようになること」がよく目標に掲げられます。
たとえばバイタルサインの変化、皮膚の状態、浮腫の有無、排泄の異常など、数値や視覚的な変化から異常を見極める訓練がなされます。
高齢者の浮腫であれば、足首を押せば深い圧痕が数十秒残るような状態で、これはもう一目で「異常」と判断できます。
実際、Kagayaも看護実習ではこういった明らかな所見にはすぐに気づけるようになっていきました。
しかし、グレーゾーンのような症状、たとえば「靴下の跡が少し残っている」程度の浮腫はどうでしょう?
医師に相談しても「そんなの正常範囲だよ」と軽く流され、看護師もいちいち記録に残すようなものではないという認識が一般的です。
でも、エステの世界ではまったく話が違います。
「むくんでいますね~」と丁寧に対応され、マッサージやリンパドレナージュの施術へとつながっていきます。
「美」や「快適さ」を追求する場面では、医学的な「異常」ではなくても、十分に「ケアすべき状態」とされるのです。
このあたりが、鍼灸の面白さでもあり、難しさでもあるところです。
鍼灸師は、数値化された異常だけではなく、数ミリ単位の皮膚のざらつきや張り、色の変化、触診で感じるわずかな熱感や圧痛などを「異常」ととらえます。
靴下の跡ひとつとっても、「水分代謝の滞り」や「気血の巡りの問題」としてアセスメントし、治療の対象になります。
ただし、ここで大きな壁にぶつかります。
それは、「正常な状態」がわからない、ということ。
臨床実習で出会う患者さんは、何かしらの不調を訴えて鍼灸院に来られている方です。
つまり、常に「異常な状態」の身体に触れているわけで、どこまでが正常なのか、基準がわからないのです。
Kagaya自身、看護師として働いていたときは、検査データや観察所見が「正常範囲」とされていても、患者本人が「いつもと違う」と感じていれば、それは異常ととらえて対応していました。
鍼灸も似たように、本人の自覚や体感を大切にする分野だと感じています。
でも、やはり身体に触れる以上、「標準的な状態」を自分の中に持っていないと比較ができません。
たとえば、「この皮膚の温かさはどうか?」「この張り具合はどうか?」と考えたときに、「これは普通だよね」と判断できるようになるには、正常な身体にもたくさん触れていく必要があります。
授業では「ここに圧痛があります」「ここが冷えています」と言われても、「じゃあ、圧痛のない状態ってどう感じるの?」「温かい皮膚の基準って?」という感覚的な部分は、結局「見て感じて学べ」という現場任せになっています。
こうした感覚は、教科書では身につかないもので、まさに経験と場数の中で育っていくものです。
けれども、今の鍼灸実習では触れる人数も限られており、ましてや正常な身体に触れる機会はほぼゼロ。
だからこそ、卒業後も積極的にボディワークや他流派の勉強会などで経験を積まないと、本当の意味で「正常と異常がわかる鍼灸師」にはなれないのだと思います。
「ここにコリがある」ではなく、「これが正常です」と言える感覚を、少しずつでも自分の中に育てていきたい。
そう強く感じています。
🌟まとめ:ジプシーナースKagayaの本音
Kagayaの通っている鍼灸学校では、臨床実習は以下のように構成されています。
- 臨床実習1・2(2年生):教員が主導するほぼ見学型の実習
- 臨床実習3・4(3年生):学生が主体となる体験型の実習
- 各フェーズ23コマずつ(合計46コマ)で構成
- 1グループ5~6人で1人の患者さんを担当
- 患者不在時は学生同士で模擬治療を実施
- 実習中にカンファレンスや振り返りの時間あり
こうして見ると、少なくとも「臨床に触れる機会が設けられている」という点では、ありがたいカリキュラムではあります。
国家試験合格がゴールである学校教育において、実技の時間が確保されているだけでも意味があるのかもしれません。
ただし、やはり「現場に出て使えるレベルの技術が身につくか?」という視点で見ると、実習時間や内容には物足りなさが残るのも事実です。
特にKagayaのように、看護師として実習や臨床経験があると、その差に戸惑いを覚えることもあります。
鍼灸師は、国家試験に合格すればすぐに「開業権」が与えられます。
これは非常に大きな権限であり、同時に大きな責任も伴います。
マッサージやカッサのように“気持ちいい”を提供するリラクゼーションとは異なり、鍼灸は身体に異物を入れたり、熱刺激を加えるという、ある意味「侵襲的」な施術です。
実際、施術者の腕によっては、身体に不調や痛みを残してしまうリスクもゼロではありません。
Kagayaは「身体が資本」です。
だからこそ、「信頼できる施術者」にしか身を委ねたくないと思っています。
世の中には、資格を持たずに堂々と「治せます」と言い切る無免許施術者もいます。
消費者として、誰に治療を任せるかを見極める力も求められる時代です。
国家資格があるからといって、それだけで信頼に足るとも限らない。
これは、施術者側も強く自覚しておくべきことです。
とはいえ、看護師の実習をどれだけ積んだとしても、いざ国家試験に合格したからといって、即戦力として働けるかといえば難しいもの。
結局のところ、「現場で学ぶ」姿勢が不可欠であり、資格はあくまでスタート地点にすぎません。
鍼灸師としても、国家試験に合格してからが本当の学びの始まり。
自分がやりたい治療法を見つけ、臨床で経験を積み、失敗から学び、少しずつ自信を積み重ねていくしかありません。
だからこそ、学生のうちに焦る必要はないとも言えます。
大切なのは、卒業後どんな鍼灸師になりたいかを明確に描いておくこと。
そして、その理想に向かって、少しずつでも前に進んでいくことなのだと思います。
Kagayaも、まだ模索中の身ではありますが、看護と鍼灸をつなぐ新しいスタイルを築けるよう、自分の道を一歩ずつ進んでいきたいと考えています。