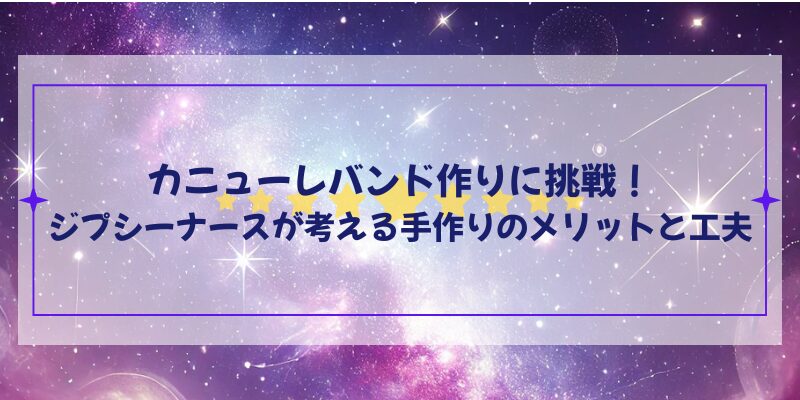🌟ジプシーナースが挑戦!カニューレバンドを手作りしてみた理由
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
このたび、長らく「ゴミ部屋」と化していた一室を、ようやく事務所兼作業スペースに生まれ変わらせることができました。
ミシン専用に折り畳み式テーブルも購入し、これまで諦めていた「手芸プロジェクト」に本格的に取り組める環境が整いました。
その第一弾が、カニューレバンドの手作りです。
実はこれまで、市販のカニューレバンドの「デザイン性のなさ」や「皮膚トラブルの多さ」に疑問を感じていました。
「何でこんなにダサいの?」とツッコミを入れたくなるようなものばかりで、特に成人用はほとんど選択肢がありません。
かわいさや快適性を大切にしたい気切の方々の声が、まったく反映されていない現状に、正直もどかしさを感じていました。
ちなみに、最初は「気切バンド」という呼び方をしていたのですが、正確には「カニューレ(=気管切開用の管)」を固定するバンドなので、“カニューレバンド”と表記するようにしました。
穴(=気切)にバンドをつけるわけではないので、医療者としての表現も大事にしたいところです。
そんな中、昔に購入して使わずにいた業務用ミシンを引っ張り出して試し縫いをしてみると、驚くほど快調に動きました。
5年ぶりとは思えない安定感。
やはり、業務用は違いますね。
いざ、作ってみよう!と思ったものの、一般的に病院で使用されているのは「真田紐(さなだひも)」でカニューレを固定するタイプが多く、意外とその存在が知られていません。
訪問先で「真田紐取ってきて~」と言っても伝わらなかったことが何度かあります。
あの真田幸村の家紋にも使われた伝統的な強度のある紐なのに…(笑)
さらに驚いたのは、重心病院で勤務していた際、医師がカニューレだけ交換して紐はそのままという場面に何度も遭遇したこと。
市販バンドどころか、そもそも「紐を交換する」という認識すらない職場があるのだと知って驚愕しました。
常識って、本当に施設によって違います。
新人のころ、「マーゲンチューブのテープは毎回交換する」と教わったのに、別の病院では1週間前のテープのまま患者さんが退院してきたこともあります。
そうした経験から、「だったら自分で作る!」という想いが芽生えました。
大人も楽しめるカニューレバンドを展開していけたら…そんな願いを込めて、このプロジェクトをスタートさせました。
将来的には「きらぼしShop」での販売を目指し、試作を重ねています。
🌟ジプシーナース式!2種類の手作りカニューレバンドデザイン
今回、Kagayaが試作したカニューレバンドは、マジックテープタイプと紐タイプの2種類。
それぞれに特長があり、目的や装着する方の好みによって選べるように工夫しました。
「市販品では満足できない」「もっと肌に優しく、かわいく、安全なものを作りたい」との想いから、デザインにもこだわりを詰め込みました。
マジックテープタイプ

こちらは、装着と取り外しが簡単なマジックテープ式のカニューレバンドです。
市販品のようにマジックテープ部分がむき出しにならないよう、フラップ(かぶせ布)を追加して見た目をすっきり整えています。
このフラップは、装着中にパタパタと浮かないように、スナップボタンで固定できる仕様にしました。
デザイン面の美しさだけでなく、バンドが緩んで不意に外れたりしないよう安全性にも配慮しています。
また、内側にマジックテープの縫い目がゴツゴツと当たらないように縫製方法も見直し、肌当たりのやさしさにもこだわりました。
実際に使用してみると、装着が片手でも行えるため、介護者にも優しい設計になっていると実感しました。
日々のケアの中で「さっと交換できる」「外れにくい」「見た目がかわいい」という3つの要素を兼ね備えたタイプです。
紐タイプ

こちらは、カニューレの両端に蝶結びで固定する紐タイプです。
昔ながらのスタイルですが、意外と使い勝手が良く、マジックテープが苦手な方や皮膚が敏感な方におすすめです。
今回は手元に適した紐がなかったため、共布(同じ布地)を使用して手作り紐を作成しましたが、本来は「真田紐」や「綾テープ」などを活用するとより頑丈で仕上がりもきれいです。
真田紐は色柄も豊富で、バンドの個性を出すのにもぴったりなアイテム。
ただし、カニューレ孔に通す部分は幅5mm以下でないと通らないこともあるため、太さの調整が必要です。
「きらぼし布地」のような柄ものの本体に合わせて、紐部分は無地の綾テープなどを合わせると、デザインバランスが取りやすいです。
紐タイプの魅力は、耐久性とやさしい肌当たり。
マジックテープのように劣化して粘着が弱くなる心配がないため、経済的にも優れています。
ただし、結び方が甘いと抜管のリスクがあるため、しっかりと蝶結びする必要があります。
「かわいいけど、ちょっと手間がかかる」そんな方にはマジックテープタイプがおすすめです。
それぞれの特徴を理解したうえで、使用者に合ったタイプを選べるように、今後はカスタムオーダーも想定していきたいと思っています。
🌟カニューレバンドの作り方と参考サイト
手作りカニューレバンドに挑戦してみたいけれど、いざ作り方を調べてみると、意外にも情報が少なく、写真付きで丁寧に解説しているサイトはほとんどありませんでした。
特に、見た目が整っていて、実用性もあるデザインとなると、選択肢がさらに限られてきます。
医療的ケア児のママさんが発信している手作り情報は多いものの、画像が少なかったり、サイズ感が不明だったりして、「これなら真似して作れる!」というものがなかなか見つからず、試行錯誤の連続でした。
そんな中、Kagayaが実際に参考にさせていただいたのが、以下の2つのサイト・動画です。
それぞれ、マジックテープタイプと紐タイプに分かれているので、自分の目的に合わせて選んでみてください。
マジックテープタイプの試作レポートと改良ポイント
マジックテープタイプのカニューレバンドは、装着や取り外しが簡単なことから、介護や訪問看護の現場でも多く使用されています。
Kagayaも、まずはこのスタンダードなタイプから試作に取り掛かりました。
参考にさせていただいたのは、「医療的ケア児ママの手探り育児」という育児ブログ。
写真付きで丁寧に手順が紹介されており、「折り紙のように畳んで縫う」という構造がとても印象的でした。

実際に作ってみると、パーツは少ないものの、厚手の布だと畳んだときにゴワついてしまい、縫いづらさを感じました。
薄手のコットンやガーゼ生地など、柔らかくて扱いやすい素材を選ぶのがポイントです。

写真のように、表から見るとフラップがマジックテープを目隠ししてくれて見た目もスッキリ。
ただ、フラップを開けると、裏側にがっつり縫い目が露出していて驚きました。

これはちょっと美しくない…。
そして何より問題なのは、この縫い目が肌に当たる面にきてしまうことです。
使用者の中には皮膚が弱い方も多く、少しの刺激で赤みや発疹が出てしまうこともあります。
縫い目の凸凹は皮膚トラブルの原因にもなりかねません。
そこで、試作品を作り直すことにしました。



改良バージョンでは、縫い目を内側に隠す縫製に変更。
上下で縫い合わせてひっくり返すことで、どちらの面にもゴツゴツした縫い目が出ないように仕上げました。
実際に完成したものは、表裏の区別がつかないほどきれいな仕上がりになりました。
肌への刺激も最小限で済みそうですし、見た目にも満足感があります。
試作品を通して実感したのは、「縫いやすさ」より「着け心地」を重視したほうが、結果的に使いたくなるバンドになるということです。
今後は素材やサイズバリエーションも増やして、利用者ごとのニーズに応えられるよう調整していきたいと思います。
紐タイプのカニューレバンド制作レポート
マジックテープタイプに続き、今回は紐で固定するカニューレバンドの制作にも挑戦してみました。
参考にさせていただいたのは、YouTubeで公開されている「springhascome.」さんの動画です。
手元がよく見える丁寧な作り方で、初心者でも安心して真似できる構成になっていました。

マジックテープタイプに比べて、構造がシンプルで作りやすいのが紐タイプの良いところ。
バンド本体の縫製も直線が中心で、初心者向けのミシンワークでも十分対応できます。
ただし、バンドの「紐」部分を作るときには一工夫が必要です。
動画内では割りばしやループ返しを使って布をひっくり返していましたが、これが想像以上に難しい…。
細く作りすぎると布が通らなくなり、太くすると今度はカニューレの穴に通らないというジレンマが生じます。
Kagayaも試作中に試行錯誤し、最終的には幅5mm程度で落ち着きました。
これくらいが、通しやすさと強度のバランスが良く、安全に使えると感じています。
今回は手元に使える紐がなかったため、バンドと同じ布で共布(ともぬの)の紐を作って代用しました。
見た目の統一感は出ますが、力が加わる部分でもあるため、強度が心配な方には既製品の真田紐や綾テープの活用をおすすめします。
真田紐は丈夫でカラフルなものも多く、バンドのワンポイントとしても映えます。
ただし、カニューレに通す穴が小さい場合は、厚みや幅に注意が必要です。
また、紐タイプはマジックテープと違って劣化しづらいという利点があります。
結びさえできれば何度でも繰り返し使用でき、交換頻度も少なくて済むため、環境にもやさしい構造です。
ただし、「ちょうちょ結びが苦手」「片手での介助が必要」など、現場での実用性を重視する方には不向きな面もあります。
使用者本人が装着できるようにするには、練習や工夫が必要かもしれません。
🌟手作りカニューレバンドの素材と安全性に関する考察
カニューレバンドは、直接皮膚に接する部分であるため、素材の選び方や構造によっては皮膚トラブルの原因になることがあります。
実際、Kagayaが訪問看護や施設で見てきた中でも、市販のバンドによって発赤やかぶれ、汗疹を起こしているケースは少なくありませんでした。
あまりに皮膚トラブルがひどいときには、「ティッシュを一枚はさんで調整する」という現場の工夫も見られます。
症状の原因は個人差がありますが、多くは次の2つに集約されます:
- 汗による蒸れ(特に夏場)
- 硬い素材や縫い目による圧迫・刺激
このような問題に対して、通気性がよく、肌当たりのやわらかい素材を選ぶことが、予防や軽減につながると考えています。
たとえば、以下のような冷感素材や吸湿性のある布地は、夏場に特におすすめです。
こういった布地は見た目にもやさしく、医療的ケアが必要な方にも「かわいさ」や「快適さ」を届けられます。
手作りなら、30cm四方のハギレ布でも十分に作れるため、コスパも良く、気軽に素材を変えて試せるのも魅力のひとつです。
マジックテープタイプについては、「見た目がスッキリしていて簡単に装着できる」というメリットがある一方で、硬いテープを使うと皮膚に食い込みやすくなるというデメリットもあります。
そのため、選ぶ際は必ず柔らかく、低刺激なマジックテープを使用するのが望ましいです。
ただし、マジックテープは使用しているうちに粘着力が弱くなるため、定期的な点検と交換が必要です。劣化したバンドをそのまま使い続けると、固定力が低下して抜管リスクが高まる可能性があります。
一方、紐タイプのバンドは劣化が少なく、丈夫で繰り返し使用できます。
とはいえ、結び方が甘いと解けてしまうことがあるため、しっかりと蝶結びできることが前提条件となります。
かわいいリボン風に見えるのは魅力ですが、「自分で結ぶのが苦手」「支援者が1人で装着する」といった場合は、やや手間がかかる印象です。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、使用者の状況に合わせて最適なタイプを選ぶことが大切です。
Kagayaとしては、安全性と快適性のバランスを重視しながら、誰もが楽しく使える「おしゃれな医療用グッズ」を今後も発信していきたいと思っています。
まとめ
気管切開をしている方にとって、カニューレバンドは単なる医療的な道具ではなく、「おしゃれを楽しむ」ための大切なアイテムでもあります。
直接、傷口にバンドが接触するわけではないため、普段のファッションと同じように「今日はこのデザインにしようかな」とコーディネートを楽しむことができます。
実際にインターネットで「カニューレバンド 作り方」などと検索すると、多くは障がい児のお母さんや訪問看護師が作っているハンドメイド品が紹介されています。
さまざまな生地で、色や模様もかわいく、お子さんのキャラクターや雰囲気に合わせて工夫されています。
メルカリやminneなどのハンドメイドマーケットでも、気軽に検索・購入できますが、その多くは子どもサイズが中心です。
大人サイズのカニューレバンドはあまり見かけず、選択肢が限られている印象です。
このような背景から、「大人用のおしゃれなカニューレバンド」を手作りしたり販売したりするニーズは、今後さらに広がっていく可能性があります。
市販のものは便利ですが、サイズが合わない・デザインが物足りない・皮膚トラブルが起きる…といった問題があるため、手作りによる自由なカスタマイズは、大きな魅力です。
今回、実際に作ってみて感じたのは、思った以上に簡単にできるということ。
そして、自分の好きな布や素材を使える楽しさです。
肌にやさしい接触冷感の生地や、柔らかいマジックテープを選ぶことで、皮膚トラブルの予防にもつながります。
カニューレの位置や固定の強さに気を配りながら、安心・安全・かわいいを叶えるアイテムを一緒に作っていけたらと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。