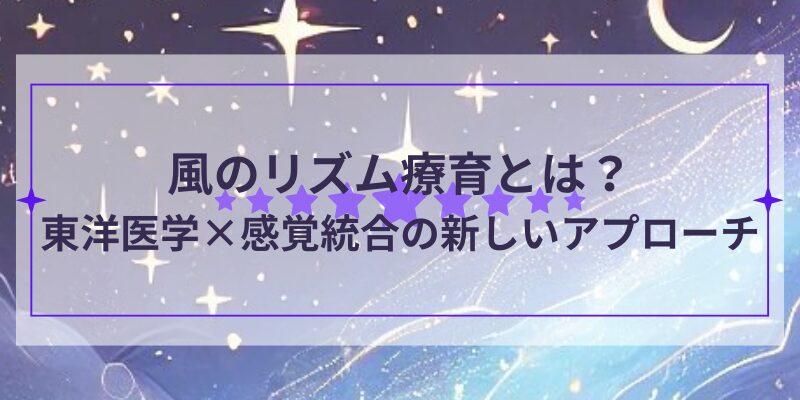🌟「風のリズム療育」療育ってなに?支援者として出会った“発達を支えるケア”
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
Kagayaはこれまで、医療的ケアが必要な重症心身障がい児のご家庭を訪問し、看護と鍼灸ケアを行ってきました。
吸引や胃ろう管理などの医療処置をしながら、同時に「からだとこころのリズム」をどう整えるかを大切にしてきた日々です。
支援の現場にいる中で、ふと立ち止まる瞬間がありました。
それは、「療育=訓練」という枠にとらわれ過ぎていないか?という問いです。
もちろん、座る・手を伸ばす・言葉を引き出すなど、機能訓練や学習支援はとても大切です。
でも、その子の呼吸や生活リズム、気持ちの安定といった“内なる世界”を感じ取れているだろうか?そんな問いがKagayaの中に生まれたのです。
ある日、全身をほとんど動かせないお子さんと向き合っていたとき、気圧の変化や生活リズムによって表情や呼吸が微妙に変わることに気づきました。
手足は動かせなくても、「外の世界とつながりたい」「心地よく過ごしたい」という思いは確かに伝わってきました。
そこでKagayaが取り入れたのが、東洋医学の「気・血・津液」や「五臓六腑」という視点。
現代医学では見落とされがちな“感覚のズレ”や“過敏さ”を、身体の巡りのバランスとして捉えることができるのです。
また、感覚統合やスヌーズレン療法など、脳の感覚処理に働きかけるアプローチとも融合させ、より包括的な支援ができるようになりました。
この実践の中から生まれたのが、「風のリズム療育」という考え方です。
「風」は、東洋医学で“気の動き”“変化”“感覚の情報”を表す概念であり、目には見えないけれど、生きていく上で欠かせない存在。
そして「リズム」は、呼吸・睡眠・食事・感情・社会的な関わりなど、日々の暮らしの中にある時間の流れです。
この「風」と「リズム」を大切にすることで、その子本来の「育ちの力」に寄り添えるのではないか。療育とは、がんばらせるものではなく、“寄り添い、整えて、見守る”もの。そんな思いから生まれたのが、「風のリズム療育」というスタイルです。
このブログでは、支援者としての視点に加え、東洋医学の知恵を活かして、発達の特性があるお子さんの暮らしに役立つ情報をお届けします。
ツボやセルフケア、感覚遊び、親子の関わり方など、今日からできる実践をたっぷりご紹介していきます。
「なんだか子育てがしんどいな」「うちの子、育てにくいのかな?」と感じたときに、このブログが“ひとつの光”となれたら嬉しいです。
🌟Kagayaの体験:重症児のケア現場で感じた“育ちの支援”
Kagayaが「療育」という言葉と本格的に向き合うようになったのは、特別支援学校での勤務がきっかけでした。
重度の障がいをもつ子どもたちと過ごす日々は、それまでの看護や鍼灸の現場とはまったく異なる学びと発見の連続でした。
そこにいたのは、自力で動くことが難しい子、発語がなくても豊かな感情をもつ子、医療的ケアが日常的に必要な子どもたち。
はじめは「どう関わればいいのだろう」と戸惑う気持ちもありましたが、目と目を合わせ、肌に触れ、日々を一緒に過ごしていく中で、彼らがしっかりと周囲を“感じて”いることを実感しました。
そしてある日、強く思ったのです。
「この子たちは、発達を“止めている”のではなく、“ゆっくり進めている”だけなんだ」と。
その子なりの時間軸で、呼吸し、反応し、少しずつ“育っている”。
そう感じた瞬間、Kagayaの中で「育てる支援」から「育ちに寄り添う支援」へと意識が大きく変わりました。
たとえ筋力が弱くても、言葉がなくても、繰り返し関わり続けることで、小さな変化に出会うことができます。
たとえば、目線が合うようになったり、音や匂いに対する反応がはっきりしてきたり、手を動かす回数が増えたり——それらすべてが「育ちのサイン」なのです。
Kagayaは、鍼灸師として「気・血・津液」の巡りを整えながら、看護師として生活の安全と安心を支え、そして一人の人間として「その子らしい時間の流れ」を大切にしてきました。
療育は、単なる訓練や学習支援ではなく、「その子の命のペースに伴走すること」。
この考え方を、東洋医学の視点から改めて捉え直すことができたのは、まさに現場での体験があったからこそです。
そもそも「療育」とは?
療育とは、「治療(Medical)」と「教育(Education)」を組み合わせた概念で、発達に特性のある子どもたちを包括的に支援するアプローチです。
ただ単に運動機能や言語を「できるようにする」ための訓練ではなく、心身の成長を促し、その子らしく社会と関われるように導くことが目的です。
- 身体機能の支援:理学療法・作業療法・小児鍼灸などで運動機能や身体の協調性を育てます。
- 認知や行動の支援:感覚統合遊びやABA療法などで、思考の柔軟さや適応力を育てます。
- 社会性・言語の支援:ソーシャルスキルトレーニング(SST)や構造化支援を通じて、他者とのやりとりをサポートします。
- 親子関係や生活支援:育児相談やレスパイト(短期休息)サービスで、家庭の負担を軽減します。
療育の対象は、発達障がいの診断がある子に限りません。
診断前のグレーゾーンの子や、医療的ケア児、ダウン症などの染色体異常、肢体不自由、知的障がいがある子など、育ちに特性があるすべての子どもたちが対象です。
療育の目的は「その子のペースで育つことを支える」
療育において、もっとも大切にしたいこと。
それは「早くできるようになること」ではなく、「その子の歩みに寄り添うこと」です。
大人が期待する「○歳までにこれができるように」というスケジュールから離れ、その子の表情、呼吸、感情の変化に耳を傾けてみてください。
すると、少しずつ、確かに「育ち」は動いています。
支援者や保護者がそのことに気づき、共有し、協力していくことで、お子さんはより安心して自分の力を発揮できます。
「今できていないこと」ではなく、「今この子がもっている力」に目を向ける。
これこそが、真の療育のはじまりだと私は思います。
🌟なぜ療育が必要なの?発達の多様性と社会のニーズ
近年、「発達の多様性(Neurodiversity)」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
この言葉は、子どもたちの発達にはさまざまなパターンがあるという前提に立ち、従来の「普通・標準」という基準では捉えきれない個性や特性を尊重しようという考え方です。
すべての子どもが同じ発達曲線を描くわけではありません。
言葉が早く出る子もいれば、運動が得意な子、感覚に敏感な子、想像力が豊かな子など、それぞれに「得意」と「苦手」が存在します。
こうした発達の違いは、その子の価値や可能性を否定するものではなく、むしろ大切な個性の一部だと考える視点が広まりつつあります。
しかし一方で、その多様性の中で「日常生活に支障をきたすレベルで困っている」お子さんがいるのも現実です。
集団行動が難しい、言葉で気持ちを伝えられない、感覚過敏で服を着るのがつらい——そんな子どもたちにとって、社会生活は大きなストレスになり得ます。
そこで必要となるのが「療育」です。
療育は、発達に特性があるお子さんが、自分らしく生きる力を育んでいくためのサポート。
決して「普通に近づける」ための訓練ではなく、その子の現在地を見つめながら、安心して社会とつながっていけるよう支える取り組みです。
また、療育はお子さん本人だけでなく、保護者の孤立を防ぐ役割も担っています。
「ほかの子と違うのでは…」「なぜわかってもらえないのか」「相談できる場所がない」——そんな不安や孤独を抱える保護者の方々にとって、療育施設や訪問支援は心の拠り所となります。
社会全体で発達に特性がある子どもたちを理解し、支える仕組みをつくっていくことが、これからの時代にますます求められているのです。
多様な発達を理解する:脳機能の発達と環境要因
発達に特性があるお子さんの多くは、脳の情報処理の仕方に“個性”があります。
たとえば、五感の感受性が非常に高かったり、音や光に過敏だったりする子どもたちは、私たちが「何気ない」と感じる刺激にも大きく反応します。
また、切り替えが苦手だったり、集団の中での人間関係に戸惑いやすい傾向もあります。
こうした特性は「わがまま」「育て方の問題」ではなく、脳の構造や神経発達の違いによって生じていることが、近年の神経科学や発達心理学の研究からも明らかになっています。
また、発達には遺伝的要因に加えて、家庭環境、愛着形成、栄養、睡眠、社会的関係性など、外的な環境要因も大きく関わります。
東洋医学では、「心身一如(しんしんいちにょ)」という考え方を大切にします。
これは、心と体はひとつにつながっており、生活環境や感情の状態も含めてバランスを整えていくことが、健やかな成長に不可欠だという考えです。
療育の科学的根拠と重要性:専門機関からの情報
「療育」と聞くと、まだ一部では「遊びの延長?」「本当に効果があるの?」と思われることもありますが、療育の有効性は国内外で科学的に証明されています。
厚生労働省の資料では、発達障害やその傾向があるお子さんに対して、早期からの支援介入が、その後の学習・社会適応・心身の健康に良い影響を与えると明記されています。
各自治体の支援制度や、支援方法に関する専門的な情報が公開されており、保護者・支援者ともに役立つ内容が満載です。
さらに、小児の発達に対する東洋医学的アプローチ(小児はり・経絡治療・漢方など)に関する研究も進んでおり、心身の調和を促すケアとして注目が集まっています。
これらの情報が示す通り、療育は決して「一部の人のための特別なもの」ではなく、社会全体で共有し、理解し、支えるべき基盤的な取り組みなのです。
🌟西洋医学と東洋医学のいいとこ取り
療育の現場では、子どもたちの発達に寄り添うために、さまざまな視点や手法が取り入れられています。
その中でも注目されているのが、西洋医学と東洋医学を融合したアプローチです。
たとえば、感覚統合療法やスヌーズレン療法は、西洋医学の理論に基づいて感覚処理の困難さを理解し、脳の感覚統合機能に働きかける支援方法です。
子どもたちの「過敏」「鈍感」「こだわり」などの行動に対して、「脳がどう情報を処理しているか」というメカニズムからアプローチしていきます。
一方で、東洋医学では「五臓六腑」「気・血・津液」という概念を用いて、身体と心の状態を総合的に見ていきます。
「気のめぐりが悪い」「脾が弱っている」「腎の精が足りない」といった形で、子どもの体調や情緒、睡眠、集中力などを“全体のバランス”として捉えるのが特徴です。
Kagayaは、このふたつの視点を日々の支援の中で統合し、子どもたちの状態を多角的に観察しています。
あるお子さんが「落ち着きがなく動き回る」時、西洋医学では感覚過敏や多動傾向として評価されるかもしれませんが、東洋医学では「肝の気が昂ぶっている」という見立ても可能です。
このように、それぞれの理論が持つ“違った視点”を重ねることで、より深く子どもを理解できるようになります。
つまり、西洋医学で「脳・感覚の機能」にアプローチし、東洋医学で「体質・内臓バランス」にアプローチすることで、子どもたちの“育ち”を丸ごと支えることができるのです。
東洋医学から見る「育ち」と五臓の関係
東洋医学では「心身一如(しんしんいちにょ)」という言葉があります。
これは、心と身体は切り離せない一つの存在であり、どちらかが乱れればもう一方にも影響が出るという考え方です。
特に子どもの場合は心身の発達が密接に関係しているため、この考え方は療育にも非常に有効です。
以下は、東洋医学で重視される五臓と育ちの関係です:
- 肝(かん):感情や自律神経、筋肉運動に関係します。肝のバランスが崩れると、イライラしやすい、夜泣き、落ち着きのなさといった症状が出ることがあります。
- 脾(ひ):消化吸収、学習、集中力に関わります。脾が弱ると、食欲不振、便秘・下痢、集中力の低下が見られます。
- 腎(じん):成長・骨・耳・脳・免疫に関係する、いわば“成長の土台”。腎のエネルギーが不足すると、発達がゆっくり、疲れやすい、風邪をひきやすいといった特徴が出ます。
- 心(しん):精神活動、睡眠、情緒とつながります。心のバランスが乱れると、興奮しやすい、眠りが浅い、不安感が強くなるといった症状が出ることがあります。
- 肺(はい):呼吸、皮膚、免疫と関係します。肺が弱いと風邪をひきやすくなったり、アレルギー、乾燥肌などが出やすくなります。
たとえば「よく転ぶ」「不安が強い」「すぐに風邪をひく」といった症状も、五臓のバランスを見直すことで、その背景にある体質や状態を見立てられる可能性があります。
このように、東洋医学の視点を療育に取り入れることで、目に見える行動の“奥にあるもの”にもアプローチできるようになります。
🌟セルフチェック|こんな様子はありませんか?
お子さんの日々の様子を見ていて、「なんだか気になるな…」と感じたことはありませんか?
現代では、発達のスピードや反応の仕方に個性があることが広く知られるようになりましたが、小さな変化や行動のクセにこそ、からだやこころのサインが隠れていることがあります。
東洋医学では、こうしたサインを「気・血・津液」や「五臓六腑」のバランスの乱れとして捉えます。
つまり、「ただの癖」「個性」と思っていたものが、実は心身のアンバランスによる表れかもしれないということです。
以下に、Kagayaが臨床や家庭支援の中でよく目にする“気になるサイン”をセルフチェック形式でまとめました。
当てはまる項目がないか、ぜひ一度見直してみてくださいね。
- ( ) ちょっとしたことでイライラしたり、怒りっぽい。気持ちの切り替えが苦手。
- ( ) よく転ぶ、動きがぎこちない。あるいは、落ち着きがなく常に体を動かしている。
- ( ) 便秘や下痢が続く。食欲にムラがあり、お腹が張って苦しそうなことがある。
- ( ) 新しい環境や予定の変更に強い不安を感じ、こだわりが強く見られる。
- ( ) 夜泣きが続く、寝つきが悪い、眠りが浅く夜中に何度も目を覚ます。
- ( ) すぐ疲れる、朝なかなか起きられない、元気のムラが大きい。
- ( ) 肌が乾燥しやすい、風邪を引きやすい、アレルギー症状が出やすい。
いかがでしたか?
これらのサインは、東洋医学の観点から見ると、「肝」「脾」「腎」「心」「肺」のどこかにアンバランスがある可能性を示しています。
たとえば:
- イライラ・怒りっぽさ → 肝の気が上がりすぎている(肝実)
- 便秘や消化不良 → 脾の虚弱(脾虚)
- 疲れやすい・夜泣き → 腎や心の気虚、陰虚
- こだわりや不安感 → 心の不安定、肝の気滞
- 風邪をひきやすい → 肺の気虚、衛気の不足
もちろん、ひとつひとつの症状が深刻なわけではありませんが、毎日の積み重ねがその子の発達の土台をつくります。
体と心の小さなズレを放置せず、早めにケアしてあげることで、トラブルの予防や不調の軽減につながります。
また、こうしたチェックを通して「うちの子のタイプ」が見えてくると、声かけの仕方や生活リズムの整え方、ツボの選び方なども具体的になります。
心配しすぎる必要はありませんが、子どもの「今の状態」を知るきっかけとして、ぜひ定期的にセルフチェックを取り入れてみてください。
🌟Kagaya式|東洋医学的セルフケア
東洋医学の知恵を活かしたセルフケアは、お子さんの発達において「心地よさ」「安心感」「自然なリズム」を支える重要な方法です。
ここでは、五臓のバランスを整えるための簡単なケアを紹介します。
親子のふれあいの中で、無理のない範囲で取り入れてみてくださいね。
① 肝タイプ|イライラ・興奮しやすい、夜泣きが多いお子さんへ
東洋医学で「肝」は、気の巡りや情緒の調整、筋肉・運動機能にも関わるとされています。
イライラしやすい、急に怒る、眠りが浅い、体がこわばっているように感じる場合は、肝の気の滞りが影響しているかもしれません。
- ツボ:
・太衝(たいしょう):足の親指と人差し指の間、骨の付け根より少し手前。イライラや興奮を鎮めるのに役立ちます。
・百会(ひゃくえ):頭のてっぺん、両耳と鼻を結んだ線の交点。自律神経を整え、リラックス効果が期待できます。 - ケア法:
・ホットタオルで足の甲を温める:太衝周辺を温めることで、肝の気の巡りをスムーズにします。
・お灸:煙の少ないタイプのお灸を太衝や百会に優しく置きます。温熱効果でリラックスできます。 - 生活アドバイス:
・規則正しい生活:特に早寝早起きを心がけ、自然のリズムに合わせましょう。
・適度な運動:体を動かすことで、余分な気を発散させ、ストレスを軽減します。
② 心タイプ|不安感が強い、眠りが浅いお子さんへ
「心」は、精神や意識、睡眠と深く関わる臓です。興奮しやすい、怖がり、よく泣く、夜に何度も目覚める…そんな様子が気になる時は、心のバランスが崩れているのかもしれません。
- ツボ:
・神門(しんもん): 手首の内側、小指側のくぼみ。精神安定に効果的とされ、穏やかな気持ちを促します。
・内関(ないかん): 手首の内側、指3本分ひじに向かったところ。吐き気や乗り物酔いにも使われますが、精神的な緊張を和らげる働きもあります。 - ケア法:
・優しい手首マッサージ: 神門や内関のツボを、お風呂上がりや寝る前に優しくなでるようにマッサージしてあげましょう。温かい手で触れることで、お子さんは安心感を覚えます。
・アロマを活用したリラックスタイム: ラベンダーやカモミールなど、鎮静作用のあるアロマをディフューザーで香らせたり、薄めて足の裏に塗布したりするのもおすすめです。お子さんが落ち着ける香りを選んであげてくださいね。 - 生活アドバイス:
・就寝前のルーティン: 毎日同じ時間に寝る準備を始める、絵本を読む、優しい音楽を聴くなど、安心できるルーティンを作りましょう。
・安心できる環境作り: 寝室の照明を暗くする、好きな毛布やぬいぐるみを近くに置くなど、お子さんが安心して眠れる環境を整えてあげてください。
③ 脾タイプ|お腹が弱い、集中が続かないお子さんへ
東洋医学で「脾」は、消化吸収や思考、学習に関係する臓器です。お腹が張りやすい、食欲が不安定、集中力が続かない…といった場合には脾の機能を高めるケアが大切です。
- ツボ:
・足三里(あしさんり):膝のお皿のすぐ下から指4本分下がった、すねの骨の外側。消化機能を高め、体力アップに効果的です。
・三陰交(さんいんこう):内くるぶしから指4本分上、すねの骨の後ろ。消化器系全般の調子を整えるほか、女性の生理不順などにも良いとされます。 - ケア法:
・腹部の gentle なマッサージ:おへそを中心に「の」の字を描くように優しくマッサージします。食後すぐは避けましょう。
・耳ツボで消化機能を整える:食欲不振や消化不良の際に、耳の消化器系のツボを刺激します。専門家による耳ツボジュエリーもおすすめです。 - 生活アドバイス:
・温かい食事:体を冷やすものは避け、温かく消化の良いものを中心に摂りましょう。
・よく噛む習慣:食べ物をしっかり噛むことで、消化吸収を助けます。
④ 肺タイプ|風邪をひきやすい、肌が弱いお子さんへ
「肺」は、呼吸や免疫、皮膚の働きと深く関わります。
よく風邪をひく、咳をしやすい、アトピーや乾燥肌が気になるといった症状は、肺のケアで改善することがあります。
- ツボ:
・尺沢(しゃくたく): 肘の内側、肘を曲げた時にできるシワの中央。呼吸器系の不調に良いとされます。
・合谷(ごうこく): 手の甲、親指と人差し指の骨が交わるくぼみ。体の不調全般に用いられる万能なツボで、免疫力アップにも期待できます。 - ケア法:
・背中を温める: 特に首の後ろから背中にかけて、薄手のベストを着せたり、温かいタオルでじんわりと温めたりしましょう。風邪の引き始めなどにも効果的です。
・乾燥対策と皮膚の保湿: 肺と皮膚はつながっているため、特に乾燥する季節は加湿器を使ったり、保湿剤で肌を丁寧にケアしたりすることが大切です。
・優しい呼吸遊び: シャボン玉を吹いたり、風車を回したりする遊びは、楽しく呼吸を促し、肺の働きをサポートします。 - 生活アドバイス:
・適度な外気浴と軽い運動: 埃っぽい場所を避け、清浄な空気の中で体を動かすことは、肺を強くすることにつながります。
・体を冷やさない工夫: 冷たい飲み物や食べ物を避け、旬の野菜や体を温める食材をバランスよく摂りましょう。
⑤ 腎タイプ|成長がゆっくり、疲れやすいお子さんへ
「腎」は成長や発達、体力の根本を支える大切な臓です。
体が小さい、疲れやすい、冷えや夜尿が気になるといった場合は、腎のケアが必要かもしれません。
- ツボ:
・湧泉(ゆうせん):足の裏、足指を曲げた時に一番くぼむ部分。生命力や元気を養うツボです。
・命門(めいもん):背中、おへその真裏。腎の働きをサポートし、体を温めます。 - ケア法:
・腰の温灸:命門周辺に温灸をすることで、体を芯から温め、腎の働きを助けます。
・足湯:湧泉を温めるように足湯をすることで、全身の血行を促進し、リラックス効果も高まります。
・背中へのタッチング:優しく背中をさすったり、なでたりするスキンシップは、お子さんの安心感を高め、心身のバランスを整えます。 - 生活アドバイス:
・十分な睡眠:成長ホルモンは睡眠中に多く分泌されるため、質の良い睡眠を確保しましょう。
・栄養バランスの取れた食事:特にミネラルやビタミンを意識して摂り、腎の働きをサポートします。
🌟Kagayaがおすすめする!育ちをサポートするアイテム3選
日々のセルフケアをより効果的に、そして楽しく続けるために、Kagayaが厳選したアイテムを3つご紹介します。
どれも実際に私自身もおすすめしているものばかりです。
【1】煙と匂いが気にならない!せんねん灸 太陽
自宅でお灸をする際、煙や匂いが気になるというお声もよく聞きますよね。
そんな方におすすめなのが、『せんねん灸 太陽』です。
- 特徴:火を使わず、貼るだけでじんわりと温かさが持続する台座灸です。煙も匂いもほとんどないので、お子さんが寝ている間や、リビングでも手軽に使えます。皮膚に直接触れないため、火傷の心配も少なく、安心して使えます。
- 使用感:ほんのりとした温かさが心地よく、リラックス効果も抜群です。お子さんの気になるツボに貼ってあげると、気持ちよさそうにしてくれます。Kagayaも、日々の疲れを感じたときや、体が冷えると感じたときに愛用しています。
忙しい保護者の方でも、これなら手軽に東洋医学のケアを取り入れられますよ。
【2】目立たず手軽に継続ケア!スキンペレット
ツボ刺激はしたいけど、お子さんが嫌がるかも…という方におすすめなのが、『スキンペレット』です。
- 特徴:医療用テープに小さな金属粒がついたもので、耳のツボに貼るだけで持続的に刺激を与えられます。見た目も可愛らしいジュエリータイプなので、お子さんにも抵抗なく受け入れてもらいやすいです。
- 使用感:貼っているのを忘れるほど自然で、日常生活に支障なくケアができます。耳には全身のツボが集中しているので、食欲不振や落ち着きのなさなど、お子さんの様々な気になる症状に対応できます。Kagayaの施術でも、ご希望の方にはお勧めしています。
専門知識がなくても、貼るだけで手軽にケアできるのが魅力です。
【3】親子のふれあいを深める!ベビーてい鍼
もっと深くお子さんのケアを学びたい方や、日々のふれあいの中で東洋医学を取り入れたい方には、『ベビーてい鍼』がおすすめです。
- 特徴:お子さんにも分かりやすいイラストで、ツボの位置やマッサージ方法が丁寧に解説されています。発達支援に役立つツボや、親子のスキンシップを深めるためのマッサージなど、実践的な情報が満載です。
- 使用感:読みやすく、すぐに実践できる内容なので、東洋医学の知識がない方でも安心して始められます。お子さんと一緒に「ここが気持ち良いね」とコミュニケーションを取りながらマッサージすることで、絆も深まります。
この本があれば、ご自宅でいつでもお子さんの健康をサポートできますよ。
🌟Kagayaの「きらぼし」が提供する、あなたとお子さんのためのサポート
ここまで、療育や東洋医学の考え方、ご家庭で実践できるセルフケアについてお伝えしてきました。
「もっと深く学びたい」「子どもに合ったケアを知りたい」「自分では対処が難しいときに専門家に相談したい」そう感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな時は、ぜひ プライマリ・ケアサポート きらぼし にご相談ください。
Kagayaは、看護師と鍼灸師のダブルライセンスを活かし、医療的ケア児や発達特性をもつお子さん、そのご家族を対象にした「オーダーメイドのサポート」を提供しています。
一人ひとりに合わせた、やさしく、あたたかな支援をお届けする3つの柱をご紹介します。
きらぼし鍼タッチケア|刺さない鍼で穏やかな発達支援
「鍼(はり)」というと「痛そう」「怖そう」と思われがちですが、きらぼしの鍼ケアは刺しません。
やさしく皮膚をなでるように使える「てい鍼(ていしん)」という道具を使い、お子さんの体調や発達状態に合わせたツボに刺激を与えます。
刺激はとてもやさしく、感覚過敏のあるお子さんや、重度障がいのあるお子さんでも安心して受けていただけます。
- 神経系や自律神経を整える
- 睡眠や排便リズムをサポート
- 気分の安定や身体の緊張緩和
訪問形式なので、お子さんのペースでゆったりと施術を受けられます。
ナースケア|制度にとらわれない柔軟な訪問看護
医療的ケア児の夜間見守りや、放課後のサポートが必要なケースも多くあります。
しかし、制度の縛りで対応が難しい場面も。そんなとき、きらぼしのナースケアがお役に立てます。
- 平日夕方~夜間、土日も応相談
- 人工呼吸器や吸引、胃ろう対応
- 発熱・てんかん・緊急時の様子見
医療的な判断力が求められる場面でも、経験豊富な看護師として対応可能です。
もちろん、ご家族の不安や育児ストレスへの寄り添いも大切にしています。
きらぼし整体|耳ツボ中心の親子リラックスケア
耳ツボ鍼灸+やさしい整体を組み合わせた施術を行っています。
耳には、内臓や神経系、自律神経などとつながるツボが密集しており、やさしく刺激することで全身にアプローチできます。
- リラックス・睡眠の質向上
- 感覚過敏・緊張への対応
- 親子のスキンシップタイムに
Kagayaの施術は、シェアサロン or 訪問どちらも選べます。施術を通して、お子さんの変化だけでなく、ご家族の安心と癒しも一緒に支えていきたいと考えています。
どんなご相談でも、まずはお気軽にLINEやお問い合わせフォームからご連絡くださいね。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら
🌟こんな方に読んでほしい
ここまで、東洋医学の視点から見た「育ち」の理解、そして感覚統合・スヌーズレン療法と融合したアプローチ、さらにご家庭で実践できるセルフケアまでご紹介してきました。
「もっと詳しく知りたい」「専門家の意見を聞きたい」「我が子に合った方法を探したい」と思われた方も多いのではないでしょうか。
プライマリ・ケアサポート きらぼしでは、医療・看護・東洋医学・療育を統合的にとらえ、あなたとお子さんの「その子らしさ」を支えるお手伝いをしています。
こんな思いやお悩みをお持ちの方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。
- 療育の成果が感じられず、焦りや不安を感じている
- 医療的ケア児・重症心身障がい児のケアに疲れている
- 感覚過敏やこだわりの強さなど、特性に合ったアプローチを探している
- 通院やデイサービスだけでは満たされない部分を補いたい
- お子さんの夜泣きや情緒の不安定さに悩んでいる
- 西洋医学以外の視点(東洋医学・自然療法)にも興味があるけど、誰に相談すればいいか分からない
- 医療や福祉の現場で働いており、東洋医学の視点を学びたい支援者の方
特に、以下のようなキーワードが気になる方に、きらぼしの支援はお役に立てるはずです。
- 「子どもとの信頼関係を大切にした療育がしたい」
- 「一人ひとりの発達ペースを尊重したい」
- 「夜泣き・便秘・情緒不安など、体と心を一緒に見てほしい」
- 「療育・看護・東洋医学のトータルケアを知りたい」
私たちが目指すのは、「がんばらせる療育」ではなく、「寄り添い、整える療育」です。
一人ひとりのお子さんとご家族のペースに合わせたケアを、対話を通じて一緒につくっていきましょう。
気になることがあれば、どんなに小さなことでも構いません。
まずはお気軽にご相談ください。
🌟参考文献
- 厚生労働省:発達障害情報・支援センター「発達障害の理解と支援について」
- 厚生労働省:こころの健康「発達障害」
- 『子どものための東洋医学』 医道の日本社
- 「五臓と情緒発達の関係」日本東洋医学会誌
- 日本東洋医学会:小児疾患に対する漢方治療の現状と課題に関する検討