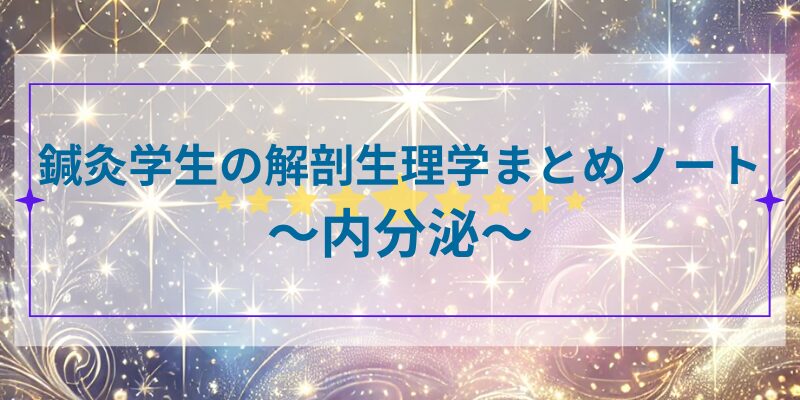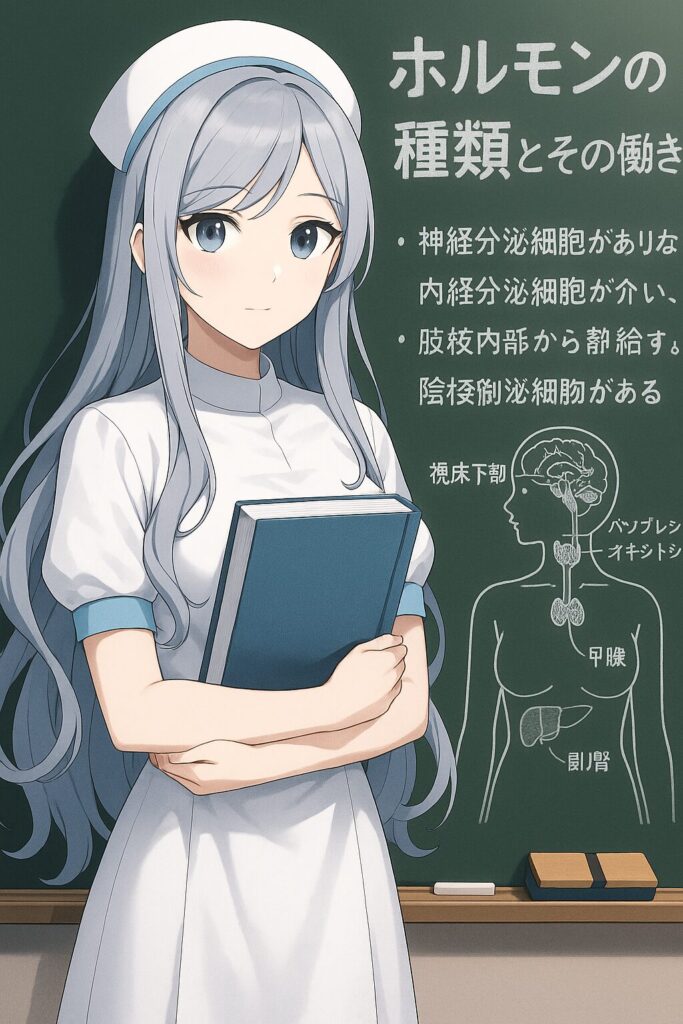
こんにちは~。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
Kagaya自身、学生時代に内分泌系のホルモンがなかなか覚えられず苦労しました……。
でも、しくみがわかると一気に得意分野になったんです!
今回は、そんな私が国家試験対策のためにまとめた「内分泌系のホルモン一覧ノート」をご紹介します。
🌟内分泌系とは?特徴と全体像
内分泌系は、ホルモンを使って体内の恒常性(ホメオスタシス)を調節するシステムです。
外分泌腺(汗腺や唾液腺など)と異なり、内分泌腺はホルモンを血液中に直接分泌し、遠く離れた特定の標的器官に作用します。
- ホルモンは体内の通信手段の一つ(神経系との違いに注意)
- 内分泌腺から血中にホルモンが分泌され、標的細胞に到達
- 体温・血糖・水分量・性周期などをコントロール
🌟主なホルモンとその働き一覧(器官別まとめ)
国家試験では「ホルモンの名前・分泌場所・標的・作用・疾患との関連」がよく出題されます。
以下に各器官ごとのホルモンをまとめます。
視床下部
間脳にあり、下垂体から分泌されるホルモンの調節を行っている。
| ホルモン名 | 標的組織 | 作用 |
|---|---|---|
| 成長ホルモン放出ホルモン(GRH / GHRH) | 下垂体前葉 | 成長ホルモン(GH)分泌を促進 |
| プロラクチン放出ホルモン(PRH) | 下垂体前葉 | プロラクチン(PRL)分泌を促進 |
| 甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH) | 下垂体前葉 | 甲状腺刺激ホルモン(TSH)とプロラクチン分泌を促進 |
| 副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH) | 下垂体前葉 | 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)分泌を促進 |
| 性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH) | 下垂体前葉 | 卵胞刺激ホルモン(FSH)および黄体形成ホルモン(LH)の分泌促進 |
| 成長ホルモン抑制ホルモン(GIH / ソマトスタチン) | 下垂体前葉 | 成長ホルモン(GH)とTSHの分泌を抑制 |
| プロラクチン抑制ホルモン(PIH / ドパミン) | 下垂体前葉 | プロラクチンの分泌を抑制 |
下垂体
視床下部の下に位置するソラマメ状の器官で、全身のホルモン調節の中枢です。
腺性下垂体(前葉):視床下部からのホルモンにより調節され、各種ホルモンを合成・分泌します。
神経性下垂体(後葉):視床下部で産生されたホルモンを蓄積・放出するのみで、自ら合成は行いません。
下垂体前葉
| ホルモン名 | 標的組織 | 作用 |
|---|---|---|
| 成長ホルモン(GH) | 多くの組織 | タンパク質合成促進、成長促進、血糖上昇作用 |
| プロラクチン(PRL) | 乳腺 | 乳腺の発育、乳汁の産生・分泌促進 |
| 甲状腺刺激ホルモン(TSH) | 甲状腺 | 甲状腺ホルモン(T3・T4)の分泌促進 |
| 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH) | 副腎皮質 | 糖質コルチコイド(コルチゾールなど)の分泌促進 |
| 卵胞刺激ホルモン(FSH) | 性腺(卵巣・精巣) | 卵胞成熟、精子形成、エストロゲン分泌促進 |
| 黄体形成ホルモン(LH) | 性腺(卵巣・精巣) | 排卵誘発、黄体形成、テストステロン分泌促進 |
下垂体後葉
| ホルモン名 | 標的組織 | 作用 |
|---|---|---|
| オキシトシン(OXT) | 子宮・乳腺 | 子宮収縮(分娩時)、射乳反射の促進 |
| バソプレシン(ADH) | 腎集合管 | 水の再吸収促進、尿量抑制(抗利尿作用)、血圧上昇 |
松果体
間脳の背面に位置し、光の刺激に応じてメラトニンを分泌。概日リズム(サーカディアンリズム)を調節する役割がある。
| ホルモン名 | 標的組織 | 作用 |
|---|---|---|
| メラトニン | 視床下部(視交叉上核)ほか | 概日リズムの調整 夜間に分泌増加、眠気を誘発 |
甲状腺
頚部前面下部、甲状軟骨の下に位置し、代謝の調整に関わるホルモンを分泌する。
主に濾胞細胞と傍濾胞細胞からなる。
濾胞細胞:甲状腺ホルモン(T3・T4)を分泌
傍濾胞細胞:カルシトニンを分泌(骨代謝に関与)
| ホルモン名 | 標的組織 | 作用 |
|---|---|---|
| サイロキシン(T4) | 多くの組織 | 基礎代謝促進、体温上昇、成長・発育促進 |
| トリヨードサイロニン(T3) | 多くの組織 | T4より強力な作用、迅速に基礎代謝を高める |
| カルシトニン | 骨・腎臓 | 血中カルシウムイオン濃度を低下させる 骨形成促進、骨吸収抑制 |
副甲状腺(上皮小体)
甲状腺の背面に4つ存在し、カルシウム代謝の調節に重要なホルモンを分泌する。
主細胞よりパラソルモン(PTH)を分泌。
| ホルモン名 | 標的組織 | 作用 |
|---|---|---|
| パラソルモン(PTH) | 骨・腎臓・小腸 | 血中カルシウムイオン濃度を上昇させる 骨吸収促進、腎での再吸収促進、活性型ビタミンD生成促進 |
膵臓(ランゲルハンス島)
膵臓の尾部に多く分布し、内分泌機能を担うランゲルハンス島には以下のような細胞が存在します。
α細胞:グルカゴン分泌
β細胞:インスリン分泌
δ細胞:ソマトスタチン分泌
※血糖値上昇を起こすホルモンは、グルカゴンのほか、成長ホルモン、甲状腺ホルモン、副腎髄質ホルモン(アドレナリン)なども含まれます。
| ホルモン名 | 標的組織 | 作用 |
|---|---|---|
| グルカゴン | 肝臓・脂肪組織 | 糖新生・グリコーゲン分解を促進、血糖値上昇 |
| インスリン | 多くの組織(筋・脂肪・肝) | グルコース取り込み促進、血糖値低下 |
| ソマトスタチン | 膵島・消化管 | インスリン・グルカゴン・消化管ホルモンの分泌抑制 |
副腎
副腎皮質
腎臓の上に乗る三角形の臓器。皮質は外側から以下の3層構造:
- 球状帯:鉱質コルチコイド(アルドステロン)分泌
- 束状帯:糖質コルチコイド(コルチゾール)分泌
- 網状帯:アンドロゲン(男性ホルモン)分泌
※コルチゾールは血糖上昇、抗炎症、抗ストレス作用、胃酸分泌促進など多彩な働きを持ちます。
| ホルモン名 | 標的組織 | 作用 |
|---|---|---|
| アルドステロン | 腎臓(遠位尿細管・集合管) | Na⁺再吸収・K⁺排泄促進 → 血圧・血液量の維持 |
| コルチゾール | 肝臓・免疫系・脂肪・筋 | 血糖上昇、抗炎症、蛋白質代謝促進 |
| アンドロゲン | 全身 | 思春期の第二次性徴発現(男女ともに)、男性化作用 |
副腎髄質
交感神経と類似の働きを持つクロム親和性細胞から構成され、ストレス時にカテコールアミン(アドレナリン・ノルアドレナリンなど)を分泌します。
| ホルモン名 | 標的組織 | 作用 |
|---|---|---|
| アドレナリン | 心筋、血管、肝臓、脂肪組織 | 心拍数・血圧・代謝・血糖上昇 |
| ノルアドレナリン | 血管平滑筋 | 血管収縮、血圧上昇(末梢血管抵抗↑) |
| ドパミン | 腎臓・中枢神経 | 腎血流増加、利尿作用、神経伝達調節 |
性腺
卵巣
卵巣は卵胞と黄体から女性ホルモンを分泌します。
卵胞膜:エストロゲン分泌
黄体:プロゲステロン分泌
妊娠中には胎盤の絨毛膜からヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)が分泌され、黄体を刺激してプロゲステロン分泌を促進し、妊娠を維持します。
| ホルモン名 | 標的組織 | 作用 |
|---|---|---|
| 卵胞ホルモン(エストロゲン) | 子宮・膣・乳腺など | 女性第二次性徴の発現 子宮内膜の肥厚、卵胞発育促進 |
| 黄体ホルモン(プロゲステロン) | 子宮・乳腺 | 子宮内膜の分泌期維持、妊娠維持 乳腺発達促進 |
精巣
精巣の間細胞(ライディッヒ細胞)から男性ホルモンであるテストステロンが分泌されます。
| ホルモン名 | 標的組織 | 作用 |
|---|---|---|
| テストステロン | 精巣・筋肉・骨・生殖器官など | 男性第二次性徴の発現 精子形成、筋骨格系の発達促進 |
消化管
消化管ホルモンは主に小腸や胃から分泌され、消化酵素や胆汁の分泌を調整します。
| ホルモン名 | 標的組織 | 作用 |
|---|---|---|
| ガストリン | 胃 | 胃酸分泌促進、胃粘膜成長促進 |
| セクレチン | 膵臓・胃 | 膵液(重炭酸)分泌促進、胃酸分泌抑制 |
| コレシストキニン(CCK) | 膵臓・胆嚢 | 膵酵素分泌促進、胆嚢収縮、胃排出抑制 |
腎臓
腎臓は尿生成のほか、内分泌器官としても重要な働きを担います。特に血圧や造血の調整に関わるホルモンを分泌します。
| ホルモン名 | 標的組織 | 作用 |
|---|---|---|
| レニン | 血漿中のアンジオテンシノーゲン(肝臓由来) | アンジオテンシンI→IIに変換を促進 →副腎皮質からのアルドステロン分泌促進 →血圧上昇・ナトリウム保持 |
| エリスロポエチン(EPO) | 骨髄の造血幹細胞 | 赤血球の分化・増殖促進(貧血対策ホルモン) |
🌟ホルモンと疾患との関係
ホルモン異常による疾患は国家試験で頻出です。
以下に主なホルモンとその異常に伴う疾患を整理します。
| ホルモン | 状態 | 代表的な疾患 |
|---|---|---|
| 成長ホルモン(GH) | 亢進 低下 | 【亢進】巨人症(成長期)、末端肥大症(成人) 【低下】下垂体性小人症 |
| 下垂体前葉ホルモン | 低下 | シモンズ病(汎下垂体機能低下症) シーハン症候群(分娩後虚血による) |
| バソプレシン(ADH) | 低下 | 尿崩症(腎性・中枢性) |
| 甲状腺ホルモン(T3・T4) | 亢進 低下 | 【亢進】バセドウ病(甲状腺機能亢進症) 【低下】粘液水腫(成人)、クレチン症(小児) |
| パラソルモン(PTH) | 亢進 低下 | 【亢進】骨粗鬆症・汎発性線維性骨炎 【低下】テタニー(手足の痙攣、Chvostek徴候など) |
| インスリン | 亢進 低下 | 【亢進】低血糖症 【低下】糖尿病(I型・II型) |
| アルドステロン(電解質コルチコイド) | 亢進 | 原発性アルドステロン症(コン症候群) |
| コルチゾール(糖質コルチコイド) | 亢進 | クッシング症候群 |
| 副腎アンドロゲン | 亢進 | 副腎性器症候群(女性における男性化) |
| 副腎皮質ホルモン全般 | 低下 | アジソン病(慢性副腎皮質機能低下症) |
🌟ホルモンの科学的分類と性質
ホルモンはその構造・溶解性・作用機序により、以下のように分類されます。
- ステロイドホルモン(脂溶性):副腎皮質ホルモン(コルチゾール・アルドステロンなど)、性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン・テストステロン)
- アミン類ホルモン:カテコールアミン(アドレナリン・ノルアドレナリン・ドパミン)、甲状腺ホルモン(T3・T4)
- ペプチドホルモン(水溶性):上記以外のほとんど(インスリン、グルカゴン、バソプレシン、成長ホルモンなど)
🌟ホルモンの作用機序
ホルモンはその性質により、標的細胞の受容体への作用部位が異なります。
- 細胞膜上の受容体に作用(速効型)
ペプチドホルモン、カテコールアミン
例:インスリン → 細胞膜に結合 → グルコース取り込み促進 - 細胞内受容体に作用(遅効型)
ステロイドホルモン、甲状腺ホルモン
例:コルチゾール → 核内受容体 → 転写調節 → タンパク質合成
🌟ホルモンの分泌調整メカニズム
ホルモン分泌は精密なメカニズムで制御されており、代表的な調整方式は以下の通りです。
- 階層的支配
視床下部 → 下垂体前葉 → 末梢内分泌腺 の順に命令が伝達される - 負のフィードバック
末梢ホルモンが視床下部・下垂体に働きかけて分泌を抑制(例:T3・T4) - 自律神経・血中成分による調節
血糖、Ca²⁺濃度、浸透圧などの変化で直接分泌される(例:インスリン、パラソルモン) - 生体リズム
コルチゾール・成長ホルモンなどは日内リズムで分泌(睡眠と深く関係)