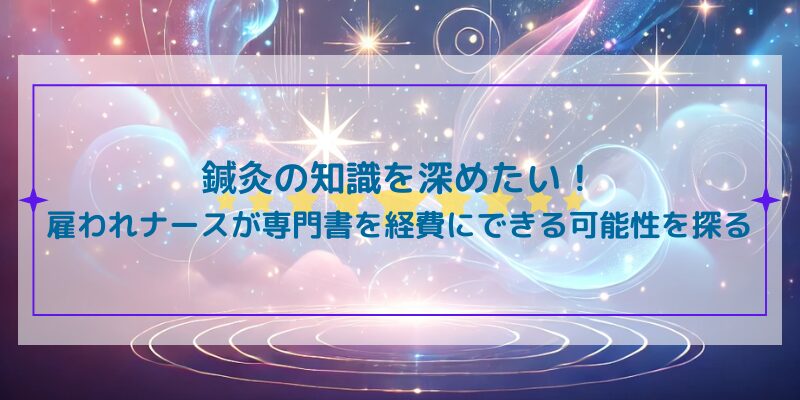こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
🌟経費とは?雇われナースと個人事業主の違い
鍼灸の勉強に必要な専門書って本当に高いですよね。
特にマイナーな分野の本は出版部数が少ないため、価格が高騰しやすくなっています。
たとえば、重症心身障がい児のケアに関する専門書や、すでに絶版になってしまった書籍は、中古でも数千円から数万円することがあります。
実際、鍼灸学生の間で人気の「ツボ単」は新品が販売されておらず、フリマアプリや中古書店でプレミア価格になっていることも珍しくありません。
「欲しいときに買っておかないと、手に入らなくなる」という危機感から、Kagayaも少し高くても書籍を買い揃えるようにしています。
しかし、時給2,000円のパートナースにとって、毎月数冊の専門書を購入するのはなかなか大きな負担です。
SNSや知り合いから「経費で落とせばいいじゃん」と聞くたびに、「そもそも経費って何?」という疑問がわいてきました。
調べていくうちに、「開業準備中でも『開業費』として計上できる可能性がある」ということを知り、これはきちんと整理しておこうと思ったのです。
これから鍼灸師として独立を目指すなら、確定申告や節税についてもしっかり学ぶ必要があります。
この章では、そもそも経費とは何か、雇われナースと個人事業主の違い、そして今から準備できることについて解説していきます。
🌟経費とは?雇われナースと個人事業主の違い
経費(必要経費)とは、「収入を得るために直接必要な支出」のことを指します。
たとえば、商品を仕入れるための費用や、宣伝のためのチラシ作成費、仕事に使うスマホの料金、そして専門書の購入費などが該当します。
こうした経費を確定申告で申請することにより、課税対象となる所得(=収入から経費を差し引いた額)を減らすことができるため、納税額が少なくて済むのです。
会社員やアルバイトなどの「給与所得者」は、経費を個別に申告することはできず、「給与所得控除」というあらかじめ決められた額しか差し引けません。
年収が増えると税金も増えますし、扶養や配偶者控除があっても微々たる差にしかならないケースが多いです。
一方で、個人事業主は「売上-経費=所得」という仕組みのため、たとえば年間売上が600万円でも、経費が700万円かかっていれば、所得はマイナス100万円=赤字となり、所得税はゼロ。
住民税や国民健康保険料も抑えられる可能性があります。
街中で「都営住宅に住んでいるのにベンツに乗ってる人」を見かけたことがありませんか?
不思議に思っていましたが、これこそ“経費マジック”なのかもしれません。
見かけは贅沢でも、帳簿上は赤字。
課税される所得が少ないため、非課税世帯として各種支援が受けられる可能性すらあります。
もちろん、何でもかんでも経費にできるわけではありませんし、あまりに過剰な申請は税務署に目をつけられてしまいます。
ただ、事業に関係していると正当に説明できるものは、堂々と経費として扱って良いのです。
給与所得者には真似できない、これが個人事業主だけに許された「経費活用」という強み。
だからこそ、Kagayaも雇われナースのままで終わるのではなく、鍼灸師として独立する道を選びました。
🌟鍼灸師として申請できる具体的な経費項目
ここでは、Kagayaが実際に調べたり先輩開業鍼灸師から聞いたりした「経費にできる支出項目」について紹介していきます。
あくまで“事業に関連する支出”であることが前提ですが、知っておくことで節税の幅が大きく変わります。
- 広告宣伝費: ホームページ作成、チラシ印刷、ロゴ制作、パンフレット配布など。ネット広告費も含みます。特にSNS広告は費用対効果が高く、開業初期における集客の鍵です。
- 通信費: 業務用スマホの契約費、LINE公式アカウント、Zoom、電話代、インターネット通信料など。プライベートと分けるためにも仕事専用端末の導入がおすすめです。
- 地代家賃: サロンや施術所のテナント家賃、自宅兼用スペースの按分、駐車場代など。按分する場合は「床面積割合」や「使用時間割合」で計算し、根拠のメモを残すと安心です。
- 仕入費: 鍼、お灸、カッサ、精油、オイル、消毒液、ディスポ鍼、衛生用品など。開業前のまとめ買いは「開業費」として計上可能です。
- 水道光熱費: 電気・ガス・水道代。冬場の灯油・暖房費もOK。自宅兼用の人は領収書とメーター数を写真で残すと良いです。
- 旅費交通費: 勉強会や市場調査、視察出張の交通費・宿泊費。観光も兼ねる場合は旅程メモや勉強資料を保存し、事業との関係性を記録しておきましょう。
- 接待交際費: 他の治療家との交流、患者さんへのお茶菓子、紹介元への挨拶など。用途や相手の属性を書いたメモがあると説明しやすいです。
- 消耗品費: ティッシュ、トイレットペーパー、タオル、文房具、掃除用品、スリッパ、芳香剤など。意外と多い日常的な備品は定期的に見直しましょう。
- 減価償却費: 高額な物品(10万円以上)のパソコン、施術ベッド、空気清浄機、冷暖房機器などは耐用年数に応じて分割処理します。例:パソコンは4年。
- 新聞図書費: 鍼灸・看護の専門書、経営・会計書籍、開業マニュアル、セミナー資料など。Kagayaも『無税入門』や『治療院開業マニュアル』を購入済です。
- 車両費: 訪問鍼灸で使う軽自動車のガソリン代、保険料、車検費、タイヤ代など。プライベートと兼用なら走行距離の按分が必要になります。
- 取材費: 同業調査を兼ねた他院の施術体験、美容鍼や整体の視察費。税務署から聞かれたときのためにレポート的な記録を残しておくと無難です。
- 諸経費: 鍼灸学会の年会費や研究会の登録料、資格更新費、イベント出展料なども該当します。
これらを経費として認めてもらうには、必ず「記録・保存・説明」がカギになります。
Kagayaは「仕事用財布」「仕事用スマホ」「事業用通帳」を明確に分けて管理していく予定です。。
レシートはノートに貼って用途をメモ、クラウド会計アプリに随時登録しておくと、確定申告時の手間が激減します。
個人事業主にとって経費は「合法的に税金を減らす仕組み」です。
怖がらず、正しく賢く使っていきましょう。
🌟開業前の書籍は「開業費」でOK?
ここまで紹介した経費は、「すでに開業している」個人事業主が対象となります。
では、まだ開業届を出していないKagayaのようなケースでは、現在購入している鍼灸関連の本や開業準備にかけたお金はどう扱えばいいのでしょうか?
実はそれらは「開業費(繰延資産)」という形で、開業後に経費として処理することが可能です。
開業費とは、事業を始めるための準備にかかった費用のことで、個人事業主として活動を開始した年にまとめて申告することができます。
たとえば、以下のような支出が「開業費」として計上可能です:
- 鍼灸・東洋医学関連の書籍、DVD、電子教材など
- 名刺印刷やチラシ作成など、事業開始の準備に必要なアイテム
- 開業セミナー、経理・税務の勉強会などへの参加費用
- 物件探しのための交通費、下見時の宿泊費
- ウェブサイトやSNSアカウントの初期設計・制作費
重要なのは、「開業前の費用でも領収書や明細をしっかり保管しておくこと」です。
どんな目的で支払ったのか、日付と金額と用途を記録しておけば、開業後の確定申告で開業費として一括または分割で経費処理できます。
ただし注意点として、国家資格の取得にかかる費用(鍼灸学校の学費など)は開業費として計上できません。
これは“事業の準備”ではなく“資格取得”のための支出として扱われるため、税務上の取り扱いが異なるからです。
Kagayaも、現在はまだ学生の立場でありながら、将来の開業に向けて書籍や教材をコツコツと集めています。
それらの購入履歴やレシートは封筒にまとめて保管し、開業届を出すタイミングで「開業費」に計上する予定です。
ポイントは、「開業届を出す前にかかった費用」でも、事業に直接関係しているものであれば、立派な開業費として認められるということです。
ぜひ、今からでも記録・管理を始めてみましょう。
🌟パート+個人事業主の併用が最強な理由
「鍼灸で独立したい」と思っても、いきなり個人事業主として食べていくのは難しいのが現実です。
Kagayaのように、すでに応援してくれる患者さんが数人いたとしても、それだけで生活を成り立たせるのは至難の業。
特に開業初期は、経費もかさみますし、安定した売上が見込めない時期が続きます。
そこでおすすめなのが、「パート勤務」と「個人事業主としての活動」を並行する働き方です。
これは収入のリスクヘッジになるだけでなく、保険・税金・精神的安定の面でも大きなメリットがあります。
以下に、Kagaya自身も実践予定の“ハイブリッドワーク”の利点をご紹介します。
収入が安定する
個人事業主としての収入は不安定ですが、パート勤務があることで毎月一定の給与収入が確保されます。
たとえ売上がゼロの日が続いたとしても、生活費をパート収入でまかなえるという「安心感」は何物にも代えがたいです。
特に開業初年度は、収入よりも支出のほうが多くなることもあるため、Wワークは大きな助けになります。
社会保険に加入できる
パートで一定の労働時間・給与条件を満たしていれば、社会保険に加入することができます。
これは健康保険と厚生年金に同時加入できる仕組みで、保険料の半額を事業主(会社)が負担してくれます。
つまり、国民健康保険や国民年金よりも負担が軽く、保障も厚いということです。
老後の年金額が増えるだけでなく、病気や事故など“もしも”のときには障害年金や傷病手当など、思わぬ形で助けになる制度も充実しています。
独り身であるKagayaにとっても、将来どうなるかわからないからこそ、この制度を活用しない手はないと感じています。
節税ができる
パートで得た給与所得と、個人事業で出た赤字(必要経費が売上を上回る場合)を「損益通算」できるのも、このスタイルの魅力のひとつ。
たとえば、パート収入が年間200万円、個人事業が-50万円の赤字なら、所得は150万円とみなされ、税額が軽減されます。
また、医療費控除や生命保険料控除、扶養控除なども加味すれば、最終的に課税所得がゼロまたはマイナスになり、所得税・住民税ともに非課税になる可能性もあります。
Kagayaのようにパート先で源泉徴収されていれば、年末調整や確定申告で税金が戻ってくることも。
「稼ぎながら赤字が出せる」という一見不思議な状態こそ、パートと個人事業主の併用による強みです。
もちろん、実態のある活動と帳簿管理が前提ですが、しっかり計画的に動けば節税効果は絶大です。
収入を安定させつつ、社会保険に守られながら、将来の独立に向けた準備もできる——それがこの“ハイブリッドな働き方”の最大の魅力だとKagayaは考えています。
🌟確定申告について
会社勤めの方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、個人事業主にとって「確定申告」は避けて通れない大切な手続きです。
ですがご安心ください。
確定申告は、思っているほど難しいものではありません。
現在では、e-Taxという国税庁のオンラインシステムを使えば、スマートフォンやパソコンから簡単に申告ができます。
以前はマイナンバーカードリーダーなどの機器が必要でしたが、今ではスマホ1台でも申告が完結します。
やることはシンプルで、源泉徴収票やレシート、必要な控除(医療費、生命保険料、住宅ローンなど)の情報を入力して送信するだけです。
国税庁の公式サイト「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」から、誰でも無料で利用できます。
わからない箇所があれば、サイト内にある手引きやQ&A、さらには動画解説もとても充実しています。
また、確定申告の時期(例年2月中旬~3月中旬)になると、税務署や市役所でも申告相談の窓口が設置され、職員さんが丁寧に対応してくれます。
初めての方でも、必要書類さえ揃っていれば安心です。
青色申告と白色申告の違い
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。
青色申告を選ぶと、65万円または55万円の控除が受けられ、さらに赤字を3年間繰り越せるなど多くのメリットがあります。
Kagayaも開業時は青色申告にする予定です。
確定申告で必要なもの
- マイナンバーカード(または通知カード)
- 源泉徴収票(パート収入がある場合)
- レシートや領収書(経費の証明)
- 医療費や保険料の証明書
- 帳簿(収支内訳書 or 青色決算書)
- e-TaxのID・パスワード(初回は税務署で取得)
帳簿はExcelやクラウド会計ソフト(freee、やよいの青色申告など)で作成しておくと便利です。
これらのツールでは、確定申告書類も自動で作成できます。
なお、赤字になった年の所得は、翌年の黒字と相殺できる(損益通算)ため、記帳と申告は毎年行うのがベストです。
確定申告をきちんと行うことで、還付金が戻ってくることもありますし、控除を受けられて節税につながる場合もあります。
申告を面倒がって放置すると、税金を払い過ぎたり、逆に延滞税が発生するリスクもあるので注意しましょう。
正しい申告と記帳で、賢く安心して個人事業を育てていきたいですね。
🌟まとめ
今回は、鍼灸師として独立する際の「経費」や「開業費」、そして「個人事業主としての働き方」について、実体験や調査をもとにまとめてみました。
雇われナースとして働いているだけでは見えなかった世界が、節税や確定申告の知識を持つことで、こんなにも違って見えるとは思いませんでした。
特に、開業前の準備費用でも「開業費」として計上できるというのは、これから開業を目指す方には知っておいて損はないポイントです。
「個人事業主+パート勤務」という働き方も、リスクを分散しながら安定収入と挑戦の両立が可能になる選択肢です。
節税は「ズル」ではありません。
国が認めた制度を上手に活用することが、これからの時代を生き抜く力になると思います。
Kagayaもまだまだ勉強中ですが、「自分らしい鍼灸のかたち」をつくるために、できることから一歩ずつ進めています。
この記事が、これから開業を考える方や、個人事業と副業の両立を目指す方の参考になればうれしいです。
🌟おすすめ書籍・アイテムで開業準備をもっとスムーズに!
✅完全版 無税入門 文庫版
節税の考え方が初心者にもわかりやすい、Kagaya愛読の一冊。
開業前に必読です!
✅はじめての鍼灸マッサージ治療院 開業ベーシックマニュアル
開業届の出し方から運営まで、具体的に書かれている実用書です。