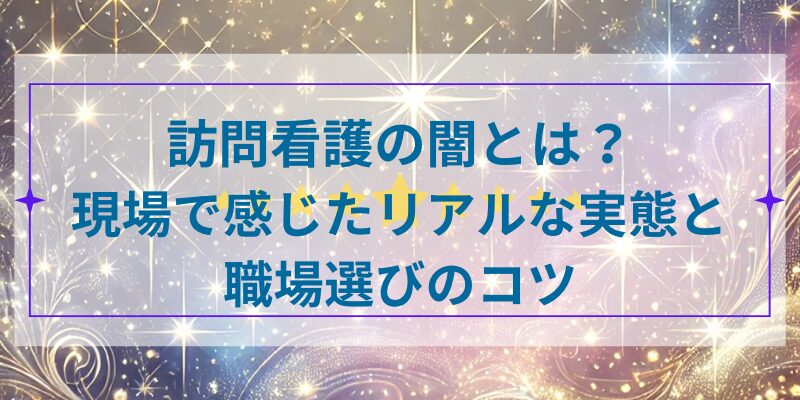こんにちは~。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
「訪問看護」と聞いて、皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか?
「病院よりもゆったりしてそう」「自分のペースで働けそう」「家に行く看護ってなんだかかっこいい」など、良い印象を持たれている方も多いと思います。
実際、私自身も初めて訪問看護という言葉を知ったとき、「自由なスタイルで、人とじっくり向き合える看護ができそう」というワクワク感を抱いていました。
しかし、現場に足を踏み入れてみると、そのイメージとは少し違う現実も見えてきます。
もちろん、やりがいや魅力もたくさんあります。
でも、表からは見えにくい、いわゆる“訪問看護の闇”と呼ばれるような部分があるのも事実です。
たとえば、悪天候の日でも外に出なければならない過酷さ、人間関係の密な職場環境、オンコールで夜中に呼び出される緊張感、営業ノルマが課せられるストレス、そして制度の隙間を突いたような運営方針など……。
「こんなはずじゃなかった」「こんなに大変だとは思わなかった」と戸惑う新人さんも少なくありません。
でもだからといって、訪問看護が悪い仕事かというと、決してそんなことはありません。
むしろ、自分の価値観や働き方に合っていれば、これ以上ないほどやりがいのある仕事だとKagayaは思っています。
この記事では、Kagaya自身が訪問看護の現場でリアルに体験してきた「闇」とも言える出来事を、包み隠さずお話ししていきます。
ただし、誰かを非難する目的ではありません。
「こんなこともあるんだな」「自分ならどう向き合えるかな」といった視点で、訪問看護という働き方を現実的に考えるきっかけになればうれしいです。
これから訪問看護にチャレンジしようとしている方や、今まさに現場で悩みを抱えている方にとって、少しでもヒントや安心材料となりますように。
では、さっそく本題に入っていきましょう。
🌟訪問看護の「闇」と感じた瞬間
悪天候でも休めない現場
訪問看護の現場では、「どんな天候でも行くのが当たり前」という空気が今なお根強く残っています。
利用者様のご自宅に訪問して、直接ケアを行うという特性上、天気に関係なく訪問スケジュールは基本的に変わりません。
晴れの日はもちろん、台風の日、猛暑日、雪の日、強風の日であっても、「必要なケアがあるなら行くしかない」と判断されることが多いのです。
Kagayaも実際に、台風が接近している中、強風と豪雨の中で訪問を続けた経験があります。
「今日は中止にしましょう」と言える事業所もありますが、実際はそういった判断がなされるのは稀。
とくに訪問看護が収益事業として運営されている法人では、訪問をキャンセルすることは即ち収入減につながるため、強行スケジュールが組まれることも少なくありません。
さらに厳しいのは、移動手段が自転車やバイクの場合です。
Kagayaがかつて勤めていたステーションでは、スタッフの多くが電動自転車で訪問しており、夏場は熱中症リスクと闘いながらの業務、冬は手足の感覚がなくなるような寒さの中での訪問が続いていました。
ある日、大雪が降った翌朝、雪かきも不十分な道を自転車で滑りながら訪問した同僚が転倒し、骨折してしまうという事故がありました。
それでも、その事故の翌週には「勤務表通りで」と指示があり、Kagaya自身も「これって普通なの?」と疑問を抱きました。
もちろん、緊急性が高い利用者様の訪問が必要なこともあります。
でも、本来は「職員の安全あってのサービス」であるべきです。
命を守る看護の仕事が、看護師自身の命を脅かすような状態になってしまっては、本末転倒ですよね。
安全に働ける環境があるかどうかは、求人を選ぶうえでとても大事なポイント。
求人情報だけではわからないことも多いですが、「悪天候時の対応はどうなっていますか?」と面接時に確認しておくのがオススメです。
また、訪問手段が自家用車なのか、事業所貸与の車なのか、自転車なのか、そして荒天時の判断基準(稼働or中止)を誰がどう決めるのかなども確認しておくと、後から「こんなはずじゃなかった…」というギャップを防げます。
「雨でも、風でも、雪でも、あなたのところに行くよ」——そんな信頼が訪問看護の魅力であることは間違いありません。
でも、自分の健康と安全も、同じくらい大切にしてほしいとKagayaは心から思います。
人間関係が“濃密”すぎることも
訪問看護のステーションは、基本的に小規模な運営が主流です。
1つの事業所に所属する看護師の人数は、平均して3~6人程度。
大規模病院の病棟と比べれば、はるかに少人数です。
この「少人数制」がうまく機能すれば、風通しの良い職場環境になり、相談しやすく、お互いをよく理解し合えるというメリットもあります。
しかし、その反面、人間関係の距離が近すぎてしまうことで、ストレスやトラブルの原因になることも少なくありません。
とくに事務所での待機時間に、気まずい相手と2人きりになる場面……これは精神的にかなりつらいです。
Kagayaも実際に、ある先輩スタッフとの関係がこじれてしまった時期がありました。
その方はとても仕事ができる方でしたが、人に厳しく、自分のやり方を強く主張するタイプで、朝の申し送りの段階からピリピリした空気に……。
気にしすぎかもしれませんが、自分が出勤する日だけ口数が少ない、書類の受け渡しが素っ気ない、そんな些細なことでも、人間関係に敏感な時は心がすり減ってしまうのです。
もちろん、訪問に出てしまえば1人の時間を持てます。
しかし、帰ってきたときにギスギスした雰囲気が漂っていたり、グループLINEのやり取りが冷たかったりすると、その一瞬で気持ちが沈んでしまうことも。
また、少人数ゆえに「派閥」や「一部の人間だけでの情報共有」といった、閉鎖的な人間関係が生まれてしまうケースもあります。
例えば、ある利用者さんの対応方針について「聞いてない」「私は知らされてない」というすれ違いが起きたときに、「それって私への当てつけ…?」と被害妄想が膨らむほど、心が疲れてしまうこともありました。
看護の質を高めるうえでコミュニケーションは非常に重要ですが、それが「濃密すぎる」「近すぎる」と逆に負担になってしまうのが、訪問看護の難しさだと感じています。
また、上司やリーダーの存在も非常に大きな影響を与えます。
トップの人が柔軟で思いやりのあるタイプであれば、職場の雰囲気は自然と穏やかになりますが、逆に感情的・高圧的なリーダーの場合、職員全体が萎縮してしまうことも。
訪問看護は「ひとりで看護する」仕事ですが、「ひとりで悩む」仕事ではありません。
だからこそ、相談できる関係性、安心して過ごせる空間があることは、働き続けるうえでとても大切です。
見学や面接の際は、できるだけスタッフの雰囲気を見て、「ここでなら人として尊重されながら働けそうか」を自分なりに感じ取ってみてくださいね。
人間関係が良い職場は、それだけで「また明日も頑張ろう」と思える原動力になります。
オンコールに振り回される
訪問看護を続けていると、避けて通れない課題のひとつが「オンコール」です。
訪問看護ステーションの多くでは、夜間・休日対応のためにオンコール体制を導入しています。
これは医療法人でもない限り、ほとんどのステーションで実施されています。
オンコールの担当は、事業所によって様々です。管理者のみが担当するケースもあれば、スタッフで持ち回り制にしているところもあります。
一見「持つだけなら大丈夫そう」と感じるかもしれませんが、実際にはその負担は決して軽くありません。
特に精神疾患を抱える利用者様や、高齢者住宅と提携しているステーションでは、夜間や休日の問い合わせが頻繁にあります。
例えば、「今日は眠れない」「不安が強い」などのメンタル系の訴えが深夜に入り、30分以上電話で話を聞いて落ち着かせる必要があることもあります。
また、「この間も訪問したばかりなんだけど…」という内容で、すぐに駆けつける必要がないような相談が長引いてしまうこともあります。
高齢者住宅では、夜間スタッフが看護師にすぐ頼りがちで、「発熱」「息が苦しそう」「転倒していないか確認してほしい」など、実際に訪問が必要になるケースも多いです。
Kagayaもかつて、深夜2時に「お腹が痛い」と言われて起こされ、内服を促すだけのために高齢者住宅へ訪問した経験があります。
こういったオンコール対応は、実働が少ない月もありますが、精神的な緊張感は常に伴うのが現実です。
「今日の夜は鳴るかもしれない」「寝ていてもいつ呼ばれるか…」という緊張感の中での生活は、地味にストレスがたまります。
また、オンコール手当の扱いも事業所によってまちまちです。
「基本給に含まれています」とされ、実際に何件も電話対応や訪問をしても、追加手当が一切出ないというケースもあります。
正直、それはかなりつらいです。
最近では、「オンコールなし」や「外部コールセンターと連携してオンコールを軽減している」ステーションも増えてきました。
また、小児特化や自費訪問型など、一部の事業所ではオンコール体制を取っていないところもあります。
大切なのは、自分のライフスタイルと合うオンコール体制かどうかを、あらかじめ確認しておくこと。
求人票にオンコールの詳細が書かれていないことも多いので、面接時に必ず以下の項目を確認しておくのがおすすめです:
- オンコールの頻度(月に何回か)
- 誰が持つのか(管理者のみ or 持ち回り)
- 実働があった場合の手当有無
- 訪問対応があるかどうか(電話対応のみか)
- 緊急対応が多い利用者層かどうか
オンコールは、訪問看護の重要な役割のひとつです。
だからこそ、制度設計がしっかりしている事業所を選ぶことで、無理なく、長く働き続けることができるはずです。
営業ノルマを課される職場も
訪問看護師として働くうえで、意外と見落とされがちなのが「営業ノルマ」の存在です。
一般的に、医療法人や社会福祉法人が運営する訪問看護ステーションでは、営業活動を看護師に求めるケースはほとんどありません。
なぜなら、系列病院からの紹介や、地域のケアマネジャーとのネットワークがすでに整っているため、営業しなくても安定して利用者様が集まる仕組みがあるからです。
しかし、株式会社が運営する小規模ステーションでは状況がまったく異なります。
特に、まだ開設して間もない事業所や、地域に根ざした実績がない場合、「看護師が営業も担う」ことが当たり前のように求められることがあります。
Kagayaが過去に勤務したあるステーションでは、毎月の営業目標が明文化されており、実績が低いスタッフには上司から個別指導が行われていました。
「今日は●件ケアマネ訪問してね」「医師に手紙を渡してこよう」と言われるたびに、「私は何の仕事でここにいるんだろう…」というモヤモヤが募っていきました。
もちろん、事業を継続するためには利用者を確保することが不可欠であり、営業活動自体を否定するわけではありません。
ただし問題なのは、それが看護業務と両立できないレベルで要求されることや、営業成績で評価される風潮が現場にあることです。
なかには、訪問の空き時間にアポなしでケアマネ事業所を回らされたり、自家用車で飛び込み営業を求められたりする事例もあります。
「看護がしたくて入職したのに、気づけば営業職になっていた」――これは決して冗談ではなく、現実に起きていることです。
また、営業ノルマを達成できないと、「やる気がない」「協調性に欠ける」といった評価をされ、賞与査定やシフト調整に影響が出るケースもあると聞きます。
このような環境では、看護師が疲弊し、本来の役割を見失ってしまうリスクが高くなります。
営業活動の有無やその内容は、求人票には書かれていないことが多いため、面接や見学の場で必ず以下の点を確認しておくことが大切です。
- 看護師に営業活動は求められるのか?
- 営業の対象(ケアマネ、医師、病院など)は?
- 営業の件数・頻度の目安はあるか?
- 営業活動が評価や給料にどう反映されるか?
もし、営業ノルマがある場合でも、それがチームで分担されているのか、個人責任なのかでも大きく感じ方は変わってきます。
訪問看護は、本来「生活に寄り添い、心と身体を支える看護」です。
営業成績よりも、どれだけ利用者様と信頼関係を築けるかが、何よりも大切な評価基準であってほしいと、Kagayaは強く願っています。
利益優先すぎる運営方針
訪問看護の報酬は、基本的に医療保険や介護保険から支払われる仕組みになっています。
例えば医療保険では、訪問時間が30分でも90分でも、同じ点数(報酬)になることがあり、一定のルール内であれば時間の長短による差はありません。
この制度設計をどう活用するかは各事業所の方針次第ですが、残念ながら「制度の穴を突くような運営」が横行しているステーションもあるのが実情です。
Kagayaがこれまで見てきた中にも、「バイタルチェックだけ」「処置なしで数分滞在」といった、実質5分の訪問を1日2回に分けて実施し、“2回訪問扱い”として報酬請求している事業所がありました。
こういった事業所の多くは、自法人が運営する障がい者グループホームや高齢者住宅に訪問しているケースが多く、外部とのチェックも入りにくい構造になっているのが特徴です。
つまり、訪問看護本来の「在宅での生活を支える看護」とはかけ離れた、“点数を取るための看護”になってしまっているのです。
もちろん、制度の範囲内で効率的に運営すること自体が悪いとは思いません。
ですが、それがあまりに利益優先になりすぎると、現場で働く看護師のやりがいや誇りが失われていくのを感じる瞬間があります。
「この人は今日も同じ時間に、血圧を測るだけでいいのだろうか?」
「この生活に、私たちの関わりは本当に必要なのだろうか?」
そんな疑問が積み重なっていくと、看護師自身が「ただの作業員」のように感じてしまうこともあるのです。
さらに問題なのは、このような訪問実績が「看護実績」としてカウントされ、表面上の稼働率や収益性が評価されることです。
Kagayaの周囲でも、やりがい搾取のような環境に疲れ果てて退職した仲間が何人もいます。
利用者様のために、というよりも、“請求点数のために動く”という感覚が、いつしか働く人の心を削っていくのです。
また、こうした利益優先の運営方針の背景には、国の制度設計そのものの課題もあります。
訪問看護の点数が時間単位ではなく内容や頻度で評価されるため、“短時間・高頻度”の方が経営的に効率が良いという構造が生まれてしまっています。
これは現場にとって非常にやりづらい矛盾であり、看護の本質と制度の論理が噛み合わない問題とも言えます。
だからこそ、求人を見るときには、「利益より人を大切にしているか」という視点で、以下のような点を確認してみてください。
- 訪問1件あたりの時間設定(30分未満ばかりではないか)
- 法人運営の施設ばかりに訪問していないか
- 日報や記録が形式的になっていないか
- 実際のケア内容が曖昧になっていないか
私たち看護師が「本当に意味のあるケア」に集中できる環境こそ、訪問看護の価値を最大限に引き出すカギだと思います。
短時間で稼働をこなすのではなく、「一人ひとりの人生に向き合う看護」ができるステーションを選びたいですね。
🌟それでもKagayaが訪問看護を続ける理由
ここまで、訪問看護の厳しさや“闇”と呼ばれる一面についてお話ししてきました。
「そんなに大変なのに、なんでKagayaさんは続けているの?」と聞かれることもあります。
Kagaya自身、これまで病院、学校、福祉施設など、いろいろな現場で看護師・鍼灸師として働いてきました。
その中でずっと感じていたのは、「同じ空間で、同じ人と、毎日同じような時間を過ごすことの息苦しさ」でした。
病棟勤務では、8時間以上も閉鎖的な空間にいて、ひとつのナースステーションを何人ものスタッフで共有し、食事の時間すら気を遣うことも。
休憩室に入っても、「この人と一緒か…気まずいな」と感じることが続いたり、息をつく間もなくナースコールが鳴り響いたり。
それに比べて訪問看護は、ひとりで訪問に出て、自分のペースで行動できる時間がある。
もちろん、夏は炎天下の中で汗だくになったり、冬は指先がかじかむほど寒かったりします。
雨の日には靴がびしょびしょになったり、風が強くて自転車で転倒しそうになったこともあります。
でも、そうした大変さがあっても、訪問の合間にコンビニでソフトクリームを買ったり、車の中で深呼吸したりする“自分だけのリズム”があることが、何よりもありがたかったのです。
ときには自然の風を感じながら、「今日もがんばってるな、自分」と励ましたり。
誰にも急かされず、誰とも話さない時間があるからこそ、次の訪問でも笑顔で関われる。
この感覚は、建物の中でずっと同じ空気に包まれる勤務形態では味わえないものだと思います。
また、訪問先では利用者様との距離が近く、「お互いに気を使いながらも、人として向き合える関係」を築けるのも魅力です。
病院のように“時間に追われて処置するだけ”ではなく、その人の生活や人生を、まるごと見て関わることができる。
「今日も来てくれてありがとう」「来てくれるだけで安心する」と言っていただけると、「この仕事を続けていてよかった」と思える瞬間があります。
もちろん、すべてが理想通りではありません。ステーションによって方針も人間関係もまったく違いますし、相性の問題もあります。
でも、自分の中で「ここまでは許容できる」「この条件なら頑張れる」とラインを引けるようになれば、訪問看護は想像以上にやりがいのある仕事です。
Kagayaにとって訪問看護は、人間らしさを取り戻せる働き方であり、自分らしく生きるための選択でもあります。
🌟訪問看護に向いている人とは?
訪問看護は、病院とはまったく異なるフィールドで看護を提供する仕事です。
「1人で現場に行くのは不安そう…」「判断を任されるなんて無理かも」と感じる方もいれば、「自分のペースで働けそう」「人と深く関われるのが魅力」と感じる方もいるでしょう。
では実際、どんな人が訪問看護に向いているのでしょうか?
Kagaya自身の経験や、同僚たちを見て感じたポイントを以下にまとめてみました。
- 他人の家に上がることにあまり抵抗がない人
- 在宅医療や地域ケアに興味がある人
- ある程度、自分で判断して動ける人
- 医療処置よりも「対話」や「寄り添い」にやりがいを感じる人
- スケジュールや時間管理が自分でできる人
まず大前提として、訪問看護は利用者様の「生活の場」に入っていく仕事です。
病院では、患者さんが「来る側」ですが、訪問看護では私たちが「お邪魔する側」。
そのため、家庭ごとの生活リズム、文化、価値観に配慮できる柔軟さが求められます。
また、訪問先では基本的にひとりで看護を提供することになるため、判断力や責任感も必要です。
「この処置で大丈夫かな?」「様子を見ていい?医師にすぐ連絡すべき?」など、現場で判断を迫られる場面は意外と多くあります。
とはいえ、最近はスマートフォンやICTツールが普及し、困ったときはすぐに事業所と連絡を取れる体制が整ってきています。
Kagayaが勤務していたステーションでは、LINEワークスやチャットワークなどのツールを使い、リアルタイムで情報共有や相談ができました。
それでもやっぱり、「ある程度のひとり判断に自信が持てるか?」は、訪問看護に向いているかを考えるうえで大切な視点です。
もうひとつの大きなポイントは、“治す看護”ではなく“支える看護”に魅力を感じるかどうか。
訪問看護では、急性期の治療よりも、慢性疾患や高齢者ケア、障がい支援、精神科訪問など、生活に寄り添う看護が中心になります。
点滴や処置よりも、話を聞く、そばにいる、日常生活を整えることの方が多いのです。
だからこそ、「手技が好き」「救急が好き」という人よりも、「人とじっくり関わることに喜びを感じる人」にこそ向いている職場だと思います。
もしあなたが今、「もっと利用者さん一人ひとりと向き合いたい」「マニュアル通りじゃない看護がしたい」と感じているなら、訪問看護という選択肢を前向きに検討してみてほしいです。
あなたの感性と人柄が、誰かの生活を支える大きな力になります。
🌟チェックしておきたい「闇を避ける」求人のポイント
人数構成(看護師3人以下は要注意)
求人を見るとき、意外と見落とされがちなのが「看護師の在籍人数」です。
訪問看護ステーションは、法律上、常勤換算で2.5人以上の看護職員を配置することが義務づけられています。
つまり、極端な話をすれば、常勤2人+非常勤1人というギリギリの体制でも開設は可能なのです。
しかし、実際にそこで働く側としては、「3人以下」という体制はかなりリスキーです。
Kagayaが以前勤めていた事業所でも、看護師が3人しかおらず、誰かが体調を崩すと、その日のスケジュールが一気に崩壊する状況でした。
1人が急に休むと、他の2人で全訪問をカバーしなければならず、「朝から夕方までノンストップ」という日が何度もありました。
また、看護師が3人以下の職場では、オンコールの負担が集中しやすくなるのも大きなデメリットです。
月の半分以上オンコールを持たされている…という方も少なくなく、これでは長く働き続けるのは難しいですよね。
もちろん、個人で立ち上げたステーションなど、小規模でもスタッフ同士の関係が良好で、無理のない運営ができているところもあります。
しかし、大手やチェーン展開の事業所で看護師が3人以下という場合は、退職者が続いて運営が傾いている可能性も否定できません。
そのような職場では、スタッフの定着率が低く、業務の引き継ぎや教育体制も不十分であることが多いです。
「教育制度あり」と書いていても、実際には誰も教えてくれる人がいない…というケースもあり、入職後のギャップに悩む方も多いです。
求人を見る際には、看護師の在籍人数と、職種の内訳(PTやOT、事務職含む)をしっかり確認しましょう。
できれば、見学や面接の際に「今は何名体制ですか?」「前任者が辞めた理由は?」といった質問をしておくと、内部のリアルな事情が見えてきます。
また、1人辞めたら成り立たなくなる職場では、あなた自身の体調不良や家庭の事情による休みすら取りづらくなってしまうかもしれません。
安心して長く働くためには、「最小人数ではない」運営ができているかを確認することが、求人選びの大切なポイントです。
人員に“ゆとり”がある職場は、働く人にも“ゆとり”があります。
オンコールの頻度と手当の有無
訪問看護ステーションを選ぶとき、オンコールに関する制度は必ず確認すべき重要ポイントです。
オンコールとは、夜間・休日の緊急時に備えて携帯電話などを持ち、自宅などで待機する勤務のこと。
すべてのステーションにオンコールがあるわけではありませんが、医療保険を中心に運営している事業所では導入しているところが多く、とくに精神科訪問看護専門や、高齢者住宅と連携しているステーションでは、昼夜問わず電話が鳴るリスクが高くなります。
Kagayaの体験でも、ある精神科特化のステーションでは、夜間の相談電話が毎回30分以上に及ぶこともあり、深夜に起こされることで生活リズムが崩れ、体調を崩したスタッフもいました。
高齢者住宅と提携している事業所では、夜間スタッフが些細なことで連絡してくるケースも多く、「発熱している気がする」「様子がおかしいかも」といった不明確な理由での訪問要請が入ることもあります。
ここで重要になるのが、「誰がオンコールを持つのか」「持ったときに報酬が出るのか」という点です。
制度がしっかり整っているステーションでは、担当のローテーションが明確で、手当(待機手当・実働手当)がきちんと支払われるようになっています。
しかし一方で、「基本給に含まれています」と説明され、電話応対や緊急訪問をしても1円も手当がつかないという事業所も少なくありません。
これは本当にきついです。
特に月に何度もオンコールがまわってきて、休日や夜間にも精神的な緊張感を強いられるにも関わらず、何の報酬もない……。これは、モチベーションの低下や離職につながる大きな要因になります。
オンコールがあるステーションで働く場合は、必ず以下の項目を面接や見学時に確認しておきましょう:
- オンコールの頻度(1ヶ月あたり何回か)
- オンコールを持つのは誰か(全員持ち回り?管理者のみ?)
- 待機手当の金額は?(1回●円 or 月固定)
- 実際に訪問した場合の実働手当はあるか?
- 夜間・休日の対応件数の平均(どのくらい鳴るか)
また、オンコール免除の相談が可能かどうかも重要です。
家庭の事情やWワーク、体調管理の観点から「オンコールは難しい」と感じる場合、それを配慮してくれるかどうかも、働きやすさに直結します。
なかには、オンコール専属のスタッフを置いているステーションや、そもそもオンコールがない運営スタイルを取っているところもあります。
自分のライフスタイルや体調管理に合わせて、「無理なく続けられるかどうか」という視点で求人を比較してみてください。
オンコールの仕組みは、見落とされがちですが、“心身の健康を守るうえで非常に大切なポイント”です。
「どうにかなるだろう」と曖昧にせず、しっかり確認して納得したうえで入職することが、後悔のない選択につながります。
移動手段と訪問間の時間設定
訪問看護において、実は見落とされがちなポイントのひとつが「移動手段」と「訪問スケジュールの余裕」です。
「自転車で訪問します」「社用車あります」と一言で言われても、それが貸与なのか自家用なのか、交通費の支給があるのか、駐車場はどうなっているのかまでを確認しないと、あとから大きな負担になります。
特に移動手段が自家用の電動自転車などの場合、夏は熱中症リスク、冬は凍結した路面での転倒リスクが高く、体力的にも精神的にもきつい場面が増えます。
また、雨の日にレインコートを着て、ずぶ濡れで次の訪問先に向かう…ということも珍しくありません。
Kagayaの知人では、訪問中に転倒し自転車ごと骨折してしまった方もいて、その後の対応や補償について事業所とトラブルになったケースもありました。
そのため、求人を選ぶ際は、以下の点を必ず確認することをおすすめします。
- 移動手段は何か?(徒歩/自転車/車)
- 自家用車や自転車を使う場合、交通費やメンテナンス費は出るか?
- 社用車がある場合、誰が使えるのか?(全員 or 限定)
- 駐車場の確保や運転に関する規定はあるか?
- 雨天・荒天時の訪問方針はどうなっているか?
もうひとつ重要なのが訪問と訪問の合間の時間設定です。
例えば「10:00にA宅」「10:30にB宅」など、移動距離を考慮せずにギチギチに詰められたスケジュールでは、次の訪問先に急ぎすぎて事故のリスクが高まることも。
しかも中には、「移動時間も含めて訪問時間とみなす」という運営方針のステーションも存在し、実質的に訪問ケアの時間が削られてしまうこともあります。
その結果、利用者様との関わりが浅くなり、看護の質も下がってしまうという悪循環に陥るのです。
安心・安全に働くためには、訪問と訪問の間に10〜15分以上の移動・休憩時間が設定されているかを確認しましょう。
見学時にシフト表や1日の流れを見せてもらえると、リアルな勤務感覚がつかめて安心です。
また、「1人あたり何件訪問しているか?」「移動距離はどれくらいか?」など、実際の運用ルールを確認することも大切です。
訪問看護は移動が多い仕事だからこそ、“移動そのものがストレスにならない体制”が整っているかどうかが、働きやすさに直結します。
求人票に記載がなければ、面接や見学で積極的に質問して、自分のライフスタイルや体力に合った職場かどうかを判断していきましょう。
管理者・リーダーの人柄と経歴
訪問看護の職場環境において、最も大きな影響力を持つのが管理者やリーダーの存在です。
これは病院や施設でも同じことが言えますが、特に訪問看護ではスタッフ数が少ない分、リーダーの人柄や価値観がチーム全体の雰囲気を強く左右します。
管理者が支援的で柔軟な姿勢を持っていれば、スタッフは安心して働けます。
一方で、経験が浅く管理職経験もない若手がリーダーをしていたり、年配の管理者が昔ながらの上下関係やハラスメント体質を引きずっていたりすると、ミスマッチやストレスが生まれやすくなります。
Kagaya自身も、過去に「雰囲気が良さそう」と思って入った職場で、実際はリーダーの独断的な運営が続いており、スタッフの声が全く届かない環境だったことがあります。
また、他の看護師さんからは「前の職場で上司と価値観が合わず、心身ともに疲弊して退職した」という話もよく耳にします。
では、どうすれば求人段階でそのリスクを避けられるのでしょうか?
- 管理者の年齢・経験年数・訪問看護のキャリア歴をチェック
- 医療職のバックグラウンド(看護師/理学療法士など)を確認
- 管理職としての実績やマネジメント研修の受講歴があるか
- スタッフの定着率や離職理由について率直に聞いてみる
また、見学を受け入れている事業所であれば、必ず足を運びましょう。
訪問同行ができなくても、ミーティングや休憩中の雰囲気を観察するだけでも得られる情報は多いです。
「管理者がどんな言葉づかいをしているか」「スタッフとの距離感は近すぎず遠すぎずか」「意見を受け入れる空気があるか」など、チェックポイントはたくさんあります。
求人票やホームページには、管理者の理念やメッセージが書かれていることもあるので、それも事前に見ておくと良いでしょう。
もし「なんとなく怖そう…」「ちょっと支配的かも?」と感じたら、直感は意外と当たります。
訪問看護は、チームの支え合いが何より大切です。
だからこそ、安心して相談できるリーダーかどうかを見極めることが、長く働き続けるための第一歩です。
利用者層と看護の内容
求人票やホームページには、給与や勤務時間などの条件はしっかり書かれていても、「どんな利用者さんが多いのか?」「看護の内容はどの程度か?」までは具体的に書かれていないことがよくあります。
けれども、訪問看護の満足度や働きやすさを大きく左右するのは、実はこの“中身”の部分なんです。
たとえば、あなたが「医療的ケアにしっかり関わりたい」「吸引や点滴、終末期ケアをもっと学びたい」と思って入職したのに、実際は清拭とバイタル測定がメイン、なんてことも珍しくありません。
逆に、「精神疾患のある方とじっくり向き合いたい」と思って入ったのに、実際はほとんどが高齢者のADL維持で、傾聴と安否確認ばかりだったというケースもあります。
もちろん、どんなケアにも意味があり、すべての利用者さんにとって必要な看護です。
しかし、自分のやりたい看護とのズレが大きいと、やりがいや成長実感を持ちにくくなることも事実です。
だからこそ、入職前に以下のような点をしっかり確認しておくことが大切です。
- 利用者の主な年齢層(高齢者中心か、障がい児・精神・難病など)
- 1日の訪問件数と、1件あたりの平均所要時間
- 医療処置の内容(吸引、褥瘡ケア、点滴、ストマ、看取りなど)
- 精神疾患の方への対応頻度や、訪問先の環境(家族同居/単身など)
- ターミナルケア・小児・障がいなど、専門分野の有無
これらは面接時や見学時に聞くのも良いですし、事業所のブログやSNSなどから雰囲気を読み取るのも一つの方法です。
また、訪問件数が多い=忙しすぎる/医療処置が多い=大変そう、というわけではありません。
あなたのキャリアビジョンに合っていれば、負荷のある業務でも前向きに取り組めるはずです。
Kagaya自身も、「子どもと関わりたい」という思いで小児や障がい児の訪問に携わっていますが、事業所によってはそのような利用者がいないところも多くあります。
ですから、自分のやりたい看護、身につけたいスキル、関わりたい対象があるなら、それを事前に伝え、マッチするかを見極めることがとても重要です。
「どんな利用者さんと関わるのか」は、看護師の満足度や定着率に直結する部分。
求人票だけではなく、中身のリアルをしっかりチェックしていきましょう。
🌟安心して働ける訪問看護ステーションの特徴
ICT活用で記録・連携がスムーズ
訪問看護は「一人で訪問する」からこそ、情報共有の仕組みが非常に重要です。
最近では、ICT(情報通信技術)を活用した訪問看護ステーションが増えており、電子カルテやチャット機能付きアプリ、AI記録補助ツールなど、さまざまな工夫が取り入れられています。
特に、スマホやタブレット端末からリアルタイムで記録ができる環境が整っていると、ケアの直後に記録が完了でき、帰社後の残業時間を大幅に減らすことができます。
また、電子カルテを通じて医師やケアマネジャーと情報共有できる仕組みがあれば、連携ミスの防止やケアの質の向上にもつながります。
Kagayaがこれまで経験してきた中でも、「LINE WORKS」や「Chatwork」「メディカルケアステーション」などを導入している事業所は、他職種間の情報の行き来がとてもスムーズでした。
訪問中に困ったときも、スマホでチャットを送ればすぐに返答がもらえる安心感があります。
最近ではAIを活用して、報告書や計画書を自動生成できるシステムを導入している事業所もあり、事務作業の負担が大きく軽減されているケースもあります。
たとえば「クラウド型電子カルテ(バイタルリンク・カナミック・iBowなど)」は、音声入力対応や看護記録のテンプレート機能もあり、使い慣れるととても便利です。
とはいえ、ICT機器に苦手意識があるスタッフも少なくありません。実際、Kagayaも音声入力やAI補助機能はまだ上手く使いこなせていません(笑)
紙の記録の方が安心するというスタッフもいますし、大切なのは、ICTの有無そのものではなく「スタッフ全員がストレスなく使えているかどうか」です。
導入していても活用されていなければ意味がありませんし、誰か一人が使いこなせずに困っていると、記録の分担や負担感にも影響してきます。
安心して働けるステーションとは、ICTツールを活用しながら、誰もが「ちゃんと伝えられている」「ひとりじゃない」と感じられる環境があること。
求人を見る際には、「電子カルテの種類」「記録時間の確保」「連絡ツールの種類」「ICT研修の有無」などもチェックしてみてください。
訪問看護だからこそ、ICTの整備状況は“働きやすさ”と“安全なケア”を両立させるカギになります。
チーム制で孤独を感じにくい
訪問看護は、基本的に1人で訪問し、1人でケアを完結させる仕事です。
そのため、「朝の申し送り以降は誰とも話さずに1日が終わる」という日も珍しくありません。
とくに担当制を採用している事業所では、特定の利用者さんを一人で抱える傾向が強く、困りごとや不安を相談しにくい空気になりがちです。
「今日はこんなことがあった」「あの対応でよかったのかな?」
そうした日常の“つぶやき”を共有できる場がないと、孤独や不安は積み重なっていきます。
その点、チーム制を導入している訪問看護ステーションは、スタッフ間で情報や気持ちを共有しやすい体制になっています。
チーム制とは、「全員で全利用者をみる」または「数人の小グループで利用者を担当する」仕組みのこと。
誰かが困っていれば他のスタッフが代わりに訪問することもでき、急なお休みやフォロー対応にも柔軟に動けます。
また、定例のミーティングやケースカンファレンスが設定されている事業所は、スタッフ同士のコミュニケーションが活発です。
「この利用者さん、最近こういう変化があったよ」
「この場面、どう対応したらいいかな?」
そういった日々のやりとりがあるだけで、心理的な安心感や連携力がまったく違います。
また、Kagayaが以前いた事業所では、週に一度の「振り返りの時間」があり、お互いの悩みや成功体験を共有していました。
訪問看護において孤独感は大敵です。
とくに新卒や経験が浅いスタッフは、些細なことで不安になりがちですし、気軽に相談できる環境があるかどうかで離職率も大きく変わってきます。
求人を見るときには、「チーム制か担当制か」「カンファレンスの頻度」「相談しやすい雰囲気があるか」などをチェックしてみてください。
孤独を感じにくいステーションは、職場の定着率が高く、スタッフの満足度も高い傾向があります。
人間関係のストレスを減らしながら、自分らしく看護を続けたい方には、チーム体制が整った事業所をおすすめします。
スタッフの雰囲気が穏やか
どんな職場にも言えることではありますが、訪問看護のように少人数かつ密接なチームで動く現場では、スタッフの雰囲気が何よりも大切です。
「職場の人間関係が悪くて辞めた」という話は、看護の世界では珍しくありません。
Kagaya自身も過去に、LINEや業務連絡ツール上で喧嘩腰なメッセージが飛び交う職場に当たったことがあります。
顔を合わせれば挨拶もそこそこ、申し送り中もピリピリ。
そんな職場では、どんなにやりがいがあっても長く続けるのは難しくなります。
とくに訪問は「1人で動く時間が多い分、拠点での人間関係が心の支えになる」側面があります。
孤独な現場で、戻ってきても相談しにくい、空気が悪い、愚痴ばかり……そんな環境では、心も身体も疲れ切ってしまいます。
逆に、穏やかで思いやりのあるスタッフが揃っている職場は、働きやすさが段違いです。
お互いの負担や感情に配慮しながら、ちょっとした冗談や励ましの言葉が交わされるようなチームは、日々の訪問に行くモチベーションにもつながります。
「ありがとう」「助かりました」「大丈夫?」そんな声がけが自然に飛び交う現場は、緊張を和らげ、スタッフの定着率にも大きく影響します。
また、管理者の人柄が職場の空気を大きく左右します。
「上下関係が厳しく、スタッフの意見が通りにくい」「ミスをすると強く責められる」ような風土があると、萎縮して本来の看護ができなくなってしまうことも。
こうした空気感は、実際に見学してみないとわからない部分でもあります。
可能であれば、見学時に「朝礼の雰囲気」「スタッフ同士のやりとり」「管理者の対応の仕方」などをよく観察してみてください。
訪問に出る前後のひとときが、ほっとできる空間かどうか。
それが、長く安心して働けるかどうかの鍵になるとKagayaは思います。
求人票や条件だけでなく、「この人たちと一緒に働きたい」と思えるかどうかも、職場選びでは大切にしてほしいポイントです。
オンコールが分散されている
訪問看護の働き方を左右する大きな要素のひとつがオンコール体制です。
オンコールとは、夜間や休日などの緊急対応に備えて、携帯電話を持って待機する業務のこと。
利用者の病状によっては、夜間の相談や急変時の対応が求められるため、一定の負担が伴う業務でもあります。
ステーションによっては、管理者が一手に引き受けているところもあれば、スタッフで持ち回り制にしているケースもあります。
また、オンコール自体がない(訪問診療医との契約で対応)というステーションも少数ながら存在します。
ここ数年は「ワークライフバランス」を重視する流れもあり、オンコールの持ち方や頻度を柔軟に調整してくれる職場も増えつつあります。
例えば、子育て中のスタッフには免除したり、回数を減らすなど、家庭の事情に配慮した体制づくりをしている職場もあります。
一方で、スタッフ数が少ない事業所ではオンコールが偏ってしまうこともあり、月の半分以上持たされている、という声も……。
また、オンコールが鳴っても実働手当がつかない、もしくは制度が曖昧なところもあります。
働きやすさは、「制度の明確さ」と「無理なく回せる人数体制」にかかっているといえるでしょう。
見学や面接の際には、以下の点を確認しておくのがおすすめです。
- オンコールは誰が持っているのか?(全員/一部のスタッフ)
- 頻度はどのくらいか?(月◯回、週◯回など)
- 鳴ったときの出動はどの程度あるか?(実際に対応が多いのか)
- 手当はどうなっているか?(待機・実働それぞれ)
- 体調や家庭事情による免除など柔軟な対応が可能か?
Kagayaとしては、スタッフ全員でバランスよく分担しつつ、無理のない範囲で回せる体制が整っている職場が、長く続けやすいと感じています。
オンコールは訪問看護の「裏側のリアル」でもあります。
ライフスタイルや価値観に合った働き方を選ぶためにも、ぜひこのポイントを事前にチェックしてみてください。
研修やカンファレンスが定期的にある
訪問看護は、基本的に一人での判断力が求められる仕事です。
だからこそ、日々の実践を振り返ったり、他のスタッフと情報を共有したりする時間がとても大切。
ところが、スタッフ数が少なく、日々の訪問で手一杯の事業所では、
「研修?カンファ?行く暇ないよ」という雰囲気が蔓延していることも少なくありません。
参加できたとしても、「自分の休みを使って行く」という暗黙の了解がある職場も……。
これではモチベーションも続かず、学びが習慣化されることも難しくなります。
一方で、業務時間内に定期的な研修やカンファレンスの時間を確保している事業所は、スタッフの学びと成長を大切にしている証拠。
こうした職場は、教育体制が整っているだけでなく、風通しがよく、人間関係も良好な傾向があります。
とくに新卒や訪問看護未経験で入る場合、研修があるかどうかは安心感に直結します。
また、カンファレンスで定期的に利用者情報を共有していれば、担当外の利用者についてもチームでサポートし合える風土ができます。
たとえば、以下のような体制があるステーションは、非常に働きやすいといえます。
- 月1回以上の全体カンファレンス(事例検討・利用者情報共有)
- 外部研修の費用補助や勤務扱い
- 新人研修マニュアルの整備
- OJT担当スタッフの配置(プリセプター制など)
- 訪問同行や定期的なフィードバックの時間がある
Kagayaの経験でも、研修やカンファがきちんと行われている職場は、スタッフの定着率も高かったです。
研修=厳しい指導ではなく、学びを楽しめる場であること。
「こんなとき他の人はどうしてる?」「最近の対応で不安だったことがある」など、気軽に話し合える関係性が、訪問看護の安心感につながります。
求人をチェックする際には、単に「教育あり」と書かれているだけでなく、実際にどういう研修やカンファが行われているかを具体的に聞いてみましょう。
入職前に見学や体験同行ができれば、どんなふうに学びを深めている職場かをリアルに知るチャンスにもなります。
「学び続けられる環境かどうか」は、訪問看護を長く続けるうえでとても大切なポイントです。
🌟訪問看護に強い!おすすめ転職サイト3選
「もっと自分らしく働ける職場がいい」「今の職場、ちょっと合わないかも…」
そう感じたとき、次の一歩を安心して踏み出すためのパートナーとして頼れるのが、看護師向けの転職サイトです。
とくに訪問看護は、自由度が高い反面、事業所ごとに働き方や人間関係、教育体制に大きな差があります。
「実際に入ってみたら雰囲気が違った…」という失敗を防ぐためにも、エージェントの力を借りて客観的な情報を得るのはとても重要です。
おすすめは、自己応募+転職エージェントの併用。
気になる事業所があれば自分でも調べつつ、希望条件や不安な点はエージェントに相談して、うまく役割分担するとスムーズに転職活動が進みます。
ここではKagayaもチェックしている、訪問看護に強いおすすめ転職サイトを3つご紹介します。
- ▶ レバウェル看護(旧 看護のお仕事)
▶ 地方にも強く、LINE対応OK。求人数が業界最大級でスピード感がある
LINEで気軽に相談できるので、忙しい現役ナースにもぴったり。非公開求人も多く、地方や訪問看護にも強い印象です。 - ▶ ナースパワー人材センター
▶ 単発・短時間の求人に強く、派遣や応援ナース制度もあり
柔軟な働き方ができるので、「しばらく短時間だけ働きたい」「地方応援ナースで経験を積みたい」という方にもおすすめです。 - ▶ ナースJJ
▶ 匿名で求人検索OK!施設の口コミ情報が見られるのが強み
名前を出さずに情報収集できるので、在職中の方にも使いやすい。転職後のミスマッチを防ぐためのサポートが手厚いのも魅力です。
※訪問看護ステーションの求人選びは、自己開拓+転職エージェントの併用が安心です。
日々の訪問業務や人間関係に疲れて、「もう無理かも…」と思っている方へ。
がんばっている自分を、どうかもっと大切にしてください。
つらい現場に耐え続ける必要はありません。
「環境を変える」という選択肢があることを、どうか忘れないでください。
信頼できる転職サポートを味方につけて、あなたらしい看護ができる場所を一緒に探していきましょう。
🌟合わせて読みたい
- 💡 【保存版】看護師こそ身体が資本!目的別に選ぶ治療院のすすめ
通い分けのコツを解説。Kagayaの体験談つき! - 💡 新卒でも訪問看護に就職できる?失敗しない選び方ガイド
未経験OKなステーションの見極めポイントとは? - 💡 法人別で異なる訪問看護ステーションの特徴と見極めポイント
医療法人・NPO・株式会社…それぞれのメリットと注意点を解説!