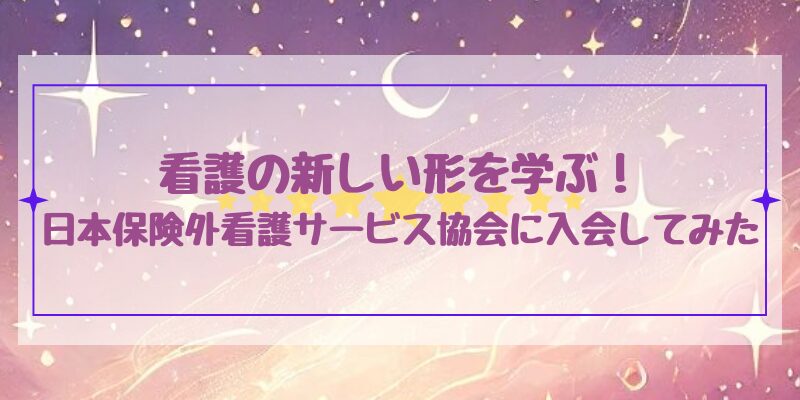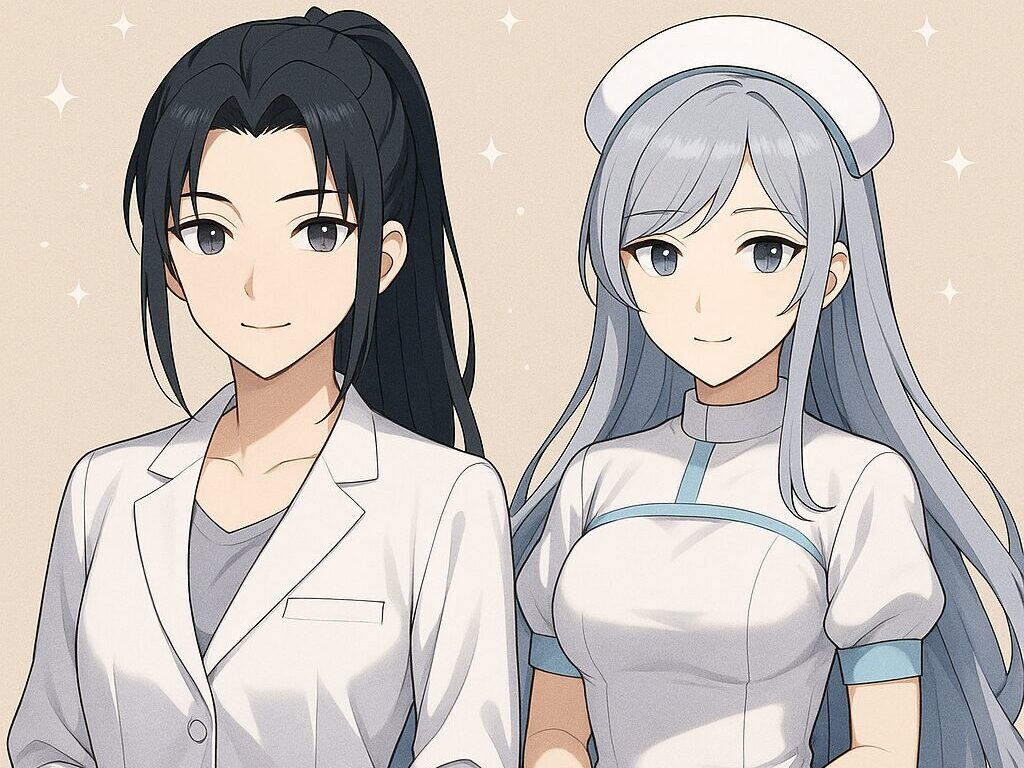
🌟看護師として独立したKagayaが「組織から離れて感じたこと」
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
看護師として長く働いていると、「どこかの団体に所属していること」が一種の安心材料のように感じることがあります。
特に病院や訪問看護ステーションなどに勤務していると、新人時代に半ば強制的に加入させられるのが「日本看護協会」。
Kagayaも例に漏れず、看護師1年目のころに「とりあえず入っておくように」と言われるがまま加入しました。
入会金、年会費、それに加えて研修費……けっこうな出費です。
しかし、実際に協会に加入してみて感じたのは、それに見合ったメリットがほとんど実感できなかったということでした。
たしかに、研修には割引価格で参加できたり、会報が届いたりはします。
でも、日々の臨床現場で本当に役に立つ情報がどれだけあるかというと……私にとっては「あまり恩恵を感じられなかった」のが正直な感想でした。
その後、Kagayaは看護師4年目で最初の職場を退職。
そのタイミングで、看護協会も思い切って退会しました。
協会を辞めてから十数年が経ちますが、特に困ったことはありません。
働いている職場で必要な研修を受ければ十分でしたし、インターネットで情報を得たり、現場で経験を積む中で自然と知識やスキルは増えていきました。
ですが、そんなKagayaの考え方が大きく変わったのは、独立してフリーランスとして活動を始めたときです。
これまでのように「職場を通して情報が勝手に入ってくる」わけではなくなり、制度改正や業界動向、他の看護師の働き方などをキャッチするのがとても難しくなったのです。
「このままでは取り残されるかも……」という不安。
「自分のやっていることが制度的にグレーじゃないかな?」というモヤモヤ。
「そもそも看護師が“開業”するって、どういうこと?」という疑問も含め、調べることが一気に増えました。
そんな中で感じたのは、「やっぱり、ひとりでは限界がある」ということ。
職場に守られていた頃には見えなかった、独立開業者としての“情報の孤立”を痛感しました。
そこで改めて、「本当に自分のしたい活動に近い団体やコミュニティに所属したい」と思うようになりました。
たとえ有名な団体でなくても、自分のビジョンに共感してくれる仲間がいる場所の方が、はるかに価値があると気づいたのです。
こうして、Kagayaは「日本保険外看護サービス協会」という団体に出会うことになります──。
🌟自費看護サービスの開業ってどうするの?
看護師としての経験を積む中で、Kagayaは次第に「もっと柔軟な形で看護を提供したい」と思うようになりました。
高齢者や障がいを持つ方、子育て中のご家庭など、「本当に必要なケア」が保険制度の枠に収まらないケースを日々目にしてきたからです。
そこでKagayaがたどり着いたのが、「鍼灸×看護のハイブリッドケア」という新しいスタイル。
鍼灸の技術で自律神経を整えたり、疼痛緩和を図ったりしながら、看護師としての視点で生活支援・医療的ケアにも対応する──そんな自費訪問サービスを始めたいと考えました。
でも、いざ動き出そうとすると、壁にぶつかります。
調べても調べても、自費での看護サービスの「正解」が見えてこないのです。
たとえば、こんな疑問が次々に浮かびました。
- 税務署への開業届は必要?
- 保健所へも何か届け出が必要なの?
- 医療的ケアを行うには医師の指示書が必須?
- そもそも看護師って“開業”できるの?
ネットで「看護師 開業」と検索すれば、確かにたくさんの記事が出てきます。
でも、そのほとんどは医療保険を活用した訪問看護ステーションの設立方法について。
法人格の取得、看護職員の常勤配置、契約医との連携、都道府県への指定申請……など、制度に沿った“事業所”としての始め方が解説されています。
それに対して、Kagayaがやりたいのは、もっと自由で個人に寄り添った支援。
医療保険や介護保険に縛られない「保険外・自費」の訪問サービスです。
ところがこの分野はまだ前例が少なく、書籍やネット記事でも情報がとても限られています。
「個人事業主としての届け出は必要そうだけど、保健所への提出義務は?」
「医療行為って、どこまでがOKで、どこからがグレーなの?」
「看護師が“店舗を持たない出張サービス”を行うには、法的にどんな注意点があるの?」
……調べれば調べるほど、疑問は増えていく一方でした。
しかも、役所に問い合わせても明確な答えが返ってこないことも多く、「制度のはざま」で手探り状態になるのが、自費看護の難しさだと痛感しました。
そんな中、Kagayaは「このまま一人で調べ続けるのは限界がある」と感じ、情報を求めてコミュニティを探し始めます。
🌟出会ったのは「日本保険外看護サービス協会」
自費で看護サービスを提供するための情報を必死に探していたある日、Kagayaは「日本保険外看護サービス協会」という名前に出会いました。
それまで、どこを探しても見つけられなかった“自費で看護をするための具体的なサポート”を打ち出していたのが、この協会です。
公式サイトを開いてみると、「保険に依存しない新しい看護の形」というキャッチコピーに目が留まりました。
まさにKagayaが目指していたもの──鍼灸と看護を組み合わせたハイブリッドケアや、自費での訪問支援など、従来の枠にとらわれない働き方を志す人たちが集う場所。
「ここなら、今の自分に必要なヒントが得られるかもしれない」そう直感し、すぐに会員登録を申し込みました。
入会のきっかけは、「開業支援準備講座」というオンライン講座を受講したいと思ったからです。
この講座では、自費看護を始めるうえでの基本的な考え方や、開業に必要な手続き、リスク管理、契約書の整備、トラブル事例など、現場に即した情報が丁寧に解説されていました。
正直、内容の半分以上は、Kagayaがこれまでに自力で調べてきたものでした。
ですが、この講座を受けて一番価値を感じたのは、「誰かに質問できる場がある」ことです。
独立してからは、ちょっとした疑問を投げかけられる先がないことが一番の悩みでした。
たとえば──
- 契約時に交わす書類はどうしたらいいの?
- 自費であっても医療的ケアを行う場合、指示書は必要?
- 保健所に届け出る必要があるケースとそうでないケースの違いは?
- もしトラブルが起きたときの対応策や保険加入の選択肢は?
こうした「行政にも聞きにくい」「ネットにも明確な答えがない」疑問に対して、協会のスタッフさんが丁寧に、現実的な視点からアドバイスしてくれるのがとてもありがたかったです。
しかも、単なるマニュアル的な回答ではなく、「あなたのサービス内容なら、こういう方法もありますよ」と、実情に応じた代替案や工夫まで教えていただけました。
Kagayaのように、鍼灸師としての開業手続きは終えていても、「看護師として自費訪問をどう位置づけるか?」に悩んでいる方には、まさにぴったりのサポートだと感じました。
また、事務局の方だけでなく、実際に自費で訪問看護やセルフケア支援を行っている先輩ナースの体験談を聞けるのも、大きな学びになりました。
「保険が使えないからこそ、できることがある」──この言葉に深く共感したのを、今でも覚えています。
自費だからといって、制度から逸脱するわけではなく、「制度にないからこそ必要とされるケア」を丁寧に届けるという姿勢。
Kagayaにとって、日本保険外看護サービス協会は“法律の壁”にビクビクするのではなく、“知識と工夫で超えていく”勇気をくれる場所でした。
そしてここから、学びと仲間とのつながりがさらに広がっていくことになります。
🌟継続サポートと交流が魅力!ZOOMセミナー&座談会
日本保険外看護サービス協会の魅力は、単発の講座やマニュアル提供だけではありません。
「学んで終わり」ではなく、「学び続けられる仕組み」が整っていることが、フリーランスとして活動を始めたばかりのKagayaにとって、とても心強い支えとなりました。
特に魅力を感じたのは、以下のような継続サポートの存在です。
- 月1回のZOOMセミナー(最新の制度情報・会員の活動紹介など)
- 会員限定のテーマ別座談会
- Facebookでの情報交換と相談
このZOOMセミナーでは、たとえば「医療と福祉をつなぐ自費サービスの届け方」や「契約トラブルを防ぐ工夫」といった、実務に直結するテーマが扱われます。
登壇されるのは、実際に自費でサービスを提供している現場の看護師さんや、法制度に詳しいアドバイザーの方など。
リアルな成功談・失敗談が聞ける場として、とても貴重な学びの時間です。
そしてセミナーの後には、希望者が参加できる「座談会タイム」があります。
Zoomのブレイクアウトルーム機能などを使って、少人数での自由なおしゃべりができる時間。堅苦しい会議ではなく、肩の力を抜いて話せる場だからこそ、本音で話せる雰囲気があります。
「実はこんなことで悩んでるんだけど……」
「自費で訪問してるけど、料金設定ってみんなどうしてる?」
「契約書ってやっぱり弁護士に見てもらった方がいいのかな?」
そういったモヤモヤを、そのまま共有できる場があるって本当にありがたいんです。
特に、地方で活動している方や、まだ開業準備中で周囲に同じ境遇の人がいない場合など、「一人じゃない」と感じられることは大きな励みになります。
また、Facebookとても便利です。
「厚労省のこの資料、どこに載ってたっけ?」
「こういうケアって保健所的にNGかな?」
そんな疑問を日常的に投稿できて、誰かがコメントを返してくれる──この即時性とフラットな関係性が、制度のはざまで活動する私たちにとって本当にありがたいのです。
Kagayaも、はじめは「Zoom交流会とか、ちょっと緊張するな…」と思っていたのですが、実際に参加してみると、温かく迎えてくれて安心して話すことができました。
顔も名前も知らないけれど、同じようにチャレンジしている仲間がいる。
それだけで、前に進む勇気がもらえます。
日本保険外看護サービス協会は、単なる情報提供の場ではなく、「つながりと実践」が重視された、実に実用的なコミュニティだと実感しています。
🌟鍼灸師としての開業とハイブリッドケアの可能性
Kagayaは鍼灸師としても活動しています。
鍼灸師の開業は、看護師と違って比較的明確です。
「保健所への施術所開設届」と「税務署への個人事業の開業届」を提出することで、正式に鍼灸院として開業することができます。
これは、国家資格としての「開業権」が認められている鍼灸師ならではの利点です。
施術所を構える場合は構造設備基準(6.6㎡以上、手洗い場、衛生設備など)を満たす必要がありますが、訪問専門で開業する場合はその限りではなく、柔軟に展開できます。
この開業手続きや準備の参考になったのが、以下の書籍でした。
この本には、実際の申請書の書き方から、保健所でのチェック項目、開業後に注意すべき運営面のアドバイスまで、「現場目線の情報」が詰まっています。
鍼灸と看護、それぞれの資格を持っているKagayaだからこそできること──それは、両方の専門性を活かした「ハイブリッド型の訪問ケア」だと確信しています。
たとえば、次のような組み合わせが可能です:
- 疼痛や慢性疾患の方へ:東洋医学的なアプローチ+バイタル管理
- 不眠や精神的不調:耳鍼・灸+カウンセリング・生活指導
- 障がい児への訪問支援:YNSAやスヌーズレン的刺激+看護的観察
どれも保険の範囲内ではなかなか届けにくいケア。
でも、求めている人は確実に存在しています。
「自費だからこそ、時間も内容も自由に設計できる」──これは看護師だけ、鍼灸師だけでは実現しにくいケアスタイルです。
地域包括支援センターやケアマネージャーとの連携も視野に入れながら、「制度の外にいる人」を支える役割を果たせたらと考えています。
また、訪問鍼灸としても受領委任制度(保険取り扱い)を活用しながら、自費サービスを併用するスタイルも、今後の展開として非常に有望です。
たとえば:
- 週1回:保険対応の訪問鍼灸
- 週1回:自費でのリラクゼーション灸+生活相談
こうした柔軟な組み合わせは、地域住民のニーズに応えながら、自身の収益確保にもつながります。
Kagayaはこのようなハイブリッドケアを通じて、「制度に頼らずとも成立する、もう一つの在宅ケアの形」を模索しています。
誰かの“余白”に寄り添うような支援。医療と福祉のはざまにいる人たちの“困った”を解消できるサービス。
そこにこそ、これからの鍼灸師・看護師に求められる役割があると信じています。
🌟まとめ:未来の看護師像に向けて、今できること
少子高齢化が進む日本において、医療・福祉・地域支援の在り方は大きく変化しています。
そんな中で、これまでのように「保険制度の範囲でしかケアを提供できない」という枠組みは、徐々に見直されつつあります。
Kagayaが目指しているのは、制度に縛られない、でも制度を理解したうえで選択できるケアスタイルです。
保険適応ではできないこと、制度外だからこそ可能なケア──それを届けられるのが、自費サービスの強み。
もちろん、それは「好き勝手にやる」という意味ではありません。
むしろ、制度をよく理解し、グレーゾーンを避けながら、倫理的・安全にサービス提供を行うという、高い専門性と責任が求められます。
それを支えてくれるのが、「日本保険外看護サービス協会」のような学びとつながりの場でした。
ここでは、単なる情報提供にとどまらず、「どうやって実現するか?」「どこにリスクがあるか?」「どんな工夫で乗り越えたか?」といった、リアルで実践的な知見が共有されます。
そして、同じように道なき道を歩む看護師たちと出会うことができました。
自費でケアを提供したい人、施設外で活躍したい人、地域に密着して活動したい人──立場は違っても、根底には「もっと良いケアを届けたい」という共通の想いがあります。
今までは「一人で考えて、一人で動く」しかなかったかもしれません。でも、今は違います。
情報も、仲間も、相談できる仕組みも、ちゃんとあります。
未来の看護師像とは、病院という枠を超えて、自分のスタイルでケアを届けることができる存在。
地域で、家庭で、施設と連携しながら、専門性を活かして働ける自由な形。
Kagaya自身もまだ模索の途中ではありますが、「制度に頼らずとも、自分の想いをかたちにできる」という希望を、確かに感じています。
もし、あなたが今、「自費看護なんて無理かも」「制度が壁になりそう」と感じているなら──。
まずは一歩、学びや仲間とのつながりの中に飛び込んでみてください。
それが、きっとあなた自身のケアスタイルを築いていく原点になるはずです。
自費看護、フリーランス、ハイブリッドケア……どんな働き方にも、「意味」と「使命」があります。
一人では難しいことも、仲間となら乗り越えられる。
Kagaya自身、それを実感したからこそ、これからも前を向いて歩いていきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。