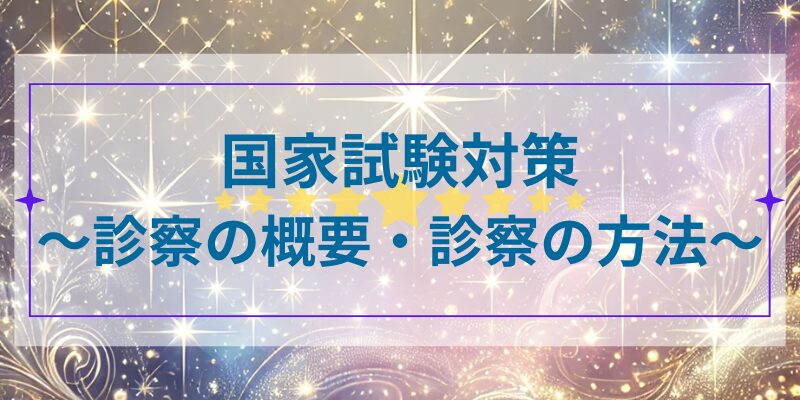🌟診察の基本順序|視診・聴診・打診・触診の違いと覚え方
身体診察を行う際には、「視診 → 聴診 → 打診 → 触診」という基本的な順序があります。
これは、患者への侵襲を最小限にしつつ、正確な情報を得るための黄金ルールです。
たとえば腹部の診察では、聴診を先に行わないと、打診や触診によって腸の蠕動音が変化してしまうため、正しい情報が得られなくなることがあります。
以下で、それぞれの診察法の特徴と注意点を詳しく見ていきましょう。
🔍視診(ししん)
視診は、「見ることによる診察」です。
皮膚の色や発疹、呼吸の状態、顔色、姿勢、歩き方、患部の腫脹などを観察します。
- 視診は最初に行うのが原則
- 無意識の動作や表情も重要な手がかりになる
- 関節の変形や浮腫、皮膚の色調変化を観察
ポイント: 視診は「聞かずとも訴えている症状」を見抜く力を養う訓練にもなります。
🎧聴診(ちょうしん)
聴診は、聴診器を使って体内の音を聞き取る方法です。
心音、呼吸音、腸音などを確認します。
聴診の位置や順序は解剖学的位置に従い、左右差や異常音(ラ音など)を聴き分けます。
- 腹部では打診・触診より先に行う
- 高音域はダイアフラム型、低音域はベル型を使用
- 心音・肺音・腸音など、異常音の有無に注目
国家試験頻出:「高周波音はダイアフラム型、低周波音はベル型」で聴診する。
🥁打診(だしん)
打診は、身体を軽く叩いて音を聴き、臓器の状態を推測する方法です。
音の響きにより、空気の多い部位(肺)や液体のある部位(腹水など)を識別します。
- 打診音には清音・濁音・鼓音・濁音などがある
- 胸部や腹部の異常(胸水、腫瘍など)を推測できる
- 心臓部は濁音を呈する(試験対策)
※打診のあとに触診を行うのが基本ですが、腹部の診察ではこの順序を守ることで腸音への影響を避けます。
🖐触診(しょくしん)
触診は、手で直接触れて腫瘍、硬結、圧痛、熱感などを確認する方法です。
深部臓器を触れる際には両手を使うこともあります(例:腎臓)。
- 必ず最後に行う(他の検査に影響するため)
- 疼痛部位には最後に触れるのが原則
- 腫瘍、圧痛、腫脹、熱感などの異常を確認
例: 腎臓の触診は両手で行い、深く腎臓をはさむように触れます(国家試験で出題あり)。
📌まとめ:診察順序のゴロと覚え方
「視・聴・打・触(し・ちょう・だ・しょく)」という語呂で覚えましょう。
腹部診察の基本手順や、異常所見を誘発させない配慮の視点からも、この順序は非常に重要です。
国家試験でも「どの順序で行うのが正しいか」「腹部の診察で最初に行うべきは?」といった出題が繰り返しされていますので、しっかりと定着させておきましょう。
🌟SOAP記録とは?構造と書き方を徹底解説
SOAPとは、医療現場や鍼灸・リハビリなどで用いられる記録フォーマットの1つで、患者の状態を体系的・客観的に記録するための枠組みです。
S(Subjective)→ O(Objective)→ A(Assessment)→ P(Plan)の順に記録され、問題志向型記録(POMR)の基本形式としても知られています。
📝S:主観的情報(Subjective)
患者本人が感じている症状や訴えのこと。
例としては、「膝が痛い」「夜間に咳が止まらない」「最近疲れやすい」などがあります。
自覚症状とも言えます。
- 主訴(CC:chief complaint)
- 現病歴
- 生活背景や訴え
👉医療面接で聞き出した内容を、患者の言葉を尊重しつつ正確に記録します。
📊O:客観的情報(Objective)
医療従事者が測定・観察した事実を記載します。
バイタルサインや検査結果、視診・触診・打診・聴診などの所見がここに該当します。
- 体温、脈拍、血圧など
- 浮腫、発赤、関節の可動域制限
- 筋力テスト、痛覚テストなど
👉国家試験でも「Oは他覚所見」として定義され、頻出ポイントです。
🧠A:評価・アセスメント(Assessment)
主観的・客観的情報から分析・考察を加えた医療者側の判断です。
「なぜ症状が出ているのか?」「どのような状態なのか?」を記述します。
- 「腰痛は筋緊張型と考えられる」
- 「改善傾向あり、ストレッチの効果がみられる」
👉国家試験では「A=病態の評価」として問われることがあります。
🗂P:計画(Plan)
今後の治療・ケア・生活指導の方針を記載します。
具体的な施術内容やアドバイス、次回予定などが含まれます。
- ツボへの施術:曲池・合谷に鍼通電
- 生活指導:入浴とストレッチの継続
- 次回:2日後再診予定
SOAPの書き方は鍼灸院・接骨院・訪問看護などでも共通語です。
学生のうちに慣れておきましょう!
🌟国家試験に頻出!自覚症状と他覚症状の違いとは?
診察やSOAP記録において重要なキーワードが「自覚症状」と「他覚症状」です。
国家試験では「どちらに分類されるか」を問う問題が多く出題されます。
🧍♀️自覚症状(Subjective Symptom)とは
患者本人が主観的に感じる症状のことです。
医療者が直接確認できないのが特徴で、S(SOAP)に記録されます。
- 頭痛
- 吐き気
- 動悸
- 耳鳴り
- 倦怠感
👉 国家試験では「動悸・頭痛・息切れ・しびれ・かゆみ」は自覚症状に分類される。
👩⚕️他覚症状(Objective Sign)とは
医療者が視診・触診・検査などで客観的に確認できる症状です。
O(SOAP)に記録されます。
- 発熱
- 血圧の上昇
- 心尖拍動
- 発疹
- 浮腫、出血、呼吸音の異常
👉 試験では「高熱・心尖拍動・発疹・打診所見」は他覚症状として正答になります。
📌ポイントまとめ
- 自覚症状:患者が訴える(例:かゆみ、痛み、めまい)
- 他覚症状:他人が確認する(例:発熱、腫脹、呼吸音)
ゴロ合わせ:「自分が感じる → 自覚」「他人がわかる → 他覚」で覚えておくと便利です。
SOAPとの対応も意識しながら、問題を解く力を養っていきましょう!
🌟鍼灸国家試験過去問
按マ指 第8回-73
他覚的身体所見䛿どれか。
- 動悸
- 胸痛
- 息切れ
- 心尖拍動
按マ指 第9回-58
自覚症状でないのはど れか。
- 耳鳴り
- 頭痛
- かゆみ
- 高熱
按マ指 第23回-38
他覚症状はどれか。
- 頭痛
- 発熱
- 耳鳴り
- 吐き気
按マ指 第24回-39
疾病の見通しを意味するのはどれか。
- 病期
- 転帰
- 治癒
- 予後
按マ指 第27回-38
他覚症状はどれか。
- 掻痒感
- 頭痛
- 発熱
- 食欲不振
鍼灸 第2回-61
問診について正しい記述はどれか。
- 信頼関係が重要である。
- 最初から特定の疾患を 推定して行う。
- 訴えは医学専門用語で 記載する。
- 患者の職場の上司には問診の内容を話す。
鍼灸 第17回-52
問診(医療面接)を行う際の注意として適切でな い記述はどれか。
- 温かみのある態度で接し、患者との信頼関係を築く。
- ある症状がみられないといった陰性症状は重要である。
- 特定の疾患を推定し、そ れに沿って行う。
- 患者の個人情報が漏れないようにする。
鍼灸 第18回-52
医療面接において適切でないのはどれか。
- 前半は「閉ざされた質問」を中心に進める。
- 患者の言葉を繰り返して 理解していることを示す。
- 言い換えによって訴えを明確化する。
- 最後に言い残しがないかどうかを聞く。
鍼灸 第26回-125
医療面接で開放的質問に相当するのはどれか。
- 今日はどうされました か。
- いつから痛みますか。
- アレルギーをおもちです か。
- 過去に大きな病気にかかったことがありますか。
鍼灸 第31回-43
医療面接について正しい のはどれか。
- 患者が話したことは繰り 返さない。
- 別居している家族の健康状態も聞く。
- 問診は特定の疾患を推定して始める。
- 医学用語を用いて説明する。
按マ指 第12回-65
問診で誤っている記述はどれか。
- 問診は主訴から始める。
- 問診内容については守秘義務がある。
- 家族歴は現病歴に含める。
- 輸血歴は既往歴に含める。
鍼灸 第31回-127
医療面接の態度について最も適切なのはどれか。
- 患者の正面に座る。
- 患者の話を共感的に聴く。
- 導入は閉ざされた質問から行う。
- アドヒアランスよりコンプライアンスを目指す。
按マ指 第23回-113
SOAPについて適切な組合せはどれか。
- S---評価
- O---客観的所見
- A---治療計画
- P---主訴
鍼灸 第24回-116
変形性膝関節症の患者に対するSOAP方式による経過記録でPに相当するのはどれか。
- 階段昇降時䛾膝䛾痛み
- 膝関節䛾屈曲拘縮
- 内側広筋䛾萎縮
- 大腿四頭筋訓練
鍼灸 第25回-121
鍼灸治療についてSOAP形式で記録する場合、Aに該当するのはどれか。
- 医療面接の内容
- 他覚的所見
- 治療内容
- 治療経過の評価
26 按マ指 121
SOAPについて正しい組合せはどれか。
- S---検査所見
- O---自覚症状
- A---病態䛾評価
- P---治療効果
鍼灸 第27回-125
上腕骨外側上顆炎の患者に対するSOAP方式による記録で、Pに相当するのはどれか。
- タオルがしぼりにくい
- トムゼンテスト陽性
- 動作後のアイシング
- 短橈側手根伸筋の過緊張
按マ指 第28回-120
関節リウマチの診療においてSOAP形式で記録する場合、Oに該当するのはどれか。
- パラフィン浴
- スワンネック変形
- 手指のこわばり感
- 機能障害分類クラスⅢ
鍼灸 第28回-124
腰部脊柱管狭窄症に対する診療においてSOAP 形式で記録する場合、A に該当するのはどれか。
- 間欠跛行距離300m
- 腰下肢への低周波鍼通電療法
- ケンプ徴候陽性
- 神経根型
按マ指 第29相-110
脊椎分離すべり症の経過観察記録においてSOAP形式で記録する場合、Oに該当するのはどれか。
- 鈍い腰の痛みがある。
- マイヤーディング分類3度である。
- 脊椎の階段状変形がみられる。
- コルセットによる固定をする
按マ指 第31回-111
肩関節周囲炎患者に対する診療においてSOAP 形式で記録する場合、P に該当するのはどれか。
- 夜間痛
- 結帯動作制限
- 運動療法
- ペインフルアークサイン 陽性
按マ指 第7回-73
触診で発見できないのはどれか。
- リンパ節腫脹
- 胸部大動脈瘤
- 肝臓の腫大
- 腹部の腫瘤
按マ指 第9回-70
身体の診察で正しい記述はどれか。
- 腹部触診は疼痛部から行う。
- 橈骨動脈の拍動は左が右より強い。
- 心臓部の打診で濁音を呈する。
- 高周波音はベル型で聴診する。
10 按マ指 74
打診音はどれか。
- 清音
- グル音
- ラ音
- 捻髪音
鍼灸 第10回-66
両手で触診する臓器はどれか。
- 胃
- 肝臓
- 胆嚢
- 腎臓
按マ指 第24回-50
触診について正しいのはどれか。
- 聴診より先に行う。
- 最初は力を強く加える。
- 疼痛のある部位は最後に行う。
- 体位変換は避ける。
鍼灸 第28回-53
腹部触診について正しいのはどれか。
- 聴診より先に行う。
- 最初は柔らかく触れる。
- 疼痛部位を最初に触れる。
- 体位変換は必要ない。