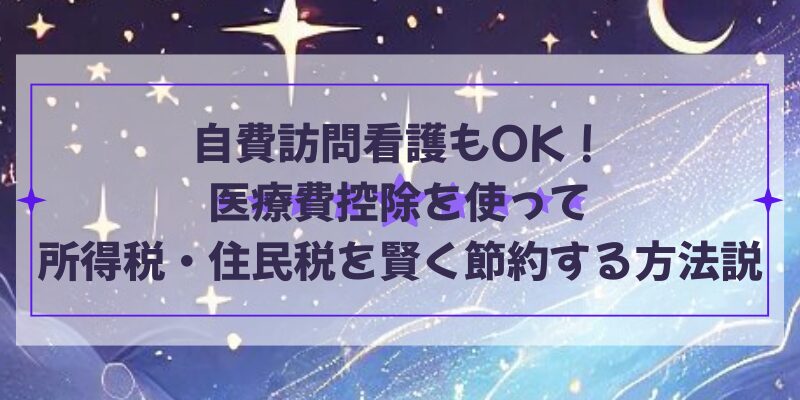こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
みなさんは「訪問看護」と聞いて、どんなイメージをお持ちでしょうか?
「病気の人が利用するもの」「退院後のお年寄りが使う」「ケアマネージャーが手配してくれる」など、少し特別なサービスというイメージをお持ちの方が多いかもしれません。
実際、Kagayaの身の回りでも、ソーシャルワーカーやケアマネージャーさんなど、専門職からの紹介がないと、訪問看護というサービス自体の存在を知らないという方がとても多くいらっしゃいます。
そしてもう一つ驚かれるのが、「訪問看護にも自費という選択肢がある」こと。
「え?訪問看護って保険が使えるんじゃないの?」「自費なんて高そう!」と感じた方もいると思います。
たしかに、訪問看護は医師の指示書のもと、保険適用で利用することができます。
しかし、その一方で、保険が使えないケースも実は少なくありません。
たとえば――
- 医師の指示書がもらえない(主治医がいない/協力が得られない)
- 1回あたりの訪問時間が長く、制度上の上限を超えてしまう
- 療育や見守りなど、制度の範囲外のサポートを希望される
- 医療ニーズは少ないが、専門的なサポートが必要な障がい児(者)
このようなケースでは、保険制度ではカバーしきれないため、自費による訪問看護という形で対応する必要があります。
Kagayaも、なるべく公費制度を活用して負担を少なくしたいと考えて日々取り組んでいます。
しかし、人員配置の制約や契約要件の厳しさ、そして「受領委任制度」などの制度の壁によって、どうしても自費での提供になる場面も出てきます。
では「自費は高いからダメ」なのでしょうか?
答えはNOです。
たしかに保険よりも料金は高く感じるかもしれません。
でも、自費だからこそできる柔軟なケアがあります。
制度に縛られず、必要なタイミングに必要な時間だけ、必要な人が訪問できる。
これは大きなメリットです。
そして、ここが今日の一番大事なポイントなのですが――
実は「自費の訪問看護」も、条件を満たせば「医療費控除」の対象になります!
これはあまり知られていませんが、国税庁の定める「医療費控除」には、保健師・看護師・准看護師による療養の世話に支払った費用も含まれています。
つまり、医師の指示がなくても、医療的な世話や生活支援としての看護が行われた場合には、一定の要件で控除の対象となるのです。
同様に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術も対象になりますので、Kagayaのように鍼灸と看護を組み合わせた自費サービスを提供している場合でも、賢く使えば所得税や住民税の節税につながります。
医療費控除と聞くと「入院や手術のときだけ使うもの」と思われがちですが、実は日常的なケアや介護、訪問サービスにも適用されるケースがたくさんあるんです。
本記事では、そんな「医療費控除」の基本と、自費訪問看護や鍼灸施術を利用されている方にとっての活用ポイントを、わかりやすくお伝えしていきます。
「費用はかかるけど、控除で少しでも取り戻せるなら助かる!」という方、ぜひ最後までご覧くださいね。
🌟医療費控除とは
「医療費控除」という言葉、なんとなく耳にしたことはあっても、実際にどういう制度かを正確に理解している方は少ないかもしれません。
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までのあいだに、本人または家族のために支払った医療費が合計10万円を超えた場合、あるいは所得が200万円未満の方はその所得の5%を超えた場合に、超えた金額分を所得から差し引くことができる制度です。
たとえば、年間で15万円の医療費を支払ったとします。
この場合、超過分の5万円が医療費控除の対象となり、所得から差し引かれます。
つまり、課税対象となる所得が減るということです。
課税所得が減ることで、所得税や住民税の金額も下がるという節税効果が得られます。
控除の対象となるのは、ご自身だけではなく、同一生計の家族全員の医療費です。
ここでいう「同一生計」とは、必ずしも同居していなくても、生活費を一緒にしている状態であれば該当します。
たとえば、仕送りしている大学生の子どもや、遠方で一人暮らししている親御さんの医療費も条件次第で対象になる可能性があります。
そして見落としがちなのが、保険診療だけでなく、自費診療で支払った費用も対象になる場合があるということです。
鍼灸・マッサージ・整骨院、そして看護師による自費の訪問サービスなどが、その一例です。
Kagayaも自費で訪問看護や鍼灸を提供する際、「少し高く感じられるかもしれませんが、医療費控除の対象になることで、後から税金が戻ってくる可能性がありますよ」とお伝えしています。
特に、年間を通じて定期的なケアを必要とする方にとっては、医療費が10万円を超えることはよくあることです。
この制度は、日々の医療・介護にかかる費用負担を少しでも軽減するための大切な仕組みです。
知らないまま申告をしなければ、当然ながら控除も受けられません。
逆に言えば、「ちょっと面倒くさそう」と思っていても、知っていれば取り戻せるお金があるということなんですね。
医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
会社員などで年末調整だけで済ませている方も、医療費控除を受けたい場合は自分で申告しなければなりません。
このあたりも後の章で詳しく解説していきます。
この制度は特に、障がい児・重症児・難病の方など、医療ニーズが高く医療費がかかりがちなご家庭にとって非常に大きなメリットとなります。
正しく活用して、少しでも家計の負担を軽くしていただけたらと思います。
次の章では、具体的にどんな医療費が控除の対象になるのかを一覧で解説していきます。
🌟医療費控除の対象となる医療費
医療費控除が受けられるのは「医療費を支払った場合」と言っても、その対象範囲は非常に幅広く、想像以上に多くのケースが該当します。
ここでは、実際に国税庁が認めている「医療費控除の対象となる医療費」の具体例をご紹介していきます。
✅医療費控除の対象となるもの
- 医師・歯科医師による診療や治療費
- 治療に必要な薬の購入(市販薬も対象:風邪薬など)
- 健康診断や人間ドックで重大な病気が見つかり、治療に至った場合の費用
- 病院・診療所・介護施設(老健・療養型・特養など)への入院・入所費
- はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師の施術費
- 看護師・保健師・准看護師・療養世話人への依頼費用(自費訪問看護など)
- 助産師による出産の介助費用
- 介護福祉士によるたん吸引・経管栄養サポートの費用
- 介護保険の自己負担分(訪問介護・デイサービスなど)
- 通院・入退院時の交通費、食事・個室費用、医療用コルセット等の器具代
- 義手・義足・義歯・松葉杖などの購入費
- 長期療養中の寝たきり患者のおむつ代(医師の証明書が必要)
- 骨髄移植・臓器移植のあっせん費用(患者負担分)
- 高齢者への特定保健指導に伴う自己負担金
こうして見ると、いわゆる「病院にかかった費用」だけでなく、訪問による看護・介護・鍼灸などのケアも控除対象であることがわかります。
とくに注目したいのが、保健師・看護師・准看護師による療養の世話を依頼した費用が対象になるという点です。
これは、医療機関に勤務する看護師に限らず、訪問や自宅内で療養上の世話を提供した場合も対象となります。
つまり、自費の訪問看護サービスや、個人で活動している看護師への支払いも控除の対象になるのです。
Kagayaのように看護師資格を持つ者が提供する「自費訪問ケア」「療育支援」も、一定の医療的意義があれば認められる可能性があります。
これは知られていないだけで、非常に大きな支援策となります。
また、鍼灸師による施術も医療費控除の対象です。
国税庁の公式見解において、「はり師・きゅう師の施術」は、治療を目的としたものであれば保険適用の有無に関わらず控除対象とされています。
よく質問を受けるのが「オムツ代」についてです。
これも条件を満たせば控除対象になります。
具体的には、6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている患者で、医師から「おむつ使用証明書」を発行してもらった場合、その年のおむつ代が全額医療費としてカウントされます。
障がい児や高齢者介護をされている方にとって、オムツ代は家計への大きな負担です。
毎月数千円〜1万円以上かかるご家庭も多いので、忘れずに証明書を主治医にお願いしておくことをおすすめします。
さらに、近年ではレーシック手術などの視力回復手術、海外旅行中に受けた現地の医師による治療費用も、条件を満たせば控除可能です。
あくまで「治療を目的としていた」ことが前提になります。
このように、医療費控除の対象は思っているよりも広く、日常的にかかっている医療・看護・介護費用の多くがカバーされていることがわかります。
次の章では「控除の対象とならないもの」についても具体的に解説していきます。
🌟医療費控除とならないもの
医療費控除はとても便利な制度ですが、すべての医療・健康関連費用が対象になるわけではありません。
「治療に直接関係があるかどうか」が大きな判断基準となります。
ここでは、控除の対象とならない主な費用を解説していきます。
見落としがちな項目もあるので、確定申告の前にぜひ確認しておきましょう。
❌医療費控除の対象とならないもの
- 人間ドック・健康診断の費用(異常が見つからず治療に至らなかった場合)
- 医師や看護師への謝礼(お礼の品やお金など)
- ビタミン剤・サプリメント・健康食品など、病気予防・健康維持目的のもの
- あん摩・マッサージ・鍼灸などのうち、リラクゼーション目的での施術
- 看護師などへの心付け(所定料金以外の個人的な謝礼)
- 親族や知人への付添い費(家族に頼んで支払った交通費・謝礼など)
- 自家用車による通院時のガソリン代・駐車料金
たとえば、健康診断を受けて「異常なし」と診断された場合、その費用は対象外になります。
異常が見つかって、その後の治療につながった場合のみ対象になるため注意が必要です。
また、医師への謝礼やお見舞い金・菓子折りなどの贈答は、たとえ感謝の気持ちであっても、控除対象にはなりません。
これは正式な医療行為への対価ではないためです。
鍼灸・マッサージ施術についても、「肩こりをほぐしたい」「リフレッシュしたい」など慰安や疲労回復目的の利用は対象外です。
逆に、診断名がついていて治療の一環として行っている場合は対象になりますので、領収書の内容や診療目的の記載はしっかりと確認しましょう。
意外と多いのが、家族に付き添ってもらって「付添料」を支払った場合。
家族・親族に支払った費用は医療費控除の対象にはなりません。
ただし、付き添いをプロのヘルパーや家政婦に依頼して、療養の世話をした場合は控除対象となる可能性があります。
そして最後に、自家用車での通院にかかるガソリン代・駐車場代なども、医療費控除の対象外です。
ただし、公共交通機関を利用した通院費(バス・電車・タクシーなど)は対象になるため、領収書やメモを残しておくと良いでしょう。
このように、医療費控除には「治療目的であること」「対価性があること」が大前提です。予防・慰安・感謝・美容・娯楽などの目的で支払ったものは基本的に認められません。
どちらに分類されるか迷うような支出があれば、国税庁の公式サイトにある「税についての相談窓口」を利用するのがおすすめです。
「せっかくたくさん支払ったのに、控除の対象にならなかった…」ということがないよう、判断に困ったら早めに専門家や税務署に相談してみてくださいね。
次章では、医療費控除によって実際にどれだけ節税につながるのか、「所得税」や「住民税」との関係をくわしく解説していきます。
🌟医療費控除は所得税と住民税の節税になる
医療費控除は、支払った医療費の一部を「所得から差し引く」ことで税金を軽減する制度です。
ここでポイントなのは、控除の対象になるのは医療費そのものではなく、課税される所得金額を減らすという点です。
つまり、年間の所得が500万円あった人が、医療費控除によって10万円の控除を受けると、課税対象の所得が490万円になるという仕組み。
これによって、所得税と住民税の両方を節税できるのです。
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
ここが意外な落とし穴。
個人事業主やフリーランスは毎年確定申告をしているためこの制度に敏感ですが、会社員やパートなど給与所得者の多くは年末調整だけで済ませているため、医療費控除を知らない、または申請していないというケースが多くあります。
実は、年末調整では適用されない控除がいくつかあり、それらは別途確定申告することで初めて受けられるのです。
📌年末調整で反映されない主な控除
- 医療費控除
- 寄附金控除(ふるさと納税など)
- 雑損控除(災害や盗難など)
- 住宅ローン控除の初年度
年末調整を受けた会社員であっても、これらの控除を適用したい場合は、自分で確定申告をしなければならないというわけです。
さらに医療費控除は、本人だけでなく同一生計の家族の医療費も合算して申請することができます。
ご家庭でお子さんの通院、配偶者の通院、介護中の親の医療費などを合わせると、年間10万円以上になることも珍しくありません。
控除の仕組みをもう少し具体的に解説すると、たとえば年間の医療費が20万円かかり、所得が300万円だったとします。
この場合、20万円-10万円=10万円が控除され、課税所得が290万円になります。
これに応じて、所得税や住民税の負担が軽くなるのです。
住民税においては、基本的に一律で10%(都道府県税4%、市町村税6%)が課税されるため、医療費控除額の10%分がそのまま住民税の軽減に繋がるというイメージです。
ただし、住民税の控除分は還付されるわけではありません。
医療費控除により軽減された住民税は、翌年6月以降に納める税額から差し引かれる仕組みになっています。
これも見落としがちなポイントです。
一方で、所得税の控除分は「還付金」として返ってくるため、確定申告をすることで振り込みで返金される場合があります。
このように、医療費控除は「所得税と住民税の両方」に効果がある、とても優秀な節税方法です。
特に障がい児の育児や、持病のあるご家族をサポートしているご家庭では、毎年申請するだけで家計の負担を少し軽くすることができます。
次の章では、この記事のまとめとして、控除制度の活用ポイントを簡単に振り返ってみましょう。
🌟まとめ
ここまで、医療費控除について詳しくご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
医療費控除とは、その年に支払った医療費が10万円以上になった場合に、確定申告をすることでその超過分が所得から控除され、所得税や住民税を軽減できるという仕組みでしたね。
よくある節税対策としては「ふるさと納税」や「iDeCo」などがありますが、医療費控除もそれらと同様に活用すべき制度の一つです。
特にご家族に障がいや持病がある場合、医療費がかさみやすく、控除額も大きくなりやすいため、ぜひ知っておいてほしい内容です。
「病院に通っていないから医療費控除は関係ない」と思われがちですが、実は訪問看護、鍼灸、マッサージ、介護、療育支援など、保険外の支出でも対象になるケースが多いということを今回お伝えしました。
とくに、Kagayaのように自費で看護や鍼灸を提供している場合、公費の制限に該当してしまう方(医師の指示書がもらえない・制度に該当しない)でもケアが受けられるという利点があります。
たしかに自費サービスは、見た目の料金だけを見ると「高い」と感じられるかもしれません。
しかし、それが医療費控除の対象になるということであれば、実質的な自己負担が軽減され、安心して必要なケアを受けられる環境が整います。
さらに医療費控除は、同一生計の家族の分も合算できるため、ひとりの医療費が少なくても、家族全体で申請することで10万円を超えることもよくあります。
お子さんの通院や、親御さんの介護費用なども含めて、申告対象になるか確認してみてくださいね。
そして、年末調整だけで終わっている会社員の方も、医療費控除の申請には確定申告が必要です。
「手続きが面倒」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、最近ではe-Taxや会計ソフトの普及で、スマホから簡単に申告できる環境も整ってきています。
ほんのひと手間で、何千円、場合によっては何万円も戻ってくることもあります。
ぜひ、必要なケアを我慢するのではなく、制度をうまく活用して、家計と健康を両立していきましょう。