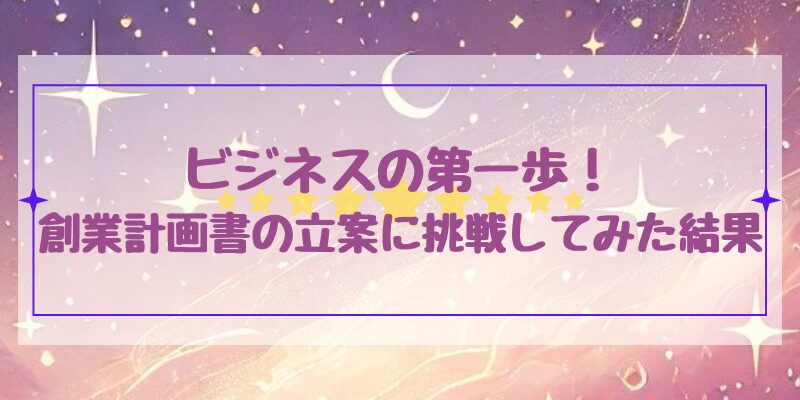🌟はじめに:鍼灸院の開業と創業計画書の第一歩
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
鍼灸院を開業しようと思ったとき、最初に直面するのが「どんなスタイルで始めるか」という選択です。
たとえばテナントを借りて店舗を構えるのか、それとも訪問専門の形にするのかによって、必要な資金は大きく変わってきます。
店舗を持つスタイルでは、物件の初期契約費用、内装工事、設備投資、広告宣伝など、まとまった開業資金が必要になります。
特に都市部でテナントを借りる場合は、家賃も高額になりやすく、開業時に数百万円単位の出費が発生するケースも少なくありません。
一方、訪問型のスタイルであれば、こうした固定費をぐっと抑えることができます。
必要なものは、自分自身と施術に使う道具、それと交通手段くらいです。
もちろん、それでも一定の備品や名刺、パンフレット、事務用品などは必要になりますが、比較的少ない資金でも始めやすいのが大きなメリットです。
しかし、どちらのスタイルであっても「創業計画書」は欠かせません。
なぜなら、開業には何らかの形で資金が必要であり、その資金を融資で補う場合には、日本政策金融公庫や地方自治体、民間金融機関などにきちんとした事業計画書を提出しなければならないからです。
「でも融資って、結局は借金じゃないの?」と思う方も多いでしょう。
もちろん、融資を受けるということは、将来的に返済していく責任が生じるということです。
だからこそ、なるべくなら最初から大きな借金をせず、リスクを抑えたスタートを切りたいとKagayaは考えています。
そのため、まずは借入に頼らない開業を目指しつつ、国や自治体が提供している給付金や助成金制度を徹底的にリサーチしています。
給付金であれば返済の必要はなく、自己資金を補う心強い味方になってくれます。
ただし、申請には厳しい審査があることがほとんどです。
「給付金=タダでもらえるお金」と考えがちですが、実際は相手に納得してもらえるだけの事業計画や社会的意義が求められます。
つまり「なぜこの事業が必要なのか」「どんな人の役に立つのか」「収益はどう見込めるのか」といったことを、具体的に説明する必要があるのです。
そこで大きな助けとなるのが、日本政策金融公庫の創業計画書フォーマットです。サイトから無料でダウンロードでき、どの項目をどのように書けばよいかのガイドラインもついています。
また、「創業の手引き」という小冊子では、創業の心構えから資金繰り、集客のヒントまで、かなり実践的な内容が網羅されています。
Kagayaもこの資料を活用しながら、自分なりに計画書の作成に取り組んでいます。
ちなみに、給付金に応募するかどうかに関わらず、創業計画書は一度しっかり作っておくことをおすすめします。
なぜなら、書いていく過程で自分自身の方向性やサービス内容が整理され、何を優先するべきか、どこに強みがあるかが明確になるからです。
Kagayaも、「本当に自分がやりたいことってなんだろう?」「誰のために、どんな形で提供するのがベストなんだろう?」と自問自答しながら、創業計画書の各項目に向き合っています。
これは単なる資金集めの書類ではなく、まさに自分自身の夢を言語化する作業だと感じています。
というわけで、これから何回かに分けて、Kagayaが作成した創業計画書の内容と、そこに込めた想い、試行錯誤の様子などを、できるだけリアルにお伝えしていきます。
訪問型で鍼灸や看護のサービスを立ち上げたいと考えている方にも、参考になる記事になると嬉しいです。
🌟創業の動機
Kagayaがこのたび訪問型の鍼灸×看護サービスで創業しようと決意した背景には、10年以上にわたる看護師としての経験と、そこで感じてきた「やりたいこと」と「やらなければならないこと」のギャップが大きく関係しています。
病院や施設で働いていると、どうしても「組織の方針」や「制度の枠組み」に沿って動かなければなりません。
そこでは患者さん一人ひとりに寄り添いたくても、時間や人手、制度上の制限により、十分なケアができない場面も多々ありました。
特に重症心身障がい児(者)とそのご家族に向き合う中で、Kagayaの中には「もっとこうしてあげたい」「本当はこういう支援が必要なのでは」という想いがどんどん積み重なっていきました。
けれど、雇用されている立場では、その理想を実現するのは難しかったのです。
その結果、Kagayaは「やらなければいけないこと」と「本当にやりたいこと」が一致しないまま、日々の仕事に違和感を覚えるようになりました。
そんな中で一つの答えにたどり着きました。
「それなら自分で事業を立ち上げよう」と。
Kagayaはこれまで、回復期病棟や特別支援学校、重症心身障がい児の病棟や発達センター、そして訪問看護ステーションで勤務してきました。
どの現場でも、子どもたちや家族に寄り添う看護を学び、療育や福祉制度の現実を知ることができました。
そして現在は、鍼灸師として新たなスキルを学びながら、東洋医学の視点も取り入れた支援の形を模索しています。
Kagayaの理想は、「療育の中に看護と鍼灸を融合させること」です。
心身の緊張が強く出やすい障がい児に対しては、西洋医学的なリハビリや看護だけでは対応しきれないことがあります。
そうした時に、鍼灸による自律神経の調整や情緒の安定は、大きな可能性を秘めていると感じています。
また、障がい児の支援は子ども本人だけでなく、家族全体の生活や心のケアも含めた包括的な視点が求められます。Kagayaは、訪問というスタイルを活かして家庭内の空気や背景も感じ取りながら、きめ細やかな看護・鍼灸支援を届けていきたいと考えています。
さらに、公費制度ではどうしても対応できない部分があります。
例えば、医療ケアを必要とする子の外出支援や、保護者自身の心身ケア、余暇活動のサポートなどは、公的制度の対象外であることが多く、サービスが十分に提供されていないのが現状です。
だからこそ、Kagayaはあえて「自費サービス」という形で、制度に縛られない柔軟な支援を提供していこうと決めました。
もちろん簡単な道ではありませんが、「本当に必要とされること」を大切にした事業を形にしたいという強い想いがあります。
創業にあたり、家族や周囲の理解と協力にも支えられています。
また、創業支援機関や地域の支援サービスなども活用しながら、少しずつ準備を進めているところです。
立地については、小平市を中心に、訪問しやすいエリアに活動を絞ることで、効率よく支援が行えるように計画しています。
このような想いと経験を元に、「きらぼし」という訪問型ケアサービスを立ち上げようとしています。
これは単なる仕事ではなく、Kagayaにとっての人生の使命だと感じています。
🌟経営者の略歴など
Kagayaはこれまで約15年にわたり、看護師として医療や福祉の現場に携わってきました。
なかでも重症心身障がい児(者)のケアを中心に、病院・学校・施設・訪問など、さまざまなフィールドで経験を積んできました。
以下に、これまでの経歴とその中で学んだことを簡潔にまとめます。
- 平成○年3月:看護専門学校卒業。看護師免許取得。
- 平成○年4月~:回復期リハビリテーション病棟にて3年間勤務。
- 主に脳梗塞や大腿骨骨折など運動機能障害を抱える患者の看護を担当。
- 多職種連携の中で、リハビリテーションの基礎知識を習得。
- バイタル管理、清潔ケア、褥瘡予防など、基本的な臨床看護技術を徹底的に学ぶ。
- 平成○年4月~:特別支援学校にて学校介護職員として2年間勤務。
- 重度の肢体不自由や医療的ケアが必要な児童の介助を担当。
- 教育現場での子どもとの関わり方や、障がい児の学習支援について学ぶ。
- 平成○年5月~:重症心身障がい児(者)専門の病棟にて3年間勤務。
- 医療的ケア(経管栄養、吸引、酸素管理)を日常的に実施。
- ご家族との関係構築、レスパイトケアの提供など、社会資源としての医療の役割を体感。
- 平成○年4月~:発達センター(放課後等デイサービス)にて2年間勤務。
- 生活支援だけでなく、療育プログラムや余暇活動にも積極的に参加。
- 地域支援事業の仕組みと、子どもたちの成長支援の方法を学ぶ。
- 平成○年4月~:重症心身障がい児(者)専門の訪問看護ステーションにて4年間勤務。
- 在宅における医療的ケアや保護者支援を実践。
- 家族との信頼関係構築、医療と生活の橋渡し役としての訪問看護の重要性を実感。
- 地域の行政や学校、福祉施設との連携経験も豊富。
- 平成○年4月~:鍼灸専門学校に入学。現在在学中。
- 東洋医学の基礎理論と経絡治療、耳鍼・舌診・腹診の実技を学習中。
- 将来、看護と鍼灸を融合させた療育支援を実現するため、臨床実習にも積極的に参加。
このように、Kagayaのキャリアはすべて「障がい児(者)とそのご家族のQOL向上」を軸に積み重ねてきたものです。
特に訪問看護においては、病院とは異なり“生活の現場”で看護を提供するという視点を得たことで、サービスの本質を深く理解できました。
これまでの職場では、特定の役職や管理職ではなかったものの、スタッフ育成やチーム内の調整、保護者対応を任されることが多く、現場での信頼は厚かったと自負しています。
特にご家族との信頼関係づくりにおいては、「またKagayaさんに来てほしい」と言っていただけることが励みでした。
こうした経験の集大成として、今後は個人事業主として、自分の手で“本当に必要とされる支援”を届けることにチャレンジしていきたいと考えています。
この創業計画では、Kagaya自身の経歴がそのままサービスの強みであり、社会的意義や信頼の裏付けにもなります。
だからこそ、この略歴を正直に、そして丁寧に伝えていくことが大切だと考えています。
🌟取扱商品・サービス
当事業で提供する商品・サービスは、すべて自費での訪問型支援となります。公費制度では対応しきれない「家族全体へのケア」や「心身の予防的アプローチ」に焦点を当て、きめ細やかで柔軟なサービスを目指しています。ここではそのサービス内容と強み、販売戦略について詳しくご紹介します。
取扱商品・サービスの内容
以下のサービスはすべて税込・完全自費制での提供となります。
訪問先は小平市・東村山・東大和エリアを中心に対応しています。
- 見守り看護(120分):9,000円
- 日中一時預かりとして、保護者のレスパイトに対応
- 学校後の夕方支援(例:学童的なケア)
- 移動支援:公園や余暇活動への付き添い
- 医療的ケア児の通学・通所同行や見守り支援
- 鍼灸施術(60分):5,000円
- 発達支援目的の全身調整
- リラクゼーションと自律神経の安定
- 初回カウンセリング+施術(90分):2,000円
- 療育鍼灸(感覚統合や情緒安定のサポート)
- リハビリ鍼灸(拘縮や筋緊張へのケア)
- 保護者向けの美容鍼・肩こりケア・疲労回復
- オンライン療育相談(30分):3,000円
- 在宅療育の進め方、日常生活の困りごとへのアドバイス
- 保護者のメンタルサポート
これらのサービスは、すべて「家庭という現場で完結できるケア」を重視しています。
訪問看護や通所サービスでは届きづらい細やかな部分に目を向け、個別性の高い対応が可能です。
セールスポイント
- 公的制度では提供困難な「余暇活動支援」や「付き添い支援」にも対応
- 訪問看護×鍼灸×療育の統合により、心身の発達と安定を支援
- 障がい児本人へのアプローチだけでなく、保護者のQOL向上にも重点
- 柔軟な時間設定・予約制により、多忙な家庭にも合わせやすい
- 自宅という安心できる環境でサービスを受けられる
特に「公費ではここまでしてもらえなかった」「親子一緒にサポートしてもらえるのがありがたい」といったご感想を多くいただいています。
サービス内容は今後、利用者の声を反映しながら柔軟にアップデートしていく予定です。
販売ターゲット・販売戦略
- 主な対象は、重症心身障がい児(者)およびその家族
- 医療ケア児を在宅で育てる保護者(特に24時間介護を担う方)
- 訪問看護を利用中で、さらにきめ細かいサポートを求める家庭
集客方法としては、保護者同士のクチコミを中心に、地域イベントへの参加、医療機関・行政機関(障がい支援課など)へのチラシ配布や営業活動を予定しています。
また、公式ブログやInstagramを通じて、実際の支援事例やセルフケア情報を発信し、共感・信頼を得る仕組みも整えています。
競合・市場環境
- 障がい児(者)に特化した訪問看護・自費看護サービスは極めて少数
- 公費サービスは利用しやすいが、制度上の支援範囲が限定的
- 自由度の高い自費サービスは、保護者からの要望が大きい分、需要が高い
- 小平市・東村山・東大和エリアには同種の自費訪問ケアの競合が少なく、ブルーオーシャンである
このように、市場環境としてはニッチではあるものの、高いニーズが確実に存在する分野です。
特に“訪問+鍼灸+療育”という複合型サービスは希少性が高く、地域における独自ポジションの確立が期待できます。
🌟取引先・取引関係
創業当初の販路は非常に重要であり、安定した固定顧客の存在は継続的な売上を支える土台となります。
Kagayaがこれまで勤務してきた訪問看護ステーションや医療・福祉の現場で関係性を築いてきた保護者や医療関係者とのつながりは、今後の大きな財産です。
現在も看護師として勤務する中で、支援を必要とするご家庭から「もっと柔軟な支援が欲しい」「鍼灸などの代替療法にも興味がある」といった声を日常的に受け取っています。
創業にあたっては、そういった既存の関係性から徐々に固定客へとつなげていくことを想定しています。
また、地域でのつながり(行政・病院・支援学校・相談支援事業所)を活かして、必要な方にサービス情報を届ける活動も積極的に行っていく予定です。
新規顧客に対しては、訪問地域でのクチコミ、紹介、公式ブログやInstagram等のSNS発信を通じて、安心と信頼を育てながら顧客獲得を図っていきます。
販売先
- 重症心身障がい児(者)およびその家族
- 医療的ケアが必要な在宅児のご家庭
- 訪問看護・放課後等デイサービスをすでに利用しているが、「公費の枠外」で困っている家庭
- 育児や介護に疲弊しており、休息・ケアを求める保護者
販売活動に関しては、開業当初から営業やPRに積極的に取り組む予定です。
主な手法は以下の通りです。
- 現勤務先での非公式紹介(適切なガイドラインを順守の上)
- 障がい児支援を行う相談支援専門員への情報提供
- 地域の訪問看護ステーション・デイサービス・療育施設との連携
- InstagramなどSNSによるビフォーアフター紹介・セルフケア情報発信
- 地域のイベント・マルシェ出展(耳つぼ体験など)を通じた顔出し営業
なお、営業スタイルはあくまで信頼関係を重視し、無理な勧誘や押し売りにならないよう配慮しています。
障がい児家庭のニーズは非常に個別性が高いため、サービス提供前にしっかりとカウンセリングや面談を行い、ご本人・ご家族の意向を尊重した形で契約を進めます。
仕入先
サービスを提供する上で必要となる備品や消耗品に関しては、以下のようなルートから仕入れを予定しています。
- Amazon:衛生材料、紙エプロン、文房具、在宅用品など
- 鍼灸専門通販サイト(例:日本メディカル鍼灸社、メディコム):鍼、灸、アルコール綿、ディスポ手袋などの医療消耗品
- 看護師向け通販サイト(例:ナースステージ、看護のお仕事ストア):ユニフォーム、訪問バッグ、医療用品
- 地元のドラッグストア・文房具店:急ぎの消耗品・補充品対応
現在は一人で運営予定のため、在庫を多く抱えすぎず、こまめに発注する体制をとります。
今後、定期的なサービス提供が軌道に乗った段階で、業務用卸業者との取引や定期便なども検討していく予定です。
訪問鍼灸・看護では「衛生面」「携帯性」「使い捨て資材の充実」が重要です。
そのため、価格だけでなく品質やレビューも比較しながら、信頼できる仕入先を選定しています。
今後はサービス拡大や物販との連携も視野に入れ、セラピスト向けアイテムや保護者ケアグッズ(例:温熱アイマスク、アロマ、耳つぼジュエリー)なども取り扱えるよう準備を進めていきます。
🌟従業員
開業時点では、Kagaya一人での運営を予定しています。訪問専門という特性上、店舗スタッフや受付を配置する必要がなく、予約制にすることで業務の効率化を図ることができます。
また、マンパワーが限られている分、提供できるサービスの質と個別性にはこだわりたいと考えています。将来的に利用者数や訪問件数が増加してきた場合は、事務的な業務をサポートしてくれるスタッフや、同じ志をもつ看護師・鍼灸師の協力を視野に入れています。
🌟お借入れの状況
創業時点での主な借入は以下のとおりです。
- 住宅ローン:○○円(毎月の返済額 ○○円)
- 車ローン:○○円(毎月の返済額 ○○円)
いずれも生活に必要な範囲での借入であり、事業用の資金ではありません。新たな事業用ローンは極力控え、自己資金の範囲でスモールスタートを目指します。
🌟必要な資金と調達方法
訪問型の鍼灸・看護サービスは、テナントを借りたり大きな設備投資を行う必要がないため、開業資金を抑えることが可能です。
ただし、事務用品や消耗品、広告費など、最低限の初期費用と運転資金は必要になります。
設備資金
訪問専門でスタートするため、机やベッドといった店舗設備は不要です。
最低限必要な設備としては、以下のような備品を想定しています。
- 訪問用バッグと中身(鍼、お灸、消毒用品、使い捨て手袋など)
- ユニフォーム(スクラブまたは動きやすい服)
- 名刺・パンフレット・診療記録用紙
- ノートPCまたはタブレット、プリンターなどの事務機器
まだすべてを揃えているわけではなく、実際に稼働しながら必要なものをリストアップし、無理のない範囲で段階的に購入していく方針です。
運転資金
運転資金は、サービスを継続していくために必要な日々の経費です。
幸いにも、以下の点から大きなランニングコストは想定されていません。
- 家賃:なし(店舗を持たないため)
- 人件費:なし(当初は1人で対応)
- 光熱費:ほぼ不要(訪問型で事務所も持たない)
- 消耗品費:月3万円程度(鍼灸・衛生用品・事務用品)
これらの運転資金については、事業開始後の売上から徐々にまかなっていく見通しです。
初期段階では、余裕をもって準備しておくことで、不測の事態にも備えます。
資金調達方法
資金はすべて自己資金からの拠出を予定しています。
- 自己資金:100万円
この自己資金は、鍼灸学校に通いながら毎月3万円ずつ積み立ててきたものです。
開業当初からすべてを完璧に揃えようとせず、必要最小限の投資でスタートし、事業の成長に応じて設備やサービスを拡充していく形をとります。
また、今後必要に応じて、創業補助金や自治体の支援制度の活用も視野に入れていますが、現時点では融資や借入の予定はありません。
リスクを最小限に抑えつつ、着実に事業を軌道に乗せていくことを目指します。
🌟事業の見通し
開業後に想定以上の経費がかかってしまい、資金繰りが厳しくなるという話は少なくありません。
特に個人事業主としてスタートする場合は、売上が安定するまでに一定の時間を要するため、慎重な資金計画と現実的な売上予測が欠かせません。
Kagayaの事業モデルは、店舗を持たない訪問専門型であり、初期コストも運転資金も抑えられる設計となっています。
下記の表は、創業当初と1年後を見据えた簡易的な損益シミュレーションです。
| 創業当初 | 1年後 | |
| 売上① | 260,000 | 520,000 |
| 売上原価② | 30,000 | 30,000 |
| 人件費③ | 0 | 28,000 |
| 家賃 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 利益①-②-③ | 230,000 | 462,000 |
売上高、売上原価、経費の根拠
- 売上高
- 訪問1回あたりの平均単価:5,000円
- 1日2件 × 26日 稼働 = 260,000円/月
- 1年後には1日4件訪問が可能となり、月52万円の売上を想定
- 売上原価
- 使用する鍼やお灸
- アルコール綿、ペーパータオル、ディスポ手袋、エプロン等の消耗品
- 月あたり平均:30,000円程度
- 人件費
- 当初は一人で運営のため 0円
- 1年後に経理や事務サポートとしてパート勤務を想定(例:時給1,200円 × 3時間 × 月8回=28,800円)
- その他
- 店舗を持たないため家賃不要
- 自己資金開業のため、支払利息もなし
このように、経費構造が非常にシンプルかつ軽量なため、比較的早い段階で黒字化が見込めます。
特に家賃や固定人件費がない分、低リスクでスモールスタートできる点が本事業の強みです。
また、売上の伸びに応じて少しずつサービス範囲や訪問件数を拡大し、無理なくステップアップしていく方針です。
必要に応じて料金の見直しやメニューの改定も行い、需要に応じた柔軟な対応が可能な体制を構築していきます。
ただし、最初の半年~1年間は売上が安定しないことも想定し、生活費と切り分けた運転資金(最低3ヶ月分)を事前に確保しておくことも重要です。
経費や損益の把握、簡易帳簿による記録は、開業初期からしっかりと行っていく予定です。
🌟まとめ
今回、Kagayaなりに一から創業計画書を作成してみました。
見よう見まねではありましたが、実際に書き出してみることで、自分の事業が何を目指しているのか、どんなサービスを誰に届けたいのかが少しずつ明確になってきました。
創業計画書は、融資や助成金申請のときに必要となるだけでなく、自分自身の頭の中を整理し、道筋を描くためにも大切なツールです。
最初は大げさなものに感じるかもしれませんが、事業の設計図として活用することで、将来的な軌道修正もしやすくなります。
もし計画づくりに不安がある場合は、TOKYO創業ステーションTAMAなどの支援機関を活用するのも良いと思います。
コンサルタントが無料で相談に乗ってくれたり、創業計画書の添削をしてくれるサービスもあります。
まだKagayaは利用していませんが、いざという時にはぜひ頼りたいと思っています。
とはいえ、最初から完璧な計画書を作る必要はないと感じています。
大切なのは「自分が何をやりたいのか」「なぜそれをやるのか」「どうやって続けていくか」を自分の言葉で明確にすること。
それを土台に、必要な支援や資金調達を考えていくことが本質ではないでしょうか。
Kagayaの頭の中には、まだまだ未完成な部分があります。
看護の視点から見える支援の必要性と、鍼灸の力を活かしたアプローチ。
それらをどう融合し、障がい児(者)とその家族にとって本当に意味のあるサービスとして届けるのか。今も試行錯誤の真っ最中です。
本音を言えば、もっと先のビジョンとして、ご家族同士が情報共有できる場や、保護者が社会参加できるような「コミュニティサロン」もつくりたいと考えています。
そこでは施術や支援だけでなく、ちょっとしたおしゃべりやお茶ができるような居場所を提供したい。
けれど、それには人手が必要です。
だからこそ、まずは「自分一人でできること」からスタートします。
訪問での鍼灸や看護、療育支援。現場で感じてきた「こうだったらいいのに」を一つずつ形にしていきたい。
マンパワーが限られているからこそ、できるだけシンプルに、そして誠実に。
今の職場では尊敬できるナースもいますが、Kagayaと目指す方向が違うため、いっしょに事業を始めることはできません。
志がずれている人と組んでも、結局はストレスになってしまうからです。
だから、もし同じ志を持つ人が現れたら、その時にはコミュニティ型の発展も視野に入れたいと思っています。
まずは第一歩として、訪問型サービスを始め、地道に信頼を積み重ねていくこと。
そしてその歩みの中で、自分の事業を必要としてくれる人たちと出会いながら、Kagayaらしい事業スタイルをつくっていけたら、それが何よりの成功だと思っています。
…その前に。
まずは鍼灸師の国家試験に合格しなければですね(笑)