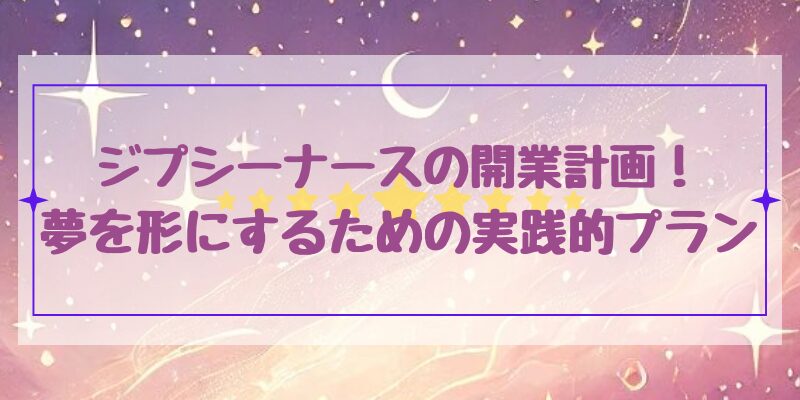こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
🌟1人で自由に働くために──社会人鍼灸学生のリアルな開業準備
鍼灸学生としての学びも、気づけば残り1年と半年。
時間が経つのは本当に早いものです。
実は、鍼灸学生1年目にして人生で初めて「赤点」というものを経験しました。
慣れない東洋医学の用語や構造、実技の繊細さに加えて、社会人としての生活との両立。
正直に言えば、思っていたよりもずっとハードでした。
結局追試を受けることになり、なんとか乗り越えましたが…。
20代の頃のように「前日に詰め込めば何とかなる」という勉強法では、もう限界があると痛感しました(脳のメモリ容量が足りません…)。
とはいえ、国家試験にはきっと「コツ」があるはずです。
暗記に頼らず、仕組みを理解し、臨床との接点で覚える勉強法を模索すれば、乗り越えられると思っています。
現役の若い学生さんにとっては、卒業後の進路はまだまだ先の話かもしれません。
でも、Kagayaのような社会人学生は「卒後の動き出し」が遅れると、その後の展開に大きく響きます。
だからこそ、今のうちから実践的な開業準備を進める必要があると感じています。
卒業後は、現在所属している訪問看護ステーションで週20時間の社保付き勤務を継続しながら、どこかの鍼灸院で研修を積もうと考えていました。
安定とスキルアップを両立させる無難な選択肢です。
しかし本音を言えば、「できるだけ早く、自分の力だけで働きたい」という気持ちが強くあります。
Kagayaは自他ともに認める「自由人」。
協調性がないとは言いませんが(笑)、組織の中で誰かの指示を受けて働くより、自分の価値観や想いを軸に、自由に仕事をしたいタイプです。
また、誰かを雇って「管理者」として動くような働き方にもあまり魅力を感じていません。
自分の責任で、自分の好きな対象に、自分のやり方で向き合いたい。
それが私の理想の働き方です。
例えば、看護師資格を活かして「健康相談」や「高齢者のケア」に特化した鍼灸院を立ち上げれば、一定の集客は見込めると思います。
実際、こうしたニーズは地域に多く存在しています。
けれども、Kagayaは高齢者分野にそこまで情熱を持てません。
むしろずっと心にあるのは、「障がい児(者)、特に重症心身障がい児」への支援です。
学生時代から、そして今の訪問看護の現場でも関わってきたこの分野に、Kagayaは特別な使命感を感じています。
現在ご利用いただいているご家庭の一つに、気管切開・人工呼吸器・酸素療法を受けながら生活している小学生の利用者様がいます。
そのご家族は、下に兄妹児もいて、休日にはその子たちと一緒に外出や散歩をしたいという希望をお持ちです。
でも、医療的ケアが必要な重症児がいるご家庭にとって、それは簡単なことではありません。
そこで、「その子自身が安心して楽しく過ごせる場」を用意できれば、ご家族にも「兄妹児と過ごす時間」を提供できる。
それこそが、私が目指す開業の原点です。
単に「稼げる場所」や「自由に働ける空間」ではなく、目の前の人の役に立てる場所、そして家族全体にとって心が軽くなるような拠点をつくりたい。
このブログでは、そんな私の思いと開業に向けた試行錯誤を、少しずつ綴っていきたいと思います。
🌟障がい福祉事業:制度と現実のギャップを考える
障がい児(者)支援の選択肢を探る中で、まず浮かぶのが「通所系福祉サービス」の存在です。
療育や生活支援、社会参加を目的としたこれらの事業は、地域における障がい児支援の中核的役割を担っています。
障がい児(者)通所支援系サービスの種類と内容
児童発達支援
児童発達支援は、主に未就学児を対象にした療育支援です。
障がいのある子どもが、日常生活に必要な基本動作(例:歩く・座る・着替えるなど)を身につけたり、言葉や人との関わり方を学んだりするための訓練を行う場所です。
発語が遅い、集団生活に馴染みにくい、自閉傾向があるなど、さまざまな困難を抱えた子どもたちにとって、「遊びを通じた療育」は非常に有効とされています。
保育士や児童指導員、言語聴覚士などがチームとなって関わります。
放課後等デイサービス
通称「放デイ」と呼ばれるこのサービスは、6歳~18歳の障がいのある児童・生徒を対象に、放課後や長期休暇中に療育や社会性の訓練を提供する施設です。
学校が終わった後の「居場所」としての機能も兼ねています。
例えば、SST(ソーシャルスキルトレーニング)や創作活動、地域交流イベントなどが行われ、将来の就労や自立を見据えた支援が特徴です。
家庭以外で安心できる環境があることが、保護者にとっても大きな安心材料になります。
生活介護
生活介護は、18歳以上で常時介護が必要な障がいのある方を対象にした日中活動の場です。
医療的ケアが必要な重度の方も多く利用しており、生活支援、身体機能訓練、創作・生産活動などを通じて、生活の質を維持・向上させることを目指します。
いわば、障がいのある方の「通いの居場所」であり、長年通っている利用者さんにとっては第二の家のような存在になっているケースも多く見られます。
これらの通所支援事業は非常に意義ある制度ですが、開業を目指す立場から見ると現実はそう甘くありません。
というのも、指定基準のハードルが高いのです。
例えば、スタッフは最低でも3人必要。うち1人は管理者、もう1人は児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者といった専門職を配置しなければなりません。
さらに、療育スペースや訓練室、相談室など物理的な要件もクリアしなければならず、開業資金だけでも数百万円は必要になります。
Kagayaのように「1人で、身軽に、質の高い支援をしたい」という場合、このスタイルは正直かなり難しいです。
医療的ケア児の身体支援という観点から見れば、鍼灸やリハビリとの組み合わせは最高なのですが、それを福祉事業の枠で実現するには仲間と場所が不可欠です。
「仲間を見つけなさい」と利用者ご家族にもよく言われます。
でも、それはKagayaの自由気ままな性格とビジョンを理解して共に歩める人でないと難しい…と感じています。
現時点では、この通所系福祉サービスは一旦保留。
今後、本当に信頼できるパートナーに出会えた時には、もう一度検討したい案ではあります。
訪問系サービス:自宅に届けるケアと支援のかたち
「施設は難しいけれど、1対1で支援を届けたい」という場合、訪問系サービスは非常に現実的な選択肢になります。
施設型の通所支援に比べると、人員や設備の面での制約が小さく、利用者一人ひとりの生活に直接寄り添えるスタイルです。
移動支援:地域の外へ、心の外へ
障がい者総合支援法に基づく「移動支援」は、屋外での移動が困難な障がいのある方に対して、外出をサポートする制度です。
病院や役所への送迎だけでなく、買い物や散歩、地域イベントへの参加など、“生活の豊かさ”を支える目的を持っています。
多くのヘルパーステーションは、この移動支援を含む複数の訪問系サービスをまとめて提供しています。
実施主体は市区町村で、地域差はあるものの、比較的柔軟に運用されている印象があります。
ただし、「移動支援のみ」での事業指定は取りづらい自治体もあるため、実際には居宅介護や重度訪問介護と組み合わせた運営が主流です。
個人開業としてはややハードルがありますが、他事業との連携や兼業なら活用可能性があります。
居宅訪問型児童発達支援:通えない子どもにこそ
「居宅訪問型児童発達支援」は、医療的ケアや重度障がいにより通所が難しい子どもたちを対象としたサービスです。
家庭という最も安心できる場所で、日常生活の基本動作や生活スキルの訓練を行うものです。
この制度は2017年度から本格施行され、特に医療的ケア児の増加に対応する形で重要視されつつあります。
通所施設の代替というより、“訪問ならではの支援”が求められる領域です。
ただし、サービス提供には既存の児童発達支援事業所の指定を受けていることが前提となるため、「この制度単体で開業する」ことは難しいのが現状です。
あくまで“オプション”としての訪問という位置づけになります。
10年以上の看護師経験をもとに、Kagaya自身も「鍼灸×リハビリの訪問看護ステーションを立ち上げられたら…」と真剣に考えました。
でも、指定事業として訪問看護ステーションを開業するには、看護師2.5人+理学療法士などのリハ職が必要。
1人では始めることができません。
人件費や連携体制、管理者の条件など、超えなければならないハードルが多くあります。
そこで思いついたのが「自費訪問看護」のスタイルです。
制度の枠に縛られず、ニーズに合わせた支援ができるかもしれないという希望。
でも、その一方で課題もたくさんあります。
- 訪問1件あたりいくらもらえる価格設定にすべきか
- 医療的ケアが必要なケースに、どこまで対応できるのか
- 保険外で本当に継続的な契約がとれるのか
それでも、「制度に合わせるために必要な支援ができない」という現状よりは、自費でも“やるべきこと”に集中できる方が理想的かもしれません。
今はまだ模索段階。
でも、訪問で療育やリハビリ、鍼灸ケアを届けるスタイルは、きっとKagayaにしかできない働き方だと感じています。
🌟日中一時支援事業:家族にとっての「休息」としての役割
日中一時支援事業とは、障がいのある方が日中に過ごせる場所を確保し、その間の介護・見守り・活動支援などを提供するサービスです。
一見すると放課後等デイサービスや生活介護と似たような支援に見えますが、この制度の最大の特徴は「家族の休息」を目的としている点にあります。
例えば、重度障がいのあるお子さんと24時間生活を共にするご家族にとって、数時間でも預け先があることは心身のリフレッシュや、きょうだい児との外出など「家族全体の生活の質」に直結します。
介護をしている側が心の余裕を持てることが、長期的に安定した在宅生活を続けるためには欠かせない要素なのです。
この事業のもう一つの大きな特徴は、年齢制限がないこと。
放課後等デイサービスは18歳で制度の対象外になりますが、日中一時支援は制度上、未就学児から成人まで対応可能とされており、障がいのある方が“卒業後”も継続して利用できる柔軟な仕組みとなっています(※自治体により条件差あり)。
実際、最近では「卒後の夕方支援」として日中一時支援を活用するケースが増えてきています。
たとえば、生活介護を利用している方は16時頃には帰宅してしまいますが、保護者の就労時間などを考えると“もう少し預けられる場所がほしい”というニーズはとても大きいのです。
ところが、この制度にも大きな壁があります。
それは自治体ごとの運用差です。
Kagayaが拠点として検討している小平市や東大和市では、日中一時支援事業を単独で立ち上げることは認められていません。
必ず他の指定福祉サービス(例:居宅介護や放デイなど)と組み合わせた形でないと設置できない仕組みとなっており、「このサービスだけを提供したい」と思っても、事業者としては不可能なのが現実です。
制度そのものはとても意義があり、家族支援の視点から見ても有効であるにもかかわらず、「現場での実現性」が自治体ルールに左右されてしまうのは非常にもったいないことだと感じています。
もし将来的にこのサービスを単独事業として設置できる制度改正や補助枠が出てくれば、そのときこそKagayaのような“小さく始めたい支援者”が活躍できる場面が広がるはずです。
そのために今は、制度や地域ルールを研究しながら、共に実現を目指せる仲間を探すことも重要なステップだと考えています。
「小さな拠点で、日中に子どもが楽しく過ごせて、家族も少し休める」──そんな居場所づくりをいつか実現できるよう、準備と情報収集を続けていきます。
🌟鍼灸院として:1人で働くための選択と覚悟
ここまで、障がい福祉や訪問看護、日中一時支援といった様々な支援の形を模索してきましたが、やはりKagayaの原点は「鍼灸院として開業すること」にあります。
Kagayaが鍼灸の世界に飛び込んだ一番の理由。
それは、「自分一人でも開業できる国家資格」であることでした。
看護師は医療職として非常に重要な存在ですが、制度上、医師の指示がなければ治療行為を行うことはできません。
また、開業という点においても、訪問看護ステーションを立ち上げるには複数の職員と組織体制が必要となり、個人で気軽に始められるものではありません。
その点、鍼灸師は法律上、1人で開業し、施術を提供できる資格です。
あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師も同様ですが、Kagayaにとっては「看護師としての臨床経験」と「鍼灸師としての手技」を組み合わせることで、もっと自由で本質的な支援ができるのではないかという希望がありました。
福祉制度に目を向けることはとても大切です。
保険内で支援が受けられることは、家族や利用者様にとって大きな安心につながります。
しかし、制度には制度の制限があり、「本当に必要なことが、保険ではできない」という現実もあるのです。
だからこそ、「自由にできる支援」のフィールドとして、鍼灸院をベースに構想するのは理にかなっています。
制度の枠に縛られず、ニーズや想いに寄り添った形でサービスをつくることができます。
さらにKagayaは、「鍼灸と療育を融合させた場」をつくりたいと考えています。
耳つぼやYNSA(山元式新頭鍼療法)、さらにはスヌーズレン的な感覚統合の要素を取り入れながら、重症心身障がい児や発達に特性のあるお子さんたちに対し、心と体にアプローチするケアを提供したい。
例えば、医療的ケアを受けているお子さんでも、「病院」や「施設」ではなく、リラックスできる空間で安心して過ごせる居場所があっていいはずです。
鍼灸を受けながら、呼吸や感覚を整え、笑顔が引き出せるような時間を提供したい。
もちろん、すぐに大きなことはできません。
でもまずは、訪問型や間借りサロンなどで、「1人でできる小さな事業」から始めていこうと考えています。
この小さな一歩が、いつか「鍼灸×療育」の新しいスタンダードになるように。
そして、ご家族と利用者さん、そして支援者のすべてが笑顔になれる仕組みになるように。
そんな未来を目指して、まずは鍼灸院としての立ち上げ準備を着実に進めていきたいと思います。
🌟まとめ:制度に頼らず、志をかたちに
ここまで、障がい児(者)支援に関連する様々な福祉事業や訪問サービス、そして鍼灸院としての開業について検討してきました。
どの制度も、支援を必要とする方々にとって大切な存在であることは間違いありません。
ですが、1人で始めるという視点で見たとき、現実には多くのハードルがあります。
福祉施設として事業を設置するには、最低限必要な人員配置(3名以上)や広いスペース、設備投資、そして複数の事業を組み合わせることが前提になることが多く、Kagayaのような個人事業レベルでは手が届きません。
また、国の制度(=税金を使った支援)に乗るためには、その分のルールや管理、書類の整備など“やらなければならないこと”も増えます。
制度を活用すれば費用面でのメリットはあるかもしれませんが、「やりたい支援」や「必要だと感じているケア」が制度上できないというジレンマもあるのです。
だからこそ、あん摩マッサージ指圧師や鍼灸師、柔道整復師といった施術者たちは「自費」で自由なスタイルの開業を選ぶのかもしれません。
Kagayaもまた、自分にしかできないケア、自分にしか見えないニーズを大切にしたいと思っています。
制度の枠を飛び越え、利用者とそのご家族にとって“本当に意味のある支援”を、鍼灸と療育のかけ合わせで実現していきたい。
もちろん、最初から完璧な形にはなりません。
まずは「自分ひとりで始められる鍼灸院」という小さな一歩から。
そこから、少しずつ必要な機能を積み重ね、仲間ができたら連携し、地域の中での居場所を育てていければと思っています。
これから本格的な国家試験勉強も始まっていきますが、学びを支援につなげられるように、地に足のついた開業準備を続けていきます。
今後も、同じように「自分の力で誰かの役に立ちたい」と思っている方々と、こうして想いや情報を共有していけたらうれしいです。
🌟お問い合わせはこちらから
「療育と鍼灸を組み合わせたケアに興味がある」「家族支援について一度相談したい」など、お気軽にご連絡ください。
訪問相談・シェアサロンご予約も受付中です。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら