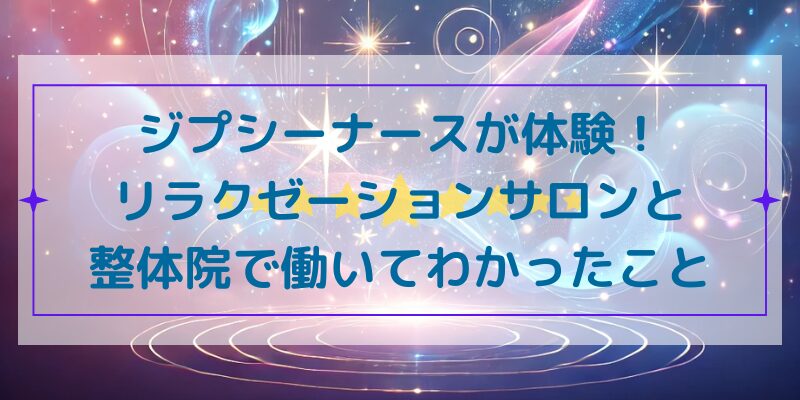🌟はじめに:なぜリラクゼーション業界で働こうと思ったのか?
こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
Kagayaは現在、パートの訪問看護師として働いています。
仕事内容にはやりがいを感じているものの、勤務日数や拘束時間の制限があるため、どうしても収入には限界がありました。
「もう少し収入を増やしたいな」「どうせなら将来の鍼灸院開業にも役立つ経験がしたい」と思い、ふと目に入ったのが、リラクゼーションサロンと整体院の求人募集でした。
「開業前に他の施術スタイルを実地で見てみたい」「民間の治療系サービスの経営の現場に触れてみたい」という思いで、軽い気持ちで応募してみました。
採用され、研修も始まり、現場デビューに向けて数日働いたのですが……
結論から言えば、Kagayaの価値観や倫理観とは相容れない部分が多く、わずか1週間で辞めることにしました。
もちろん、すべてのリラクゼーションサロンや整体院が同じとは思っていません。
ですが、今回の体験を通じて、
- 雇用形態の違い
- 歩合制の報酬システム
- 施術の考え方やマニュアル化
- 同業者同士の関係性(競争か協調か)
といった点で、医療職の現場とは大きく異なるカルチャーショックを受けました。
今回は、鍼灸・看護の知識を持つKagayaが、実際に働いてみて感じた「リラクゼーション業界・整体業界のリアル」について、率直に、そして丁寧にお伝えしていきます。
ちなみに現在は、知的障がいのある方が暮らすグループホームで、掃除のアルバイトをしています。
この仕事は、黙々と取り組む作業でありながら、利用者さんや職員さんとの日常的な交流もあり、「癒す」「整える」というKagayaの根本理念にとても近い感覚があります。
それに比べると、サロンでの競争的な空気や、施術という名の営業活動には、どうしても違和感を抱かずにはいられませんでした。
この記事が、「これから開業したい」「どんな働き方が自分に合っているか悩んでいる」という方にとって、一つの参考材料になれば嬉しいです。
🌟給料について:歩合制VS時給制、その裏にある現実
Kagayaがアルバイトとして入ったリラクゼーションサロンでは、まずは無給の研修を受け、テストに合格すれば晴れて現場デビューという仕組みでした。
「しっかり技術を身につけてから働く」というスタイルに見えますが、実際にはマニュアルの暗記と実技チェックが中心で、研修期間中は一切の報酬なし。
むしろ、研修費を取られるサロンもあり、「働くためにお金を払う」という矛盾すら感じました。
そしてデビュー後は完全歩合制
たとえば、1人施術すれば3,000円程度の報酬になることもありますが、3時間待機してもお客様ゼロなら1円も発生しません。
しかも雇用ではなく、あくまで業務委託契約=個人事業主という立場。
経営者ではなくても「自己責任で集客し、稼げなければ自己責任」という厳しい現実が待っていました。
そのため、サロン内でも「仲間」ではなく「ライバル」という空気がありました。
- スタッフ同士で同じお客様を取り合う
- 指名されれば収入UP
- 指名がなければ、待機してもゼロ円
当然のように起こるのが、ギスギスした人間関係や、セラピスト同士のマウンティングです。
お客様にトラブルが起きた場合も、「自分の責任で解決してください」と言われ、サロン側は基本的に関与しない方針。
良く言えば自由、悪く言えば「放任」。
これはKagayaが大切にしている「安全性」「倫理性」とは、大きく異なるものでした。
一方で、整体院では雇用契約+時給制。
勤務時間中は施術をしていなくても、一定の時給1,200円が発生しました。
ただし、施術1回あたりの料金(6,000円前後)に対して、施術者に支払われる対価としては「安い」と感じたのも事実です。
時給で守られる安心感はあるものの、技術や知識への対価としては不十分に感じました。
さらに、いわゆる「慰安目的」のサロンでは、回数券や高額サプリメントの販売が業務に組み込まれていることも。
中にはローンを組ませて高額な商品を買わせるというケースもありました。
こうした仕組みが「この仕事でいいのか?」という疑問を深める原因となり、Kagayaはこの業界からすぐに身を引くことを決意したのです。
もちろん、歩合制の方が「やった分だけ稼げる」という魅力はありますし、それが合っている方もいます。
でも、ケア職・治療職の本質を大切にしたいというKagayaには、相容れない世界でした。
🌟経営について:回数券と強制リピートの裏側
Kagayaがバイトしていたリラクゼーションサロンや整体院で感じたことのひとつに、「経営の在り方」があります。
よく言われるように、リラクゼーションサロンや整体院は今やコンビニよりも多いともいわれるほど激戦業界。
開店してもすぐに閉店してしまう例も少なくなく、それほど生き残るのが難しい世界なのだと実感しました。
経営を続けていくには、「新規のお客様」を常に獲得しながら、「リピーター」になってくれる方を増やしていかなければなりません。
そのため多くの店舗では、回数券の販売や、次回予約の強制、さらには施術後に高額な健康グッズ・サプリメントなどの購入を勧めるなど、いわゆる押し売り営業のような仕組みが導入されていました。
中には、「お得に続けるためにはローンを組んで回数券を買うべきです」といった勧誘を行う店舗もあり、正直なところ医療・福祉職の視点では受け入れがたいものでした。
Kagayaの感覚としては、リラクゼーションサロンや整体院は「なんとなく気持ちよかった」「疲れが取れた気がする」といった慰安目的の施設が多く、治療効果を期待して通うというよりも、雰囲気や接客の良さで「通ってもいいかな」と思わせる場所、という印象です。
もちろん、「気持ちよさ」自体に価値があることは理解しています。
ただしそれを根拠に、次回予約を取らせたり、施術とは関係のない商品を売ったりするのは、Kagayaにはどうしても納得できませんでした。
例えば「次回の予約も入れておきますね」と、お客様の意思確認なしに予約を取るような手法。
これはもうケアでもサービスでもなく、ほぼセールス。
本当に施術が良くて、お客様が気に入ってくれたなら、こちらが促さずとも自然に次の予約をしてくれるはずです。
こうした「経営戦略」に違和感を抱きつつも、「ああ、こういう世界なんだな」と客観的に見ることができたのは、とても良い経験だったとも思っています。
開業を目指すKagayaとしても、どういう運営はしたくないかをはっきり確認できたという意味で、この経験には大きな価値がありました。
今後、Kagaya自身が鍼灸院を開業する際は、「予約を強制しない」「不要なものは売らない」「施術の意味を説明する」――そういった信頼を重ねるスタイルを大切にしていきたいと思っています。
サロンでの体験を通じて、経営とケアのバランスについて深く考えるきっかけになりました。
🌟施術について:マニュアル施術と“治療”の違い
経営や給料体系の面でも驚きが多かったリラクゼーションサロン・整体院ですが、Kagayaが最も強く違和感を覚えたのは施術内容そのものでした。
「これ、本当にお金をいただく内容なの?」
――そう疑ってしまうほど、理論的な裏付けのない“マニュアル施術”が当たり前に行われていたのです。
リラクゼーションサロンでの研修では、まず「揉みほぐしの流れ」を丸暗記することが求められました。
- どこをどう触るか?手順のみを暗記
- その筋肉の名称や機能は知らなくてOK
- そもそも目的が説明されない
Kagayaが疑問を投げかけると、指導者は明らかに不機嫌に。
「余計なことは聞かずに覚えて」という空気感に、強烈な違和感を覚えました。
理論なき施術、説明なき流れ作業。
それは、私にとって「ケア」でも「治療」でもなく、ただのサービス業の一部にしか感じられなかったのです。
整体院もまた似たような印象でした。
メインの施術は「首をぐっと押す」――それだけ。
理屈としては、「首の筋肉を緩めることで自律神経に作用する」とのこと。
ツボで言えば「天柱」や「風池」のあたりでした。
確かに、それらのツボには効果があることは東洋医学的にも理解できます。
しかし、なぜこの順番なのか?なぜこの圧で?といった説明は一切なく、コミュニケーションさえ禁止されているという方針でした。
施術時間は20分、料金は6,000円。
その金額に見合う技術・知識・対応だとは正直思えませんでした。
何よりも気になったのは、施術者のお客様に対する態度。
- 上から目線で説明する
- 効果を誇張する
- お客様の声を“操作”したような広告
セラピスト自身が“治療している感”に酔っているような空気すらあり、「治療したいならもっと学んでほしい」と思いました。
ただ、そんな施術でもお客様が通い続けている現実もまた事実です。
ホームページには「○○に効果があります」「お客様の声」といった文言が並び、広告にかなりのお金をかけている印象もありました。
そして実際にリピートしている方がいるということは、「癒された」「楽になった」という実感を得ている人もいるということ。
Kagayaとしては、それが間違っているとは言いません。
ただ、「施術」=「責任ある行為」であるという意識を持たないまま、型だけの手技を繰り返すことには、どうしても賛同できませんでした。
この経験から、“施術とは何か?”をあらためて考え直すきっかけをもらいました。
🌟まとめ:働いてわかった“合わないもの”と学びの本質
今回、Kagayaがリラクゼーションサロンや整体院で実際に働いてみたのは、単なる「副業」ではなく、将来的な鍼灸院開業の参考にするためという目的がありました。
普段はお客様の立場でしか見ることのなかった店舗運営や施術の裏側を、“スタッフの視点”で体験できたことは、とても大きな意味がありました。
実際に現場に入ってみて分かったのは、本やネットの情報だけでは見えてこないリアルな現実です。
- 歩合制と時給制の実態
- 強引な営業や予約の仕組み
- 意味のない施術の流れ作業化
- セラピスト間の競争と孤独感
Kagayaにとっては、これらの多くが「違和感」や「倫理観に合わない」と感じるものでしたが、逆に言えば、「自分にとって大切にしたいこと」をはっきりさせるきっかけにもなりました。
事実として、Kagayaがバイトしていたサロンや整体院は、今でも営業を続けています。
それは、その場所を求めているお客様がいるということの証です。
どんなスタイルにも、合う・合わないはあります。
それを頭で考えるのではなく、現場で体験してみることが何よりも勉強になると強く感じました。
たとえ違和感を持ったとしても、そこから得られる気づきや学びは大きいものです。
世の中には、「○○式経営」や「売上10倍戦略」などの高額コンサルがあふれていますが、何十万円も払う前に、まずはバイトでも現場経験をしてみる――これがKagayaのおすすめです。
気になったお店で働いてみる。
やってみて嫌ならやめる。
その繰り返しの中で、少しずつ「自分に合うスタイル」が見えてくると思います。
Kagayaは今回の経験で、慰安目的のみのお店では働けないという自分の特性を再確認できました。
だからこそ、これからは「治療・ケア・寄り添い」を軸にした、自分らしい鍼灸スタイルを模索していこうと、あらためて心に決めたのです。
この記事が、「これから何か始めたい」「働き方に悩んでいる」という方のヒントになればうれしいです。
🌟Kagayaおすすめ!鍼灸開業を考える人への役立つアイテム
今回の体験から「自分らしい施術スタイルを大切にしたい」「押し売り型の経営に違和感がある」と感じた方に、Kagayaが実際に良いと思った、信頼できる学び・準備・サポートアイテムをご紹介します。
📘 書籍:『治療院経営の教科書』
施術初心者からでも、月商100万円超を目指す治療院の経営ノウハウがわかりやすくまとまっています。
具体的には、集客、メニュー設計、お客様対応など、現場で即役立つ内容が揃っており、「理念と利益のバランス」に悩む方にピッタリです。
📘 書籍:『はじめての鍼灸マッサージ治療院 開業ベーシックマニュアル』
「何を大切にした治療院をつくりたいのか?」という理念設計から、物件選び・備品・広告・保健所手続きまで丁寧に図解で解説されています。
専門学校の開業実習でも使われるほど信頼性が高く、誠実な院づくりをしたい方には必読です。
実際に働いてみて違和感を覚えたKagayaだからこそ、「こういう院を作りたい」という想いに気づけました。
🛠️ 鍼灸・整骨 新規開業セット
施術ベッドや基本器具がひとまとめになった開業セット
。大きな初期設備投資を避けたい訪問型や小規模院に最適です。
セット一式で届けられるので、「何を揃えたらいいかわからない」という初心者にも心強い内容です。
📩 ご相談・お問い合わせはこちら