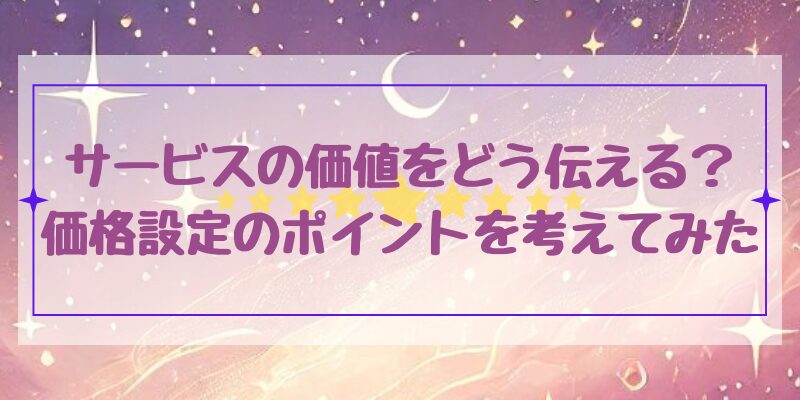こんにちは。
プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
Kagayaは、看護師の国家資格と鍼灸師の技術を組み合わせ、障がいのあるお子さまやご家族の生活に寄り添うためのオリジナルサービスを提供しています。
「鍼灸治療をしながら、見守り看護と療育も一緒にできる」このような新しいスタイルの訪問ケアは、一般的な訪問看護ステーションや福祉サービスでは実現しづらい、一人ひとりに寄り添ったオーダーメイドの支援です。
特に、重症心身障がい児(者)を対象にした場合、医療的ケアやコミュニケーション支援、感覚刺激など多岐にわたる対応が求められます。
Kagayaはこれまで、療育病院・特別支援学校・放課後等デイサービス・訪問看護など、医療・福祉・教育の現場を横断的に経験してきました。
その中で、制度の狭間にいる子どもたちやご家族のニーズをたくさん見てきました。
「もっと長く見守ってほしい」「家族も安心して休める時間がほしい」「でも病院でも福祉でもカバーしきれない」――そんな声に応えるために、“看護×療育×鍼灸”という統合ケアを形にしました。
具体的には、以下のようなサービスが可能です:
- 鍼灸治療:神経や筋肉のバランスを整え、発達の促進や体調管理をサポートします
- 見守り看護:呼吸器管理・経管栄養などの医療的ケア、体位変換や排泄介助などの介護的支援も含みます
- 療育支援:視覚・触覚・音刺激などのスヌーズレン的アプローチ、個別の発達段階に応じた関わり
加えて、ご家族へのケアも大切にしています。子どものケアだけでなく、保護者の休息時間の確保、就労継続支援、メンタルケアなども重視しています。
「この子のために、でも自分も壊れそう」という方を、一人でも減らしたい。
その思いで、この事業を立ち上げました。
ご自宅での対応だけでなく、外出先への同行やレンタルスペースでの施術なども柔軟に対応可能です(別途費用)。
「看護」「療育」「鍼灸」をバラバラに受けるのではなく、一つのサービスの中で包括的に受けられるというのが、Kagayaのサービスの最大の特徴です。
一人でも多くの子どもと家族が、「その子らしく」「その人らしく」安心して暮らせるように――
Kagayaは、今日も現場に向かいます。
こんにちは~。プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。
🌟サービス内容
看護師と鍼灸師の両資格を持つKagayaが、重症心身障がい児(者)とそのご家族に向けて、「鍼灸治療×見守り看護×療育支援」を統合した自費訪問サービスを提供しています。
単なる慰安や単独医療ではなく、ご家庭の暮らしに密着しながら、医療的ケア・発達支援・保護者の休息をトータルでサポートする新しい形のケアです。
訪問では、鍼灸施術による体調管理とともに、日常の中での姿勢保持・呼吸管理・コミュニケーションへの配慮・感覚遊びの提供などを同時に行い、“その子らしさ”の実現をめざします。
また、保護者に対しても、就労・休息・育児支援の観点から「使えるサービス」となることを大切にしています。
「仕事をしたいけれど、生活介護が早く終わってしまう」「お迎えに間に合わない」「学校行事に同行してもらえる人がいない」――そんなお悩みに寄り添えるのがKagayaの訪問サービスです。
以下は、サービスの具体的な案内です。
訪問地域
拠点は東京都小平市。東大和市・東村山市・立川市・国分寺市・武蔵村山市など(小平特別支援学校・村山特別支援学校の通学圏内)を訪問可能地域としています。
ご自宅への訪問に抵抗のある方は、レンタルスタジオやスペースのご利用もご相談いただけます(別途ご家族負担)。
ご利用対象者
- 重症心身障がい児(者)で医療的ケアが必要な方
- 重度知的障がい・発達障がいを持つ18歳以下の方
また、介護や学校行事への同行、放課後支援などで働けなくなってしまった保護者の方のサポートも対象にしています。
「きらぼし」開設のきっかけ・思い
Kagayaはこれまで、療育病院・特別支援学校・訪問看護・放課後等デイサービスなど様々な現場で経験を重ねてきました。
その中で感じたのは、福祉サービスは制度の中では手厚い一方で、ご家族が本当に必要としているサポートが届いていないということです。
「仕事をしたいのに、医療的ケアがあって無理…」「自分の時間をつくれない」そんな悩みを抱える方のために、“身近な専門職”として寄り添える存在でありたいと思い、『きらぼし』を立ち上げました。
ご利用案内
- ● 鍼灸治療(60分/症状に合わせた全身調整)
- ● 療育サポート(感覚刺激・音や光のスヌーズレン的療育など)
- ● 見守り看護(吸引・呼吸器管理など医療的ケアにも対応)
- ● 学校行事・通院同行(内容応相談)
「一人でお出かけするのは不安」「医療的ケアがあって外出できない」「人手が足りず外部サービスが使えない」――そんな時にKagayaを頼っていただけると嬉しいです。
自費サービスだからこそ、枠にとらわれず、必要な支援を必要なタイミングで提供することができます。
🌟価格設定の基本的な考え方
サービスの提供にあたり、価格設定はとても大切な要素です。
安すぎると質に不安を感じられたり、高すぎると選ばれにくくなったりします。
Kagayaも「保険が使えない自費サービス」において、どうすれば納得してもらえるかを悩みました。
そこで、基本的な価格設定の考え方を3つの視点から整理し、自分の事業に落とし込みました。
まず1つ目は、競合の価格を基準にする方法です。
これは「市場価格追随法」とも呼ばれます。
多くの人は複数のサービスを比較検討する際に、料金を大きな判断材料にしています。
そのため、周囲の同業者と大きく異なる料金設定をしてしまうと、「なんでこんなに高い(または安い)の?」と不信感につながる可能性があります。
とくに初めて利用される方にとっては、「相場と同じくらい」という安心感が、サービスの導入ハードルを下げるポイントになります。
また、この方法には応用形もあり、たとえば人気や信頼のある他店舗の価格帯に合わせる「プライスリーダー追随法」、もしくは地域に根付いた昔からの料金を踏襲する「習慣価格法」なども同じカテゴリーに含まれます。
2つ目の考え方は、サービス提供にかかるコストをベースにした方法です。
これは「コストプラス法」や「目標利益法」として知られています。
たとえば、開業にかかる初期投資、月々の家賃・保険料・交通費・機材消耗品などの固定費と、患者さんごとの移動や準備などに関わる変動費をすべて計算し、必要な利益を上乗せして価格を設定します。
これは「いくら稼げば赤字を出さずに継続できるか」という経営視点に立った非常に現実的な方法です。
Kagaya自身も、「最低限自分が生活できる分」「必要機材の更新費」などを想定しながら目標売上を逆算しました。
3つ目の視点は、マーケティング戦略に基づく価格設定です。
これは、単にコストや相場だけでなく、顧客にどういう価値を感じてもらうか、また商圏や立地、競合との違いなどを考慮した方法です。
たとえば、地域に類似サービスが少ない、またはKagayaのように「看護×療育×鍼灸」という希少な統合型サービスを提供している場合、その独自性を評価して価格を高めに設定することも可能です。
この手法では、高くても納得される理由をしっかりと説明できることが鍵になります。
「価格差別法」という形で、ターゲット顧客やサービス内容に応じて価格を柔軟に変える方法も含まれます。
Kagayaはこの3つの視点すべてを参考にしながら、特に「公共制度とのバランス」と「家族の経済状況」を重視して価格設計を行いました。
単なる施術時間の長短ではなく、「その人らしい生活を支えるために必要な支援」であるという観点で、価格の意味と価値を伝えていきたいと考えています。
🌟市場価格追随法による価格設定
Kagayaが提供する「鍼灸×看護×療育」という統合型の訪問ケアサービスは、既存の制度では対応しきれないニーズをカバーするものです。
そのため価格を設定する際に悩んだのは、同じようなサービスがほとんど存在しないということでした。
とはいえ、見守り機能があるサービスという点では共通項がある、自費看護・民間学童・ベビーシッターなどの価格帯を調査し、参考にしました。
自費看護サービスとの比較
まず、プライベートナースなどの自費看護サービスは、1時間あたり6,000~8,000円が相場とされています。
多くの事業所では「2時間以上」からの利用が基本となっており、医療行為が必要な場合は加算料金が発生します。
看護師がマンツーマンで訪問し、医療的ケアや見守りを提供するスタイルはKagayaのサービスとも近い部分がありますが、高齢者向けが主流であり、重症心身障がい児(者)を対象にしたものはまだ少ないのが現状です。
また、障がい児・者の場合は医療保険の助成があり、訪問看護の自己負担がかからない方も多いため、「あえて自費で利用する意味」を説明しなければ選ばれません。
民間学童との比較
自治体が運営する学童保育は月3,000~7,000円とリーズナブルですが、民間学童は月額30,000~100,000円+入会金・年会費が必要です。
その代わり、夜間延長・学習支援・英語レッスン・送迎対応など、独自のサービスが充実しており、保護者からは「学童代のために働いているようなものだけど、助かっている」という声もあります。
Kagayaのサービスも「高いけど助かる」と思ってもらえるように、サービス内容を具体的に見える化することを意識しています。
ベビーシッターとの比較
最近では、看護師によるベビーシッターも広まりつつあります。
特に病児保育や医療的ケア児への対応をウリにしたサービスでは、時給6,000~8,000円とプライベートナースとほぼ同等の価格帯が設定されています。
ただし、入会金や年会費がかかるところも多く、保育というより「ビジネス感」が強い印象を受ける方もいます。
Kagayaとしては、富裕層だけが対象の高額サービスにはしたくないという思いがあります。
できるだけ一般家庭にも届くよう、医療制度の価格(訪問看護や保険鍼灸)の1割負担を基準に設定しました。
リラクゼーション業界との違い
リラクゼーションサロンでは、60~90分の施術で8,000~10,000円が相場です。
美容鍼などは30,000円を超えることもありますが、これは“特別なご褒美”としての価格設定です。
Kagayaが提供するのは、ご褒美ではなく日常の中で安心して使える「生活の一部としての医療・ケア」。
それゆえ、高額な贅沢品のような価格にはせず、継続利用できる金額を目指しています。
これらの市場価格を参考にしつつ、Kagayaのサービスは「見守り+鍼灸+療育」という複合性を評価し、訪問看護や福祉サービスの価格に準じた独自の料金体系を組み立てました。
価格は単なる数字ではなく、サービスの信頼性や継続性を左右する重要な要素です。
これからも市場の動向を見ながら、必要に応じて柔軟に見直していく予定です。
🌟Kagaya的な価格設定の考え方
Kagayaの考える価格設定は、“誰かのご褒美”ではなく“誰かの生活の一部”になるサービスとしての価値を大切にしています。
美容鍼灸や高級サロンのように、1回数万円のサービスもありますが、私が目指すのは、日々の暮らしの中で無理なく利用できる、継続可能なケアです。
実は、Kagayaは“ガッツリ稼ごう”というタイプではありません。
独り身で、ちょっと贅沢できるくらいの生活ができれば十分ですし、頑張っても税金で持っていかれるばかり(笑)。
でも、価格を下げすぎてしまうと、サービスの継続が難しくなります。
だからこそ、公的制度に準じた価格設計に落ち着きました。
たとえば、訪問看護の10割料金は1回の訪問で10,000円以上になることもありますが、実際にKagayaが受け取るのは、時給換算で2,000円程度。残りは会社の運営費や管理費に回ります。
同じように、保険適応の訪問鍼灸も1回約5,000円が標準。
しかも、時間の長さに関係なく一律です。
5分で終えても60分かけても、同じ料金です。
Kagayaは、最低でも1回60分程度の鍼灸治療を行いたいと思っているので、質と時間に見合った価格で設定する必要があると感じました。
そこで、あくまでも基準は医療制度の10割料金としつつ、「1割負担で受けられる価格設定」を採用することにしました。
たとえば、児童発達支援の在宅訪問の料金は、1回あたり17,140円(居宅訪問型の場合)です。
これをベースに、1割負担とすると約1,700円。
この金額感を参考に、サービスごとの価格を設計しています。
以下が現在の価格構成です。
利用料金
- 鍼灸治療:5,000円(60分)
- 療育:2,000円(感覚刺激や発達支援)
- 見守り看護:9,000円(120分)
以降延長30分ごとに2,000円 - 交通費:実費
- 施設レンタル:実費(希望者のみ)
あまりに高額では利用が続きません。
でも、安すぎると質の担保が難しくなる。
そして何より、「やっていけない」とKagaya自身が疲弊してしまいます。
だからこそ、制度の価格に近い金額で、かつ生活に取り入れやすい価格を意識して設定しました。
また、国の制度価格は数年に一度、改定があります。
これをベースにしておけば、値上げする際の説明にも説得力があるのではと考えています。
一方で、在宅療育の実費相場は非常に高額で、実際のサービス単価は2~3万円を超えることもあります。
なのに、スタッフは必ずしも高収入ではない。
それが現場のリアルです。
だからこそ、Kagayaは、自分自身の働きが「ちゃんと届く」価格にしたかった。
収入に応じて負担を抑える「1割負担」の考え方を応用しつつ、家庭にとっても、Kagayaにとっても無理のないラインを探って、今の価格にしています。
まだ試行錯誤中ですが、これが今のKagaya流価格設定の考え方です。
🌟まとめ
重症心身障がい児(者)を対象とした福祉サービスは、公的支援が充実しており、多くの場合、自己負担は月数千円以内に抑えられています。
特に0歳~15歳の期間は、自治体の助成制度や福祉医療費助成制度(マル障・マル子等)により、医療費がほとんどかからない環境が整ってきました。
ですが、2022年までは「魔の16歳問題」と呼ばれる時期が存在しました。
これは、高校進学を機に福祉医療助成の対象から外れてしまい、突然2~3割の医療費が自己負担になるという制度上のギャップです。
高校生でも定期的な医療が必要な方、訪問看護を利用している方にとって、このタイミングでの医療費増加は家計を大きく圧迫する要因となっていました。
「病院に行かないわけにはいかない」「訪問看護をやめるわけにもいかない」と悩まれるご家庭も少なくありませんでした。
実際に、「お金の問題じゃない」と訪問看護を継続したご家庭がある一方で、「この負担は現実的ではない」と泣く泣くやめたご家庭もありました。
ですが、2023年からは東京都で「マル青」制度がスタートし、高校生にも医療費助成が再度適応されるようになりました。
高校生への助成制度「マル青」
2023年より、東京都では「マル青」制度により、16歳以上でも医療費の助成が継続可能になりました。福祉的な支援が高校段階でも中断されることなく、安心して医療サービスを受けられる環境が整いつつあります。
とはいえ、公的制度には限界もあります。
訪問看護や福祉サービスは「枠」が決まっており、「この時間しか対応できない」「医療的ケアが対象でなければ使えない」など、家庭の実情と噛み合わないこともあります。
そこで必要とされるのが、自費サービスという選択肢です。
自費であっても、「このサービスが必要だ」「価値がある」と感じてくださったご家庭は、価格ではなく“信頼”で選んでくださいます。
自費だからこそできること――それは、看護・療育・鍼灸が一体となった柔軟な対応であり、「その子らしく」「家族らしく」生きていくためのサポートです。
私自身、会社に縛られない分、もっとそのご家庭の暮らしにフィットした形で寄り添えると感じています。
もちろん、制度の中で補えるものは公費を活用しながら、その外側を自費でサポートするという形が理想です。
「お金の問題ではない」と言っていただけるような、本当に価値あるサービスを目指して、これからも改善を重ねていきたいと思います。
そして、そのサービスが、ご家族の安心と笑顔、そして未来につながるものであれば、Kagayaにとってこれ以上の喜びはありません。